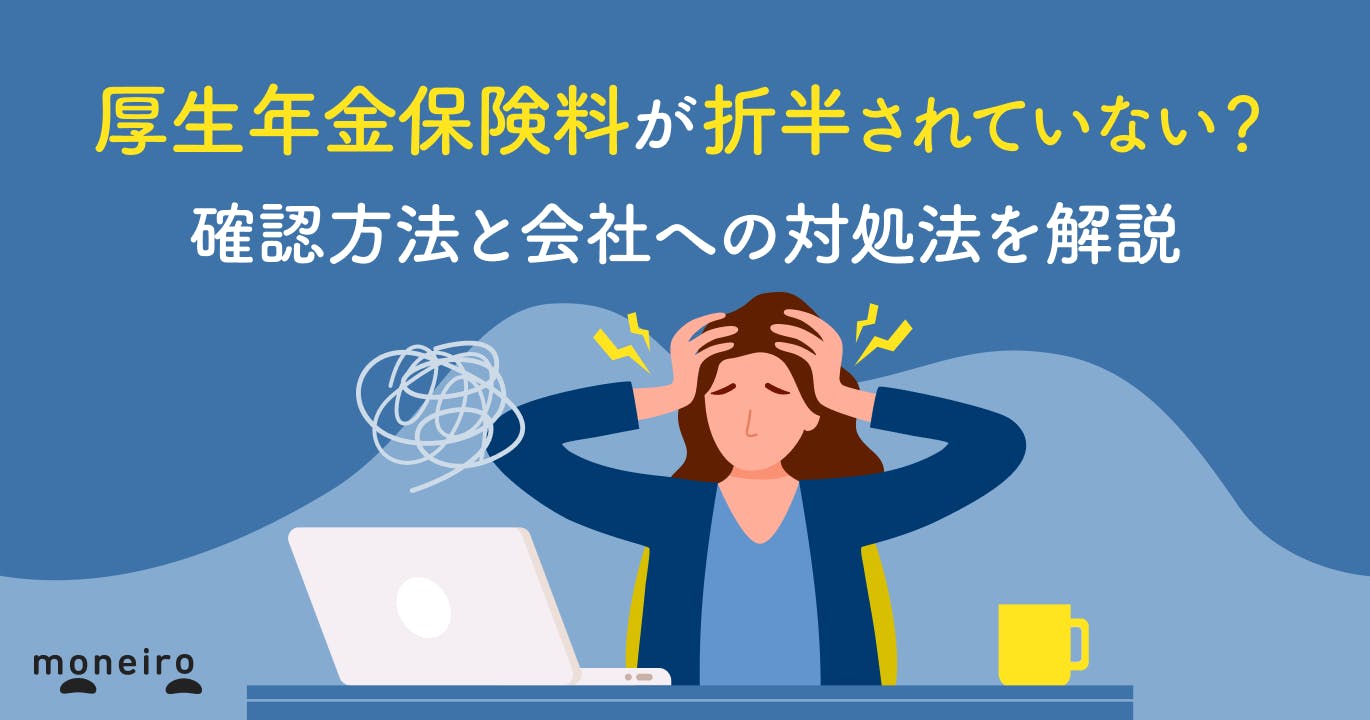厚生年金保険料が折半されていない?確認方法と会社への対処法を解説
≫あなたは老後にいくら必要?年収や資産から3分で診断
「厚生年金保険料、会社と折半されていないのでは?」そんな不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。この制度では従業員と会社が保険料を半分ずつ負担するのが原則です。
本記事では、自身の給与明細での確認方法から、もし計算が合わない場合の具体的な対処法、さらには相談窓口まで詳しく解説します。仕組みをしっかり理解し、疑問や不安を解消していきましょう。
- 厚生年金保険料の「折半」の基本ルールと、その重要性について
- 給与明細から厚生年金保険料が正しく控除されているかを確認する方法
- 折半されていない疑いがある場合の、会社への対処法
厚生年金保険料が気になるあなたへ
年金はいくらもらえて、いくら不足する?将来の資金準備は、まず大まかに将来を想定するところから始めましょう。
マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶40代からの老後資金作り:30分の無料オンラインセミナー
そもそも厚生年金保険料の「折半」とは?基本をおさらい
厚生年金保険料の「折半」とは、企業に勤める従業員が加入する厚生年金保険において、その保険料を従業員と会社が半分ずつ負担するという制度上の原則を指します。これは日本の社会保険制度において義務付けられている重要なルールです。
厚生年金保険料の折半は義務
厚生年金保険料は、会社と従業員がそれぞれ公平に、定められた割合で負担することが法律で義務付けられています。
具体的には、従業員が支払う厚生年金保険料と同額を、会社も負担し、合計額を日本年金機構に納付する仕組みです。
この仕組みにより、従業員は全額を自己負担することなく、将来の年金受給資格を確保することができます。
なぜ折半が義務付けられているのか?
厚生年金保険料の折半が義務付けられているのは、社会保険制度が「労使折半」を基本としているためです。これは、企業が従業員の福利厚生の一部を担うという考え方に基づいており、社会保障制度の安定的な運営を労使が協力して支えるという理念が背景にあります。
会社が保険料の一部を負担することで従業員の負担が軽減され、厚生年金制度への加入が促進されるというメリットもあります。また、会社側も社会保険への加入義務があるため、従業員の社会保険料を適正に納めることは、法令遵守の観点からも重要です。
標準報酬月額と保険料率の決まり方
厚生年金保険料の計算には、「標準報酬月額」と「保険料率」が用いられます。
標準報酬月額
標準報酬月額は、従業員の毎月の給与を一定の幅で区分した等級に当てはめたものです。厚生年金保険料は、実際の給与額に直接保険料率をかけるのではなく、この標準報酬月額に保険料率をかけて算出されます。
標準報酬月額は、毎年4月から6月までの報酬をもとに算定され、9月以降の保険料に適用されるのが一般的です。昇給や降給などで報酬額が大きく変動した場合には、随時改定が行われることもあります。
保険料率
厚生年金保険料の総額に対する割合で、法律で定められています。現在の保険料率は、労使合わせて総報酬の18.3%であり、このうちの半分である9.15%を従業員が負担します。
2004年(平成16年)の年金制度改正では、厚生年金の保険料率(改正前は13.58%)を徐々に引き上げ2017年(平成29年)以降は18.3%で固定することが決まりました。
これは現役世代の負担増を抑えるための改正で、年金財政の均衡を図るために年金の給付水準を抑える仕組み(マクロ経済スライド)が導入されました。少子高齢化による保険料収入の減少に対して、給付抑制で対応する構造改革の一環です。
厚生年金保険料が折半されているかの確認方法
厚生年金保険料が正しく折半されているか確認するには、以下のステップで自身の給与明細と標準報酬月額を照らし合わせるのがよいでしょう。
ステップ1.給与明細で「厚生年金保険料」の控除額を確認する
まずは、毎月会社から発行される給与明細を確認しましょう。給与明細には、基本給や手当の他に、控除項目として「厚生年金保険料」が記載されています。この項目に記載されている金額が、あなたが会社と折半している厚生年金保険料の「自己負担額」です。
ステップ2.自分の「標準報酬月額」を把握する
次に、自身の「標準報酬月額」を把握します。標準報酬月額は、給与明細には直接記載されていないのが一般的です。確認する方法としては、以下のいずれかの方法が考えられます。
- 会社の人事・経理担当者に問い合わせる
- 日本年金機構の「ねんきんネット」で確認する
- 会社から7~8月頃に交付される「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額決定通知書」を確認する
自身の標準報酬月額が分かったら、一旦メモを取っておきましょう。
ステップ3.標準報酬月額と保険料率から自己負担額を計算し比較する
標準報酬月額を把握したら、現在の厚生年金保険料率(自己負担分)を用いて、本来負担すべき厚生年金保険料の金額を計算します。
計算式は以下の通りです。
例えば、標準報酬月額が20万円で、自己負担の保険料率が9.15%の場合、20万円 × 0.0915 = 1万8300円となります。この計算で出た金額と、ステップ1で確認した給与明細の控除額を比較してみましょう。
計算が合わない?考えられる原因
もし計算結果と給与明細の控除額が一致しない場合、いくつかの原因が考えられます。
- 標準報酬月額の適用時期のずれ:標準報酬月額は年に一度見直されますが、給与変動により随時改定されることもあります。給与明細の月の保険料に、最新の標準報酬月額が反映されていない可能性があります。
- 保険料率の改定:厚生年金保険料率は法律で定められています(2017年以降は18.3%)が、過去の給与明細を見ている場合、現在の保険料率と異なる可能性があります。
- 会社の計算ミス:単なる入力ミスや計算ミスである可能性も考えられます。
- 会社が意図的に折半していない:特別な対応が必要なケースですが、後述します。
まずは、これらの一般的な原因を考慮し、確認を進めることが重要です。
もしかして折半されていない?疑わしいケースと原因
給与明細と自己計算の結果が一致しない場合、誤解や勘違いの可能性もあれば、会社が意図的に保険料を折半していない可能性も考えられます。
よくある誤解や勘違いのパターン
保険料率の誤認:厚生年金保険料率は労使合計で18.3%ですが、自己負担分は9.15%です。全体の保険料率で計算している場合があります。
- 標準報酬月額の誤認:毎月の給与額と標準報酬月額は異なります。標準報酬月額は等級に区分されるため、正確な金額を把握していないと計算が合いません。また、残業代や通勤手当なども含んだ総支給額が対象となることを理解していないケースもあります。
- 標準報酬月額の計算に使用される手当の誤解:慶弔金や結婚祝い金などは標準報酬月額の対象外ですが、労働の対価として支払われるものは含まれます。
- 賞与からの控除:賞与(ボーナス)からも厚生年金保険料が控除されますが、その計算方法は月々の給与とは異なるため、混同している場合があります。
これらの誤解がないか、改めて確認することが重要です。
会社が意図的に折半していない可能性も?考えられる手口
非常に悪質かつ稀なケースですが、会社が意図的に厚生年金保険料の折半を怠っている可能性もゼロではありません。考えられる手口としては、以下のようなものがあります。
従業員負担分を多く徴収し、会社負担分を少なくする
給与明細に記載されている従業員負担分が、本来の折半額よりも多くなっているケースです。会社は従業員から多く徴収した分を、自社の負担分として納付し、差額を不正に利益としている可能性があります。
社会保険の加入自体を遅らせる、または未加入にする
従業員を雇用しているにもかかわらず、社会保険への加入手続きを怠り、保険料の納付自体を逃れようとするケースです。
この場合、給与明細に厚生年金保険料の控除項目自体がないか、異常に低い額しか記載されていないことがあります。
これらの手口は、法令違反であり、会社にとって大きなリスクを伴う行為です。
なぜ会社は折半しないことがある?(会社側の事情や誤解)
会社が厚生年金保険料を適切に折半しない背景には、さまざまな事情や誤解が考えられます。
まず考えられるのが経営状況の悪化です。会社の経営が厳しい場合、人件費削減の一環として、社会保険料の負担を減らそうとすることがあります。もちろんこれは違法行為です。
他にも、社会保険制度への知識不足があり、誤った計算や手続きを行ってしまうことがあります。悪意はなくとも、結果的に折半が正しく行われない事態が生じることがあります。
また、社会保険料を従業員の福利厚生や将来への投資と捉えず、単なる「コスト」として見て、削減対象にしようとする意識がある会社も存在します。
当然ながら、これらの事情はいずれも会社側の問題であり、従業員が不利益を被る理由にはなりません。
厚生年金保険料が気になるあなたへ
年金はいくらもらえて、いくら不足する?将来の資金準備は、まず大まかに将来を想定するところから始めましょう。
マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶40代からの老後資金作り:30分の無料オンラインセミナー
厚生年金保険料が折半されていない場合の対処法
もし厚生年金保険料が正しく折半されていない疑いがある場合、放置せずに適切に対処することが重要です。
まずは冷静に証拠を集める(給与明細、就業規則など)
会社に確認する前に、まずは自身で証拠を整理しましょう。
まず確認すべきは給与明細と「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額決定通知書」です。過去数ヶ月分、可能であれば1年分以上の給与明細を保管し、控除額の変動などを確認しましょう。
次に、就業規則を確認します。会社の就業規則に社会保険に関する規定が記載されている場合があります。
入社手続きの際にもらう雇用契約書が手元にある場合は、社会保険加入に関する記載があるか確認しておくとよいでしょう。これらの書類は、後の話し合いや相談の際に根拠となります。
会社の人事・経理担当者に確認する際のポイントと伝え方
書類をそろえたら、まずは会社の人事・経理担当者に冷静に確認することが大切です。
「給与明細の厚生年金保険料の控除額が、自分で計算した額と異なるようです。標準報酬月額と保険料率で計算すると〇〇円になるのですが、間違っていないでしょうか?」など、事実に基づいた具体的な数字を挙げて質問しましょう。
口頭でのやり取りだけでなく、メールなど形に残る方法で質問を送り、返答も書面で求めるようにするのがおすすめです。
外部の専門機関に相談する
会社との交渉が難しい場合や、より専門的な見解が必要な場合は、外部の専門機関に相談することも検討しなければいけません。
年金事務所(日本年金機構)
厚生年金保険の運営主体である日本年金機構の年金事務所は、公的な機関であり、客観的な情報提供や調査を行うことができます。
厚生年金保険料に関するもっとも直接的な相談窓口であり、会社が保険料を滞納している場合や、社会保険に未加入の疑いがある場合も相談できます。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働者の権利保護を目的とする公的機関です。
賃金の未払い、不当解雇、労働条件の不備など、労働基準法違反に関する相談がメインとなりますが、社会保険料の不適切な控除も、結果的に賃金の問題として扱われることがあります。
年金事務所のように直接的に年金保険料の問題を解決する機関ではないため、あくまで「賃金からの不当控除」という側面での相談が中心となります。
弁護士や社会保険労務士などの専門家
より個別具体的な対応や法的な手段を検討する場合には、社会保険労務士や弁護士といった専門家への相談が有効です。
- 社会保険労務士:社会保険や労働問題の専門家です。複雑な社会保険料の計算、会社への交渉代行、年金事務所や労働基準監督署への手続きサポートなど、専門的なアドバイスや実務的な支援を期待できます。
- 弁護士:会社との交渉がこじれた場合や、損害賠償請求など法的な紛争に発展する可能性がある場合に相談します。法的な観点から最適な解決策を提案し、訴訟などの代理人となることができます。
これらの専門家は初回無料相談を実施している場合もあるため、困った時は、気軽に相談してみるとよいでしょう。
折半されていない状態を放置するリスクとは?
厚生年金保険料が適切に折半されていない状態を放置することは、従業員と会社の双方にとって大きなリスクを伴います。
従業員側のデメリット
将来の年金受給額への影響
厚生年金保険料が適正に納付されていない場合、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性があります。これは、年金額がこれまでの保険料納付額や期間に基づいて決定されるためです。
正規の保険料が納付されていなければ、記録上の標準報酬月額が低くなったり、加入期間が短縮されたりする恐れもあります。
過払い分の損失
もし会社が従業員から本来よりも多くの保険料を徴収している場合、その過払い分は従業員の損失となります。この過払い分は本来であれば賃金として受け取るべきお金であり、返還を求める権利があります。
傷病手当金や出産手当金への影響
厚生年金保険と合わせて加入する健康保険も同様に標準報酬月額に基づいて給付額が決定されるため、保険料が適正でないと、病気や出産で休業した際の給付金が少なくなる可能性があります。
会社側のデメリット
追徴金、延滞金
会社が厚生年金保険料の納付を怠ったり、不正に過少申告していたりした場合、日本年金機構から過去に遡って不足分の保険料を追徴されます。これには延滞金も加算されるため、会社の金銭的負担は非常に大きくなります。
社会的信用の失墜
社会保険料の不適切な扱いは、企業の法令遵守意識の欠如と見なされ、社会的信用を大きく損ないます。従業員からの信頼を失うばかりでなく、将来の人材採用にも悪影響が出る可能性があります。
罰則
悪質なケースでは、法律に基づき罰則が科される可能性もあります。例えば、社会保険料の不正な徴収や納付逃れは、刑事罰の対象となることがあります。
税務調査での指摘
社会保険料の不適切処理は、税務調査の際に指摘事項となり、会社経営の健全性が疑われる原因にもなりかねません。
これらのリスクを回避するためにも、会社は法令を遵守し、適正な保険料を納付する義務があります。
厚生年金保険料の折半に関するQ&A
最後に、厚生年金保険料の折半に関するよくある質問に回答します。
Q. アルバイトやパートでも折半になりますか?
はい、アルバイトやパートの方でも、厚生年金加入条件を満たし、実際に加入している場合は保険料の折半の対象になります。
Q. 過剰に保険料を支払っていた場合、過去に遡って請求できますか?
会社が厚生年金保険料を適切に納付していなかった場合や、従業員から過剰に徴収していた場合には、時効の範囲内で不足分の納付や過払い分の返還を求めることができます。
年金事務所に相談し、過去の納付状況を調査してもらうことで、会社への指導や是正を求めることができます。
とはいえ、手続きには専門的な知識も必要になるため、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることをおすすめします。
まとめ
厚生年金保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する「折半」が義務付けられており、これは将来の年金受給に直結する重要なルールです。
もし「折半されていない」「計算が合わない」と感じた場合は、まずは誤解がないか確認し、次に冷静に会社の人事・経理担当者へ問い合わせてみましょう。それでも解決しない場合や、質問しにくい状況であれば、年金事務所、労働基準監督署、弁護士や社会保険労務士といった外部の専門機関へ相談しましょう。
厚生年金保険料の不適切な処理は、従業員の将来の年金受給額に悪影響を及ぼすだけでなく、過払い分の損失にもつながります。一方、会社にとっても追徴金や延滞金、社会的信用の失墜、さらには罰則といった深刻なデメリットがあります。
自身の厚生年金保険料について正しい知識を持ち、少しでも疑問を感じたら早めに行動を起こすことが、結果的に権利を守り、将来の安心を確保することにつながります。
≫あなたは老後にいくら必要?年収や資産から3分で診断
厚生年金保険料が気になるあなたへ
年金はいくらもらえて、いくら不足する?将来の資金準備は、まず大まかに将来を想定するところから始めましょう。
マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶40代からの老後資金作り:30分の無料オンラインセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。