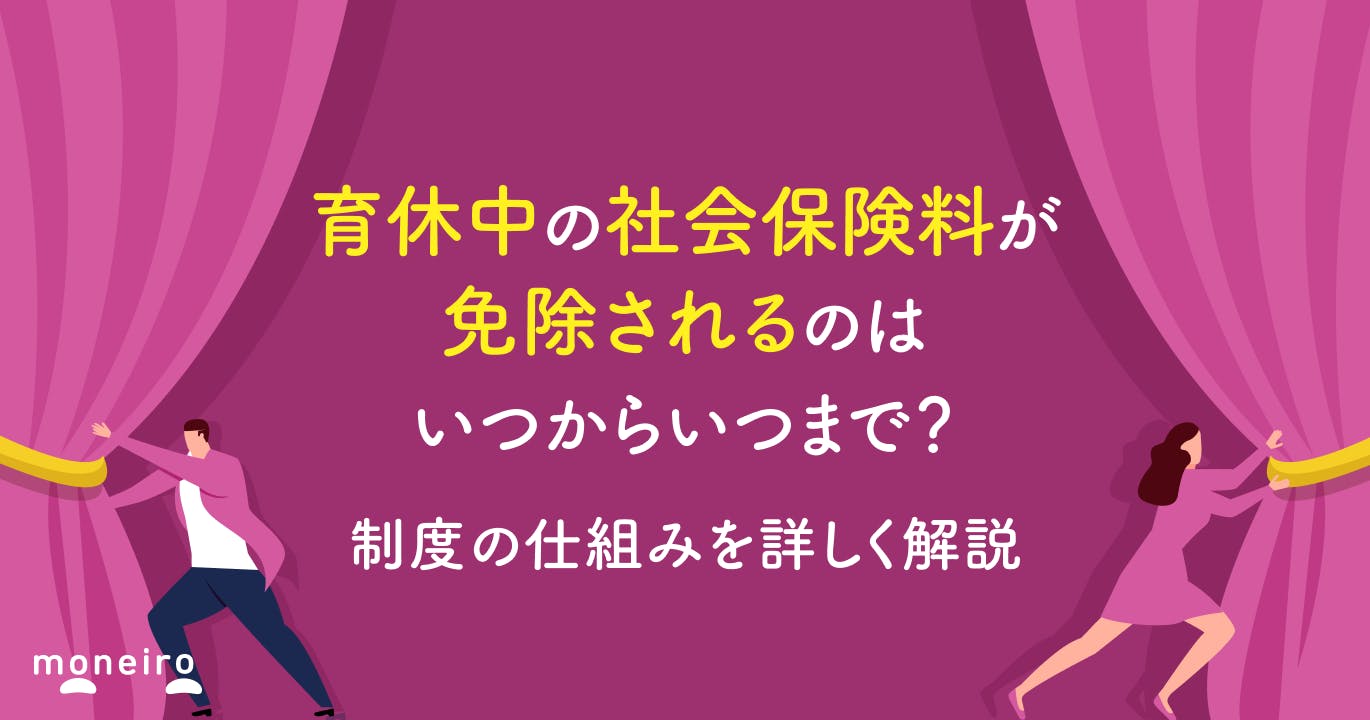育休中の社会保険料が免除されるのはいつからいつまで?制度の仕組みを詳しく解説
>>将来のお金はいくらかかる?あなたの必要額を3分で診断
育児休業中の家計のやりくりに不安を感じたり、お金の心配から育児休業の取得をためらったりしていませんか? 育児休業中には、さまざまな経済的支援制度が用意されており、その1つが社会保険料の免除です。
この記事では、育休中の社会保険料免除の条件や仕組み、手続きなどを詳しく解説します。この記事を参考に、安心して制度を利用できるようにしておきましょう。
- 育児休業中に免除される社会保険料や発生しない税金の種類
- 2022年10月からの育休中の社会保険料免除に関する要件の変更点
- 育児休業中の社会保険料免除の手続き方法
子育てのお金が気になるあなたへ
子育てや教育資金、住宅ローンなど将来の負担はさまざまです。この先必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
育休中は社会保険料が免除される
育児休業中は、給与が支給されない期間があるため、経済的な負担が増える可能性があります。これを軽減するため、社会保険料や一部の税金について、免除や非課税の措置が設けられています。これにより、休業前の手取り賃金と比較して、育児休業給付と社会保険料免除を合わせると、一定期間8割程度がカバーされることになります。
免除される(または発生しない)保険料・税金
育児休業中には、主に以下の保険料や税金が免除されたり、実質的に発生しなかったりします。
健康保険料
産前産後休業期間、育児休業期間(勤務先が認めた3歳未満までの育児休業期間を含む)、および産後パパ育休期間中については、事業主からの申し出により健康保険料の支払いが免除されます。この免除は、被保険者本人負担分と事業主負担分の両方に適用されます。
健康保険料が免除されたとしても、健康保険の給付は通常通り受けることができますので、医療費の心配をすることなく安心して育児に臨めます。
厚生年金保険料
健康保険料と同様に、産前産後休業期間、育児休業期間(勤務先が認めた3歳未満までの育児休業期間を含む)、産後パパ育休期間中は、事業主の申し出により厚生年金保険料の支払いが免除されます。この免除も、被保険者本人と事業主の双方に適用されます。
さらに重要な点として、厚生年金保険料が免除された期間も、将来の年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われるため、年金額が減額される心配はありません。
これは、育児によるキャリアの中断が将来の年金受給に不利にならないように配慮された措置です。
雇用保険料
雇用保険料は、給与が支払われる場合にその額に応じて発生する保険料です。そのため、育児休業中、産後パパ育休中、介護休業中など勤務先から給与が支給されない場合は、雇用保険料の負担は発生しません。
また、育児休業給付金や介護休業給付金は雇用保険から支給されますが、これらの給付金は非課税所得として扱われ、雇用保険料が課されることはありません。
所得税
所得税及び復興特別所得税は、収入に対して課税されるものです。上述のとおり、育児休業給付金や介護休業給付金は非課税であるため、これらの給付金から所得税等が差し引かれることはありません。
また、育児休業中に会社からの給与が支給されない場合、所得が発生しないため、所得税も実質的に発生しないことになります。そのため、所得税についても育休中の負担はありません。
免除されない税金
育児休業中であっても、一部の税金は引き続き支払いが必要です。
住民税
住民税は、前年の所得に基づいて税額が決定され、今年度課税される仕組みです。そのため、育児休業期間中であっても、前年に所得があった場合は、今年度の住民税を支払う必要があります。
ただし、育児休業給付金や介護休業給付金は非課税であるため、これらの給付金は次年度の住民税の算定対象となる収入には含まれません。したがって、育休中の収入が給付金のみであれば、次年度の住民税は大幅に軽減されることになります。
育児休業期間中の住民税納付が困難な場合、申請により1年間に限り納付猶予してもらえます。猶予された住民税は仕事に復帰後に支払います。
固定資産税
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産の所有者に対して課される地方税です。この税金は所得の有無に関わらず、固定資産を所有している限り発生します。
そのため、育児休業中であっても、固定資産を所有している場合は、引き続き固定資産税を支払う必要があります。育児休業による免除は適用されません。
社会保険料が免除される期間はいつからいつまで?
次に、育児休業中の社会保険料の免除期間について詳しく解説します。
免除期間は原則「育休開始月から終了月の前月まで」
健康保険・厚生年金保険の社会保険料が免除される期間は、原則として、「育児休業等を開始した日が含まれる月から、その育児休業等が終了した日の翌日が含まれる月の前月まで」とされています。この免除措置は、子が3歳に達するまでの期間に適用されます。
例えば、1月15日に育児休業を開始し、7月10日に復帰した場合、免除の対象となるのは1月から6月までの社会保険料です。復帰月である7月は、休業終了日の翌日が含まれる月であるため、社会保険料が発生します。
社会保険料は翌月の給与から天引きされるため、実際に支払いが発生するのは給与支給が始まる8月からです。
子育てのお金が気になるあなたへ
子育てや教育資金、住宅ローンなど将来の負担はさまざまです。この先必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
2022年10月改正「育休中の社会保険料免除要件の見直し」要点
2022年10月1日、育児休業中の社会保険料免除要件が改正されました。この改正は、男女ともに仕事と育児を両立できるよう、より柔軟な育児休業の取得を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的としています。
主な変更点は、月額保険料の免除要件の拡充と、賞与にかかる保険料の免除要件の厳格化です。
月額保険料の免除要件が拡充
従来の育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までという免除要件に加え、2022年10月からは、育児休業等を開始した日の属する月内に14日以上(休業期間中の就業予定日を除く。土日等の休日も期間に含む)育児休業等を取得した場合も、当該月の保険料が免除されるようになりました。
この変更により、月の途中で育児休業を開始しても、その月に一定期間の休業があれば、その月の社会保険料が免除される可能性が高まります。また、2022年10月1日施行の「産後パパ育休(出生時育児休業)」も、この保険料免除の対象となります。
賞与にかかる保険料の免除要件が厳格化
2022年10月以降、賞与にかかる社会保険料の免除要件が変更され、厳格化されました。
具体的には、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、賞与保険料が免除の対象となります。1ヶ月を超えるかどうかは暦日で判断され、土日等の休日も期間に含みます。
例えば、賞与支給月に1ヶ月以内の育児休業を取得した場合、その月の賞与にかかる社会保険料は免除されません。この変更により、賞与月の短期的な育休では免除の恩恵を受けられなくなるため、育休期間の計画には注意が必要です。
社会保険料免除の手続きと必要書類
育児休業等期間中の社会保険料の免除を受けるためには、所定の手続きが必要です。流れや必要書類についても確認しておきましょう。
手続きは会社(事業主)が行う
健康保険・厚生年金保険の社会保険料免除の手続きは、被保険者本人ではなく、被保険者を雇用している事業主が年金事務所または健康保険組合に対して行います。
事業主は「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」または「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することで、社会保険料の免除措置が適用されます。
手続きの流れと提出書類
社会保険料免除の手続きは、以下の流れで行われます。
- 被保険者から事業主への育児休業等の申出:育児休業を取得する従業員は、会社に育児休業を申し出ます。
- 事業主による提出書類の作成:事業主は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を作成します。産前産後休業の場合は「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を提出します。
- 提出先:作成した申出書を、事業所の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合に提出します。
これらの手続きを通じて、社会保険料の免除が適用されます。
育休中の社会保険料免除に関するQ&A
育児休業中の社会保険料免除について、よくある質問とその回答をまとめました。
Q. 育休で社会保険料が免除になる条件は?
育児休業中の社会保険料免除の主な条件は以下の通りです。
- 休業の種類:産前産後休業、育児休業(勤務先が認めた3歳未満までの育児休業期間を含む)、産後パパ育休(出生時育児休業)が対象です。
- 期間:原則として、育児休業を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間が免除対象です。ただし、子が3歳に達するまでの期間に限られます。2022年10月以降は、短期間の育児休業でも休業を開始した日の属する月内に14日以上育児休業等を取得した場合、当該月の月額保険料が免除されます。
- 賞与保険料:2022年10月以降、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合にのみ免除されます。
これらの条件を満たすことで、社会保険料の免除を受けることができます。
Q. 月の途中で育休を開始した場合、その月の社会保険料はどうなる?
育児休業中の社会保険料は、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで、原則として免除されます。つまり、月の途中で育休を開始した場合でも、その後も育休を継続するのであれば、その月の社会保険料は免除の対象となります。
ただし、育児休業の開始月と終了月が同一の場合に限り、月内に14日以上の育児休業を取得していることが免除の条件となります。この「14日以上」には、土日などの休日も含まれます。
まとめると、以下のようになります。
- 育休開始月と育休終了月が異なる場合:育休開始月の社会保険料は原則として免除されます。
- 育休開始月と育休終了月が同一の場合:その月のうちに14日以上育休を取得していれば、社会保険料が免除されます。
Q. いつから育休を取得すると一番お得?
「一番お得」という表現は個人の状況によって異なりますが、社会保険料の免除という観点からは、以下の点を考慮して育休の開始時期を検討するとよいでしょう。
月額保険料の免除
- 2022年10月以降の改正により、月の途中で育休を開始しても、その月内に14日以上育児休業を取得すれば、その月の社会保険料が免除されます。そのため、短期間の育児休業を取得する場合など、月の初日に育休を開始しなくても、14日以上の休業期間を確保できる月の途中から開始することで、その月の免除の恩恵を受けることができます。
- 例えば、特定の月に13日の育児休業を取得予定の場合、1日増やして14日取得すれば、1ヶ月分の免除を受けられるます。また、1日から育休開始予定の場合、1日増やして(または1日ずらして)前日(前月末日)から開始すれば、免除月を1ヶ月増やすことができます。
賞与保険料の免除
- 賞与にかかる社会保険料の免除を受けるには、賞与支給月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業を取得する必要があります。そのため、賞与が支給される月に育休を計画する場合は、その月の末日を越えて1ヶ月以上の連続した休業となるように取得することで、賞与にかかる社会保険料も免除の対象となります。
- 例えば、6月に賞与が支給される会社であれば、5月下旬から育休を開始し、6月末日を跨いで7月上旬まで育休を取得することで、6月分の賞与保険料の免除を受けられます。
これらの制度を最大限に活用するためには、自身の賞与支給月、会社の育児休業制度などを確認し、人事担当者と相談しながら最適な育休期間を計画することが重要です。
まとめ
育児休業は、お子さんの成長を間近で見守り、家族の絆を深める貴重な期間です。しかし、その間の経済的な不安は、育休取得をためらう大きな要因となりがちです。
本記事で解説したように、日本では、育児休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料が免除されるほか、雇用保険料や所得税も実質的に発生しないように制度が整備されています。
また、2022年10月には社会保険料の免除要件が見直され、短期間の育児休業でも14日以上休業すればその月の保険料が免除されるなど、より柔軟な育休取得に対応できるようになりました。一方で、賞与にかかる保険料の免除は「1ヶ月を超える連続した育休」が条件となるなど、一部厳格化された点には注意が必要です。
これらの制度を理解し、計画的に育児休業を取得することで、経済的な心配を軽減し、育児と仕事の両立を図ることができます。社会保険料の免除手続きは原則として事業主が行いますが、不明な点がある場合は会社の人事担当者などにも相談しながら計画的に進めていくとよいでしょう。
>>将来のお金はいくらかかる?あなたの必要額を3分で診断
子育てのお金が気になるあなたへ
子育てや教育資金、住宅ローンなど将来の負担はさまざまです。この先必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。