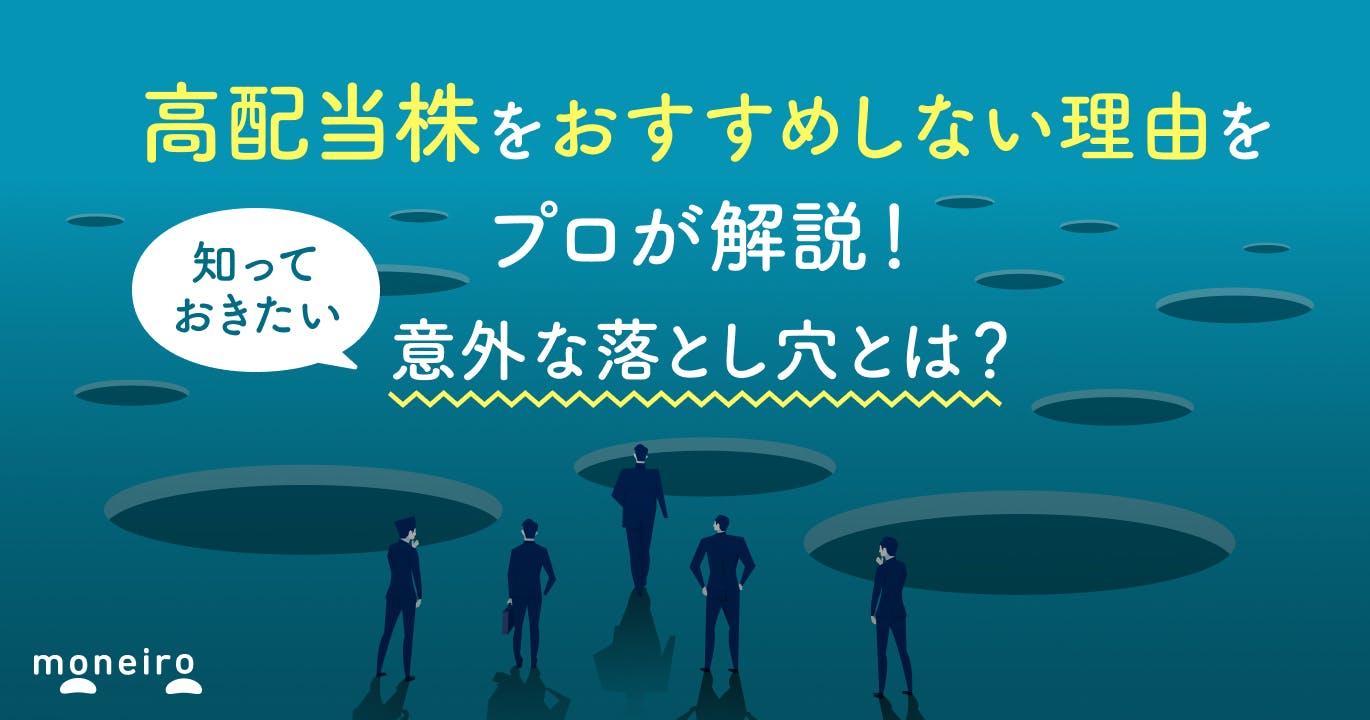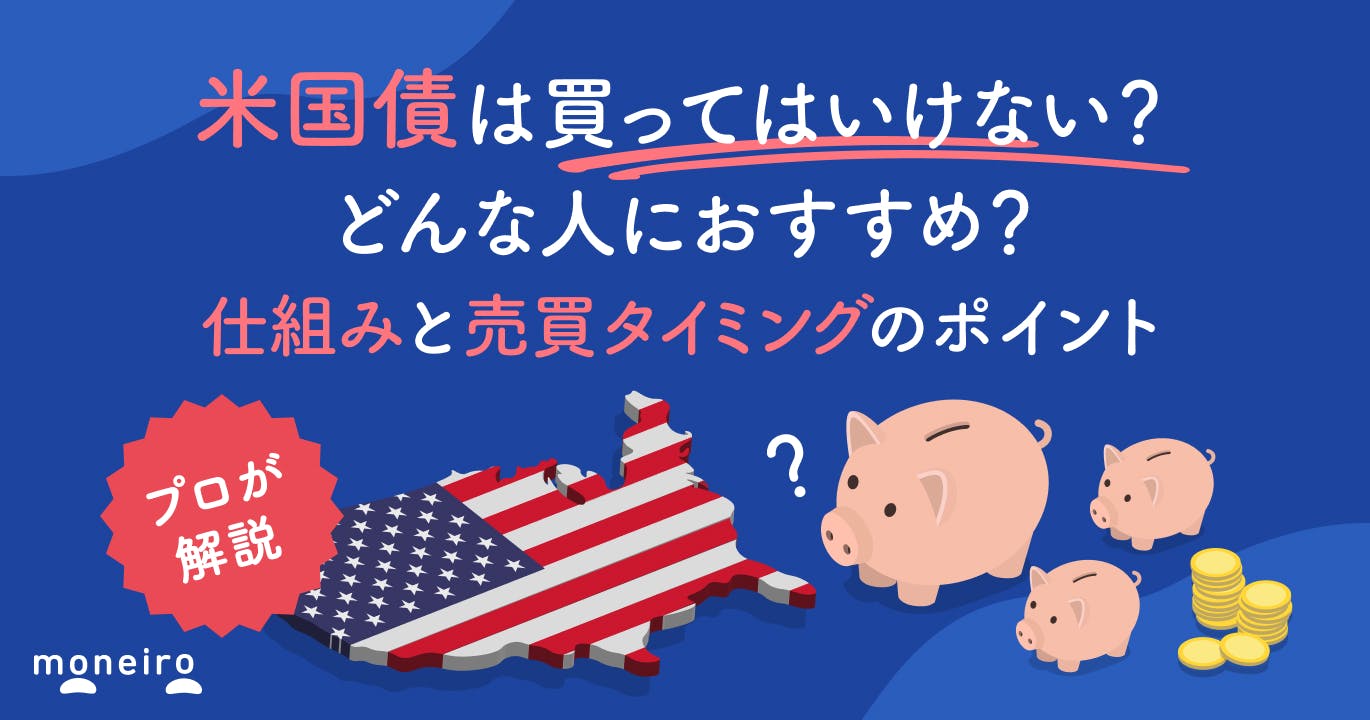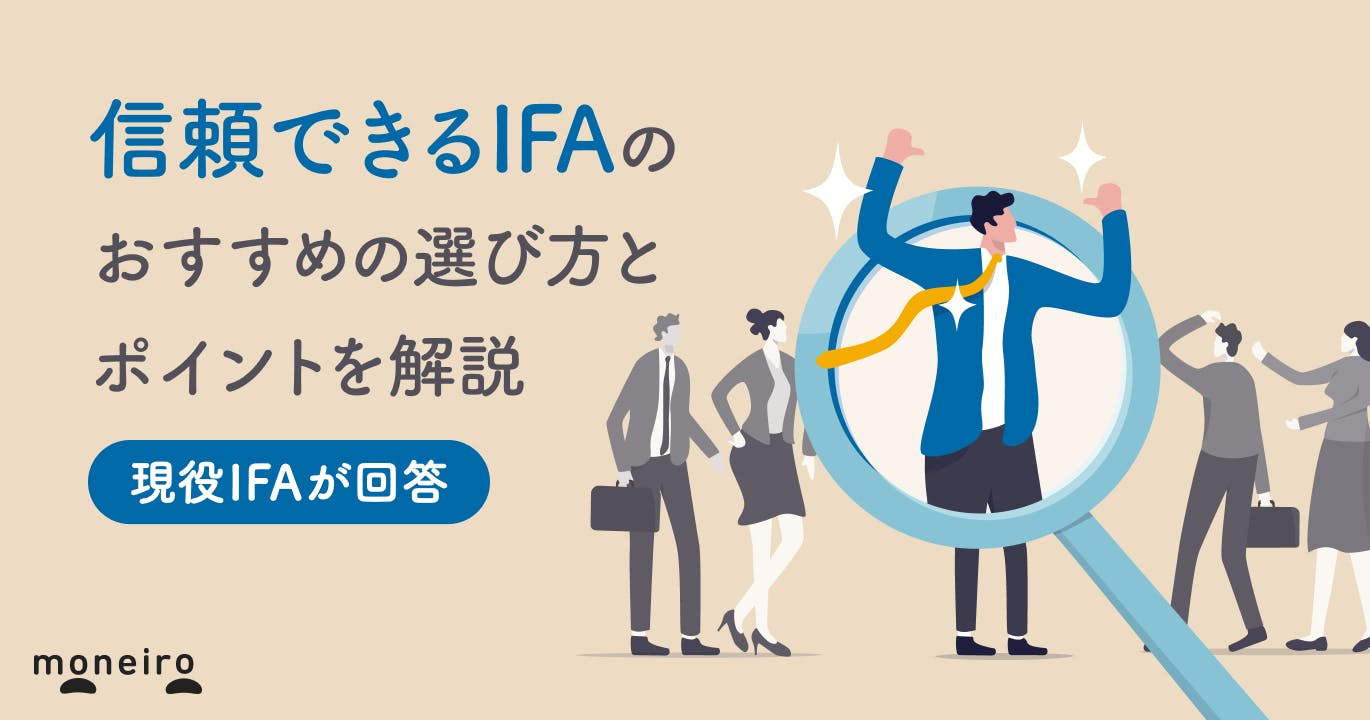高配当株はおすすめしない?意外な落とし穴を投資のプロが解説!知っておきたいリスク
≫自分に合う投資がわかる!3分投資無料診断
「高配当株が良いって聞いたけれどおすすめしない理由はある?」「魅力的に見えるけれどリスクはある?」と高配当株のデメリットや注意点を知りたい人も多いのではないでしょうか。
高配当株とは配当利回りが高い銘柄のことをいいます。配当利回りは「1株あたりの年間配当金額÷1株あたりの現在値」で算出できます。
一見魅力的に見えますが、配当利回りは企業の業績に大きく影響されるため、業績悪化の場合や株価下落があった場合、減配・無配になる可能性があります。
本記事では「高配当株をおすすめしない理由を知りたい人」に向けて、知っておきたい高配当株の注意点についてプロがわかりやすく解説します。
- 高配当株とは、配当利回り(%)が比較的高い水準にある株式のこと
- 高配当株をおすすめしない理由は「実は配当だけでは資産が増えにくい」「配当が減るリスクがある」など
- 要注意な高配当株の特徴は「一時的に配当利回りが高くなっている」など
高配当株への投資が気になるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:専門家にスマホで直接相談
高配当株とは?知っておきたい基本知識
まずは高配当株の基本知識について、詳しく見ていきましょう。
高配当株とは
高配当株とは、配当利回り(%)が比較的高い水準にある株式を指します。配当利回りは以下の計算式を使って計算します。
例えば、1株あたりの配当金が50円、株価が1000円の場合、配当利回りは5%となります。
なお、配当利回りが何パーセント以上であれば高配当株といえるのか、明確な基準はありません。
東証プライム市場の2025年2月月中における単純平均利回り(1株当たり平均配当金を単純株価平均で割ったもの)は2.31%です。
そのため、この数値を超えていれば、比較的高配当な銘柄といえるでしょう。
(参考:株価平均・株式平均利回り | 日本取引所グループ|株式平均利回り(2025年2月))
(参考:単純平均利回り | 三菱UFJ eスマート証券(旧社名:auカブコム証券))
高配当株が注目される背景
日本では長期にわたり低金利政策を続けており、銀行預金などでは十分な利息を得にくい状況です。
その結果、比較的安定した収益が期待できる高配当株に、多くの投資家の関心が集まっています。
かつて、株式投資を対象商品とする一般NISAは、非課税保有期間が5年と限られていましたが、2024年から始まった新NISA(新しいNISA)では「成長投資枠」に仕組みが引き継がれ、非課税保有期間が無期限となりました。
これにより、企業が配当金を還元し続ける限り、要件を満たせば非課税で配当金を受け取り続けることができるようになったのも、高配当株が注目される一因といえます。
高配当株への投資をおすすめしない理由【プロが解説】
配当利回りが高い高配当株は一見魅力的に見えますが、実はリスクや落とし穴があります。
高配当株に投資をする際は、以下の点をきちんと理解することが大切です。
配当だけでは資産が増えにくい
成長段階にある企業は利益の多くを再投資に回し、事業規模の拡大や株価上昇を狙う傾向があります。
一方、高配当を重視する企業は、成長投資へ回せる資金が限られがちです。長期的に株価が伸びにくくなり、売却益を得る機会が減る可能性があります。
たとえ配当収入があっても、株価上昇の恩恵が小さい場合は総合的なリターンが限定的になるかもしれません。
配当がなくなる、減るリスクがある
高配当株だからといって、その配当利回りや金額がいつまでも保証されるわけではありません。景気や企業業績が悪化すれば、減配(配当金が減る)や無配(配当金がゼロになる)に転じることもあります。
また、高い配当利回りが続いていたとしても、突然配当が大きく減れば株価が急落するリスクがあります。
このように、高配当株とは安定的とは言い難い面があり、今後の投資先の企業業績や企業を取り巻く経済情勢などを頻繁に確認する必要があります。
高配当株のみでは効率的に資産形成できない
高配当株のみでは効率的な資産形成が難しい理由として、配当にかかる税金が複利効果を損ねてしまう点が挙げられます。
運用で得た利益を再度投資されることで利益がさらに利益を生み、資産が効率的に増える効果のこと
配当には20.315%の税金が課されるため、受け取った配当金を再投資する場合に課税分だけ原資が減ってしまいます。その結果、利益が雪だるま式に増えていく複利のメリットが受けにくくなるでしょう。
投資信託であれば、分配金を自動で再投資できる仕組みが利用できるケースが多く、課税によるロスを抑えられます。こうした仕組みと比較すると、高配当株はどうしても再投資時に不利になりがちです。
NISAの成長投資枠で運用すれば配当金は非課税になります。しかし、成長投資枠はすべて使い切ったとしても1200万円が上限です。
例えば、配当利回り5%の銘柄に投資しても、年間60万円(1200万円×5%)までしか非課税の配当を受け取れません。
より大きな配当金を得たい場合、NISAの成長投資枠の非課税保有限度額を超える投資金額を用意する必要があります。
買ってはいけない?避けた方が良い高配当株の特徴
高配当株の中でも、以下の特徴に当てはまる銘柄には注意が必要です。
配当利回りが異常に高い
配当利回りが極端に高い銘柄には慎重になるべきです。
配当利回りは「配当利回り(%)=配当金÷株価×100」で計算されるため、株価が大きく下がった場合でも配当利回りは上昇します。
株価の下落が原因で配当利回りが高くなっている銘柄は、業績不振や将来の不安材料などネガティブな要因による株価低迷が背後にあるかもしれません。
また、株主をつなぎとめるために無理な配当利回りを堅持しているかもしれません。
高配当に目を奪われる前に、なぜその利回りになっているのかをしっかり調べましょう。
一時的に配当利回りが高くなっている
一時的に配当利回りが高くなっている場合、何らかの事情で株価が急落しているというネガティブな要因と、増配というポジティブな要因に分かれます。
株価が暴落している場合、業績が悪化しているニュースが報じられた、不祥事があったなどの理由が考えられるでしょう。
一方、企業業績が良好だった、あるいは会社の創立や創業などを記念して行われる記念配当により、一時的に増配が行われることも考えられます。
しかし、記念配当は一時的なものに過ぎません。業績連動による増配も、下振れすれば減配になってしまうかもしれません。
業績予想や企業分析に慣れていない投資初心者のうちは、配当利回りが不安定な銘柄は避けるべきでしょう。
営業利益や経常利益が減少傾向にある
営業利益や経常利益が減少傾向にある高配当株は、配当利回りが魅力的でも注意しなければなりません。なぜなら最終的に利益が安定しなければ、減配や無配になるリスクが高いためです。
営業利益とは本業の儲けを表す利益、経常利益は営業利益に営業外収益(受取利息など)やマイナス要因である営業外費用(支払利息など)を反映させた利益を指します。
企業の配当金の原資は「経常利益から法人税や消費税を控除して残った金額を指す純利益」ですが、土地の売却や火災による損失といった臨時の出来事に左右されてしまいます。
そのため、配当金狙いの投資家は、臨時の影響を受けない営業利益と経常利益をチェックし、減少傾向にある銘柄は避けるべきでしょう。
高配当株へ投資する時におさえておきたいポイント
現在配当利回りが高い状態でも、企業の業績次第で減配・無配になる可能性もあります。配当金が継続的に続くのかという視点を持つことが大切です。
高配当株へ投資をする際は以下の3つのポイントを確認しましょう。
①配当性向
配当性向とは、その期の純利益のうちどれくらい配当金を支払っているかをパーセンテージで表したもので、以下の計算式で計算をします。
配当性向が高い企業は、純利益から多くの配当金を還元してくれる投資家にとって良心的な会社と考えてしまうかもしれません。
ただし、配当性向が高い会社は無理をして配当金を出している可能性があります。配当性向は業種や会社規模にもよりますが、配当性向が100%を超えている場合は注意が必要です。
企業が事業活動で得たお金のうち、自由に使用できるお金であるフリーキャッシュフローが潤沢な可能性もあるため、企業業績を見て配当性向が高い理由を確認する必要があります。
また、配当性向がマイナスになっている場合は、当期純損失だったにもかかわらず配当金を出していることを指すため注意が必要です。
②過去の配当実績
過去の配当実績を確認し、連続増配が見られるようであれば、投資家に配当を還元しようという意識が高い企業と考えられます。
なかには20年、30年と連続増配をしている企業もあります。安定した配当金を狙いたい場合は、こうした企業を選ぶと良いでしょう。
ただし、連続増配と高配当を両立しているケースは限られるため注意しましょう。
③企業の業績の動向・成長性
企業の収益がなければ、配当金を継続的に支払う原資は生まれません。長期にわたって安定的に配当金を受け取りたい場合は、投資先企業が継続的に成長していることが前提となります。
そのため、企業業績の動向や、将来性をあらかじめ確認しておくことは欠かせません。
また、企業の不祥事や災害などによって大きな損失を被る可能性があります。投資先企業や関連する業界の情報は、常に収集しておきましょう。
高配当株への投資をおすすめしない人
高配当株投資は、安定した配当金を受け取れる反面、受け取った配当金を自身で再投資しなければ複利効果が働きにくくなります。
複利効果は運用期間が長いほど大きくなる傾向があるため、老後資金準備など長期的な投資目標を立てている場合はあまり向かないでしょう。
また、減配や無配のリスクを避けるためには、企業の業績や銘柄を分析する必要があります。そうした手間を省きたい人や、分析が得意ではない投資初心者にも、高配当株は向いていないかもしれません。
長期・分散投資なら「投資信託」がおすすめ
- 将来資金を準備したい
- リスク分散をしたい
と考えている人には、投資信託がおすすめです。
高配当株と投資信託の特徴を比較しながら解説します。
投資信託のメリット・デメリット
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を専門家が運用する金融商品です。
少額から複数の株式や債券といった金融商品に分散投資を行うことができ、長期投資によって複利効果も期待できます。
さらに積立投資も組み合わせて購入価格を平準化すれば、初心者でもリスクを抑えた運用が可能です。
一方、運用成果によっては元本割れのリスクがあります。さらに信託報酬などのコストがかさむ点もデメリットといえます。
投資信託も株式投資と同様、投資目的やどのくらい損失に耐えられるかなどを踏まえたリスク許容度を踏まえ、慎重に商品選びを行うことが大切です。
投資信託の選び方
投資信託を選ぶ際には、まず投資目的を明確にすることが大切です。長期的な資産形成なのか、短期的な収益を狙うのかで商品選びが変わります。
次に、リスク許容度に応じて、株式中心か債券中心かといった資産配分を検討しましょう。
また、商品を選ぶ時は基準価額(投資信託の価格)で現在の価値を確認し、騰落率(基準価額の値上がりや値下がり率)で過去の運用成績も確認します。
騰落率は将来の値動きを約束するものではありませんが、資産の成長期待度を確認する際の参考になります。
純資産残高も投資信託を選ぶ際に重要なポイントです。純資産残高とは、投資信託に組み入れている投資商品を時価評価したもので、その投資信託の規模を表します。
純資産残高が30億円未満になると繰上償還といって、運用が終了してしまう可能性があります。純資産残高は、投資信託の目論見書や運用レポートで確認することが可能です。
Q.オルカンやS&P500だけでリスク分散は可能?
オルカンは全世界に投資する投資信託ですが、その構成の多くを米国株が占めています。一方、S&P500は構成銘柄の時価総額(株価×発行済株式数)を指数化した指標です。時価総額の合計が米国株式市場全体の約80%を占めるため、その影響力は極めて大きいでしょう。
そのため、オルカンやS&P500だけでは、投資先が米国に偏っており、十分な分散投資によるリスク軽減効果が働いているとはいえません。
さらに債券や商品、不動産といった資産や米国以外の国への投資も組み合わせることで、より相場の変動に対する耐性が高い資産配分になります。
投資判断に迷ったら専門家に相談を
高配当株は配当金による安定した収入が期待できる一方、株価下落リスクにどう備えるかが重要になります。また、配当金は必ず支払われるわけではなく、減配・無配になるリスクもあります。
高配当株が本当に自身に合っている投資なのかどうかを知りたい方は、専門家に相談してみましょう。
自身の投資目標やリスク許容度を考慮した結果、高配当株よりも合っている投資先があるかもしれません。判断に迷う時こそ、専門家の知見を上手に活用することが大切です。
≫オンライン無料相談サービスを見てみる
まとめ
高配当株は配当利回りが高い銘柄で、配当収入が得られる魅力がある一方で、減配・無配になるリスクや、再投資時の課税などで総合的なリターンは限られる場合もあります。
また、高配当株は、企業業績や配当性向の確認が不可欠で、同業種や同規模に比べて極端な数値を示している銘柄は注意が必要です。
長期・分散投資を検討するなら、投資信託なども視野に入れましょう。投資判断に迷ったら、専門家への相談も有効です。
高配当株への投資が気になるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:専門家にスマホで直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください