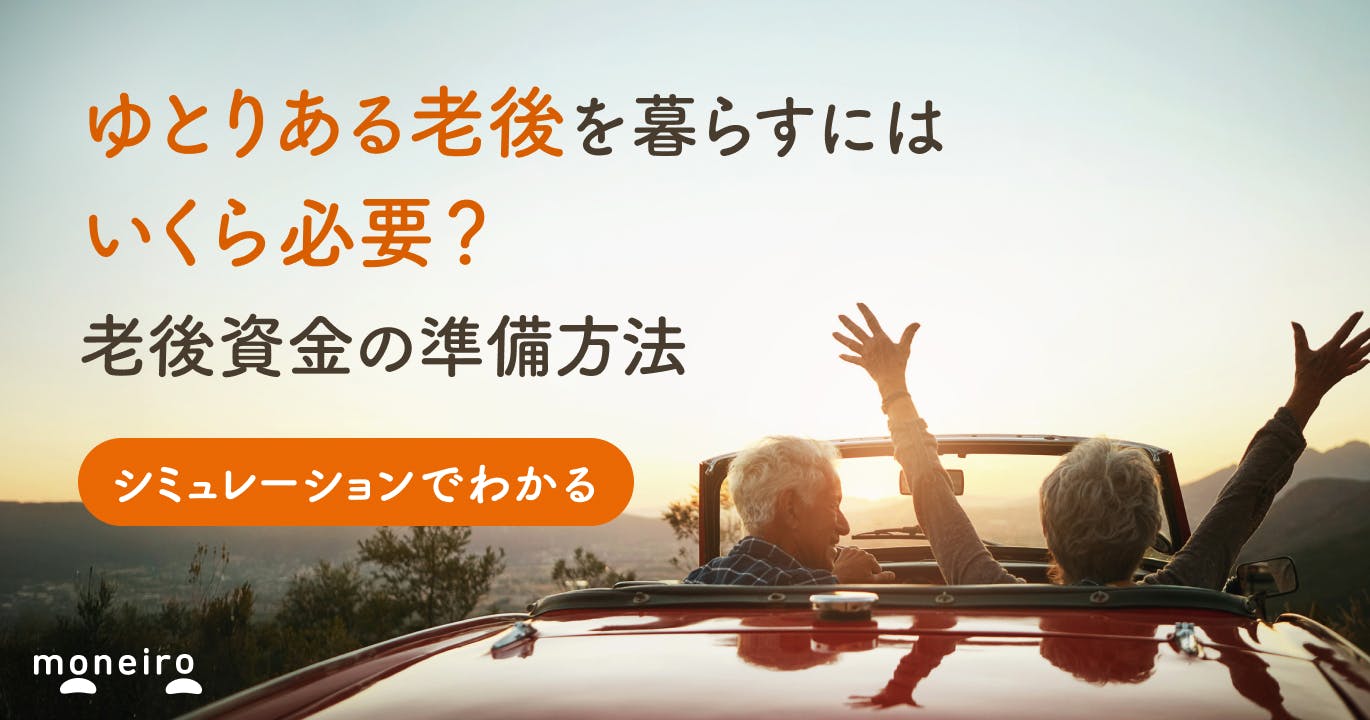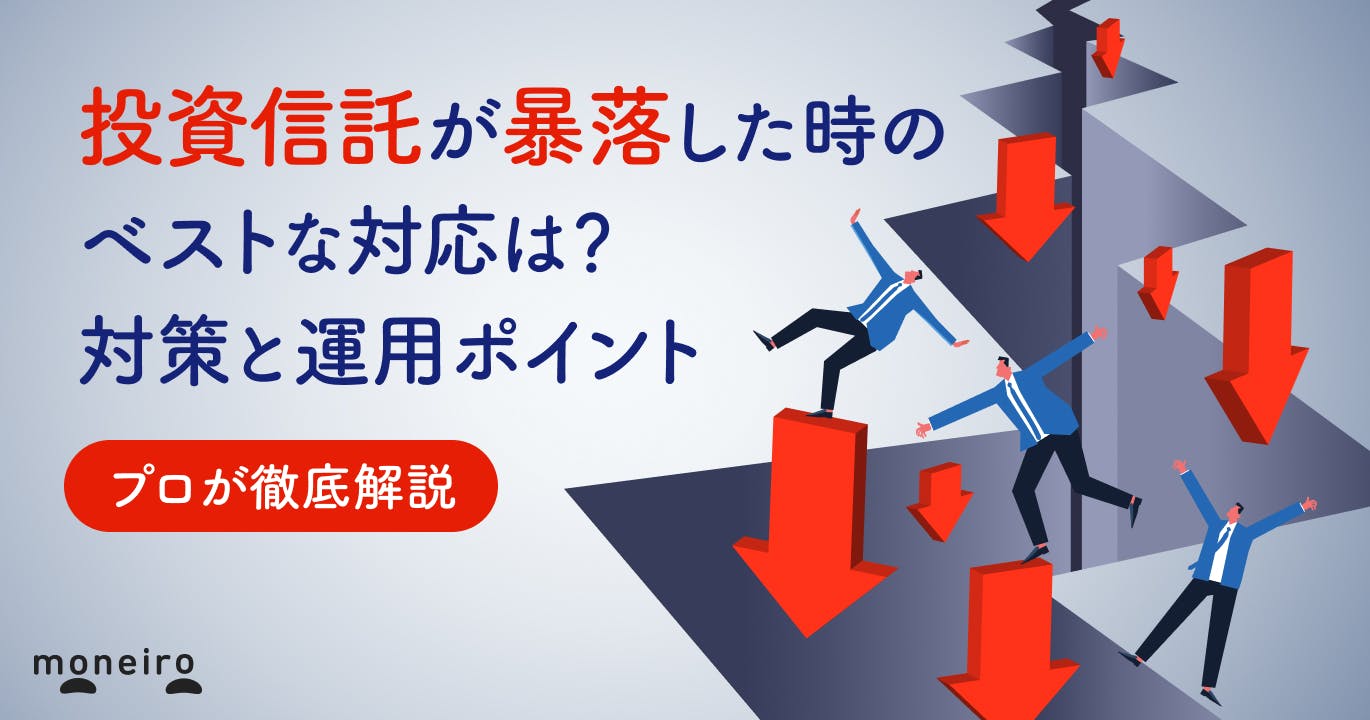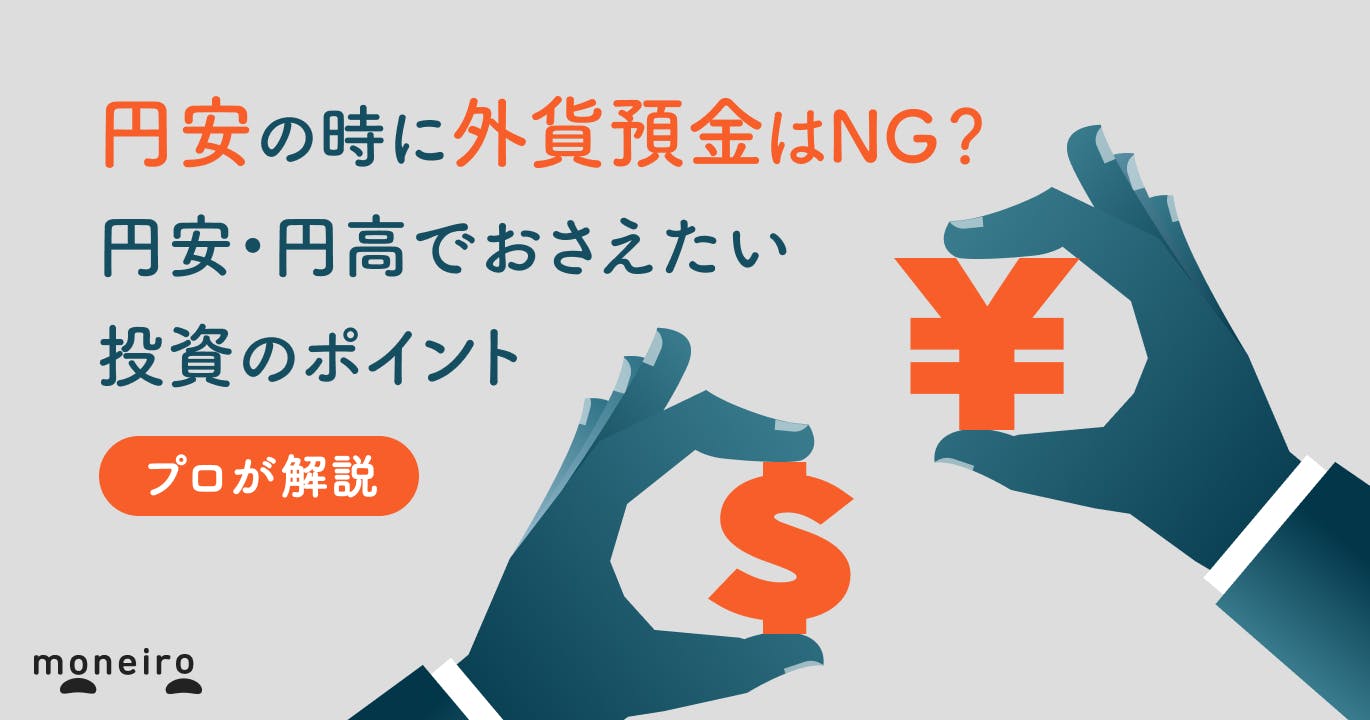インフレに強い資産とは?特徴や具体例、投資のポイントを解説
物価高で老後資金はいくら必要?いますぐシミュレーション
昨今の物価高で、家計が苦しくなったと感じている方もいらっしゃるでしょう。物価が上昇するインフレ時には、通貨の価値が目減りするため、インフレに強い資産(株式・金・不動産・コモディティ)などを保有することをおすすめします。
この記事では、インフレの仕組みや、初心者でも始めやすいインフレ対策のための資産運用について説明します。
- インフレになると物価が上がり家計が圧迫される
- インフレ時は通貨の価値が下がるため、実物資産や物価の上昇に合わせて価格が上がる資産を保有するのがおすすめ
- インフレ対策として投資を始める場合には少額から分散投資するのがよい
物価高が気になるあなたへ
物価高に対応し、将来のお金の不安をなくすために、まずは将来に必要な金額を把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶“世界株”だけに頼らないリスク分散の投資術:30分の無料オンラインセミナー
知っておきたいインフレの仕組み
まずは、意外と知らない人も多い「インフレ」の仕組みについて説明します。
インフレが発生する原因
インフレは「インフレーション」の略で、経済全体で物価水準が継続的に上昇し、貨幣価値が下落している状態のことで、需要が供給を大きく上回ったり、貨幣の流通量が増えすぎたりすると発生します。
近年では、2022年頃から世界的にインフレが進み問題となりました。大きな要因は、コロナ禍からの経済活動再開に伴う需要の急増に加え、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で原油や天然ガスなどのエネルギー供給が制約され、価格が高騰したことです。
また、サプライチェーンの混乱や、労働市場のひっ迫による賃金上昇圧力も、物価高騰につながりました。
このようなインフレを抑制するため、各国の中央銀行は金融引き締め政策を行います。具体的には、政策金利の引き上げや、量的引き締め(中央銀行が保有する資産の売却をして資金供給を減らす)などです。
金利が上がると、企業は設備投資を控え、家計も住宅ローンなどを利用しにくくなるため、経済活動が停滞し、需要が抑制されることで、インフレは鎮静化していきます。
インフレが家計や資産に与える影響
インフレが家計や資産に与える影響は大きく以下の2つです。
- 生活費が上昇し家計を圧迫する
- 資産が目減りしてしまう
それぞれについて解説します。
生活費が上昇し家計を圧迫する
インフレによる物価上昇のもっとも大きな影響と言えるのが、今まで購入できていた価格で買い物ができなくなることです。例えば、従来は100円で買えていたパンが、120円支払わないと買えなくなる、といったことが起こります。
昨今では円安の影響もあり原材料を含む輸入品の価格が上がっており、食料品や日用品、ガソリンなどの価格も上昇傾向にあります。
身の回りのさまざまな商品・サービスの値上がりが蓄積し、実際にこの数年で家計が苦しくなったと感じている方も多いでしょう。
資産が目減りしてしまう
インフレ時は相対的に通貨の価値が下がるため、現金を多く所有している場合は資産価値の目減りが大きくなってしまいます。
一方、インフレに付随して価値が上がる資産もあります。インフレが進行すれば、インフレの恩恵を受ける資産を所有する人と現金しか保有しない人の格差も拡大していくことが考えられます。
良いインフレと悪いインフレの違い
インフレは大きく「良いインフレ」と「悪いインフレ」に分類することができます。
良いインフレ(需要牽引型インフレ) は、経済全体の需要が供給を上回ることで起こります。
需要が増えることにより商品やサービスの物価は上がりますが、企業の業績が向上し、実質賃金も上昇します。賃金が上がると人々の購買意欲が高まり、さらに消費が拡大し、企業の売上・利益が増加するという好循環が生まれます。
一方、悪いインフレ(スタグフレーション) は、原材料費の高騰や供給制約など、供給側の要因によって起こります。
物価が上昇する一方で実質賃金は低下します。そして食料品や日用品などの値上がりが家計を圧迫し、消費が低迷します。
生活費が高騰する中で本業の賃金を上げるのも難しい状況となれば、資産運用や副収入の確保などの対策が必要になります。
インフレに強い資産の4つの特徴
ここでは、インフレに強い資産の4つの特徴を紹介します。
1.実物資産として価値を持っている
インフレに強い資産の特徴の1つに、実物資産であることが挙げられます。実物資産とは、現金や預金などの金融資産とは異なり、物理的な実体を持ち、それ自体に価値がある資産を指します。
代表的なものとして、不動産や金(ゴールド)・貴金属、美術品などが挙げられます。これらの資産は、インフレで貨幣価値が下落しても、モノとしての価値は比較的保たれるため、資産の目減りを防ぐ効果が期待できます。
特に不動産は、土地の価値に加え、賃貸収入もインフレに合わせて上昇する傾向がある点もインフレに強いと言われる理由の1つです。
他にも、供給量がコントロールされている高級時計やブランドバッグは需要が高く、通貨価値が下がる中でも2次流通でプレミアム価格で取引されることからインフレに強い資産であると言えるでしょう。
ビットコインはインフレに強いか
発行上限があり「デジタルゴールド」とも呼ばれるビットコインは、希少性の観点で価値があると言えます。2024年12月には時価総額約300兆円(発行上限2100万BTCベース)を超え、金やアメリカのビックテック企業に続く経済規模に達しています。
ただし、ビットコインは歴史が浅く、長期的な価値の安定性については未知数です。また、投機的な側面が強く、値動きが激しいのも特徴です。
今後、インフレが進行する時に、ビットコインの価格が上がるかは読めません。そのため、現段階ではインフレに強い資産と断言するのは難しいと言えます。
2.物価上昇に連動しやすい
物価上昇に連動しやすいこともインフレに強い資産の特徴の1つです。物価上昇に合わせて価格が上昇しやすい資産には株式・不動産・物価連動債・コモディティなどがあります。
例えば株式の場合、インフレ時には企業の売上や利益が増加する傾向にあり、それが株価に反映されることになります。特に資源高で価値が高まる鉱業や石油・石炭などのエネルギー関連銘柄はインフレに強いといわれています。
また、不動産も土地や建物の価値、賃料が物価とともに上昇する傾向があります。さらに物価の連動に合わせて元本や利率が調整される物価連動債や、物価に合わせて上昇する傾向にあるコモディティ(原油、貴金属、穀物などへの投資)もインフレ対策として有効です。
3.需要が安定している
需要が安定的であるものを扱う業種の株式もインフレに強い資産の1つです。
例えば、食料品(特に主食)や、トイレットペーパーなどの日用品、電気・ガス・水道といったエネルギー関連は、多少物価が上がったとしても需要が維持されやすいため、原材料費や人件費の上昇分を価格転嫁しやすいという特徴があります。
これらの業種は、提供価格を上げても売上が下がりにくく、収益を確保しやすいため、インフレ時にも強い傾向があります。
4.自国の通貨価値に依存しない
インフレ下では、物価の上昇により通貨の価値(購買力)は低下していきます。そのため、特に自国通貨の価値に依存しない資産を持つことが有効なインフレ対策になります。
例えば、インフレによって自国通貨の価値が下がる場合は、相対的に外国通貨の価値が高くなります。
そのため、日本円だけでなく米ドルやユーロといった外貨も分散して保有しておくことで、インフレ時でも全体的な資産の目減りを抑えることができます。
物価高が気になるあなたへ
物価高に対応し、将来のお金の不安をなくすために、まずは将来に必要な金額を把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶“世界株”だけに頼らないリスク分散の投資術:30分の無料オンラインセミナー
インフレ対策で投資する上でのポイント
インフレ対策に有効な資産を紹介しましたが、投資する上での注意点もあります。ここでは、インフレ対策で投資する上でのポイントをご紹介します。
初心者は積立投資が基本
経済の専門家でもインフレの発生を完璧に予測することはできません。そのため、「インフレが起きそうになってから対策しよう」と思ってもなかなかできるものではありません。そこで実践していきたいのが積立投資です。
特に投資初心者は投資のタイミングを見極めるのは困難です。毎月同じ金額を積立投資すれば、投資タイミングによるリスクを分散することができるため、インフレ対策だけでなく、相場の下落リスク対策としても有効に働きます。
また、積立投資を長期間にわたって行えば、複利効果で資産を効率的に増やすこともできます。
初心者でも始めやすい投資信託には株式を対象にしたものだけでなく、金や債券を対象にしたものもあり、さらにネット証券が提供している投資信託なら月100円~など少額からでも投資できるものもあります。
最初の一歩として投資信託の積立投資を始めるのはおすすめできる方法の1つです。
余剰資金で投資することを心がける
投資は余剰資金で行うのが基本です。
インフレ時は、株価や金などの実物資産の価格が上がりやすいため、少しでも多くの資金を投資に回したいと思うかもしれません。
しかし、投資で生活を圧迫しては本末転倒です。損失を抱えれば心理的に換金しにくくなる可能性もあるため、毎月の生活資金や近々で使う予定があるお金は、投資に回さないようにしましょう。
一般的に、病気やケガ・災害などの不測の事態に備え、生活防衛資金として生活費の3~6ヶ月分を現金で持っておくとよいと言われています。家族構成や仕事内容によって必要な生活防衛費の金額は異なるので、自分に必要な分を常に確保しておくようにしましょう。
インフレに備えるための具体的な投資法
最後に、インフレに備えるための具体的な投資法を説明します。
ひと口に投資法と言っても、現在の資産額や投資に使える金額によって、おすすめの方法は異なります。ここでは、下記の2つに分けて、インフレに備えるための投資法を解説していきます。
- 少額から始めたい人におすすめの投資法
- まとまったお金がある人におすすめの投資法
少額から始めたい人におすすめの投資法
インフレ対策として投資を始める場合、投資信託やREIT(不動産投資信託)、純金積立などが比較的少額から始められ、投資初心者にもおすすめです。
例えば投資信託では、株価指数に連動するインデックスファンドやコモディティ投資信託などがおすすめです。
加えて、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用すれば、運用益が非課税になるなどオトクに資産運用が行えます。
NISAは保有期間の縛りもなく、自由度が高い運用ができるのが魅力です。また、積立の設定をすれば、自動的に銀行口座から引き落として投資してくれるので手間もかかりません。
また、インフレ時に価格が上がりやすく、換金しやすい純金投資もおすすめです。純金は貴金属・地金会社や証券会社で積立投資ができ、ゴールドバーやコインで現物を受取ることもできます。
ネット証券の純金積立であれば月1000円から始められるところもあるので、投資初心者でも始めやすいでしょう。
まとまったお金がある人におすすめの投資法
まとまったお金がある人は、投資信託はもちろん、成長性の高い企業や高配当株などの個別株、現物不動産、金、物価連動債などにも分散投資するのがおすすめです。
個別株投資は、投資信託(インデックスファンド)に比べると価格変動のリスクが高くなりますが、そのぶん大きな利益を得られる可能性もあります。インフレ時に強い分野の企業に投資することで、ハイリターンを狙うのもよいでしょう。
また、インフレ時は不動産の価格も上がりやすいため、都心など不動産需要の高いエリアの物件に投資するのもおすすめです。賃貸に出すことで家賃収入を得られるほか、不動産価値が上がれば売却益を得ることも可能です。
不安な時は専門家への相談も検討を
最適なポートフォリオは、目指す資産額や現状の収支・資産、家族構成、ライフステージ、リスク許容度などによって異なります。そのため、すべての人にとって「これが最適」というものはありません。
例えば、子どもの将来に向けて教育資金を着実に備えたい人や、損失を抱えるのがストレスになりそうな人、あるいは50代以上のシニア層の人などは、リスクの高い投資商品は避けたほうがよいといえます。
反対に、独身の人、20~30代の人の場合には多少のリスクを取って株式への投資比率を高めて資産を増やしていく戦略が有効になる可能性があります。
ただし、最適な投資金額や分散の割合は人それぞれです。もし自分で投資の方針を決めることが難しい、あるいは不安があるという場合は、お金の専門家への相談も検討してみるとよいでしょう。
まとめ
インフレ時には物価が上がり、相対的に現金の価値は目減りします。このような事態に備えるために、日頃からインフレに強い資産を意識してポートフォリオに組み込んでおくことが大切です。
例えば、実物資産として価値がある金や不動産、インフレに合わせて価格が上がりやすい株式や投資信託などへの投資はインフレ対策として有効に働きます。
また、投資をする際は分散投資を徹底するようにしましょう。1つの資産に偏らず、複数の投資先に投資を行うことで一気に資産を減らすリスクを抑えることができます。
さらに投資タイミングによるリスクを分散するための積立投資も、特に投資初心者にはおすすめです。
とはいえ、どんな投資方法が合うかは、人によって異なります。まずは自分の家計や資産の状況を整理してみて、どんな投資がよいかを検討していくのがよいでしょう。
不安な場合はお金の専門家に相談してみるのもよい手段です。
物価上昇の影響を受けにくい資産配分は、年齢・収入・保有資産で最適解が変わります。
3分投資診断なら、老後必要額の試算と、インフレに耐性のある最適な投資スタイルを自動で提案。
»老後資金の不足リスクと最適な資産配分を3分で診断(無料)
物価高が気になるあなたへ
物価高に対応し、将来のお金の不安をなくすために、まずは将来に必要な金額を把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶“世界株”だけに頼らないリスク分散の投資術:30分の無料オンラインセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください