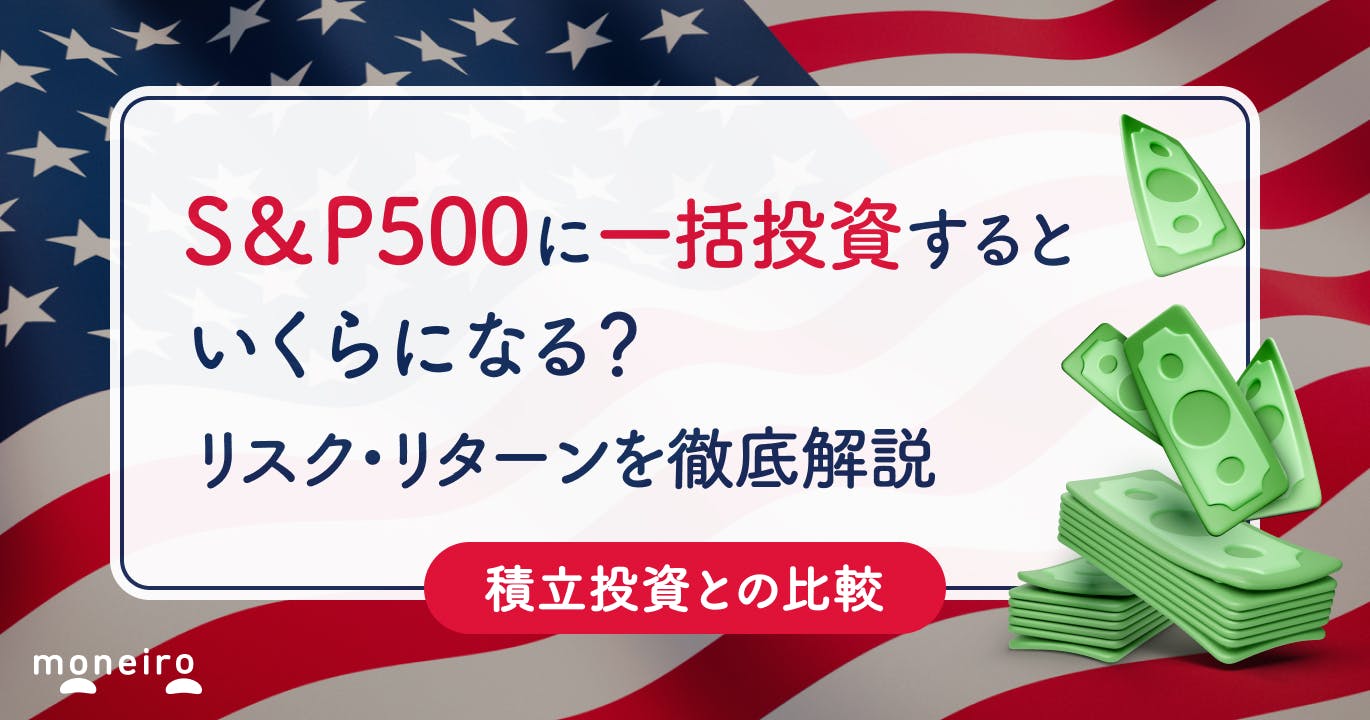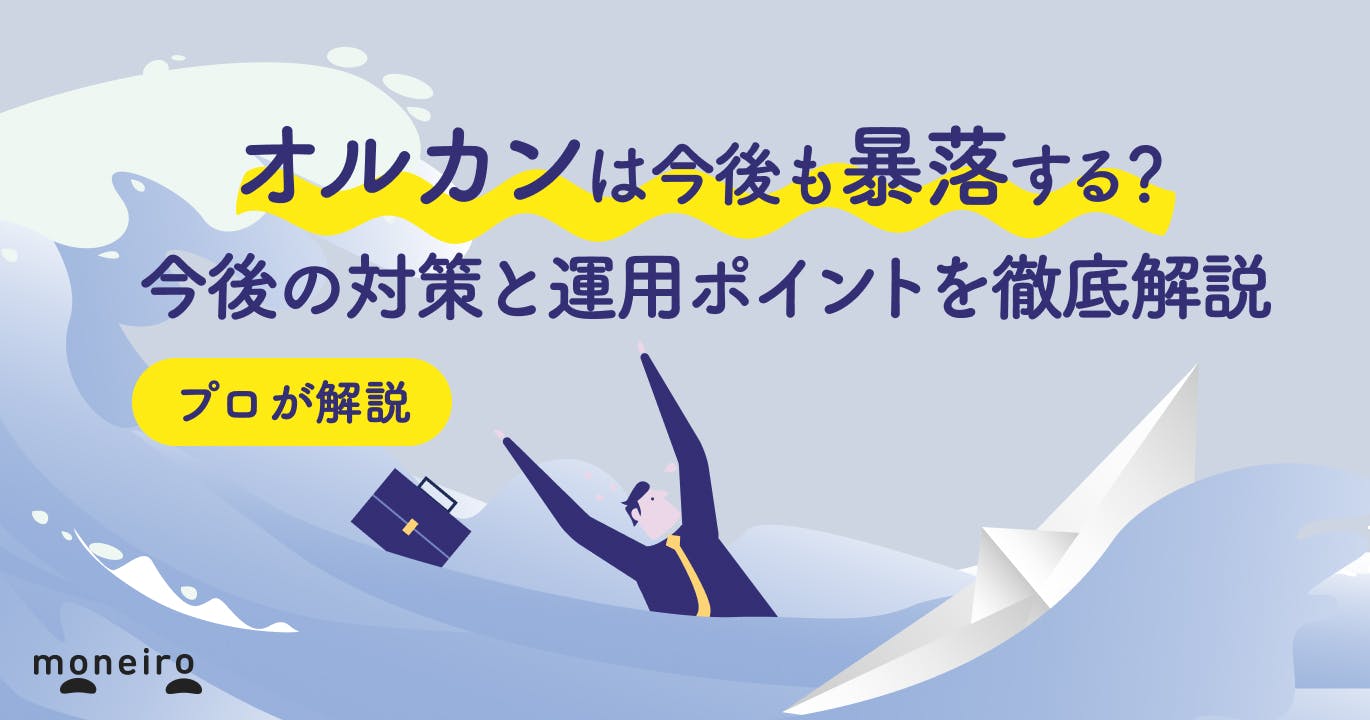S&P500今買うべきか?プロが今後の見通しと投資戦略や判断ポイントを徹底解説
»あなたにはどんな投資が向いている?無料診断
「S&P500をベンチマークとする投資信託は、今買うべき?」「S&P500の今後の見通しは?」など、S&P500の動向について気になっている人も多いでしょう。
S&P500とは米国を代表する株価指数で、この指数に連動する投資成果を目指す代表的なインデックスファンドには「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などがあります。
S&P500がベンチマークの投資信託は、米国株式市場や為替などによって基準価額が変動するのが特徴です。
本記事では「S&P500に連動する投資成果を目指す投資信託を、今買うべきか悩んでいる人」に向けて、判断する上で知っておきたい知識や基本の投資戦略について、プロが徹底解説します。
- S&P500に連動する投資信託を今買うべきかを判断するには「為替の影響」や「市場の動向」を理解することが重要
- S&P500を構成する銘柄は米国株式のみのため、米国経済の影響を大きく受ける
- S&P500に連動する投資信託に投資をする際はタイミングに問わず長期運用を心がける
S&P500の今後が気になるあなたへ
資産運用の不安を解消するために、さまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶世界株式だけに頼らない投資術とは?:スマホで見られる30分の無料セミナー
▶資産運用の不安をプロに相談:自分専任の担当者に無料相談
S&P500の特徴
S&P500とは、米国企業約500社の時価総額をもとに算出される、米国の代表的な株価指数です。
S&P500をベンチマークとするインデックスファンドは多数設定されていますが、このような投資信託には、どのような特徴があるのでしょうか。まずは見ていきましょう。
主な特徴
S&P500は米国を代表する企業、約500社から構成される株価指数のことで、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしています。
S&P500を構成する銘柄は、四半期ごとに見直しが行われ、業績が基準を満たさなくなった企業は除外されます。2025年1月時点では、情報技術(30.7%)が最も多く、次いで金融(14.1%)、一般消費財・サービス(11.4%)となっています。
市場の変化に応じて業種の割合が変わる一方、業種の分散も考慮されているので、指数の質が維持されていることも特徴のひとつです。米国市場の動きを把握する上でも、重要な指標と言えるでしょう。
S&P500がベンチマークの投資信託を選ぶメリット
S&P500は、米国株式市場の時価総額の約8割をカバーしています。米国に本拠地を置く各企業が成長し、米国経済も順調に発展していけば、指数自体も同じように上昇していくことになります。
したがって、S&P500に連動する運用成果を目指す投資信託やETFを購入すれば、米国経済の発展とともに、大きな運用成果を得られる可能性が高まります。
基準価額の変動要因がわかりやすいこと、また、インデックス投信やETFであれば運用コストが低いことなども、投資するメリットに挙げられるでしょう。
S&P500がベンチマークの投資信託を選ぶデメリット
S&P500指数は、米国の大企業、約500社の株価などから算出されています。したがって、各企業の業績等が悪化し、米国の景気が悪くなると、指数自体も下落することになります。
特に、S&P500は米国企業のみで構成されているため、S&P500をベンチマークとする投資信託のみに投資をすると、保有資産のリスクが大きくなりがちです。
保有資産が大きく減少するのを防ぐためにも、米国株式以外にも分散投資を行い、他の資産と組み合わせて保有することも検討してみましょう。
S&P500に連動する投資信託を今買うべきか
「S&P500に連動する投資信託を今買うべき?」と考えている人も多いのではないでしょうか。
S&P500に投資するタイミングを判断するには、為替の影響や市場の動向を理解することが重要です。
投資タイミングを決める際に知っておきたい基本知識をわかりやすく解説します。
基準価額が上昇・下落する主な要因
S&P500に連動する投資成果を目指す投資信託の場合、基準価額は米国株式市場の動向や為替の動きに影響を受けます。
主な要因について、詳しく見ていきましょう。
要因①米国株式市場の動向
S&P500は、米国を代表する約500社の株価などをもとに算出され、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしています。そのため、米国株式市場の動向が指数に大きく影響します。
特に、以下のような要因がS&P500の上昇・下落に関係します。
米国の景気、金利、物価や消費の動向などの経済状況(マクロ環境)は、企業の株価に大きな影響を与えます。
当然ながら、株価等から算出する指数にも影響があり、これらはS&P500をベンチマークとする投資信託の基準価額の変動要因になります。
米国経済が好調で景気が良ければ、基準価額の上昇要因となり、経済指標や金利動向などが投資家に好感を持って受け止められれば、これらも上昇の要因になるでしょう。
基準価額が下落する場合は、この反対の状況が起こる場合です。
機関投資家など大口投資家の資金の流れも基準価額の変動要因になります。
生命保険会社や年金基金などの機関投資家は、株式市場と債券市場の状況を見ながら、大量の資金を使って双方に投資をしています。
例えば、将来的に景気が悪化すると判断すれば、債券投資の割合を多くするため、株式を売却することもあります。
また、新興国や欧州の株式市場が米国よりも好調であると判断すれば、米国株を売却して、新興国や欧州に資金を振り分ける可能性もあります。
つまり、大口の投資家を含め、多くの投資家が米国株を選考しなければ株価は下落し、基準価額の下落につながることになります。
要因②為替(ドル円)の影響
S&P500をベンチマークとする投資信託に組み入れられているのは、米国株式で外貨建て資産です。このような投資信託には為替リスクがあるので、基準価額は為替の影響を大きく受けることになります。
特に、米国のトランプ大統領は、貿易赤字の元凶はドル高にあり、貿易不均衡を解消するにはドル安に誘導すべきと、第一次政権時から繰り返し発言しています。仮に為替がドル安円高方向に進むとなると、基準価額は下落する可能性があります。
また、S&P500指数はドルベースであり、S&P500をベンチマークとする投資信託の場合、委託会社は指数を円換算ベースに計算し直しています。そのため、指数(円換算ベース)では、円高・円安によるズレが生じる点も理解しておきましょう。
長期運用ができるならなるべく早めに投資をする
下記に該当する人は、S&P500に連動する投資成果を目指す投資信託での運用が向いています。
- 長期運用ができる人
- 積立投資を続けられる人
- 短期の値動きを気にせず、時間を味方につけられる人
S&P500は長期的な成長が期待できる指数であるため、運用期間が長ければ長いほど資産が増える可能性が高まります。
できるだけ早く投資をスタートして、時間を味方につけることも大切です。
≫マネイロの無料相談サービスを見てみる
短期で利益を狙いたい場合は要注意
S&P500に連動する運用成果を目指す投資信託はリスクが高く、価格変動が大きいのが特徴です。短期間で利益を得られる場合もありますが、大きく下落することもあるので注意が必要です。
お金が必要な時に含み損を抱えている可能性もあるので、近い将来に必要な資金を投資することは避けましょう。
また、投資初心者やリスク許容度が低い人は、基準価額の大きな変動が精神的な負担になる場合もあります。
投資をする前に、S&P500指数、S&P500のインデックス投信などの価格が、どのように変動しているか確認しておくことをおすすめします。
S&P500の今後が気になるあなたへ
資産運用の不安を解消するために、さまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶世界株式だけに頼らない投資術とは?:スマホで見られる30分の無料セミナー
▶資産運用の不安をプロに相談:自分専任の担当者に無料相談
S&P500の今後の見通しは?
今後S&P500指数がどのように推移するかを正確に予測することはできませんが、S&P500を構成する銘柄は米国株式のみなので、米国経済の影響を大きく受けることは確かです。
米国には世界をけん引する大企業が多く、イノベーションも活発です。企業業績が好調で、米国社会や政治が安定した状況が続くかぎり、S&P500指数は今後も上昇する可能性があるでしょう。
しかしながら、米国では2025年1月に新政権が誕生し、米国のみならず世界中が、トランプ新大統領の型破りな政権運営を驚きをもって受け止めている状況です。
少なくとも今後4年間は政権が継続するため、従来の基本的な経済指標に加え、トランプ大統領の発言、特に関税政策、紛争国への対応なども注視しておくことをおすすめします。
S&P500に連動する投資信託の基本投資戦略
S&P500に連動する投資信託に投資する際、投資の基本である
- 長期投資
- 積立投資
- 分散投資
をおさえておきましょう。
S&P500に連動する投資信託を運用する時のポイントを投資のプロが解説します。
①長期投資→価格変動に動揺せず長期運用
資産を長期間にわたって運用することは、特に積立投資と相性が良く、長期運用で価格変動リスクを抑える効果が期待できます。
安定した資産形成にもつながるので、一時的な値動きに動揺しないでコツコツと投資を続けることが大切です。
長く運用を続けるためにも、自身の投資目的や目標金額を運用前に決めておくと良いでしょう。
②積立投資→ドル・コスト平均法
一般的に毎月決まった日に、決まった額を購入する投資方法のこと
この方法は「ドル・コスト平均法」とも呼ばれ、基準価額が低い時には多くの口数が購入でき、基準価額が高い時には口数を少なく購入できるので、購入単価を平準化できるなどのメリットがあります。
投資初心者や長期運用を考えている人に適した投資方法と言えるでしょう。
ただし、ドル・コスト平均法は将来的に上昇していく資産に投資をしなければ、効果は限定的です。その点、S&P500指数のように、将来的に値上がりが期待できる資産はドル・コスト平均法に向いていると言えます。
Q.積立投資と一括投資、どっちが良い?
S&P500は、米国を代表する企業から構成される株価指数です。そのため、S&P500をベンチマークとする投資信託は、比較的値動きが大きく、リスクが高い金融商品になります。
できるだけリスクを抑えながら運用するのであれば、少額をコツコツと投資する積立投資がおすすめです。
一括投資は一度のタイミングで大きな額を投資するので、リスクが大きくなりがちです。購入のタイミングを自分で決められる人や余裕資金がある人、長期運用ができる人は検討しても良いでしょう。
積立投資、一括投資、どちらにもメリット、デメリットがあります。自身の投資目的やリスク許容度に合わせて決めることが大切です。
③分散投資→他の商品と組み合わせる
分散投資とは、投資先(資産)や投資のタイミング(時間)を分散させる投資方法のことです。
投資先を分散することで、特定の市場や資産に依存することを防ぎ、リスクを軽減しながら安定した運用を目指すことができます。
S&P500に連動する成果を目指す投資信託のみに投資している場合、数多くの株式が組み入れられているとはいえ同じ米国企業ばかりなので、分散投資にはなりません。
リスク分散のためには、他の資産と組み合わせることが大切です。
例)低リスク資産との組み合わせ
S&P500をベンチマークとした投資信託の組み入れ銘柄は米国株式のみになります。したがって、S&P500に連動する投資成果を目指す投資信託のみを保有していると、効果的な分散投資ができません。
運用のリスクを小さくするためには、欧州や日本などの先進国株式、先進国債券などを投資先とするファンド、また、格付けの高い債券や貯蓄型保険など、低リスク資産と組み合わせてみましょう。
「S&P500とどんな商品を組み合わせるべきかアドバイスがほしい」
悩んだ時は金融機関出身の専門家に無料相談がおすすめ
≫投資信託の選び方、見直しはマネイロにお任せ
Q.全世界株式(オール・カントリー)と組み合わせるのはNG?
S&P500指数をベンチマークとするインデックス投信に加えて、MSCI オール・カントリー・ワールド指数 (ACWI)をベンチマークとするインデックス投信を組み合わせて保有するのは、効果的な分散投資とは言えません。
MSCI ACWIは構成する銘柄の国別内訳では米国が約67%(※)を占めています。つまり、これらの指数をベンチマークとするインデックス投信を組み合わせると、保有資産に占める米国株の割合が極端に高くなってしまいます。
市場環境は常に変化しており、過去を振り返ると米国株式だけが運用成果のトップにあり続けたわけではありません。分散投資の意味はここにあります。
運用リスクを軽減するためにも、投資対象が異なる資産やファンドを組み合わせることが大切です。
※(参考:MSCI オール・カントリー・ワールド指数 (ACWI)2024年10月末現在)
NISAを活用した投資戦略
NISA(少額投資非課税制度)を通じて投資をすれば税を負担することなく、将来に向けた資産形成が可能になります。
NISAは本来長期・積立・分散投資に適した制度でしたが、2024年に制度が改正され、投資可能期間や非課税保有期間の撤廃などにより、さらに長期運用に適した制度になっています。
非課税の恩恵が受けられるだけでなく、複利を活かした効率的な運用が長期にわたってできるようになったこともメリットと言えるでしょう。
特に、S&P500に連動する成果を目指す投資信託やETFはNISAのつみたて投資枠、成長投資枠、どちらでも投資可能なので、積極的に活用することをおすすめします。
投資のタイミングに悩んだ時の解決方法
「今から投資を始めるべき?」「どの商品を選べば良い?」など、投資のタイミングや商品選びに悩んだ時は、投資の専門家に相談してみるのもひとつの方法です。
金融機関の多くは口座開設をしても担当者がつくことはほとんどなく、投資の相談をしたくても、すぐに相談できる体制とは言い難いのが現状です。
サポートが必要な場合は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)やFPの活用も検討してみましょう。
特にIFAは金融業界の経験が豊富で、専門的な知識をもつお金の専門家です。売買のタイミングなど、自分だけでは判断が難しい時は、アドバイスを受けてみるのもおすすめです。
マネイロなら商品選びから運用までしっかりサポート
投資を始める際、「自分の投資目的に合った商品はどう選べば良い?」「運用を続ける中で困った時に相談できる人がいるのか?」と不安に感じることも多いでしょう。
マネイロは、はたらく世代向けの診断・相談サービスとして、商品選びから運用までしっかりサポートしています。
金融機関出身のIFAがサポート
マネイロなら、運用に関するアドバイス経験が豊富なIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に、お金の相談をすることができます。
マネイロのIFAは証券会社・銀行・保険会社の出身者で、投資と保障、両方の専門資格を保有しています。そのため、さまざまなお金の悩みごとに対応することが可能です。
商品選びから運用中のサポートまで、同じ担当者からサービスを受けられるのもメリットのひとつです。
投資金額に関係なく、全員に担当者がつく
多くの金融機関では、投資金額が一定以上でないと担当者がつかないケースがあります。しかし、マネイロなら投資金額に関係なく、すべての相談者に担当者がつくため、初心者でも安心して相談できます。
口座開設後も無料で運用をサポート
証券会社や銀行などの金融機関では、口座開設後の運用サポートはほとんどありません。
一方、マネイロでは初めてお金の相談をした後でも担当者がついて、運用に関する悩みや不安を解消できるように無料でサポートします。
例えば「市場が不安定だけど、このまま投資を続けても良い?」など、相談すれば適切なアドバイスを受けられます。
まとめ
S&P500は、米国を代表する500社の株価指数に連動しており、長期的な成長が期待できる投資対象です。S&P500に連動した投資信託やETFを活用することで、米国経済の成長の恩恵を受けることができます。
しかし、米国株式市場や為替の影響を受けるため、リスクが高い点には注意が必要です。特に、円高や米国経済の不調などがあると、一時的に資産が大きく目減りする可能性もあります。
「S&P500に連動する投資信託を今買うべきか?」を判断する際には、自身の投資目的や目標金額、運用期間と照らし合わせて慎重に検討することが大切です。
高値づかみが怖い、下落が不安と感じる時ほど、 老後に必要な金額・不足額・投資期間・許容リスクを可視化して判断軸を整えることが大切です。
タイミングに惑わされず、長期的に続けられる設計が重要になります。
3分投資診断なら、老後必要額・不足額・あなたに最適なS&P500投資のスタンスを自動で算出。「今買うべきか」「積立で様子を見るべきか」を根拠をもって判断できます。
»S&P500の最適な始め方を3分で診断(無料)
S&P500の今後が気になるあなたへ
資産運用の不安を解消するために、さまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶世界株式だけに頼らない投資術とは?:スマホで見られる30分の無料セミナー
▶資産運用の不安をプロに相談:自分専任の担当者に無料相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
土屋 史恵
- ファイナンシャルプランナー/金融ライター/編集者
神戸市外国語大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。遺言信託など資産承継ビジネスに強み、表彰歴あり。その後は長年の金融機関勤務経験を活かし、金融メディアに転職。記事執筆や編集などを担当。現在はフリーランスとして活動中。AFP、FP2級、証券外務員一種を保有。
執筆
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。