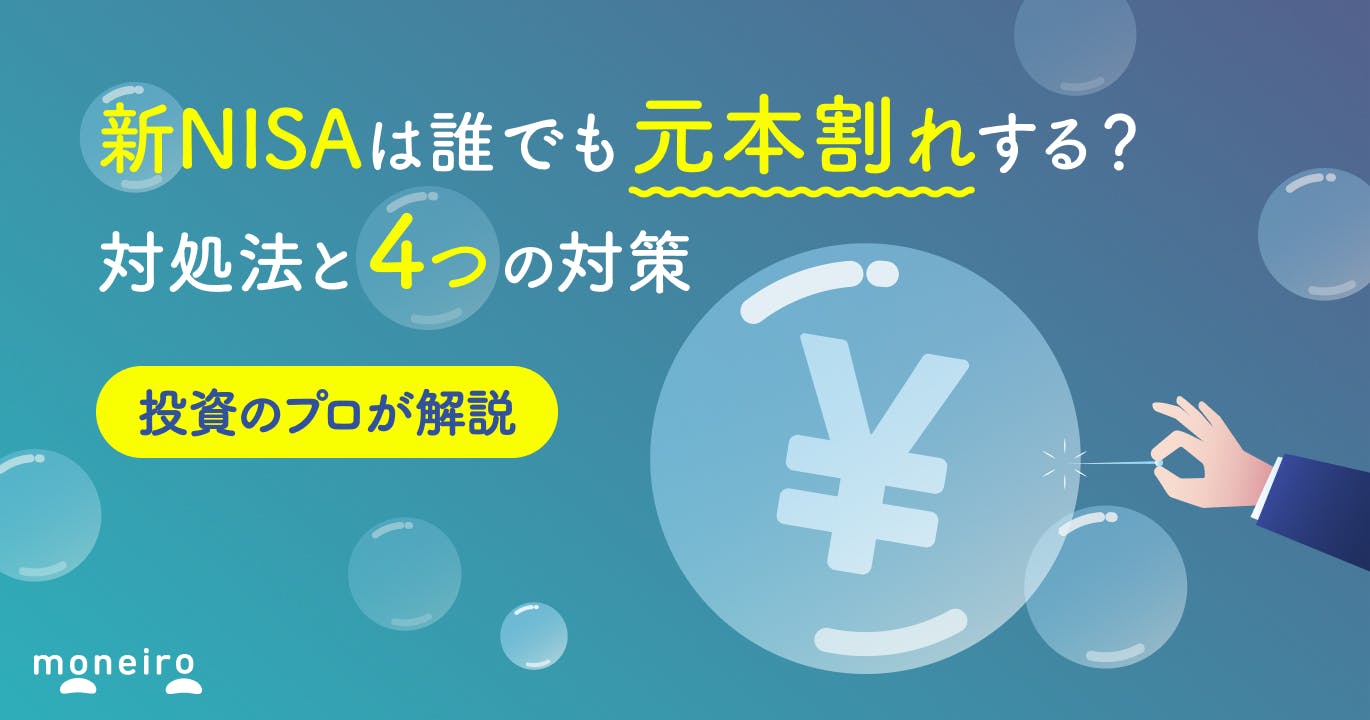.jpg?w=490&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
オルカンは今後も暴落する?トランプ自動車関税の影響や今後の対策・運用ポイントを解説
»あなたの最適な投資方針を無料診断
「オルカンが下落した理由は?」「オルカンは今後暴落する可能性はある?」など、オルカンで運用中の方は今後の価格推移に不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
オルカンとは、全世界株式(オール・カントリー)を投資対象とするインデックスファンドのことで、特に「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のことを指します。ファンドの投資先の半分以上が米国企業で占められており、米国経済の影響を受けやすいなどの特徴があります。
本記事では「オルカンが下落・暴落する要因は?」「このままオルカンに投資しても良い?」と悩んでいる人に向けて、オルカンの基本知識や下落の要因、対策について投資のプロが解説します。
※“オルカン”は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の略称として商標登録されています
※オルカンは全世界株式(オール・カントリー)を投資対象とするインデックス投資信託の総称として呼ばれる場合もあります
- オルカンが2024年8月に暴落した主な要因は「円高の進行」「株式市場の乱高下」
- トランプ大統領による「自動車関税25%引き上げ」がオルカンにも影響を与える可能性
- 暴落は誰にも予測できないため「ドル・コスト平均法」「分散投資」の対策を行う
- 暴落した時に備えて「資産や運用スタイルが異なる投資信託」などの商品に投資を行う
オール・カントリーの今後が気になるあなたへ
「知識ゼロでも、ただしい資産運用ができる」をスローガンに、さまざまな資産運用サポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶世界株式だけに頼らない投資術とは?:スマホで見られる30分の無料セミナー
▶暴落に備えるNISA運用相談会:あなたのNISAをプロが無料見直し
.jpg?w=490&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
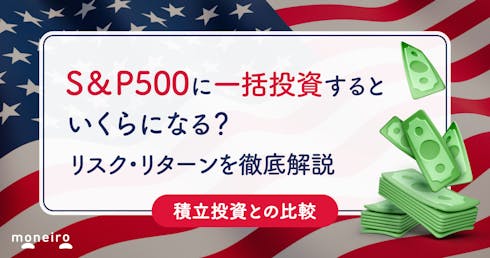
暴落とは株価が急激に下降すること
株価が一気に、もしくは短期間で大きく値下がりすること
過去に起きた代表的な暴落の例で言うと、2000年の「ドットコムバブル崩壊」、2008年の「リーマンショック」、2020年の「コロナショック」などが挙げられます。
例えば、2007年のサブプライムローン問題から発生した、2008年のリーマンショックでは、米国株式(S&P500)は1年半にわたって約50%下落し、その後の影響は長期間に及びました。
自分の資産が短期間で半値になり、回復にも時間がかかれば、投資家にとってたまったものではありません。しかし、このような暴落、金融ショックは約10年に1度のペースで発生しており、珍しいことではなくなっています。
(参考:コロナショックとリーマンショックの比較|三井住友DSアセットマネジメント)
暴落が起こる理由
株価が下落・暴落する理由はさまざまですが、多くの場合、企業の業績見通しや経済状況の悪化、政情の不安定化などにより、人々の金融に対する不安心理が高まった時に発生します。
このような状況になると、投資家はまず手元のポジションを解消し、お金を低リスク資産へ避難させます。
その額や人数が少なく、株価に対して影響が少なければ大きな下げにはつながりませんが、機関投資家などの大口投資家、あるいは大勢の投資家が売りに出すと株価に対するインパクトが大きく、暴落につながります。
また、自動的に売買を繰り返すアルゴリズム取引も大きな下落につながりやすいと言われています。
あらかじめ設定した条件で、高速・大量に売買が成立するメリットがある反面、売りが売りを呼ぶ展開になりやすいという指摘もあります。
オルカンが2024年8月に暴落した主な要因
2024年7月、オルカンは過去最高値2万7282円(当時)をつけたのち、8月6日には2万2688円まで下落しました。実に約17%の下落です。
主な下落の要因としては、下記の2つの要因が挙げられます。
- 円高の進行
- 株式市場の乱高下
具体的に見ていきましょう。
オルカン(オール・カントリー)の基本知識
オルカンは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(MSCI ACWI)に連動した投資成果を目指すインデックスファンドで、先進国23カ国と新興国24カ国の株式市場に上場する中・大型株が投資対象です。(2024年11月末時点)
時価総額加重型を採用していることから、時価総額の大きな銘柄の構成比率が高くなりやすく、現状では組み入れ銘柄の半分以上が米国の有名企業が占めています。
そのため、米国経済や米国市場の動向などで、基準価額が左右されやすくなる面があります。
2024年のヒット商品にも選ばれたオルカンは、純資産残高が4兆円(2024年12月現在)を超え、5兆円にも迫る勢いです。
MSCI ACWIがベンチマークの投資信託は他にもありますが、オルカンがここまで支持されている理由に、手数料の安さも挙げられるでしょう。
(参考:MSCI ACWI Index|MSCI)
下落要因①円高の進行
円高ドル安が進んだ要因にはさまざまな理由が考えられますが、以下の大きな要因があります。
- 日銀が行った7月の追加利上げ
- 7月30日、31日に行われたFOMCで9月の利下げが示唆されたこと
ドル円相場は日米の金利差と連動しているため、日本が利上げ、米国が利下げをすれば、日米金利差の縮小が強く意識され、円高ドル安に振れやすくなります。
加えて、8月に公表された米国の経済指標が軒並み悪化しており、米国の景気減速が一段と懸念される事態となりました。
このような状況下で、円高ドル安が一気に進み、7月に160円台をつけていたドル円相場は、8月に入ると140円台まで急上昇しました。(2024年12月現在は150円台で推移)
オルカンに限りませんが、オルカンのように海外資産に投資をするファンドで為替ヘッジがない場合、円高円安は基準価額にダイレクトに影響します。
そのため、円高が進行すると基準価額が大きく下落する大きな要因となります。
下落要因②株式市場の乱高下
米国や日本の株安が進んだ要因には、8月に米国で公表された製造業の景況感指数や雇用統計など、米国の重要経済指標が予想よりも悪化したことが挙げられます。
このことが日米の投資家に、米国の景気に対する不安を与え、株安につながったと考えられます。
一方で、円高の影響もあります。輸出企業の業績悪化につながる円高は、株価にとってはマイナスのイメージです。投資家によっては円高を「売り」ととらえることもあり、円高は株安につながりやすくなります。
オルカンの組み入れ銘柄には、米国の時価総額の大きい企業が上位を占めるため、株安は円高と同様、オルカンの基準価額にも影響を与えることになります。
オルカンで言えば、米国企業の業績が悪ければ下落要因に、好調であれば上昇要因になります。
オルカンが2025年に入っても下落基調な理由は?
オルカンは2024年8月に大きく下落したものの、その後はほどなくして回復に転じ、以降は堅調に推移して同年12月27日はその時点での設定来高値である2万7876円をつけました。
そして、2025年に入ってからは伸びこそ鈍化したものの、1月24日に2万8060円をつけ、設定来高値をさらに更新しています。
転換点となったのは、2025年2月18日のトランプ米大統領の発言です。トランプ大統領は、米国に輸入される自動車に25%程度、また半導体と医薬品に対しても同程度の関税を課す考えを示し、これを機に市場相場が大きな動きを見せました。
トランプ政権の関税政策による不確実性の高まり
トランプ大統領のこの発言は、以降投資家の間に貿易戦争再燃への懸念を広げています。
関税は企業コストを増加させ、特に自動車産業や関連サプライチェーンに依存する企業に打撃を与えると予想され、オルカンにも組み入れられている多くの銘柄にもマイナスの影響を及ぼしたと考えられます。
ハイテク株が調整局面へ
近年、米国の代表的な株価指数であるNASDAQやS&P500の上昇を牽引してきたのは、「マグニフィセント・セブン(アップル、アマゾン、マイクロソフト、アルファベット、メタ、テスラ、NVIDIA)」と呼ばれるテクノロジー大手です。
オルカンにおいても上記銘柄の構成比率は非常に大きく、7社の株式だけでオルカン全体の15~20%を占めます。つまり、7社の株価がオルカンの基準価額にも大きな影響を与えるということです。
2025年に入る前後からこれらの銘柄が調整局面に入っており、さらに低コストな中国製AI「DeepSeek」の登場によりNVIDIA株が大幅下落しているほか、トランプ政権の要職を担うことになったイーロン・マスクCEOへの反発による不買運動などでテスラ株も急落しています。※いずれも2025年3月27日時点
上昇を続けた銘柄が一時的に下落に転じること。大きな暴落とは異なり、比較的小規模で短期的な下落を指します。
米国経済の減速懸念も
米国経済の成長鈍化の兆候が、投資家の不安を煽っています。例えば、2025年3月に発表された2月の雇用統計では伸びが予想を下回り、さらに消費者信頼感指数が低下するなど、景気後退リスクが指摘されています。
米国株はオルカンの大きな構成要素であるため、この減速懸念が下落の要因の1つとなっています。
トランプ大統領「自動車関税25%引き上げ」の影響は?
2025年3月26日、トランプ大統領は「米国に輸入されるすべての自動車に25%の追加関税を課す」と正式に発表し、市場に大きな影響を与えています。
この発表は、カナダやメキシコ、中国など主要貿易相手国との貿易摩擦を再燃させ、報復関税の連鎖を引き起こす懸念を高めたといえ、さらにグローバル企業のサプライチェーンにおいては、コスト増や需要減が予想されます。
そのため、上述のカナダやメキシコのほか、日本やドイツ、韓国といった輸出依存度の高い国の株式市場でも下落圧力を強めている状況です。
オルカンは米国株が大きな割合を占めていますが、その他の国の企業の株価も反映されるため、下落の要因の1つになり得ます。
半導体需要にも影響?
「マグニフィセント・セブン」の1つであるNVIDIAは自動車産業向けに重要な半導体を提供しており、特に自動運転技術や車載AIチップで知られています。
トランプ大統領の関税政策で輸入自動車に25%の追加関税を課すことで、カナダやメキシコから輸出するメーカーが生産計画を見直し、NVIDIAチップの需要が減退する可能性があり、業績にも影響を与えるリスクが指摘されています。
インフレ加速でオルカンにも影響する可能性
関税が引き上げられると、米国内では輸入品価格の上昇が起き、インフレ加速の要因になります。インフレが加速すると米連邦準備制度(FRB)は、経済を冷やすために利上げ(金利上昇)を検討する可能性が出てきます。
関税を課せられた国が、自動車などの米国製品に報復関税を課せば、逆にGMやフォードといった米国産自動車の輸出が減少することになり、収益が悪化する可能性もあります。
また、GMやフォードもメキシコやカナダに大きな生産拠点を持つことから、この関税政策がアメリカの自動車産業にとって裏目に出る可能性も指摘されています。
オール・カントリーの今後が気になるあなたへ
「知識ゼロでも、ただしい資産運用ができる」をスローガンに、さまざまな資産運用サポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶世界株式だけに頼らない投資術とは?:スマホで見られる30分の無料セミナー
▶暴落に備えるNISA運用相談会:あなたのNISAをプロが無料見直し
オルカンの今後の見通しは?
オルカンの今後の見通しを明確に予測することはできませんが、オルカンには将来、成長が期待できる企業が多く組み入れられています。
米国を中心として世界の名だたる企業に分散投資をしているため、米国はもちろんのこと、組み入れられている国々の景気が上向けば、値上がりも期待できるでしょう。
とはいえ、オルカンの基準価額が大きく下落する可能性がないわけではありません。これは他の株式型の投資信託でも同様です。基準価額の変動要因となる、株価や為替の動きには十分注意しておきましょう。
オルカンの組み入れ上位国の米国では、トランプ新政権が誕生し、その政策に注目が集まっています。
米国の政治や経済状況が、結果的にオルカンの基準価額に影響を与えるので、トランプ大統領がどのような政策を掲げ、どのような結果をもたらすか、各識者から発せられる見通しや経済指標には注目しておくと良いでしょう。
暴落は誰にも予測できないため対策を行う
「ドットコムバブル崩壊」や「リーマンショック」などと呼ばれる金融不安は、約10年に1度の割合で発生しています。
一度暴落してしまうとその影響により、銘柄によっては運用中の資産が半分になってしまうことも珍しくありません。
暴落は後から振り返ってみると予兆があるものですが、実際に起こるまでは、個人の投資家レベルで察知したり、予測することはなかなか難しいものです。
相場の急変や暴落に備えて、以下の2つの対策を行うことが大切です。
暴落の対策①ドル・コスト平均法
投資信託や外貨預金など、リスク性商品を定時定額でコツコツと購入する投資手法のこと
決まったタイミングで一定額を投資することから、自然と分散投資ができるのが特徴です。
一度にお金を投資してしまう方法だと、暴落による損失を解消するには、相場の回復を待つ、あるいはナンピン買い(※)をするくらいしかありません。これらは投資家に新たな負担が生じるので一般的にはおすすめしにくい方法です。
一方、ドル・コスト平均法のような分散投資を行えば、下落時にも購入を続けることになります。
例えば投資信託などの場合、下落時の購入は口数を多く購入できるので、将来値上がりした時に大きな利益が得られるメリットもあります。
ドル・コスト平均法は、将来的に値上がりが期待できる資産や銘柄に投資をすることで効果を発揮します。投資する商品はよく吟味して選ぶようにしましょう。
※ナンピン(難平)買い…保有銘柄の価格が下落した時に、あえて買い増して平均購入単価を下げる方法
暴落の対策②分散投資
投資のリスクを抑えるには分散投資が有効です。また、長い時間をかけて分散投資をすることで、安定した運用成果も期待できます。
実はオルカンだけでは分散投資ができていない
オルカンは、時価総額加重型を採用して算出している指数をベンチマークとしています。そのため、時価総額の大きい企業への投資比率が高くなる傾向にあります。
例えば、米国株の組み入れ比率は約6割、情報技術や金融セクターへの投資比率は約4割にのぼるなど、投資先にはやや偏りが生じます。(2024年11月末時点)
また、オルカンは株式指数に連動して運用するファンドなので、当然ながら債券など他の金融商品は組み入れられていません。
オルカンだけを保有することが悪いわけではありませんが、リスクは大きくなります。先進国債券などに投資をするファンドを保有するとリスクが分散され、安定的な運用につながりやすくなります。
(参考:MSCI ACWI Index|MSCI)
リスク軽減のためのポートフォリオを作る
オルカンだけにお金を投資すると、米国偏重の資産配分になり、リスクが大きくなりがちです。できれば、米国以外の国々の株式や、株式以外の資産、例えば債券など、値動きの異なる金融資産を組み合わせてリスクを軽減させましょう。
そのためには、まずどのような資産を、いくら組み入れるか、資産の種類と配分を決めて(アセットアロケーション)、具体的な商品を組み合わせます。この具体的な商品の組み合わせのことを「ポートフォリオ」と呼びます。
ポートフォリオは、それぞれのリスク許容度に応じて、より良い運用成果を得ることを目的として作成するものです。
ポートフォリオにしたがって運用すれば、運用目標を達成できる可能性が高まります。
オルカンが暴落した時に備えてどんな商品に投資するべき?
ここからはオルカンが暴落した時に備えて投資すべき金融商品について解説していきます。ぜひ参考にしてみましょう。
資産や運用スタイルが異なる投資信託
オルカンと同じベンチマークのファンドに投資をすると、オルカンと同じような値動きをすることになります。これでは暴落時の対策にはなりません。
オルカンと一緒に保有して暴落に備えるファンドを選ぶなら、投資対象とする資産や地域がオルカンとは異なるファンドにしましょう。
例えば、いくつかの資産を組み合わせたバランスファンドなどは、資産を分散している分、オルカンよりも暴落の影響が少なくて済む可能性が高くなります。
また、為替ヘッジがある投資信託は為替リスクが小さくなるので、暴落の要因のひとつが円高である場合は影響を軽減させることが可能です。
債券、貯蓄型保険などの低リスク資産
一般的に先進国の債券や、終身保険や養老保険などの貯蓄型保険は低リスク資産に分類されます。そのため、投資先が株式のみの投資信託と比較すると、暴落時の影響は限定的です。
特に債券と株式は負の相関関係にあるとされ、株式投資のリスク分散として債券が選考されます。バランスファンドなどがその例です。
また、終身保険などの貯蓄型保険は、解約返戻金があらかじめ決まっているため、暴落の影響をほとんど受けません。
仮に暴落時に急な支出があっても、保険商品であれば解約したり、貸付を受けられるので、万が一の事態にも対応しやすくなります。
暴落の対策や資産の見直しはプロに相談がおすすめ
株価の暴落に備えて、どのような準備をしたら良いか、自分ひとりでは考えるのが難しい場合は、お金の専門家に相談してみましょう。
経験豊富なFPやIFAであれば、リーマンショックなど、さまざまな大きな暴落を経験しているので、実際の相場がどのように動いたか、また暴落からどのように回復したかも熟知しています。
経験から得られた教訓をもとに、どのような運用をすべきかアドバイスしてくれることでしょう。
特にIFAであれば、現在の運用商品や投資方法が適切かどうかの判断もしてくれます。リスク許容度の低い方がハイリスク商品を保有していることもあるので、株価の大きな変動に備えてIFAと一緒に見直ししておくのも良いでしょう。
IFAであるマネイロは働く世代向けのお金の診断・相談サービスを提供しています。
・相談者全員に担当者がつく
・SBI証券と連携しているためネット証券のサポートが充実
マネイロでは少額からまとまったお金の運用まで、相談者に合わせたご提案が可能
≫マネイロの無料相談サービスを見てみる
まとめ
せっかく運用を始めたのだから、自分の資産が順調に増えてほしいと考えるのは当然のことです。
しかし、長く運用をしていれば、誰しも一度くらいは暴落を経験する可能性があること、また、暴落が発生すると自分の資産が大きく減る可能性があることを理解しておきましょう。
暴落に対する備えとしては
- 運用期間を長く確保する
- 成長が期待できる資産に投資する
- 異なる特徴を持つ複数の資産に分散投資する
などが有効です。
オルカンの暴落局面でどう行動すべきかは、“あなたの投資方針”で最適解が変わります
暴落のニュースを見ると不安になりますが、老後の必要額・不足額・投資期間・許容リスクを整理すると、取るべき行動が明確になります。
3分投資診断なら、老後必要額・不足額・暴落時の最適な投資スタンスを自動で算出。 「続けるべきか」「積立額をどうするか」迷う方の判断材料になります。
»暴落に左右されない最適な投資方針を3分で診断(無料)
オール・カントリーの今後が気になるあなたへ
「知識ゼロでも、ただしい資産運用ができる」をスローガンに、さまざまな資産運用サポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶世界株式だけに頼らない投資術とは?:スマホで見られる30分の無料セミナー
▶暴落に備えるNISA運用相談会:あなたのNISAをプロが無料見直し
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
土屋 史恵
- ファイナンシャルプランナー/金融ライター/編集者
神戸市外国語大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。遺言信託など資産承継ビジネスに強み、表彰歴あり。その後は長年の金融機関勤務経験を活かし、金融メディアに転職。記事執筆や編集などを担当。現在はフリーランスとして活動中。AFP、FP2級、証券外務員一種を保有。
執筆
鶴田 綾
- ファイナンシャルアドバイザー
福岡女学院大学・人文学部英語学科卒。卒業後、日本郵便株式会社にてリテール営業に従事。投資信託や生命保険の販売では商品分析を得意とし、豊富な商品知識を持つ。現在はこれまでの金融商品の知識を生かし、Instagramを中心に、SNSにて資産運用のはじめ方や資産形成のコツについて積極的に情報発信をしている。一種外務員資格(証券外務員一種)、保険募集人資格などを保有。
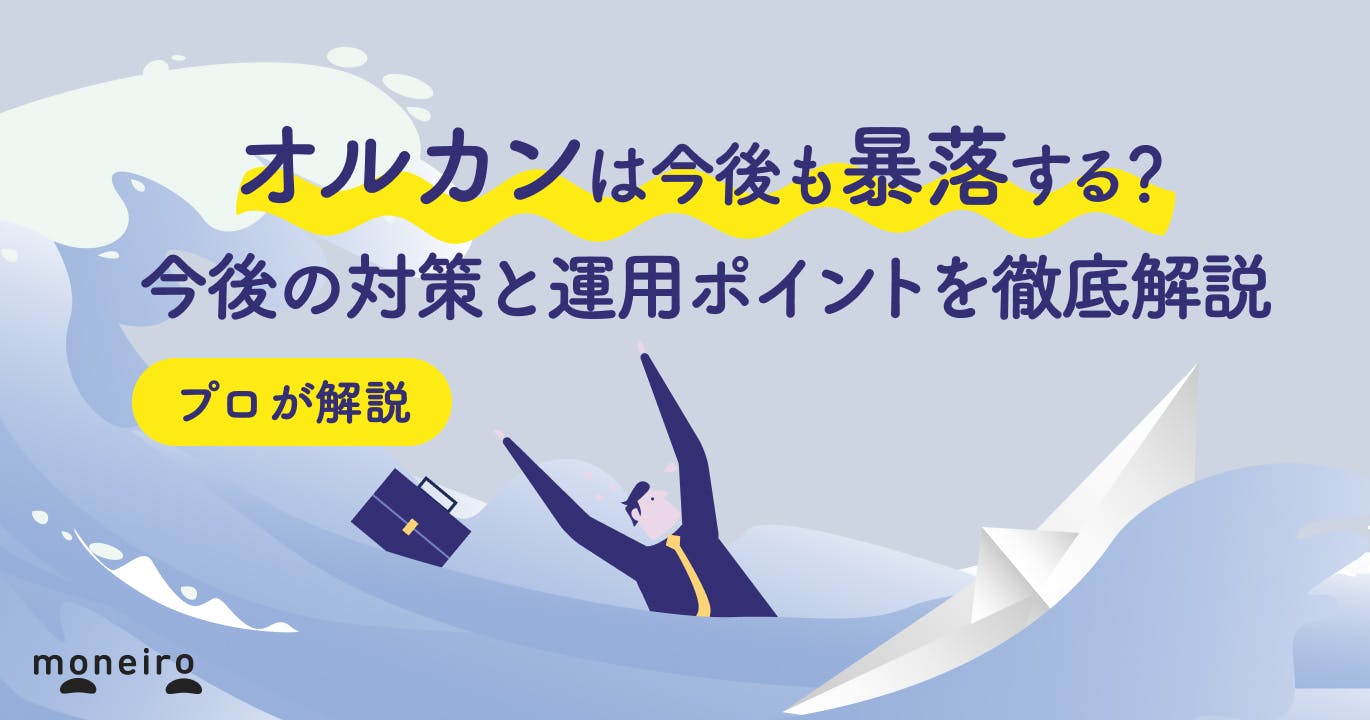
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)