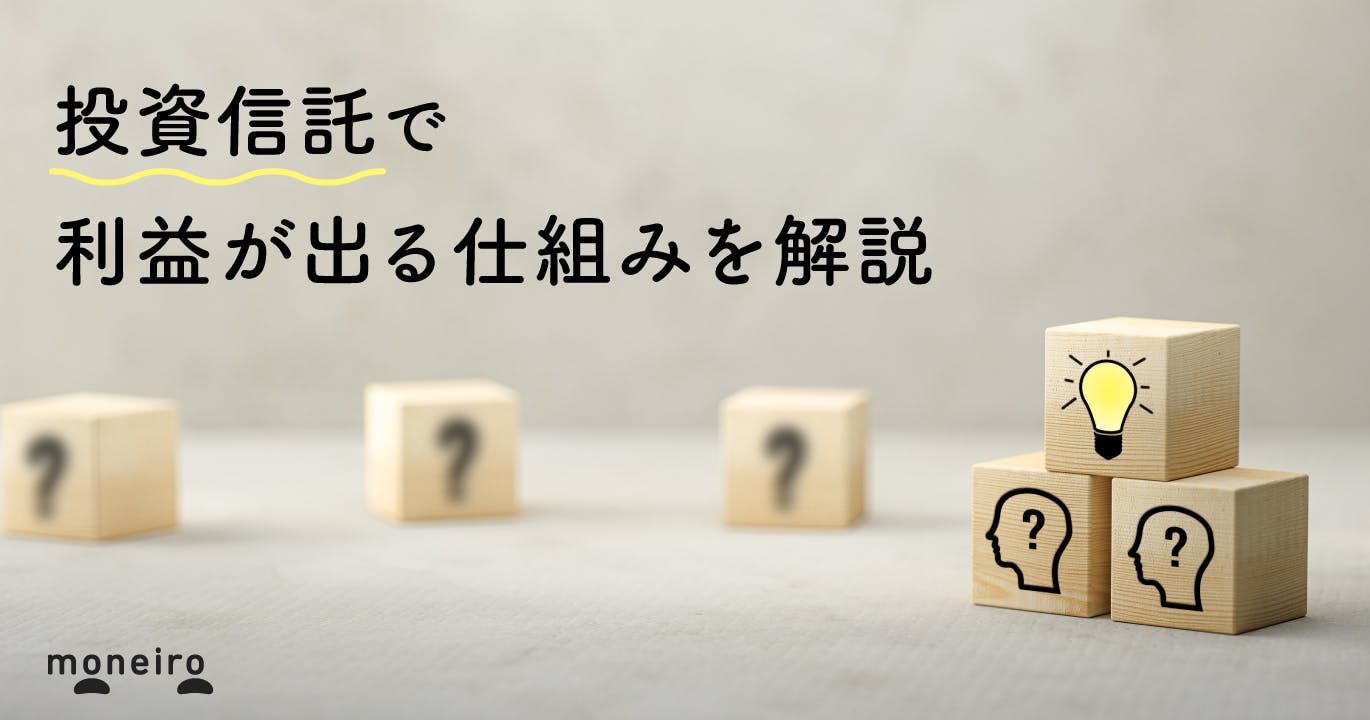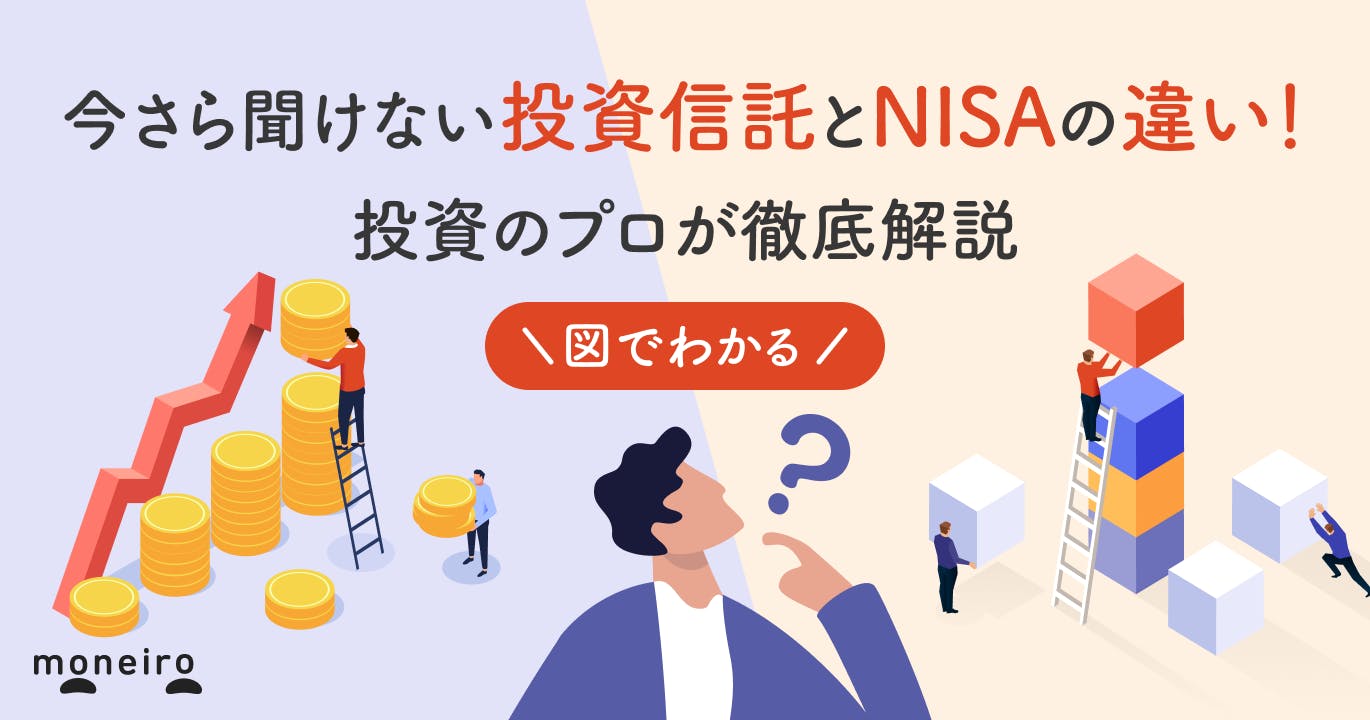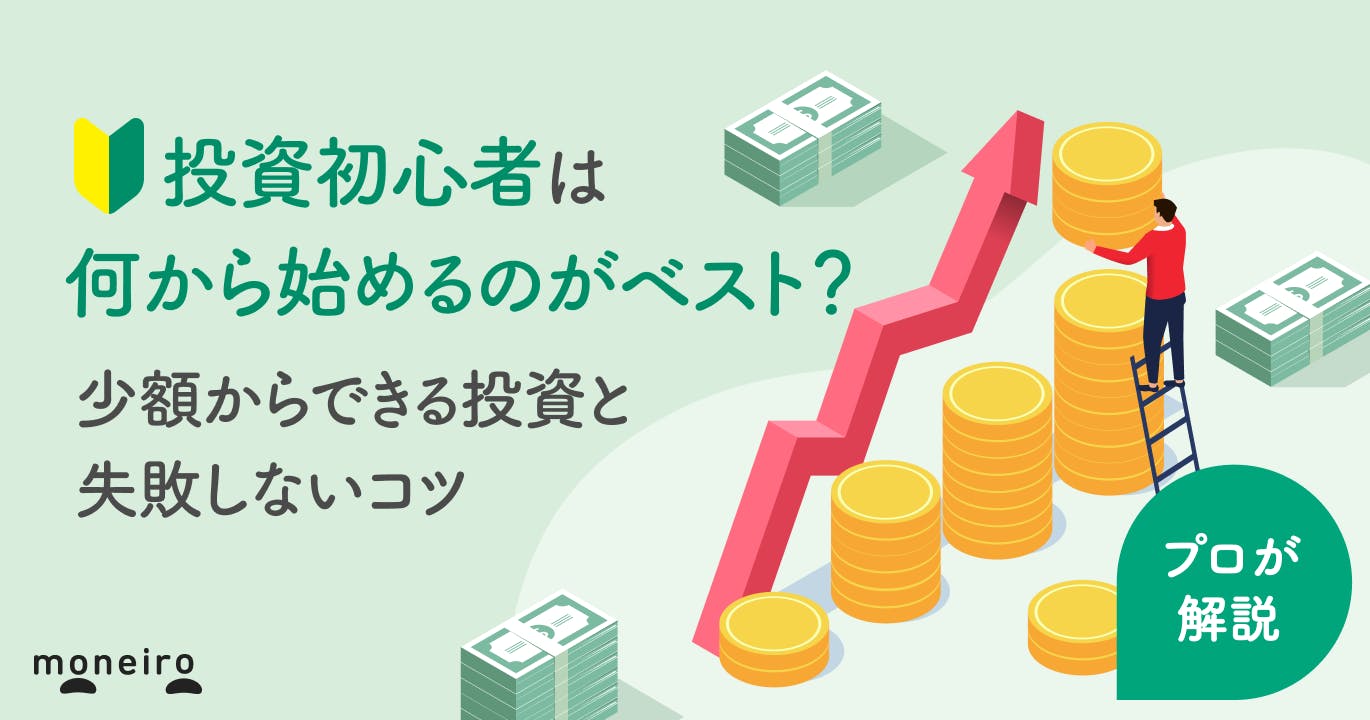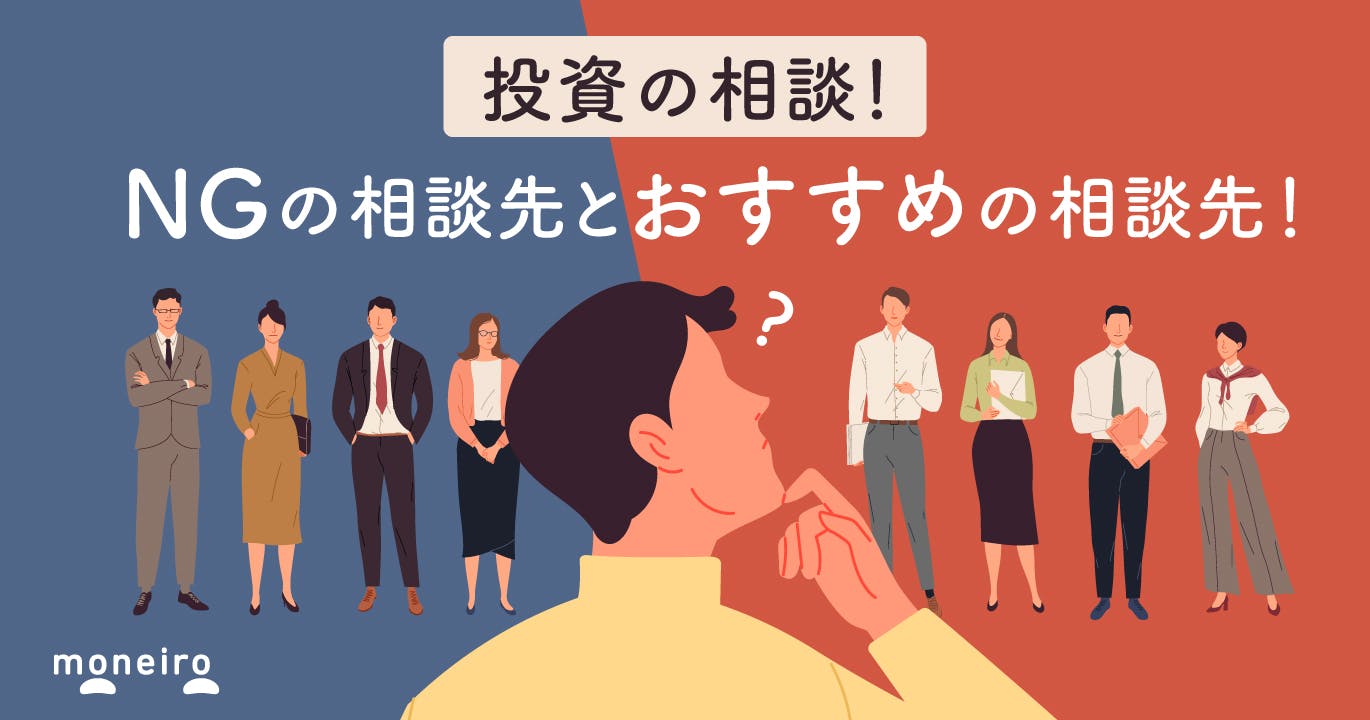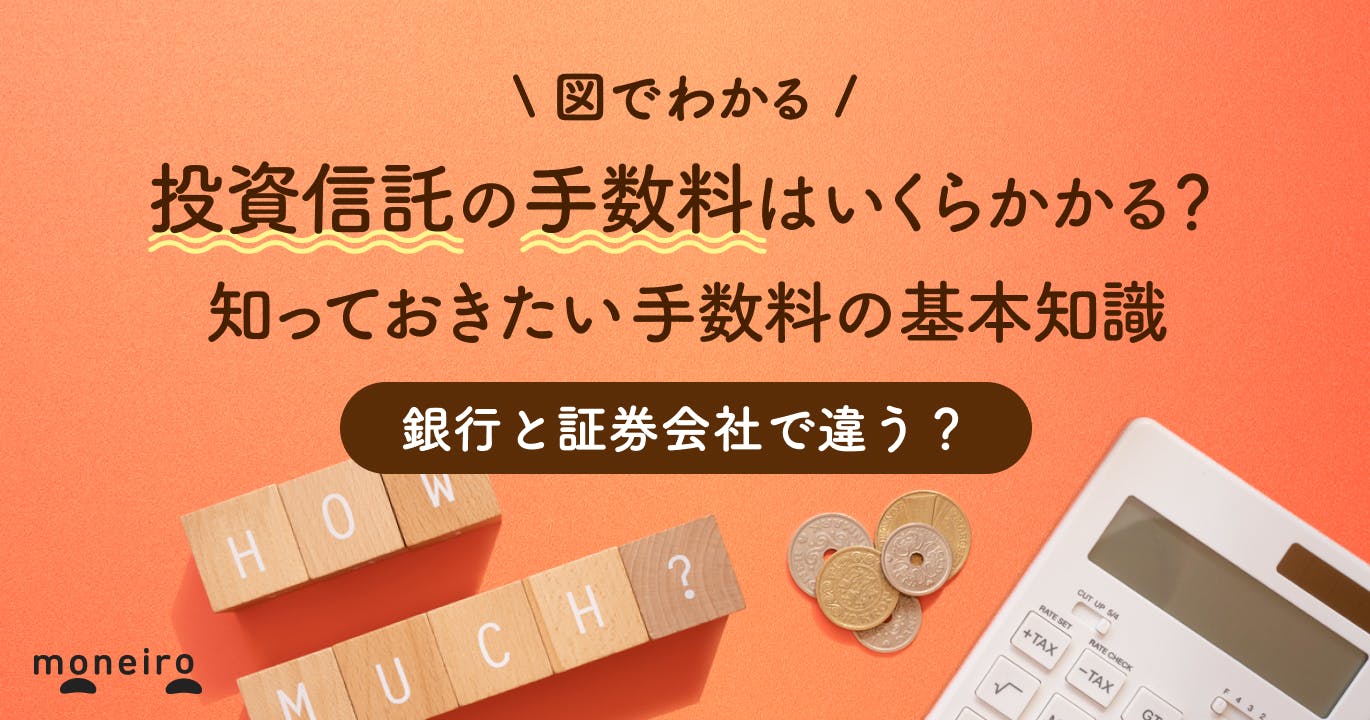投資信託の仕組みとは?なぜ利益が出る?図解でわかる基本知識とポイントを専門家が解説
「投資信託の仕組みを知りたい」「投資信託はどのように利益が出る?」と投資信託の仕組みを知りたい人も多いのではないでしょうか。
投資信託とは、投資家から集めたお金をもとに、資産運用のプロが運用する金融商品です。
投資信託の投資先には、株式や債券、不動産(REIT)などがあり、投資信託に参加することで、さまざまな資産に分散投資ができます。
また、金融機関によっては100円から投資を始められるため、初心者でも手軽に始められるのが魅力です。
一方で、投資信託の種類は数多くあるため、その中から自分に合った商品を選ぶのは至難の業かもしれません。
本記事では、「投資信託の仕組みを詳しく知りたい」と思っている人に向けて、初心者向けに投資信託の仕組みについて投資のプロがわかりやすく解説します。
- 投資信託とは投資家から集めたお金を資金としてプロが運用する金融商品のこと
- 投資信託で得られる主な利益は「売却益(キャピタルゲイン)」「分配金(インカムゲイン)」
- 投資信託を選ぶ時のポイントは「投資対象と商品の特徴」「リスクとリターン」
投資信託が気になるあなたへ
投資信託での資産形成の始めかたを学べる無料サービスをご用意しました。
▶NISAで始める資産運用の基本:投資信託とは?から30分で解説
▶成長投資枠の失敗しない銘柄選び:NISAの投資信託選びを解説
▶投資信託えらびをプロがアドバイス:専門家に資産運用を無料相談
▶3分投資診断:あなたと相性良い投資がわかる
投資信託とは「プロが運用する金融商品」
投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめ、プロが運用する金融商品のこと
投資信託は、複数の投資家が資金を出し合って、専門のファンドマネージャーがその資金を運用し、さまざまな金融商品に分散投資する仕組みです。
投資信託は株式、債券、不動産などの幅広い資産に投資することができます。
個人投資家が一つひとつの金融商品に直接投資する必要がなく、投資信託を通じて多様な資産に分散投資できるため、リスク分散が可能です。
投資信託は、一般の個人投資家にも手軽に投資ができる金融商品として人気があります。投資家は投資信託の口数(投資口の数)に応じて資産の増減を受け取ります。
ただし、投資信託にはリスクがあり、価格変動や経済の影響を受けることがあります。
上記をふまえて、投資信託の仕組みについて詳しく見ていきましょう。
投資信託の全体の仕組みと種類【図解】
投資信託のポイントは以下の3つです。
②運用の専門家(=ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資・運用する
③各投資家の投資信託の購入金額を元本として、運用成果が投資家にとってのリターンまたはロスとなる
投資信託を始める時、銀行や証券会社(=販売会社)で投資信託の売買や、管理のための証券口座を開きます。
投資家は銀行や証券会社のアドバイスなどを参考にしながら、どの投資信託を購入するのか選択します。
投資信託の口座は信託銀行にて分別管理されます。口座を開いた銀行や証券会社が破綻しても、投資家の資金は守られていることになります。
管理するのは信託銀行ですが、肝心の運用方針を考えるのは別会社の運用会社です。
運用会社は方針に沿って信託銀行に指示を出します。信託銀行は指示に従って資産を売買し、運用管理していきます。
投資信託の種類と区分
投資信託にもさまざまな種類や区分があります。
これらを完璧に覚える必要はありませんが、きちんと把握することによって、より自分に合った投資信託を選ぶことができます。
投資対象(REIT・株式・債券・金・その他)
投資対象は主にREIT(不動産投資信託)・株式・債券・金・その他があります。
REITは不動産投資信託とも呼ばれ、オフィスビルや商業施設・住居といった不動産を投資対象として運用する、不動産専門の投資信託です。
株式は「株式会社が出資者に対して発行する証券」で、債券は「国や企業などが、投資家から資金を借り入れるために発行する証券」です。
また、金は「有事の金」といわれ、世界情勢が不安定な時期に購入される傾向があります。
そしてREITや株式・債券・金以外のものをその他資産とします。
独立区分(MMF・MRF・ETF)
MMFは「マネー・マネージメント・ファンド」と呼ばれ、1992年から証券会社で発売されました。
主に国内外の公社債や譲渡性預金(CD)、コマーシャル・ペーパーなどの短期金融資産に投資するオープン型の公社債投資信託です。
似て非なるのがMRFです。MRFは「マネー・リザーブ・ファンド」と呼ばれ、投資対象はMMFと同じです。
MMFとMRFの違いはMMFの場合、購入する度に手続きが必要になりますが、MRFの場合は証券口座に入金するだけで運用が開始できます。
一方ETFは「上場投資信託(Exchange Traded Fund)」と呼ばれ、証券取引所に上場している投資信託で、リアルタイムで売買できます。
運用方法(アクティブ・インデックス)
投資信託の運用方法にはアクティブとインデックスがあります。
投資信託においてアクティブとは「TOPIXなどの特定の指数を上回る成果を目指す」ことを表し、インデックスとは「指数と連動した動きをする」ことを意味します。
アクティブはプロが分析しながら運用を調整するため、購入者の支払う運用コストは高いですが、指数以上のリターンが期待できます。
一方、インデックスの場合は特定の指数とパフォーマンスを合わせるよう調整するため、指数以上のリターンが期待しづらいですが、運用コストは低いです。
購入方法(単位型・追加型)
投資信託を購入する場合、「単位型投資信託」と「追加型投資信託」があります。
単位型は「ユニット型」とも呼ばれ、定められた募集期間中にのみ購入ができます。また、3年や5年といった信託期間が決まっています。
一方、追加型は「オープン型」とも呼ばれ、運用中であればいつでも購入ができ、信託期間が長期間または無期限となっています。
基準価額が下落した場面を狙い目として追加購入したい場合は追加型投資信託のみ可能です。
投資対象地域(国内・海外・内外)
投資対象となる地域の区分は「国内・海外・内外」があります。投資信託協会によると、それぞれの定義は下記のようになっています。
- 国内…主たる投資収益が、実質的に国内の資産を源泉とするもの
- 海外…主たる投資収益が、実質的に海外の資産を源泉とするもの
- 内外…主たる投資収益が、実質的に国内及び海外の資産を源泉とするもの
投資信託で利益が出る仕組み
「投資信託はどういう時にお金が増えるんだろう?」と疑問に思ったことはないでしょうか。
初心者でもわかる投資信託で利益が出る仕組みをわかりやすく解説していきます。
①基準価額が上がることで得られる「売却益(キャピタルゲイン)」
投資信託の価格を「基準価額」といいます。原則、日本の証券取引所が開いている日であれば、毎日基準価額は変動します。
ただし、当日の基準価額は国内外で異なるため、前日以前の組入銘柄の価格を反映したものとなります。
例えば、日本株で運用している投資信託であれば、前日の終値を基準として当日の投資信託の基準価額を決定します。
そのため、前日新たに投資信託を購入した投資家の元本は、1日前の株価が反映された本日の基準価額になります。
自分が購入して以降、基準価額が上がり、そのタイミングで売却すれば「売却益(キャピタルゲイン)」を得ることができるのです。
②運用の収益である「分配金(インカムゲイン)」
投資信託の中には投資している株式や債券などの値上がり益や配当、利息などの利益が生じている場合に「収益分配金」を受け取れるものがあります。
収益分配金が支払われるのは投資信託の決算日です。投資信託には企業と同じように決算日があり、各投資信託によって毎月・3ヶ月・半年・1年ごととタイミングが異なります。
この決算日では収益分配金が支払われるほか、損益・資産の状況が計算・報告されます。
さらに、分配金は支払われず、運用資産として再投資する投資信託もあります。
Q.「分配金あり」と「分配金なし」の違いとそれぞれのメリットは?
分配金ありのメリットは、運用期間中細かく利益確保できることです。
基準価額1万円の投資信託が決算日に1.2万円になり、その後9000円に下落した場合を考えてみましょう。
分配金ありの場合は、1.2万円の時に利益を分配金として支払われます。仮に2000円出た場合、その後9000円に下落しても手元の2000円と合わせれば当初の1万円よりは増えていることになります。
一方、分配金なしの場合は一度1.2万円まで上がったものの、利益が確保されることなく9000円まで下がったことになるため、トータルで損している状態になります。
ただし、分配金が出ないため運用益が再投資され、長期的に運用することで複利効果を得られやすいメリットがあります。
運用益が再投資され、運用資産がその分増えることで、リターンも大きくなる効果のこと
「分配金あり」と「分配金なし」はどちらが良いのでしょうか?
投資家の好みや資金ニーズによって異なります。
分配金ありの場合は、運用中に利益を確保したい投資家に向いています。
しかし、途中で利益を確保し増えた部分を分配金として受け取ってしまうため、複利効果が上手に働かず、大きな資産を作りづらくなります。
既に大きな資産ができていて、その資産で上手く分配金を受け取り、現金収入を得たい場合は良いのかもしれません。
一方、分配金なしの場合は、分配金を受け取らず増えた部分を再投資し最大限運用に回せるため、複利効果が時間とともに大きくなります。
長期的に運用して、複利効果を高めて大きな資産を作っていく資産形成層は「分配金なし」が良いでしょう。
Q.「普通分配金」と「特別分配金」の違いは?
分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類があります。
運用によって得られた利益を元に払われる分配金のことです。普通分配金は投資家の利益となるため、課税対象になります。
利益ではなく元本の一部を投資家へ「返す」仕組みです。タコ足配当といわれています。
特別分配金の場合、個別元本から支払われる分配金のため、運用資金が減っていきます。
普通分配金と違い、特別分配金では「元本の一部が戻ってくる仕組みであるため、利益ではない」という考えから、課税対象外になります。
投資信託の主なメリット
投資初心者でも始めやすい投資信託ですが、大きく分けて3つのメリットがあります。
メリット①少額から投資ができる
投資信託は少額から投資することが可能です。販売会社によっては100円程度から始められます。
ただし、投資する金額が少なすぎると、リターンが上がっても投資の効果が実感しにくいため、月1万円~2万円程度から始めると良いでしょう。
メリット②分散投資でリスクを抑えることができる
投資信託に投資をすれば、分散投資でリスクを抑えた投資が可能です。
投資信託は投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品です。
そのため、投資信託に投資をするだけで資金の投資先は分散していることになります。
株式や債券、不動産などにはそれぞれ値動きの特徴があり、この値動きの方向感や強弱が異なる商品を組み合わせることで、リスクを抑えることが可能になります。
株式のみ、または債券のみに投資した場合よりも、さまざまな資産・銘柄に分散している投資信託の方がリスクは分散され、結果としてリスク軽減につながります。
他にも「先進国株式・新興国株式」「先進国国債・新興国国債」「国内株式・海外株式」といったように地域の分散をすることでリスクを減らすケースもあります。
これらがパッケージ化され、異なる資産が組み合わさった場合に互いの値動きが相殺されることで、投資信託のパフォーマンスに安定感が出てくる(=リスクが抑えられる)のです。
メリット③専門家が運用するから初心者でも始めやすい
投資信託のメリットの一つは、専門家が運用を担当していることです。
投資信託では、ファンドマネージャーと呼ばれる専門家が資金を運用します。
彼らは市場の動向や企業の分析など、投資に関する豊富な知識や経験を持っています。
初心者の場合、自身で市場を追いかけることや企業の分析を行うことは難しいかもしれませんが、ファンドマネージャーはその専門知識を活かして適切な投資を行ってくれます。
自分で投資をする際の判断やリサーチの負担が軽減されるため、投資に関するハードルが下がり、初心者でも比較的始めやすい金融商品だといえるでしょう。
投資信託が気になるあなたへ
投資信託での資産形成の始めかたを学べる無料サービスをご用意しました。
▶NISAで始める資産運用の基本:投資信託とは?から30分で解説
▶成長投資枠の失敗しない銘柄選び:NISAの投資信託選びを解説
▶投資信託えらびをプロがアドバイス:専門家に資産運用を無料相談
▶3分投資診断:あなたと相性良い投資がわかる
投資信託の主なデメリット・リスク
投資信託には以下のようなリスクがあります。運用をするうえで把握しておきましょう。
価格変動リスク
投資信託における価格変動リスクとは、投資信託の価値が市場環境や経済状況の変化により上下するリスクのことです。
投資信託は株式や債券、不動産など、さまざまな金融商品に投資されているため、これらの資産価格が変動する影響を受けます。
例えば、株式が投資対象となっている投資信託では、株式市場の動向によって価値が大きく上下することがあります。
同様に、債券が含まれる投資信託であれば、金利の変動によって債券価格が上下し、投資信託の価値にも影響を与えます。不動産(REIT)を含む場合は、不動産市場の影響を受けるため、景気の変動による価格変動リスクも考慮しなければなりません。
金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利の変動が資産の価値に影響を及ぼすリスクのことです。債券を含む投資では、このリスクが重要な要素となります。
金利の上下に伴う債券価格の変動が、債券を含む投資信託の価値に影響を与えるリスクを指します。
為替変動リスク
為替変動リスクとは、外国の資産に投資する際に、為替レートの変動が資産価値に影響を与えるリスクのことです。
特に外国株や海外債券を組み入れている投資信託では、このリスクが重要になります。
例えば、日本の投資家が米ドル建ての資産に投資している場合、円高が進むと、ドル建てでの資産価値は変わらなくても、日本円に換算した時に資産価値が減少する可能性があります。
一方で円安が進むと、同じ資産が円換算で高く評価されるため、利益が増えることもあります。
為替レートの変動によって外貨建て資産の価値が上下し、投資信託の基準価額や運用成績に影響を与えるリスクを指します。
信用リスク
信用リスクとは、投資先の企業や国が財務状況の悪化などにより、債務の返済が困難または不可能になるリスクのことを指します。
例えば、投資信託が企業債や国債などの債券に投資している場合、その発行体(企業や国)が経済的な問題により利息の支払いや元本の返済ができなくなる可能性があります。
発行体がデフォルト(債務不履行)に陥ると、投資した債券の価値が大幅に下がり、場合によっては投資家が損失を被ることもあります。
投資信託の利益を少しでも増やすポイント
投資信託を運用する際は以下のポイントをおさえましょう。
- 長期運用を心がける
- 投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶ
- 価格変動に動揺しない
- 定期的に運用状況を確認する
- NISAやiDeCoを活用する
投資信託は長期運用を行うことで複利効果を活かし、より効率的にお金を増やすことが期待できます。そのためにも、一時的な価格変動に動揺せず、回復期を含めた運用を心がけましょう。
また、投資信託を活用した国の制度としてNISAとiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。
NISAは少額投資非課税制度と呼ばれ、少額から投資を行うことができ、投資で得た利益は非課税で受け取ることができます。
2024年からは新NISA(新しいNISA)となり、投資可能期間や非課税保有期間の制限がなくなり、より長期運用が実現できる制度となりました。
一方、iDeCoは自分で年金を増やす私的年金制度であり、掛金は全額所得控除、投資で得た利益はNISAと同様に非課税となり、資産を受け取る時にも税控除などがあります。
自身の投資目的に合わせて商品を選んだり、国の制度を上手く活用しましょう。
プロが教える投資信託を選ぶ時のポイントは2つ
投資信託を選ぶ時は下記のポイントをおさえましょう。
投資信託の投資対象は主に「REIT・株式・債券・金・その他」があり、さらに対象地域まで考えると資産の組み合わせはさまざまです。
商品の特徴についても「分配金あり・分配金なし」「アクティブ・インデックス」といったような選択肢があります。
投資対象やそれぞれの特徴は最終的にリスク・リターンに影響を与えます。
総合的に考え、自分に合った投資信託を選ぶことが大切です。
投資信託を始めるなら!おすすめの証券会社
投資信託をするには、まず証券口座の開設が必要です。
ネット証券であれば、口座開設をインターネットで完結できるうえ、手数料も安く抑えられます。
ここでは初心者におすすめのネット証券を2つご紹介します。
証券口座は複数開設できるため、特徴に合わせて使い分けるのもおすすめです。
SBI証券
2023年1月時点でSBIグループ証券口座開設数が910万を突破しており、ネット証券でのシェアが最多となっています。
誰もが馴染みのある証券会社であり、銘柄選びをマネイロでもサポートすることが可能です。
また、2021年の6月から三井住友カードでの積立投資ができるようになりました。
ポイントを貯めつつ、資産運用ができるのも嬉しいポイントです。
SBI証券は、金融商品の網羅性が高く、取引したい商品を見つけることができるでしょう。
\SBI証券ならマネイロで銘柄選びまでサポート中/
楽天証券
サイトが見やすく直感的に操作でき、ツールの種類が豊富で使いやすいことも初心者に人気のポイントです。
また、楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」では、普通預金の金利が大手銀行の場合0.001%なのに対し、最大0.1%に増えるプログラムも。
さらに、
楽天カードで積立投資をすれば、毎月ポイントも貯まります。ポイント投資をすることで、SPU(スーパーポイントアップ)のランクも上がるため、楽天市場で買い物した分のポイント還元率も上げることができます。
楽天経済圏を活用している人は、預金も投資もポイントも、お得に資産運用がはじめられます。
まとめ
投資信託は約6000本あり、この中から、自分に合った投資信託を探すのは知識と労力が必要です。
将来の資金づくりを目指すならば、適切な投資信託を選ぶことで資産を効率よく増やすことができます。
マネイロコンシェルは、数多くある投資信託を運用のプロがしっかりと分析し、より良い投資信託を選別してお客さまにご案内しています。
「どの投資信託が自分に合うかわからない…」とお困りの際は、お気軽にご相談ください。
»無料:投資信託えらびについて、専門家に無料でオンライン相談する
»まずは投資信託が自分に合うか知りたい人は無料診断がおすすめ
投資信託が気になるあなたへ
投資信託での資産形成の始めかたを学べる無料サービスをご用意しました。
▶NISAで始める資産運用の基本:投資信託とは?から30分で解説
▶成長投資枠の失敗しない銘柄選び:NISAの投資信託選びを解説
▶投資信託えらびをプロがアドバイス:専門家に資産運用を無料相談
▶3分投資診断:あなたと相性良い投資がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
泉田 良輔
- 証券アナリスト/経営者/元機関投資家
愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2018年11月、株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)を共同設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。
執筆
柴又 順平
- ファイナンシャルアドバイザー
専修大学・経営学部を卒業後、株式会社三井住友銀行に入社。おもに富裕層向けに、約17年間資産運用コンサルティング業務に従事。投信、保険、債券、住宅ローン、遺言信託、資産承継など、幅広い金融商品の取り扱いが可能で深い知識を有している。キャリアの途中からは管理職として部下の育成にも関わる。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社。現在は、金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。AFP(Affiliated Financial Planner)、一種外務員資格(証券外務員一種)、プライマリーPB(プライベートバンカー)資格を保有
宮内 勇資
- ファイナンシャルアドバイザー
ファイナンシャルアドバイザー。専修大学商学部卒業後、水戸証券株に入社。リテール営業に従事し、国内外株式、投資信託、債券などが得意分野。キャリアの途中からは人材育成にも携わり、主に若手社員の能力向上に大きく貢献した。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社。現在は個人向け資産運用コンサルティング業務を行う。AFP(Affiliated Financial Planner)、一種外務員資格(証券外務員一種)保有