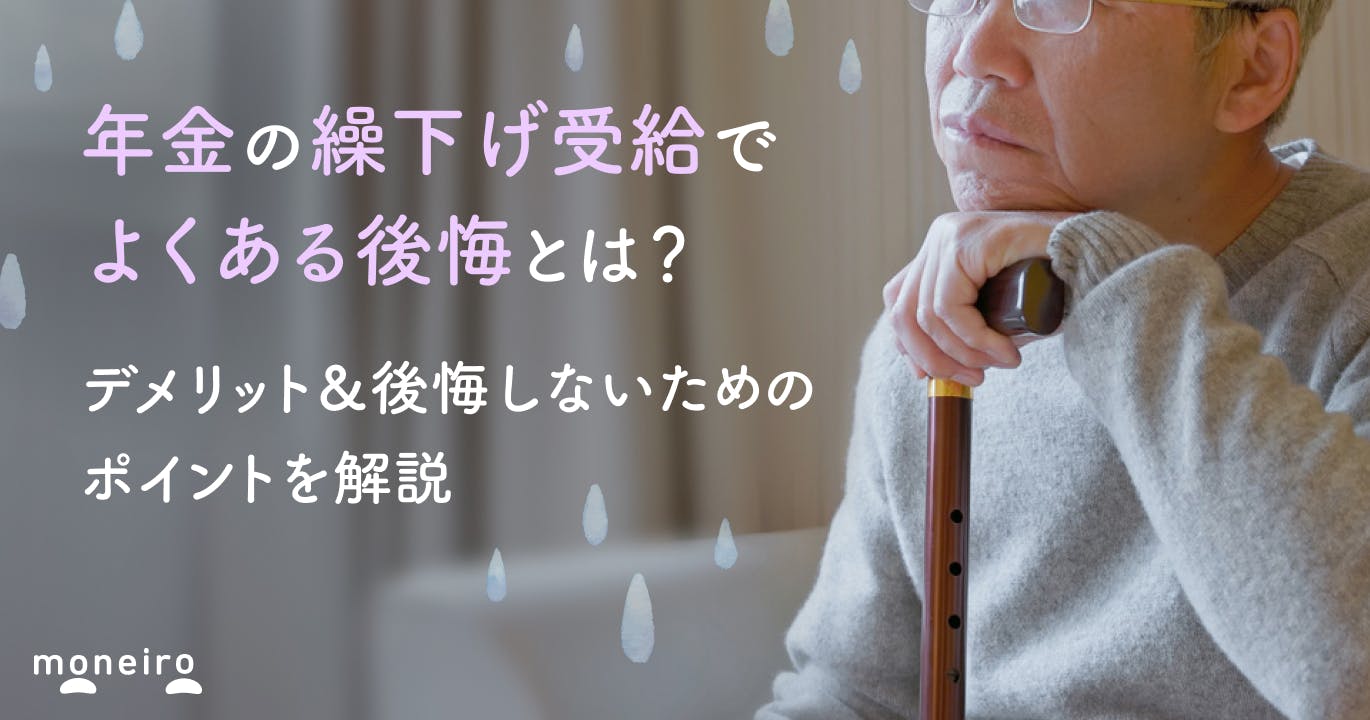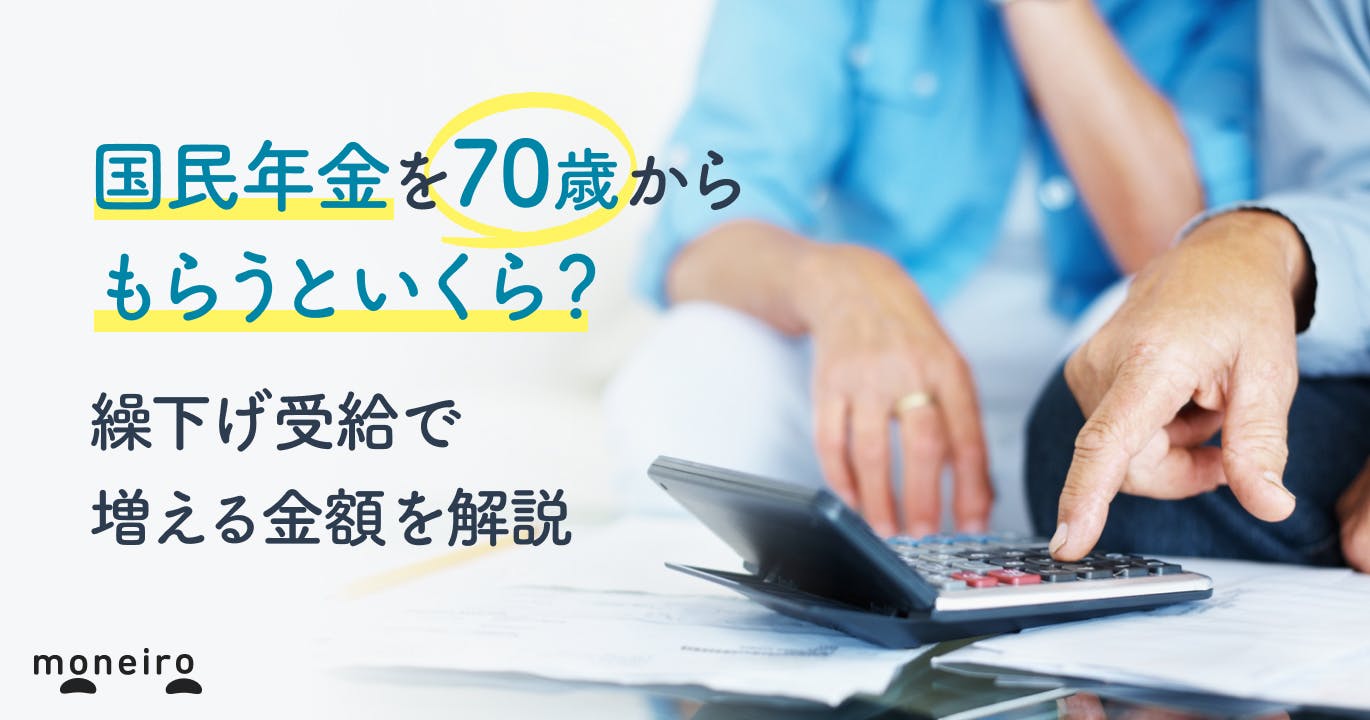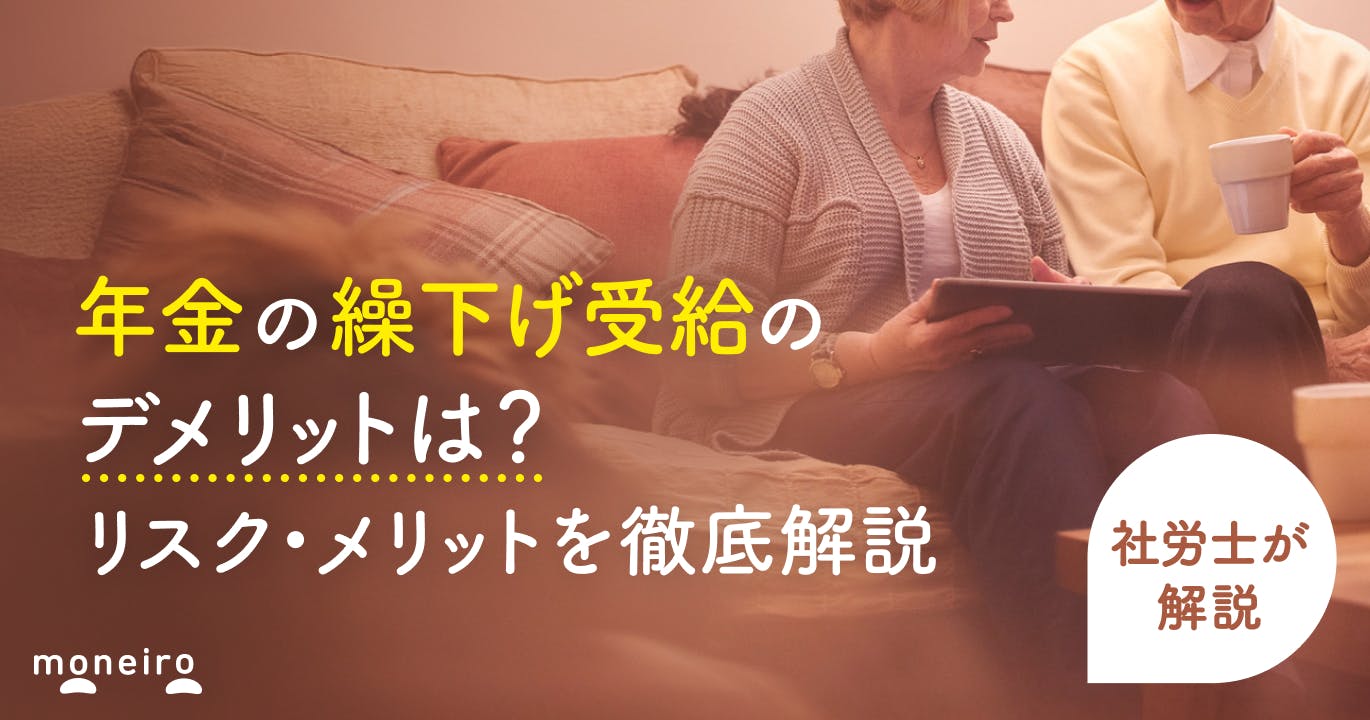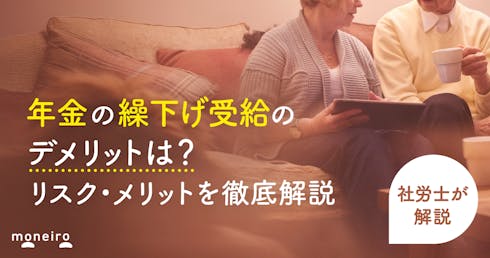
年金の繰下げ受給でよくある後悔とは?デメリット&後悔しないためのポイントを解説
≫老後資金は足りる?あなたの必要額を3分で診断
年金は原則65歳から受け取れますが、「繰下げ受給」を選択すれば、受け取り開始を遅らせる代わりに、将来受け取る年金額を増やせます。長生きリスクに備えられ、老後の生活にゆとりを持たせられる可能性がある魅力的な制度ですが、一方で「繰り下げなければよかった」と後悔するケースも少なくありません。
そこでこの記事では、年金の繰下げ受給で後悔しがちな具体的なケースと、その背景にあるデメリットを詳しく解説します。さらに、ご自身が後悔しない選択をするための重要な判断ポイントや、繰下げ受給が向いている人の特徴、万が一後悔した場合の対処法まで網羅的に紹介します。
① 年金の繰下げ受給の仕組みと、どれくらい年金額が増えるのか
② 繰下げ受給のメリットと、よくある後悔・デメリット
③ 繰下げ受給を選ぶべきか判断するための確認事項と、どんな人に適しているか
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
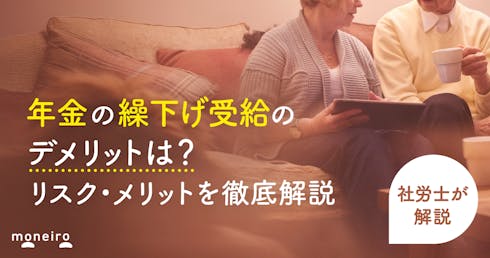
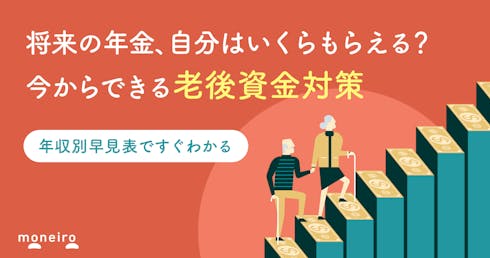
年金の繰下げ受給とは?制度の基本をおさらい
「年金の繰下げ受給」という言葉を聞いたことはあっても、詳しい仕組みはよく知らない、という方もいらっしゃるかもしれません。まずは、繰下げ受給制度の基本的なルールについて、しっかりとおさらいしておきましょう。
繰下げ受給の条件と手続き
繰下げ受給を選択できるのは、65歳で老齢年金を受け取る権利が発生した人です。
繰下げ受給をするには、65歳の誕生日の前月に日本年金機構から送られてくる「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を、すぐには提出せず、実際に受給を開始したい時期(66歳以降75歳まで)に提出します。
繰下げ受給による増額率は?
年金の受給開始は、66歳0ヶ月から、最長で75歳0ヶ月までの間で、1ヶ月単位で自由に選択して繰り下げることができます。
繰り下げた場合の年金の増額率は、繰り下げた月数×0.7%で計算されます。この増額率は生涯変わりません。
具体的に、受給開始年齢ごとの増額率と、65歳時点の年金額が年間200万円の場合の受給額例を見てみましょう。
※年間受給額、月額受給額、年間差額は概算です。
このように、表を見ると繰下げ期間が長くなるほど増額率が高くなり、将来の受給額が大きく増えることがよく分かります。
繰下げ受給のメリット
繰下げ受給を検討すべきかどうか、まずは3つのメリットを確認した上で考えてみましょう。
毎回の受給額を大きく増やせる
最大のメリットは、増額された年金額が生涯にわたって続くことです。1ヶ月あたり0.7%(1年で8.4%)、受給開始を75歳まで遅らせた場合は84%も年金額が増えます。安定的な収入を多く確保できることは、老後生活の大きな安心感につながります。
長生きリスク対策になる
当然ながら、長く生きるほど生活に必要な資金は大きくなります。「人生100年時代」ともいわれる現代では、「長生きしすぎて資金が足りなくなる」という長生きリスクへの備えは重要です。
繰下げ受給による増額率は一生涯変わりません。終身年金である公的年金の額自体を増やしておくことは、長生きリスクに対する非常に有効な備えとなります。
インフレリスク対策になる
将来の物価上昇(インフレ)は、現金の価値を実質的に目減りさせます。
公的年金は物価上昇率などによって給付額が1年毎に改定されますが、完全にインフレをカバーできるとは限りません。
繰下げによって年金そのものを増やしておけば、インフレによる購買力の低下を抑えることができます。
将来のお金の価値が不安な場合、繰下げ受給は有効なインフレリスク対策の1つとなり得ます。
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
年金の繰下げ受給でよくある後悔・デメリット
魅力的な繰下げ受給ですが、安易に選択すると後悔につながる可能性もあります。主なデメリットやリスクを見ていきましょう。
想定よりも長生きできない可能性がある
もっともよく聞かれる後悔が、「繰り下げたものの早くに亡くなり、結果的に65歳から受け取っていたほうが得だった」というケースです。
繰下げ受給は、待機期間中に受け取れなかった年金額を、増額された年金で回収していく仕組みです。そのため、元を取る(65歳受給開始の場合の受給総額を上回る)には、ある程度の期間長生きする必要があります。
この「元が取れる年齢」=損益分岐点は、上記の図のように70歳で受給開始した場合で「81歳11ヶ月」、75歳で受給開始した場合なら「86歳11ヶ月」となり、この年齢より前に亡くなると、生涯の受給総額は65歳開始より少なくなります。
繰下げ待機期間中に貯蓄が底をつく
年金の繰下げを選択すると、65歳から受給開始までの間の生活費は貯蓄や他の収入で賄う必要があります。
繰下げ期間が長引けば、それだけ多くの生活資金が必要になります。貯蓄を取り崩して生活費に充てる場合、例えば病気による高額な医療費、家族の介護費、収入の予期せぬ減少などが重なると、準備していた貯蓄が想定より早く底をついてしまう危険性があります。
資金が尽きれば生活は困窮し、不本意ながら繰下げ受給の計画を変更せざるを得なくなるかもしれません。余裕を持った資金計画とリスク管理が不可欠です。
健康状態が悪くなり、お金を使い切れなくなる
ようやく増額された年金を受け取り始めたものの、「病気やケガで健康状態が悪化し、思うように活動できなくなった」という後悔も聞かれます。
せっかく増やした年金を趣味や旅行などに使えないのは精神的に辛く、「身体が元気なうちから年金をもらっておけば」と後悔する可能性があります。
加給年金が受け取れない
厚生年金に20年以上加入している人が、65歳時点で生計を維持している配偶者や子がいる場合に受け取れる「加給年金」は、老齢厚生年金の繰下げ待機期間中は支給されません。
配偶者が65歳になると加給年金は終了し、配偶者の年金に「振替加算」がつく場合がありますが、この振替加算も繰下げ待機中は受け取れません。加給年金の対象となる人は、繰下げ受給による影響を慎重に検討する必要があります。
税金や社会保険料の負担が増える
年金は「雑所得」となるため、繰下げ受給によって受給額が増えると所得税や住民税の負担が増えることになります。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて算定されるため、同様に社会保険料の負担も増えることになります。
≫あなたの老後資産は大丈夫?将来の必要額を今すぐチェック
年金繰下げ受給で後悔しないための確認事項
繰下げ受給を選択するかどうかは、個々の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。
以下の点を確認してみましょう。
通常受給や繰上げ受給との比較
繰下げ受給を検討する際は、必ず65歳からの「通常受給」や、60歳から64歳の間に受給開始する「繰上げ受給」と比較することが重要です。
繰上げ受給は早く年金を受け取れますが、1ヶ月早めるごとに0.4%ずつ減額され(最大24%減)、その減額率は生涯続きます。一方、繰下げ受給は1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額(最大84%増)されます。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の健康状態や就労状況、貯蓄額、受給総額の逆転年齢(損益分岐点)を考慮して、どの受給方法が最適かシミュレーションしましょう。
例えば、「早くリタイアしたいが貯蓄は少ない」なら繰上げ受給も選択肢ですが、「長く元気に働けそうで老後資金を増やしたい」なら繰下げ受給が有利かもしれません。日本年金機構の「ねんきんネット」や年金事務所の窓口、ファイナンシャルプランナーなどに相談して具体的な試算を行うことをおすすめします。
(男女別)平均寿命と自分の健康状態
繰下げ判断の基本として、自身の余命や健康寿命についても考えてみましょう。
まずは厚生労働省「令和5年簡易生命表」で公表されている、日本人の平均寿命(2023年は男性81.09歳、女性87.14歳)や65歳時点での平均余命(男性19.52年、女性24.38年)を参考にしましょう。
また、「健康寿命の令和4年値について」では、健康上の問題なく生活できる健康寿命(2022年は男性72.57歳、女性75.45歳)も公表されていますのでこちらも参考にするとよいでしょう。
その上で、持病の有無や定期健診の結果、食生活や運動習慣、ご家族の既往歴なども考慮し、何歳まで元気に活動できそうか具体的にイメージします。
繰下げ受給の損益分岐点と比較し、メリットを享受できる可能性を検討することが重要です。
60歳以降の働き方の見通し
繰下げ受給を選択する場合、資産状況によっては65歳以降も働き続ける必要が出てくる可能性があります。重要なのは意欲だけでなく、具体的な働き方と収入の見込みです。
勤務先の定年・再雇用制度や、継続雇用される場合の給与水準、勤務時間などの条件を確認しておきましょう。働くことで年金がなくても生活できる十分な収入を確保できれば、繰下げ受給を選択しやすくなります。
逆に、定年退職を希望している、健康不安がある、あるいは再雇用後の収入が低い見込みの場合は、待機期間中の生活が苦しくなる可能性があるため慎重な判断が必要になります。
貯蓄や他の収入源の状況
繰下げ待機期間中は年金収入がないため、その間の生活費を賄える十分な貯蓄や、他の収入源が不可欠です。また、年齢を重ねると病気やケガなどで思わぬ出費が発生する可能性も高まるため、余裕を持った資金計画が重要になります。
待機期間中のキャッシュフローを具体的に試算し、資金ショートのリスクがないか慎重に確認することが大切です。
なお実際には、貯蓄を取り崩して繰下げ受給する人は多くはありません。給与収入のほか、安定した不動産収入や配当収入、個人・企業年金など、貯蓄の取り崩しに頼らなくていい状態をつくっておくことが大切です。
繰下げ受給をしたほうがよい人とは?
上記の確認事項を踏まえ、繰下げ受給が特に適していると考えられるのは以下のような人です。
長生きする可能性が高い人
ご自身の健康状態に自信があり、ご両親や祖父母など血縁者も長生きしている家系であるなど、統計的な平均寿命以上に長生きする可能性が高いと考えている人です。
このような方にとっては、繰下げ受給による「生涯にわたる増額された年金」というメリットを最大限に享受できる可能性が高まります。損益分岐年齢を大きく超えて長生きすればするほど、65歳受給開始の場合との受給総額の差は開いていきます。
貯蓄や他の収入が十分にある人
繰下げ待機期間中の生活費について心配する必要がない人です。
具体的には、65歳以降も高い収入を得られる就労を継続できる方や、繰下げ待機期間中の数年間の生活費を余裕で賄えるだけの十分な金融資産(預貯金、退職金、有価証券など)を保有している人、あるいは安定した家賃収入や個人年金など、年金以外の不労所得が十分に確保できている人などです。
経済的な基盤が盤石であればあるほど、安心して繰下げを選択し、そのメリットを享受できるでしょう。
老後の生活水準を上げたい人
現役時代の生活レベルをできるだけ落とさずに老後も暮らしたい、あるいは、老後は旅行や趣味、孫へのお小遣いなど、ゆとりのある豊かな生活を送りたいと具体的に考えている人です。
繰下げによって増額された年金は、そのような希望を実現するための強力な資金源となります。特に厚生年金の加入期間が長く、もともとの年金額が多い人は、繰下げ受給による増額効果も大きくなるため、より生活水準の向上に貢献するでしょう。
インフレに備えたい人
将来、物価が継続的に上昇していくインフレによって、お金の価値が実質的に目減りしていくリスクに強い懸念を持っている人です。
年金額は物価や賃金の変動に応じて改定されますが、繰下げによってそもそもの年金額を増やしておくことで、インフレ下でも年金の購買力を維持しやすくなる効果が期待できます。
将来のお金の価値に不安を感じ、少しでも実質的な年金価値を確保しておきたいと考える人にとって、繰下げは有効なインフレ対策の1つとなり得ます。
繰下げ受給をしてしまった後悔を取り戻すには?
もし繰下げ受給を選択したものの、後になって「しなければよかった」と感じた場合、残念ながら一度開始した年金の受給開始年齢を遡って変更することはできません。しかし、状況を改善するためにできることはあります。
収入源を増やす
年金の繰下げ待機期間中や、受給開始後の生活にゆとりを持たせるためには、年金以外の収入源を確保・増加させることが有効な対策となります。体力や意欲に応じて、まずは再就職やパート・アルバイトを探してみましょう。
支出を減らす
収入を増やす努力と同時に、日々の支出を見直し、無駄を削減することも非常に重要です。まずは、家計簿アプリやノートなどを活用して、毎月の収入と支出を正確に「見える化」することから始めましょう。
何にどれくらい使っているかを把握することで、改善点が見えてきます。特に効果が大きいのが固定費の見直しです。
例えば、住居費(住宅ローンの借り換えや住み替え検討)、通信費(スマートフォンやインターネット回線のプラン変更、格安SIMへの乗り換え)、保険料の見直し、利用頻度の低いサブスクリプションサービスの解約などが挙げられます。無理のない範囲で節約を心がけましょう。
健康管理を徹底する
老後の生活の質(QOL)を高く保ち、安心して暮らすためには、何よりも健康が重要です。
健康寿命(健康上の問題なく日常生活を送れる期間)をできるだけ長く維持することは、医療費や介護費といった将来的な支出を抑制することにもつながります。
また、自覚症状がなくても、定期的に健康診断やがん検診を受け、身体の状態をチェックし、病気の早期発見・早期治療に努めましょう。持病がある方は、医師の指示に従い、適切に管理することが重要です。
専門家に相談する
年金の繰下げに関する判断や、老後の資金計画、家計の改善策などについて、自分一人で悩んでしまうこともあるでしょう。
そのような時は、お金や年金の専門家に相談することも有効な手段です。現在の資産状況や将来の収入予測から、必要資金を割り出し、どのような受け取り方が最適なのかアドバイスを受けることができます。
「専門知識がなく不安」「何を聞いたらよいかわからない」という場合でも一人ひとりに合わせたサポートを受けられるので、年金や老後資金について不安がある場合は、ぜひ専門家への相談を検討してみましょう。
>>年金についてマネイロサポートに相談してみる
まとめ
年金の繰下げ受給で後悔することは実際にあり得ます。繰下げ受給は、受給額を最大84%増やせる魅力的な制度ですが、そのメリットを享受できるかどうかは、個人の健康状態、寿命、経済状況、ライフプランによって大きく異なります。
「長生きできなかった」「思ったより早く資金が尽きた」「健康を損ねてお金を使えなかった」といった後悔をしないためには、制度の仕組みやメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の状況と照らし合わせて慎重に判断することが何よりも重要です。
ご自身のセカンドライフをより豊かにするために、繰下げ受給の基本を押さえた上で、最適な年金の受け取り方を見つけましょう。
≫あなたの老後資産は大丈夫?将来の必要額を今すぐチェック
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。