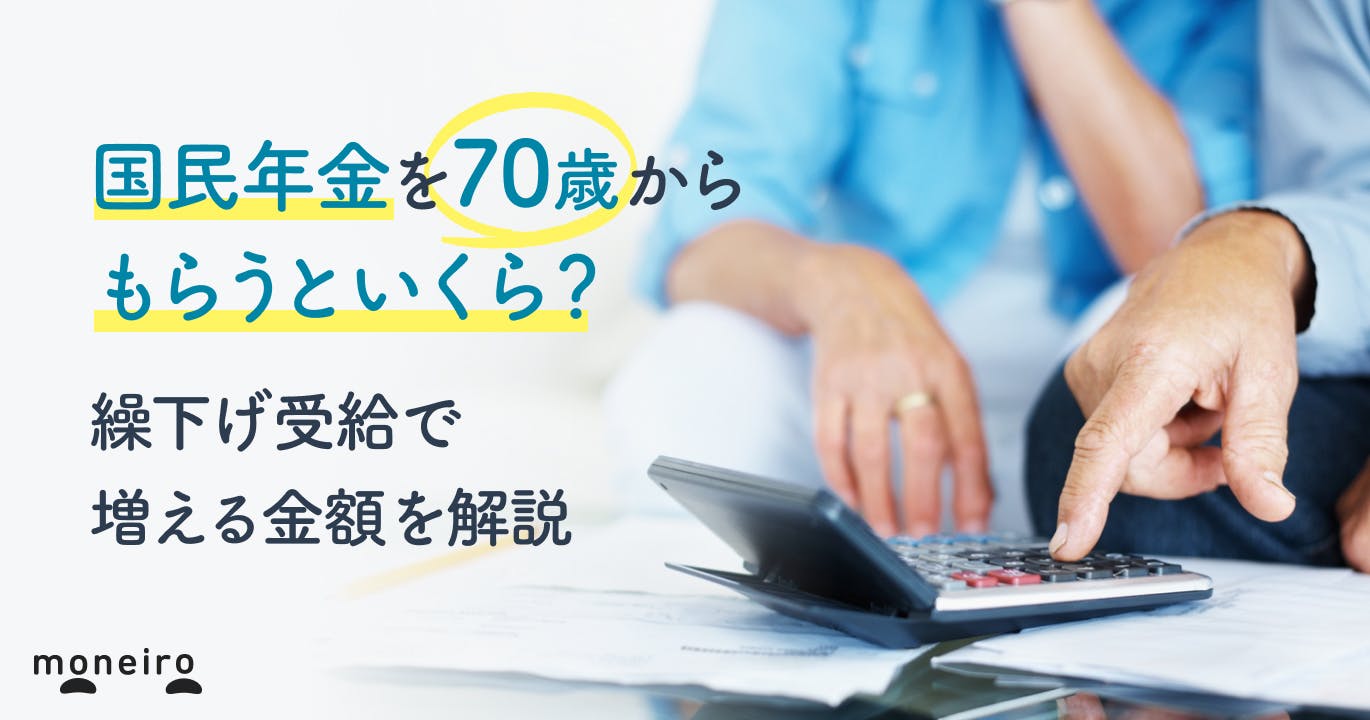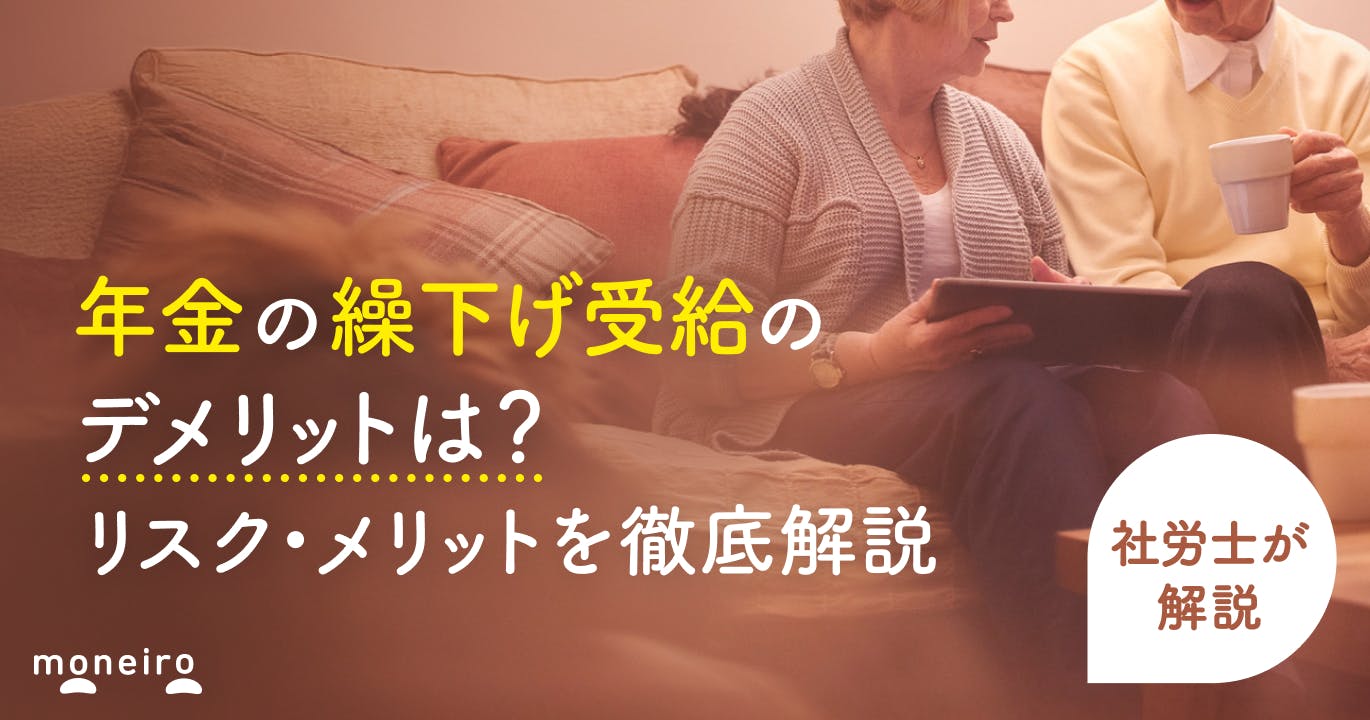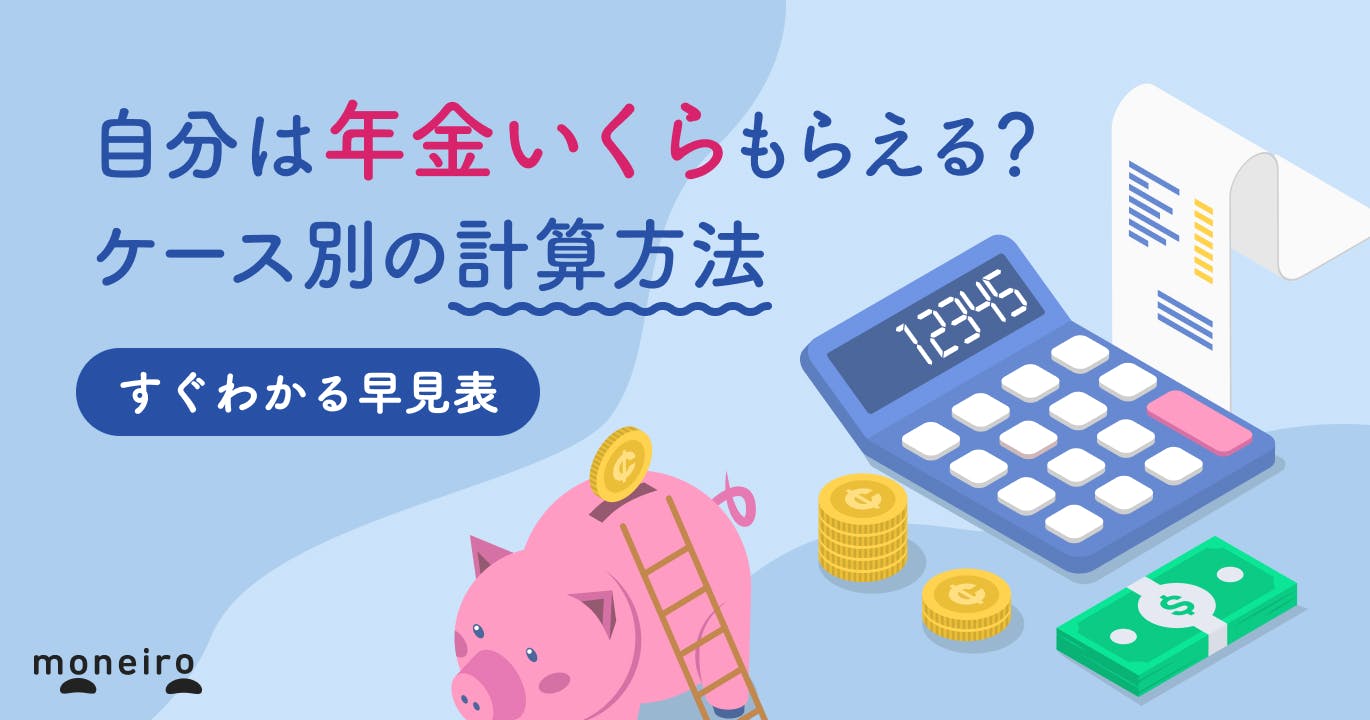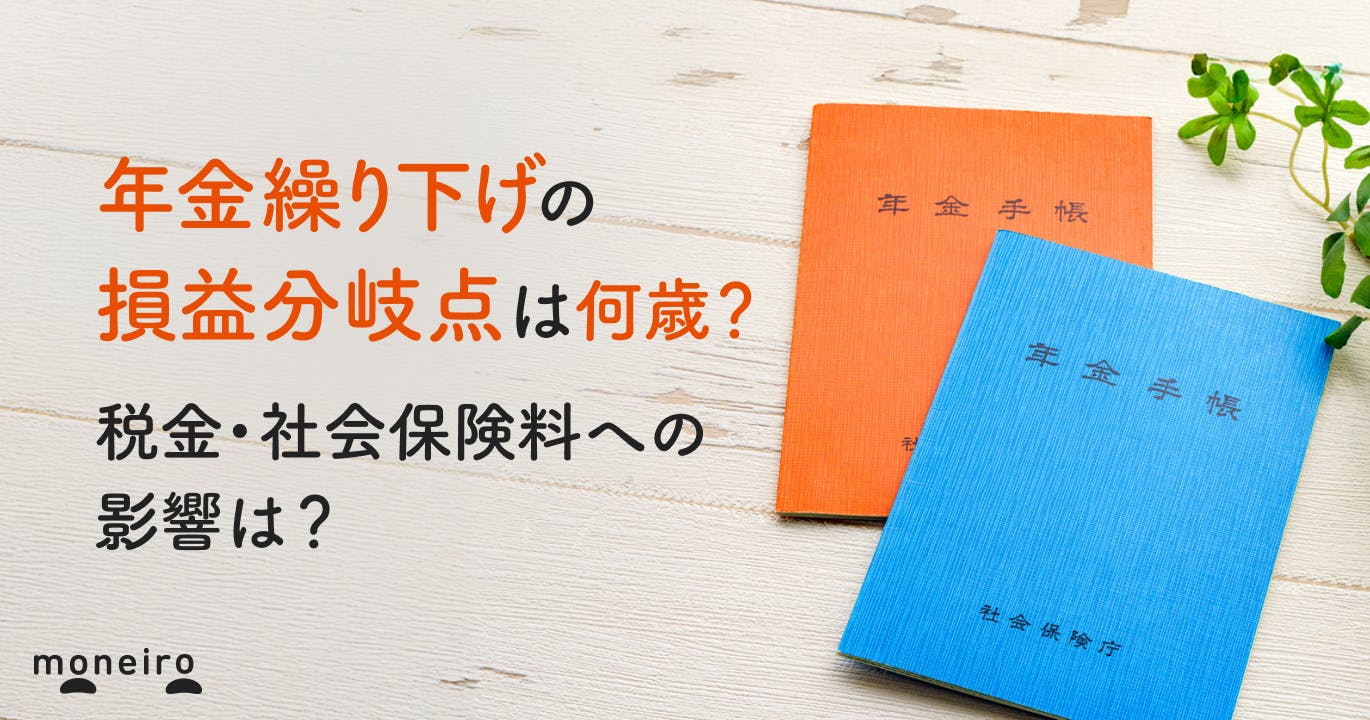
国民年金を70歳からもらうといくら?繰下げ受給で増える金額&注意点を解説
【無料】あなたの老後資金は足りる?必要額を診断
年金の受給を70歳まで待ち、繰下げ受給を選択すると、増額された年金を一生涯受け取れます。65歳から受け取れる年金額よりも42%増額されるため、老後の安心につながるでしょう。
そこで今回は、国民年金の受給開始を70歳まで繰り下げた場合の年金額や増額率、メリットなどを解説します。デメリットや損益分岐点なども解説するため、最適な受給開始年齢を選択する際の参考にしてみてください。
- 年金を70歳からもらうと、42%増額された金額を一生涯受け取れる
- 長生きリスクに備えるために、繰下げ受給は効果的な選択肢となる
- 繰下げ受給を選択するには、年金を受け取れない期間の生活費を考える必要がある
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金を70歳からもらうといくらになる?具体的な金額を計算
現行制度において、公的年金を受給する基準となる年齢は65歳です。しかし、受給開始する年齢は60歳から75歳までの間で選択できます。
受給を開始する年齢によって受給額は変わるため、まずは受給開始時期によってどのような影響があるのかを確認しましょう。
年金は繰上げ受給・繰下げ受給ができる
60~64歳から年金を受給開始することを「繰上げ受給」、66歳以降に年金を受給開始することを「繰下げ受給」といいます。それぞれの受給方法が年金額にもたらす影響を見ていきましょう。
繰上げ受給した場合の受給額の計算
繰上げ受給を選択した場合、65歳を基準としたときの年金額から、繰上げ月数1ヶ月あたり0.4%が減額されます(1962年4月1日以前生まれの方は0.5%)。計算式で表すと、以下のとおりです。
減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
例えば、60歳時点で繰上げ受給を選択すると、減額率は24%(0.4%×60ヶ月)です。減額された年金額は一生涯続くため、長生きするほど損をしてしまう可能性が考えられます。
繰下げ受給した場合の受給額の計算
繰下げ受給を選択した場合、65歳を基準としたときの年金額から、繰下げ月数1ヶ月あたり0.7%が増額されます。計算式で表すと、以下のとおりです。
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
例えば、70歳から受給を開始した場合、増額率は42%(0.7%×60ヶ月)、75歳まで繰り下げた場合は、84%(0.7%×120ヶ月)の増額率となります。
繰下げにより増額された年金は一生涯続きます。長寿化が進み老後期間が長期化している状況を考えると、可能な範囲で繰下げ受給を選択することで、経済的な安心につながるでしょう。
国民年金を70歳から受給開始した場合はいくらもらえる?
実際に、国民年金の受給を70歳から開始した場合、いくらもらえるのかをシミュレーションしてみましょう。なお、2025年における満額の老齢基礎年金は月額6万9308円、年額83万1700円です。
この金額をベースにすると、年金の月額と年額はそれぞれ以下のとおりです。
最近では65歳以上になっても働く方が増えています。できるだけ長く働き、勤労収入で生活費をカバーし、できるだけ年金を繰下げるという選択肢が考えられます。
受給できる年金額を増やせば、老後の経済的不安の軽減につながるでしょう。
【参考】60歳から繰上げ受給したらどうなる?
逆に、60歳から繰上げ受給を選択すると、どの程度の減額となるでしょうか。同じく、満額の老齢基礎年金をベースにシミュレーションしました。
繰上げ受給は早く年金を受給できる一方で、減額された年金額が一生涯続きます。ご自身の健康状態や今後のライフイベントなどを踏まえて、本当に繰り上げる必要があるのかどうかを慎重に考える必要があるでしょう。
≫あなたの老後資金は大丈夫?将来不足する金額を3分で診断
国民年金を70歳から受給するメリット・デメリット
年金は老後生活を支える軸となる収入であるため、受給するタイミングは慎重に判断しましょう。国民年金を70歳から受給するメリットとデメリットについて、詳しく解説します。
70歳から受給するメリット
まずは、70歳から受給するメリットについて見ていきましょう。
受給額が増える
受給額が増える点は、もっともわかりやすいメリットです。満額の老齢基礎年金を受給できるケースであれば、70歳からの受給開始で月額で3万円近い増額となります。
年金は生きている間、定期的に収入を運んでくれる頼れる社会保障制度です(給付は2ヶ月に1回)。一般的に、高齢になるほど医療費や介護費がかかるため、少しでも定期収入を増やしておけば安心につながるでしょう。
長生きリスクに備えられる
厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年です。また、同資料の中では、65歳時点の平均余命として男性が19.52歳、女性が24.38歳であることも示されています。
日本人の平均寿命は、年々延びており、喜ばしいことである一方で、「長生きリスク」という言葉も注目されるようになりました。長生きリスクが顕在化すると、生活費の不足や、医療費・介護費を支払えないといった事態になりかねません。
しかし、年金を70歳まで繰下げることで増額された年金を一生涯受け取れるため、長生きリスクへの備えとなります。「年金額>基礎生活費」という状況を維持できれば、老後に破産するリスクを大幅に軽減できます。
予想以上に長生きしてしまい、老後の生活資金が足りなくなってしまうリスクを指します。
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
70歳から受給するデメリット
続いて、70歳から繰下げ受給する際のデメリットについて見ていきましょう。
年金収入のない期間が増える
繰下げ期間中(受取までの待機期間)は、年金を受給できません。例えば、60歳でリタイアする場合、10年間は年金を受給できない期間が発生します。
年金収入のない期間は、他の手立てを講じて生活を支える必要があります。できるだけ長く働いて収入を得たり、退職金や企業年金を活用して生活費を工面したり、さまざまな方法が考えられるでしょう。
繰下げ受給を選択するためには、事前に「何歳まで働くか」「60歳・65歳時点での保有資産はいくらか」などをトータルで考える必要があります。
受給総額で損する可能性がある
繰下げ受給を選択すると、年金を受給できない期間が発生する分、65歳時点で受給した場合よりも受給総額で損をする可能性があります。
65歳時点で受給した場合と70歳から繰下げ受給を開始した場合の損益分岐点は「81歳11ヶ月」です。つまり、81歳10ヶ月よりも前に亡くなってしまうと、結果的に損をしてしまいます。
しかし、年金の本質は老後で収入がなくなったとき、安心して生活できるように備える「保険」です。事前に自分が何歳で亡くなるか分からない以上、年金を損得のみで考えるのは得策とはいえません。
「老後生活における経済的な不安を軽減したい」と考えるのであれば、身体的に無理のない範囲で労働を継続し、繰下げ受給をするのが合理的な判断といえるでしょう。
繰下げ受給を選択し70歳まで働く場合の注意点
70歳まで働いて収入を得られる場合は、70歳からの繰下げ受給が現実味を帯びてきます。ただし、70歳まで働く場合は、「在職老齢年金」や「加給年金」との兼ね合いに注意が必要です。それぞれ、詳しく見ていきましょう。
在職老齢年金制度で年金カットの可能性がある
60歳以上で、給与と年金をそれぞれ受給している方は、在職老齢年金の影響を受ける可能性があります。
「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が51万円を超える場合は、超えた分の1/2が老齢厚生年金からカットされます。なお、基本月額と総報酬月額相当額の定義は以下のとおりです。
例えば、以下のようなケースで考えてみましょう。
- 基本月額:18万円
- 総報酬月額相当額:35万円
- 合計:53万円
この場合、支給停止となる年金は「(53万円-51万円)×1/2=1万円」です。つまり、支給される老齢厚生年金は17万円に減額されます。老齢厚生年金のみ65歳から受給し、かつ65歳以上になっても働く方は、ご自身の年金額や報酬を確認しておきましょう。
厚生労働省の資料「在職老齢年金について」によると、65歳以上で在職している年金受給権者の16%が、在職老齢年金制度により支給停止の対象となっています。※2022年度末のデータ
加給年金への影響も
国民年金と一緒に厚生年金も繰下げ受給する場合には「加給年金」にも影響が及ぶ可能性があります。
65歳時点で厚生年金に20年以上加入していて(または65歳以降に厚生年金加入期間が20年になり)、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満の子(1級・2級の障害を持つ子は20歳未満)がいる場合、以下の金額が厚生年金に加算されます。
加給年金は、在職老齢年金によって老齢厚生年金が全額支給停止になっている間や、老齢厚生年金の繰下げ期間中は支給されません。つまり、「加給年金だけ受け取る」という対応はできません。
年金の繰下げ受給に関するQ&A
最後に、年金の繰下げ受給に関するよくある質問と回答を紹介します。
Q.70歳を過ぎても繰下げ受給はできますか?
現行制度において、最長で75歳まで繰下げ受給が可能です。75歳から受給を開始した場合、65歳時点と比較して84%増額された年金を受給できます。
ただし、昭和27年(1952年)4月1日以前生まれの方は、70歳までしか繰下げできません。
Q.繰下げ受給の待機期間中に、65歳からの受給に変更できますか?
はい、可能です。65歳時点で受給の申請をしなかった場合、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することができます。
例えば、67歳時点で繰下げをやめて65歳から通常受給することを選択する場合で考えてみましょう。65歳での受給額が年額180万円(月額15万円)だったとすると、2年分の360万円が一括で支給され、以降は増額なしの月額15万円が生涯支払われることになります。
ただし、過去に遡って年金を一括で受け取ると、その年の所得として扱われるため、所得税や住民税、さらには介護保険料などに影響が出る場合があります。
Q.国民年金と厚生年金、両方とも繰下げ受給できますか?
国民年金と厚生年金は、ともに繰下げ受給できます。増額率は同じで、両方を繰下げ受給すれば、さらに年金額を増やせます。
また、いずれか一方を65歳から受給して、一方のみを繰下げるという対応も可能です。
Q.繰下げ受給で増額した金額はずっと変わりませんか?
一度決まった増額率は、一生涯変わりません。増額された年金を受給し続けることができます。
ただし、公的年金額は物価上昇率や賃金上昇率を加味したうえで、毎年改定されます。そのため、ベースとなる年金額が改定され、受給額が変動する可能性がある点に留意しましょう。
まとめ
年金を70歳から繰下げ受給すると、年金の受給額を増やせるため、老後生活の安心につながるでしょう。国民年金と厚生年金の両方を繰下げれば、より受給額を増やせます。
ただし、すべての方にとって、繰下げ受給はベストな選択になるとは限りません。健康状態や働き方など、老後生活をどのように送りたいのかによって、適切な受給タイミングを選択しましょう。
年金は老後生活を支える収入となるため、安易に判断すべきではありません。65歳になってから慌てないように、早い段階から老後のマネープランを考えることをおすすめします。
≫あなたの老後資金は大丈夫?将来不足する金額を3分で診断
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。