.png?w=1370&h=727&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
20代の貯金、平均と中央値はいくら?手取り額別の貯蓄目標&資産形成術
≫将来いくら必要?あなたの不足額をシミュレーション
「周りの20代はどれくらい貯金しているのだろう?」と気になっている方も多いでしょう。近年の物価上昇や社会保険料の増加などにより、若い世代にとって資産形成は喫緊の課題です。
本記事では、金融広報中央委員会の最新データに基づき、20代の貯蓄額の平均と中央値を詳しく解説します。さらに、手取り額に応じた貯蓄目標のシミュレーションや、NISA・iDeCoといった税制優遇制度を活用した無理のない資産形成術を分かりやすく紹介します。
- 最新データに基づく20代の貯蓄額(平均値・中央値)のリアルな実態
- 手取り月収から逆算した無理のない貯蓄目標の立て方
- NISAやiDeCoを活用し、20代で1000万円を目指す具体的な資産形成術
周りの貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、自分にとっての必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
20代の貯金実態1:平均値と中央値はいくら?
金融広報中央委員会が公表した「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、20代の金融資産保有額の平均値と中央値は、世帯構成によって大きな違いがあることが明らかになっています。
20代の単身世帯の平均貯蓄額は161万円、2人以上世帯の平均貯蓄額は382万円となっています。
平均値は、一部の多額の資産を持つ世帯によって引き上げられる傾向があるため、より多くの世帯の実態に近い数値を示すのが中央値です。中央値とは、データを小さい順に並べたときに、ちょうど真ん中に位置する値のことを指します。
中央値を見ると、単身世帯は15万円、2人以上世帯は84万円であり、貯蓄が進んでいない層が比較的多いことがうかがえます。
20代の貯金ゼロ世帯はどれくらい?
20代の貯金に関する調査で、多くの方が気になるのが、「金融資産を保有していない世帯」、すなわち貯金ゼロ世帯の割合でしょう。同調査によると、20代の金融資産非保有の割合は以下の通りです。
単身世帯では36.6%と、3分の1を超える世帯が金融資産をまったく保有していません。一方、2人以上世帯では22.8%と、単身世帯に比べて貯金ゼロの割合は低くなっています。
これは、結婚や出産といった将来のライフイベントに備える必要性から、夫婦などの2人以上世帯のほうが、計画的に貯蓄を進めている傾向があるためと考えられます。
20代の貯金実態2:貯金額の分布
20代の貯金は、平均値や中央値だけでは実態を把握しにくいほど、貯蓄額に大きな偏りがあります。ここでは、単身世帯と2人以上世帯に分けて、貯金額の分布を詳しく確認し、自分の現在の立ち位置を把握しましょう。
単身世帯
20代の単身世帯における金融資産保有額(金融資産非保有世帯を含む)の分布は以下の通りです。
20代単身世帯では、貯蓄額が100万円未満の世帯が、非保有世帯と合わせて全体の62.9%(36.6% + 26.3%)を占めています。このことから、20代の単身世帯の多くは、手元の貯蓄が少ない状態にあるといえます。
2人以上世帯
次に、20代の2人以上世帯における金融資産保有額の分布を見てみましょう。
2人以上世帯では、貯蓄額が100万円未満の世帯は、非保有世帯と合わせて全体の46.2%(22.8% + 23.4%)となっており、単身世帯(62.9%)よりも割合が低いことが分かります。
特に、100万円以上300万円未満を保有している世帯が16.4%(11.1% + 5.3%)存在しており、単身世帯よりも、ある程度の貯蓄ペースを安定して保っている世帯が多い傾向がうかがえます。
20代は毎月いくら貯金すべき?
平均値や中央値はあくまで参考値です。あなたが結婚や住宅購入などの目標に向けて着実に資産を築いていくためには、手取り額に基づいた明確な貯蓄目標を設定することが重要です。具体的な貯金割合と、世帯環境別の目標額を見ていきましょう。
理想は手取りの10〜20%
一般的に、無理なく継続できる貯金の目安は、手取り月収の10%から20%が理想とされています。
例えば、手取り月収が20万円の場合、毎月2万円(10%)~4万円(20%)を貯金に回す計算です。この割合であれば、日々の生活費を大きく圧迫することなく、貯金を継続しやすいでしょう。
仮に手取り25万円の人が毎月20%(5万円)を貯金できれば、年間で60万円貯まります。25歳から30歳までの5年間継続できれば、300万円の貯金が可能です。
この金額は、将来的なライフイベント(結婚資金や引っ越し費用など)の準備資金として十分役立ちます。まずは現在の支出を見直し、無理のない範囲で手取りの20%を目標に設定してみるとよいでしょう。
実家暮らしなら手取りの40%以上も可能
実家暮らしをしている場合は、家賃や水道光熱費といった固定費の負担が大幅に軽減されます。これは、一人暮らしで必要な家賃相当分(地方であれば6万円、都心であれば10万円程度)をそのまま貯蓄に回せることを意味します。
もし手取り月収25万円で、家賃分の8万円を全額貯蓄に充てられた場合、この時点で月々の貯金額として8万円確保でき、さらに食費や雑費を抑えることで、手取りの40%以上(月10万円以上)を貯金することも夢ではありません。
実家暮らしは期間限定の大きな貯蓄チャンスと捉え、その間に可能な限り高い割合で資産形成を進めるのが賢明な戦略といえます。
≫いくら必要?あなたの将来の不足額をシミュレーション
お金が貯まらない20代の「3大浪費」と対策
自分の貯金額が平均値や中央値よりも低く、困惑している方もいらっしゃるかもしれません。なぜ毎月給料が入ってもお金が残らないのでしょうか。20代がお金が貯まらない原因は、特定の「浪費パターン」に陥っているケースがほとんどです。ここでは、特に注意すべき3つの浪費と対策を解説します。
1.ラテマネーの浪費
ラテマネーとは、毎日何気なく使っている少額の支出の積み重ねのことです。たとえば、毎朝コーヒーショップで買うコーヒー(ラテ)代の数百円や、仕事終わりに立ち寄ったコンピにでのお菓子代などが該当します。
一回あたりの金額は小さくても、積み重なると大きな出費となります。仮に毎日のコーヒー&お菓子代500円を週5回続けた場合、1ヶ月で1万円、年間で12万円の出費です。もしこの12万円を貯金や年率4%で積立投資に回せていたとしたら、数年後にはかなりの差がつくことになります。
対策としては、このラテマネーを完全にやめるのではなく、意識的に回数を減らすことが有効です。例えば、水筒を持参したり、職場で提供されるドリンクを利用したり、週に1回だけ贅沢するといった「節約とご褒美」のメリハリをつける工夫で、ストレスなく出費を抑えられます。
2.見栄消費
見栄消費とは、「他人からどう見られるか」を意識して行う支出のことです。特に20代は、友人や同僚との付き合いの中で、ブランド品や最新のガジェット、高級なレストランでの飲食や派手な旅行などに流されがちです。
見栄消費の厄介な点は、それが自己肯定感を一時的に満たすため、支出が増えていることに気づきにくい点です。他人との比較ではなく、「自分にとって本当に必要なものか」という軸で判断することが重要です。
対策として、高額なモノを購入する際は、衝動買いを避け、1日以上考える期間を設けてください。本当に必要であれば購入し、そうでなければ見送るというルールを徹底しましょう。また、SNSなどで他人の華やかな生活と比較するのを避けることも、見栄消費を防ぐために効果的です。
3.固定費の放置
変動費(食費や娯楽費)ばかりに目を向け、毎月必ず発生する固定費を放置しているのも、貯まらない人の特徴です。固定費は一度見直せば、継続的に節約効果が得られるため、費用対効果が高い対策です。
主な固定費として、以下の項目が見直しの対象となります。
- 通信費(大手キャリアから格安SIMへの乗り換えなど)
- 保険料(必要のない保障の削減や保険内容の見直し)
- サブスクリプション費用(利用頻度の低いサービスの解約)
対策として、年に1回、固定費の見直し日を設けて、契約内容をチェックする習慣をつけましょう。これらを見直すことで、毎月数千円以上もの節約につながり、それをそのまま貯金に回すことができます。
【重要】リボ払い・カードローンにも要注意
浪費対策において、一時的な出費よりもっとも危険なのが、リボ払いやカードローンといった高金利な負債です。これらは手軽に利用できる反面、金利が非常に高く、特にリボ払いは毎月の支払い額が一定のため、利息ばかり支払うことになり元金がなかなか減らず、雪だるま式に利息が増えてしまう危険性があります。
20代のうちに高金利な負債を抱えてしまうと、将来の資産形成のスタートが大幅に遅れてしまいます。
一番の対策は、リボ払いを極力利用しないことです。もし現在利用している負債がある場合は、他の何よりも返済を優先し、早期に完済を目指す必要があります。
負債の金利は、投資の利回りよりもはるかに高いため、まずはマイナスをゼロにすることが最重要課題です。
周りの貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、自分にとっての必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
貯まらない20代が今すぐやるべき「お金の整え方」
浪費を抑え、固定費を削減したら、次は「貯まる仕組み」を構築するフェーズに移ります。意志力に頼るのではなく、自動で、かつ税制優遇を活用しながら資産を増やす仕組み作りを始めましょう。
給料天引きによる「先取り貯蓄」の自動化
貯蓄が成功するかどうかは、個人の意志力ではなく仕組みにかかっています。もっとも効果的な仕組みが、給料が入る前に貯蓄分を強制的に確保する「先取り貯蓄」です。
活用できる制度には、「財形貯蓄制度」や、金融機関が提供する「自動定額振替サービス」があります。
- 財形貯蓄:勤務先が制度を導入していれば、給与から自動的に貯蓄分が天引きされます。
- 自動定額振替サービス:給与振込口座から、毎月決まった日に決まった金額を貯蓄用口座や投資用口座へ自動で振り替えるサービスです。
給料が振り込まれたらすぐに、目標とする貯蓄額(例:手取りの20%など)を別の口座へ移動させることで、残ったお金だけで生活する習慣が自然と身につきます。
NISAで守りながら増やす
貯蓄を確保する仕組みができたら、次は「増やす」段階です。20代は、これから投資できる期間が非常に長く、複利効果を最大限に享受できる最強の世代といえます。この世代に最適なのが、2024年から新しくなったNISAです。
新NISAの最大のメリットは、運用益が非課税になることです。特に20代は、リスクを抑えつつ長期で運用する「つみたて投資枠」を活用することが強く推奨されます。
投資の原則は、「長期・分散・積立」です。毎月一定額を、幅広い銘柄(例えば全世界株式や先進国株などのインデックスファンド)に積み立てることで、短期的な値動きに一喜一憂することなく、リスクを抑えながら堅実に資産を増やせます。
税制優遇制度の活用で「入金力」を強化
単に貯蓄するだけでなく、税制優遇制度を上手に活用することで、実質的な手取りを増やし「入金力」を高めることができます。20代から利用を検討したい主な制度は以下の通りです。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):毎月の掛け金全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。将来の年金対策として優れていますが、原則60歳まで引き出せない点に注意が必要です。
- ふるさと納税:実質2000円の負担で、さまざまな返礼品を受け取りながら、翌年の住民税が控除される仕組みです。
特にiDeCoは、現役世代の税負担を軽減しながら老後資金を準備できる強力な手段です。資産運用と同時に節税による手取り増も狙えるため積極的に利用しましょう。
20代の貯金に関するQ&A
最後に、20代の方が抱きやすい貯金に関する具体的な疑問について、詳しく回答します。
Q. 20代で貯金300万円持っている人の割合は?
20代で金融資産保有額が300万円以上ある世帯は、単身世帯、2人以上世帯ともに少数派です。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」に基づくと、以下の通りです。
- 単身世帯:300万円以上の金融資産を保有している割合は、全体の19.0%です
- 2人以上世帯:300万円以上の金融資産を保有している割合は、全体の29.1%です
単身世帯では約5人に1人、2人以上世帯では約3〜4人に1人が300万円以上を保有しています。20代で300万円以上の貯金を確保できていれば、上位層に入りつつあり、順調に資産形成ができているといえるでしょう。
Q. 20代で1000万円貯めることは可能?
結論からいうと、非常に高いハードルですが、戦略的に行動すれば不可能な数字ではありません。
データ上、20代で1000万円以上の資産を持つ世帯は、単身世帯でわずか3.2%、2人以上世帯でも8.7%と、達成している人はごく一部です。しかし、実家暮らしなどで手取りの40%以上を貯蓄に回せるケースでは、資金をNISAで年率4%程度の運用をすることで、達成の可能性は高まります。
例えば、22歳から月10万円を積立投資し4%の運用ができれば、8年で運用資産額は1126万円に達する計算です。これが5%なら7年で999万円となり、20代での1000万円達成が見えてくる計算です。重要なのは、若いうちから複利の力を利用し、時間を味方につけることです。
試算参考:つみたてシミュレーター|金融庁
Q. 貯金なし(ゼロ)ですが、何から始めればいい?
貯金ゼロの状態から始める場合でも、慌てる必要はまったくありません。まずは、以下の3ステップを順序立てて実行しましょう。
- 支出の把握と固定費の削減:まずは家計簿アプリなどを使い、毎月の支出を詳細に把握してください。次に、通信費や保険料といった固定費の削減を最優先で行います。
- 生活防衛資金の確保:生活費の6ヶ月分程度にあたる金額を、いつでも引き出せる銀行口座に貯めることを目標とします。これは「万が一」のときの予備資金であり、投資に回すお金とは区別します。
先取り貯蓄の自動化:給料が入ったら自動で貯蓄口座に振り替える「先取り貯蓄」の仕組みを構築し、毎月自動で貯まる状態を作ります。
生活防衛資金が貯まった段階で、NISAを活用した資産運用を開始しましょう。このステップを踏むことで、貯蓄が習慣化され、将来の資産形成の土台が築かれます。
まとめ
本記事では、金融広報中央委員会のデータをもとに、20代の貯蓄実態を詳しく解説しました。単身世帯の平均貯蓄額は161万円、中央値は15万円、2人以上世帯の平均は382万円、中央値は84万円であり、貯蓄が進んでいない世帯が半数以上を占めているという現実が明らかになっています。
貯蓄を成功させるカギは、個人の意志力ではなく、「仕組み化」することです。固定費を見直し、浪費を抑えた上で、手取り月収の10〜20%を目標とした先取り貯蓄を実践しましょう。
さらに、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を最大限に活用し、「守りながら増やす」戦略を実行することが、20代で大きな資産を築くための王道です。今日から家計を見直し、将来の目標に向けた第一歩を踏み出しましょう。
≫いくら必要?あなたの将来の不足額をシミュレーション
周りの貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、自分にとっての必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
.png?w=1370&h=727&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
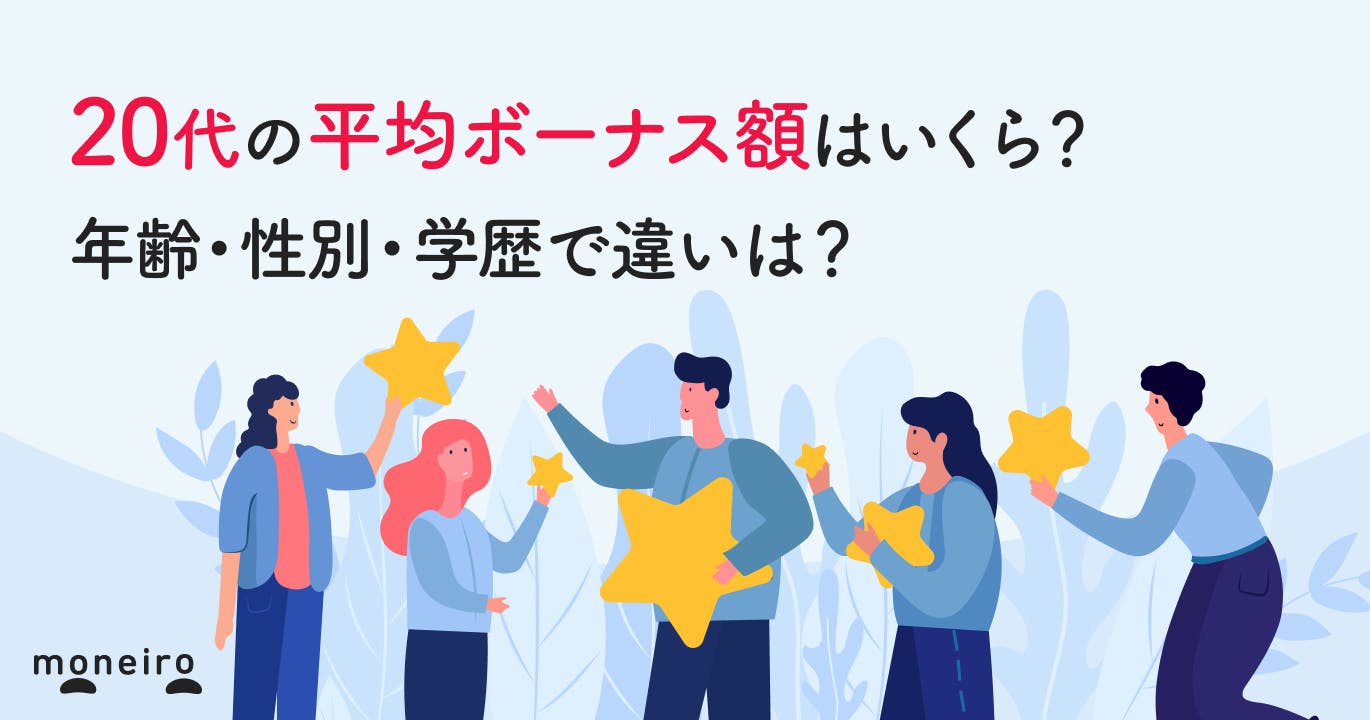
20代のボーナス平均額はいくら?男女・学歴・企業規模別に徹底解説!

金融資産の年代別平均・中央値は?20代〜70代の貯蓄額を世帯構成別に解説
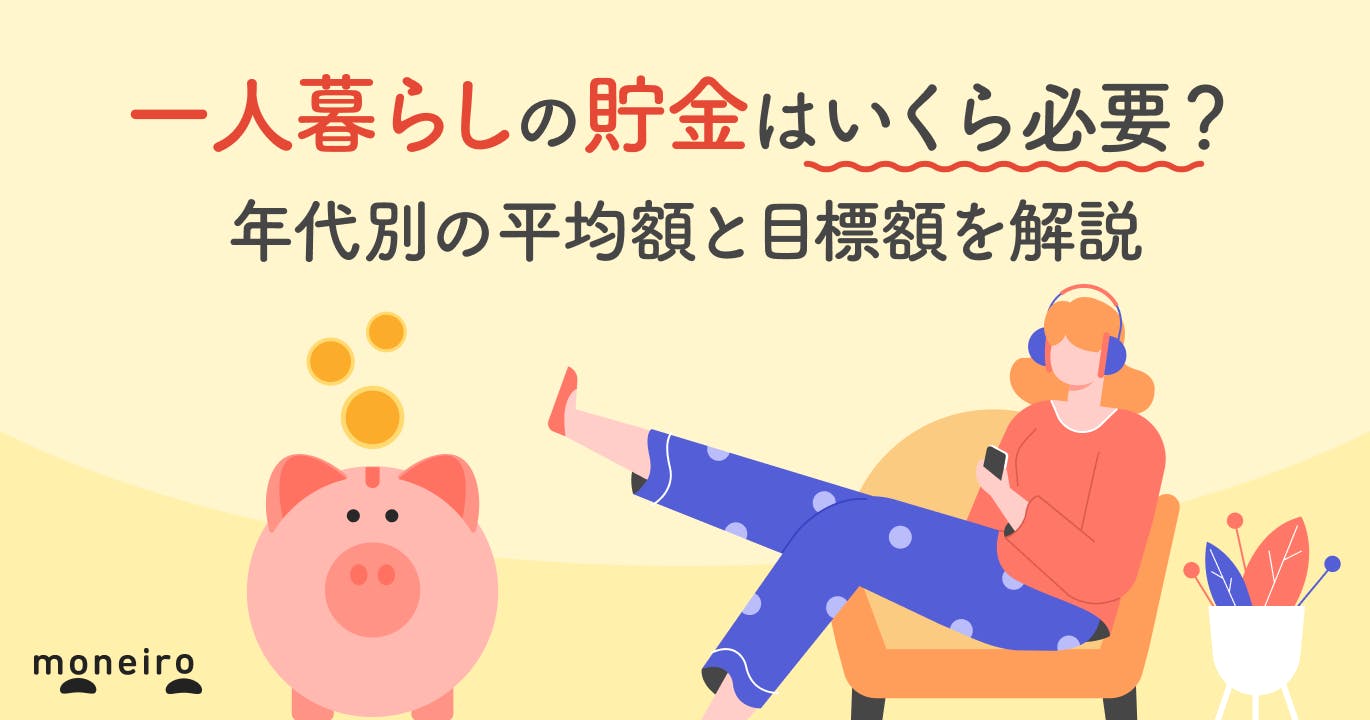
一人暮らしの貯金はいくら必要?年代別の平均額と目標額を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
.jpg?auto=format,compress&fit=max&w=3840)