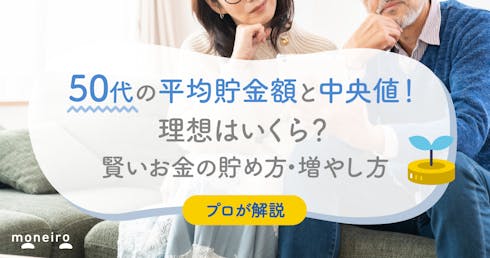
50代から始める老後資金の貯め方とは?目標達成への効率的な方法を解説
【無料】あなたの老後に必要な金額はいくら?3分で診断
50代になると退職が近づき老後資金の貯め方で不安になる方も多いでしょう。
子どもがいる家庭であれば教育費の目途がある程度立ち、住宅ローンを返済中の人であれば完済が近づくなど、ライフプランに変化が現れる年代です。
そこでこの記事では、50代の老後資金の貯め方について、詳しく解説していきます。
- 50代の平均貯蓄額
- これから必要になる老後資金の準備方法
- 資産形成の目標達成が難しいと感じたときの対処法
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
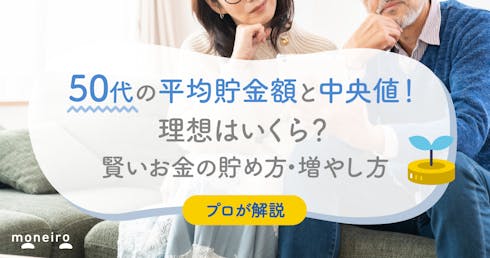
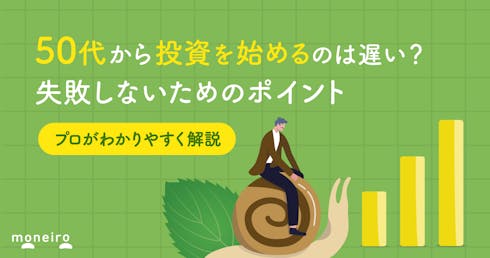
50代の貯蓄額の現実は?平均値と中央値
他の人がどのくらい貯蓄しているかは気になるでしょう。50代の貯蓄額の平均値、または中央値がどの程度なのか見ていきます。
50代の平均貯蓄額と中央値
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、50代の金融資産保有世帯の平均貯蓄額は1677万円です。中央値だと700万円となっています。
平均値はすべての数字を足して、その足した人数で割った数値のことをいい、中央値は上から数字を並べて真ん中にくる数値のことをいいます。
平均値では、極端なデータ(外れ値)も含めて計算するため実態から遠くなってしまうことがあります。一方の中央値は真ん中にくる数字であるため、中央値のほうがより実態に即した数字になります。
年収別・50代の貯蓄額
では、年収別での50代の貯蓄額を平均値と中央値で確認してみましょう。
(参照:「家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯)」)
基本的には年収が増えるほど貯蓄額も多くなる傾向がありますが、収入なし世帯、300万円未満世帯でともに貯蓄ゼロが中央値となっています。また、他の年収帯のデータを見ても、いずれも中央値は平均値の半分以下であり、数値の乖離が大きいことがわかります。
そんな中、「老後2000万円問題」が話題になったり、一部では「4000万円必要」という議論も出てきたりしており、老後資金づくりに不安になっている方も多いでしょう。次の項では具体的な資金計画の立て方について考えていきましょう。
50代から始める老後資金計画の立て方
50代から老後資金を貯めていくにはどのように計画を立てていけばいいのでしょうか。順を追って解説していきます。
1. 現状把握:収入と支出の洗い出し
まずは収支の現状把握をするのがスタート地点です。50代は、役職定年を迎えたり、一度退職して再雇用契約に切り替わったりと収入が変動しやすい年代です。今後の収入がどのように変化するのかを把握しておくとよいでしょう。
また支出についても大きな変化が訪れるのが50代です。子どもがいる家庭では、子どもの就職による経済的な独立も考えられます。そうなった際にどの程度支出を減らせそうかを考えてみましょう。
もしできるなら、将来収支の洗い出しもしておくのが理想です。リタイア後は多くの場合、収入が大きく減少します。年金や継続雇用、副業などでどれくらいの収入が確保できそうか、またどれくらいの支出で生活できそうかを事前に洗い出しておくことをおすすめします。
老後の収支を計算するためにも、将来いくら年金を受け取れるのか把握しておく必要があります。毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」や、オンラインでいつでもチェックできる「ねんきんネット」で事前に確認しておきましょう。
2. 目標設定:必要な老後資金を計算し、目標金額を決める
大まかな収支の目安を把握できたら、次に目標設定をしていきます。
老後の想定収支がプラスであれば当面は大きな問題はありませんが、マイナスの場合は保有資産額を取り崩しながら老後生活を送ることになります。そのマイナスを補填するための資金を老後のために用意する必要があります。
例えば、毎月3万円の赤字が見込まれる場合、65歳でリタイアし90歳まで生きると仮定すると、年間36万円(3万円×12ヶ月)、25年間で900万円(36万円×25年)の老後資金が必要です。
もし現在500万円の資産を保有しているのであれば、老後までに必要な資金は差し引きで「400万円」になります。
老後は生活費の他にも、医療費や介護費、その他子どもの結婚費用・住宅費用のサポートなど、突発的に発生する費用も少なくありません。これらも想定しつつ、余裕を持った目標を立てることが大切です。
3. 期間設定:いつまでに達成するかを決める
目標金額が見えてきたら、その目標金額をいつまでに達成するのかを決めましょう。
例えば、現在50歳の方が65歳までに1,000万円を貯めたい場合、年間約66.7万円(月平均約5.6万円)の貯蓄が必要になります。しかし、仮に70歳まで働けるとすれば、年間50万円(月平均約4.2万円)の貯蓄で達成できます。
このように目標金額と達成したい期日が決まると、今からいくら貯金をしなければいけないのかが分かります。
50代からでも間に合う、老後資金の貯め方
それでは実際にこれから老後資金を貯めようと思った場合に何から取り組めばいいのでしょうか。
その方法について見ていきましょう。
固定費を見直し、毎月の貯蓄を増やす
貯蓄を増やすには、まず貯蓄ができる家計にする必要があります。そのためにも支出の見直しが必要です。まずは固定費を見直し、毎月貯蓄できるお金を増やせるようにしましょう。
見直し例としては通信費(スマホ代)や保険の見直し、人によっては住宅ローンの借り換えなどが選択肢として挙げられます。
固定費は毎月必ずかかるお金で、一度見直せば節約の意識がなくても支出を減らすことができます。見直しには多少の手間がかかることが多いですが、支出削減効果は大きいといえます。
変動費も見直せるならそれに越したことはありませんが、固定費より支出削減効果が低めで、節約に精神的ストレスを伴う場合もあるため、まずは固定費から考えるのがおすすめです。
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
資産運用で資金を増やす
支出の見直しができ、貯金ができるようになったら、そのうちの一定額を資産運用に回すのもよい手段です。資産運用をする上で大切なのはお金の置き場所(どこで運用するか)です。資産運用に有利な制度がありますので、上手に活用しましょう。
NISA(少額投資非課税制度)の活用
投資を行う際、通常は運用で得た利益に対し20.315%の税金がかかります。NISAは、専用の口座を利用することで、投資の運用益にかかる税金が非課税になる制度です。
投資枠は、金融庁が設ける基準をクリアした投資信託に投資できる「つみたて投資枠(年間120万円が上限)」と、上場株式や投資信託などに投資できる「成長投資枠(年間240万円が上限)」があり、非課税保有限度額は合計で1800万円となっています。
NISAを上手に活用することで、資産運用による利益を最大化させることができます。特に長期目線での資産づくりに向いている制度といえます。
投資にはリスクが伴います。元本保証はなく、特に短期的には損をする可能性がある点には十分に留意しておく必要があります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
NISAと一緒に活用を検討したいのが、私的年金制度の1つであるiDeCoです。iDeCoはNISAと同様に資産運用の運用益にかかる税金が非課税になります。
NISAと異なる点は、掛金を拠出した際や、受け取る際にも恩恵がある点です。拠出した掛金は全額所得控除にでき、節税の面で大きなメリットがあります。また、受け取るときには一時金で受け取る場合には退職所得控除、年金で受け取る場合には雑所得の公的年金控除を受けられます。
デメリットとして、原則60歳まで引き出せない点が挙げられます。NISAはいつでも引き出しが可能ですが、iDeCoはできないため、突発的に現金が必要になった時などに対応できない点には留意が必要です。
iDeCoでは、国民年金の被保険者区分によって掛金の上限額が異なります。また第2号被保険者の場合には勤務先の企業年金の有無などによっても上限額が変わります。自分の上限額がわからない場合は勤務先に確認してみるとよいでしょう。
個人年金保険を検討する
老後資金を準備する方法として、NISAやiDeCo以外に個人年金保険があります。個人年金保険のメリットは、支払った保険料が生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税の所得控除を受けられる点です。
保険料は保険会社が運用し、契約時に定めた年齢から、年金または一時金として受け取ることができます。受け取り方法や期間は契約時に選択可能です。
節税メリットのある制度ですが、NISAやiDeCoと比較すると税制優遇は限定的です。そのため、NISAやiDeCoを優先的に活用し、余力がある場合に個人年金保険を検討する、というくらいの考えでよいでしょう。
目標達成が難しいと感じたときの対処法
さまざまな手段を検討しても目標達成が難しい場合もあるでしょう。そんな場合に検討したい対処法について解説します。
老後の支出計画を見直す
どうしても目標達成が難しいと感じる場合、まずは老後の支出計画の見直しをしましょう。支出見直しの大きなポイントになるのが、住居費と日々の生活費です。
例えば住宅費であれば住み替えで支出を減らすことが可能です。子どもがいる家庭であれば、子どもの独立を機に、少し狭い家に住み替えをしたり、郊外に引っ越したりすることで住居費を抑えられる可能性があります。
もちろん、子どものいない世帯でも生活費の見直しはできます。例えば、老後は外食を減らすことを考える、お金のかからない趣味を見つけるなど、見直せそうなポイントを探してみましょう。
長く働くことを視野に入れる
支出の見直しが難しい場合には老後の収入を増やす方法を考える必要があります。今働いている職場で再雇用もしくは業務委託で働き続けることができるかどうか確認してみましょう。
もし難しい場合でも、今までの経験や保有している資格などを活かしてできる仕事がないか、50代のうちから探しておくのもよいでしょう。最近では副業ができる職場も増えてきています。今から副業を行い、退職した際には副業を本業にするといったこともできるでしょう。
お金の専門家に相談してみる
もし自分一人で支出の見直しや収入の改善、資産運用の方法で不安を感じる場合には、お金の専門家に相談してみるのもよいでしょう。
客観的に家計の状況を見てもらうことで自分では分からなかった支出の見直し改善ポイントや、収入の改善方法が見つかるかもしれません。
またどうやって資産運用をすればよいのか、どの制度を活用すべきなのかなど、相談者の考えや価値観を聞いた上で最適なアドバイスをもらえるでしょう。
50代の老後資金準備に関するQ&A
50代の老後資金準備でよくある質問とその回答を見ていきましょう。
50代からでも老後資金準備は間に合いますか?
50代でも老後資金準備は間に合います。ただし、老後までの時間が限られているため、計画と対策が重要になってきます。
まずは現在の資産状況、将来受け取れる見込みの年金額や支出を把握しましょう。その上で、どの程度老後の資金が必要になるのかを考える必要があります。50代はそれまで負担になっていた住宅ローンの支払いの完済目途が見えてきたり、子どもの教育費の目途が立ってきたりとライフプランに変化が現れる年代でもあります。
今まで支出の多くを占めていた部分がなくなることで貯蓄ができるようになるタイミングでもあります。支出の見直しと資産運用をうまく組み合わせることで老後資金の準備をしていきましょう。
投資初心者でもNISAやiDeCoは始められますか?
NISAやiDeCoは、投資初心者でも始めやすい制度です。投資信託であれば、証券会社によっては最低100円から投資できるので、少ない資金であっても投資を始めることができます。
投資にはリスクが伴いますが、NISAやiDeCoには税制上のメリットがあり、特に長期目線で運用を行う場合には恩恵を受けやすいといえます。
もし、最適な投資金額や投資先に迷った場合には、お金の専門家に相談してみるのも1つの手です。
年金だけで生活するのは難しいですか?
年金だけで生活できるのが理想ではありますが、現実には難しいケースも少なくありません。
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金保険の男性の平均受給額は16万6606円、女性で10万7200円となっており、夫婦での平均の受給額は27万円強ということになります。
ただし、自営業・フリーランスで国民年金のみに加入していた場合や、配偶者が専業主婦(主夫)であった場合などでは、これよりも年金額が大きく下がることもあり、十分とはいえない世帯も多いでしょう。
また、物価の上昇や老化に伴う医療費の増加など、もともと想定していなかった支出の増加も考えられます。さらに年金の支給開始年齢の引き上げや支給額の調整といった制度改正がなされる可能性もゼロではないため、こうしたリスクも頭に入れながら、余裕を持った資産形成を心がけましょう。
まとめ
50代までは子どもの教育費や住宅ローンの返済といった支出を考える必要がありますが、50代になると自身の老後資金についても本格的に考えていく必要があります。
一時期、「老後2000万円問題」が話題になりましたが、実際にどのくらい老後資金が必要になるかは人によって異なります。まず重要なのは、老後の収支を想定し、現在の資産額も考慮しながら、どれくらいの老後資金を用意する必要があるのかを把握することです。
目標が決まれば、そこへ向かうための道筋を考えることができます。固定費の見直しで支出を減らし、貯金や資産運用に回す金額を今から増やしていくことで、不安の少ない老後に向けた将来資金づくりを進めていくことができるでしょう。
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください




