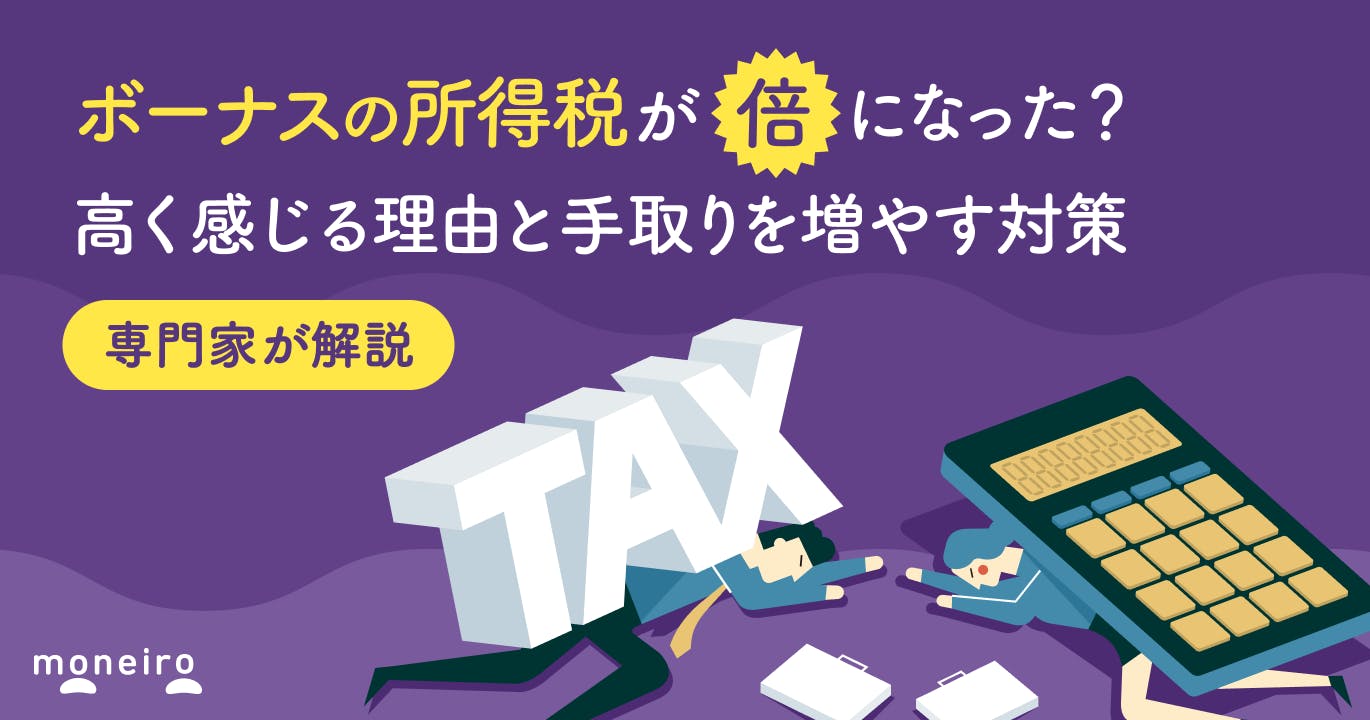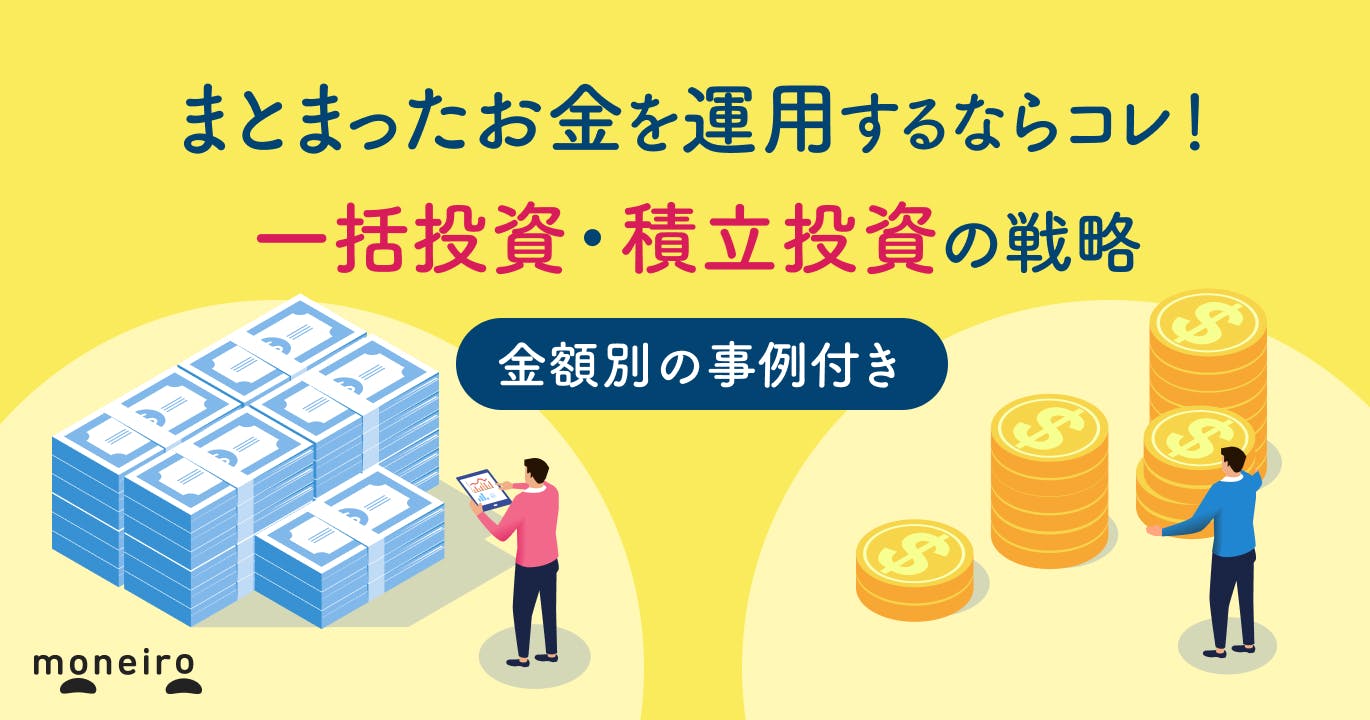世帯年収1000万円で共働きが「損」と感じるのはなぜ?知っておきたい対策を徹底解説
現在の貯蓄で老後は足りる?3分無料診断
「共働きで世帯年収1000万円なのに、思ったよりお金が残らない…」と感じたことはありませんか。
実はこの収入帯は、各種支援制度の所得制限に該当する年収ラインといわれています。また、税負担や保育料の増加など、可処分所得が目減りする要因も多く存在します。
本記事では、共働きで世帯年収1000万円の家庭がなぜ損と感じやすいのか、その背景を制度・税制・家計の視点からお金のプロがわかりやすく解説します。
- 共働きで世帯年収1000万円の実収入は約864万円(2024年家計調査報告より)
- 世帯年収1000万円で共働きが損と感じる理由は「一部の子育て支援に所得制限がある」「税金や社会保険料負担が重い」など
- 世帯年収1000万円の共働き世帯が損しないために行える対策は「生命保険や医療保険などの所得控除」「住宅ローン控除」など
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ

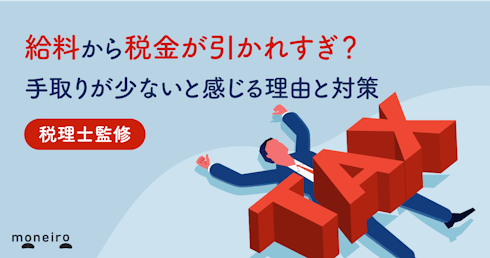
世帯年収1000万円は珍しい?手取りはいくらくらい?
世帯年収1000万円と聞くと、多くの人が「裕福な家庭」というイメージを持つかもしれません。しかし、現在の日本では共働き世帯が増え、決して珍しい年収帯ではなくなっています。
共働き世帯の実収入
総務省の「家計調査報告|家計収支編2024年(令和6年)平均結果の概要|妻の就業状態,世帯類型別」によると、共働き世帯の実収入は1ヶ月平均72万167円、年間で864万2004円になります。
世帯年収1000万円のリアルな手取り
世帯年収1000万円の手取りは、夫婦の収入配分、扶養家族の有無、住んでいる地域などによって大きく変動します。
一般的に、手取りは額面年収の70〜80%程度と言われますが、世帯年収1000万円の場合は税金や社会保険料の負担が重くなるため、手取り年収は概算で約750万円から800万円程度になることが多いです。
1人で1000万円稼ぐ vs 共働きで稼ぐ?
世帯年収1000万円を「1人で稼ぐか」、それとも「夫婦2人で稼ぐか」は、税金や社会保険料の負担によって大きく異なります。
1人で1000万円稼ぐ場合、所得税や住民税は累進課税制度のため、所得が増えるほど税率が高くなります。1人で1000万円を稼ぐと、高い税率区分に単独で到達するため、税負担が重くなります。
一方、2人で合わせて1000万円稼ぐ場合、夫婦それぞれが所得を得るため、所得が分散されます。税率の低い区分が適用される部分が増え、世帯全体での税負担が軽減されるケースが多いです。
よって、夫婦で分散して稼ぐ方が、世帯全体の手取りが最終的に多くなります。
世帯年収1000万円共働きが「損」と感じる理由
世帯年収1000万円の共働き家庭は、一見すると経済的に恵まれているように見えます。しかし、税金や社会保障制度の仕組みなどの視点で、「損をしている」と感じてしまうかもしれません。
一部の子育て支援に所得制限がある
一部の制度では所得制限が設けられています。世帯年収1000万円の共働き家庭はこれらの所得制限に該当し、支援を受けられない、あるいは受けられる額が少なくなることがあります。
手当がない分を自己負担する必要があり、「損をしている」と感じる一因となります。
保育料が高い
2歳児クラス以下の認可保育園の保育料は、世帯の住民税額(所得)に基づいて決定されます。世帯年収1000万円の共働き家庭は、夫婦ともに一定の収入があるため、保育料が最も高い区分に該当することが多くなります。
保育園を利用する限りは、毎月の保育料が高額になり、家計を圧迫すると感じることがあります。
税金や社会保険料の負担が重い
夫婦それぞれが所得を得ているため、世帯全体で見ると高収入となりますが、税金や社会保険料の負担が重くなることがあります。
夫婦それぞれが会社員の場合、各々が健康保険料と厚生年金保険料を負担します。
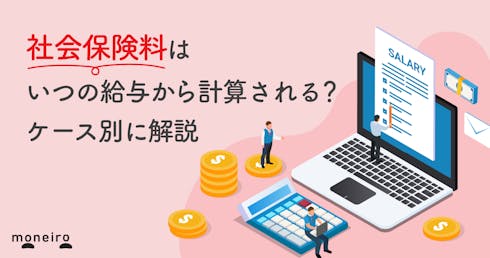
家計を圧迫するその他の支出(保育料・外注費など)
高収入共働き家庭が「損」と感じる背景には、高収入ゆえに見過ごされがちな支出の増加もあります。
例えば、多忙な共働きゆえに、家事の外部委託や外食、中食(宅食など)が増え、生活費全体が上がりやすい傾向があります。
また、子どもの習い事や塾、私立学校の選択など、教育への投資額が増えることがあります。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
世帯年収1000万円の共働き世帯ができる賢い税金対策
世帯年収1000万円の共働き家庭は、適切な税金対策を行うことで、手取り収入を最大化し、家計の負担を軽減できます。
生命保険や医療保険などの所得控除
生命保険料控除や医療保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
夫婦それぞれで加入している場合、各々で控除を適用できるため、世帯全体での節税効果が高まります。
住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末時点のローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる場合(ペアローンなど)、各々で控除を適用できるため、大きな節税効果が期待できます。
医療費控除
1年間にかかった医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合、医療費控除を適用できます。
夫婦合算して申告できるため、どちらか一方の所得が高い方で申告することで、世帯全体での節税効果が高まります。
NISAやiDeCoの活用
NISAやiDeCoは、投資で得た運用益が非課税になる制度です。夫婦それぞれが口座を開設できるため、世帯として非課税投資枠を最大化し、効率的な資産形成を目指せます。
特に、iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となり、老後資金を準備しながら節税できるメリットがあります。

ふるさと納税の活用
世帯年収1000万円の共働き世帯にとって、ふるさと納税は賢く活用することで家計に大きなメリットをもたらす制度です。
税制上の優遇措置を最大限に活用し、実質的な支出を抑えながら、魅力的な品々を手に入れることが可能になります。
共働きで子どもがいない(もしくは中学生以下)の場合、17万6000円分のふるさと納税が可能です。
還元率70%の返礼品を選んだ場合、12万3200円相当の返礼品を受け取ることができ、自己負担2000円を差し引いても12万円以上の実質的なメリットが得られます。
.jpg?w=490&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
世帯年収1000万円の共働き世帯が「損」をしないためのポイント
世帯年収1000万円の共働き家庭が「損をしている」と感じる部分を解消し、効率的に資産を増やしていくためには、以下のポイントを意識しましょう。
①国の制度を活用する
NISA、iDeCoなど、活用できる国の制度を活用しましょう。これにより、所得税や住民税の負担を軽減できます。
②家計全体の支出を見直す
固定費(住宅ローン、保険料など)を中心に無駄な支出がないかを確認し、見直すことが大切です。
共働きゆえに増えがちな家事代行費や外食費なども、費用対効果を冷静に評価しましょう。
③資産運用を行う
銀行預金だけではインフレに負けてしまうため、NISAやiDeCoなどを活用し、インフレ対策も兼ねて資産運用を積極的に行いましょう。
手元に残ったお金を効率的に増やすことで、将来資金の準備につながります。
④お金のプロに相談する
最適な資産運用戦略については、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)やFP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家の相談サービスを活用しましょう。
自分たちに合ったアドバイスをもらうことが、損をしないための近道です。
世帯年収1000万円の共働き世帯のよくある質問
世帯年収1000万円の共働き世帯のよくある質問について、マネイロのIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が回答します。
Q.世帯年収1000万円の理想的な月々の貯金額は?
理想的な貯蓄額は、家庭のライフプラン(子どもの有無、住宅ローン、教育費、老後資金目標など)によって大きく異なります。
一般的には、手取り収入の20%〜30%程度を貯蓄に回せると理想的と言われます。
Q.家計のやりくりのコツは?
家計が苦しいと感じるときは、税金や社会保険料の負担、固定費・変動費の高さが原因となっていることがあります。
まずは家計全体を「見える化」し、特に固定費の見直しから始めるのが効果的です。
自分だけで判断が難しい場合は、専門家に相談するのも有効な選択肢です。
Q.ボーナスの効果的な使い方は?
ボーナスは、日常の家計とは別に、まとまったお金を有効活用できる貴重なチャンスです。
まずは生活防衛資金が不足している場合、最優先で確保しましょう。住宅ローンがある場合は、繰り上げ返済によって利息負担を減らすのも一案です。
余裕資金があれば、NISAなどを活用した資産運用も検討しましょう。また、自己投資や家族との時間など、「無形資産」への投資も長期的に価値ある使い方です。
まとめ
世帯年収1000万円の共働き家庭が「損をしている」と感じる主な理由は、子育て支援の所得制限、高額な保育料の負担が増えることにあります。
しかし、これは制度の仕組みによるものであり、決して「損」ばかりではありません。
夫婦それぞれが収入を得ることで、所得税の税率を分散できるメリットもあります。重要なのは、利用できる節税制度を最大限に活用し、家計の見直しなど、現状を把握して対策を行うことです。
専門家のアドバイスも活用しながら、世帯年収1000万円という収入を最大限に活かし、豊かな家庭生活を実現しましょう。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください