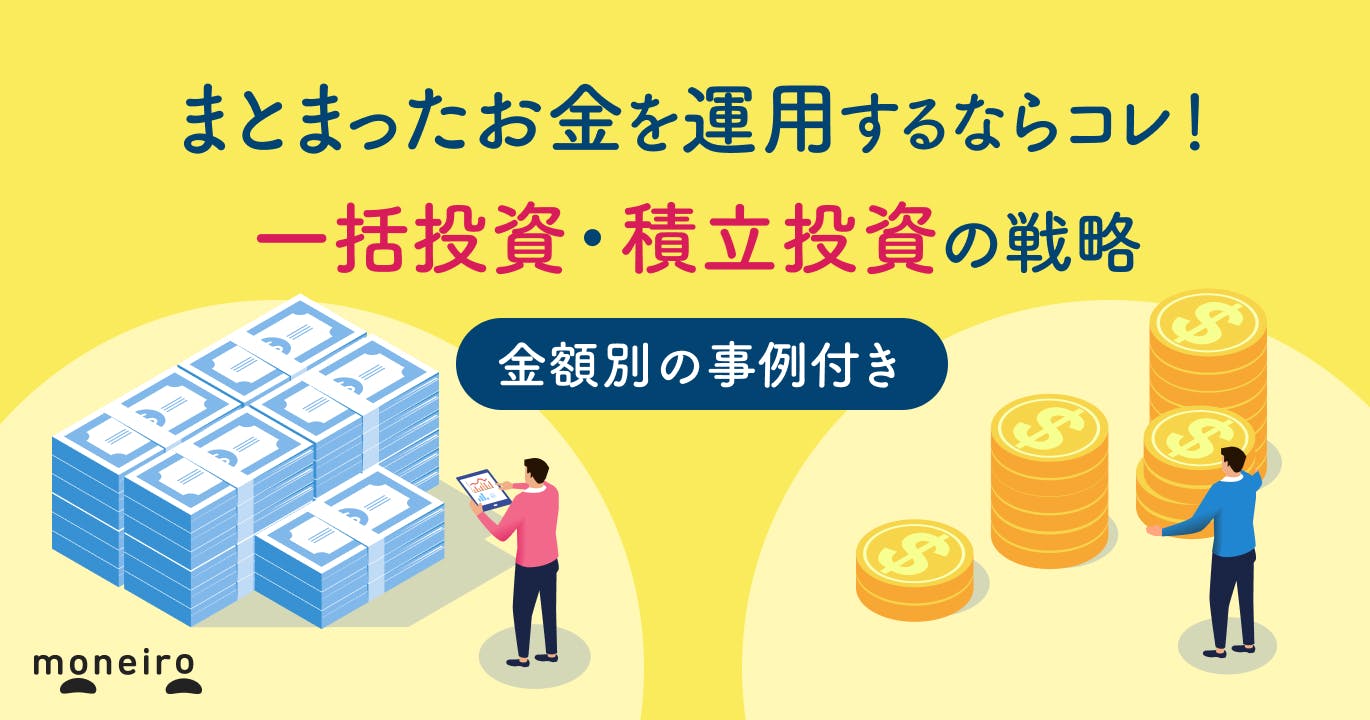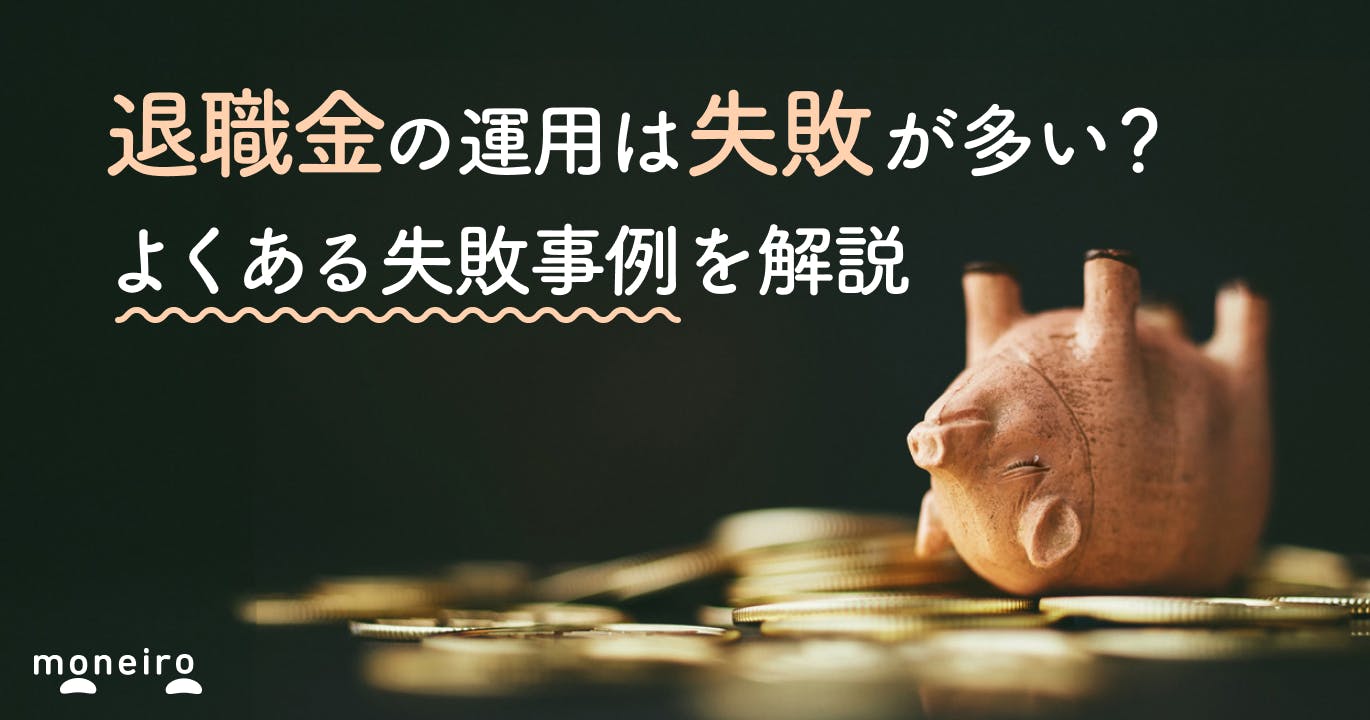65歳からの資産運用は老後の資産を守りながら増やす!プロが賢い運用戦略を徹底解説
»60代のベストな資産運用は?簡単診断はこちら
「65歳から資産運用を始めても問題ない?」「定年後の資産運用のポイントは?」と60代で資産運用を検討している人や運用について悩んでいる人もいるでしょう。
65歳からの資産運用では資産を守りながら増やすことがポイントとなります。また、手元にあるお金をきちんと使用用途ごとに色分けをして、余裕資金で資産運用を行うようにしましょう。
本記事では「65歳から資産運用を行いたい人」「60代の資産運用で気をつけることを知りたい人」に向けて、定年後の資産運用のポイントについて、事例を参考に投資のプロが徹底解説します。
- 65歳からの資産運用では資産を守りながら運用することが大切
- ポートフォリオを組む際は安定性を重視した運用になるように、債券や貯蓄型の保険商品などのリスクが比較的低い資産の割合を増やす
まとまったお金の運用方法が気になるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶500万円から始める債券投資セミナー:まとまったお金の運用方法がわかる
▶オンライン無料相談:専門家にスマホで直接相談
そもそも65歳から資産運用を始めても良い?
65歳から資産運用を始めることは、決して遅すぎるということはありません。平均寿命が延び、いわゆる「人生100年時代」といわれる今、老後の生活資金を長持ちさせるための運用は重要な選択肢のひとつです。
たとえ十分な貯蓄があっても、使い方によっては早い段階で資金が尽きてしまう可能性があります。老後資金の「寿命」を延ばすためには、計画的な資産運用が欠かせません。
また、近年は日本でも物価上昇が続いており、インフレ対策としての資産運用も求められています。現金をただ保有するのではなく、インフレに負けない運用を検討することが大切です。
ただし、リタイア後は収入が限られるため、若い世代とは異なり、リスクを抑えた安定的な運用が基本となります。元本割れリスクの少ない商品や分散投資を活用し、慎重な運用方針を心がけましょう。
老後のお金を3つに色分けをする
資産運用を始める前に、老後の資金を目的別に「3つの色」に分けて整理しましょう。これは、必要な時期や用途に応じて資金を分類し、無理のない運用を行うために必要なステップです。
① 生活防衛資金(すぐに使うお金)
まず確保すべきは、当面の生活費としての「生活防衛資金」です。病気や怪我、予期せぬ支出が発生した場合に備えて、現金で確保しておきましょう。
再雇用などで収入がある場合は、生活費の6ヶ月分を目安とすると良いでしょう。
年金のみが収入の方や自営業・フリーランスの場合は、傷病手当などの公的保障がないため、生活費の1年分以上を確保しておくと安心です。
② 近い将来に使う予定資金(5年以内のお金)
次に、5年以内に使う予定のある資金を整理します。具体的には以下のような支出が該当します。
- 自宅のリフォームや住み替えなどの住居費
- 旅行などのレジャー費
- 子どもや孫への贈与
- 冠婚葬祭にかかる費用
など
この資金は、元本割れのリスクが低い安全性の高い運用先に置いておくのが適切です。
③ 余裕資金(長期運用が可能なお金)
上記①と②を差し引いて残るお金が「余裕資金」です。この資金は生活に直接影響を及ぼさないため、比較的リスクを取った運用にも活用できます。
インフレ対策や資金寿命の延伸を目的に、長期運用を前提とした資産形成に役立てましょう。
使い道が決まっていないお金を運用する
当面、使い道が決まっていない余裕資金で資産運用をしましょう。
資産運用は、リスクが低いものや安定的な運用でも多少の価格変動はつきものです。そのため、余裕資金で運用することで、多少の変動に臆することなく目的に向かって運用が続けられます。
65歳からの資産運用は資産を守りながら増やす
65歳以降の資産運用では、高いリターンを追い求めるよりも、「資産を守りながら着実に増やす」ことが大切です。
ここでいう「資産を守る」とは、単に元本を維持することだけでなく、資産の「実質的な価値」を減らさないことを意味します。
特に、現在のようにインフレが続く局面では、現金の購買力が目減りするため、資産価値の維持が難しくなります。
このような状況に対応するには、インフレ率と同程度、あるいはそれを上回る利回りを目標にした運用が求められます。
リスクを抑えながらも、物価上昇に負けない運用手段を選ぶことが、老後の資産を長持ちさせる鍵となります。
まとまったお金の運用方法が気になるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶500万円から始める債券投資セミナー:まとまったお金の運用方法がわかる
▶オンライン無料相談:専門家にスマホで直接相談
65歳からの資産運用におすすめの方法
65歳から始める資産運用においておすすめの方法について、リスクを抑えながらも、資産を守りつつ増やしていく方法を中心に解説します。
おすすめ①NISAで積立投資
NISA(少額投資非課税制度)を活用した積立投資は、老後の資産運用にも有効な手段です。
NISAでは、投資によって得られた売却益や配当金が非課税になるため、税負担を抑えながら効率的な運用が可能です。さらに、積立投資を活用すれば「ドル・コスト平均法」により、高値掴みのリスクを軽減することができます。
ただし、リタイア後の資産運用では、若い世代と比べて投資期間が限られ、リスク許容度も低くなりがちです。そのため、資産の全体のバランスを見つつ、投資先を選ぶようにしましょう。
Q.iDeCoは65歳からでも活用できる?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、原則として65歳未満の国民年金被保険者が加入できる制度であり、掛金の拠出も65歳までが上限です。
そのため、65歳から新たに加入することはできませんが、それまでに積み立てた資産は最大75歳まで運用を継続することが可能です。
受け取り時期を後ろ倒しにすることで、より長く複利の効果を活かすことができ、運用益を増やす可能性があります。
(参考:iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等|iDeCoってなに?|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】】)
おすすめ②退職金の一部を債券に一括投資
退職金の運用先として、債券への一括投資は選択肢の一つです。債券は、株式と比較して価格の変動が小さく、安定性の高い低リスク資産とされています。
債券の魅力は、定期的に利子が得られる点と、満期時には原則として額面金額が返還される点です。計画的に資金を管理したいシニア世代にとって、非常に扱いやすい資産といえます。
また、国内債券だけでなく、米国など金利水準の高い国の外国債券に目を向けることで、インフレ率を上回るリターンが期待できる点も魅力です。ただし、為替リスクには注意が必要です。
65歳以降のポートフォリオの考え方と事例
65歳以降でポートフォリオを組む際のポイントと資産運用事例について詳しく見ていきましょう。
ポートフォリオを組む時の考え方
65歳以降にポートフォリオを組む際は、まず「生活防衛資金」や「近い将来に使う予定資金」を除いた余裕資金を対象に運用を行うことが基本です。
この世代では、収入源が限られるため、若い世代よりもリスク許容度が低くなる傾向にあります。したがって、資産の大部分をリスクの低い資産に配分し、安定性を重視した運用を心がけることがポイントです。
リスクの低い資産の例:
- 債券
- 貯蓄型の保険商品
など
一部取り入れるリスク資産の例:
- 株式型投資信託
- バランス型投資信託(株式+債券などを組み合わせた商品)
など
これらを自身のリスク許容度や目標利回りに応じて配分し、分散投資を意識してポートフォリオを組みましょう。
また、マーケット環境や生活状況は時間とともに変化します。年に1〜2回程度の定期的な見直しを行い、必要に応じて資産配分を調整しましょう。
ポートフォリオ例①
社債を中心に運用することで、定期的な利子収入の確保を重視。
複数の社債に分散投資することで、信用リスク(発行体の倒産等)を軽減。また、異なる満期や利払いスケジュールの商品を組み合わせることで、利子の受取時期を分散し、キャッシュフローの安定化を図っている。
ポートフォリオ例②
(1) 一時払い保険は20年間の固定金利で、将来(80代)に向けた資産形成に活用。死亡時には保険金として相続対策にもなる。
(2)米ドル建て社債は、安定的な利息収入を得る目的で選択
(3)残りの資産(約2000万円)の一部は、インフレや長寿リスクに備えてリスク資産に分散。積立投資にすることで、購入時期を分散(ドル・コスト平均法)しながら長期的な資産成長を目指している。
65歳からの資産運用で避けるべきリスクと注意点
65歳以降の資産運用では、「増やすこと」以上に「守ること」が大切です。リスクを避けながら安定的に資産を維持していくための注意点を見ていきましょう。
商品選びは慎重に行う
60代の資産運用では、リスクを最小限に抑えながら、資産の寿命を延ばすことが目的になります。そのため、自身のリスク許容度を見極めたうえで、投資商品を慎重に選ぶことが大切です。
退職直後には、金融機関から「退職金キャンペーン」などの案内が届くことがありますが、条件や内容をしっかり確認し、自分の老後のライフプランに合っているかを冷静に判断しましょう。
生活資金を投資に回しすぎない
老後は収入が限られる一方で、医療費や介護費といった予測できない支出が増えるリスクもあります。そのため、日常生活に必要な資金は現金や預貯金で安全に確保しておくことが基本です。
投資に回すのは、あくまで余裕資金の範囲に留めましょう。生活費や近い将来に使う予定の資金まで投資に充ててしまうと、市場の暴落などによって大切な資金を失う恐れがあります。
詐欺商品・高利回り案件に注意
「元本保証」「必ず儲かる」などと謳う投資商品は、詐欺の可能性が高いため注意が必要です。65歳以上の世代はまとまった資金を保有していることから、詐欺のターゲットになりやすい傾向があります。
また、異常に高い利回りの商品には、リスクが非常に高いか、仕組みが不透明なものも含まれています。金融庁の登録がない事業者や、内容が理解できない商品には手を出さないようにしましょう。
資産運用は、信頼できる金融機関や専門家に相談しながら、納得できる範囲で進めることが大切です。
相続税対策も視野に入れる
家族や相続人がいる場合、資産をどのように引き継ぐかという視点も大切になります。相続が発生すると、遺産分割協議や各種手続きに時間がかかるほか、相続税が発生する可能性もあります。
あらかじめ渡す相手が決まっている場合や、相続をスムーズに進めたいと考えている場合は、生命保険の活用を検討してみましょう。
保険金は、受取人を指定しておけば直接渡すことができ、相続時のトラブル回避にもつながります。
また、生命保険には「500万円×法定相続人」の非課税枠があるため、相続税対策としても有効です。
(参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁)
65歳から始める資産運用で悩んだ時の相談先
資産運用に迷った時は、一人で抱え込まずに専門家に相談することが大切です。
代表的な相談先を見ていきましょう。
証券会社・銀行の無料相談を活用する
店舗型の証券会社や銀行では、窓口で資産運用に関する無料相談を受けられる場合があります。予約が必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
証券会社は、NISA・株式・債券・投資信託などの取り扱いが幅広く、投資に特化したアドバイスが受けられます。
銀行はお金全般の相談ができる反面、扱っている投資商品は主に投資信託や国債に限られる傾向があります。
対面で相談したい場合には便利ですが、金融機関によっては担当者が固定されないこともあるため、その点も確認しておくと安心です。
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談する
IFAは、銀行や証券会社など特定の金融機関に属さない独立系のアドバイザーです。中立的な立場からアドバイスを受けられるのが特徴です。
IFAは、さまざまな金融機関の商品を比較したうえで、相談者に合った資産運用の提案が可能です。特定の商品を売ることを目的としないため、利益ではなく顧客目線での提案が期待できる点も魅力です。
資産運用の全体設計や、ライフプラン・相続まで含めた総合的な相談をしたい人におすすめです。
資産運用に悩んだ時はマネイロに相談がおすすめ
「マネイロ」は、SBI証券と提携するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)サービスです。銀行や証券会社出身のアドバイザーが在籍しており、資産運用・保険・相続まで幅広く対応可能です。
- 相談は主にオンラインで完結、全国どこからでもアクセス可能
- 何度でも無料で相談可能
- SBI証券の口座を活用した投資アドバイスや、複数の保険商品にも対応
老後資金の運用に不安がある方は、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。
マネイロの無料相談予約はこちら▼
まとめ
65歳からの資産運用は老後資金を長持ちさせるため、そしてインフレから資産を守るためにも必要だといえます。
まずは、手元のお金を「生活資金」「予定資金」「余裕資金」の3つに分け、余裕資金を中心に運用を検討しましょう。
運用対象としては、債券など比較的リスクの低い資産を中心にポートフォリオを組み、定期的に見直すことがポイントです。
失敗が許されない老後資金だからこそ、自分ひとりで判断せず、IFAなど中立的な立場の専門家に相談しながら、安心できる資産運用を目指しましょう。
»自分に合う資産運用がわかる!無料診断はこちら
まとまったお金の運用方法が気になるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶500万円から始める債券投資セミナー:まとまったお金の運用方法がわかる
▶オンライン無料相談:専門家にスマホで直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください