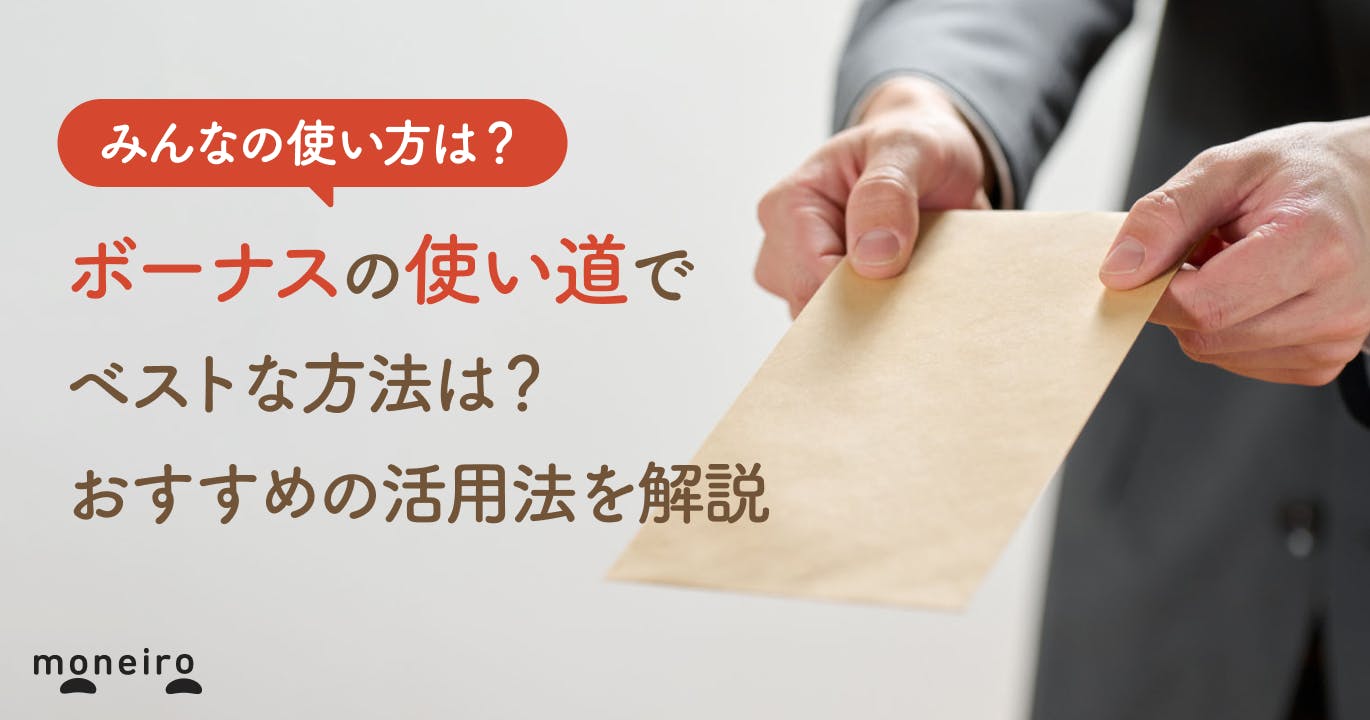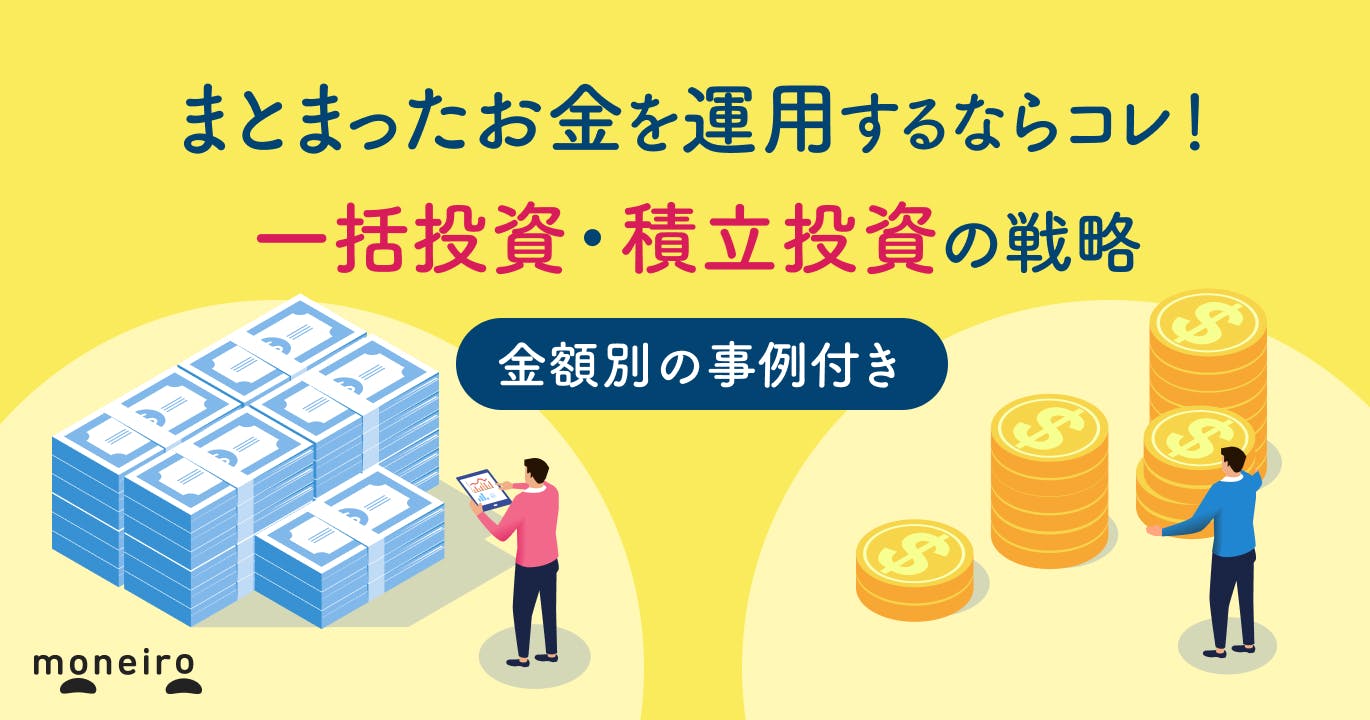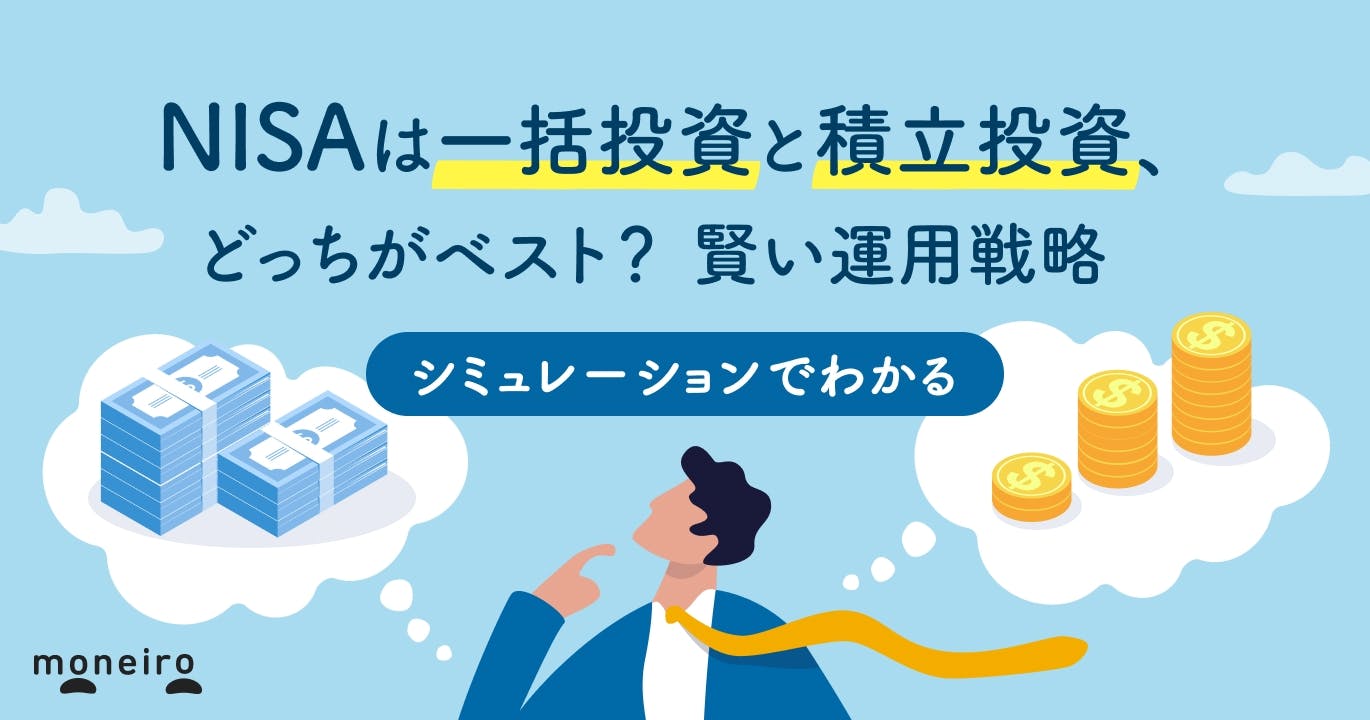ボーナスで投資をするなら何がベスト?ケース別の賢い使い方と運用のポイントを徹底解説
»ボーナスの使い道、3分で“最適な投資先”を診断
ボーナスはまとまった資金を投資に回せるチャンスです。しかし「貯金だけでは不安」「どこに投資するべきか」と悩む人も多いでしょう。
本記事では、ボーナスの使い道の優先順位や投資の基本を整理しつつ、NISAを活用したボーナス投資のメリットを解説します。
さらに、一括投資と積立の違いやリスク管理の工夫、初心者でも取り組みやすい商品選びのポイントも併せて投資の専門家が解説していきます。
- ボーナスを使う前におさえておきたい投資の考え方
- 投資先を決める時のポイント
- NISAを活用したおすすめの投資方法
ボーナスの使い道が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:まずは将来のお金の悩みを相談br>
ボーナスをどう使う?貯金と投資のバランス
ボーナスは臨時収入と思われがちですが、年間収入の一部として計画的に活用することが大切です。特に、ボーナスを活用して投資を検討する際は、以下の点をおさえておきましょう。
生活防衛資金をまず確保する
投資を始める前に、何よりも優先すべきは「生活防衛資金」の確保です。これは、病気やケガ、突然の失業といった予測できない事態に備えるためのお金です。この資金がなければ、いざという時に投資で作った資産を取り崩すことになり、計画的な資産作りが困難になります。
生活防衛資金の目安は、一般的に毎月の生活費の3ヶ月から6ヶ月分とされています。家族構成や職業によって必要な金額は異なりますが、この基準に達していない場合は、ボーナスを最優先で充当すべきです。
この資金は、投資には回さず、すぐに引き出せる普通預金などで確保しておくことが鉄則です。
ローン返済や将来の支出と投資の優先順位
生活防衛資金が十分に確保できたら、次に検討すべきは、近い将来に予定されている支出への備えです。
例えば、3年以内に車の買い替えや住宅購入の頭金、子どもの進学費用など、使い道が決まっているお金は、リスクのある投資ではなく預貯金などで確実に準備しておく必要があります。
また、住宅ローンや自動車ローンなど、金利の高い借り入れがある場合は、繰り上げ返済も有効な選択肢です。支払うべき利息を減らすことは、実質的にリスクなく高いリターンを得るのと同じ効果があります。
ただし、繰り上げ返済によって手元の現金が不足しないよう、生活防衛資金とのバランスを十分に考慮することが大切です。
これらの準備を整えた上で、残ったお金を投資に回すのが賢明な順序と言えるでしょう。
投資に回せる金額の目安
投資に回す金額は、生活防衛資金や近い将来の支出を確保した上で残る「余剰資金」と考えるのが大原則です。ボーナスが入ったからといって全額を投資に回すのは、急な出費に対応できなくなるリスクがあるため避けるべきです。
投資に回せる金額の目安は個々の収入や家族構成、ライフプランによって異なります。自身の家計状況を把握し、「消費」「貯蓄」「投資」のバランスを考え、無理のない範囲で投資額を決めましょう。
参考)臨時収入からの貯蓄割合
金融広報中央委員会が実施した「家計の金融行動に関する世論調査](令和5年)」によると、臨時収入等からの貯蓄割合は以下のとおりです。
臨時収入等からの貯蓄割合(金融資産保有世帯)の平均:単位%
ボーナスで投資をする際の考え方
ボーナスを投資に回す際は、一度にまとめて投資するのか、分散して投資するのかといった「タイミング」を意識することが大切です。また、既に保有している資産とのバランスを考え、全体のポートフォリオが偏らないように調整することも欠かせません。
短期的な値動きに振り回されず、長期的な資産形成の中でボーナスをどのように活かすかを検討しましょう。
ボーナス投資の基本|一括投資vs積立投資
ボーナスのようなまとまった資金を投資する際には、大きく分けて「一括投資」と「積立投資」の2つのアプローチがあります。
それぞれにメリットとデメリットが存在し、どちらが最適かは市況や個人の投資スタイルによって異なります。両者の特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
一括投資のメリット・デメリット
一括投資の最大のメリットは、投資したタイミングから相場が上昇基調となった場合に、大きなリターンを期待できる点です。
まとまった資金を一度に投じるため、複利効果を早期から最大限に享受できる可能性があります。特に、市場が割安だと判断できる局面で実行できれば、効率的に資産を増やすことが可能です。
一方で、デメリットは高値掴みのリスクが伴うことです。購入した直後に相場が下落局面に入ると、大きな含み損を抱えることになりかねません。購入タイミングが一度きりであるため、その後のパフォーマンスが購入価格に大きく左右される、タイミングに依存した投資手法と言えます。
積立投資のメリット・デメリット
積立投資は、定期的に一定額を投資し続ける手法です。この方法の最大のメリットは、「ドルコスト平均法」の効果により、購入価格を平準化できる点にあります。
価格が高い時には少ない口数を、価格が安い時には多くの口数を購入することになるため、結果的に高値掴みのリスクを抑え、平均購入単価を引き下げる効果が期待できます。
デメリットとしては、投資を開始した時点から相場が一貫して上昇し続けるような右肩上がりの市場では、一括投資に比べてリターンが小さくなる可能性が挙げられます。
また、資産が大きく成長するまでには時間を要するため、短期的な成果を求める方には不向きな手法と言えるでしょう。
一括投資と積立投資で悩んだ時の選び方
投資初心者や市場の見極めに自信がない場合は、積立投資(分割投資)が有効です。ボーナスを数ヶ月から1年に分けて投資することで時間分散の効果が働き、高値掴みのリスクを抑えられます。精神的な負担も少なく、長期的に続けやすい点もメリットです。
一方で、投資経験があり市場分析に基づいて判断できる場合は、一括投資も選択肢となります。ただし、全額ではなく一部にとどめ、残りを積立に回すなど、リスクを分散させる工夫が欠かせません。
両者を組み合わせた運用も効果的です。
ボーナスの投資先を選ぶ時のポイント
ボーナスを投資に回すと決めたら、次に大切なのが投資先の選定です。やみくもに話題の銘柄に飛びつくのではなく、いくつかの重要なポイントをおさえることで、失敗のリスクを減らし、自身の目的に合った資産運用が可能になります。
投資先を選ぶ上で欠かせない3つのポイントを解説します。
ポイント①投資の目的・目標金額
投資を始める前には、「何のために」「いつまでに」「いくら必要か」をはっきりさせることが大切です。例えば「20年後に老後資金2000万円」「10年後に教育費500万円」といった具体的な目標を設定しましょう。
目的が明確になれば「どの程度リスクを取るか」「選ぶべき商品」なども自然と見えてきます。長期目標なら成長重視、短期目標なら安定重視といった運用方針を決めやすくなり、必要な利回りを逆算して現実的な計画を立てられます。
ポイント②金融商品の特徴とリスク
世の中には多種多様な金融商品があり、それぞれ異なる特徴とリスクを持っています。
例えば、投資信託は運用の専門家が複数の株式や債券に分散投資してくれるため、初心者でも手軽に始めやすい商品です。しかし、元本が保証されているわけではなく、市場の動向によっては価格が下落するリスクがあります。
一方、株式投資は、企業の成長によっては大きなリターンを期待できる魅力がありますが、その企業の業績悪化や倒産など、個別銘柄特有のリスクを直接的に負うことになります。
これらの商品のメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の投資目的やリスク許容度に合ったものを選ぶことが、賢明な投資の第一歩です。
ポイント③運用できる年数
投資に充てる資金を「いつまで運用できるか」という期間の長さは、投資戦略を決定する上で極めて重要な要素です。
一般的に、運用期間が長いほど、複利の効果を最大限に活かすことができ、市場が一時的に下落しても価格の回復を待つ時間的余裕が生まれます。10年以上の長期的な視点で運用できる資金であれば、株式などのリスク資産の割合を高め、積極的なリターンを狙う戦略も選択肢に入ります。
一方、3年以内など短い期間で使う予定のある資金は、元本割れのリスクを避けるため、投資には適していません。これらの資金は預貯金など安全性の高い方法で確保することが賢明です。
ボーナスのようなまとまった資金は、短期的な値動きに一喜一憂せず、中長期的な視点でじっくりと育てることを基本戦略と考えるべきでしょう。
ボーナスの使い道が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:まずは将来のお金の悩みを相談br>
リスク許容度別に考えるボーナス投資先
投資先を選ぶ上で重要な基準の一つが、どれだけのリスクを受け入れられるかという「リスク許容度」です。
資産状況や年齢、投資経験によって、最適な投資対象は異なります。
ここでは、リスク許容度を「低」「中」「高」の3つのタイプに分け、それぞれに適したボーナスの投資先について解説します。
リスクを抑えたい人
投資経験が浅く、元本割れを避けたい人には、安全性を重視した商品が適しています。代表的な選択肢は定期預金や債券型投資信託などです。
「資産を増やす」よりも「資産を減らさない」ことを優先し、数年以内に使う予定のある資金を置く場として有効です。
利回りは低めですが、元本が守られる安心感が大きなメリットといえます。基本的には預貯金を中心に据え、無理のない範囲で運用を考えるのが現実的です。
ある程度リスクを取れる人
短期的な値動きを許容しながら、中長期的に資産を積み上げたい場合は、インデックス型投資信託やバランスファンドといった分散効果の高い商品が適しています。
複数資産への配分や投資時期の分散を意識することでリスクを抑制できます。
また、毎月の積立投資とボーナスによるスポット投資を併用する手法は、時間分散と金額分散の両面で効果的です。
市場の短期的な変動に左右されず、長期的な資産形成を目指す場合に合理的なアプローチといえるでしょう。
積極的に増やしたい人
長期運用を前提に大きなリターンを狙う場合は、株式型投資信託や海外株式インデックスファンドが有力な選択肢となります。投資経験が豊富な上級者であれば、個別株による運用も検討できるでしょう。
ただし、短期的な価格変動による下落リスクを受け入れる覚悟が必要です。その一方で、20年以上の長期投資を続ければ、複利効果が働き、大きなリターンを得られる可能性があります。
ボーナスの投資先でおすすめなのはNISA
ボーナスを投資に活用する際、NISA(少額投資非課税制度)の利用がおすすめです。
NISAは、投資によって得られた利益(配当金、分配金、譲渡益)が非課税になる、国が設けた優遇制度です。
通常、投資の利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引であればそれが一切かからないため、効率的に資産を増やすことができます。
ポイント①少額から始められる
NISAは、まとまった資金がなくても投資を始められる点が大きな魅力です。金融機関によっては、月々100円や1000円といった非常に少額から積立設定が可能です。
そのため、「ボーナスの全額を投資に回すのは少し不安」と感じる人でも、まずはボーナスの一部を使って気軽に投資をスタートすることができます。
ポイント②積立投資と一括投資、両方できる
2024年から新しくなったNISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2種類の非課税枠が設けられています。「つみたて投資枠」は、毎月コツコツと積立投資を行うのに適しており、長期的な資産形成の土台となります。
一方、「成長投資枠」は、ボーナスのようなまとまった資金で株式や投資信託を一括で購入(スポット購入)するのに向いています。
この2つの枠は併用が可能なため、柔軟な投資戦略を組むことができます。例えば、普段は「つみたて投資枠」で毎月積立を行い、ボーナスが支給されたタイミングで「成長投資枠」を活用して追加投資するといった使い方が可能です。
これにより、個々の資金状況に合わせた効率的な資産形成が実現できます。
ポイント③ボーナス設定がある
多くの金融機関では、NISAの積立設定において「ボーナス設定」という機能を提供しています。
これは、通常の毎月の積立額に加えて、ボーナスが支給される特定の月(例えば6月と12月など)に積立額を増額できる機能です。
この設定をあらかじめ行っておくことで、ボーナスが入るたびに手動で追加投資の手続きをする手間が省け、忘れずに計画的な投資を続けることができます。
NISAの年間非課税枠を効率的に使い切りたいと考えている場合に、役立つ機能と言えるでしょう。
まずはつみたて投資枠の活用がおすすめ
NISAを始める際は「つみたて投資枠」から活用することをおすすめします。
ボーナスをすぐに全額投資するのではなく、例えば次のボーナスまでの6ヶ月間などで分割し、毎月の積立額に上乗せする形を取ることで、時間分散の効果を得ながら投資を始めることができます。
また、「つみたて投資枠」で購入できる商品は、金融庁が定めた「長期・積立・分散投資」に適した基準を満たす投資信託などに限定されています。
これにより、投資初心者でも比較的商品を選びやすく、リスクを抑えやすいというメリットもあります。
ボーナスの投資先で悩んだ時はプロに相談
ボーナスの投資先や運用方法を一人で判断するのが難しいと感じたら、金融の専門家に相談することが有効です。客観的なアドバイスを受けることで、より適切な意思決定につながります。
特に、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、特定の商品に偏らず、中立的な立場から個々の資産状況やライフプランに合った提案を行います。自分では気づきにくい視点や有利な制度、適した金融商品を知ることができるのは大きなメリットです。
相談は投資初心者だけでなく、経験者にとっても有益です。ポートフォリオの妥当性を検証したり、運用戦略を見直したりすることで、資産運用の精度を高められます。
多くの金融機関やサービスでは無料相談も提供されているため、ボーナスを活用するこの機会に専門家へ相談してみるのも良い選択肢でしょう。
相談するならマネイロがおすすめ
マネイロはSBI証券と提携するIFAを通じて、投資額にかかわらず専任担当者がつき、NISAやiDeCo、ボーナスの活用まで幅広い相談を無料で行えます。中立的な立場から自分に合った運用方法を提案してもらえるのが大きな魅力です。
将来の資産形成に不安を感じている方は、この機会にプロへ相談してみませんか。
»マネイロの無料相談の詳細はこちら
まとめ
ボーナスは計画的に活用することで、将来の資産を大きく育てるための重要な元手となります。まずは生活防衛資金を確保し、ローン返済や短期的な支出を考慮した上で、余剰資金を投資に回すのが鉄則です。
投資先を選ぶ際は、ご自身の目的やリスク許容度を明確にし、一括投資と積立投資の特性を理解して最適な方法を選びましょう。
特に、利益が非課税になるNISA制度の活用は、効率的な資産形成のために不可欠です。
判断に迷うことがあれば、専門家に相談するのも賢明な選択です。後悔のないボーナスの使い方を実践し、将来に向けた資産形成の第一歩を踏み出してください。
»貯金だけじゃもったいない。今のあなたに合う投資法をチェック
ボーナスの使い道が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:まずは将来のお金の悩みを相談br>
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください