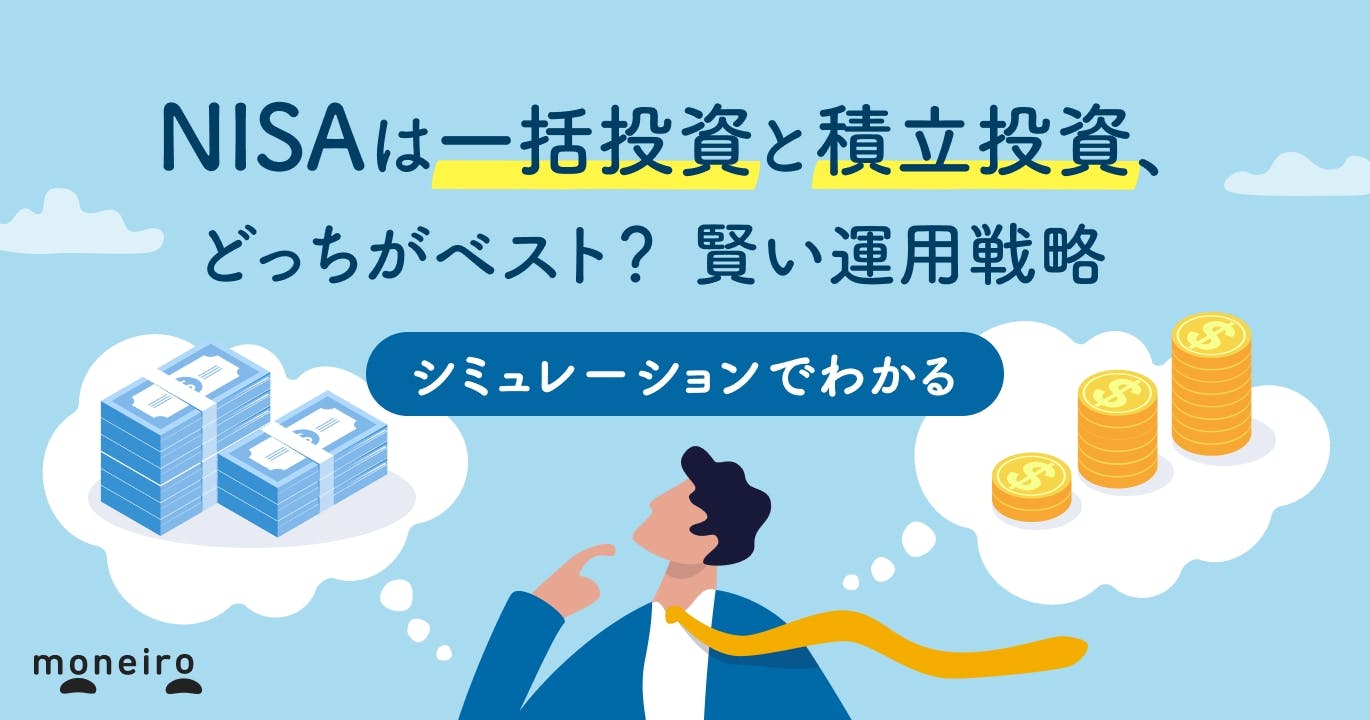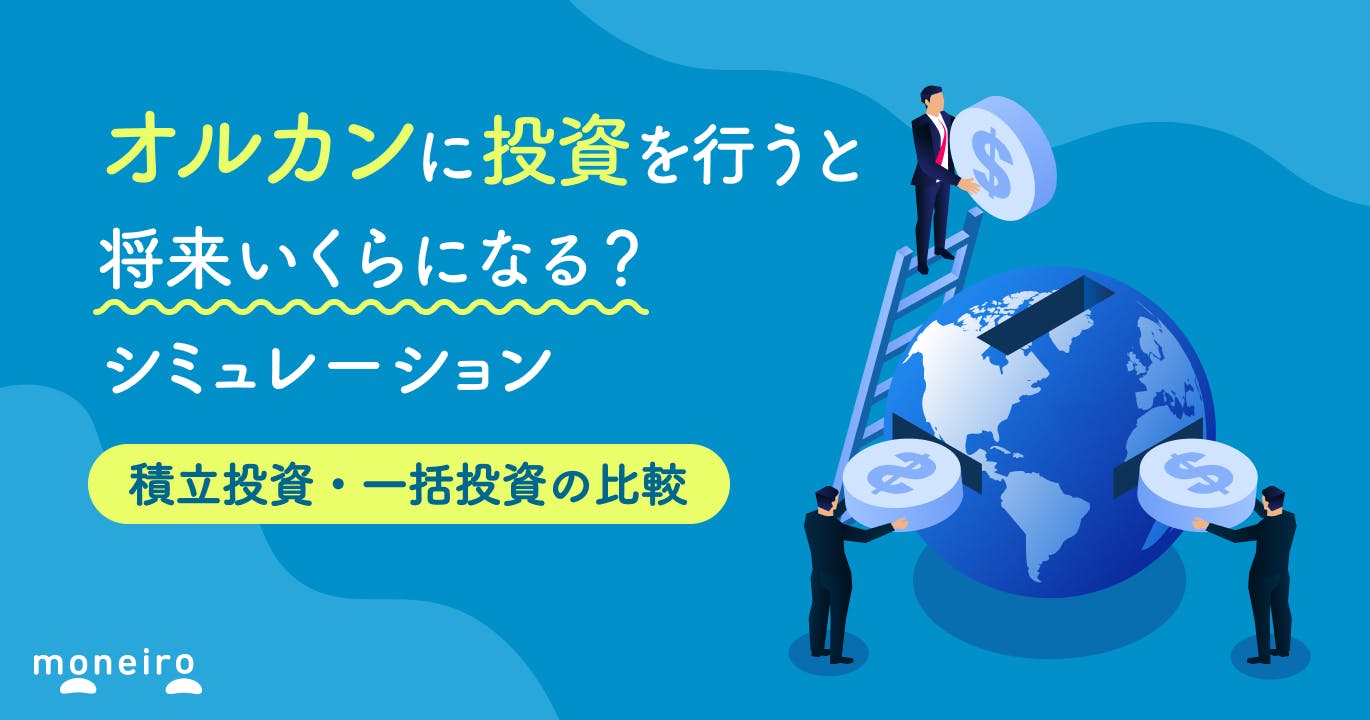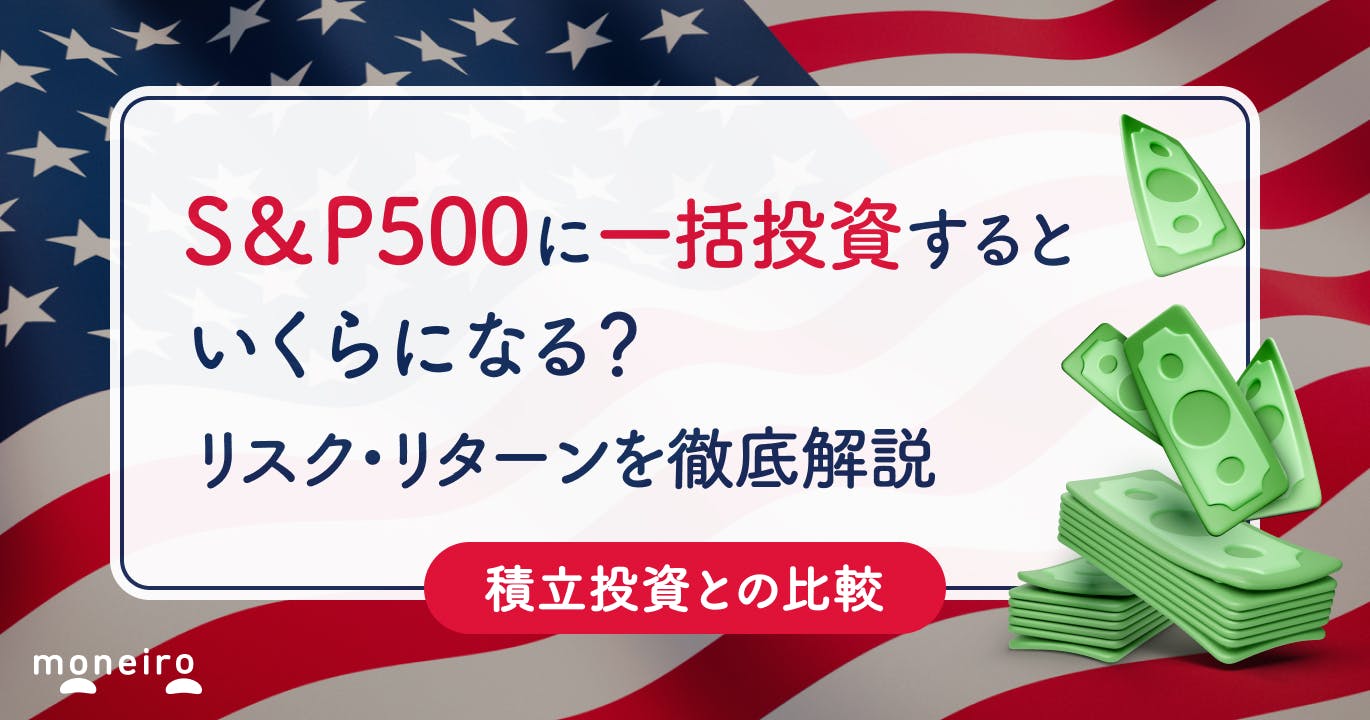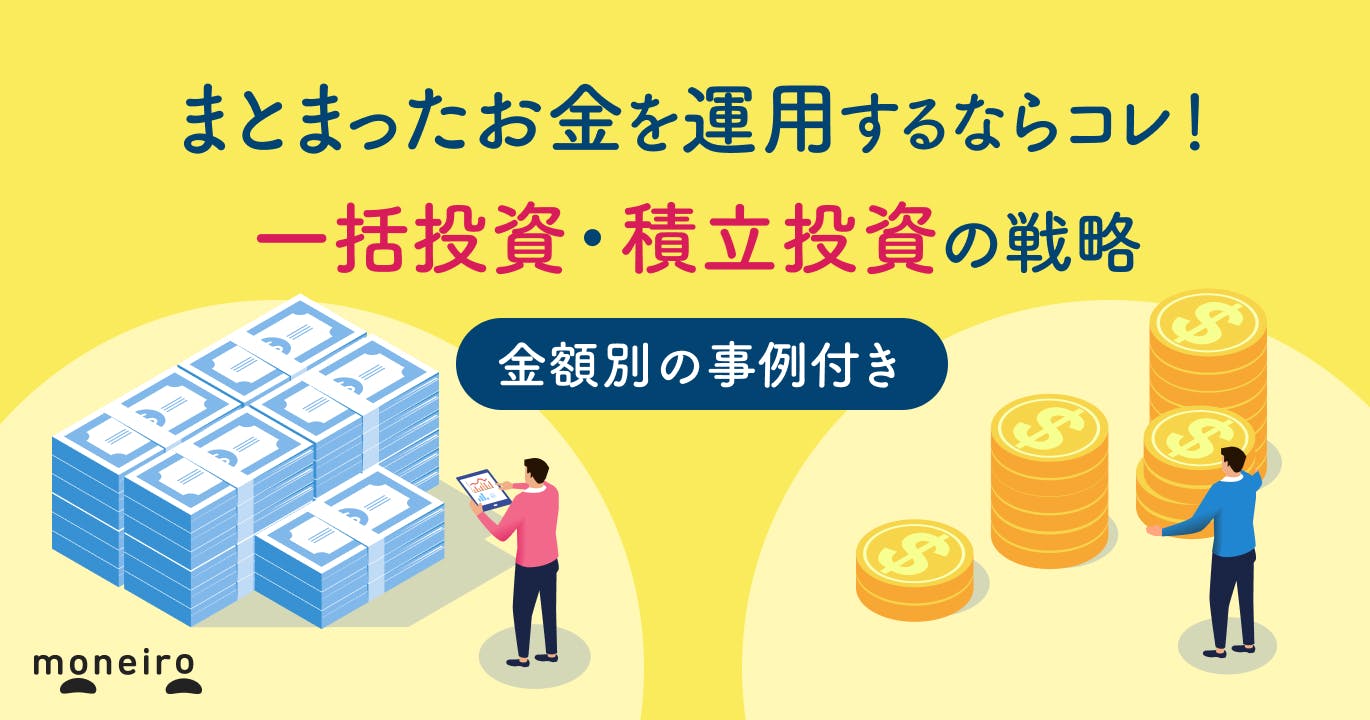NISAは一括投資と積立投資、どっち?シミュレーションと賢い運用戦略を解説
≫診断でわかるあなたに合った一括投資の方法
「NISAで一括投資をしたら将来いくらになるかシミュレーションしたい」「一括投資と積立投資、どっちが良い?」とNISAの活用法について悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
2024年からスタートした新NISA(新しいNISA)では、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になり、積立投資と一括投資の両方で非課税の恩恵が受けられます。
一括投資ができるのは成長投資枠のみですが、年間の投資上限額は240万円まで拡大し、まとまった額を株式・投資信託・ETFなど、幅広い商品に投資することができます。
本記事ではNISAで一括投資した場合のシミュレーションと、一括投資と積立投資の比較、NISAの活用法についてプロが徹底解説します。
- NISAで一括投資をする際は成長投資枠を活用する
- 一括投資は商品選びや売却タイミングの判断などが難しいため、不安であれば少額からの積立投資から始めるのがおすすめ
- 一括投資には債券などNISA以外の選択肢があることを理解する
NISAの運用に悩んでいるあなたへ
NISAの賢い始め方や運用の見直しなど、NISAのお悩みをまとめて解決
▶NISAで始める資産運用の基本:NISAの始め方がすぐわかるWebセミナー
▶NISAをフル活用!成長投資枠の活用法:NISAの活用法を解説するWebセミナー
▶NISAのお悩みをプロに相談:商品選び、運用の悩みをプロが解決

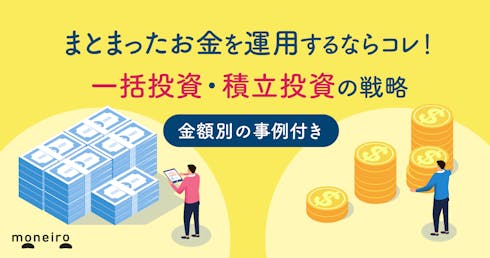
一括投資がおすすめなのは〇〇〇な人
一括投資は、まとまった金額を一度に投資する方法です。大きなお金を一括で投資をする分、リスクが大きくなるため、余裕資金がある人向きの方法と言えるでしょう。
一括投資でも少額の投資が可能な場合もありますが、まとまった金額が準備できると、購入可能な金融商品が増えることに加え、お金を効率的に運用しやすくなります。
ただし、一括投資は、投資信託や株式など、多くの銘柄のなかから自分に合う商品を選んで購入し、自分でタイミングを見計らって売却する必要があります。
まとまった額が準備できても、売買の判断や商品の選択が難しい場合は、少額から分散投資ができる積立投資を検討する方が良いかもしれません。
一括投資か積立投資か迷った場合は、資産運用に関するアドバイス経験が豊富なIFAやFPに相談してみるのもおすすめです。
NISAで一括投資をするなら成長投資枠を活用する
2024年からの新NISAでは、旧NISAのつみたてNISAと一般NISAを引き継ぐ、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が設定されています。この2つの枠は同時に利用することができます。
一括投資を行う場合は、成長投資枠を利用します。成長投資枠では、一括投資と積立投資の両方が利用できます。つみたて投資枠は積立投資専用の枠で、一括投資はできません。
成長投資枠は、つみたて投資枠よりも商品のラインナップが豊富で、株式やさまざまな投資信託やETFなどに一括で投資をすることができます。
それぞれの投資枠には、年間の投資上限額(成長投資枠:年間240万円、つみたて投資枠:年間120万円、両枠合わせて年間360万円まで、総額1800万円まで)が定められていることも覚えておきましょう。
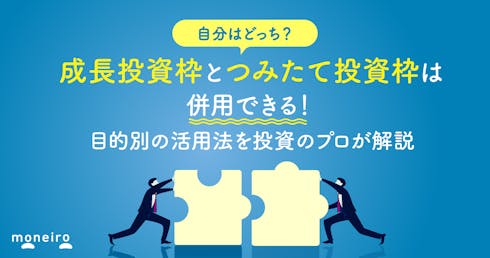
参考)成長投資枠で選べる商品
成長投資枠で購入できる商品は、日本株や米国株式、投資信託やETF、REIT(不動産投資信託)などです。つみたて投資枠よりも、購入可能な金融商品や銘柄が格段に多いのが特徴です。
ただし、NISAは長期投資による資産形成を支援する制度なので、信託期間が短い投資信託や毎月分配型の投資信託、ハイリスクの金融商品、整理・管理銘柄などは対象外です。
購入できる商品に制限がある点は注意したいポイントです。
NISAで一括投資した場合のシミュレーション
100万円を一括投資した場合、運用期間が長くなるほど複利の効果を得やすくなり、結果的に資産の増え方が大きくなっています。
また、当然ではありますが、想定年率が高い方が資産も大きく増えています。同じ100万円でも利率が3%と6%では、30年後の想定資産は3倍以上の違いがあります。
ただし、想定年率が高くなると、リスクも同時に高くなります。お金を効果的に増やすには、長期運用を前提として、自分のリスク許容度に合致する商品を選ぶことが大切です。
診断:自分に合った一括投資の方法がわかる
マネイロでは働く世代向けにお金の診断・シミュレーターを提供しています。
「一括投資診断」では以下がわかります。
- 自分に適した投資先の傾向がわかる
- 想定されるリターンとリスクから将来の資産推移を確認できる
- 投資を進めるうえでのポイントを、専門家がわかりやすく解説
※一括投資診断結果イメージ
NISAの一括投資と積立投資、どちらが有利?
NISAで投資を行う際、一括投資と積立投資、どちらの方が良いか悩んでいる人も多いかもしれません。
あらためて一括投資と積立投資の違いについて見ていきましょう。
一括投資のメリット・デメリット
一括投資はまとまった金額を投資するため、運用状況によっては、短期間で大きなリターンを得やすいのが特徴です。大きな金額を一度に投じることで複利の効果も実感しやすく、これらは一括投資ならではのメリットと言えるでしょう。
一方、一括投資のデメリットは、株価や為替など、相場の下げ局面が継続すると、大きな損失を抱えてしまう点です。購入後に景気が後退してしまうと、最悪の場合、長期にわたり含み損を抱えてしまう可能性もあります。
一括投資の場合、利益が得られるかどうかは、購入時の価格に左右されます。購入のタイミングが良ければ、すぐに大きなリターンを得られることもありますが、タイミングが悪いと、大きな損失を抱える可能性もあります。
Q.一括投資をしている時に暴落した時の対処法は?
暴落時には、様子を見る・保有を続ける・ナンピン買いをする・売却する、などさまざまな選択肢がありますが、最適な対応は資産状況や投資方針、商品によって異なります。
そのため、暴落時の行動はあらかじめルール化しておくのがおすすめです。例えば「〇%下落したら売却」などマイルールを決めておけば、冷静な判断がしやすくなります。これは暴落時に限らず、平時の資産管理でも有効です。
また、投資する際は長期運用に適した商品を選び、暴落の原因が一時的かどうかを見極めることも重要です。
一括投資では評価額が大きく下がると効率が悪化しやすいため、判断に迷った時は市況や金融商品に詳しいIFAなど専門家に相談するのも有効な選択です。
積立投資のメリット・デメリット
積立投資は決まった金額を定期的に購入することで、取得価格の平準化ができるのがメリットです。価格が高い時は少ない口数を、価格が安い時は多くの口数を購入するので、取得単価を下げる効果が期待できます。
一方、積立投資は短期間で大きなリターンを得にくいのがデメリットです。積立投資は、長い時間をかけてコツコツ投資を継続することで資産を形成していく方法です。短期間で大きなリターンを狙う方法ではないことをおさえておきましょう。
NISAで一括投資がおすすめなのは「まとまった資金がある人」
非課税制度であるNISAを利用して一括投資をするメリットは、大きなリターンが得られた場合、税金が引かれることなく、リターンをそのまま得られることです。
一括投資する金額が大きいほど、リターンも大きくなり、非課税の恩恵を受けやすくなります。したがって、一括投資は「まとまった資金がある人」に有利な方法と言えるでしょう。
ただし、購入後に相場が下落局面に入ると、資産の評価額が大きく減少する可能性もあります。保有資産のリスクを小さくするためには、基本は積立投資を行い、リスク分散の観点から余裕資金を一括で投資するのもひとつの方法です。
NISAで一括投資する際におさえておきたいポイント
ここからはNISAで一括投資をする際のポイントについて解説します。一括投資に興味がある方はぜひ参考にしましょう。
長期投資の視点を持つ
投資にはリスクがつきものですが、そのリスクをなるべく抑えるためには「長期投資」が効果的です。10年、20年、30年以上と、長い時間をかけて投資をすれば、複利効果も得られ、リスクとリターンが安定しやすくなるでしょう。
また、長期投資を行う際は、長期的に成長が期待できる資産に投資をすることも大切です。
世界の株式に分散して投資するファンドなど、過去に大きな下落を経験しても長期的に見て右肩上がりに成長している資産に投資することを意識しておきましょう。
リスク許容度をあらためて確認する
投資をする時は自身のリスク許容度を確認しておくことは非常に大事です。
長く運用を続けている間には、数回の暴落を経験する可能性がありますが、自分のリスク許容度を理解しておけば、自身が許容できるリスク以上の金融商品を省くなどして、自分に合った商品選びができます。
相場の変動に振り回されることも少なくなるでしょう。
一括投資にはNISA以外の選択肢があることを理解する
非課税で資産運用できるのは、NISAのメリットのひとつですが、場合によってはNISAを活用しないで投資する方が良いケースもあります。
例えば、債券はNISAでは購入できませんが、分散投資のためにはポートフォリオに加えておきたい金融商品です。定期的に利子を受け取れ、満期を迎えると額面金額が戻ってくるなどの特徴は、保有資産のリスクを小さくするためにも有効です。一時払いの保険商品なども同様です。
一括投資にはNISA以外の選択肢があり、家計の状況等によっては債券や保険などで運用した方が良いケースがあることも理解しておきましょう。
商品選びやタイミングに悩んだらプロに相談する
一括投資の場合、その後の運用成果は、購入時の価格によって左右されることになります。したがって、購入するタイミングについては慎重に判断することが大事です。
また、投資する商品については、自身のリスク許容度などをふまえた上で、自分に合った商品を選ぶようにしましょう。
ひとりでは判断が難しい場合は、資産運用のアドバイス経験が豊富なIFAなどに相談してみるのもひとつの方法です。
NISAの活用法を知りたい人はプロに相談
NISAは2024年に新しく制度が変わり、より柔軟で使い勝手の良い制度に変わっています。
一方、制度の柔軟性が増したことで「つみたて投資枠と成長投資枠は併用した方が良い?」や「投資するなら年間の最大上限金額を使い切るように投資をした方が良い?」など、NISAの使い方で悩む方は少なくありません。
NISAを効果的に使うノウハウが知りたい方は、金融事情に精通したIFAなどに相談するのがおすすめです。
IFAは資産運用のアドバイス経験が豊富なため、投資を始めたばかりの人にも、NISAの使い方について詳しく教えてくれるでしょう。
特徴①自分に合ったNISAの活用法がわかる
マネイロでは、マネイロコンシェルと呼ばれる、金融機関出身のお金のプロが在籍しています。
マネイロコンシェルは、各種金融商品販売の有資格者で、資産運用のアドバイス経験が豊富なIFAです。マネイロに相談すれば、NISAの活用方法はもちろんのこと、相談者に寄り添ったアドバイスが無料で受けられます。
特徴②ネット証券のサポートが充実
ネット証券は取り扱い商品も豊富で手数料も安いため、証券口座を開設する方も多いです。しかし、ネット証券は口座を開設しても自分専門に担当者がつく訳ではないため、投資に関することは全て自分で判断して運用する必要があります。
そのため、投資初心者の方で口座を開設したものの、開設後の金融商品選びや運用後の相談ができるところがなく不安に思っている方は多いです。
マネイロではSBI証券と提携しているため、口座開設から商品選び、運用後のサポートまで、資産運用に関することを気軽に相談することができます。
ネット証券で口座を開設したいけどサポートがなく不安という方は、マネイロの相談サービスを利用しながら投資を始めるのも良いでしょう。
特徴③商品の選び方、運用も無料でアドバイス
マネイロでは、証券口座の開設や商品選びのサポート、運用開始後の相談など、何度でも無料でサービスを利用することができます。
相談者が資産運用の相談をしたい時に、手数料を支払うことなく、無料で金融のプロに相談できるのは、NISAをこれから始める方だけでなく、現在運用中の方にとっても、安心のサービスと言えるでしょう。
まとめ
2024年の制度改正により、NISAで投資を始める人が増えています。ただし、NISAはあくまで非課税枠を活用して資産形成を支援する制度であり、実際には投資信託や株式などの商品に投資することになります。
上手く運用すれば資産を増やせますが、損失が出る可能性もあるため、制度の仕組みや活用方法を理解し、自分に合った資産運用の計画を立てることが大切です。
投資が初めての方は、IFAなど専門家に相談すれば、自身のリスク許容度に応じた運用プランを提案してもらえるので安心です。NISAを上手に活用したい方は、プロの力を借りてみてはいかがでしょうか。
NISAの運用に悩んでいるあなたへ
NISAの賢い始め方や運用の見直しなど、NISAのお悩みをまとめて解決
▶NISAで始める資産運用の基本:NISAの始め方がすぐわかるWebセミナー
▶NISAをフル活用!成長投資枠の活用法:NISAの活用法を解説するWebセミナー
▶NISAのお悩みをプロに相談:商品選び、運用の悩みをプロが解決
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
土屋 史恵
- ファイナンシャルプランナー/金融ライター/編集者
神戸市外国語大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。遺言信託など資産承継ビジネスに強み、表彰歴あり。その後は長年の金融機関勤務経験を活かし、金融メディアに転職。記事執筆や編集などを担当。現在はフリーランスとして活動中。AFP、FP2級、証券外務員一種を保有。
執筆
鶴田 綾
- ファイナンシャルアドバイザー
福岡女学院大学・人文学部英語学科卒。卒業後、日本郵便株式会社にてリテール営業に従事。投資信託や生命保険の販売では商品分析を得意とし、豊富な商品知識を持つ。現在はこれまでの金融商品の知識を生かし、Instagramを中心に、SNSにて資産運用のはじめ方や資産形成のコツについて積極的に情報発信をしている。一種外務員資格(証券外務員一種)、保険募集人資格などを保有。