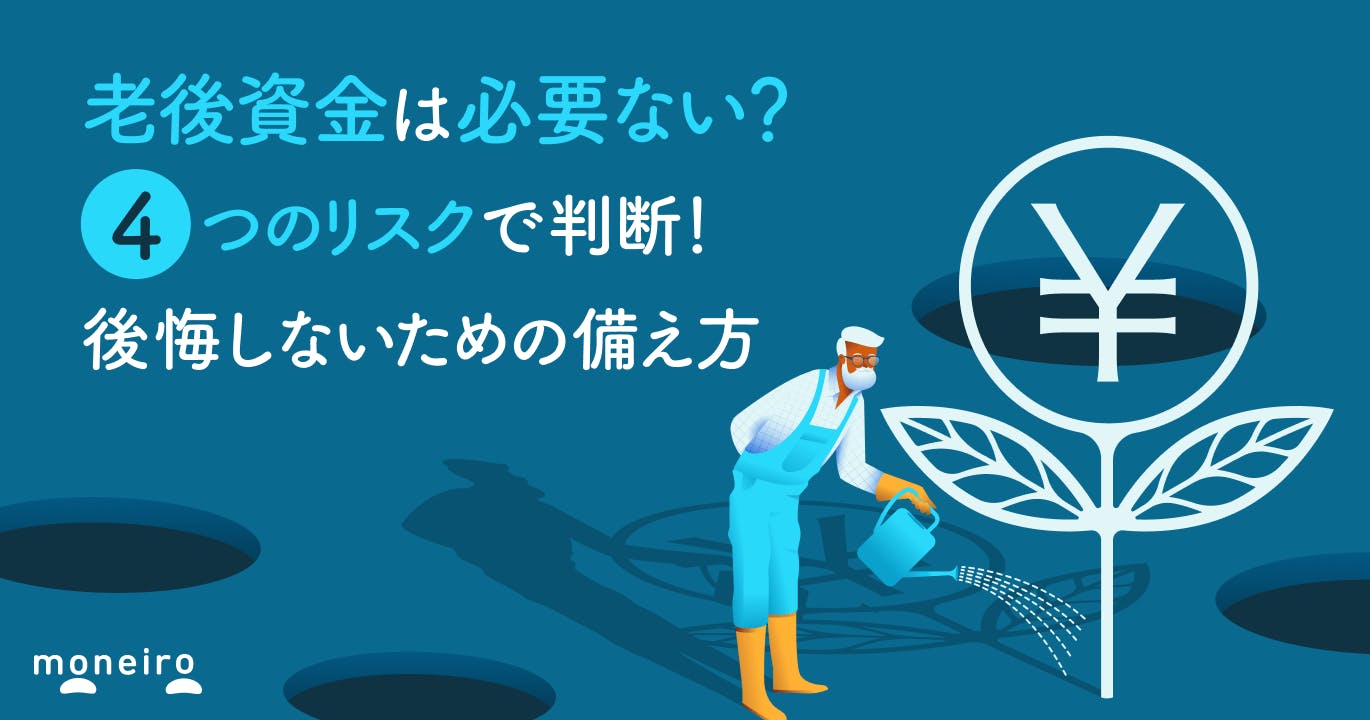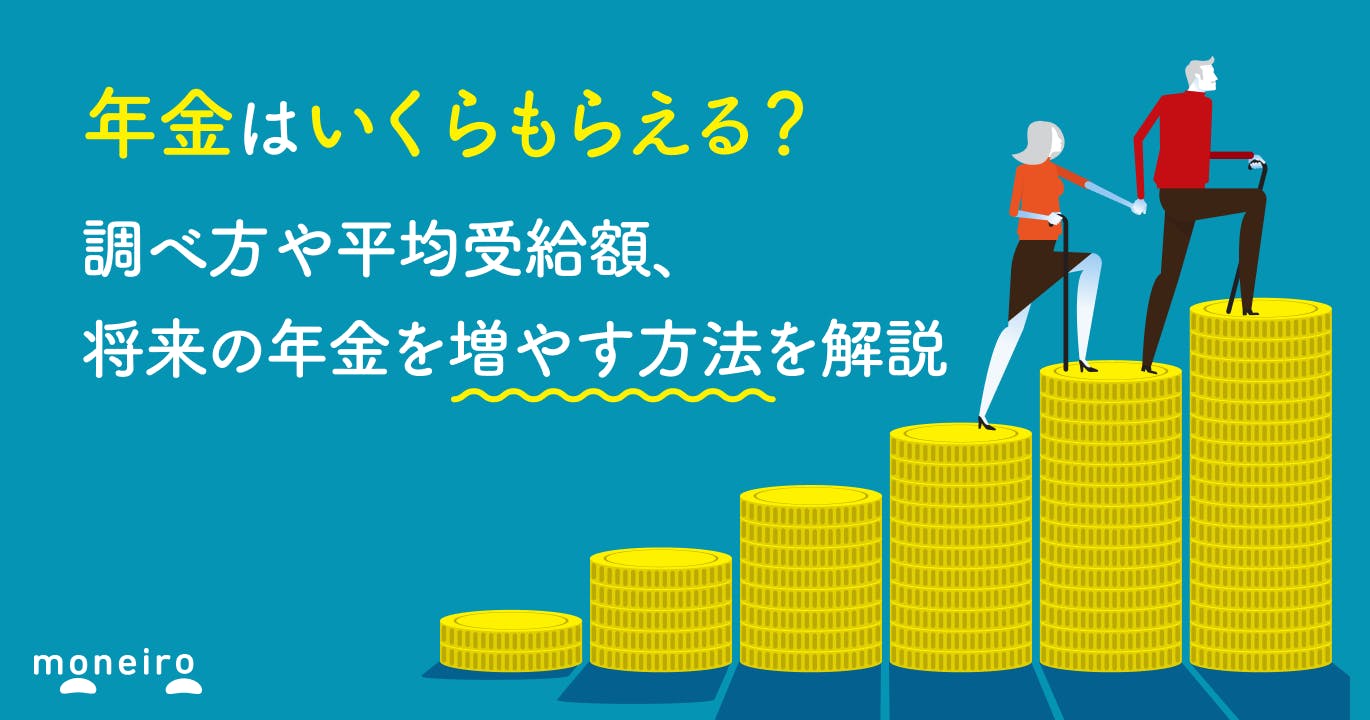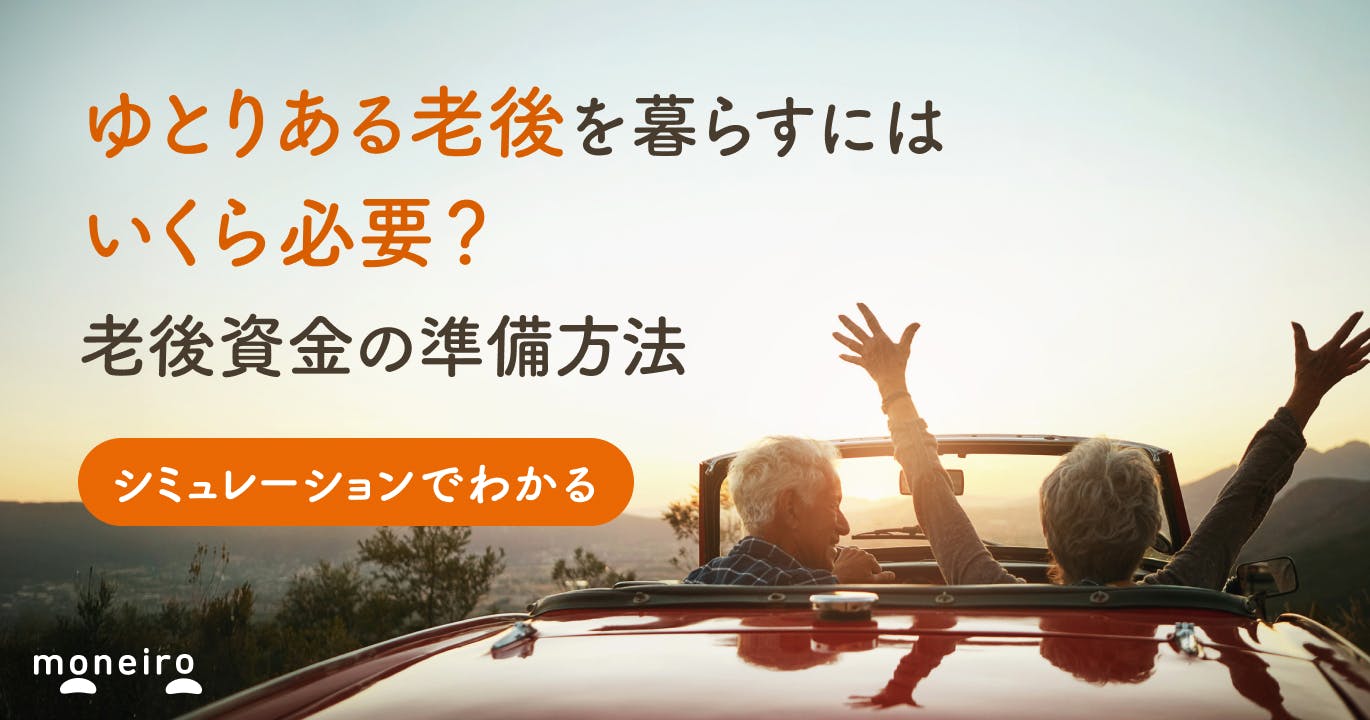老後破産する人の特徴とは?原因や破産しないための対策を解説
【無料】あなたの老後に必要なお金はいくら?3分で診断
老後破産は、定年後の生活が立ち行かなくなる深刻な問題です。自分は大丈夫だろうか、と不安を感じる方もいるかもしれません。
本記事では、お金の専門家監修のもと、老後破産の原因や陥りやすい人の特徴、そして今からできる具体的な対策を徹底的に解説します。あなたの未来を守るための回避策を、ぜひこの機会に確認しておきましょう。
- 老後破産がなぜ起こるのか、その背景にある具体的な原因と実態
- 老後破産に陥りやすい人の特徴と、自己診断のポイント
- 老後破産を回避するために今すぐ始められる具体的な対策と、困った時の公的支援
老後破産が気になるあなたへ
老後もお金の不安なく暮らすために、将来の必要資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ


老後破産とは?
まずは、そもそも老後破産とは何なのか、実態データも見ながら解説していきます。
データで見る老後破産の実態
日本弁護士連合会が発表した「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、多重債務に陥り、法的な債務整理を選択する高齢者の実態を垣間見ることができます。
2020年の調査では、破産債務者のうち「60歳代」が全体の16.37%、「70歳代以上」が全体の9.35%を占めており、全年代の破産債務者のうち4人に1人にあたる約25%が高齢者であることを示しています。
特に、70歳代以上の数値は、1997年以降の調査で最大値となっており、高齢になってからの経済的な破綻が増加傾向にあることを示しています。
「自己破産」だけではない老後破産も?
老後破産とは、必ずしも「自己破産」という法的な手続きを指すだけではありません。貯蓄が底をつき、年金やわずかな収入だけでは生活費を賄えず、最低限の生活水準(生活保護基準など)を下回るような状況に陥り、経済的に自立できない状態も「事実上の破産」とみなされます。
こうした状況では、日々の食費や光熱費にも事欠き、医療費や介護費用といった突発的な出費に対応できなくなるなど、精神的にも肉体的にも追い詰められることになります。
法的な手続きには至らなくとも、社会的に孤立し、生活の質が著しく低下している状態も「老後破産」の一種といえるでしょう。
老後破産はなぜ起こる?よくある5つの原因
老後破産に陥る原因は1つではなく、複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。ここでは、よくある5つの原因を具体的に解説します。
原因1.収入の減少と支出のアンバランス
定年退職を迎えると、現役時代に比べて収入が大幅に減少するのが一般的です。しかし、現役時代の生活レベルを維持したまま、食費や趣味、交際費などの支出を見直さずにいると、年金だけでは生活費を賄いきれなくなり、あっという間に家計が赤字に転落してしまいます。
収入に合わせて支出を調整できないことが、老後破産の典型的な原因の1つといえます。
原因2.想定外の支出(医療費・介護費)
人生の後半では、病気やケガによる医療費、あるいは親や配偶者の介護にかかる費用など、想定外の大きな支出が発生するリスクが高まります。
上述の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、負債原因として「病気・医療費」が全体の23.31%を占めており、その影響の大きさがうかがえます。これらの費用は高額になることが多く、貯蓄が十分でない場合、一気に生活が破綻する引き金となります。
原因3.終わらない住宅ローン・教育費
定年後も住宅ローンの返済が続く場合、年金収入だけでの返済は大きな負担となります。特に、退職金でローンを完済する予定だったが、それが想定よりも少なかった、あるいは別の目的で使ってしまった場合、家計を圧迫します。
また、子や孫への教育費援助や結婚資金の援助、生活費の援助などが重荷になるケースもあります。「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、負債原因として「教育資金」が全体の9.84%、を占めています。この数字は、1997年調査以降最大値となっています。
原因4.退職金の減少・運用の失敗
企業の業績悪化や制度変更により、退職金が想定していたよりも大幅に減少するケースがあります。これを見込んで老後の生活設計を立てていた場合、計画が狂い破綻につながる可能性があります。
また、老後資金を増やすために、十分な知識がないまま退職金をリスクの高い商品に投資し失敗するケースも珍しくありません。さらに、退職金を元手に、老後の趣味や夢として、自分の店を開業しようとして失敗してしまうこともあります。
原因5.熟年離婚や死別による世帯収入の減少
人生の後半に熟年離婚を経験した場合、財産分与によって生活資金が減少したり、精神的な負担から働く意欲を失ったりすることがあります。
また、配偶者との死別も大きな経済的影響を及ぼします。多くの場合、配偶者の一方の年金収入がなくなることで世帯収入が大幅に減少し、残された側の生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
老後破産しやすい人の特徴
老後破産に陥りやすい人には、いくつかの共通する特徴が見られます。これらに当てはまる場合は、早期の対策が必要です。
毎月の支出を把握していない
「何にいくら使っているか分からない」という状態では、無駄な支出を削減することも、将来の資金計画を立てることもできません。漠然とした不安を抱えながら、気づけば貯蓄が底をついているという事態になりがちです。
家計の「見える化」は、老後破産を回避するための第一歩です。
将来の年金受給額を把握していない
老後の生活費の柱となる年金について、将来いくら受け取れるのかを知らない人も少なくありません。年金だけで生活できると思い込んでいると、いざ受給が始まってから「こんなはずではなかった」と焦ることになります。
実際の年金受給額と必要な生活費とのギャップを認識しておくことが重要です。
貯蓄の習慣がない
現役時代から「お金が貯まらない体質」の人は、老後も同様の傾向が続く可能性が高いといえます。収入が増えても支出も増える「収入増=支出増」のスパイラルに陥りやすく、定年時に十分な老後資金を準備できないまま老後を迎えてしまいます。
計画的な貯蓄習慣の確立は不可欠です。
住宅ローンの完済が定年後
定年後も住宅ローンの返済が残っていると、年金収入からの返済が重くのしかかります。特に、現役時代の高い収入を前提に返済計画を立てていた場合、老後の収入減に対応できなくなるリスクが高まります。
健康に不安があり、医療費がかさみがち
持病があったり、生活習慣病を抱えていたりする人は、将来的に医療費や薬代がかさむ可能性が高いです。また、健康状態が悪化すると働くことが難しくなり、収入源を失うリスクもあります。
日頃から健康維持に努めることが、経済的なリスクヘッジにもつながります。
夫婦でお金の話をしない
夫婦間の家計管理が分業制で、お互いの収入や支出、貯蓄状況を把握していないケースも危険です。どちらか一方に任せきりにしていると、パートナーの突然の病気や死、あるいは熟年離婚といった事態に直面した際に、片方が全く状況を把握できず、経済的に途方に暮れてしまうことになりかねません。
老後破産が気になるあなたへ
老後もお金の不安なく暮らすために、将来の必要資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
今すぐ始める!老後破産を回避するための8つの対策
老後破産は、事前の対策で十分に回避できます。気づいたその時から行動を始めることが大切です。
【基本編】まず取り組むべき4つの対策
まずは、「基本」として取り組みたい4つの対策を紹介します。
家計の「見える化」と固定費の見直し
まずは、毎月の収入と支出を正確に把握することから始めましょう。家計簿アプリやスプレッドシート(エクセル)などを活用し、何にいくら使っているかを可視化します。
次に固定費の見直しを行いましょう。特に携帯電話料金、保険料、サブスクリプションサービスなどの固定費は、一度見直せば継続的に節約効果が期待できます。
家計を把握することで、どこに無駄があるのかが明確になり、削減すべきポイントが見えてきます。
老後資金のシミュレーション
将来の年金受給額や、老後に必要となる生活費を具体的にシミュレーションしましょう。公的年金は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。
想定される受給額に対して、ゆとりある老後を送るためにはいくら必要かを計算し、不足分を把握することが重要です。このシミュレーション結果に基づいて、目標貯蓄額を設定し、具体的な計画を立てることで、漠然とした不安を解消し、行動に移す原動力とすることができます。
健康寿命を延ばす生活習慣
医療費や介護費は老後破産の大きな原因になり得ます。日頃から適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけ、生活習慣病の予防に努めましょう。
定期的な健康診断も欠かせません。健康寿命を延ばすことは、医療費の削減だけでなく、将来的に働く選択肢を残すことにもつながります。
定年後の働き方を計画する
定年退職後も、収入を得る手段を確保しておくことは非常に重要です。
再雇用制度の利用や再就職、フリーランスとしての活動、地域でのパートタイム勤務など、さまざまな選択肢を検討し、具体的な計画を立てましょう。生涯現役で働き続けることで、収入を確保しつつ社会とのつながりも維持できます。
【応用編】未来の安心を盤石にする3つの対策
次に「応用」として、さらに将来の不安を軽減するための対策を紹介します。
公的年金の繰下げ受給を検討する
経済的にある程度の余裕がある場合は、公的年金の繰下げ受給を検討するのも有効な手段です。年金の受給開始時期を遅らせることで、将来受け取る年金の総額を増やすことができます。
例えば、受給開始を65歳から70歳に繰り下げると、年金額は42%増額され、この増額幅は一生涯適用されます。これにより、老後の生活をより盤石にすることが可能です。
iDeCo・NISAを活用した資産形成
老後資金の準備には、税制優遇制度を活用した資産形成が有効です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)は、運用益が非課税になるなど、将来のための資産形成を強力にサポートしてくれます。早い段階から、長期・積立・分散投資を念頭に、計画的に資産を増やしていきましょう。
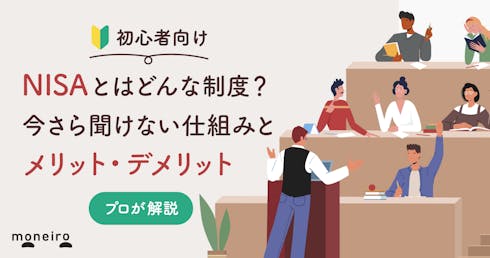

住宅ローンの繰上げ返済を検討する
住宅ローンが老後も続く場合は、繰上げ返済も検討しましょう。
特に、退職金などのまとまった資金が入った際に、繰上げ返済に充てることで、老後の返済負担を軽減できます。これにより、定年後の収入減に備え、より安定した生活基盤を築くことが可能になるでしょう。
もし老後破産しそうになったら?知っておきたい公的な相談窓口と制度
もしも経済的に厳しい状況に陥ってしまった場合でも、一人で抱え込まず、頼れる公的な相談窓口や制度があります。最終手段として知っておくべきセーフティネットも確認しましょう。
一人で悩まず専門家へ相談する
経済的な問題に直面したら、早めに専門家へ相談することが重要です。市区町村の窓口では、福祉や生活相談を受け付けています。
また、社会福祉協議会では、生活困窮者支援や資金の貸付相談に応じてくれます。さらに、「法テラス」(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない人が法的なトラブルに巻き込まれた際に、無料で法律相談を受けたり、弁護士費用等の立替制度を利用したりできる公的機関として利用できます。
もしも困難な状況になった場合は、まずはこれらに一度相談してみることをおすすめします。
最終手段としての法的整理(自己破産・個人再生)
どうにもならない状況に陥った場合の最終手段として、「自己破産」や「個人再生」といった法的整理制度があります。これらは、裁判所の手続きを経て借金を整理し、生活を立て直すための制度です。
自己破産
経済的な再スタートを切ることを目的としたもので、裁判所ですべての債務(借金)を免除してもらう手続きのことを指します。一定以上の価値ある財産は手放すことになるほか、一定期間はクレジットカードが作れなくなるといったデメリットもあります。
ただし、保証人になっていない限りは、家族に迷惑がかかることはありません。
個人再生
借金の一部を原則3~5年で分割返済することで、残りの借金を減額してもらう手続きです。特に住宅ローンがある場合に、自宅を残しながら借金を整理できる「住宅資金特別条項」の利用が可能という特徴があります。
これらの制度は、決して「逃げ」ではなく、生活再建に向けた法的に認められた手段です。手続きには専門的な知識が必要なため、必ず専門家に相談しましょう。
生活保護制度の利用も
あらゆる手段を尽くしてもなお生活に困窮する場合は、「生活保護制度」の利用も選択肢の1つです。これは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための国の制度で、資力や能力を活用してもなお生活が困難な場合に、生活費や医療費などを国が支給してくれます。
生活保護の受給には一定の条件がありますが、最後の砦として知っておくことで、いざという時の安心につながります。
まとめ
老後破産は、誰もが直面し得る深刻な問題ですが、その多くは事前の準備と対策によって回避可能です。
老後破産の具体的な原因には、収入の減少と支出のアンバランスや、医療費・介護費などの想定外の支出などが挙げられます。また、老後破産に陥りやすい人の特徴として、家計の無把握や年金受給額の無知、貯蓄習慣の欠如などが挙げられますが、これらの対策として家計の見直しや老後資金のシミュレーションを事前に行うことで老後不安を軽減することが可能です。
それでも、万が一経済的に追い詰められた場合には、一人で悩まず、法テラスなどの公的機関や専門家へ相談してみましょう。自己破産や個人再生といった法的整理制度、そして生活保護制度は、生活再建のための重要なセーフティネットです。早期の行動と適切な支援の活用が、安心できる老後を送るためのカギとなります。
老後破産が気になるあなたへ
老後もお金の不安なく暮らすために、将来の必要資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。