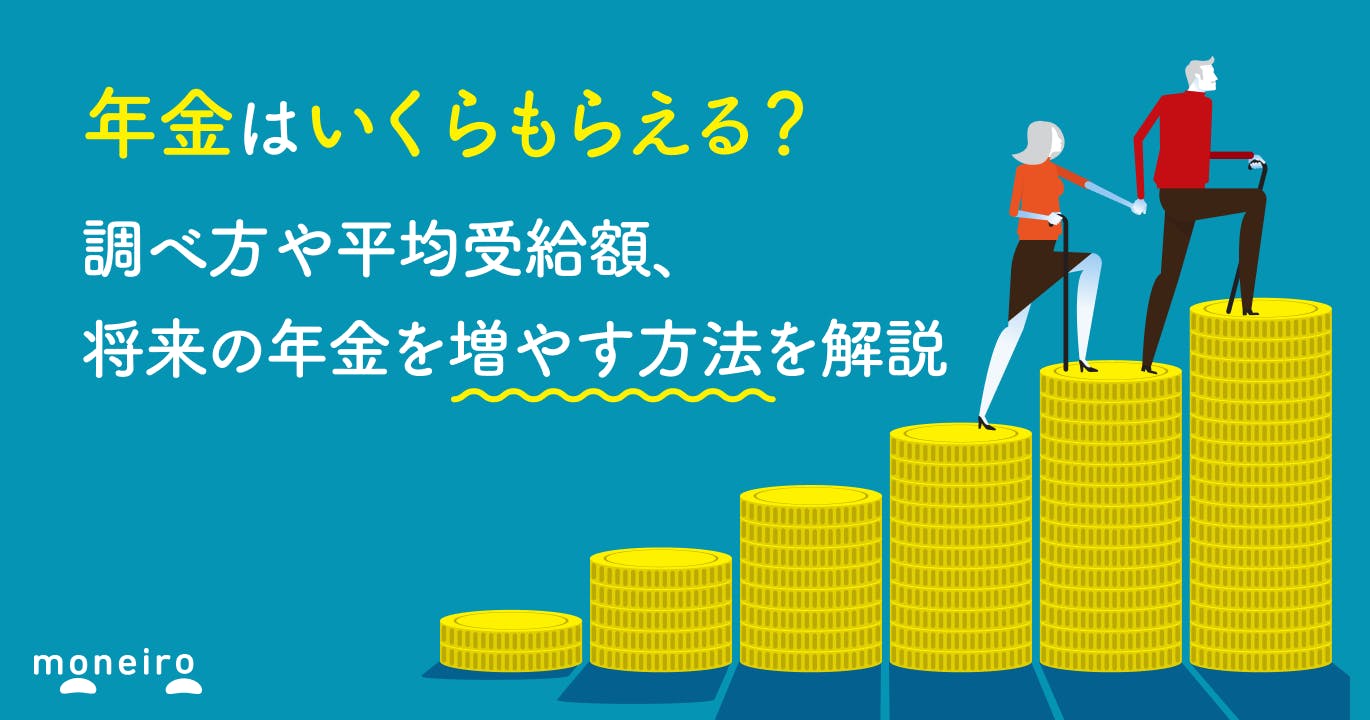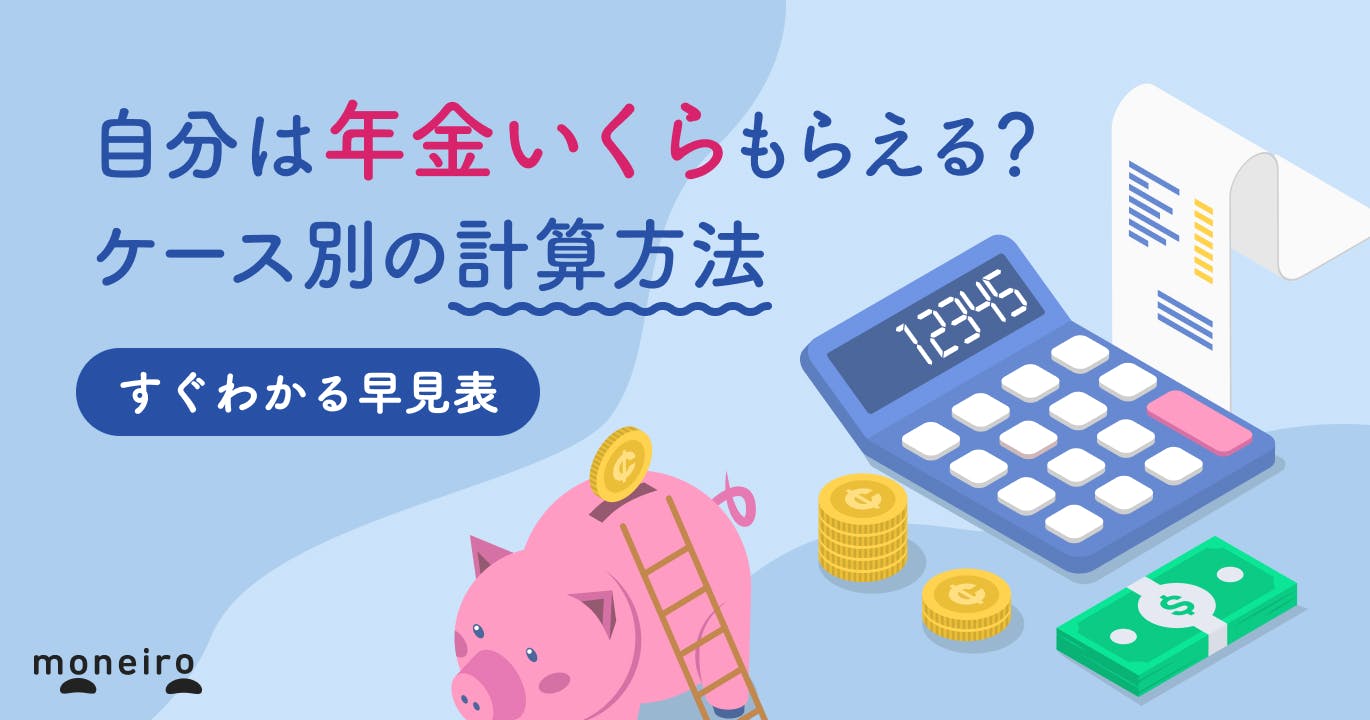年金はいくらもらえる?調べ方や平均受給額、将来の年金を増やす方法を解説
»面倒な計算は不要|受給額と老後資金を無料診断
「将来、年金をいくらもらえる?」そんな疑問や不安を抱えている方も多いかもしれません。そんな方に向けて、本記事では、将来もらえる年金額の調べ方について詳しく解説します。
また、日本人の平均的な年金受給額を紹介するとともに、将来の年金額を効果的に増やすための具体的な方法についても深掘りしていきます。
- 自身の年金受給額をスマホや郵送物で確認・試算する具体的な方法
- 日本における国民年金と厚生年金の平均受給額の現状
- 将来もらえる年金額を増やすための具体的な5つの対策
年金受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
自分の年金受給額を調べる主な方法
将来受け取れる年金額を知るためには、主に3つの方法があります。以下で詳しく紹介していきます。
ねんきんネットで確認・試算する
「ねんきんネット」は、日本年金機構が提供するオンラインサービスです。これまでの年金記録の確認や、将来の年金見込額の試算をインターネット上で行うことができます。
まずはスマホで登録
ねんきんネットの利用を開始するには、まずユーザー登録が必要です。スマートフォンから手軽に登録でき、準備物としては「アクセスキー」または「マイナンバーカード」のいずれかがあれば手続きを進められます。具体的な手順に従って登録を完了させましょう。
年金見込額を試算
ログイン後、「年金見込額試算将来の年金額を試算する」のメニューから、自分の年金見込額を確認できます。50歳未満の人と50歳以上の人では表示される情報が異なり、50歳未満の場合はこれまでの加入実績に基づく参考額が表示され、50歳以上ではより具体的な見込額が提示されます。画面の案内に従って、自分の情報を確認しましょう。
将来のプランを想定してシミュレーションしてみよう
ねんきんネットのいいところは、さまざまな条件を設定して将来の年金額をシミュレーションできる点です。
例えば、国民年金保険料の「追納(過去の未納分を支払うこと)」の有無、年金受給開始年齢を遅らせる「繰下げ受給」を選択した場合、または働き方を変えた場合など、ライフプランに応じた年金額の変化を試算し、具体的な将来設計に役立てることができます。
ねんきん定期便で確認する
「ねんきん定期便」は、日本年金機構から誕生月に毎年送付されるハガキで、これまでの年金加入記録や保険料納付額、そして将来の年金見込額が記載されています。
ねんきん定期便はいつ届く?
ねんきん定期便は、毎年誕生月に送付されます。手元にない場合や、紛失してしまった場合は、再発行の手続きも可能です。詳しくは日本年金機構のWebサイトで確認してみましょう。
【50歳未満の方】「これまでの加入実績に応じた年金額」を確認しよう
50歳未満の方に届くねんきん定期便に記載されている年金額は、「これまでの加入実績に応じた年金額」です。
これは、これまでに納付した保険料に基づいた、あくまで現時点での見込額で、将来受け取れる確定した年金額ではありません。今後の働き方や年金加入状況によって変動することを理解した上で、現在の実績を確認するポイントとして活用しましょう。
【50歳以上の方】「老齢年金の種類と見込額」で将来額がわかる
50歳以上の方のねんきん定期便には、「老齢年金の種類と見込額」が記載されており、より確定に近い将来の年金見込額が示されています。自分の受給資格期間や加入記録が反映された具体的な金額で、老後の生活設計を立てる上で重要な情報となります。
その他(ねんきんダイヤル、年金事務所窓口など)
インターネットや郵送物での確認が難しい場合や、個別の相談を希望する場合は、電話や窓口での相談も可能です。「ねんきんダイヤル」に電話をかける、またはお近くの年金事務所の窓口で直接相談することで、専門家から具体的なアドバイスを受けることができます。
年金額はどう決まる?計算方法の基本
年金額は、加入している年金の種類や加入期間、保険料の納付状況などによって計算されます。日本の公的年金制度は、主に「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっています。
国民年金の仕組みと計算
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する「基礎年金」にあたります。保険料を納めることで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの給付を受けることができます。
老齢基礎年金の年金額は、保険料納付済期間や免除期間に応じて決まり、原則として20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を納めることで、満額の基礎年金が受給できます。
国民年金の年間受給額は「満額の年金額×(保険料の納付月数÷480ヶ月)」で計算されます。令和7年度の受給額を上記に当てはめると、「83.17万円×(保険料の納付月数÷480ヶ月)」となります。
厚生年金の仕組みと計算
厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金で、国民年金(基礎年金)に上乗せされる形で給付されます。
厚生年金保険料は、給与額や賞与額に応じて決まり、事業主と被保険者が折半して負担します。厚生年金の年金額は、加入期間と加入期間中の平均標準報酬額(月々の給与や賞与)によって計算されるため、収入が高いほど将来の厚生年金額も高くなる傾向にあります。
加給年金・振替加算について
公的年金には、特定の条件を満たすことで上乗せされる加算制度があります。
「加給年金」は、厚生年金の受給権を得た人が、厚生年金に20年以上加入していて、生計を維持している65歳未満の配偶者や一定の条件を満たす子どもがいる場合に加算される年金です。
また、「振替加算」は、加給年金の対象だった配偶者が65歳に到達し、自身の老齢基礎年金の受給を開始する際に、一定の条件(生年月日・受給資格期間など)を満たしている場合に加算されるものです。
これらの制度は、自身や配偶者の年齢・加入歴によって支給の可否が異なるため、事前に日本年金機構などで確認しておくとよいでしょう。
年金受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
みんなはいくらもらっている?年金の平均受給額
実際に周りの人たちがどれくらいの年金を受給しているのかを知ることは、自身の老後生活を考える上で参考になります。厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和5年度)」を参考に平均額を見ていきましょう。
国民年金の平均月額
令和5年度の国民年金(基礎年金部分)の平均年金月額は、5万7700円です。これは、国民年金のみに加入していた人や、厚生年金加入者の基礎年金部分の平均を指します。
厚生年金の平均月額
一方の厚生年金保険(基礎年金を含む)の平均年金月額は全体で14万7360円です。この金額は、国民年金に上乗せして厚生年金を受給している方の平均額を示しています。
性別で見ると、男子は平均16万6606円、女子は平均10万7200円となっており、キャリアプランの違いによる差異が大きく出ていることが分かります。
将来もらえる年金を増やす5つの方法
自分の年金見込額を確認し、平均額を把握した上で、「もっと年金を増やしたい」と考える人もいるでしょう。ここでは、将来受け取れる年金額を増やすための具体的な方法を紹介します。
国民年金保険料の追納制度を活用する
国民年金保険料の未納や免除・猶予期間がある場合、過去の保険料を後から納める「追納制度」を利用できます。未納分は2年以内、免除・猶予期間は10年以内に追納可能で、これにより年金受給資格を確保し、将来の年金額の減額を防げます。
繰下げ受給を検討する
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、希望すれば66歳以降に受給を繰り下げる「繰下げ受給」を選択できます。
年金受給を1ヶ月遅らせるごとに受給額が0.7%増額され、最大で84%(75歳まで繰り下げた場合)増額することが可能です。
ただし、繰り下げている間は年金を受け取れない点や、受け取り開始後の健康状態などは事前に考慮に入れておく必要があります。
付加年金・国民年金基金を活用する
自営業者やフリーランスなど、国民年金のみに加入している第1号被保険者の人は、「付加年金」や「国民年金基金」といった制度を活用して、将来の年金額を上乗せする方法があります。
ただし、付加年金と国民年金基金は併用できないため、どちらか一方を選ぶ必要があります。今後のライフプランや収入状況に合わせて検討しましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、そのお金を投資信託などで運用することで、将来の年金額が決まる私的年金制度です。掛金は全額が所得控除の対象となり、さらに運用益は非課税、年金の受け取り時にも控除が適用されるなど、税制優遇が非常に大きいのが特徴です。
ただし、原則として60歳まで引き出すことができず、また運用結果によっては元本割れのリスクもあります。そのため、将来のライフプランやリスク許容度に合わせて、無理のない範囲で始めることが大切です。
60歳以降も長く厚生年金に加入して働く
60歳以降も厚生年金に加入し続けて働くことで、老齢厚生年金の受給額を増やすことができます。また、繰下げ受給と組み合わせることで、受給開始までの期間も収入を得つつ、さらにリタイア後の年金額を増やすことも可能です。
働きながら年金を受け取る場合は「在職老齢年金」が適用され、一定以上の収入があると年金が一部減額されることがありますが、長く働くことで保険料納付期間が延び、その分年金額が増加します。
まとめ
今回は、年金がいくらもらえるか調べる方法について詳しく解説しました。
具体的な確認方法として、特に便利なのが「ねんきんネット」です。年金の見込額について、さまざまな条件を設定してシミュレーションできるので、現在の状況や将来の想定も交えながら見込額を確認してみましょう。
また、将来受け取る年金額を増やすには、国民年金保険料の追納や繰下げ受給、付加年金・国民年金基金といった制度を上手に活用することが大切です。
老後の生活を安心して送るために、まずは自身の年金状況を把握した上で、必要に応じて今回紹介した各対策を講じていきましょう。
»年金額をいますぐ無料でシミュレーション
年金受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。