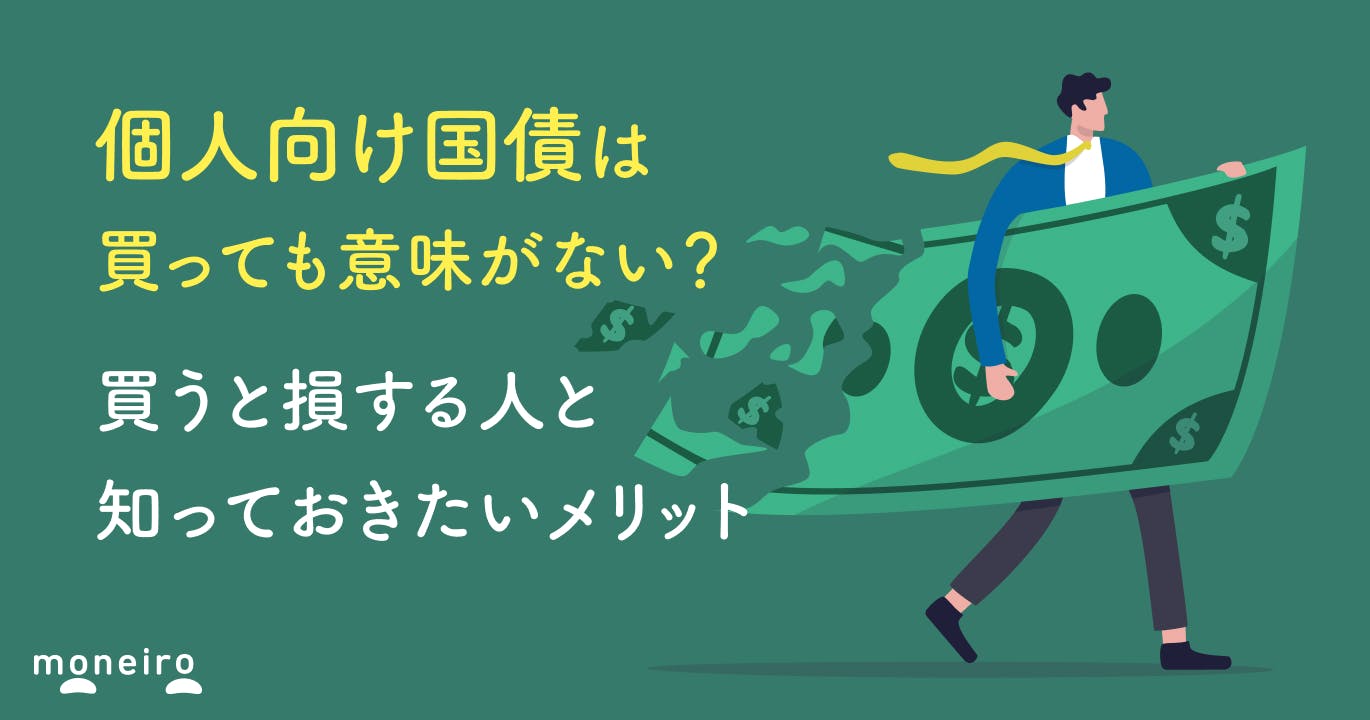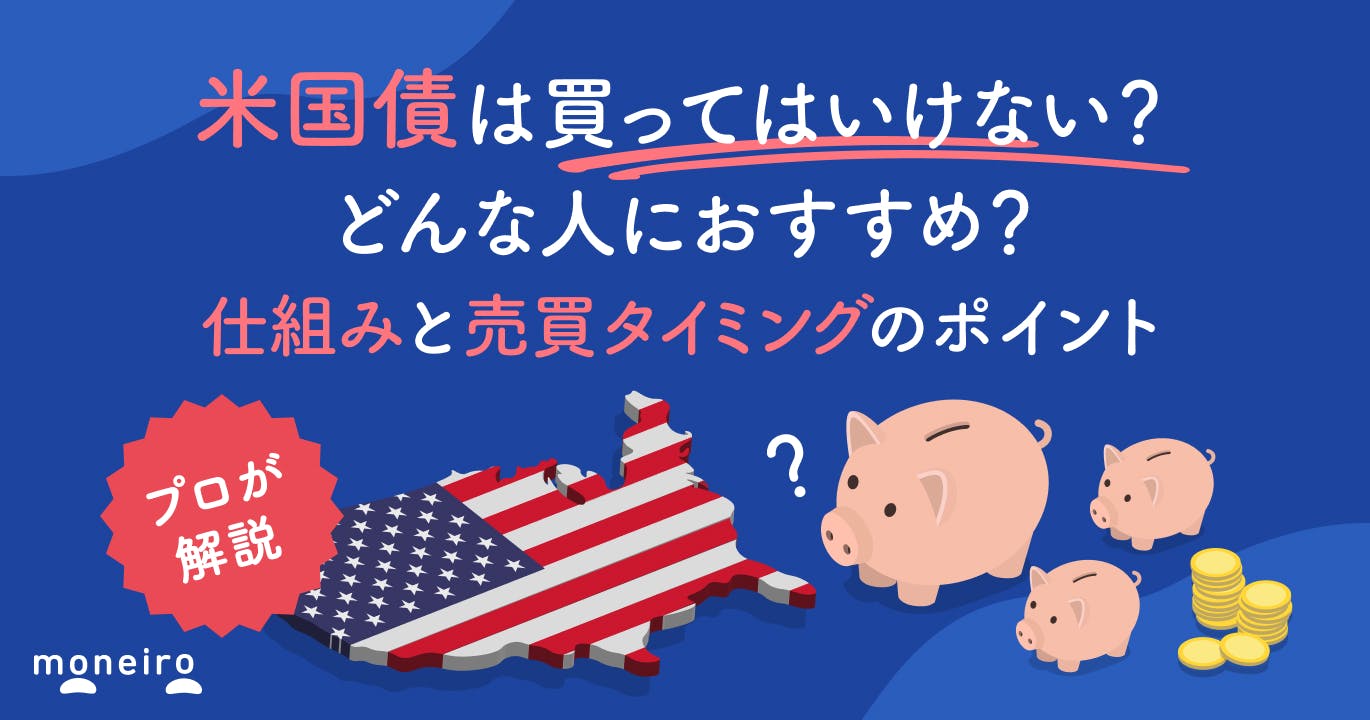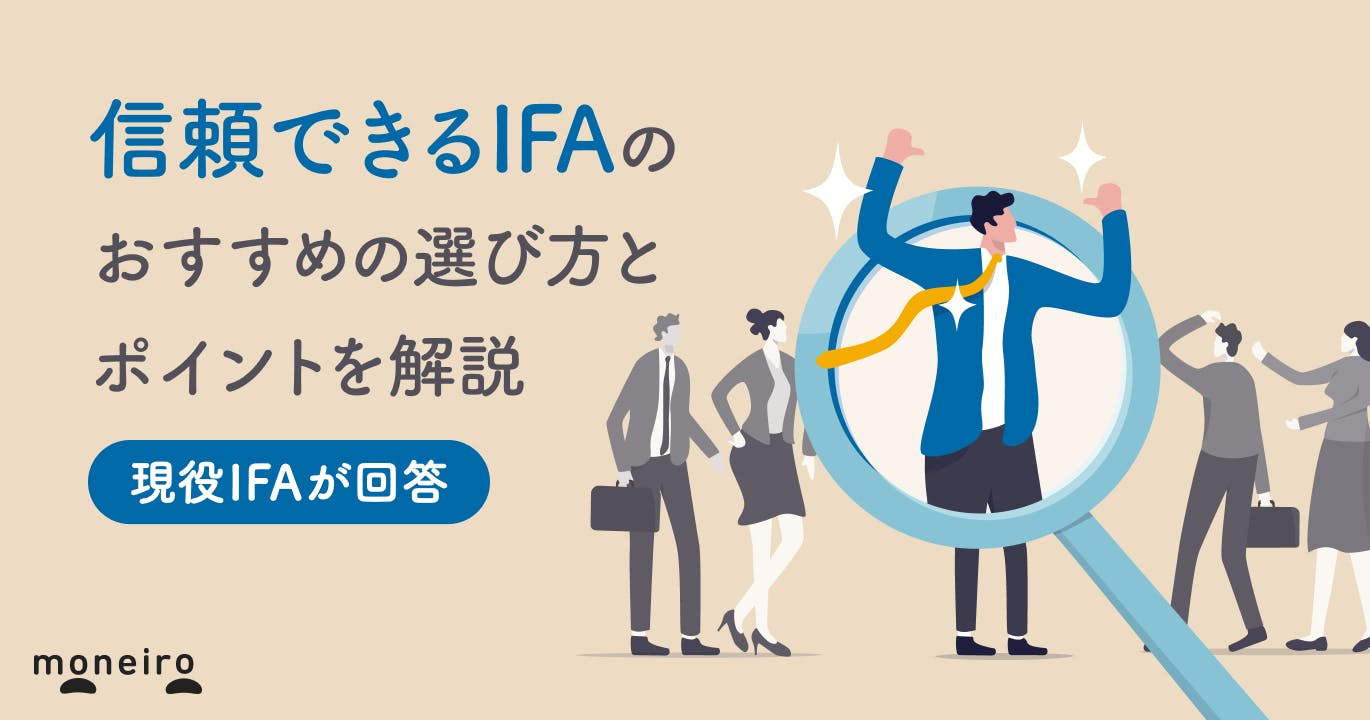社債と株式の違いは?選ぶならどっち?図でわかる違いと選び方のポイントをプロが解説
»無料:債券か株式か、投資前にプロの診断を
「社債と株式の違いは?」「企業が発行しているからどちらも特徴は同じ?」と社債と株式の特徴について詳しく知りたい人も多いのではないでしょうか。
社債とは企業が発行する債券であり、購入した投資家は定期的に利子を受け取ることができます。
一方、株式は投資家が株主となることで株価が上がった際に売却益を得ることができます。
企業が資金調達のために発行する点は共通していますが、リスクとリターンの種類が異なるため仕組みを理解して選択しましょう。
本記事では社債と株式の違いを知りたい人に向けて特徴やメリット・デメリット、活用例を投資のプロが徹底解説します。
- 社債は「社債発行による資金調達であり、企業は返済義務がある」
- 株式は「株式発行による資金調達であり、企業に返済義務はない」
- 社債は株式よりも比較的リスクが低く、リスクを抑えながら安定した収益を得たい人におすすめ
債券が気になっているあなたへ
マネイロでは、あなたに合う投資がわかる無料サービスをご用意しました。
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶500万円から始める債券投資セミナー:まとまったお金の運用方法がわかる
▶オンライン無料相談:あなたに合う銘柄をプロが診断
社債と株式とは?基本的な違い
社債と株式は、どちらも資産運用に活用される金融商品ですが、それぞれ仕組みが大きく異なります。
社債は、企業が資金調達のために発行する「借金」のようなものであり、企業には返済義務があります。購入した投資家は企業にお金を貸し、満期まで定期的に利子(クーポン)を受け取ることができます。
満期になると額面の金額が返還されるため、比較的安定した運用が可能です。ただし、企業が倒産すると額面金額が戻らないリスクがあります。
一方、株式は企業の「オーナー(株主)」になる権利を持つものです。株価が上がれば売却益(キャピタルゲイン)を得られ、企業が利益を出せば配当金や株主優待を受け取ることもできます。
しかし、業績が悪化すると株価が下がり、大きな損失を抱えるリスクもあります。
どちらも企業が市場から資金を集めるための手段ですが、リスクの度合いやリターンの種類に違いがあります。
社債の仕組みと特徴
社債は企業が発行する債券であり、証券会社を通じて購入できます。債券を購入することで、投資家は企業にお金を貸す形となり、その対価として定期的に利子を受け取ることができます。
また、社債には満期が設定されており、満期になると購入時の額面金額が返還されます。満期までの間、保有している社債からは定期的に利子(クーポン)を受け取ることができるため、安定した収益を期待できます。
参考)社債の主な種類
社債にはさまざまな種類があり、代表的なものとして以下のようなものがあります。
満期と利率が設定されており、満期までの期間中は利子が支払われる、一般的な社債
・転換社債(コンバーチブルボンド/CB)
一定の条件を満たすと、株式へ転換できる権利が付与された社債
・ワラント債(新株予約権付社債)
社債と株式購入権(ワラント)がセットになっている社債
その他にも電力会社が発行する電力債などもあります。
株式の仕組みと特徴
株式は社債と同様、企業が資金調達をするための手段の一つであり、証券会社を介して購入をすることができます。
株式は社債と比べるとリスクが高く、株式の価格(株価)によって時価が変わる特徴があります。購入した価格(取得価格)以上に株価が上昇していると利益(キャピタルゲイン)が生まれ、株価が下落をすると、損失が発生します。
その他にも、特定の株式を保有することで得られる配当や株主優待(インカムゲイン)もあります。
会社の業績や相場状況によって株価・配当・株主優待が変わるため、購入を検討している株式はしっかりと調べてから購入をすることをおすすめします。
社債と異なり、企業の所有権の一部を取得する形となるため、投資家は株主として企業の成長に応じたリターンを期待できます。
参考)株式と投資信託の違い
株式と投資信託は、投資対象としてよく比較されますが、リスクと運用方法に違いがあります。
投資信託は、複数の株式や債券などに分散投資する仕組みのため、リスクを抑えながら運用することが可能です。
投資先によって特徴が異なるため、選ぶ際にはリスクをよく理解しておくことが重要です。
一方で、株式投資は個別銘柄ごとの価格変動が大きいため、高リターンを狙える反面、リスクも大きくなります。
≫将来資金の必要額と自分に合う投資がわかる!3分投資診断
社債と株式のメリット・デメリットを比較
社債と株式のメリット・デメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。
社債のメリットとデメリット
社債のメリットは安定した定期収入(クーポン)を得られる点です。
社債の利率は発行企業の信用力によって決まり、一般的に定期預金や国債よりも高い傾向にあります。
外国債券の場合は為替変動の影響も受けますが、基本的に満期まで保有すれば額面金額が返還されるため、比較的リスクを抑えながら資産運用ができます。
一方、社債には信用リスクがあります。発行企業が倒産すると、額面金額の返済が行われない可能性があります。
特に高金利の社債は信用リスクが高い場合があるため、利率だけで判断せず、発行企業の財務状況をしっかり確認することが大切です。
株式のメリットとデメリット
株式投資の魅力の一つは、配当金を受け取れることです。企業の業績が良好であれば、定期的に配当金が支払われ、安定した収益が期待できます。また、株価が上昇した場合、キャピタルゲイン(値上がり益)を得ることができ、大きなリターンを狙うことが可能です。
一方で株式の配当金は企業業績によって左右されるため、減配・無配のリスクがあります。安定した配当を期待していた企業が業績悪化により配当を停止するケースもあるため、配当だけを目的に投資するのはリスクが伴います。
株価の変動リスクが大きいため、短期間での投資には慎重な判断が必要です。
社債と株式、どっちを選ぶ?
社債と株式は、それぞれ異なる特徴を持っているため、自分のリスク許容度と投資目的に応じて選択することが重要です。
- リスクを抑えながら安定した収益を得たい人 → 社債
- リスクを取って大きなリターンを狙いたい人 → 株式
また、投資の目的によっても選択は異なります。
- 教育資金や住宅購入資金など、元本の安全性を重視する場合 → 社債
- 老後資金や資産の長期成長を目指す場合 → 株式
投資判断は年齢・投資金額・ライフプランなどを総合的に考慮して行いましょう。
債券と株式を組み合わせてバランスよく活用する
債券と株式はそれぞれの特徴を活かして組み合わせることで、リスクを抑えながら効率的な運用を行うことができます。
株式はハイリスク・ハイリターン、債券はローリスク・ローリターンという特性を持っているため、適切に組み合わせることで、リスクを分散しながら安定したリターンを目指すことが可能です。
例えば、景気が良い時は株式のリターンが高くなる傾向がありますが、景気が悪化すると債券の安定性が際立ちます。
このように、経済状況に応じて補完し合う関係にあるため、バランスの取れたポートフォリオを構築することが重要です。
投資を検討する際は社債と株式の特徴を理解し、自分のリスク許容度や目的に合った投資戦略を考えていきましょう。
債券と株式を組み合わせた資産運用事例
債券と株式を組み合わせることで、リスクを抑えたバランスの良い運用が可能です。
ケース別に資産運用の事例について見ていきましょう。
例:30代〜40代、資産を増やしたいがリスクは抑えたい
30代〜40代は、資産運用を始めるのに適した年代です。老後まで20年以上の運用期間があるため、長期的な資産形成を目指すことができます。
リスクを抑えながら資産を増やしたい場合は、株式型投資信託を活用すると良いでしょう。個別株に比べてリスクが分散され、長期投資をすることで価格変動のリスクを軽減できます。
また、まとまった資金がある場合は、債券と株式型投資信託を組み合わせることで、リスクを分散しながら安定的に資産を増やすことができます。
ただし、株式型投資信託はあくまで株式を主要な投資対象とするため、市場の影響を受ける点には注意が必要です。運用方針を明確にしながら、長期的な視点で取り組みましょう。
例:定年後に安定収入を得たい
定年後は資産を増やすよりも、安定した収入を確保することが重要になります。特に、65歳以降は収入源が限られるため、運用のリスクを抑える必要があります。
安定収入を得るためには、債券の割合を増やすのが有効です。債券は満期まで保有すれば額面金額が戻る特性があり、安定した定期収入(クーポン)を得られるため、リスクを抑えながら運用できます。
一方、株式は値動きが大きいため、定年後の運用では資産が大幅に減少するリスクも考慮しなければなりません。
現役世代であれば、株式運用で一時的に資産が減少しても働いて補填できますが、定年後は収入源が限られるため、安全性を重視した資産運用を心がけることが大切です。
社債と株式の購入方法
社債と株式は証券会社を通じて購入できますが、取引を行うには証券口座の開設が必要です。
株式はほとんどの証券会社で購入できます。ネット証券や店舗型(対面型)証券会社など、自分の取引スタイルに合った証券会社を選びましょう。
一方、社債の取り扱いは証券会社によって異なります。特に社債は、ネット証券では取り扱いが限定的で、情報が開示されていないケースも多くあります。
また、社債は店舗型(対面型)証券会社でしか購入できないものもあり、担当者と相談しなければ案内されないこともあります。
社債の購入を検討する場合は、担当者がつく証券会社で口座を開設するとスムーズに取引が進められます。証券会社ごとの取り扱い商品を確認し、自分に合った方法で投資を始めましょう。
金融商品選びに悩んだらプロに相談
投資を始めようと思っても、「どの金融商品を選べば良いかわからない」「自分に合った資産運用の方法が知りたい」と悩む方は多いでしょう。
金融商品には、株式、債券、投資信託、ETFなどさまざまな種類があり、それぞれリスクやリターンの特徴が異なります。
適切な商品を選ぶためには、投資目的やリスク許容度、運用期間を考慮することが重要ですが、自分だけで判断するのが難しい場合は、プロに相談するのがおすすめです。
特に、初めて投資をする場合や、運用方針の見直しを考えている場合は、プロのアドバイスを活用しながら、自分に最適な金融商品を選びましょう。
マネイロは運用後も無料でサポート
マネイロでは、投資を始める前の相談だけでなく、運用開始後も無料でサポートを受けられます。
金融商品の選び方や資産運用の進め方に悩んだ時も、継続的に相談できるため、安心して投資を続けることができます。
① 相談すると専任の担当者がつく
マネイロに相談すると、一人ひとりに専任の担当者(IFA)がつき、投資の目的やリスク許容度に合わせたアドバイスを受けることができます。
ネット証券では担当者がつかないことが多いですが、マネイロでは口座開設から商品選び、運用後のフォローまで一貫してサポートを提供します。
② 幅広い社債商品から選択できる
社債の中にはまとまった資金がないと購入できないものもありますが、マネイロはSBI証券と提携しているため、取り扱い商品の選択肢が豊富です。
比較的少額から購入できる社債もあり、資産運用の幅を広げることが可能です。
投資を始めた後も、不安や疑問があれば何度でも相談できるため、長期的に安心して資産運用を続けたい方におすすめのサービスです。
まとめ
社債と株式はどちらも金融商品ですが、それぞれ仕組みや特徴が異なります。資産運用を行う際は、老後資金・教育資金・結婚費用など、目的に応じて適切な金融商品を選ぶことが重要です。
例えば、教育資金を目的とした投資には、株式での運用はリスクが高すぎるため注意が必要です。教育資金は子どもの成長に合わせて必ず必要になる資金であり、株式のように価格変動が大きい商品で運用すると、大きな損失を抱える可能性があります。
このように、まずは投資の目的を明確にし、それに適した金融商品を選ぶことが大切です。
どの商品を選べば良いかわからない場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。適切なアドバイスを受けながら、自分の目的に合った資産運用を進めていきましょう。
»無料:専門家へのオンライン相談はこちら
債券が気になっているあなたへ
マネイロでは、あなたに合う投資がわかる無料サービスをご用意しました。
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶500万円から始める債券投資セミナー:まとまったお金の運用方法がわかる
▶オンライン無料相談:あなたに合う銘柄をプロが診断
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
長井 祐人
- ファイナンシャルアドバイザー
日本大学国際関係学部卒業後、東洋証券株式会社に入社。国内外株式、債券、投資信託、保険商品の販売を通じ、主に個人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。特に中国株・投資信託の提案を得意とし、自身でも幅広く投資を行ってきたため、豊富な金融知識を活かした顧客ニーズに沿う提案が強み。現在は個人向け資産運用のサポート業務を行う。3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有