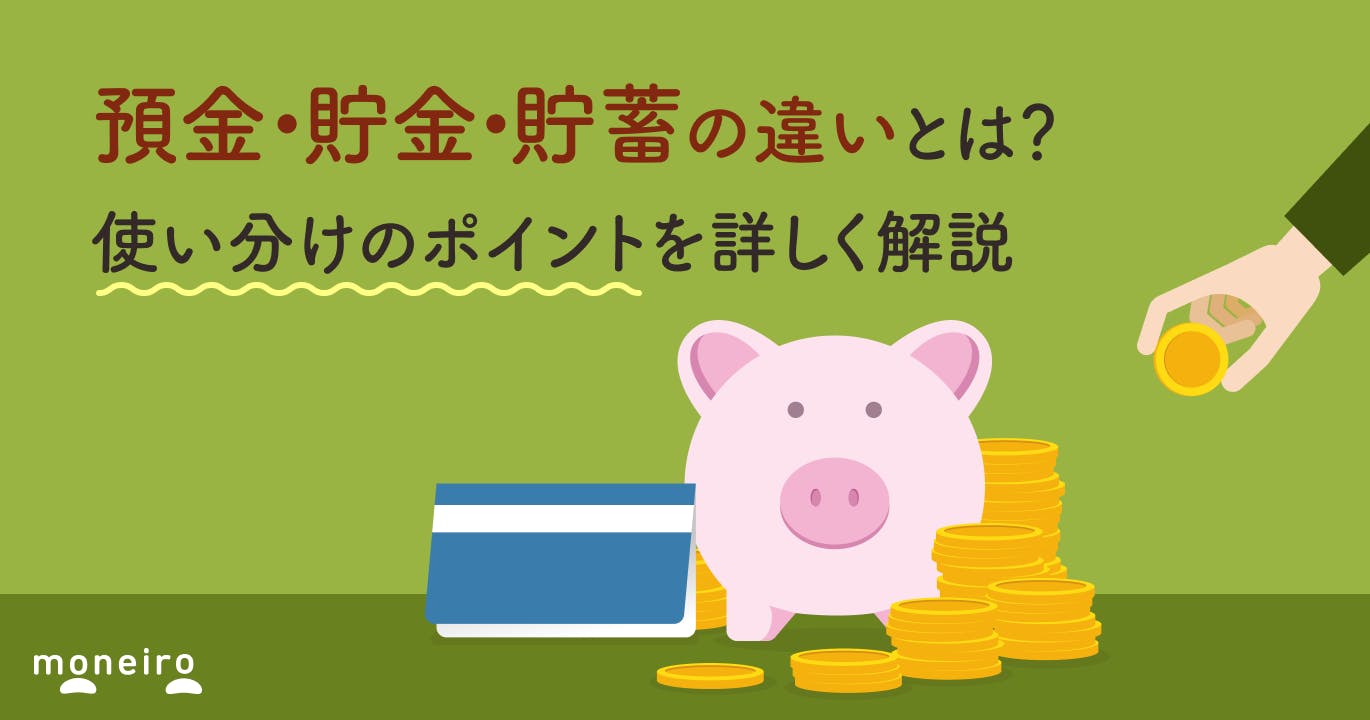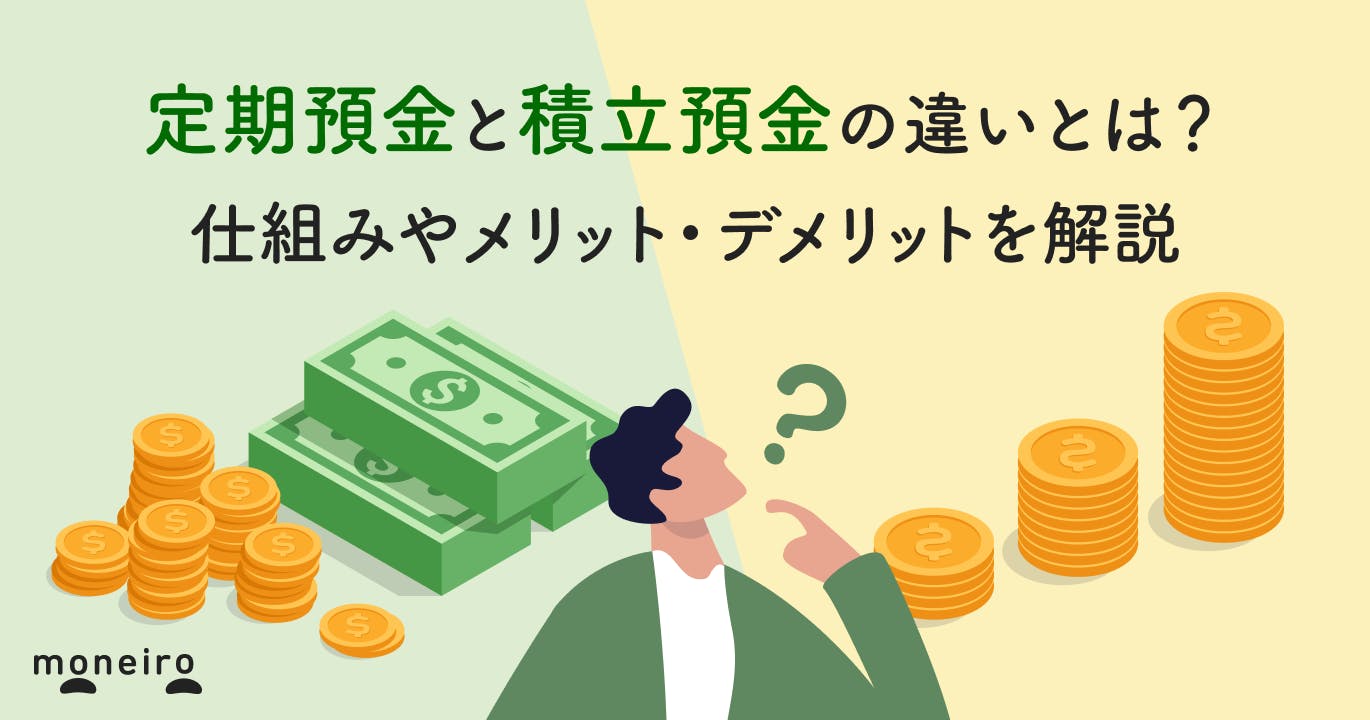預金・貯金・貯蓄の違いとは?使い分けのポイントを詳しく解説
【無料】あなたの将来に必要なお金はいくら?3分で診断
「預金」と「貯金」の明確な違いをご存知ですか? 私たちの日常生活でよく耳にするこれらの言葉ですが、実は明確な区別があります。この記事では、お金を預ける金融機関による違いから、歴史的背景、さらに「貯蓄」との関係までを分かりやすく解説します。
- 「預金」「貯金」「貯蓄」それぞれの言葉が持つ意味と違い
- お金を預ける金融機関によって言葉が使い分けられる理由
- あなたの目的に合わせた、賢いお金の貯め方や管理方法
将来に向けた貯蓄が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
預金・貯金・貯蓄とは?
まずは、「預金」「貯金」「貯蓄」、それぞれの意味するものについて解説します。
預金とは?
「預金」とは、主に銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫といった民間の金融機関にお金を預けることを指します。
これらの金融機関は、預かったお金を企業への融資や投資に活用し、経済活動を円滑にする役割を担っています。
預金は、私たちの財産を守りつつ、利息を得ることもできる、身近な金融商品です。
貯金とは?
「貯金」という言葉には、大きく2つの意味があります。
お金を貯めること全般
1つは、広義に「お金を貯める行為やその結果」を指す場合です。例えば、「貯金をする」「貯金箱」といった日常会話で使われる際の「貯金」は、方法を問わず、お金を蓄える行為そのものを意味します。この意味合いでは、「預金」や「貯蓄」とほぼ同義で使われることも多く、もっとも口語的な言葉といえるでしょう。
ゆうちょ銀行などの金融商品
もう1つは、特定の金融機関である「ゆうちょ銀行」や、JAバンク(農業協同組合)、JFマリンバンク(漁業協同組合)などにお金を預ける際に使われる言葉です。
これらの機関は、その設立経緯や目的から、銀行とは異なる独自の呼称を用いています。特にゆうちょ銀行は、郵政民営化以前の郵便貯金の歴史を受け継いでおり、預金とは区別して「貯金」という言葉を使っています。
貯蓄とは?
「貯蓄」とは、「預金」や「貯金」を含む、お金を貯めておく行為や、その結果として蓄えられたお金全般を指す、もっとも広い意味を持つ言葉です。
現金や預貯金だけでなく、株式、債券、投資信託、生命保険、個人年金など、将来のために資産を形成する、さまざまな金融商品や財産を含みます。つまり、「預金」や「貯金」は「貯蓄」という大きな枠組みの中の一部であるといえるでしょう。
日常会話での使い分けは?
一般的な日常会話においては、「預金」「貯金」「貯蓄」どの言葉を使っても、話の文脈で意味が通じることがほとんどです。特に「貯金」がもっとも万能で口語的な言葉といえます。
例えば、銀行にお金を預けている場合に「銀行に貯金している」と表現しても違和感を覚える人は少ないはずです。ただし、ビジネスの場や金融機関とのやり取りでは、正確な用語を用いることが重要になります。
預金と貯金のサービスの違い
預金と貯金は、それぞれ異なる金融商品です。代表的なものについて、サービス内容の違いを解説します。
銀行などで扱う「預金」の主な種類
銀行などで扱われる「預金」には、いくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
普通預金
「普通預金」は、もっとも一般的で、日常生活でよく利用される預金の種類です。給与の振込口座や公共料金、クレジットカードの引き落とし口座として利用されることが多く、預け入れや引き出しがいつでも自由にできる利便性が特徴です。金利は低い傾向にありますが、ATMやインターネットバンキングを通じて手軽に資金を管理できます。
定期預金
「定期預金」は、預け入れる期間(例えば3ヶ月、6ヶ月、1年、3年など)をあらかじめ決め、原則としてその期間中は引き出さないことを前提とした預金です。
普通預金に比べて金利が高く設定されることが多く、まとまった資金を一定期間、確実に増やしたい場合に適しています。
満期前でも引き出しは可能ですが、通常は途中解約の手数料が発生したり、当初の金利が適用されなかったりする場合があります。
当座預金
「当座預金」は、主に企業や個人事業主が利用する預金で、小切手や手形の発行に用いられます。預金に利息が付かないことが大きな特徴です。決済手段としての機能が重視されており、日常的な資金の管理というよりは、事業取引における支払いをスムーズに行うための口座として利用されます。
ゆうちょ銀行などで扱う「貯金」の主な種類
ゆうちょ銀行などで扱われる「貯金」にも、預金と同様にいくつかの種類があります。
通常貯金
ゆうちょ銀行の「通常貯金」は、民間の銀行における「普通預金」に相当します。預け入れや引き出しがいつでも自由にでき、給与の受け取りや公共料金の支払いにも利用できます。全国各地にある郵便局やゆうちょ銀行のATMで利用できるため、利便性が高いことが特徴です。
定額貯金
ゆうちょ銀行独自の「定額貯金」は、民間の銀行の定期預金に似ていますが、特徴的な金利システムを持っています。
預入期間は6ヶ月以上10年までで、預け入れから3年までは半年ごとに金利が段階的に上昇する「段階金利」が適用されます。また、預け入れから6ヶ月が経過すれば、いつでも払い出しが可能です。
ただし、払い出しは口数単位となり、1口の預入金額を分割して払い戻すことはできません。金利はその時点のものが適用されるため、比較的柔軟な資金運用が可能です。
定期貯金
ゆうちょ銀行の「定期貯金」は、民間の銀行の定期預金とほぼ同じ特性を持ちます。預け入れ期間と金額を事前に決め、原則として満期まで引き出しを行わないことを前提とした貯金です。定額貯金と異なり、一度決められた金利が満期まで適用されます。
預金と貯金の元本保証制度
「預金」と「貯金」では、それぞれの制度によって元本が保護されています。
預金保険制度
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などに預けた預金は、預金保険制度の対象となります。万が一、金融機関が破綻した場合でも、預金者1人あたり、1金融機関ごとに、元本1000万円までとその利息が保護されます。
なお、当座預金や無利息の普通預金などの「決済用預金」については、全額が保護されます。
貯金保険制度
貯金保険制度は、農水産業協同組合貯金保険機構が運営する制度です。JAバンク(農業協同組合)やJFマリンバンク(漁業協同組合)などに預けた貯金は、「貯金保険制度」によって保護されます。
この制度は、銀行などの「預金保険制度」とよく似た仕組みで、万が一金融機関が破綻しても、1人あたり元本1000万円とその利息までが保護対象となります(決済用貯金は全額保護)。
「貯金」と名がついていますが、ゆうちょ銀行の「貯金」は、貯金保険制度ではなく、預金保険制度によって保護されます。
将来に向けた貯蓄が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
預金と貯金どっちがいい?目的別・使い分け術
実際のところ、預金と貯金ではどちらを利用するのがよいのでしょうか。目的別の使い分けについて解説します。
普段の生活費の管理なら「預金」が便利
日常的な資金管理や決済においては、民間の銀行の「預金」が非常に便利です。
給与の振込口座や、電気・ガス・水道などの公共料金の引き落とし、クレジットカードの決済など、生活に密着したさまざまな金融サービスが充実しています。
ATMの設置台数やインターネットバンキングの機能も豊富で、日常使いのメイン口座として高い利便性があります。
コツコツ着実に貯めるなら「貯金」も選択肢に
一方で、コツコツと着実に貯蓄を進めたい場合には、ゆうちょ銀行の「貯金」も有効な選択肢となります。
ゆうちょ銀行は全国どこにでも店舗やATMがある安心感があり、特に「定額貯金」は、預け入れ期間が長くなるにつれて金利が上がる特徴があるため、長期的な視点で資産を増やしたい場合に有利です。
また、預入から3年まで半期ごとに金利が見直される柔軟性も魅力で、計画的な貯蓄に適しています。
まとめ
「預金」と「貯金」、そして「貯蓄」は、それぞれ異なる意味合いを持つ言葉ですが、その違いを理解することで、より賢明な資金管理と資産形成が可能になります。
民間の金融機関へ預ける「預金」は、日々の生活費の管理や決済に優れた利便性を提供し、ゆうちょ銀行などの「貯金」は、全国的な安心感や独自の金利システムで、着実な貯蓄に適しています。
いずれの金融商品も、ご自身のライフスタイルや貯蓄の目的に合わせて選択することが重要です。今回の記事で解説したそれぞれの特徴を踏まえて最適な選択肢を見つけ、将来に向けた資産を効果的に増やしていきましょう。
将来に向けた貯蓄が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。