.png?w=1370&h=727&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
正直みんな貯金はどのくらいある?年代別・年収別に平均額・中央値を解説
≫今の貯金で足りる?将来の必要額を3分で診断
「正直なところ、みんな貯金はどれくらいあるんだろう?」と思ったことはありませんか?この記事では、最新の調査データに基づき、年代別や年収別に見た貯蓄の平均額と中央値を、単身世帯と二人以上世帯に分けて詳しく解説します。
貯金ゼロの世帯の割合や、貯金が苦手な方でも無理なく始められる貯金のコツも紹介しますので、ぜひ、これからの貯蓄計画の参考にしてみてください。
※本記事では「貯金額=預貯金額」「金融資産保有額=貯蓄額」と表記しています
※貯蓄額は預貯金以外に保険や有価証券なども含んだ金額としています
- 単身世帯と二人以上世帯における年代別・年収別の貯蓄状況
- 貯金が苦手な人が陥りがちな共通点
- 今日から実践できる貯蓄効率化のステップ
自分や周りの貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
正直みんな貯金はどのくらいある?~単身世帯編~
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024)」のデータをもとに、まずは単身世帯の貯蓄状況を年代別に見ていきましょう。
【年代別】貯金ゼロ世帯はどれくらい?
単身世帯全体では、金融資産を「保有していない」と回答した世帯は32.8%となっています。つまり、日本の約3分の1の単身世帯は金融資産を保有していない(≒貯金がない)ということになります。
また、年代別の貯金ゼロ世帯の割合は以下の通りです。
もっとも金融資産ゼロの割合が高いのは50歳代で40.2%となっています。これは他の年代と比較して顕著に高い傾向が見られます。一方、60歳代と70歳代では金融資産ゼロの割合が20歳代や30歳代よりも低く、それぞれ27.7%、27.0%となっています。
【年代別】平均貯蓄額と中央値
金融資産を持っている世帯の全世代の平均貯蓄額は1497万円、中央値は500万円となっています。ただし、年代別に見るとそれぞれで大きく異なることがわかります。
平均貯蓄額や中央値は、年代が上がるにつれて着実に増加していく傾向が見て取れます。これは、キャリアの進展や退職に向けた準備が貯蓄額に反映されている可能性が考えられます。
60歳代と70歳代では、平均貯蓄額が2000万円を超え、中央値も1000万円近くに達しています。
【世帯年収別】平均貯蓄額と中央値
単身世帯の金融資産保有額は、年収によっても大きく変動します。以下は、年収別の平均貯蓄額と中央値です。
年収が高くなるにつれて、平均貯蓄額、中央値ともに増加する傾向が明確です。特に、年収500万円を超えると平均貯蓄額は2000万円台を大きく超え、中央値も1000万円を超えてきます。
また、収入なし世帯で平均値が1000万円を超えており、300万円未満世帯よりも高い数値となっているのも特徴的です。
収入なし世帯の保有資産額の内訳を見ると、3000万円以上世帯が11.4%を占めており、すでに経済的自由を手にした一部の資産家層が平均値を押し上げている可能性が考えられます。
≫今の貯金で足りる?将来の必要額を3分で診断
正直みんな貯金はどのくらいある?~2人以上世帯編~
次に、2人以上世帯の貯蓄状況を見ていきましょう。
【年代別】貯金ゼロ世帯はどれくらい?
2人以上世帯全体では、金融資産を「保有していない」と回答した世帯は24.0%となっています。これは単身世帯の32.8%と比較すると低い割合です。2人以上世帯のほうが一定の金融資産を保有していることがわかります。
年代別に見ると、貯金ゼロの世帯の割合は以下の通りです。
単身世帯と同様、50歳代がもっとも貯金ゼロの割合が高く29.2%となっていますが、他の年代との差は比較的小さめです。60歳代と70歳代は単身世帯と同様、他の年代に比べて金融資産ゼロの割合が低めとなっています。
【年代別】平均貯蓄額と中央値
2人以上世帯の金融資産保有世帯の全年代・平均貯蓄額は1833万円、中央値は780万円です。
これは、単身世帯の平均1497万円、中央値500万円と比較してやや高い水準です。ただし、やはり年代によってその金額には大きな違いがあります。
単身世帯と同様、年代が上がるにつれて平均貯蓄額と中央値が着実に増加する傾向が見られます。
特に60歳代、70歳代では平均貯蓄額が2000万円を超えているほか、中央値も1000万円台に達しており、高齢期に向けて資産形成を進めている世帯が多いことが分かります。
【世帯年収別】平均貯蓄額と中央値
次に、2人以上世帯の世帯年収別の金融資産保有額を見ていきましょう。
こちらも、年収が高い世帯ほど、平均貯蓄額および中央値が高くなる傾向が顕著です。世帯年収1200万円以上の世帯では、平均貯蓄額が4459万円、中央値が1900万円と、非常に高い水準となります。
これは、高い収入が資産形成を加速させる重要な要因であることを示唆しているといえます。
自分や周りの貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
貯金ができない人が陥りがちな3つの共通点
貯金はしたいと思っているけれどなかなか貯まらない人には、共通するいくつかの特徴が見られます。これらの点を自覚し改善を心がけることで、貯金体質への転換も十分可能です。
収入と支出を把握していない
貯金ができない人には、毎月の収入がいくらで、何にいくら使っているのかを正確に把握できていない人は少なくありません。
特に毎月金額が変わる支出の内容をしっかり把握していないと、何を削れるのかがわからず、貯金に向けた対策を進めることができません。
余ったら貯金をしようと考えている
「1ヶ月過ごしてみて、余った分を貯金しよう」と考えていると、なかなか貯蓄は増えません。
多くの場合、収入が入るとすぐにさまざまな支出に充ててしまい、結局貯金に回す分が残らないという状況に陥りがちです。この考え方では、誘惑に負けてしまい、貯蓄が後回しになってしまいます。
何のために貯めるか、目的・目標がない
貯蓄の目的が明確でないと、モチベーションを維持することが難しくなります。「なんとなく貯金」では、途中で挫折してしまう可能性が高いでしょう。
例えば、「来年の夏に旅行するために〇〇万円貯める」「子どもの中学受験のために3年で〇〇万円貯める」といった具体的な目標を設定することで、貯蓄への意欲が高まります。
【今日からできる】貯金を効率化する4ステップ
貯金が苦手な方でも、今日から実践できる効率的な貯蓄方法があります。以下の4つのステップを参考に、貯蓄を習慣化していきましょう。
ステップ1.毎月の支出を把握する
まずは、自分の家計の現状を正確に把握することから始めます。家計簿アプリやクレジットカードの明細、銀行口座の入出金履歴などを確認し、毎月何にどれくらいの費用がかかっているのかを洗い出しましょう。
何にいくら使っているかを知ることは、効率的な貯金の第一歩といえます。
ステップ2.「先取り貯金」を仕組み化する
収入が入ったら、まず貯蓄分を別の口座に移す「先取り貯金」を習慣にしましょう。給料日に自動で貯蓄用口座に振り替える設定をしておけば、貯蓄し忘れる心配がありません。
これにより、「余ったら貯金」から「先に貯金」へと意識が変わり、着実に貯蓄を増やすことができます。
ステップ3.固定費を見直す
一度見直すだけで継続的な節約効果が期待できる固定費の削減は、貯蓄効率を高めるうえで非常に有効です。例えば、携帯電話の料金プラン、インターネット回線、保険料、サブスクリプションサービスなど、毎月自動的に支払っている項目に無駄がないかを確認しましょう。
これらの固定費は、一度見直せばその後はほとんど手間がかからず、長期的に貯蓄に回せる金額を増やせるという大きなメリットがあります。
ステップ4.毎月の成果を可視化する
貯蓄の進捗状況を定期的に確認し、可視化することも重要です。貯蓄額が少しずつでも増えていくのを実感することで、モチベーションを維持しやすくなります。
目標達成までの道のりや、あとどのくらい貯める必要があるのかを明確にすることで、継続的な努力につながります。
貯金に関するよくある質問
最後に、貯金に関するよくある質問に回答していきます。
Q. 貯金1000万円以上ある世帯の割合は?
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024)」によると、1000万円以上の金融資産を保有している世帯の割合は以下のとおりです。
※金融資産なし世帯を含めた上で、各年齢層の「1,000万円~1500万円未満」「1500万円~2000万円未満」「2000万円~3000万円未満」「3000万円以上」を合計した割合を算出。
※小数点第二位を四捨五入
【単身世帯における1000万円以上の金融資産保有割合】
【2人以上世帯における1000万円以上の金融資産保有割合】
なお、全年代の平均で見ると、単身世帯の21.5%に対し、2人以上世帯では31.9%が1000万円以上の金融資産を保有しているというデータが出ています。
Q. 貯金がいくらあれば「富裕層」といえる?
野村総合研究所(NRI)の推計によると、世帯として保有する金融資産の合計額から負債を差し引いた「純金融資産保有額」をもとに、以下のように「富裕層」が定義されています。
超富裕層:純金融資産保有額が5億円以上の世帯
なお、野村総合研究所が発表した2023年時点のデータでは、富裕層が153.5万世帯、超富裕層が11.8万世帯存在し、両者を合わせると165.3万世帯に上ると推計されています。
まとめ
本記事では、単身世帯と2人以上世帯それぞれの金融資産保有状況を、年代別・年収別のデータで詳しく見てきました。もしかすると「思っていたよりもみんな貯金している」と感じた人もいるかもしれません。
ただし、各年代で貯金がない世帯も一定数いることや、平均値が一部の資産保有層によって大きく引き上げられてしまう可能性がある点は考慮する必要があるでしょう。
とはいえ、「100年時代」ともいわれる長い人生においては、少しでも多く貯金をしておくに越したことはありません。
なかなか貯金ができないという人は、まずは「収入と支出の把握不足」「余ったら貯金という考え方」「目的・目標の欠如」の改善を試みましょう。そして、今回紹介した貯金体質になるための4ステップを実践してみるとよいでしょう。
»今の貯金で老後は安心?3分でわかる無料診断はこちら
自分や周りの貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
.png?w=1370&h=727&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
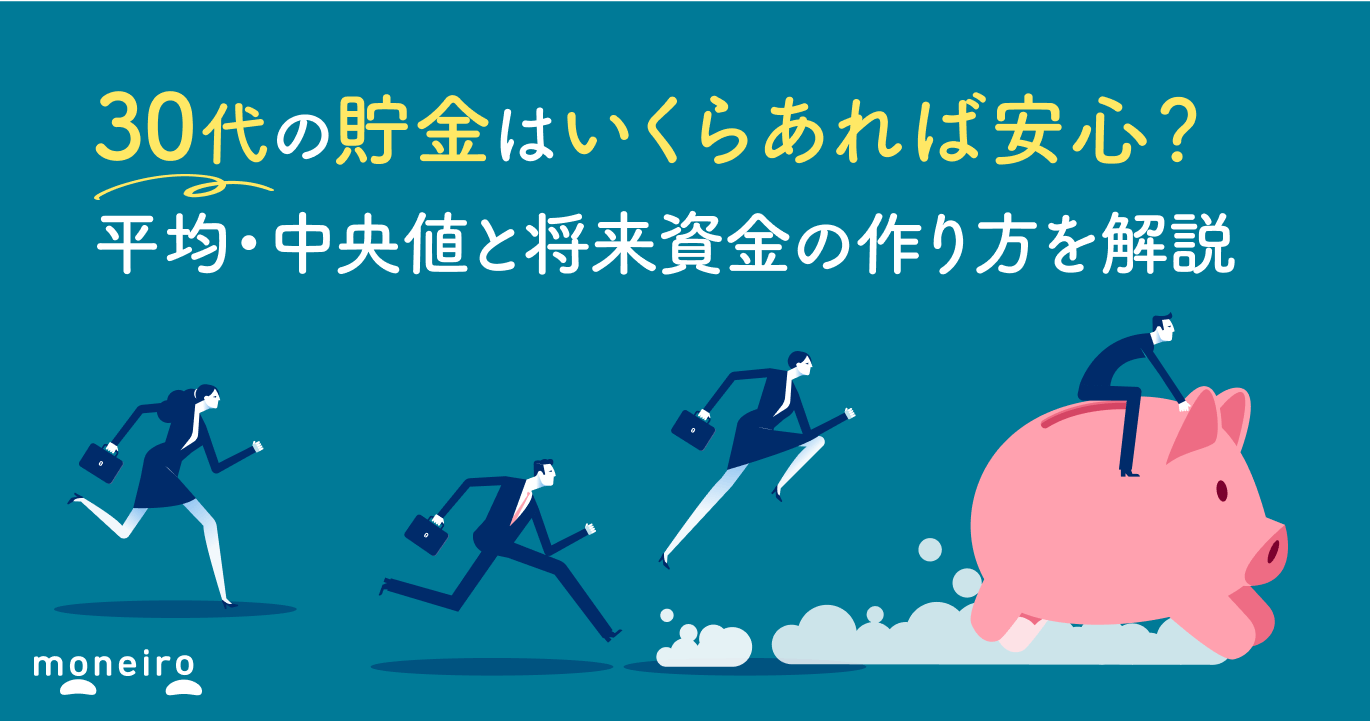
30代の貯金はいくらあれば安心?平均額・中央値と将来資金の作り方を解説
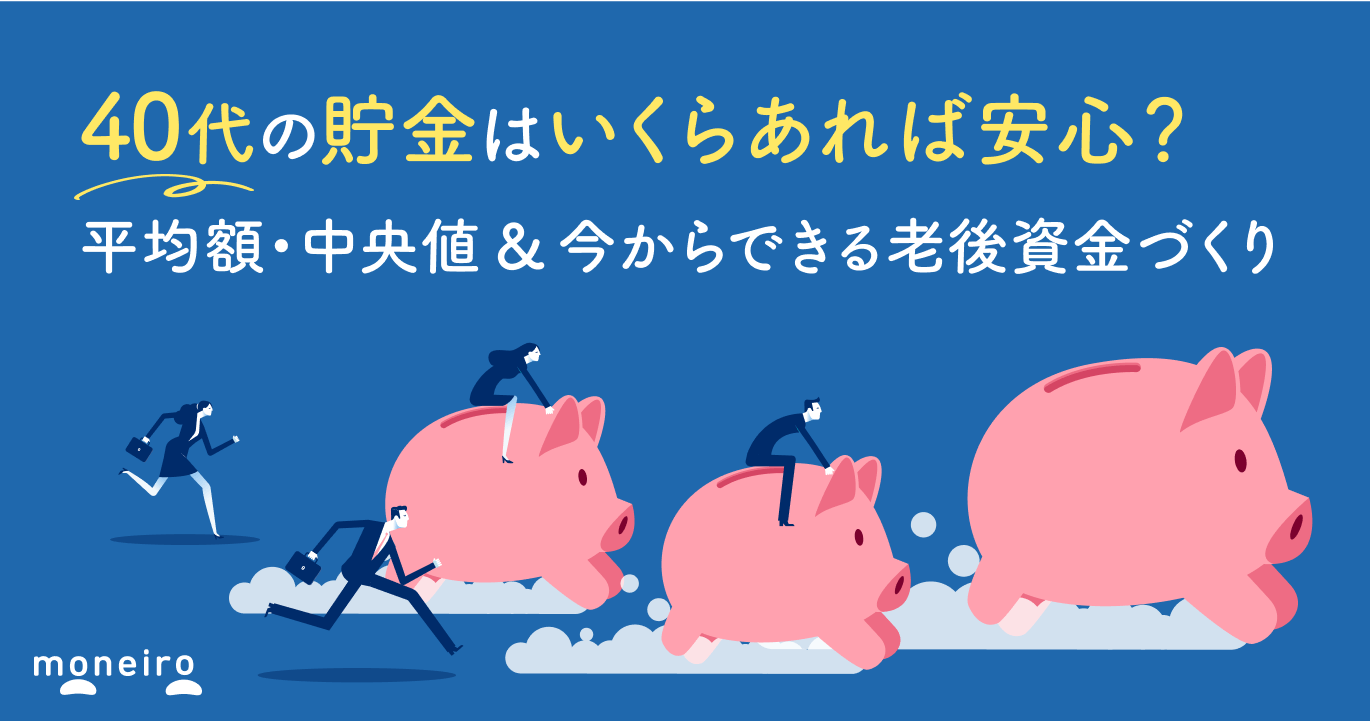
40代の貯金いくらあれば安心?平均額・中央値&今からできる老後資金づくり
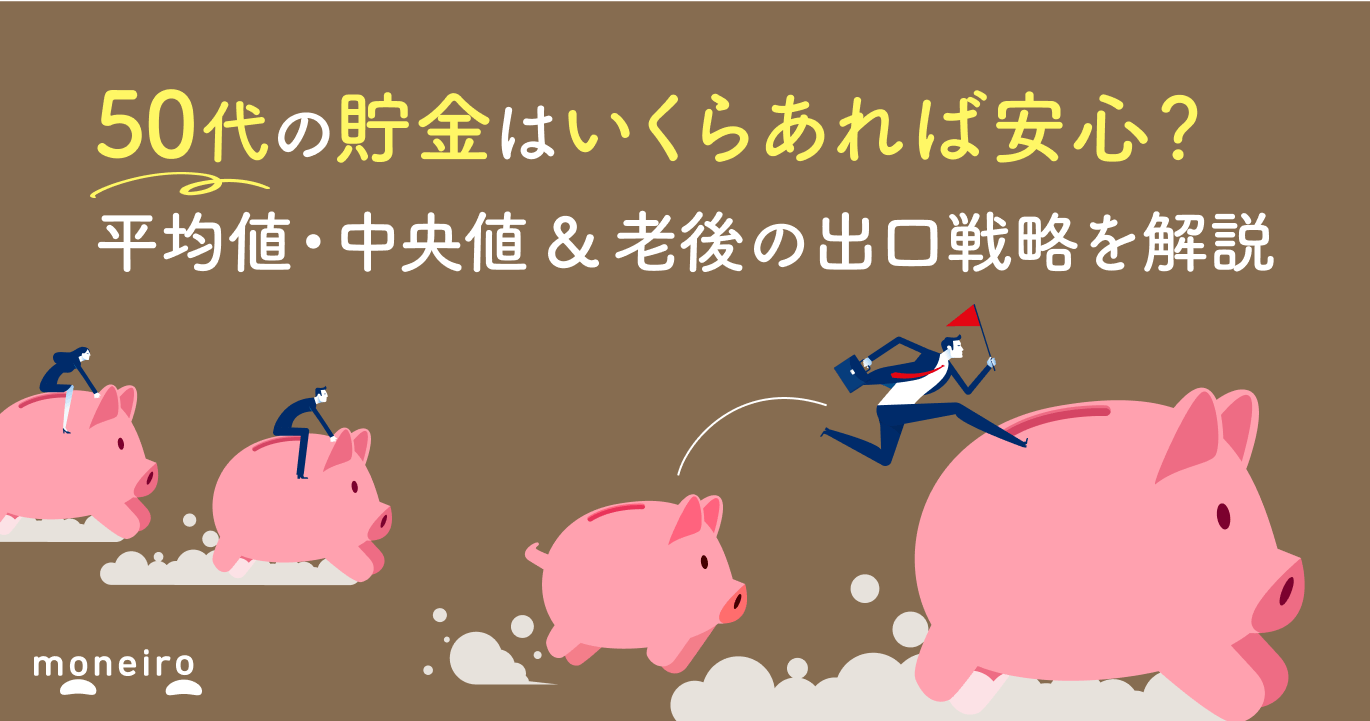
50代の貯金はいくらあれば安心?平均値・中央値&老後の出口戦略を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
