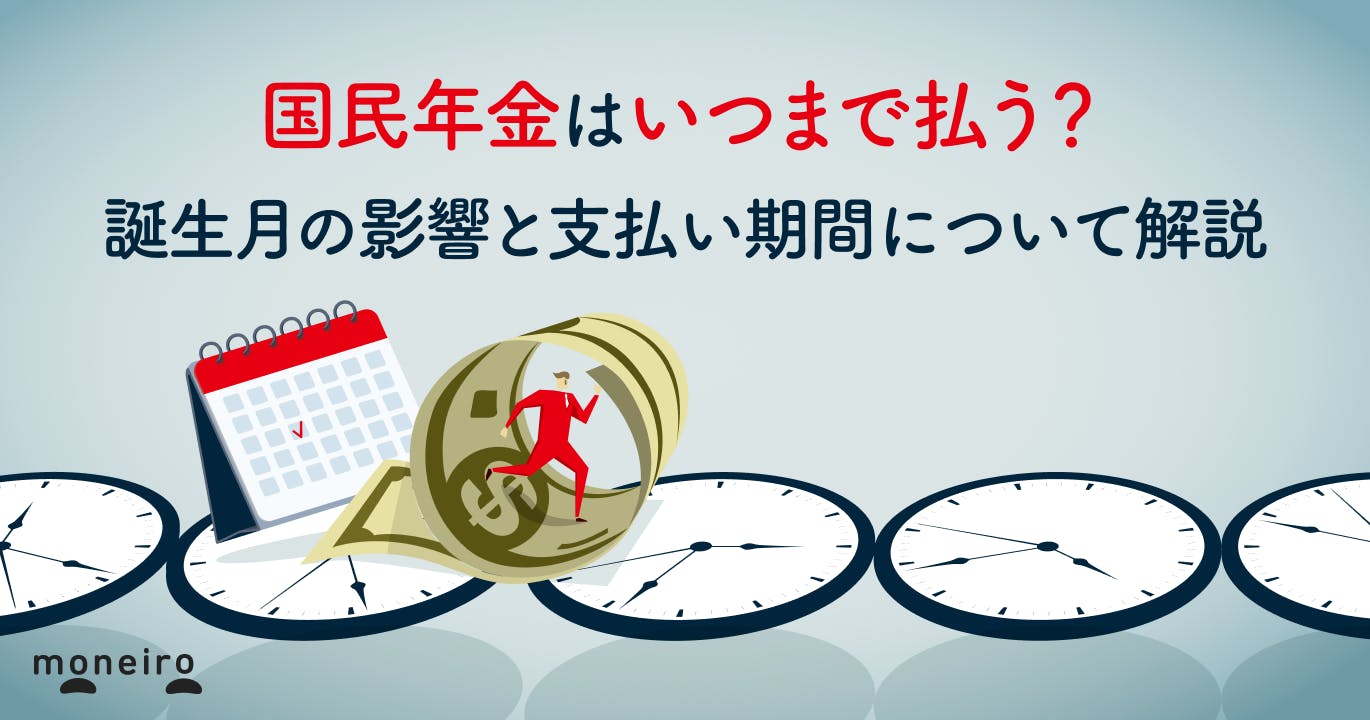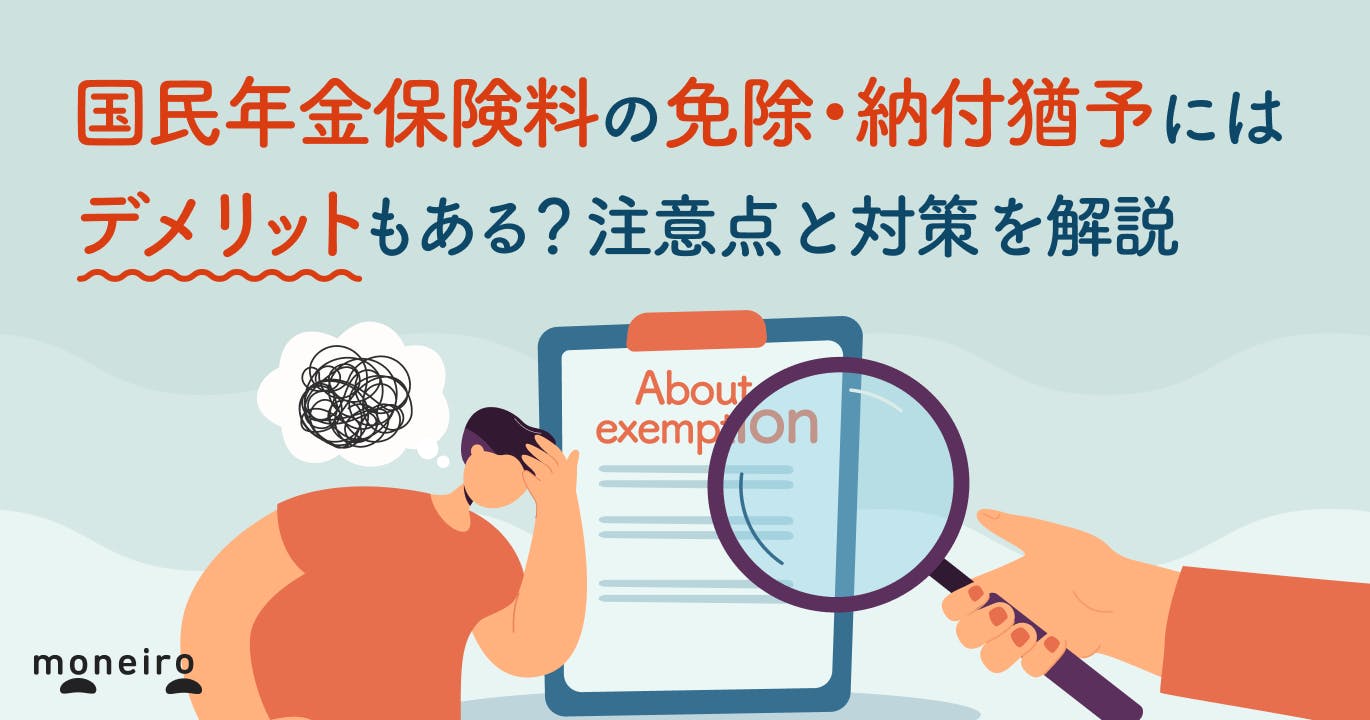国民年金はいつまで払う?誕生月の影響と支払い期間をわかりやすく解説
≫あなたの老後資金は足りる?不足額を3分で診断
「国民年金はいつまで払う?」「誕生月の影響は?」と疑問に感じている方も多いかもしれません。この記事では、国民年金の支払期間についての基本をおさらいするとともに、誕生月が与える支払期間への影響も解説します。
また、60歳以降の任意加入制度や、万が一支払いが困難になった場合の対処法についても詳しく紹介します。ぜひこの記事を参考に、国民年金について理解を深めていきましょう。
- 国民年金の支払い期間の基本と、誕生月が最終納付月に与える影響
- 60歳以降も年金額を増やすための「任意加入制度」の仕組み
- 国民年金の支払いが困難な場合に利用できる「保険料免除・納付猶予制度」について
年金の支払いが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金の支払い期間の基本ルール
まずは、国民年金の支払期間について、基本ルールをおさらいしておきましょう。
支払い開始・支払い終了はいつ?
国民年金保険料の支払いは、原則として20歳になった月から開始し、60歳になる誕生月の前月分まで です。 ただし、1日生まれの人は、誕生月の前々月分までとなります。これは、「年齢計算に関する法律」で、「60歳に達する日」を「60歳の誕生日の前日」と定められているためです。
例えば、4月15日が誕生日の人の場合、60歳に達する日は誕生日の前日である4月14日となります。この場合、国民年金保険料の最終納付月は、60歳の誕生月である4月の前月、つまり3月分までとなります。
一方、4月1日生まれの人は、「60歳に達する日」が3月31日となるため、保険料の支払いは2月分までとなります。
誕生月による支払い期間の具体例
国民年金保険料の最終納付月は、先述の「60歳に達する日=60歳の誕生日の前日」という年齢計算のルールが関係しているため、誕生月によって異なります。
支払い月数の確認方法
自分の国民年金の支払い状況や納付月数を確認する手軽な方法として、日本年金機構が提供する「ねんきんネット」が挙げられます。
ねんきんネットは、インターネットを通じて自身の年金記録をいつでも確認できる便利なサービスで、過去の納付状況や将来の年金見込額などを参照できます。
また、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」もチェックしてみましょう。保険料納付額や、加入実績に応じた年金額などを確認できます。
より詳細な相談をしたい場合は、年金事務所で直接確認することもできます。年金事務所では、専門の職員が個別の状況に応じて説明や手続きのサポートをしてくれるので、近所にある場合は活用するとよいでしょう。
国民年金と厚生年金の支払い期間の違い
会社員や公務員が加入する厚生年金は、国民年金(基礎年金)に上乗せされる形で支給される年金です。国民年金と厚生年金では、保険料の支払い期間に以下のような違いがあります。
厚生年金は、会社員・公務員として働いている間は原則として70歳まで保険料を納めることになります。
仮に、給与支払いが「当月締め翌月払い」の場合、「70歳になる誕生月の前月の支払い分」が給与から天引きされるため、「70歳になる誕生月」に支払われる給与の天引きが最後の厚生年金保険料の支払いとなります。
60歳以降も年金を増やしたい場合の「任意加入制度」
国民年金の保険料納付は原則として60歳で終了しますが、保険料の納付済期間が40年に満たない方や、将来より多くの年金を受け取りたいと考える方のために、「任意加入制度」が設けられています。
この制度を利用することで、60歳以降も国民年金保険料を任意で納め続けることができます。
≫あなたの老後資金は足りる?不足額を3分で診断
任意加入ができる条件
国民年金の任意加入制度を利用するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
引用
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
参照:任意加入制度|日本年金機構
また、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入可能です。
任意加入のメリット・デメリット
国民年金の任意加入制度を利用することには、いくつかのメリットとデメリットがあります。
メリット
任意加入の最大のメリットは、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やせる点です。国民年金の保険料を納付した期間が長いほど、満額受給に近づき、老齢基礎年金の受給額は増加します。
また、老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)を満たしていない場合でも、不足期間を任意加入で補うことで受給資格を得ることができます。
さらに、任意加入中に障害や死亡といった万一の事態が発生した場合でも、一定の保険料納付要件を満たせば、障害基礎年金や遺族基礎年金の給付対象となる可能性があります。
デメリット
一方、任意加入にはデメリットもあります。
もっとも直接的なデメリットは、60歳以降も保険料(月額約1万7510円/令和7年度)を支払う必要があり、家計への負担が増すことです。さらに、すでに厚生年金に加入している人や、国民年金を繰上げ受給している人は、任意加入制度を利用できません。
また、任意加入は一度始めても途中でやめることは可能ですが、保険料の支払いに見合った年金額の増加が見込めるかどうかを含め、計画的な資金設計が重要です。
任意加入の手続き方法
国民年金の任意加入の手続きは、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口や、お近くの年金事務所で行えます。
手続きには、本人確認書類、年金手帳、基礎年金番号通知書、預貯金通帳(口座振替を希望する場合)などが必要となりますが、詳しくは電話などで事前に確認しておくとスムーズでしょう。
任意加入の手続きは、保険料を納めたい月の前月までに行うのが一般的です。
65歳までの支払いシミュレーション
例えば、60歳で国民年金保険料の納付が終了した人が、60歳から65歳までの5年間(60ヶ月)を任意加入した場合の保険料負担と、将来の年金受給額の増加についてシミュレーションしてみましょう。
保険料負担の試算
国民年金保険料の月額が1万7510円(令和7年度)だとした場合、5年間(60ヶ月)の任意加入でかかる保険料は、1万7510円 × 60ヶ月 = 105万600円となります。
受給額増加の試算
老齢基礎年金は、40年間(480ヶ月)保険料を納付することで満額(年間83万1700円/令和7年度)が支給されます。1ヶ月あたりの納付による年金増加額は、約1732円(83万1700円 ÷ 480ヶ月)と概算できます。
したがって、5年間(60ヶ月)任意加入することで、年間の老齢基礎年金受給額が約10万3920円(1732円 × 60ヶ月)増加する計算になります。
このシミュレーションはあくまで概算であり、将来の保険料額や年金額は変動する可能性があります。
年金の支払いが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
支払いが難しい場合の対処法
国民年金保険料の支払いが経済的な理由で困難な場合でも、滞納(未納)を続けるべきではありません。
長期間に渡って滞納してしまうと、将来受け取れる年金額が減るだけでなく、年金受給資格期間に算入されず、受給権自体を失ってしまう可能性もあります。支払いで 困った際には、以下の制度の利用を検討しましょう。
保険料免除・納付猶予制度
国民年金保険料の支払いで困った場合には、「保険料免除制度」「納付猶予制度」という救済制度があります。
これらは、所得が低い、失業した、災害にあったなど、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合に、申請によって保険料の支払いを免除または猶予してもらえる制度です。
保険料免除制度
所得に応じて、保険料の全額、または一部(4分の3、半額、4分の1)の支払いが免除される制度です。免除された期間は将来の年金額に一部反映されるため、まったく保険料を納めない「未納」を続けるよりも有利です。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方を対象に、所得が一定基準以下の場合は、保険料の納付が一定期間猶予される制度です。猶予期間は将来の年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されるため、年金を受け取る権利自体は確保できます。猶予された保険料は、後から(10年以内)「追納」することも可能で、追納すればその期間も年金額に反映されます。
これらの制度を利用することで、未納期間が発生するのを防ぎ、将来の年金受給権を確保することができます。ただし、免除や猶予を受けた期間は、将来受け取る年金額に影響を与える可能性があるため、その点を理解した上で申請することが重要です。
申請条件や詳細については、お近くの年金事務所や市区町村の窓口で確認してください。
免除・猶予制度を利用した場合の年金額
免除・猶予の区分ごとの年金額は以下のとおりです。
国民年金の支払いに関するQ&A
最後に、国民年金の支払いに関するよくある質問にお答えします。
Q. 国民年金の未納期間がある場合、どうすればいい?
国民年金の保険料は、納付期限から2年を過ぎると時効となり、納めることができなくなります。しかし、過去2年以内の未納分であれば、「追納」という形で納めることができます。
追納することで、納めた 分が将来の年金額に反映され、受給資格期間にも算入されます。時効となった未納期間については、その期間の年金は受給額に反映されません。もし受給資格期間が不足している場合は、任意加入制度の利用などを検討することになります。
Q. 付加保険料の納付も誕生月の前月まで?
はい、原則として、「付加年金」の付加保険料の納付も、国民年金の通常加入期間と同じく、60歳になる誕生月の前月分までが対象となります。
なお、60歳以降に任意加入する場合でも、条件を満たせば付加保険料の納付が可能です(ただし、国民年金基金に加入している方などは対象外となります)。
付加年金は、通常の国民年金保険料に、付加保険料として月額400円を上乗せして納めることで、将来受け取る年金額を増やせる制度です。
Q. 繰上げ受給・繰下げ受給をしたい場合、納付期間は変わる?
いいえ、老齢基礎年金の「繰上げ受給」や「繰下げ受給」を選択しても、国民年金保険料の納付期間自体は変わりません。
国民年金保険料の納付は、原則として20歳から60歳になる誕生月の前月分までと決まっています。
繰上げ受給や繰下げ受給は、年金を受け取り始める時期を65歳より早めたり遅らせたりする制度であり、保険料を納める期間には影響を与えません。
まとめ
国民年金保険料の納付は、原則として20歳から60歳になる誕生月の前月分(1日生まれは前々月分)までと決まっています。特に、誕生日の前日をもって年齢が加算されるという「年齢計算に関する法律」の原則が、最終納付月に影響を与えることを理解しておくことが重要です。
また、年金額を増やしたい場合は、60歳以降も加入を継続できる任意加入制度を、経済的な理由で支払いが困難な場合は免除・猶予制度を検討するなど、国民年金では状況に応じた柔軟な対応が可能です。
自分がこれまでに納付した年金記録や、将来の受給見込額については「ねんきんネット」などで定期的に確認し、計画的な老後資金の準備を進めていきましょう。
≫あなたの老後資金は足りる?不足額を3分で診断
年金の支払いが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。