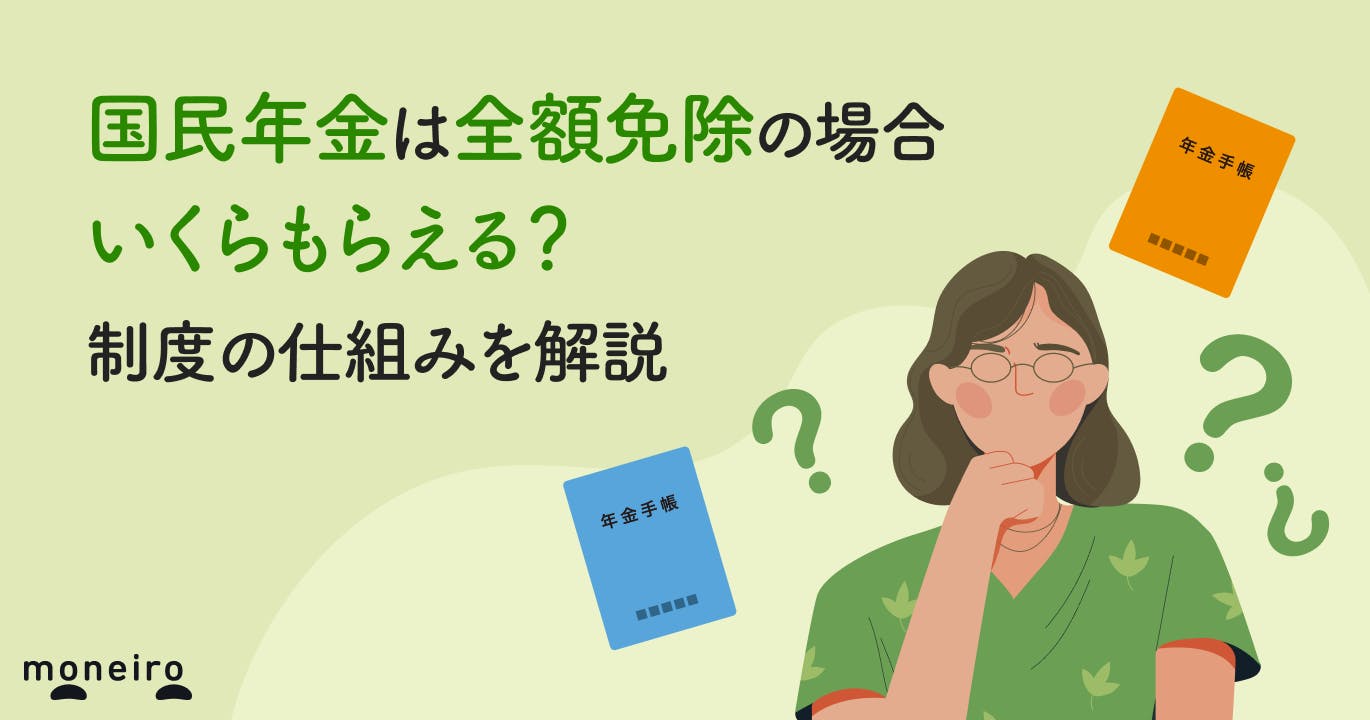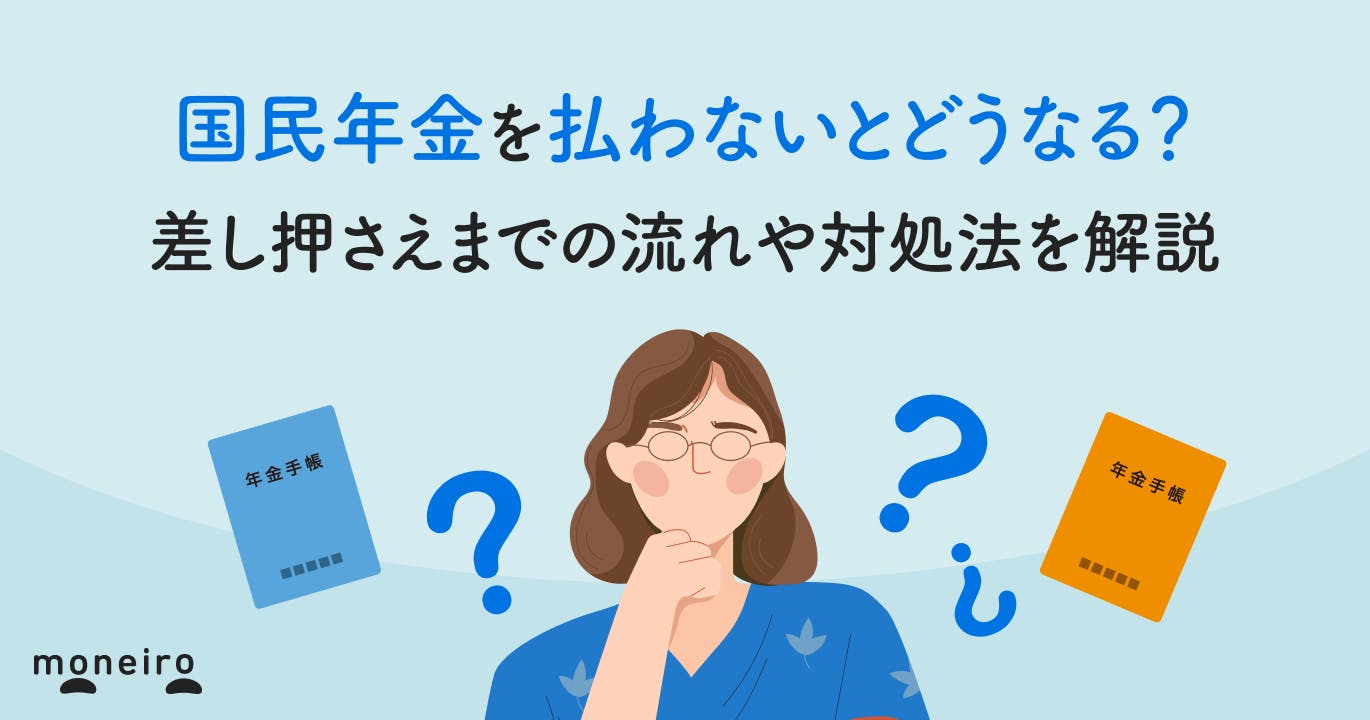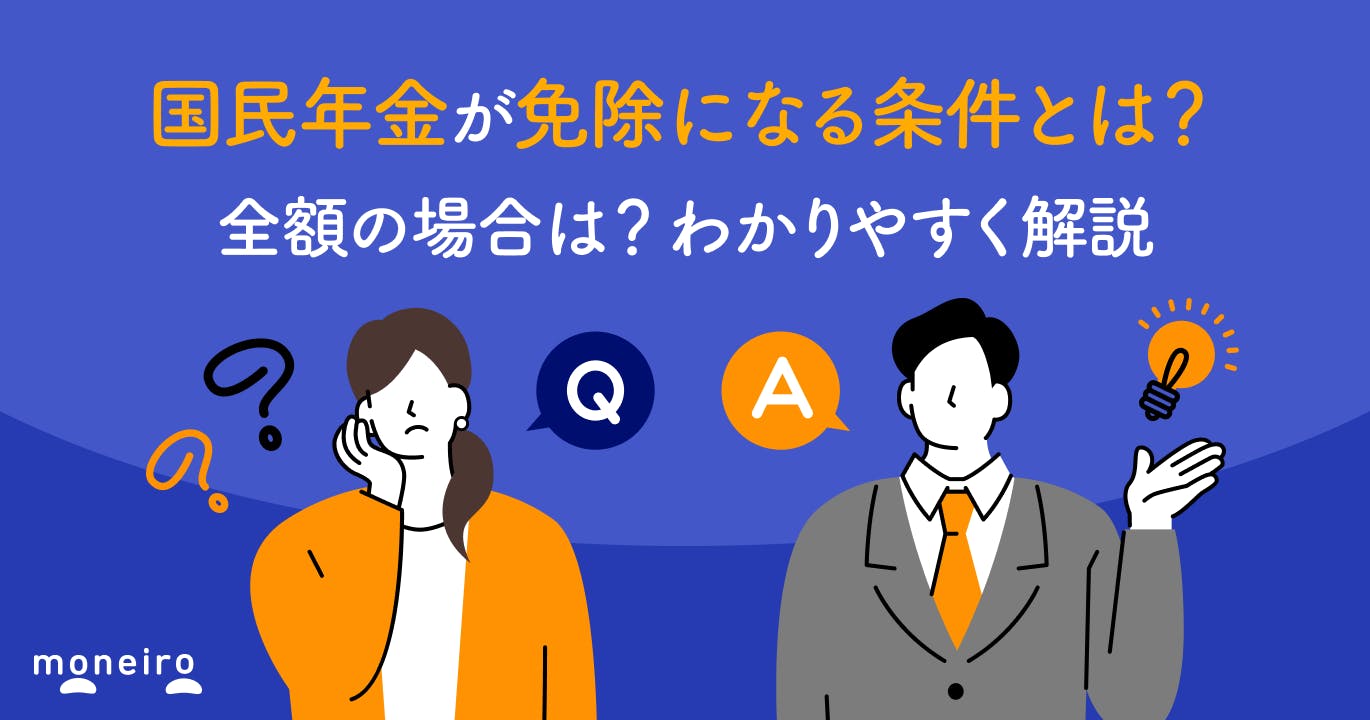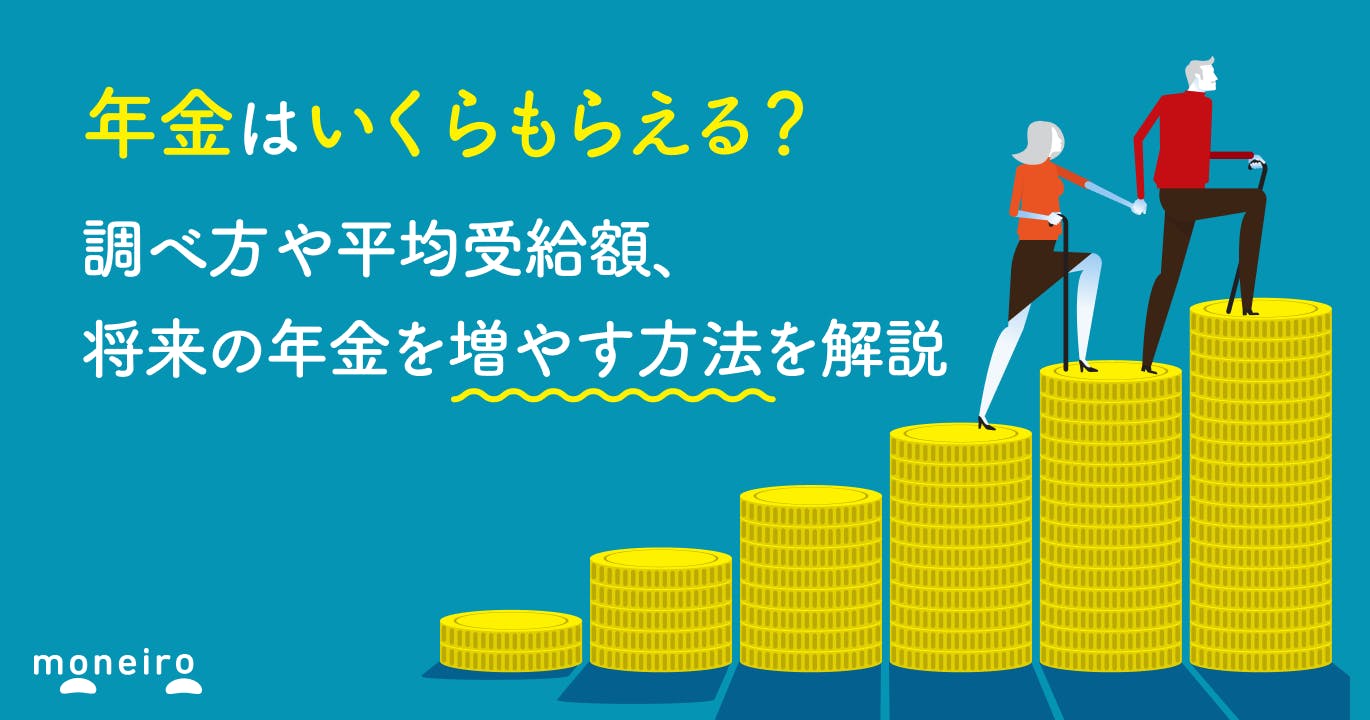
国民年金は全額免除の場合いくらもらえる?免除期間別シミュレーション
≫年金で不足する額はいくら?あなたの必要額を診断
「国民年金の保険料を全額免除されると将来いくらもらえるの?」「もしかして年金はゼロになるのでは?」と不安に感じている方もいるかもしれません。しかし、保険料を全額免除されても年金がまったくもらえなくなるわけではありません。
本記事では、国民年金の全額免除制度の仕組みから、免除期間ごとの年金額シミュレーション、そして将来の年金額を増やすための「追納」制度について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
- 国民年金保険料の免除(猶予)制度の種類と承認の条件
- 全額免除期間に応じた将来の年金額の目安
- 将来の年金額を増やすための「追納制度」のメリットと注意点
国民年金の免除が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
国民年金保険料の免除制度とは?
国民年金の免除制度(及び納付猶予制度)とは、経済的な事情などにより保険料の納付が難しい場合に、申請によって「免除」または「納付猶予」を受けられる制度です。
この制度を活用すれば、ただ未納にするのとは異なり、保険料が免除された期間も将来の老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。また、免除・猶予中に病気やけがで障害を負ったり、死亡したりした場合には、要件を満たせば障害年金や遺族年金を受給できる可能性もあります。
保険料の免除(猶予)の種類
国民年金保険料の免除制度には、本人の所得に応じて保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される「申請免除」と、失業や災害時などに特例として認められる「特例免除」があります。
これらに加え、学生向けの「学生納付特例制度」や、50歳未満の方を対象とした「納付猶予制度」も存在します。それぞれの制度には所得基準などが設けられており、申請によって承認されることで適用されます。
各免除制度・納付猶予制度の承認基準
免除や猶予の種類ごとに、承認基準が決まっています。所得が次の基準以下の場合に、免除や猶予の承認が受けられます。
失業や災害などの場合は特例免除も
失業や事業をやめることになった場合、災害で被害を受けた場合など、特別な事情がある時には「特例免除」という制度を利用できます。
この制度の大きな特徴は、失業した本人の所得を除外して審査が行われる点です。通常、免除の審査では本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も考慮されますが、特例免除では本人の前年所得にかかわらず承認を受けられる可能性があります。
免除と未納の違い
国民年金保険料の「免除」と「未納」は、どちらも保険料を納付していない状態ですが、その扱いは大きく異なります。
免除が承認された期間は、将来の老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額にも一定の割合で反映されます。一方、未納期間は受給資格期間に算入されず、年金額にも全く反映されません。
また、免除期間中は保険料を納付したのと同様の扱いになり万が一の障害や死亡時に障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となる可能性がありますが、未納ではこれらの給付も受けられないことがあります。免除は年金制度におけるセーフティネットであり、未納とは本質的に異なるものです。
国民年金は全額免除でも年金はもらえる?
結論からいうと、国民年金保険料の全額免除を受けていても、将来年金を受け取ることは可能です。老齢基礎年金を受け取るには、少なくとも10年の受給資格期間が必要です。免除が承認された期間も、受給資格期間に算入されます。
仮に40年間すべての保険料が全額免除になったとしても、受給資格期間は40年とカウントされ、65歳から年金を受け取ることができます。ただし、受け取れる年金額は、保険料を全額納付した場合と比較して減額される点に注意が必要です。
全額免除期間も国庫負担により年金の2分の1はもらえる
老齢基礎年金の財源は国民年金保険料のみではなく、2分の1(2009年4月以降)は国庫負担です。全額免除期間については、保険料を納付していなくても、国庫負担により年金額の2分の1が支給されます。
つまり、全額免除期間においては保険料をまったく支払っていなくても、国の負担分によって年金の2分の1を確保できるのです。これにより、お金に困っている状況にあっても、将来の生活基盤となる年金をもらう権利を完全に失うことなく、一定額の年金を受け取ることが可能になります。
なお、2009年3月以前に全額免除されていた期間については、国庫負担割合が3分の1であったため、年金額の3分の1を受け取れます。
国民年金の免除が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
【早見表】全額免除された場合の年金額は?満額といくら違う?
国民年金保険料を全額免除された場合、将来受け取れる年金額はどのくらいになるのでしょうか。以下で、全額免除期間ごとの受給額と満額との差額について早見表でチェックしてみましょう。
全額免除期間ごとの受給額(年額)
国民年金保険料の全額免除を受けた期間に応じて、将来受け取れる老齢基礎年金の概算額は以下のようになります。
※令和7年度の老齢基礎年金(満額831,700円)を基準に計算
※全額免除期間はすべて平成21年4月以降と仮定
※小数点以下は切り捨て
表からもわかるように、40年間すべて全額免除だったとしても、年間で約41.6万円(月額約3.5万円)の年金を受け取ることが可能です。とはいえ、満額と比較すると半分になってしまうため、老後の生活設計を考える上ではこの差額を認識しておくことが重要です。
一部免除(3/4、半額、1/4)の場合の年金額の扱いは?
全額免除だけでなく、所得に応じて設定される一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合、年金額の計算はさらに細かくなります。
これらの期間は、国の負担分(2分の1)に加えて、自分が納付した保険料分が年金額に反映されます。各一部免除期間が年金額に反映される割合は以下の通りです。
例えば、半額免除の承認を受け、保険料の半額を納付した場合、その期間は満額の8分の6(国の負担分は2分の1+自己負担分は2分の1×2分の1=4分の1)が年金額に反映されます。つまり一部免除は、減額された保険料を納める必要がありますが、その分、全額免除よりも将来受け取る年金額は多くなります。
なお、納付猶予期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。しかし、後述する「追納」を行うことで、その期間も納付済みとして扱われ、将来の受給額を増やすことができます。
将来の年金を増やせる「追納」とは?
国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、後から納付することができます。これを「追納(ついのう)」制度と呼びます。
この制度を利用することで、免除や猶予により減額されていた将来受け取る年金額を満額に近づけることが可能です。追納は、過去の保険料を清算し、将来の年金額を充実させるための有効な手段となります。
追納のメリット
追納の最大のメリットは、免除や猶予により減額されていた将来の老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられる点です。追納することで、年金として受け取れる金額が増え、老後の生活設計にゆとりが生まれます。
また、追納した国民年金保険料は「社会保険料控除」の対象となり、その年の所得税や住民税の負担を軽減できるという税制上のメリットもあります。これにより、実質的な追納額の負担を抑えることも可能です。
追納の注意点
一方で追納にはいくつかの注意点があります。まず、追納できるのは免除や猶予が承認された期間の保険料に限られ、その期間の翌月から起算して10年以内という期限があります。この期限を過ぎると追納はできません。
免除承認を受けた期間の保険料を、2年度目までは当時の保険料額で追納できますが、3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。追納を検討する際は、これらの期限や加算額を考慮し、計画的に行うことが重要です。
免除の申請手続きの方法と必要書類
国民年金保険料の免除や納付猶予の申請は、定められた手続きと書類が必要です。適切に申請を行うことで、将来の年金受給権を確保し、生活の安定を図ることができます。申請手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類を確認し、準備を整えましょう。
申請に必要な書類一覧
国民年金保険料の免除・納付猶予を申請する際には、一般的に以下の書類が必要となります。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 申請者の前年所得を証明する書類(所得が日本年金機構で確認できない場合や、申請期間の所得状況が異なる場合)
- 失業や災害などによる特例免除の場合は、それを証明する書類(雇用保険受給資格者証、り災証明書、廃業届など)
なお、申請に必要な書類は、申請理由や状況によって異なる場合があるため、事前に日本年金機構のWebサイトや最寄りの年金事務所に確認することをおすすめします。
申請窓口と申請期間
国民年金保険料の免除・納付猶予の申請は、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口、または管轄の年金事務所で行うことができます。マイナンバーカードがあれば、スマートフォンなどからマイナポータルを利用して電子申請により手続きすることも可能です。
また、申請期間については、原則として免除を受けたい期間の開始月から申請が可能で、通常は毎年7月から翌年6月までの1年を対象としています。保険料の納付期限から2年を経過していない期間であれば、さかのぼって免除申請ができます。
申請は随時受け付けていますが、申請が遅れると免除が認められる期間が短くなる可能性もあるため、経済状況に変化があった場合は速やかに手続きを行いましょう。
国民年金の免除に関するQ&A
国民年金保険料の免除制度に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q. 国民年金保険料が全額免除になる条件は?
国民年金保険料の全額免除が承認される主な条件は、前年所得が一定の基準以下であることです。具体的には、扶養親族等の人数に応じて定められた所得基準があり、「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で計算される額が目安となります。
例えば、単身者の場合は「(0 + 1)×35万円+32万円 = 67万円」となり、67万円以下の所得が承認の目安です。同様に、夫婦2人世帯で配偶者を扶養している場合は「(1 + 1)×35万円+32万円 = 102万円」となり、102万円以下の所得が目安となります。
Q. 国民年金保険料の免除には年金額が減る以外のデメリットもある?
国民年金保険料の免除の最大のデメリットは、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が満額より少なくなることです。
これ以外にも、免除・納付猶予を受けている期間は、老齢基礎年金に上乗せして給付を受けられる「付加年金」や「国民年金基金」に加入することができなかったり、iDeCoへの加入ができないといったデメリットがあります。
Q. 保険料を追納しないとどうなる?
免除期間の保険料を追納しなかった場合、将来受け取る老齢基礎年金の年金額は、追納した場合と比べて少なくなります。全額免除期間の場合、年金額には保険料の半分のみ反映されるため、追納しなければ満額の半分相当分は年金額に反映されません。これにより、老後の生活設計に影響が出る可能性があります。
また、追納によって受けられる社会保険料控除のメリットも失うことになります。追納には10年間の期限があるため、将来の年金額を増やしたい場合は計画的な追納を検討しましょう。
まとめ
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度は、経済的な理由で保険料の納付が困難な人を支援するための重要な制度です。仮に全額免除の期間があっても将来年金は受け取れますが、年金額は満額の半分として計算されるため、通常納付した場合よりも少なくなる点には注意が必要です。
ただし、追納制度を活用することで、減額分を解消し、将来の年金額を満額に近づけるためこともできます。さらに、追納は社会保険料控除のメリットも享受できるのも大きなメリットです。
将来の安心な老後生活のために、自身の状況に合わせて免除・猶予や追納制度を賢く活用しましょう。そして、もし不明な点がある場合は年金事務所や市区町村の窓口に相談するようにしましょう。
≫年金で不足する額はいくら?あなたの老後の必要額を3分で診断
国民年金の免除が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。