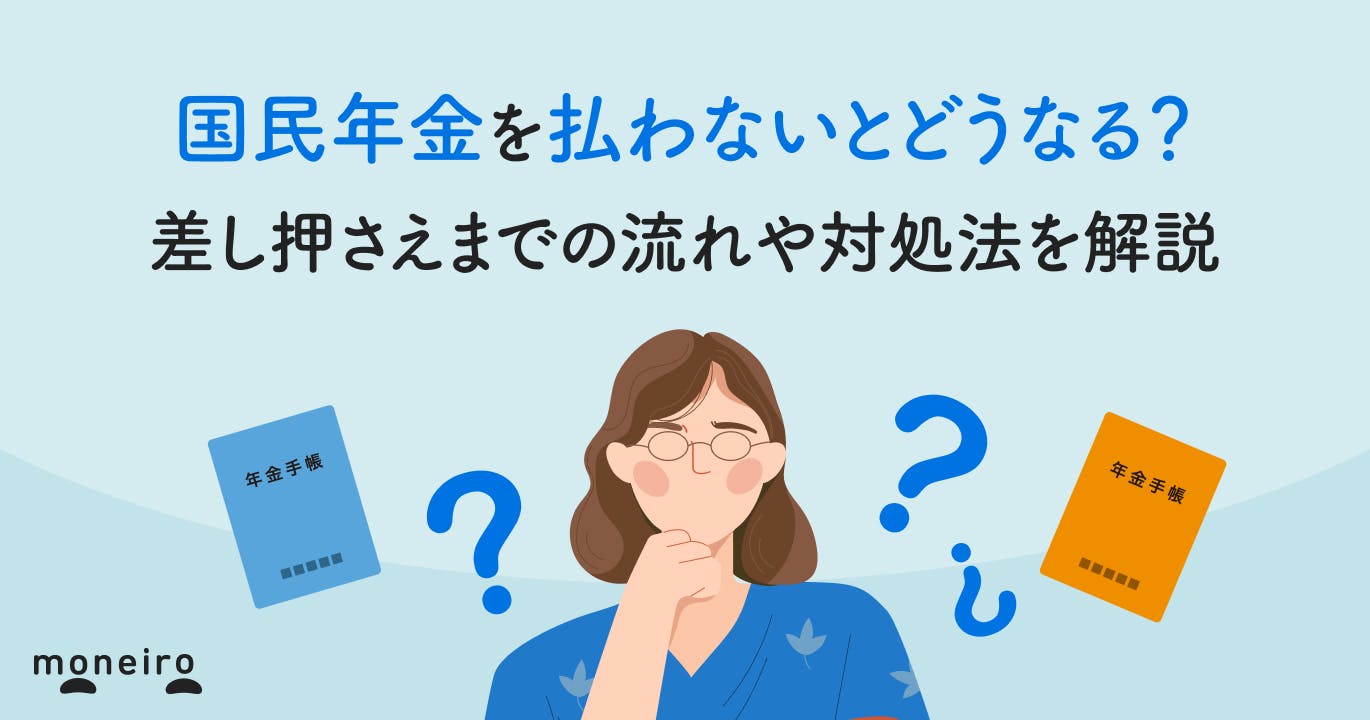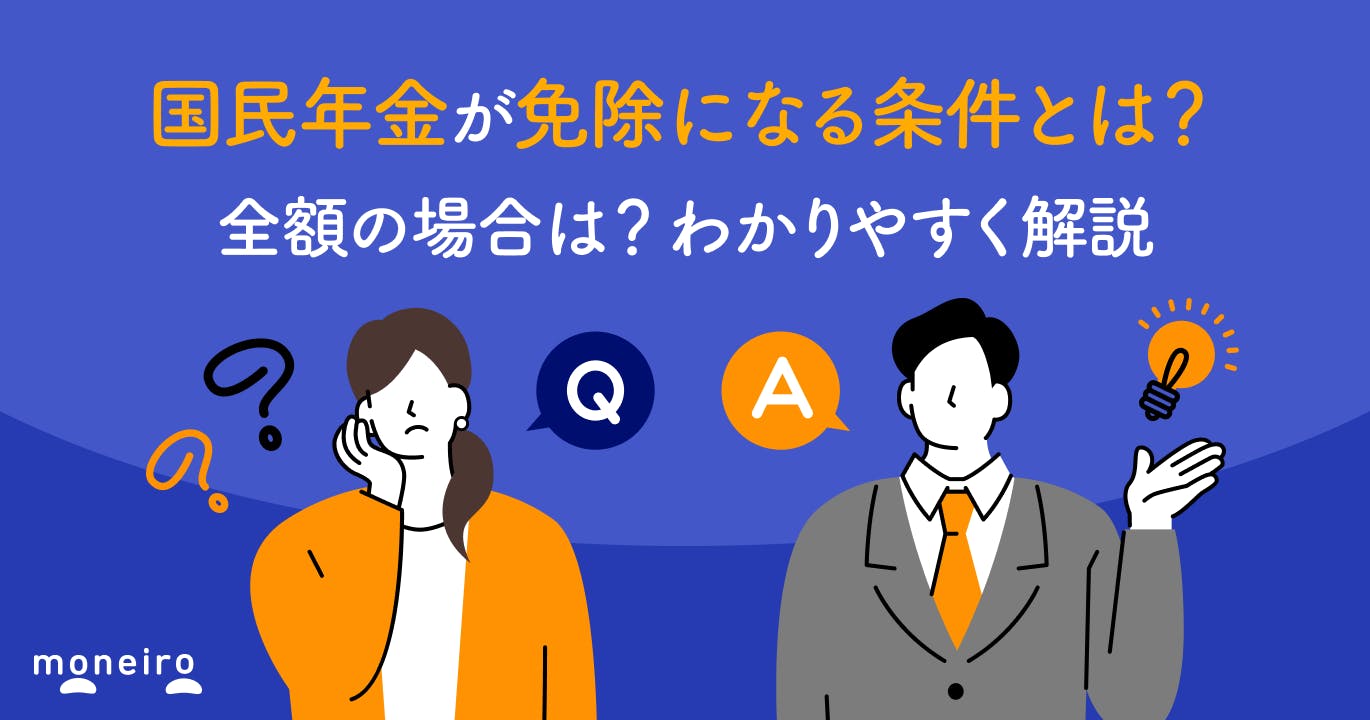
国民年金を払わないとどうなる?差し押さえまでの流れや対処法を解説
【無料】年金だけで足りる?あなたの将来に必要なお金を3分で診断
「国民年金の支払いが難しい」「もし払わないとどうなるんだろう?」そう不安に感じている方もいるかもしれません。もし国民年金保険料の未納を続けてしまうと、最終的には財産を差し押さえられる可能性もあります。
そこでこの記事では、国民年金を滞納した場合に生じる具体的なリスクや、差し押さえに至るまでの流れ、そして万が一支払いが困難になった際に利用できる免除・猶予制度までを、分かりやすく解説していきます。
- 国民年金保険料を滞納した場合に起こりうるリスクとその具体的内容
- 国民年金保険料の未納から財産の差し押さえに至るまでの具体的なフェーズ
- 国民年金保険料の支払いが困難な場合に利用できる公的な救済制度
国民年金の支払いが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
国民年金を払わないとどうなる?3つのリスクをチェック
国民年金保険料を支払わないことは、単に「お金を払わない」というだけの問題ではありません。長期的に見ると、老後や万が一の事態に直面した際の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、国民年金を支払わない場合に直面する主な3つのリスクについて詳しく見ていきましょう。
最終的に財産を差し押さえられる
国民年金保険料を滞納し続けると、最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。これは、年金事務所が滞納者に対して行った督促にもかかわらず支払いがなされない場合に、法的な手続きを経て強制的に滞納分を徴収する措置です。
差し押さえの対象となる財産は、預貯金、給与、不動産、自動車など多岐にわたります。特に、預貯金や給与は比較的小額からでも差し押さえの対象となりやすく、突然生活に支障をきたすことがあります。
また、給与が差し押さえられる場合、勤務先に通知が行くため、会社に未納の事実が知られてしまう可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、未納の状態を放置せず、早期に適切な対応を取ることが非常に重要です。
将来もらえる老齢年金が減額される
国民年金は、原則として65歳から受け取れる老齢年金の基礎となります。
老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせて、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。もし保険料を支払わずに未納期間が長引くと、この受給資格期間を満たせなくなり、将来年金を受け取れなくなる可能性が生じます。
また、受給資格期間を満たしていても、未納期間があるとその分、将来受け取れる年金額が減額されます。老後の生活設計において年金は重要な柱となるため、この減額は将来の生活設計に大きな影響を与えることになります。
万が一の際の障害年金・遺族年金が受け取れない
国民年金は、老齢年金だけでなく、現役世代の万が一の事態に備えるための重要な保障も提供しています。それが「障害年金」と「遺族年金」です。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出るほどの障害が残った場合に支給される年金です。また、遺族年金は、国民年金に加入している方や老齢年金を受給していた人が亡くなった際に、その遺族の生活を保障するために支給される年金です。
これらの年金を受け取るためには、保険料の納付要件を満たしている必要があります。もし未納期間が長いと、この要件を満たせず、いざというときにこれらの重要な年金が受け取れなくなるリスクがあります。
要チェック!差し押さえまでの5つのフェーズ
国民年金保険料の滞納から財産差し押さえに至るまでには、いくつかの段階があります。これらのフェーズを把握しておくことで、現在の状況を理解し、適切なタイミングで対処するための準備ができるでしょう。
1.納付勧奨(催告状の送付)
国民年金保険料を納期限までに支払わない場合、まず日本年金機構から「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が送付されます。この催告状は、未納の保険料があることを知らせ、速やかに支払うよう促すものです。催告状には、未納となっている期間や金額が記載されています。
この時点ではまだ、差し押さえなどの強制的な措置が取られることはありませんが、これを無視して放置すると次のステップに進むことになります。
催告状を受け取った時点で、自身の納付状況を確認し、支払いが困難な場合は後述する免除・猶予制度の利用を検討するなど、すぐに対応を始めることが重要です。
2.特別催告状の送付
催告状を受け取ってもなお保険料が支払われない場合、次に送られてくるのが「特別催告状」です。特別催告状は、警告の度合いに応じて、低い方から青(低)、黄(中)、赤(高)と色が変わっていきます。
この段階でもまだ強制徴収が行われるわけではありませんが、未納状態が続いていることへの強い警告であり、無視することはおすすめできません。この時点でも支払いが難しいと感じたら、年金事務所への相談を急ぎましょう。
3.最終催告状の送付
特別催告状が送付されても支払いが確認できない場合、いよいよ「最終催告状」が送られてきます。この最終催告状は、次に強制的な滞納処分(差し押さえ)へと移行する前段階であることを強く示唆するものです。
最終催告状には、これまでの未納履歴と最終的な納付期限が明記され、この期限を過ぎた場合は法的な措置を講じる旨が警告されます。この通知は、滞納処分を行うための最終的な警告と捉えるべきで、この通知を受け取った時点で、猶予はほとんどないと考えたほうがよいでしょう。
最終催告状の期限までに納付しない場合には督促状が届き、それでも未納状態が続けば、いよいよ財産調査と差し押さえへと移行します。
4.財産調査と差し押さえ予告通知
督促状の期限を過ぎても国民年金保険料が支払われない場合、日本年金機構は滞納者の財産調査を開始します。この調査は、滞納者がどのような財産(預貯金、給与、不動産など)を保有しているかを把握するために行われます。
調査の結果、差し押さえ可能な財産が特定されると、滞納者に対して「差押予告通知」が送付されます。この通知は、具体的な差し押さえの対象となる財産と、差し押さえを実行する旨を正式に知らせるものです。
この段階に至ると、差し押さえの準備がほぼ完了しており、差し押さえを避けるためには、記載された期限までに未納保険料を全額納付するか、年金事務所と具体的な支払いの相談を行うしかありません。予告通知を受けた後の対応は、差し押さえを避けるための最後のチャンスといえます。
5.差し押さえの実行
差押予告通知に記載された期限までに未納保険料を納付しない場合、日本年金機構は最終的に財産の「差し押さえ」を実行します。差し押さえは、法律に基づき強制的に滞納者の財産を処分し、換価(売却)した上で未納分の保険料や延滞金に充当する手続きです。
預貯金が差し押さえられれば口座が凍結され、給与が差し押さえられれば勤務先に通知が行われ、会社から直接、日本年金機構へ給与の一部が支払われます。さらに、不動産や自動車なども状況によっては差し押さえの対象となります。
差し押さえが行われれば生活や仕事への影響に加え、精神的な負担や社会的な信用低下も避けられません。このような事態を防ぐためには、滞納に気づいた段階で早めに納付や免除・猶予の相談を行うことが極めて重要です。
国民年金の支払いが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
どうしても払えないときの救済制度
国民年金保険料の支払いが経済的に困難な場合でも、決してそのまま放置してはいけません。
日本年金機構には、そういった状況の方向けに、保険料の納付を支援するいくつかの公的な救済制度が用意されています。これらの制度を利用することで、将来の年金受給資格期間を確保しつつ、現在の経済的負担を軽減することが可能です。
全額・一部が免除される「保険料免除制度」
保険料免除制度は、経済的な理由などにより国民年金保険料を納めることが難しい場合に、申請により保険料の全額または一部の支払いが免除される仕組みです。免除の区分は、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得に応じて「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4段階があります。
免除が承認された期間は、将来の年金受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金額への反映は免除割合に応じて変わります(例:全額免除は納付した場合の1/2、3/4免除は5/8など)。そのため、未納よりは有利ですが、納付済期間よりは将来の年金額が少なくなります。
また、免除期間は障害年金や遺族年金の受給資格要件を満たすためにも有効です。経済的に困難な状況にある場合は、未納にせず免除制度を利用することが望ましいといえます。
免除申請を検討する際は、自分自身や世帯の所得状況を正確に把握し、必要に応じて年金事務所に相談することが大切です。
50歳未満が対象の「保険料納付猶予制度」
保険料納付猶予制度は、20歳以上50歳未満の国民年金第1号被保険者を対象とした制度で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予される仕組みです。
猶予期間は、将来の年金受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。ただし、猶予された保険料は原則10年以内に「追納」することができ、追納すれば将来の年金額に反映されます。
また、猶予期間中も障害年金や遺族年金の受給資格要件を満たす期間として扱われるため、万が一の際の保障につながります。
この制度は、特に20~40代で一時的に収入が不安定な人にとって、未納を防ぎ、将来の年金受給資格を確保するための重要な選択肢です。
学生のための「学生納付特例制度」
学生納付特例制度は、国民年金に加入している学生を対象とした制度です。本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生である期間の経済的負担を考慮した制度であり、この制度が承認された期間は、将来の年金受給資格期間には算入されます。ただし、老齢年金額には反映されません。納付が猶予された保険料は卒業後などに「追納」することで、将来の年金受給額を増やすことができます。
学生期間中に不慮の事故や病気で障害を負った場合も、障害年金の受給資格要件を満たす期間として扱われるため、安心して学業に専念できるのも大きなメリットです。
各制度の申請方法と相談窓口
国民年金保険料の免除・猶予制度を利用するためには、申請手続きが必要です。これらの制度の申請は、お住まいの市区町村の役場にある国民年金担当窓口、または最寄りの年金事務所で行うことができます。
申請に必要な書類は、申請書、所得を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の控えなど)、雇用保険受給資格者証の写し(失業の場合)など、制度や状況によって異なります。学生納付特例制度の場合は、学生証のコピーなども必要になります。
手続きを始める前に、まずは日本年金機構のWebサイトで最新の情報を確認するか、最寄りの年金事務所に電話で問い合わせて、自分の状況に合った制度や必要な書類について相談することをおすすめします。
申請が承認されるまでには一定の時間がかかる場合があるため、未納状態が続く前に早めに相談・申請を行うことが重要です。
国民年金の未納に関するQ&A
国民年金の未納に関してよくある質問とその回答をまとめました。不安や疑問の解消にお役立てください。
Q. 保険料免除による受給額の減額は後から取り戻せる?
はい、保険料免除や納付猶予によって将来の年金額が減額される分は、後から「追納」という制度を利用することで取り戻すことができます。
追納とは、承認された免除期間や納付猶予期間の保険料を、後から支払う仕組みで、追納することでその期間が将来の老齢基礎年金額に満額反映されます。
追納できるのは、免除・猶予期間の翌月から起算して10年以内です。ただし、免除や猶予から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算金が上乗せされるため、経済的に余裕ができた際には早めに追納を検討することが望ましいです。
なお、追納は「免除」や「猶予」の承認を受けた期間のみ対象であり、「未納期間」は追納の対象外となるため注意が必要です。
Q. 保険料を支払わない場合、バレないこともある?
いいえ、国民年金保険料の未納は、いずれ日本年金機構に把握されます。年金機構は、市区町村役場からの住民情報や税務署からの所得情報をもとに、加入者の状況を確認しているため、未納を隠し通すことはできません。
未納が続くと、まずは催告状や督促状の送付といった手続きが行われ、それでも納付がされない場合には財産調査が行われます。さらに、所得や財産があるにもかかわらず納付しないと判断された「特定対象者」については、最終的に預貯金や給与、不動産などの差押えが実施される可能性があります。
このように、未納を放置すればするほどリスクは高まり、差押えや信用への影響といった不利益につながるため、早期の対応が重要です。
Q. 免除の申請で承認されなかった場合、どうすればいい?
免除申請が承認されなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。まずは、不承認となった理由を確認しましょう。所得基準を満たしていない、必要書類の不足など、考えられる理由はいくつかあります。もしその後に状況が変わり、たとえば転職や失業によって所得が減少した場合には、改めて申請することで承認される可能性もあります。
まとめ
国民年金保険料の未納は、将来の年金受給額の減額、万が一の際の障害年金・遺族年金が受け取れないリスク、そして最終的には財産差し押さえに至るという、非常に深刻な結果を招く可能性があります。
しかし、経済的に支払いが困難な場合には、「保険料免除制度」「保険料納付猶予制度」「学生納付特例制度」といった公的な救済制度が用意されています。これらの制度を適切に利用することで、現在の経済的負担を軽減しつつ、将来の年金受給資格期間を確保し、いざという時の保障も維持することができます。また、免除や猶予を受けた期間の保険料は、後から「追納」することで将来の年金受給額を増やすことも可能です。
国民年金は、自分自身の老後だけでなく、現役世代の不測の事態にも備えるための重要な社会保障制度です。未納のまま放置せず、少しでも不安を感じたら、日本年金機構や市区町村の国民年金担当窓口に相談しましょう。早期に適切な対応を取ることが、自分や家族の将来を守るための第一歩となります。
【無料】年金だけで足りる?あなたの将来に必要なお金を3分で診断
国民年金の支払いが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
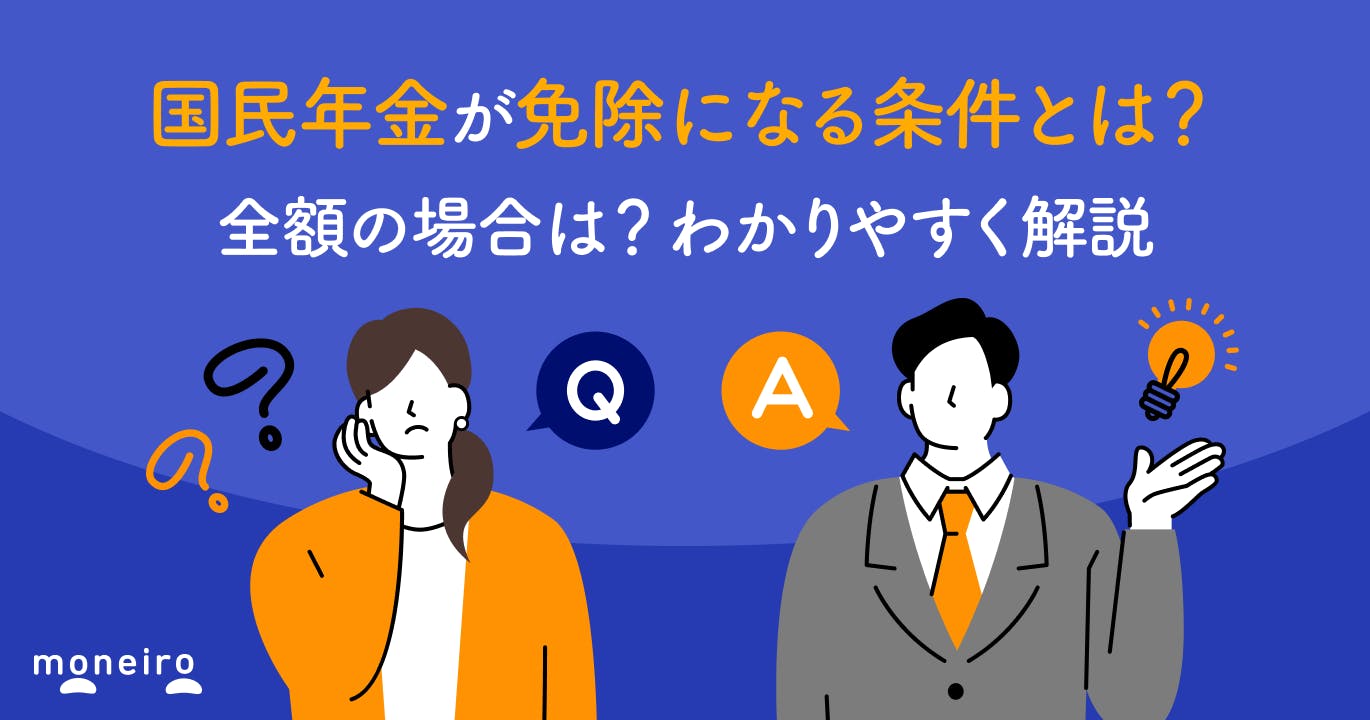
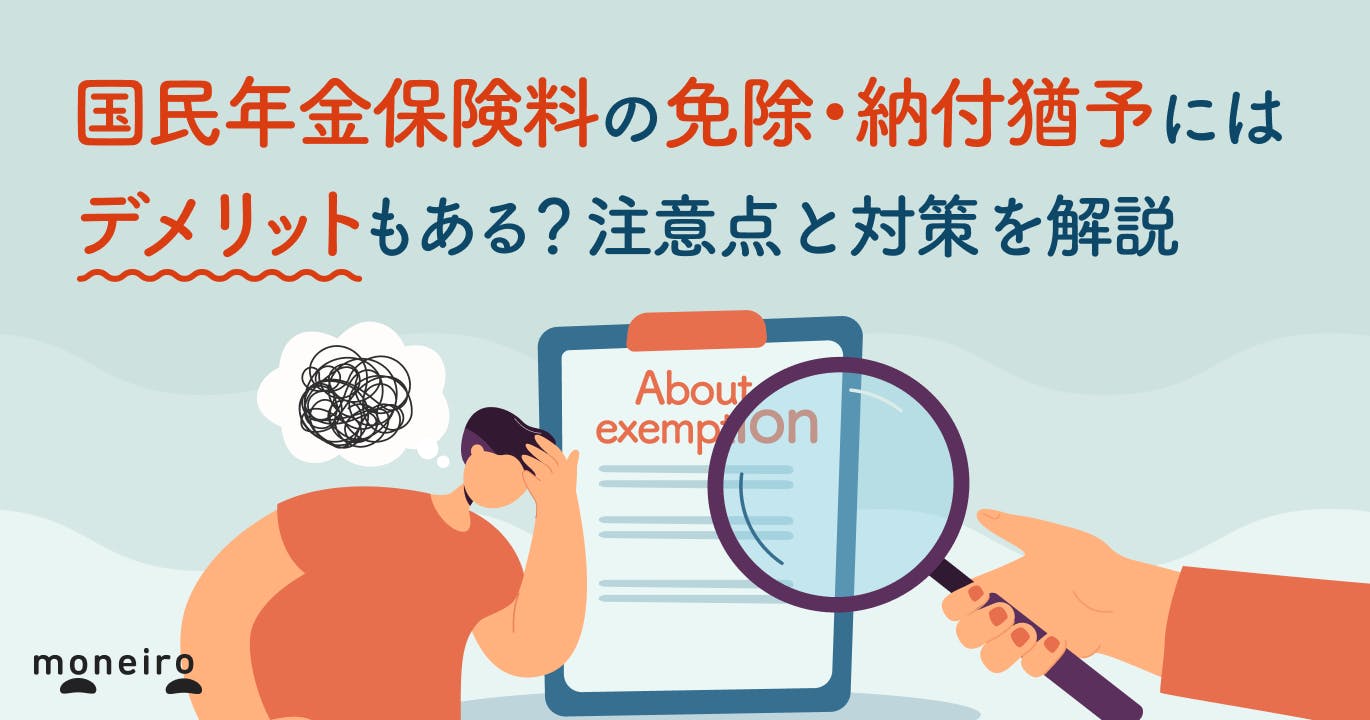
国民年金保険料の免除・納付猶予にはデメリットもある?注意点と対策を解説
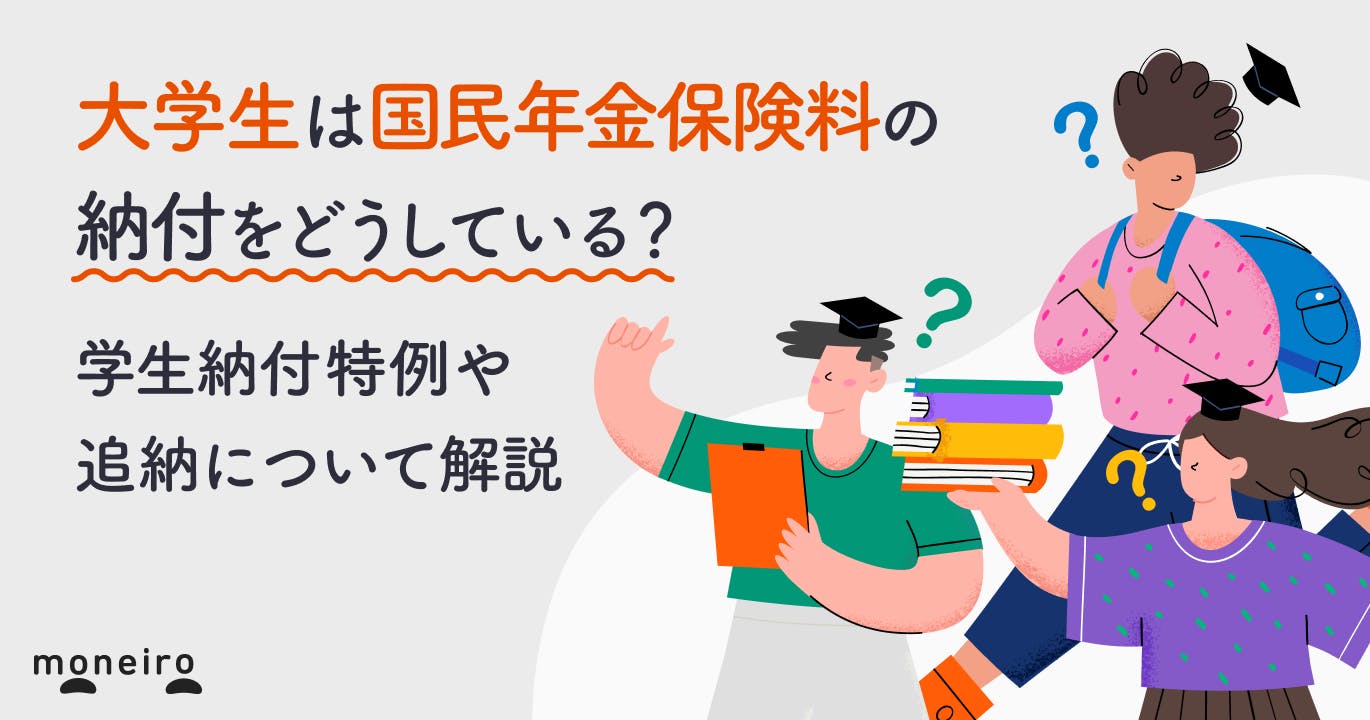
大学生は国民年金保険料の納付をどうしている?学生納付特例や追納について解説

国民年金を満額もらうには?条件と対策をわかりやすく解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。