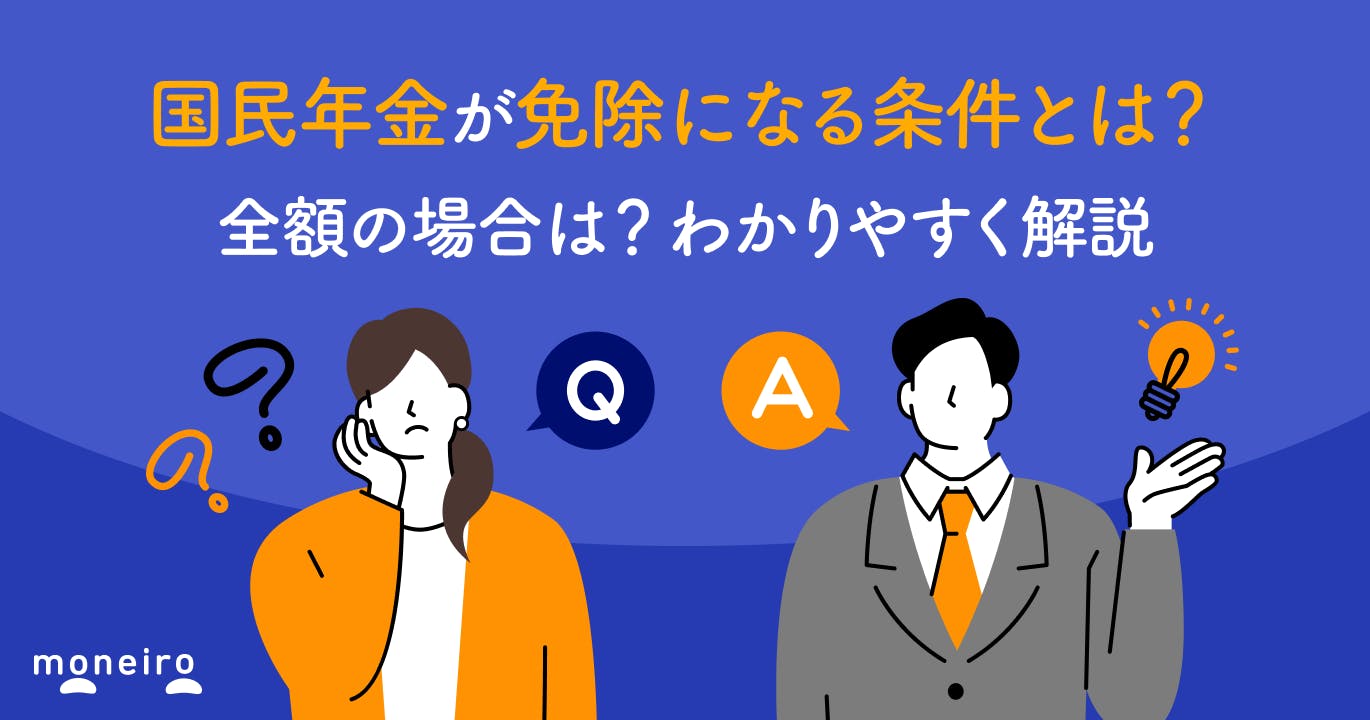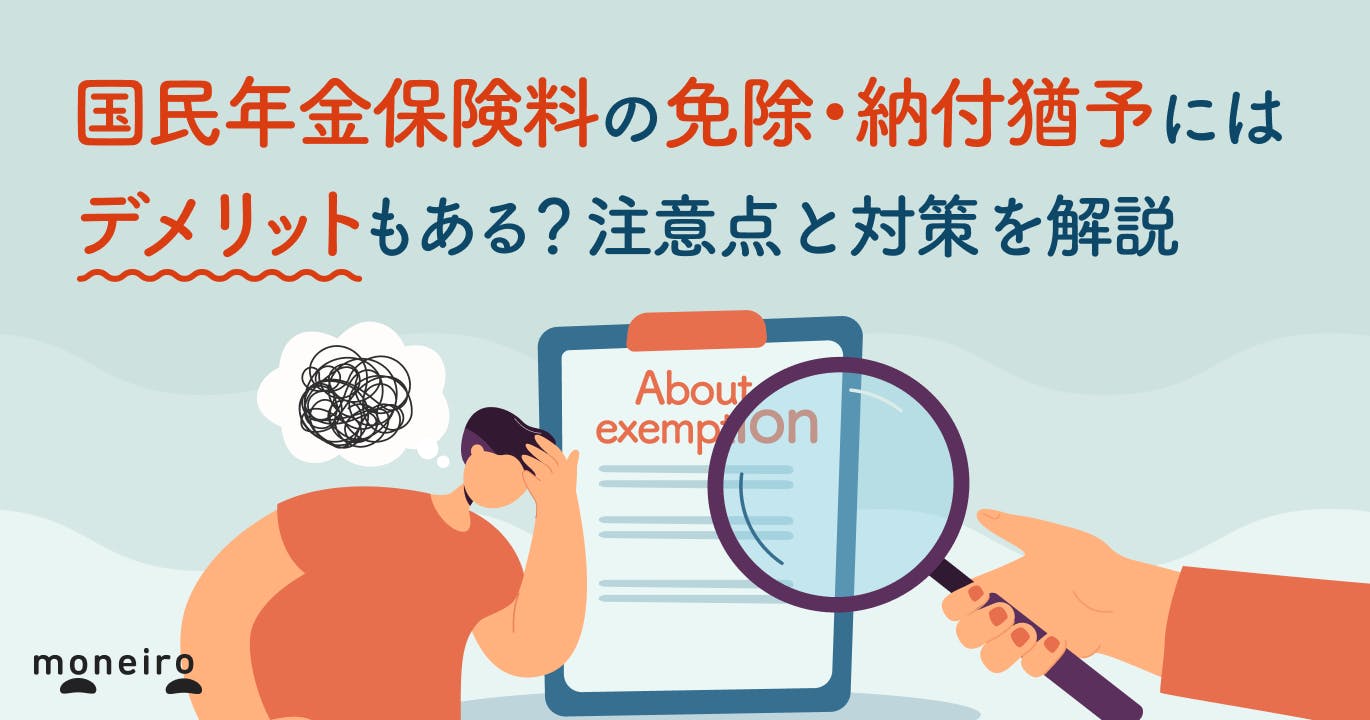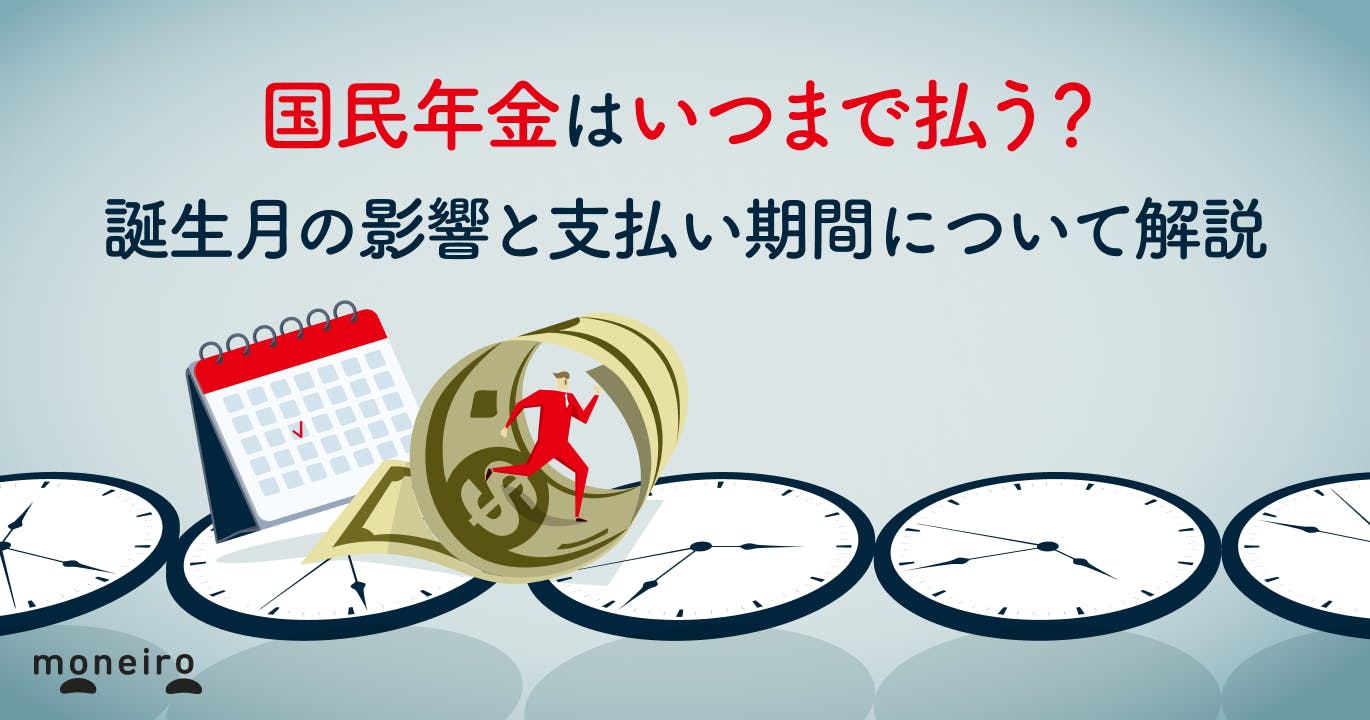
国民年金が免除になる条件とは?全額の場合は?わかりやすく解説
【無料】年金だけで老後資金は足りる?あなたの不足金額を3分で診断
国民年金保険料の支払いは、将来の年金受給のために重要ですが、経済的な理由で納付が困難になることもあります。
そのような状況で役立つのが、国民年金の免除制度・納付猶予制度です。ただし、この制度を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。この記事では、そんな国民年金の免除制度・納付猶予制度の条件を解説するとともに、各制度のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
- 国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度の条件と違い
- 年収基準や失業などの特例による免除・猶予の具体的な条件
- 国民年金保険料の免除・猶予を利用する際のメリットとデメリット
年金の支払いが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来不足する金額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金保険料の免除制度とは?
国民年金保険料の免除制度とは、経済的な理由などで保険料を納めることが難しい場合に、申請によって保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。この制度には、以下の4種類があります。
免除された期間は、将来の老齢基礎年金を受給する際の資格期間に算入されるだけでなく、一部または全額が納付済み期間として年金額に反映されるメリットがあります。ただし、免除の種類によって年金額への反映率は異なります。
納付猶予制度とは?免除との違い
納付猶予制度は、20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請によって保険料の納付が一時的に猶予される制度です。納付猶予制度と免除制度の主な違いは以下の通りです。
納付猶予制度を利用することで、経済的に苦しい期間の保険料納付を一時的に中断し、未納を防ぐことができます。猶予された保険料は、後から「追納」することで年金額に反映させることが可能です。
年金への反映はどうなる?
国民年金保険料の免除や猶予が年金受給額に与える影響は、制度の種類によって異なります。
免除・猶予期間の年金への反映
免除・猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。ただし、免除・猶予の種類に応じて、以下のように年金額が減額されます。
国民年金保険料の免除・猶予制度を利用すると年金額は減額されます。
ただし、免除・猶予が承認された期間の翌月から10年以内に「追納」することで、その期間の保険料を納めたことになり、年金額に反映させることができます。経済的に余裕が出てきたら、将来の備えとしてぜひ検討しましょう。
国民年金の免除・猶予を受けられる条件(年収基準)
国民年金保険料の免除や納付猶予を受けるにはいくつかの条件があります。詳しく見ていきましょう。
国民年金の免除・猶予を受けるための条件
対象者は、20歳以上50歳未満の国民年金第1号被保険者で、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件となります。
上記のように、一般的に所得が低いほど免除される割合は高くなります。また、所得基準を満たさない場合でも、次に説明する「特例等による免除・猶予制度」を利用できるケースがあります。
特例等による免除・猶予制度
特定の事情がある場合には、前年所得にかかわらず、国民年金保険料の免除・納付猶予を受けられることがあります。
失業等による特例免除
失業、倒産、事業の廃止などにより所得が減少した場合に適用される特例で、前年所得にかかわらず、国民年金保険料の免除を受けることができます。
これは、本人の意思に関わらず所得が失われた状況に対応するための制度であり、ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」や「離職票」などの証明書類が必要です。所得審査の代わりに、こうした書類によって失業等の事実を確認することで免除が認められます。
産前産後期間の免除制度
出産を予定している、または出産した国民年金第1号被保険者を対象とした免除制度です。出産前や出産後の経済的負担を軽減し、安心して子育てができるように支援することを目的としたもので、出産予定日または出産日を含む月の前月から4ヶ月間の期間の国民年金保険料が免除されます。
学生納付特例制度
大学、大学院、短大、専門学校などに在学している学生を対象とした制度です。学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。この制度を利用することで、学生期間中に保険料を納めることが難しい場合でも、年金の受給資格期間を確保できます。卒業後に追納することで、年金額に反映させることも可能です。
年金の支払いが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来不足する金額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
知っておきたい国民年金免除のメリット・デメリット
国民年金保険料の免除・猶予制度は、経済的な困難を抱える方にとって非常に有用な制度ですが、利用する上でのメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。
国民年金免除のメリット
国民年金免除制度を利用する主なメリットは以下の通りです。
経済的負担を軽減できる
もっとも直接的なメリットは、保険料の支払いが免除または猶予されることで、経済的な負担が大きく軽減される点です。
収入が不安定な時期や、急な出費があった際などに、生活費を圧迫することなく、国民年金制度に加入し続けることができます。これにより、生活の立て直しに集中することが可能になります。
免除・猶予期間も年金の受給資格期間に算入される
国民年金の老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上の受給資格期間が必要です。
免除や猶予が承認された期間は、実際に保険料を納付していなくても、この受給資格期間に算入されます。経済的に困難な時期であっても、将来的に年金を受け取る権利を失う心配が少なくなります。
障害年金や遺族年金の保険料納付要件を満たしやすい
国民年金には、病気やケガで障害の状態になった場合に支給される「障害基礎年金」や、加入者が亡くなった際にその遺族に支給される「遺族基礎年金」があります。これらの年金を受給するには、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料の免除期間や納付猶予期間であっても、これらの要件を確認する際には「納付済」として扱われるため、受給要件を満たしやすくなります。
国民年金免除のデメリット
一方で、国民年金免除制度にはいくつかのデメリットも存在します。
老齢基礎年金の受給額が減る
免除を受けても一定額が年金受給額に反映されますが、逆にいうと一定額が減額されるということでもあります。全額保険料を納付した場合に比べると、将来受け取る年金額が少なくなる点は、免除の最大のデメリットといえます。
また、納付猶予の期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。
追納しないと年金額が増えない
免除された保険料は、後から「追納」することで、満額納付した場合と同等の年金額に反映させることができます。追納は免除・猶予の承認翌月から10年以内に行う必要があります。追納を行わないと、免除期間に対応する年金額は低いままで、将来の年金額が増えることはありません。
なお、産前産後の免除期間については、追納しなくても保険料を全額納めたものとして扱われます。
付加年金や国民年金基金に加入できない
国民年金には、将来の年金額を増やすための「付加年金」や「国民年金基金」といった上乗せ制度があります。
しかし、国民年金保険料が免除・猶予されている期間中は、これらの制度に加入することはできません。これは、免除や猶予の制度が、あくまで基礎的な年金受給資格の確保を目的としており、年金の上乗せ部分までは対象としていないためです。
なお、産前産後期間については国民年金保険料は免除になりますが、希望により付加年金に加入して付加保険料を納めることができます。
国民年金の免除に関するよくある質問
国民年金保険料の免除制度について、よくある質問とその回答をまとめました。
Q. 自己都合による失業でも免除の申請はできる?
はい、自己都合による離職であっても、国民年金保険料の免除や納付猶予を申請することができ、また申請が認められる可能性もあります。
失業により所得が減少した場合は、「失業による特例免除」の対象となることがあります。なお、申請時には、ハローワークで発行される「離職票」や「雇用保険受給資格者証」などの書類の提出が必要になります。
Q. 国民年金の免除申請が却下されたらどうなる?
国民年金の免除申請が却下された場合は、通常通り保険料を納付しなければなりません。納付しない場合は「未納」となり、将来の年金受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されません。また、障害年金や遺族年金の受給にも影響が出る可能性があります。
なお、過去に免除が却下となった場合でも、その後の所得状況の変化などにより、再度申請できる場合があります。
Q. 国民年金の免除制度はニートでも利用できる?
はい、ニート(特定の職業に就かず、通学もしていない人)であっても、国民年金の免除制度を利用できます。
免除制度の条件は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下であることです。所得がない、あるいは少ない場合には、免除が認められる可能性がありますので、自身の状況に応じて、年金事務所や市区町村の窓口で相談し、申請を検討してみるとよいでしょう。
まとめ
国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度は、経済的な理由で保険料の納付が困難な方が、将来の年金受給資格を確保し、万一の際の障害年金や遺族年金を受け取るための重要なセーフティネットです。
所得基準に応じて免除にも種類がある他、失業、出産、学生といった特別な状況に対応する特例制度もあり、状況に応じて利用できます。
これらの制度の最大のメリットは、経済的負担を軽減しつつ、年金の受給資格期間に算入されることです。しかし、免除や猶予を受けた期間は、そのままでは将来の老齢基礎年金受給額が減少するというデメリットもあります。
将来にわたってより少しでも多くの年金を受け取るには、経済的に余裕ができた際に、免除・猶予期間の保険料を「追納」することが大切です。状況に合わせて制度を賢く活用し、安心して生活できる将来設計を立てましょう。
年金の支払いが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来不足する金額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。