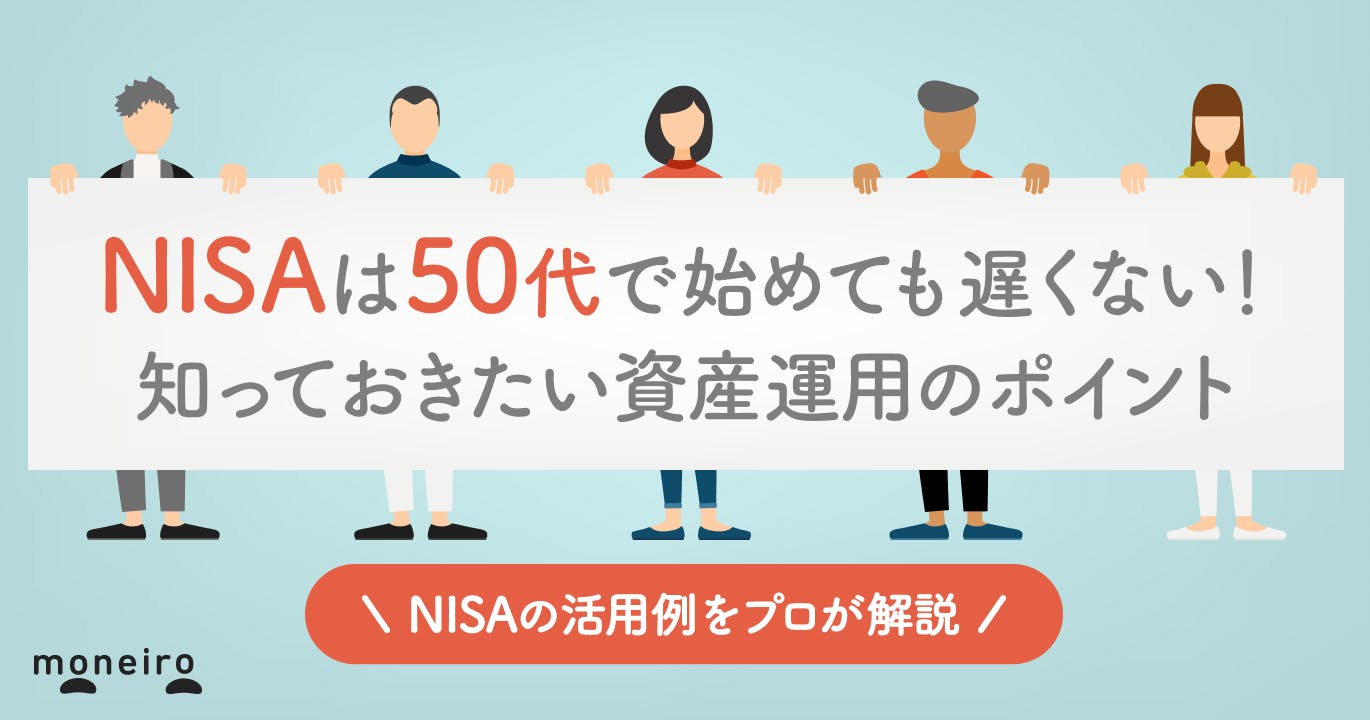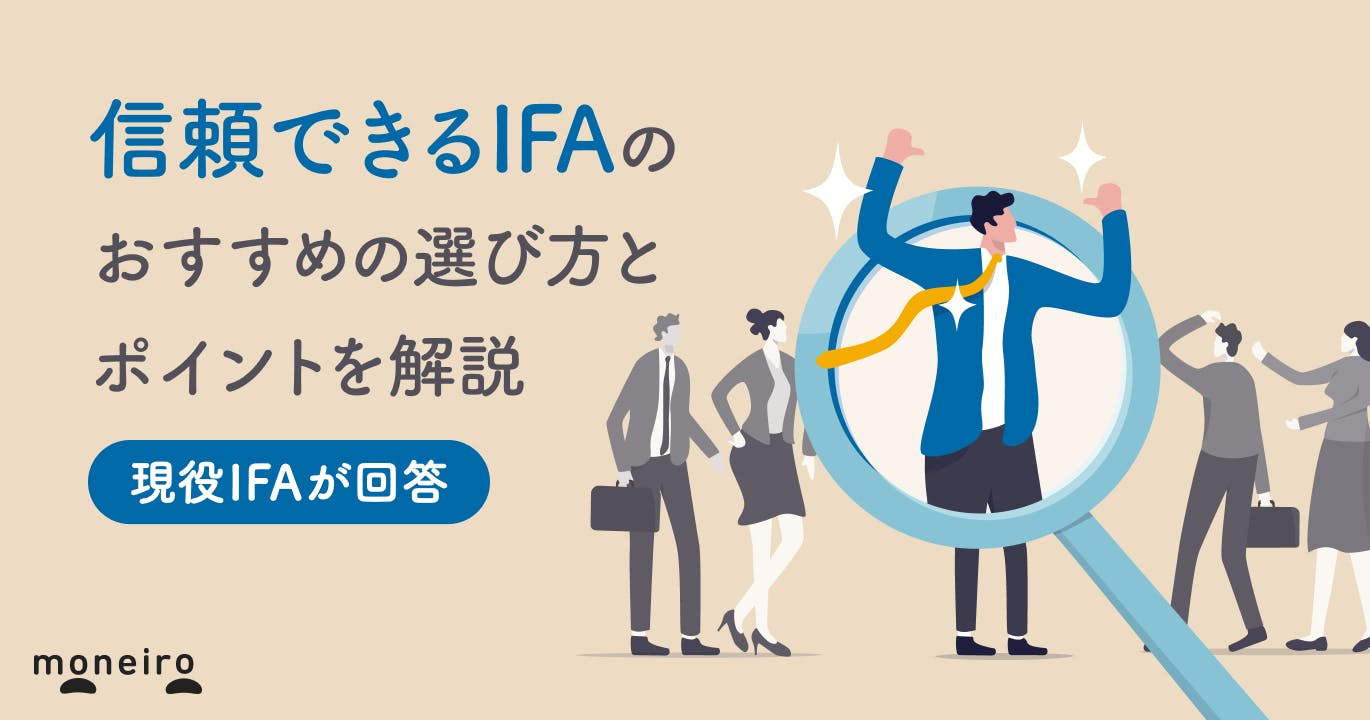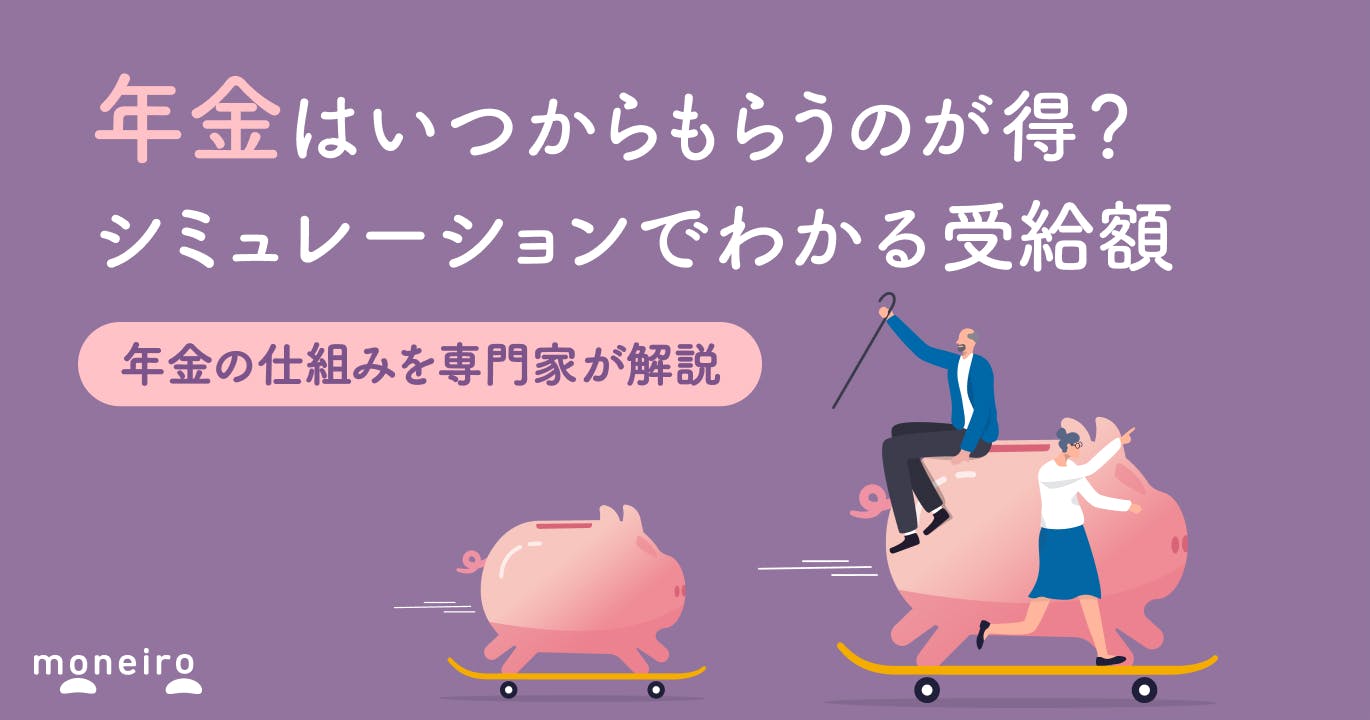50代でNISAを始めても遅くない理由は3つ!プロが運用のポイントと活用例を解説
»50代の資産運用、後悔しない選択を。まずは3分診断から
「50代からNISAを始めるのは遅い?」「50代から始めたら損をするのでは?」と、NISAを検討しつつも、今から始めても意味がないのではと思っている人も多いのではないでしょうか。
NISAを50代から始めても問題ありません。定年までの約10年を有効活用することで、お金を効率的に増やすことが期待できます。
また、NISAは非課税保有期間や投資可能期間(口座開設期間)に期限がないため、60歳以降も運用を続けることが可能です。
NISAはまとまった資金を活用したい人や、毎月の貯金の一部を積立投資に回したい人などにおすすめです。
本記事では「NISAを50代で始めるのは遅すぎ?」と悩んでいる人に向けて、NISAを始めるメリットや50代でおさえておきたい運用のポイントについて、投資のプロがわかりやすく解説します。
※本記事では2023年までのNISA制度を「旧NISA」または「旧制度」、2024年から始まった新しいNISAを「新NISA」または「新制度」と表記しています
- NISAは「まとまったお金を有効活用できる」などの理由から50代にもおすすめ
- NISAを50代で始めるなら「投資を長く続けられる環境を作る」「今後も成長が期待できる投資先を選ぶ」などのポイントをおさえて運用する
- 50代は資産を守りつつ「積立投資」と「一括投資」を組み合わせて運用することが大切
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
NISAは50代から始めても遅くない!おすすめの理由は3つ
2024年からNISAは非課税保有期間、投資可能期間の制限がなくなり、以前よりもさらに長期運用を目指せる制度となりました。
そのような中で「50代でNISAを始めても意味がないのでは?」と思っている人もいるかもしれませんが、50代にもNISAはおすすめです。
その理由について解説します。
理由①NISAはいつから始めてもメリットがある
NISAとは国民の資産形成を支援する制度として、2014年にスタートした「少額投資非課税制度」のことです。
2024年から運用されている現行制度では、非課税保有期間や口座開設期間の制限がなくなり、期限を気にすることなく、非課税のまま資産運用ができるようになりました。
始めたい時に始められ、長く運用ができる仕組みに改正されたことで、一生涯を通じた資産運用に取り組みやすくなっています。
そのため、若い世代だけでなく、50代にもメリットのある制度といえるでしょう。
少額から始められて、いつでも引き出しができる
NISAを通して購入できる金融商品は、主に投資信託やETF、株式などが対象です。
商品の種類や金融機関にもよりますが、これらの金融商品はネット証券を中心に、積立投資なら100円から、株式は1株からなど、少額での購入が可能になっています。
運用している資産は、必要であれば、いつでも売却し現金化することができます。
投資で得た売却益や分配金が非課税
通常、株式や投資信託などから得られる分配金や配当金、売却益には20.315%の税金がかかります。
例えば、一般口座や特定口座で株式に120万円投資をし、20万円の配当金、30万円の譲渡益を得た場合、合計で約10万円の税金を支払う必要があります。
一方、NISA口座を通じて上記と同じ投資を行った場合だと、これらの税金は支払わずに済むことになります。
非課税保有期間・投資可能期間に制限がない
NISAの非課税保有期間や投資可能期間(口座開設期間)には制限がありません。
運用に制限が設けられていないため、自分の好きなタイミングで投資を始めることができるだけでなく、老後に入ってからも運用を続けやすくなっています。
非課税の恩恵を受けながら投資を継続しつつ、ライフスタイルに合わせて資産を少しずつ取り崩して使うことも可能です。
理由②定年退職を迎えるまでの期間を活用できる
一般的に50代といえば、収入がピークを迎え、子育てや住宅ローンの支払いがひと段落する時期です。
老後に向けた資産形成をしやすくなることから、退職を迎えるまでの期間を上手く活用できるかが、お金を増やすポイントになるでしょう。
非課税の恩恵を受けられるNISAなら、効率的に資産運用を行うことができます。老後を迎えた後も非課税で運用を継続でき、運用しながら資産を取り崩して使うことも可能です。
50代から始めた場合のシミュレーション
毎月5万円を50歳から60歳までの10年間、年率3%で運用した場合、積み立てた元本は600万円、運用益は98万7071円となり、合計約700万円の資産を作ることができます。
NISA口座で運用すれば、運用益の98万7071円に対して税金はかかりません。そのため、利益をそのまま受け取ることができます。
上記はあくまでシミュレーションではありますが、お金を少しでも増やすには短い期間でも効率的な方法を用いることが大切です。
理由③まとまったお金を有効活用できる
一般的に、50代は平均収入や貯蓄額も高く、経済的に余裕のある年代です。子どもの教育費がかからなくなることも多く、まとまった資金を資産運用に回しやすいという強みもあります。
また、NISAはつみたて投資枠と成長投資枠の両枠を同時に活用することができます。
ある程度まとまった資金は、ローリスク・ローリターンの債券を含む投資信託等で運用し、リスクを抑えつつリターンを狙うなどの運用方法を試してみるのもひとつの方法です。
参考)50代のNISA利用率
<引用:NISA口座開設・利用状況調査結果(2023年9月30日現在)について|日本証券業協会>
日本証券業協会の「NISA口座開設・利用状況調査結果(2023年9月30日現在)について」によると、旧NISAでは、20代から40代はつみたてNISA口座を、50代以降では一般NISA口座を開設する割合が高いことがわかります。
旧NISAの利用状況ではありますが、50代以降になると、ある程度まとまった資金で運用できる方法を選ぶ傾向にあるようです。
(参考:NISA及びジュニアNISA口座開設・利用状況調査結果について | 日本証券業協会)
NISAを始める時の注意点
NISAは気軽に始められる制度ではありますが、以下の点に注意する必要があります。
元本保証ではないため、投資した額を下回ることがある
NISAでは、主に投資信託、ETF、株式などの金融商品を購入して運用を行います。
これらの金融商品は、株式市場や為替の動向、政治の状況など、さまざまな要因により、日々価格が変動します。そのため、元本は保証されていないことに注意が必要です。
リスクが高ければリターンも高くなりますが、老後を目前に控えた年代では、資産を減らさない運用を目指すことが重要になります。
投資を長く続けるためにも、自身のリスク許容度を適切に判断したうえで、商品選択を行うことが大切です。
自分で決めなければならない事項が多い
NISAは、投資初心者が投資を始める時に利用しやすい制度として広く認知されています。
しかし、実際には、自分に合った商品を選んだり、売却するタイミングを自分で判断する必要があったりと、投資に慣れていない初心者にとっては、ややハードルが高い制度であることは否めません。
自分ひとりで判断できない時、アドバイスを受けたい時は、FPやIFAなど投資に詳しい専門家に相談してみるのもひとつの方法です。
»IFAのマネイロコンシェルに無料相談
売却判断が難しい
NISAは非課税保有期間が無期限のため、投資初心者にとっては、むしろ売却判断が難しいというデメリットがあります。
売却時期に期限がないことで「すべての資産を一度に売却しても良いのか?」「無期限で資産を保有できるなら、もう少し売却時期を先延ばしにした方が良いのか?」など、自分の判断に迷いが生じる可能性があるためです。
NISAで運用する時、売却などの投資判断は自分で行う必要があります。売却に関する判断が難しいと感じる場合は、お金の専門家に相談してみるのも良いでしょう。
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
50代でNISAをやらないほうがいい人
50代でNISAをやらないほうがいい人の特徴は以下のとおりです。
そもそも余裕資金がない人
NISAを通じて購入できるのは株式、投資信託、ETF、REITなど、リスクのある商品です。したがって、運用期間中には利益が出ることもあれば、損失を抱えることもあります。
損失を抱えている状況下でお金が必要になった時、余裕資金がなければ、含み損を抱えている資産を取り崩して工面するしか方法がありません。このようなことは、できるだけ避けたいものです。
投資はあくまで余裕資金で行うことが基本です。緊急時に対応できる余裕資金を確保したうえで投資を始めるようにしましょう。
価格変動が許容できない・絶対に元本割れしたくない人
NISAでは、日々価格が上下する投資信託や株式などのリスク性金融商品に投資をすることになります。
そのため、運用中にリーマンショックのような大きな下落が起こると、自分の資産が大幅に減ることも考えられます。
絶対に元本割れをしたくないなど、元本割れが許容できない場合は、NISAも含め、値動きのある金融商品を用いた投資について再検討すべきかもしれません。
50代がNISAでおさえておきたい運用のポイント
50代がNISAで金融商品を運用する際のおさえておきたいポイントを解説します。
投資が続けられる仕組み作りをする
NISAは長期間投資をすることで資産を形成していくことが前提の制度です。この制度を上手に活用するために、長く運用を継続できる環境作りを整えておくことが大切です。
そのためには以下の2点について心がけましょう。
万一の時のために預金を確保する
50代は自身の健康だけでなく、親の健康状態にも不安を感じる人が多くなる世代です。
自身の病気に関する費用、親の介護費用など、思わぬ支出が生じることもあるため、万が一のために使えるお金を、生活費や投資に回すお金以外で準備しておきましょう。
余裕資金があれば、NISAで運用中の資産を取り崩す必要がなくなり、長期運用を実現しやすくなります。
病気に備えて保険に加入しておく
病気や怪我などで収入が減少すると、将来の生活への不安から、積立投資を途中で止めてしまうことも少なくありません。
しかし、投資は長期で行うことにより、分散投資や複利の効果を得ることができます。途中で止めてしまうと、リスクを抑えながら効率的にお金を増やすことができません。
せっかく始めた投資は、できるだけ継続することが大切です。万が一の事態が起こっても、自身の運用資産を大きく取り崩さないで済む方法を検討しておきましょう。
例えば、医療保険、就業不能保険などへ加入すれば、万が一のことが起こった場合に保険金を受け取ることができます。お金の不安が軽減するため、投資も継続しやすくなります。
今後も成長が期待できる商品を選ぶ
投資する金融商品は過去の運用成績を参考にして、一時的な下落はあっても長期的に右肩上がりに成長を続けているものを選ぶようにしましょう。
投資信託の場合なら、例えば、世界株式や米国株式の指数に連動するインデックスファンドなどが、長期間にわたり成長を続けている金融商品に挙げられます。
ただし、今後の成長が期待できるかどうかの判断は、自分だけでは難しい場合もあります。銘柄の選定など、投資に関することはFPやIFAなどに相談して、アドバイスを受けてみるのも良いでしょう。
»【初心者歓迎】IFAのマネイロコンシェルに無料相談
価格変動に動揺しない
投資初心者のやりがちな失敗の一つに「運用資産を短期間で売却すること」が挙げられます。
少しの利益が出たから売却することもあれば、株価が下落し焦って売却してしまうなど、いずれも価格変動に影響されて運用資産を売却してしまうケースです。
投資は長期運用をすることで複利を活かし、資産を大きく増やすことが期待できます。
短期的な売買を繰り返していては、将来受け取れるはずだった大きな利益を得る機会を失くすことにも繋がります。
運用を成功させたいのであれば、短期的な価格変動に動じないことがポイントです。20年〜30年の目線での長期運用をしっかり心がけておきましょう。
運用商品や売却時期に悩んだら専門家に相談する
運用を始める際や運用を開始した後でも、投資している資産の運用方法に悩んだら投資のプロに相談をしましょう。
投資のプロは、運用に関する専門的な知識を有しているため、現在の市況などに応じた適切なアドバイスを行うことができます。
具体的な相談相手としてはIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)がおすすめです。
IFAは特定の金融機関(証券会社、銀行など)に属していません。そのため、所属企業に影響されず、独立した立場で相談者のニーズに合った商品を提案することができます。
投資を始める前に、いつでも運用の相談ができるIFAを見つけておくと良いでしょう。
50代は資産を守りつつ運用することが大切
50代は年金生活が間近に迫っているため、資産を減らさず、守る運用を基本にすることが大切です。
リスクの高い金融商品だけでなく、債券の比率を高めたポートフォリオを組むことを意識しておきましょう。
NISAの具体的なポートフォリオの内訳としては、ハイパフォーマンスが期待できる世界株式、安定的な値動きが期待できる先進国の債券等をメインにして組み合わせるようにします。
各資産の割合に関しては、自身のリスク許容度や投資経験、また期待するリターンなどに応じて、調整することをおすすめします。
「毎月の積立投資」と「一括投資」の組み合わせる
50代の資産運用では「毎月の積立投資」と「まとまったお金の一括投資」を組み合わせてみるのも良いでしょう。
運用方法の異なる積立投資と一括投資を併用することで、それぞれの特徴を活かした効率的な資産運用が可能となるためです。
投資信託や株式などを、毎月決まった額で定期的に買付するのが積立投資です。
買付を長期的に継続することで、複利効果が尻上がりに高まり、元本割れなどの投資リスクを軽減することができます。
20年、30年以上など、長く運用ができるなら、ハイリターンが期待できる株式ファンド等に投資をすると資産が大きく増える可能性も高くなります。
積立投資では、資産を大きく増やしていくための運用を行うイメージで投資商品を選ぶことをおすすめします。
一方、一括投資は100万円、あるいは1000万円単位など、まとまったお金で金融商品を購入し運用する方法です。
50代が一括投資をする場合、まずは安全資産である債券や貯蓄型保険などを検討しましょう。
期待できるリターンは低くなりますが、500万円や1000万円など、まとまった資金で運用を行えば、ある程度のリターンが期待できます。
50代の投資は、特徴の異なる運用方法を併用してリスクを分散し、それぞれのメリットを活かした資産運用を心がけることが大切です。
50代のNISA活用例
50代でNISAを活用した事例について、詳しく見ていきましょう。
例:NISA(積立投資)と外貨建て債券(一括投資)
NISA(つみたて投資枠)と外貨建て債券を組み合わせて運用を行うと資産はいくらになるか、結果をシミュレーションしてみましょう。
NISAで毎月3万円、想定利回り5%の投資信託で10年間、積立運用すると、元本360万円に対し、約106万円の運用益が得られることがわかります。
一方、年利4%、償還までの期間が10年の外貨建て債券を300万円で一括投資した場合、投資したお金は約447万円になります。
10年間運用した結果、両方の資産の合計は約913万円になりました。あくまでシミュレーションではありますが、運用を行うことで資産が増える可能性が高まることがわかります。
(参考:資産運用シミュレーション : 金融庁)
(参考:資産運用かんたんシミュレーション|資産形成について|アセットマネジメントOne)
まとまったお金の運用方法に悩んだらマネイロに相談
「マネイロ」とは、証券会社や保険会社出身のお金の専門家に、投資や運用などお金に関する悩みや不安を相談できるサービスです。
マネイロでは投資の始め方から、投資を始めた後も運用に関する相談などをオンラインにて、無料で何度でも相談できます。
「これから投資を始めたいけど、知識がないから不安」という方は、マネイロで相談しながら安心して投資を始めてみてはいかがでしょうか。
»「老後に向けて、NISAを始めるべき?」そんな疑問もマネイロに相談できます
50代から始めるならNISAとiDeCo、どっち?
NISAとよく比べられる制度としてiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。iDeCoは私的年金制度のひとつで、NISAと同じく税制優遇が受けられます。
主な違いについて詳しく見ていきましょう。
iDeCoも国民年金任意加入者であれば65歳まで運用が可能
iDeCoは掛金を拠出できる期間が原則60歳までと制限がありました。しかし、2022年5月から以下の条件を満たす場合は65歳まで運用ができるようになりました。
- 60歳以降も会社員や公務員として働く65歳未満の人
- 任意加入被保険者として国民年金に加入している65歳未満の人
掛金を拠出できる期間が65歳までに延長したことで、企業に勤める人などは長く拠出できるようになりました。
そのため、節税効果を受けながら投資をしたい人は、iDeCoの活用も検討してみると良いでしょう。
NISAは投資可能期間に制限なく投資ができる
2023年までのNISAには、投資可能期間に期限があり、一般NISAで5年間、つみたてNISAは20年間と定められていました。
しかし、2024年からは投資可能期間に制限がなくなり、一生涯を通して投資ができるようになっています。
例えば、65歳で定年退職をした後、70歳であろうと80歳であろうと何歳までも投資を続けることができます。
年齢を気にせず非課税で長期投資ができる点は、NISAの大きな魅力といえるでしょう。
制限なく柔軟に運用したい場合はNISAがおすすめ
iDeCoは掛金の拠出が全額所得控除、運用中の利益が非課税、受け取り時にも控除を受けることができるなど、節税面でのメリットが大きい制度です。
しかし、iDeCoは掛金の拠出期間や資産の引き出しに制限があるため、運用において不自由を感じることも少なくありません。
一方、NISAは投資可能期間に制限もなく、いつでも資産を引き出すことができます。
利便性を重視して運用をしたい場合は、NISAがおすすめです。
50代のNISAに関するよくある質問
NISAに関するよくある質問について、投資のプロが回答します。
Q.運用の途中で死亡した場合はどうなる?
NISAで運用中に亡くなった場合、親族などの相続人は金融機関に対して速やかに死亡届を提出するなど、手続きを開始する必要があります。
所定の手続き後、亡くなった人がNISA口座で保有している資産は、相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に移管されます。
相続発生時点で運用益が発生していた分に関しては税金がかからず、非課税のまま受け取ることができます。
相続人がNISA口座を開設していたとしても、相続によって取得した株式や投資信託等を、そのまま相続人のNISA口座で受け入れることはできない点は注意が必要です。
Q.50代から資産運用、NISAとiDeCo以外でおすすめは?
50代がNISAやiDeCo以外で運用するなら、債券投資や貯蓄型保険も候補に入れておくと良いでしょう。
債券や貯蓄型保険を活用すれば、リスクを抑えながらまとまったお金を運用することができます。
ただし、人それぞれに適した金融商品や活用すべき制度は異なります。投資目的や資産状況に応じて、自分に合った運用商品を選ぶようにしましょう。
投資初心者は自分に適した金融商品や制度を見つけるのが難しい場合もあります。不安がある場合はFPやIFAなどに相談してみるのもひとつの方法です。
マネイロはSBI証券と提携しているIFA
50代からの資産づくりは、やみくもに始めないのが正解。マネイロなら無料で相談できます。
マネイロはSBI証券と提携しているIFAが、お客様のライフプランに合わせた資産運用のご提案を行ってます。
投資金額に関係なく専任がつくため、NISAの始め方だけではなく、運用後のサポートも行っています。
まずは現状の資産状況からプロと一緒に課題を見つけてみませんか?
マネイロの無料相談予約はこちらから▼
Q.NISAの始め方は?
NISAを始めるためには、証券会社や銀行などの金融機関でNISA口座を開設する必要があります。
口座開設には、運転免許証などの本人確認書類や個人番号が確認できるマイナンバーカードなどが必要です。
必要書類は金融機関によって異なる場合もあるので、NISA口座を開設する金融機関が決まったら、金融機関のHPなどで確認しておきましょう。
NISA口座を開設できる機関は1人につき1金融機関です。金融機関を変更したい場合は1年単位でしか変更できないため、金融機関選びは慎重に行いましょう。
まとめ
一般的に50代といえば、子育てが一段落つき、自分たちの老後に向けてお金を貯められるラストチャンスだと言われています。
若い頃と比べると収入も上がり、ある程度の貯蓄を有している人も多いでしょう。経済的に少しゆとりが出やすい年代だからこそ、資産運用の方法に悩む人も多いかもしれません。
資産運用について悩んでいる場合は、まずNISAを活用することを検討してみると良いでしょう。
2024年よりNISAは、年間投資可能上限額が増額し、投資可能期間が無期限となるなど、以前と比べて、より柔軟な活用ができる制度となりました。
定年退職までは投資をして、年金生活に入ったらNISAで運用中の資産を少しずつ取り崩しながら、生活費に充てたりすることも可能です。
非課税の恩恵を受けながら一生涯を通して長く運用したいという方は、50代のうちから賢くNISAを活用してみてはいかがでしょうか。
»NISAが向いているか、必要な老後資金で判断|無料診断はこちら
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
土屋 史恵
- ファイナンシャルプランナー/金融ライター/編集者
神戸市外国語大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。遺言信託など資産承継ビジネスに強み、表彰歴あり。その後は長年の金融機関勤務経験を活かし、金融メディアに転職。記事執筆や編集などを担当。現在はフリーランスとして活動中。AFP、FP2級、証券外務員一種を保有。
執筆
鶴田 綾
- ファイナンシャルアドバイザー
福岡女学院大学・人文学部英語学科卒。卒業後、日本郵便株式会社にてリテール営業に従事。投資信託や生命保険の販売では商品分析を得意とし、豊富な商品知識を持つ。現在はこれまでの金融商品の知識を生かし、Instagramを中心に、SNSにて資産運用のはじめ方や資産形成のコツについて積極的に情報発信をしている。一種外務員資格(証券外務員一種)、保険募集人資格などを保有。