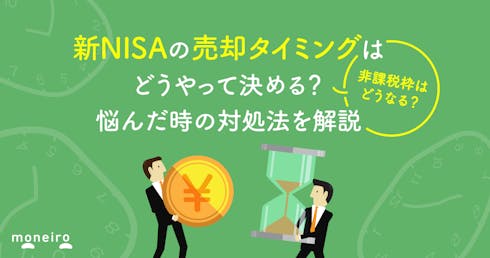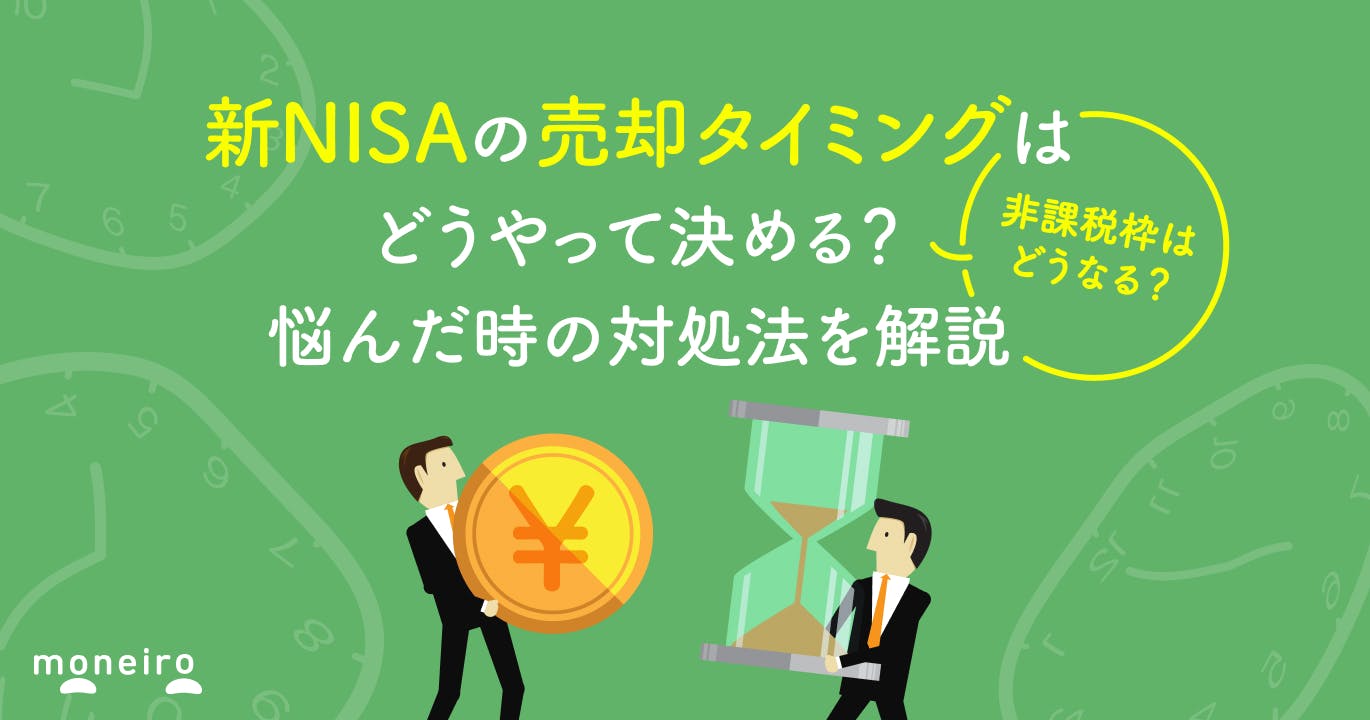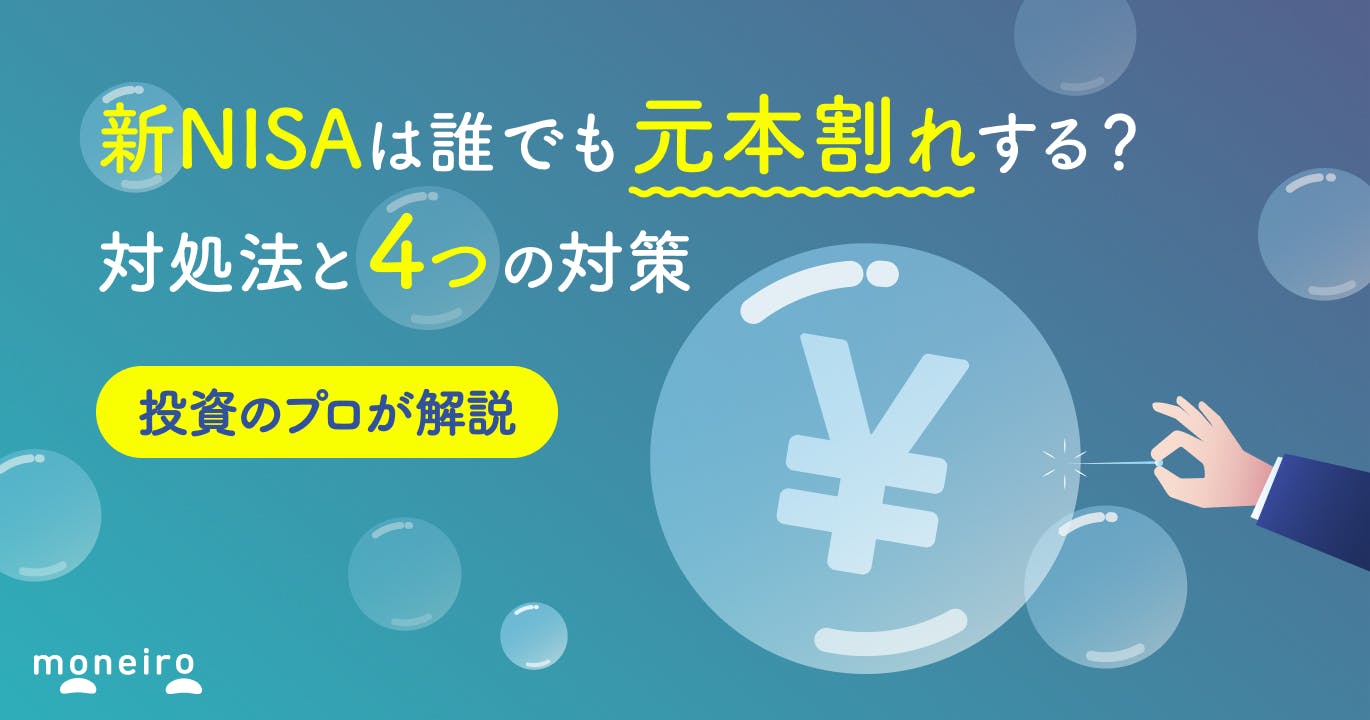NISAはデメリットしかない?失敗例から学ぶ初心者が損しないためのコツを解説
»NISAのデメリットが気になるなら、まず“自分に合うか”を診断
「NISAにはデメリットしかない?」「実はデメリットが多いのでは?」と、NISAのメリットだけではなく、デメリットについてしっかり把握しておきたいという人も多いのではないでしょうか。
NISAは少額から投資ができる少額投資非課税制度です。2024年から非課税保有期間や口座開設期間(投資可能期間)に制限がなくなり、よりメリットが増えた制度となりました。
一方で、実は意外と知られていないデメリットがいくつかあります。
本記事では「NISAって本当はデメリットしかないのでは?」と思っている人に向けて、主なデメリットと起こりやすい失敗例、損しないためのコツについて投資のプロがわかりやすく解説します。
※本記事では2023年までのNISA制度を「旧NISA」、2024年からのNISAを「新NISA」「NISA」と表記しています
- NISAは「自分で判断しなければならない場面が多い」「節税メリットが意外と少ない」などの点からデメリットしかないと言われている
- NISAで投資初心者が起こしやすい失敗例は「価格変動に動揺してすぐ売却してしまった」「成長が期待できない資産に投資してしまう」など
- NISAで損しないためのコツは「長期運用を心がける」「非課税枠の利用状況を確認する」など
NISAが気になるあなたへ
マネイロでは「あなた自身がNISAをすべきか」を判断できるよう、さまざまな無料サービスを提供しています。
▶NISAオンライン相談:専門家にスマホで直接相談
▶3分投資診断:あなたと相性良い投資がわかる
▶NISAで始める資産運用《基本編》:専門家が解説する30分のWebセミナー

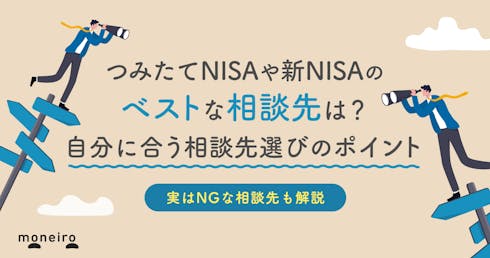
NISAとはどんな制度?
NISAは、株式や投資信託を利用した少額投資非課税制度です。NISAのメリットは投資で得た利益や分配金が非課税になることです。
通常の証券口座では、投資して売却益が出た場合、その利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAではこの税金はかかりません。
2024年からは、NISAが大幅に改良され、非課税の保有期間や投資可能期間に制限がなくなり、投資できる金額も増えました。
旧NISAと新NISAの比較
2024年からのNISA(新NISA:新しいNISA)では、非課税保有期間が無制限になり、同時に投資可能な金額も大幅に拡大されました。これにより、投資家はより柔軟かつ長期的な運用ができるようになりました。
以前のNISAと比べて新NISAは投資の自由度が高まりましたが、一方で、投資判断の難易度も上がりました。
初心者でも始めやすいNISAですが、金融商品や売却判断など、自身のリスク許容度や目標に合った選択をする必要があります。
iDeCoとの違い
iDeCoは、積立金額が所得控除の対象となり、節税の効果が期待できます。
ただし、iDeCoでの掛金の上限額は国民年金やその他年金の加入状況によって異なるため、始める前に確認すると良いでしょう。
NISAとは異なり、iDeCoは主に将来の年金作りを目的とした制度です。そのため、原則として60歳まで引き出すことができません。
この点がiDeCoのデメリットとなりますが、一方で税制面での優遇措置があるため、将来の年金収入の安定化を図るうえで有益な選択肢といえます。

一般の投資信託との違い
上記は新NISAのつみたて投資枠(新NISA口座)で投資信託利用した場合と、一般口座・特定口座で投資信託を利用した場合の比較図です。
一般の投資信託に投資する場合は、売却時に利益に対して20.315%課税されますが、NISA制度よりも投資できる商品が多く、投資金額に制限がないため、より自由に売買できます。
一方、NISAの場合、投資対象商品や投資上限額に制限があるものの、税制上の優遇を享受しながら柔軟な運用が可能です。

NISAの主なメリット
NISAの主なメリットについて見ていきましょう。
①少額から投資ができる
NISAは100円や1000円など、少額から投資できます。最低金額は金融機関によって異なるため、確認しましょう。
つみたて投資枠と成長投資枠、どちらの枠でも少額から投資が始められます。
②配当金や売却益が非課税
NISAの成長投資枠やつみたて投資枠を利用して投資信託を購入する際には、分配金が非課税となります。
また、成長投資枠を使用して株式を購入する場合には、その配当金も非課税となります。
NISA口座内の配当金を非課税にするためには、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があるため注意しましょう(※)。
※(参考:よくあるご質問 FAQ|SBI証券)
NISAで投資した商品の値上がり益もすべて非課税となります。
そのため、NISAを活用することで、投資によって生じた収益や資産の増加に対して税金がかからないメリットがあります。
③非課税保有期間が無期限
NISAでは、一度投資した資産が一生涯非課税となるため、長期運用をすることで非課税メリットが大きくなります。
④1800万円まで投資ができる
NISAでは、一生涯で1800万円まで投資が可能です。このうち、成長投資枠の上限は1200万円までと決められています。
一方で、つみたて投資枠のみを活用する場合は、全額1800万円を投資することができます。
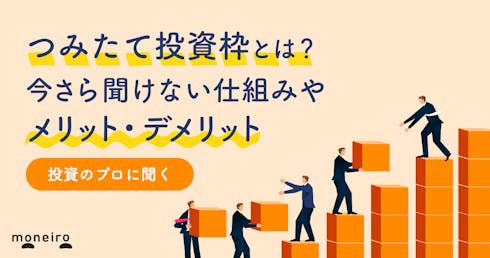

⑤投資枠を併用できる
成長投資枠とつみたて投資枠は併用することができます。
成長投資枠は年間240万円まで、つみたて投資枠は年間120万円までです。投資枠を併用すると年間360万円まで投資ができます。
それぞれ投資できる対象が異なるため、枠を併用して値動きの異なる商品に分散投資することがポイントです。
⑥いつでも引き出し可能
NISAはいつでも現金で引き出すことができます。
売却の手続き後、投資商品が現金に戻ったら指定口座へ振込し、引き出せます。
投資商品によっては現金に戻るまでの日数が異なるため、急な入用の場合は確認しましょう。

NISAはデメリットしかない?意外な4つのデメリット
「NISAにはどんなデメリットがある?」「NISAを利用するうえでどんなことに気をつければ良い?」と不安になっている人に向けて、知っておきたいデメリットについて解説します。
①元本保証ではなく、投資した額を下回る可能性がある
自由度の高いNISAですが、あくまで元本保証ではありません。運用中に投資した額よりも下回る可能性も充分にあります。
特に、短期間の運用では値段の上下は予測しづらいため、元本割れする可能性が高まります。
できるだけ元本割れを防ぎたい場合は、長期間の運用を心がけましょう。
②自分で判断しなければならない場面が多い
NISAは金融機関、投資する商品など、自分で判断しなければならない場面が多い制度です。
NISAは多くの金融機関で気軽に始められる制度ではありますが、金融機関によって投資できる商品やポイントサービス、決済方法などが異なります。
途中で金融機関変更はできるものの手続きに時間もかかるため、まずは自分に合った金融機関を選びましょう。
開設後は多くの投資商品の中から、投資先を選ぶ必要があります。
どの商品を選べば良いかわからないという人は、投資経験のある専門家に相談するのも一案です。

NISAのデメリットが気になる方へ
・3分投資診断|NISAがあなたに合うか無料で診断
・NISAの基本セミナー|基本を30分で解説。無料のオンラインセミナー
③実は売却判断が難しい
NISAは非課税期間が無期限化されたことから、売却するタイミングは自分次第となります。
そのため、投資したらそのままではなく、自分のライフプランに合わせて売却手続きをする必要があります。
自分が使いたいタイミングと、投資商品の値上がりタイミングが一致するとは限りません。
NISAを始めたら、定期的に値動きを確認しましょう。
④節税メリットが意外と少ない
iDeCoに比べると、節税のメリットは意外と少ないです。iDeCoは運用成果に関係なく、拠出(積立)しただけで控除のメリットが受けられます。
一方、NISAにおける節税メリットは、あくまで運用が上手くいって利益が出た場合のみです。
運用に失敗して元本割れした場合は、そもそも課税される対象の利益がないため、非課税効果は受けられない点に注意しましょう。
NISAで起こりやすい失敗例と損しないためのコツ
初心者がNISAで起こしやすい失敗例と、なるべく損しないためのポイントについてプロが解説します。
失敗例:価格変動に動揺し、すぐに売却してしまった
株式や投資信託などは元本保証ではないため、日々価格が大きく変動します。頭でわかっていても、いざ価格が動くと心配になる人も多いでしょう。
そのため、初めて投資する場合や投資経験があまりない場合は、まず少額から始めて徐々に金額を増やすことをおすすめします。
また、すぐに売却すると、本来長期間運用で見込めるはずだった利益を得ることができなくなります。
価格変動に動揺せずに、なるべく長期運用することを心がけるようにしましょう。
失敗例:成長が見込めない資産に投資していた
成長が見込めない資産に投資をした場合、期待していた利益が出ず、さらにNISAの非課税メリットを活かすことができません。
特に、成長投資枠で個別株式に投資する場合、タイミングや銘柄選びは難しいです。
また、投資信託でプロに運用をお任せできるといっても、どんな投資信託を選ぶかがポイントになります。
運用期間が長く確保できる場合は、成長が見込める地域の株式型投資信託を選ぶと利益が期待できるでしょう。

失敗例:非課税枠内でスイッチングができると思って売却してしまった
旧NISAでは非課税枠が復活せず、売却後はそのまま消費する仕組みでしたが、2024年からの新NISAでは非課税枠が復活します。
そのため、商品の買い換えが気軽にできるようになりました。しかし、非課税枠が復活するのは翌年になるため注意しましょう。
例えば、NISAで投資した商品を売却し、売却した分の非課税枠で他の商品に買い替える場合、年内にすぐ切り替えることはできません。
運用する際は非課税枠の利用状況を確認することをおすすめします。

失敗例:旧NISAの資産を新NISAにロールオーバーしようとしてできなかった
旧NISAのつみたてNISAや一般NISAを活用している場合、非課税保有期間に制限があります。
非課税保有期間が終了するタイミングで、新NISAにそのまま移動(ロールオーバー)することはできないため注意が必要です。
旧NISAの資産を新NISAに移したい場合、一度売却をして、その分を新NISA枠で新たに投資する流れになります。
旧NISAの運用を続けている人は、非課税保有期間がいつ終わるのか、あらかじめ把握しておきましょう。
NISAはこんな人におすすめ
NISAのデメリット・注意点をふまえたうえで、どんな人におすすめできるのかプロが解説いたします。
少額から積立投資を始めてみたい人
NISAは「投資を始めてみたいが、まず少額からお試しでやってみたい」という人に向いています。
金融機関によって最低投資金額が決められているため、確認してから口座開設しましょう。
積立投資は、無理ない資金で続けられるほか、時間を分散して投資する分、元本割れリスクが下がるというメリットもあります。
まずは少額から投資を始めて、投資に慣れることをおすすめします。
NISAのデメリットが気になる方へ
・3分投資診断|NISAがあなたに合うか無料で診断
・NISAの基本セミナー|基本を30分で解説。無料のオンラインセミナー
長期積立でコツコツお金を増やしたい人
NISAは非課税保有期間の無期限化によって長期間の投資が可能となりました。そのため、将来に向けてじっくりコツコツお金を増やしたい人にとって向いています。
長い期間運用が続けられる人ほど、大きな利益を受け取れる可能性があります。
目標金額や運用目的を明確にすると、より続けられる可能性が高まるでしょう。
柔軟に運用したい人
NISAのメリットは、投資の柔軟性が高いことです。投資金額を変更したり、ストップしたり、引き出したりすることは柔軟にできます。
その点、掛金の金額が年1回しか変えられない、原則60歳まで資産の引き出しができないiDeCoよりも、投資を始めるうえでのハードルが低いといえるでしょう。
NISAに関する初心者の疑問にプロが回答
NISAは自分で判断することが多い分、さまざまな疑問が生まれます。投資のプロがよくある初心者の疑問に回答します。
Q.どこでNISAを始めるのがベスト?
NISAは、ほとんどの金融機関で取り扱いがあります。ただし、金融機関によって最低限投資できる金額、投資できる商品が異なるため、HPなどで確認すると良いでしょう。
また、銀行か証券会社、ネットか店舗でそれぞれメリット・デメリットがあります。
プロに相談しながら始めたい場合は、ネット証券ではなく店舗型の銀行や証券会社が良いでしょう。
一方で、「手軽に始めたい」「ある程度自分で手続きができる」など、Web上で手続きを済ませたい場合などはネット証券がおすすめです。

マネイロはネット証券+プロに相談しながら始められる
マネイロでは、豊富なラインナップから商品が選べるネット証券と提携しています。
また、お金のプロに相談しながら口座開設から銘柄選びまでサポートを受けながら始めることができます。
口座開設やサポート自体は無料のため、安心してご利用いただけます。
マネイロの無料相談予約はこちらから▼
Q.商品はどうやって選べば良い?
運用商品を選ぶ際は、基本的に成長が期待できる資産を選ぶことが大切です。
まずは、過去の運用実績を見てどれくらい増えているか確認しましょう。
投資先にこだわりがなく、ある程度リスクを許容できる場合は、世界に分散できる株式型の投資信託が良いでしょう。
ただし、株式型の投資信託は変動が大きいため、あくまで長期間の運用を目指しましょう。
Q.成長投資枠とつみたて投資枠、どっちが良い?
基本的にはつみたて投資枠で積立投資することがおすすめです。
つみたて投資枠で投資できる商品は、金融庁の基準を満たしたコストの低い長期投資に向いている商品です。
これまで貯めた貯金も投資したい場合は、成長投資枠を活用することも選択肢となります。
ただし、一括投資はリスクが大きいため、一人で決めずプロに相談しながら慎重に選ぶことがポイントです。

Q.売却タイミングで悩んだらどうすれば良い?
売却タイミングに悩んだら、投資の目的や目標金額を思い出しましょう。
資金の使い道までまだ時間があるのであれば、しばらく運用を続けた方が良いです。
仮に、ライフプランの変更などで近々資金の使い道がありそうであれば、今売却すべきかどうかプロに相談してみましょう。
始めるタイミングや売却のタイミングは、ライフプランが左右します。
ライフプランをなるべく具体的に立てておくことは、運用を効果的に行う大切なポイントです。
NISAを始めるなら!おすすめの証券会社
NISAを始めるにはまずは証券口座の開設が必要です。
「どこの証券会社がいいのかわからない」という方に向けて、おすすめの証券会社を紹介します。
SBI証券
SBI証券のNISA では、国内株式売買、海外ETF買付、投資信託の取引手数料が無料です。そのため、NISAの特徴である非課税のメリットを、最大限に活用できます。
また、三井住友カードと提携しているため、一度設定してしまえばクレジットカードで投資信託を毎月自動で積み立てることが可能。もちろん、Vポイントを貯めることもできます。
コストをかけずにNISAを始めたい方に、おすすめの証券会社です。
楽天証券
楽天グループのサービスを活用している人であれば、楽天カードでのクレカ積立もできるため、資産運用をしながらポイントを貯められます。
さらに、貯めたポイントで商品を買い付けることもできるので、投資初心者の方でも気軽にはじめられるのも魅力の1つです。
また、楽天証券で口座開設をすると、日経テレコンが無料で読めるため、情報収集もしやすいのも嬉しいポイントです。
まとめ
NISAにはデメリットや注意点もありますが、使い方次第で非常にメリットの大きい制度です。
NISAの注意点を理解したうえで、積極的に活用していきましょう。
NISAに限らず資産運用においては運用の目的や目標を作ることが大切です。目的や目標によってはNISAだけではなく、他の運用方法も選択肢となります。
目標設定や商品選びに悩んでいる方は、投資のプロに相談してみてはいかがでしょうか。
また、「NISAはデメリットが多い」と感じるのは、投資方針が整理できていないだけかもしれません無理なく続けられる運用かどうかは、年齢・収入・必要額によって変わります。
3分投資診断なら、老後必要額と最適な投資スタイルを自動で提案します。NISAを始めるか迷っている人に最適です。
»老後必要額とあなたに合う投資方針を3分で診断(無料)
NISAが気になるあなたへ
マネイロでは「あなた自身がNISAをすべきか」を判断できるよう、さまざまな無料サービスを提供しています。
▶NISAオンライン相談:専門家にスマホで直接相談
▶3分投資診断:あなたと相性良い投資がわかる
▶NISAで始める資産運用《基本編》:専門家が解説する30分のWebセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
西森 遥
- ファイナンシャルアドバイザー
都留文科大学卒。大和証券株式会社にて、主にリテール営業に従事。株式、投資信託の販売など、資産運用コンサルティング業務に携わる。現在は個人向け資産運用会社にて、運用に関するコンサルティング業務を行っている。顧客に寄り添う営業をモットーとし、特に若い世代へ資産運用の必要性を伝えるべく、日々精力的に活動中。外務員一種保有。
.jpg?auto=format,compress&fit=max&w=3840)