
不労所得とは?リスク別11種類&メリット・デメリットを解説
>>あなたはいくら必要?将来の不足額を3分で診断
「不労所得とは?」「どんな種類があるの?」という疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、不労所得の正しい定義やよくある誤解、さらに不労所得の種類を「低リスク」「中リスク」「高リスク」に分けて全11種類ご紹介します。
この記事を読んで、ご自身のライフスタイルやリスク許容度に合った不労所得への第一歩を踏み出しましょう。
- 不労所得に関するよくある誤解と本当の意味
- 不労所得を得ることで享受できるメリットと、留意すべきデメリット
- リスク別の不労所得11種類と具体的な方法
不労所得が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、どれくらいの不労所得が必要か、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
不労所得とは?よくある誤解と本当の意味
不労所得という言葉を聞くと、「完全に何もしなくてもお金が入ってくる状態」をイメージするかもしれません。しかし、これは不労所得に対するよくある誤解の一つです。
不労所得とは、「完全に働かない収入」というよりは「労働時間に対して収入の比率が非常に高い収入」のことを指します。例えば、一度ブログの記事を作成したり、システムを構築したりすれば、その後の追加的な労働時間が少なくても収益が発生し続けるような仕組みがその代表的なものです。
ただし、注意すべき点として、不労所得であっても初期投資や資産の管理、市場を把握するための勉強など、「見えない労働」が必ず存在します。そのため、不労所得とは、労働から完全に解放される収入ではなく、時間と場所の制約を受けにくい仕組みから生まれる収入と定義するのが適切です。
不労所得のメリット
不労所得を確立することで、生活やキャリアの選択肢が大きく広がります。ここでは、不労所得の主なメリットを解説します。
仕組みを作れば、働かなくても収入が得られる
不労所得の最大の魅力は、自分が病気で働けない時や、旅行などで仕事から離れている時間でも、安定的に収入が発生する点です。
一般的な労働(労働集約型の収入)の場合、働いた時間や成果に応じて報酬が得られますが、不労所得はシステムや資産が自動的に価値を生み出すため、身体的な労働を必要としないことがほとんどです。これにより、急なライフイベントや体調不良に備えるセーフティネットとして機能します。
収入源を分散できる
会社からの給与のみに頼っていると、もし会社が倒産したり、リストラに遭ったりした場合、生活基盤が崩壊するリスクがあります。不労所得を持つことは、給与所得以外の収入の柱を持つこと、つまり収入源を分散させることを意味します。
複数の収入源を持つことで、1つが不安定になった場合でも、別の収入源でカバーできるため、経済的な安定性が高まります。これは、リスク管理の観点からも非常に重要です。
時間の自由が増える
不労所得によって生活費を賄えるようになると、必ずしも時間や場所に縛られる仕事を選ぶ必要がなくなります。これにより、自分の時間を自由に使えるようになります。
例えば、家族との時間を増やしたり、趣味に没頭したり、あるいはさらに別の投資や学習に時間を費やしたりすることができます。時間の自由が増えることは、人生の幸福度を大きく向上させる要因となります。
自動的に資産が増える仕組みを作れる
不労所得の多くは、投資や資産運用を通じて得られます。これは、得られた利益を再投資することで、元本が雪だるま式に増えていく「複利」の力を利用できることを意味します。
労働による収入は時間的な上限がありますが、資産が生み出す不労所得には上限がなく、自動的に資産が増大する仕組みを一度構築してしまえば、長期的に見て効率よく資産を形成することが可能です。
不労所得のデメリット
不労所得は魅力的ですが、メリットばかりではありません。仕組みを構築する際には、以下のデメリットやリスクも理解しておく必要があります。
初期投資や準備が必要
多くの不労所得の仕組みを構築するには、まとまった初期投資が必要となります。例えば、不動産投資であれば数百万円から数千万円の資金が必要ですし、株式投資や債券投資を行うにも、元となる資産が必要です。
また、資金だけでなく、収益を生み出すブログやYouTubeチャンネルを立ち上げる場合は、多くの時間と労力をかけた準備期間が必要となります。
安定的な収入にはなりにくい
給与所得と異なり、不労所得は景気の変動や市場の状況に大きく左右されるため、必ずしも安定的な収入になるとは限りません。
株式の配当金や不動産の家賃収入は、経済状況や需要の変化によって減少したり、途絶えたりするリスクがあります。特に初期の段階では、収入が不安定になりやすく、生活費を完全に不労所得だけで賄うのは難しいケースが多いといえます。
維持・管理の手間がかかる
「完全放置」で収益が継続するケースは非常に稀です。不労所得を得る仕組みを維持するためには、ある程度の管理やメンテナンスが必要です。
例えば、不動産投資であれば入居者対応や建物の修繕、ブログ運営であれば記事の更新やサーバーの管理など、定期的な手間が発生します。この維持・管理を怠ると、収益性が低下する可能性があります。
短期的には結果が出にくい
不労所得の仕組みは、一朝一夕で完成するものではありません。特にブログや動画による広告収入、あるいは資産形成型の投資など、時間をかけて複利効果を最大化する戦略においては、短期的には大きな結果が出にくいというデメリットがあります。
最初の数年間は労力に見合った収入が得られないことも覚悟し、長期的な視点を持つ必要があります。
リスク別・不労所得の種類
不労所得には様々な種類があり、それぞれリスクや初期投資の大きさが異なります。ここでは、不労所得を「低リスク」「中程度のリスク」「高リスク」の3つのレベルに分けて、合計11種類を紹介します。
Level1.比較的低リスク
比較的リスクが低く、元本割れのリスクが小さい、または初期投資が少額で済む方法です。
銀行・ゆうちょへの預貯金(利息)
もっとも身近でリスクの低い不労所得の形が、銀行やゆうちょ銀行への預貯金から得られる「利息」です。
金利が非常に低い現代においては、大きな収益は見込めませんが、日本の預金はペイオフ制度により一定額まで保護されており、元本割れのリスクはほぼありません。
現在の低金利下では、物価上昇率(インフレ率)に金利が及ばず、お金の価値が実質的に目減りしてしまう「インフレリスク」がある点には留意が必要です。
債券投資の利子
債券は、国や企業に資金を貸し付けることで、定期的に利子(クーポン)を受け取る投資方法です。国が発行する国債などは、比較的信用度が高く、株式投資に比べて価格変動リスクが小さい傾向にあります。
元本が保証されているわけではありませんが、満期まで保有すれば通常は投資元本が戻ってくるため、低リスクな不労所得と位置づけられます。
ポイ活
ポイントサイトの利用やクレジットカードの利用でポイントを貯める「ポイ活」も、一種の不労所得と捉えられます。厳密には、日々の消費活動から生まれる「お小遣い」や「節約術」と捉えるのがより実態に近いですが、特に手間をかけずに行えるものに限定すれば、労働集約性が非常に低く、手軽な収入源と言えます。
ブログや動画などによる広告収入
ブログやYouTubeなどのコンテンツを制作し、そこに広告を掲載することで収入を得る方法です。コンテンツを一度制作してしまえば、視聴やアクセスが発生するたびに収益が自動で入る仕組みとなります。
収益の仕組みを確立するまでが大変ですが、初期投資の資金的なリスクは低い方法です。
コンテンツの企画・制作・更新に継続的に膨大な時間を費やしても、必ずしも収益化できるとは限らないという「時間的なリスク」や「徒労に終わるリスク」は非常に高いことを理解しておく必要があります。
また、 これが「仕事」になってしまうと、「不労所得」とはいえなくなります。
Level2.中程度のリスク
一定のリスクは伴うものの、低リスク資産よりも高いリターンが期待できる方法です。
株式投資の配当金や優待
株式投資において、企業が株主に利益の一部を還元する「配当金」や、自社製品・サービスを提供する「株主優待」は、代表的な不労所得です。
配当金は保有しているだけで定期的に現金収入をもたらしますが、株価の変動リスクがあるため、元本割れや配当金が減額されるリスク(減配リスク)も伴います。企業分析や市場動向の確認など、適切な管理が必要です。
投資信託(分配型)
投資信託は、多くの投資家から集めた資金をプロが運用し、その収益を投資家に分配する仕組みです。特に「分配型」は、運用益を定期的に現金として受け取ることができるため、不労所得の対象となります。
複数の銘柄に分散投資されているため、個別の株式投資よりもリスクは抑えられますが、市場全体の変動による価格下落や、分配金の変動・減少リスクは存在します。
特に、分配金が運用益からではなく元本を取り崩して支払われる「特別分配金(元本払戻金)」の場合、資産が実質的に減少していることになるため、分配金の高さだけで安易に商品を選ばない注意が必要です。
不労所得が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、どれくらいの不労所得が必要か、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
外貨預金の利息
日本円ではなく、金利が高い国の外貨で預金を行い、その利息を得る方法です。日本よりも高金利の通貨を選べば、預貯金よりも高い利息収入が期待できます。
しかし、為替レートの変動リスクが大きいため、利息以上に為替差損が発生し、結果的に元本を割る可能性があります。中程度のリスクとして認識し、為替の動向を注視する必要があります。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングは、小口化した不動産にインターネットを通じて投資し、その賃料収入や売却益の一部を分配金として受け取る仕組みです。
一般的な現物不動産投資に比べて少額から始められるため、初期投資のリスクが抑えられています。運用はプロに任せられるため手間は少ないですが、利益は対象不動産の運用実績に依存するため、元本が保証されているわけではありません。
>>あなたはいくら必要?将来の不足額を3分で診断
Level3.比較的高リスク(または初期投資が大きい)
大きなリターンが期待できる一方で、損失リスクも大きく、あるいは多額の初期投資が必要となる方法です。
不動産投資
マンションやアパートなどの物件を購入し、入居者から家賃収入を得る投資です。長期にわたり安定的な収入源となる可能性がありますが、数百万から数千万に及ぶ多額の初期投資が必要であり、ローンを組む場合は金利変動リスクも伴います。
また、空室リスク、修繕費、災害リスクなど、管理の手間や維持コストも高いです。加えて、株式のようにすぐに現金化することが難しいという「流動性リスク」も考慮しておく必要があります。
駐車場経営
所有している土地や借りた土地を駐車場として貸し出し、利用料を得る経営方法です。アパート経営などに比べると初期投資や維持管理の手間は少ない傾向にありますが、立地条件に収益が大きく左右されます。
競争が激しい地域では利用者が確保できず、収入が不安定になるリスクがあります。
コインランドリー投資
店舗としてコインランドリーを開業し、利用料から収益を得る投資です。人件費はかかりませんが、設備投資が高額になること、光熱費やメンテナンス費用が発生することから、初期投資が大きいカテゴリーに分類されます。
競合店の出現や、設備の故障リスクが収益に直結するため、高リスクまたは高初期投資に分類されます。
不労所得を得る上で知っておきたい「税金」
不労所得を計画する上で、税金の知識は避けて通れません。得られた利益のほとんどは、所得税・住民税の課税対象となります。
- 所得の種類:不労所得は、その種類によって「配当所得」「不動産所得」「雑所得」などに分類されます。
- 確定申告:給与所得者(サラリーマン)であっても、給与以外の所得が年間20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要になります。
- NISAの活用:株式投資や投資信託など、一部の不労所得については、NISA(少額投資非課税制度)を活用することで、得られた利益が非課税になります。
不労所得で得た収入は、税金を支払った後の「手取り額」で考えることが重要です。始める前に、自身の状況に合わせて税金がどのくらいかかるのかを把握しておきましょう。
目指す不労所得はリスクに合わせて選ぶ
上記で解説したように、不労所得を得る方法は多岐にわたり、それぞれリスクや難易度が大きく異なります。
例えば、資金的余裕があり、リスク許容度が高い方は、不動産投資や株式投資など、大きな初期投資を伴うがリターンも大きく継続的になりやすい方法を検討すべきでしょう。
一方で、初心者のサラリーマンや、元本割れを避けたい方は、まず預貯金や債券投資、あるいはポイ活といった比較的低リスクな方法から着手し、不労所得の感覚を掴むことが重要です。
自身のライフステージ、目標とする収入額、そして何よりも許容できるリスクの度合いを正確に把握し、無理のない範囲で最適な不労所得の種類を選ぶことが、成功への鍵となります。
まとめ
不労所得とは、「完全に働かない収入」ではなく、「労働時間に対して収入の比率が非常に高い収入」、すなわち資産や仕組みが自動的に価値を生み出す仕組みから得られる収入です。
不労所得のメリットとしては、働かなくても収入が得られること、収入源が分散できること、そして時間の自由が増えることが挙げられます。
一方で、初期投資や準備が必要であること、短期的には結果が出にくいこと、そして維持・管理の手間がかかる点がデメリットとして認識しておくべきです。
不労所得を得るための方法を検討する際は、自身の目標やリスク許容度に合わせて適切なものを選ぶことが重要です。
>>あなたはいくら必要?将来の不足額を3分で診断
不労所得が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、どれくらいの不労所得が必要か、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

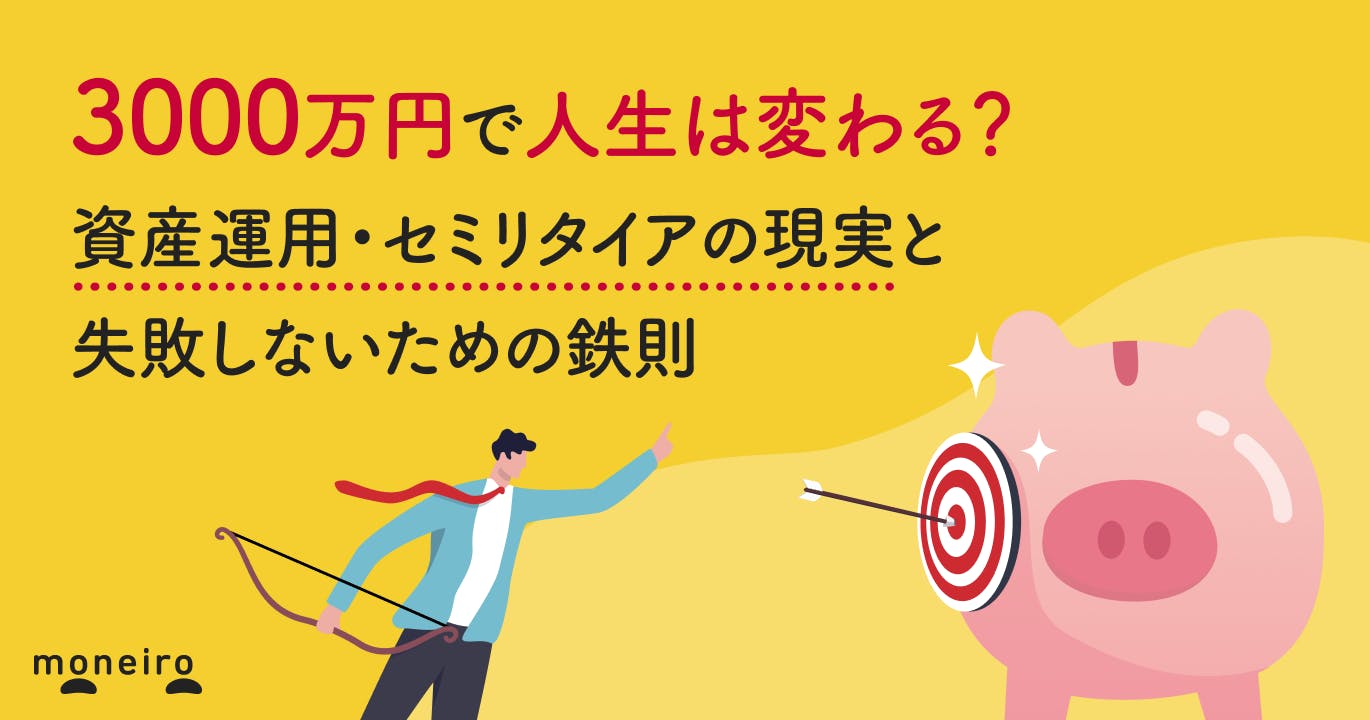
3000万円で人生は変わる?資産運用・セミリタイアの現実と失敗しないための鉄則
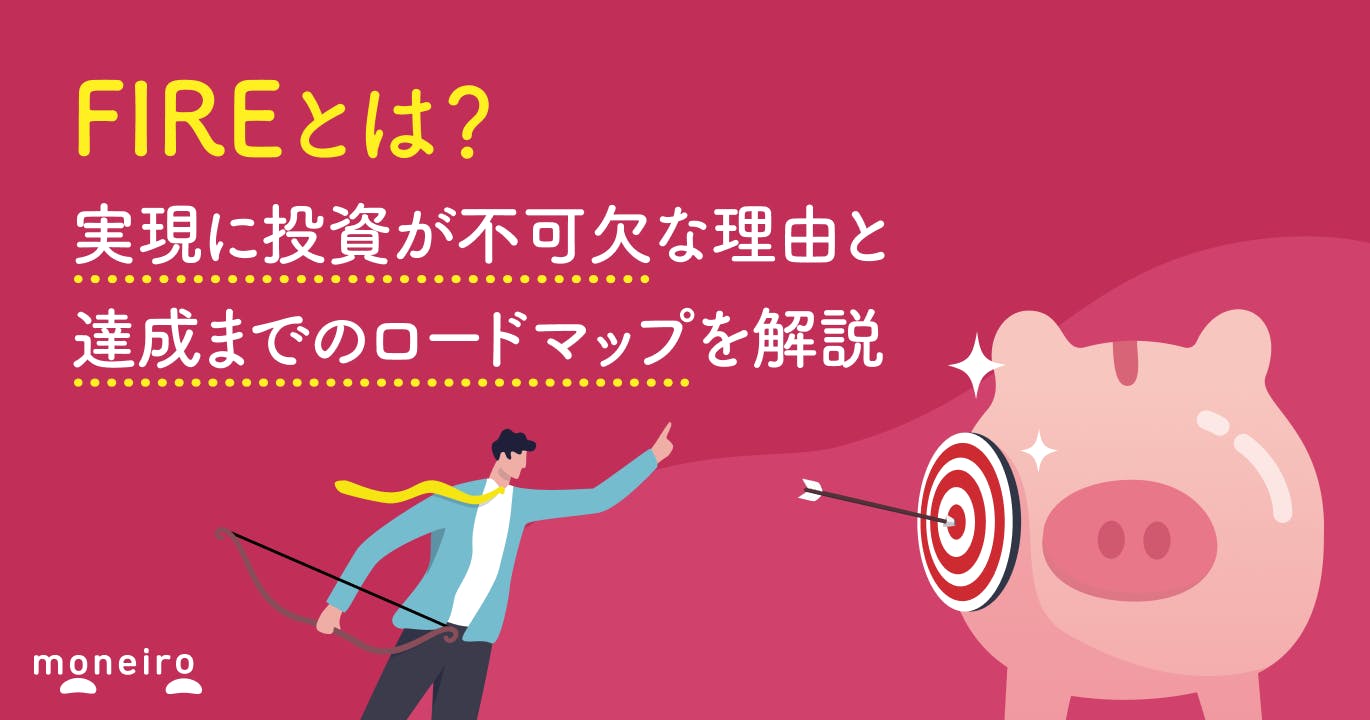
FIREとは?実現に投資が不可欠な理由と達成までのロードマップを解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

