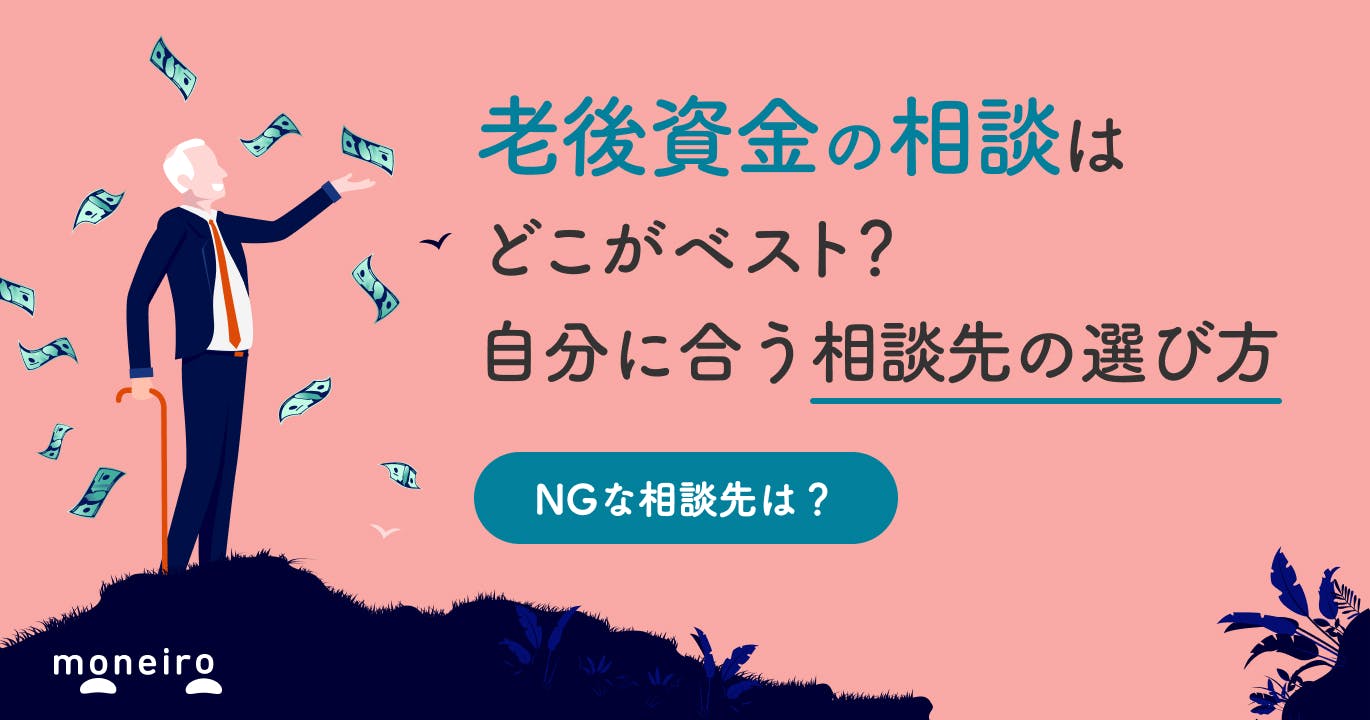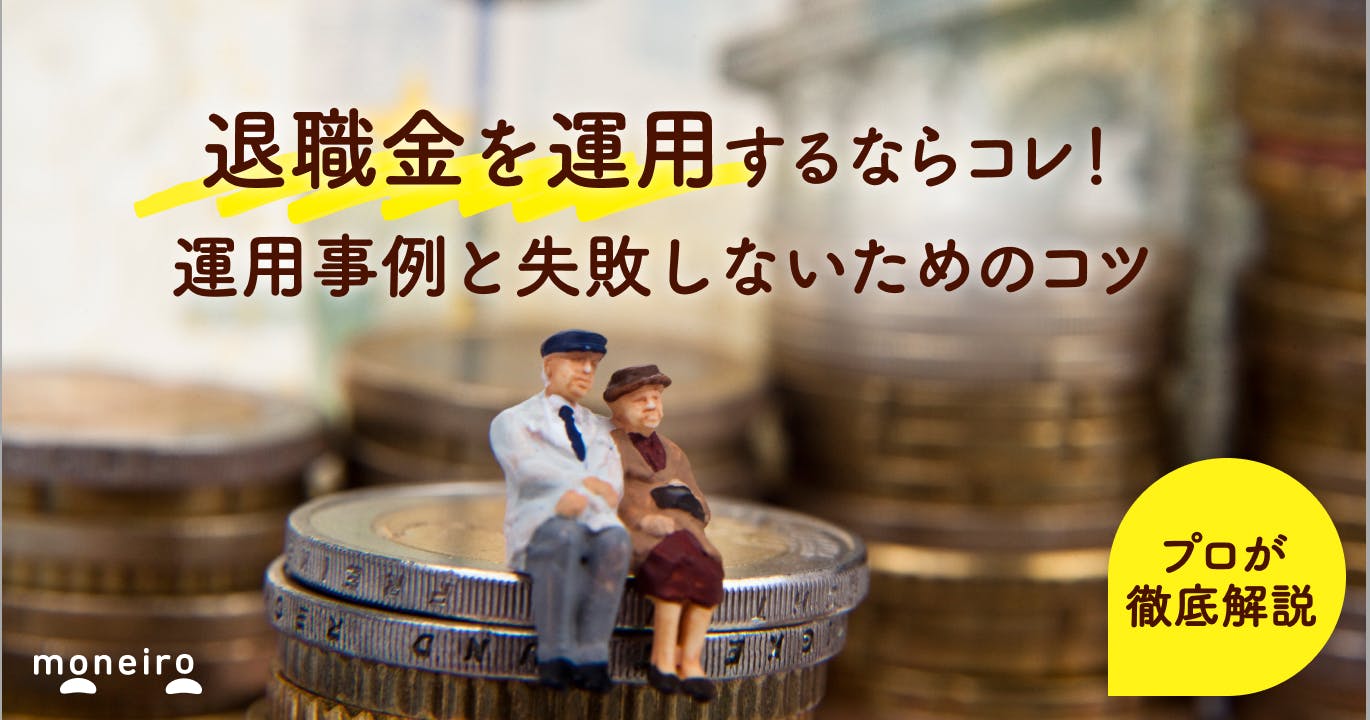70歳代の平均年金受給額はいくら?受給額を増やす方法も詳しく解説
»老後に必要な額を無料診断
70歳を迎えると、年金収入が生活の中心となる方も増えてきます。そこで気になるのが、70歳代の平均年金受給額です。
この記事では、公的データに基づき70歳代の平均年金受給額を詳しく解説します。さらに、少しでも受給額を増やすための具体的な方法もご紹介します。豊かな老後を送るための一助として、ぜひ参考にしてみてください。
- 70歳代の国民年金受給額は5万7000~5万9000円程度
- 70歳代の厚生年金受給額は14~15万円程度
- 70歳までに年金の受給額を増やす方法
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
70歳代の平均年金受給額
老後の生活費の基盤となるのは公的年金です。現在70代の人はどれくらい年金を受け取っているのでしょうか。令和5年度「厚生年金保険・国民年金事業の概況」から読み解いていきます。
70歳代の国民年金受給額
まずは、自営業者や専業主婦(夫)などが加入する国民年金(老齢基礎年金)、70歳代の月額平均受給額を1歳刻みで確認してみましょう。
【令和5年度末時点】
国民年金に40年間加入した場合、令和5年度の国民年金の満額は月額約6万6000円ですので、70歳代の基礎年金平均額はそれを下回っています。要因としては、年金加入期間が短い、もしくは後述する年金の繰上げ受給などによるものと推測できます。
なお、令和7年度の国民年金の満額は6万9308円で、昭和31年4月1日以前生まれ(現在の70代以上はこちらに該当)の方は、6万9108円となっています。
70歳代の厚生年金受給額
次に、厚生年金(老齢厚生年金)の月額平均受給額を見ていきます。会社員や公務員は2階建て(国民年金+厚生年金)の年金制度となっているため、支給される年金に基礎年金額が含まれています。
夫婦の平均年金受給額は?
最後に、国民年金・厚生年金の男女別各平均額から、夫婦二人の老齢年金受給額の平均値を算出してみましょう。年金加入実績の組み合わせはいくつものパターンがあるため、あくまで一例としてご覧ください。
【国民年金と厚生年金の男女別月額受給額平均】(令和5年度末現在)
※厚生年金受給額には国民年金受給額(基礎年金額)が含まれる。
【夫婦の平均年金受給額】
出典:厚生労働省年金局「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
総務省統計局が公表している「家計調査報告(家計収支編)2024年」の「65歳以上夫婦のみ無職世帯の家計収支」のデータによると、実収入(25.2万円)のうち年金給付額の平均は22.5万円とされており、上表でいうと②にあたります。
同調査では、65歳以上無職夫婦の1ヶ月あたりの消費支出は25.6万円であることから、不足分は勤労収入や預貯金の取り崩しなどにより補っていることが推測できます。
70歳までに年金受給額を増やす方法
先述のデータからわかるように、老後の家計収支は年金収入のみの場合、赤字家計となることが予測されます。「人生100年時代」ともいわれる中で、老後資金を枯渇させないためにできることを考えてみましょう。
長く働く(厚生年金加入期間を延ばす)
働いて収入を増やすことを考えてみましょう。働くことで手持ち資金を増やし、さらに厚生年金に加入できれば、加入した期間を受給年金に上乗せして受け取ることが可能です。厚生年金には最長で70歳まで加入することができます。
また、在職老齢年金制度を活用して、年金を受給しながら働くという選択肢もあります。令和7年4月からの在職老齢年金の支給停止調整額は51万円です。年金と勤労収入を調整しながら上手に働き、収入を増やしましょう。
付加年金に加入する
自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者の場合、年金は老齢基礎年金となります。つまり、2階建て・3階建ての年金制度を持つ会社員よりも、さらにしっかりと年金対策をする必要があります。
老齢基礎年金を増額する方法の一つが、付加年金への加入です。付加年金は国民年金の第1号被保険者が国民年金保険料に上乗せ加入できる制度です。
月額保険料は400円で、納付した月数×200円が、将来の公的年金(老齢基礎年金)に上乗せして支給されます。
例えば、40年間(480月)付加年金を納めた場合、年金額は年額9万6000円(200円×480月)増加します。増えた年金は一生涯受け取れます。月額400円掛けて月200円上乗せされることになるため、2年間年金を受給すれば、掛けた分の元が取れる計算になります。
また、支払った付加保険料は国民年金保険料と同様に社会保険料控除の対象で、所得控除できるため節税効果も望めます。
国民年金基金に加入する
国民年金基金も、自営業者やフリーランスが加入対象となる制度で、将来、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。掛金の上限額は月額6万8000円です。後述するiDeCoを併用する場合は、両方の合算で6万8000円が限度額となります。
あらかじめ65歳からの受給額が決まっているため、老後の生活設計を立てやすくなります。公的年金なので一生涯受け取れます。
なお、国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象です。配偶者の掛金を負担した場合は配偶者の掛金も控除対象となります。
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
iDeCoは私的年金づくりの手段として、自営業者やフリーランスの間で、国民年金基金と比較されることが多い制度です。両制度を併用することも可能ですが、前述の通り、iDeCoの掛金の上限は国民年金基金または国民年金付加保険料の掛金と合算して6万8000円です。
掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除となり所得から控除できるため、国民年金基金と同様の節税効果があります。
iDeCoは、投資先を自分で選び運用する制度で、運用益は非課税となります。国民年金基金と異なり、投資を行うため、選ぶ投資商品やその後の運用成績によって受け取れる年金額は変動します(元本割れのリスクもゼロではありません)。
国民年金基金が一生涯受け取れる年金である一方、iDeCoは原則60歳以降75歳までの間に一括で受け取るか、有期年金として受け取るか選択する形式になっています。
NISA(少額投資非課税制度)の活用
NISAは年金制度ではありませんが、老後資産形成に利用できる制度です。iDeCoと同様、運用から生じる利益は非課税になりますが、NISAには所得控除はありません。
NISAでは、一人当たり年間360万円まで非課税枠が設けられており、上限1800万円までの非課税投資が可能です。解約に制約はなく、必要なときに必要な金額だけを解約できるため、年金に特化した制度より利便性が高いことも特徴です。
繰下げ受給を検討する
公的年金の受給開始年齢は原則65歳です。ただし、60歳以降75歳までの間の任意の時期に受け取りを開始することも可能です。年金の受給開始を遅らせると、段階的に年金額が増加する仕組みで、増加した年金額を一生涯受け取ることになります。具体的な増加額については次の項で解説していきます。
繰上げ受給・繰下げ受給で受給額はどう変わる?
60歳から64歳の間に年金を受給開始することを繰上げ受給、66歳から75歳の間の受給開始を繰下げ受給といいます。繰上げ受給・繰下げ受給をすることで受給額はどのように変化するのか見ていきましょう。
繰上げ受給・繰下げ受給の利用状況
「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金の受給権者のうち繰上げ受給している人は全体の0.9%、繰下げ受給は1.6%であり、大半の厚生年金受給権者は65歳から受給開始していることがわかります。
一方、国民年金(老齢基礎年金)の受給権者の繰上げ受給率は24.5%、繰下げ受給率は2.2%です。厚生年金受給者と比較すると、繰上げ受給を選択する人が多いようです。
繰下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に申請することができます。例えば、基礎年金は原則通り65歳から受給し、厚生年金のみ70歳からの受給開始に繰り下げるといったことが可能です。一方、繰上げ受給では、別々に申請ができず、必ず同時に受給開始となります。
繰上げ受給の場合、受給額はどうなる?
繰上げ受給を申請した場合、申請時期に応じて年金が一定の割合で減額されます。その減額率は一生涯変わりません。
減額率は、繰り上げた月数×0.4%です。(昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)
例えば、通常より3年早い62歳から年金を受け取るよう繰上げ受給申請をすると、減額率は14.4%(3年×12月×0.4%)です。
仮に、65歳からの年金受給額の年額が168万円の人の場合、年金額は約143.8万円へ目減りすることになります。
繰下げ受給の場合、受給額はどうなる?
一方の繰下げ受給の場合は、繰り下げた月数×0.7%の割合で年金が増額します。例えば、5年間繰り下げて70歳から受給開始する場合、年金は42%(5年×12月×0.7%)増額します。受給開始は75歳まで繰り下げることができ、最大84%の増額が可能です。
年金受給額の年額が168万円の人の場合、70歳から受け取ると年額238万円に、75歳まで遅らせると年額309万円になる計算です。
年金受給額の確認方法
老後の生活設計を行うためには、将来の年金受給見込み額を知っておくことが大切です。ここでは、年金受給額の確認方法について紹介します。
ねんきん定期便
毎年、誕生日月に、日本年金機構から「ねんきん定期便」のハガキが送付されます。50歳未満の人はこれまでの年金保険への加入実績に応じた年金額が記されており、50歳以上では、現状のままの保険加入状況と考えた場合の年金受給の見込額が記されています。
その他、35歳、45歳、59歳では封書によりさらに詳しい状況を示した「ねんきん定期便」が送付されますので、年に一度、必ず確認するようにしましょう。
ねんきんネット
「ねんきんネット」は、「ねんきん定期便」の電子版で、自分の年金記録や年金受給見込み額をオンラインで確認できるサービスです。
マイナポータルとの連携か、ユーザIDを取得することで「ねんきんネット」の利用が可能となります。好きなタイミングで閲覧できるため、より利便性の高いサービスといえます。
年金事務所へ問い合わせる
上記以外では、年金事務所へ電話や直接来訪により問い合わせることもできます。ただし、直接出向く場合は、予約が必要な場合もあるため、来訪時に持参が必要なものと合わせ、管轄の年金事務所に事前に確認をするようにしましょう。
公的年金シミュレーターの活用
厚生労働省が管轄する「公的年金シミュレーター」では、これまでの加入履歴に加え、今後の収入見込み額と厚生年金加入期間などを設定すると、将来の受給年金の増減をシミュレーションすることが可能です。今後、転職の予定や収入に変動がある人など活用してみるとよいでしょう。
老後に必要な資金を今すぐ確認してみよう
将来や老後に必要な資金が気になる方は、事前にシミュレーションしておくと資金の準備や目標設定をスムーズに進められます。
マネイロの「3分投資診断」なら、現在の収入・支出や資産状況から将来の老後に必要な資金を、わずか3分で簡単に算出。さらに、その目標に向けた適切な資産運用方法が、無料で診断できます。
老後生活を豊かに、楽しく過ごせるよう、まずは現状を知るところから始めてみましょう。
>>老後に必要な資金はいくら?無料の3分診断
まとめ
70歳代の方の平均年金受給額から老後資金の寿命を延ばす方法などを解説しました。
過去には「悠々自適の年金生活」が当たり前だった時代もありましたが、現在では年金だけで老後を豊かに暮らすのは難しくなってきています。いざ70代になってから生活に困らないよう、できるだけ早い段階から老後資金の準備を始めるのがおすすめです。
iDeCoやNISAの活用、さらには身体が健康なのであれば、繰下げ受給も視野に入れながらできるだけ長く働くといった選択肢も老後資金の確保に有効です。
金銭的、精神的に豊かな老後を送れるよう、今からでも対策できることを始めていきましょう。
»年金で老後は暮らせる?まずは無料診断
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください