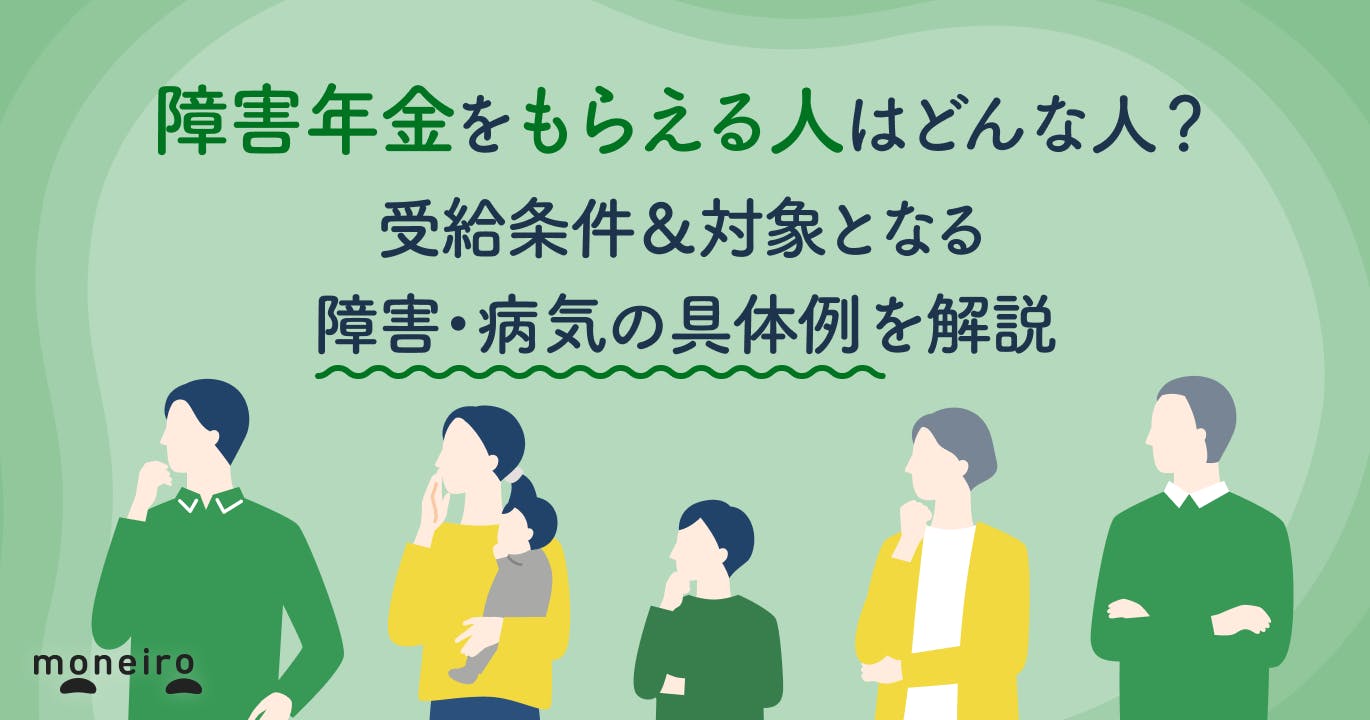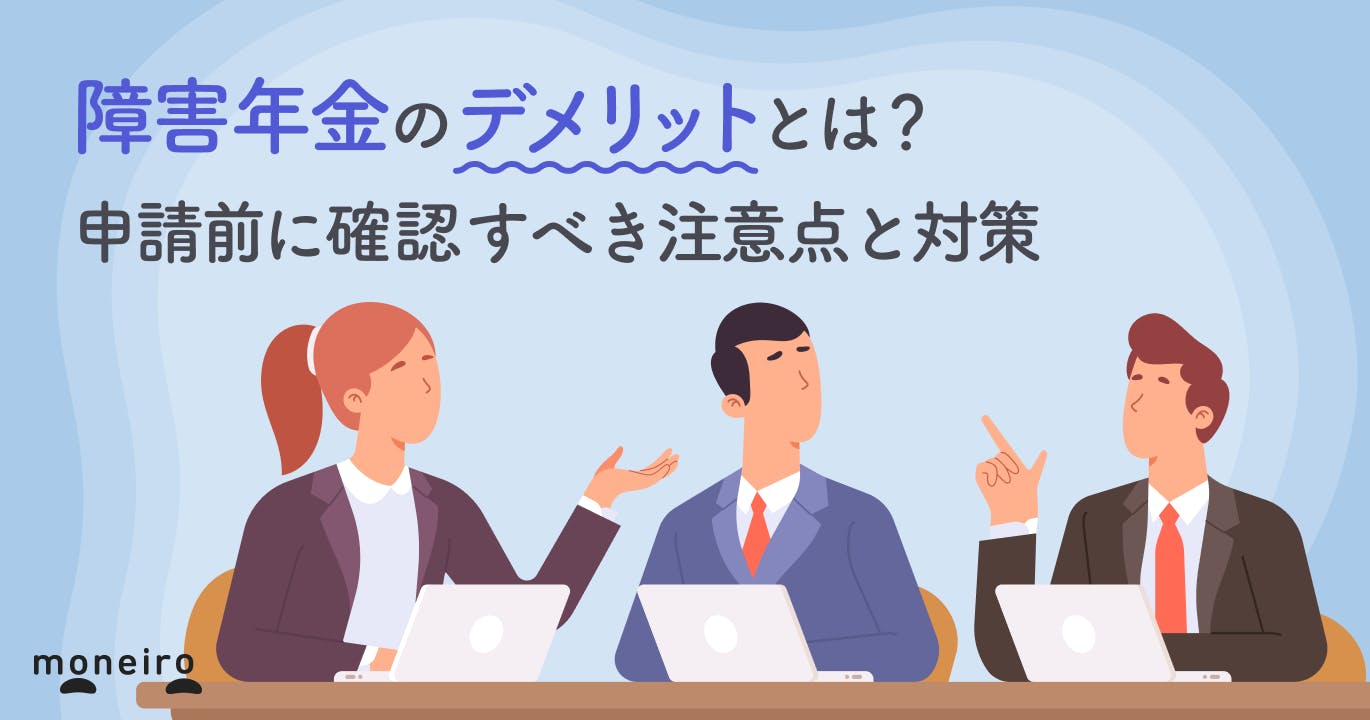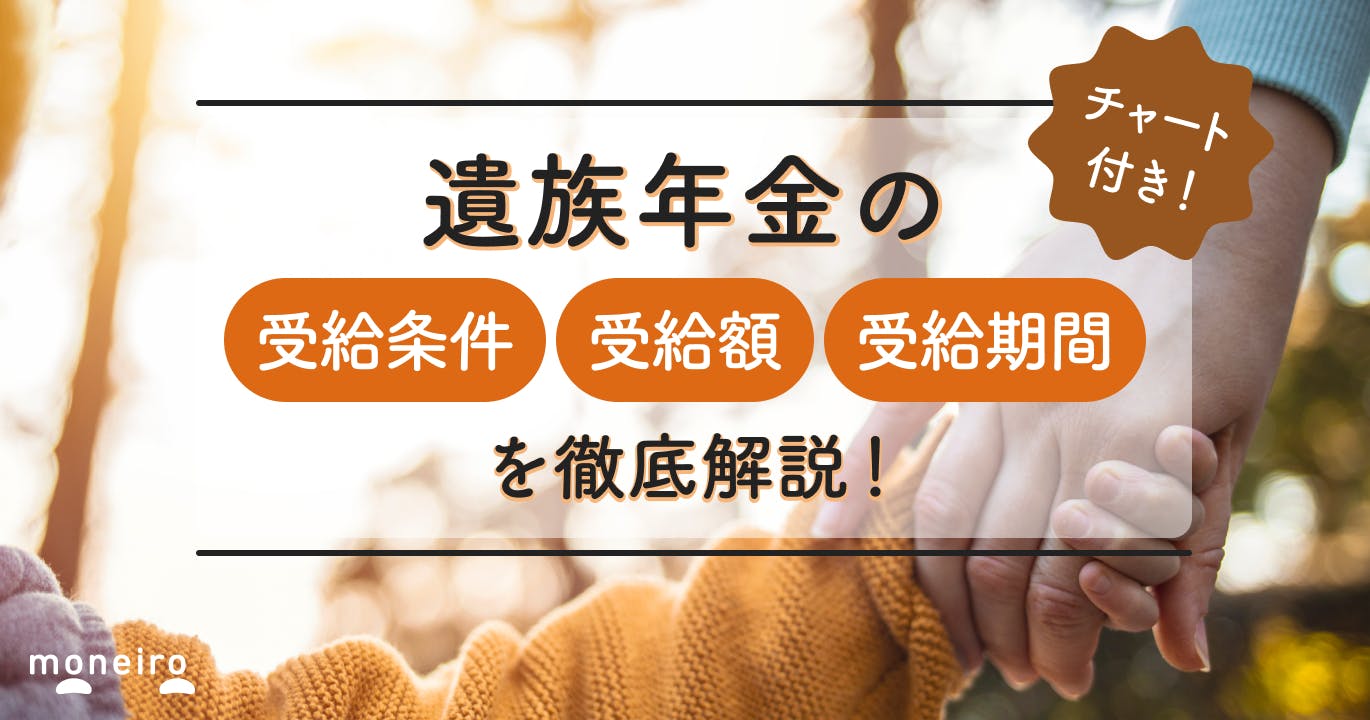障害年金をもらえる人はどんな人?受給条件&対象となる障害・病気の具体例を解説
≫もしもの備えは大丈夫?将来の必要資金を3分で診断
「障害年金がもらえるのはどんな人?」万が一、病気やケガで生活や仕事に支障が出た場合、障害年金をもらえるのか不安に思っていませんか?
この記事では、障害年金を受給できる人の条件や対象となる障害や病気の具体例を詳しく解説します。記事の内容を参考に自分の状況と照らし合わせ、受給できるかどうか確認しましょう。
- 障害年金をもらえる人の条件(受給要件)
- 障害年金の受給対象となる障害や病気の具体例
- 障害年金の申請手続きの基本的な流れ
「もしも」の備えが気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、将来必要になる資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説


障害年金をもらえる人の条件
障害年金をもらうためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」という3つの基本要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、初診日時点で加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって内容が少し異なります。
自分がどちらの年金の対象となるかを確認し、それぞれの要件を一つずつクリアしているか見極めることが重要です。
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は、国民年金被保険者であるすべての人が対象となる年金です。自営業者や学生、専業主婦(主夫)に限らず、会社員や公務員も受給できます。障害基礎年金を受給するには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 初診日要件
障害の原因となった病気やけがで最初に医師の診療を受けた「初診日」が、国民年金の加入期間中であること、または20歳前や60歳以上65歳未満の年金に加入していない期間中(国内在住の場合)であることが必要です。
初診日は、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を指します。障害年金の受給において基準となる、非常に重要な日です。
2. 障害状態該当要件
障害の程度を判断する「障害認定日」において、法令で定められた障害等級の1級または2級に該当する状態であることが求められます(3級は対象外)。
3. 保険料納付要件
初診日の属する月の前々月までの年金加入期間のうち、保険料納付済期間または保険料免除期間(学生納付特例や納付猶予を含む)を合わせて、2/3以上保険料を納付している必要があります。
ただし、初診日が令和18年3月31日までで65歳未満の場合、初診日の属する月の前々月までの直近1年間(12ヶ月)に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たすという特例があります。なお、20歳前に初診日がある場合は、この納付要件は問われません。
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している方が対象です。障害基礎年金に上乗せして支給されるもので、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金保険の被保険者期間中にあることが大前提の条件となります。
2. 障害状態該当要件
障害認定日において、障害の程度が1級・2級・3級のいずれかに該当する必要があります。障害厚生年金では、障害基礎年金よりも対象となる等級が広く、より軽度の障害(3級)も対象となるのが特徴です。
3. 保険料納付要件
この要件は障害基礎年金と共通です。原則として加入期間の2/3以上の納付・免除期間が必要ですが、初診日が令和18年3月31日までで65歳未満の場合、直近1年間に未納がなければよいとする特例も同様に適用されます。
障害年金の対象となる障害・病気
障害年金は、手足の欠損といった身体的な障害だけでなく、うつ病などの精神疾患といった見た目では分かりにくいものも含まれます。対象となる障害や病気は非常に幅広く、重要なのは、その障害によって日常生活や仕事にどれだけの支障が生じているかです。
具体的にどのような障害や病気が対象になるのか、以下で確認していきましょう。
≫もしもの備えは大丈夫?将来の必要資金を3分で診断
肢体の障害(手足の欠損・機能障害など)
手足の切断や欠損、機能障害などは障害年金の対象として代表的な例です。人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合でも、障害等級3級に該当する可能性があります。また、事故によるけがだけでなく、病気が原因で手足に障害が残った場合も含まれます。
眼の障害(視力障害・視野障害など)
視力や視野に障害がある場合も、障害年金の対象となります。障害等級は、両眼の視力の和や、視野の広さなどによって細かく定められています。例えば、両眼の視力がそれぞれ0.07以下になった場合は2級に、0.03以下になった場合は1級に該当します。
聴覚の障害(聴力障害・平衡機能障害など)
聴力レベルが一定以上に低下した場合や、平衡機能に著しい障害がある場合も障害年金の対象となります。 例えば、両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合、1級に該当します。
精神の障害(うつ病・統合失調症・発達障害など)
実は、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害といった精神の障害も、障害年金の対象となります。これらの障害により、日常生活や社会生活に著しい制限を受けている状態が認定の目安です。
外見からは分かりにくいため、症状を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらうことが特に重要になります。
心疾患・肺疾患などの内部障害
心筋梗塞や心不全などの心疾患、気管支ぜんそくや肺結核などの呼吸器疾患といった、いわゆる内部障害も障害年金の対象です。
心臓ペースメーカーやICD(植え込み型除細動器)を装着した場合は、障害等級3級に該当する可能性があります。
腎疾患・肝疾患・糖尿病などの代謝疾患
人工透析を必要とする慢性腎不全は、原則として障害等級2級に該当します。また、肝硬変などの肝疾患や、インスリンを使用してもなお血糖のコントロールが困難な糖尿病による合併症も、障害年金の対象となる可能性があります。
がんによる障害
がんそのものや、治療による副作用(抗がん剤治療による倦怠感や脱毛、手術による後遺症など)によって、日常生活や労働に著しい制限が生じている場合、障害年金の対象となります。
人工肛門や新膀胱を造設した場合、障害等級3級に該当する可能性があります。
その他の障害(てんかん・高次脳機能障害など)
上記以外にも、てんかん発作の頻度や状態に応じた障害や、脳梗塞・脳卒中などの後遺症である高次脳機能障害も障害年金の対象です。
また、血液・造血器疾患など、非常に多岐にわたる病気やケガが対象とされています。
参照:障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。|日本年金機構
障害年金がもらえない人とは?
障害年金を受給するためには、いくつかの要件をクリアする必要があり、これを満たしていない場合には残念ながら障害年金は支給されません。
申請を検討する前に、要件を満たしているかしっかり確認しておきましょう。

もらえない人1.初診日要件を満たしていない
障害年金の申請において、「初診日」を客観的に証明することは非常に重要です。大前提として、初診日が、国民年金または厚生年金の加入期間中であることなどを証明できなければ、受給資格を得ることができません。
カルテの廃棄や廃院などで初診日の証明が困難な場合、受給が難しくなるケースがあります。
もらえない人2.所定の障害等級に該当していない
障害年金は、障害の状態が法令で定められた等級に該当しない限り支給されません。障害基礎年金の場合は1級または2級、障害厚生年金の場合は1級から3級のいずれかに該当する必要があります。
医師の診断書の内容が、これらの等級に達していないと判断された場合、申請は認められません。
もらえない人3.保険料納付要件を満たしていない
障害年金を受給するためには、一定期間、年金保険料を納めていることが前提となります。原則として、初診日の前々月までの公的年金加入期間のうち、2/3以上の期間で保険料を納付または免除・納付猶予されている必要があります。
この要件を満たせない場合、障害年金は支給されません。保険料の「未納」期間が長い方は特に注意が必要です。
先天性疾患やダウン症など、20歳未満に初診日がある場合、年金加入期間外のため保険料納付要件は不要です(障害基礎年金の場合)。
また、前述の通り、初診日が令和18年3月31日までで65歳未満の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たすという特例があります。
「もしも」の備えが気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、将来必要になる資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
障害年金の支給額
障害年金には、初診日に加入していた年金制度に応じて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。ここでは、令和7年度のそれぞれの支給額について見ていきましょう。
障害基礎年金(国民年金)の支給額
障害基礎年金は、国民年金に加入していた方などが対象です。支給額は障害等級に応じて定額で、昭和31年4月2日以後生まれの方の令和7年度の年金額は以下の通りです。
- 1級:103万9625円 + 子の加算額
- 2級:83万1700円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額は、以下の通りです。
- 1級:103万6625円 + 子の加算額
- 2級:82万9300円+子の加算額
18歳になった後の最初の3月31日までの子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合、人数に応じて以下の加算があります。
- 子ども2人までは1人につき23万9300円
- 3人目以降は1人につき7万9800円
障害厚生年金の支給額
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた方を対象として、障害基礎年金に上乗せされます。支給額は、厚生年金への加入期間や納めた保険料(報酬額)に応じて計算される「報酬比例の年金額」が基礎となります。
- 1級:(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(23万9300円)
- 2級:(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(23万9300円)
- 3級:(報酬比例の年金額)
1級と2級には、条件を満たす配偶者がいる場合に配偶者の加給年金が加算されます。また、3級には、以下の最低保証額が設定されています。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方:62万3800 円
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:62万2000 円
障害手当金の支給額
障害厚生年金の対象者で、障害の原因となった病気・ケガの初診日から5年以内に症状が固定した場合で、障害年金を受けられる程度よりも軽い障害状態が残ったケースで一時金として支給されます。
支給額は、報酬比例の年金の2年分で、最低保証額(124万7600円)が設けられています。
障害年金の申請の流れと必要書類
障害年金の申請は、以下の流れで行います。
参照:障害年金の制度をご存じですか?|政府広報オンライン
なお、申請には複数の書類を準備する必要があります。事前に用意すべき書類を把握しておきましょう。
申請に必要な書類
障害基礎年金と障害厚生年金では、一部で異なります。以下で確認しておきましょう。
障害基礎年金の申請に必要な書類
・年金請求書(国民年金障害基礎年金)(様式第107号):市区町村役場、年金事務所、または街角の年金相談センターで入手可能
- 年金手帳:基礎年金番号を確認
- 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか:生年月日や住所を確認。マイナンバー記入で省略可能
- 医師の診断書(所定の様式):障害認定日(初診日から1年6か月後、または症状固定日)の状態を記載。請求日が1年以上後の場合は、直近3か月以内の診断書も必要
- 受診状況等証明書:初診日を証明(初診の医療機関と診断書の医療機関が異なる場合)
- 病歴・就労状況等申立書:障害の経過や日常生活・就労状況を補足
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義):口座番号等を確認。金融機関の証明があれば省略可
上記の他、場合によっては以下の書類も必要になります。
- 18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)がいる場合:戸籍謄本、住民票、子の収入証明書、子の診断書(障害のある子の場合)
- 第三者行為による障害の場合:第三者行為事故状況届、事故証明書、損害賠償金の算定書等
- 20歳前障害の場合:所得証明書
- その他状況に応じて:身体障害者手帳、療育手帳、年金加入期間確認通知書等
障害厚生年金の申請に必要な書類
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)(様式第104号):年金事務所または街角の年金相談センターで入手
- 障害基礎年金と同じ書類(年金手帳、戸籍謄本等、医師の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、通帳等)
- 追加書類:配偶者または子がいる場合:配偶者の収入証明書、子の収入証明書等(生計維持関係を確認)
- その他:年金証書、戸籍の附票など合算対象期間が確認できる書類
また、場合によっては以下の書類も必要となります。
- 配偶者または18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)がいる場合:戸籍謄本、住民票、配偶者の収入証明書、子の収入証明書、医師または歯科医師の診断書
- 第三者行為による障害の場合:第三者行為事故状況届、事故証明書、(被害者に被扶養者がいる場合)源泉徴収票など扶養していたことがわかる書類、損害賠償金の算定書等
- その他状況に応じて:身体障害者手帳、療育手帳、年金加入期間確認通知書等
なお、障害基礎年金・障害厚生年金いずれの場合でも、年金請求書にマイナンバーを記入することで、戸籍謄本等の添付を省略できます。
申請書類の提出先
障害基礎年金と障害厚生年金では、申請書類の提出先が異なります。間違えないよう、しっかり確認しておきましょう。
- 障害基礎年金の提出先:住所地の市区町村役場の窓口(ただし、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は近隣の年金事務所または年金相談センター)
- 障害厚生年金の提出先:近隣の年金事務所または年金相談センター
なお、書類提出後、日本年金機構による審査が行われます。審査は通常3ヶ月程度の期間がかかり、支給が決定した場合には、「年金証書」と「年金決定通知書」が送付されます。
その後、さらに1〜2ヶ月ほどで指定した口座への年金の支払いが開始されます。不支給となった場合は、その理由が記載された通知書が届きます。
障害年金に関するよくある質問
障害年金に関するよくある質問にお答えします。
障害者手帳がなくても障害年金はもらえますか?
はい、受給できます。障害年金と障害者手帳は、根拠となる法律や目的、審査機関が異なる全く別の制度です。
したがって、障害者手帳の有無や等級にかかわらず、障害年金の受給要件を満たしていれば年金を受け取ることが可能です。
うつ病で障害年金をもらうことはできますか?
はい、うつ病は精神の障害として障害年金の支給対象となります。
日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかが審査の重要なポイントとなるため、医師に自身の状況を正確に伝え、診断書に適切に反映してもらうことが大切です。
障害年金の支給は一生続きますか?
必ずしも一生続くとは限りません。障害の状態が変化しないと判断される「永久認定」の場合は生涯にわたって支給されます。
一方、症状の変化が見込まれる「有期認定」の場合は1〜5年ごとに更新が必要で、障害の状態が軽くなったと判断されると、等級が下がったり支給が停止されたりすることがあります。
働いていても障害年金はもらえますか?
はい、働いていても受給できる可能性はあります。特に人工透析や人工関節、心臓ペースメーカーなど、障害年金の等級が決まっているものについては、就労の有無は審査に影響しないため受給が可能です。
とはいえ、就労状況は障害の程度を判断する上で重要な要素となります。特に精神障害や内部障害の場合は、障害者雇用であるか、勤務時間や業務内容にどのような配慮を受けているかなど、労働に制限があることを具体的に示すことが重要です。
まとめ
この記事では、障害年金をもらえる人の条件や対象となる障害、申請手続きについて解説しました。
障害年金を受給するためには、以下の3つの基本要件を満たす必要があります。
- 初診日要件:初診日が所定の年金加入期間中にあること
- 保険料納付要件:一定期間、保険料を納付または免除されていること
- 障害状態該当要件:障害の程度が法令で定める等級に該当すること
対象となる障害は、身体の障害だけでなく、うつ病などの精神疾患やがん、糖尿病といった内部疾患まで幅広く認められています。
手続きは複雑ですが、経済的な基盤を支える重要な制度です。自分が対象かもしれないと感じた場合は、まずは年金事務所などへ相談することから始めてみるとよいでしょう。
≫もしもの備えは大丈夫?将来の必要資金を3分で診断
「もしも」の備えが気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、将来必要になる資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。