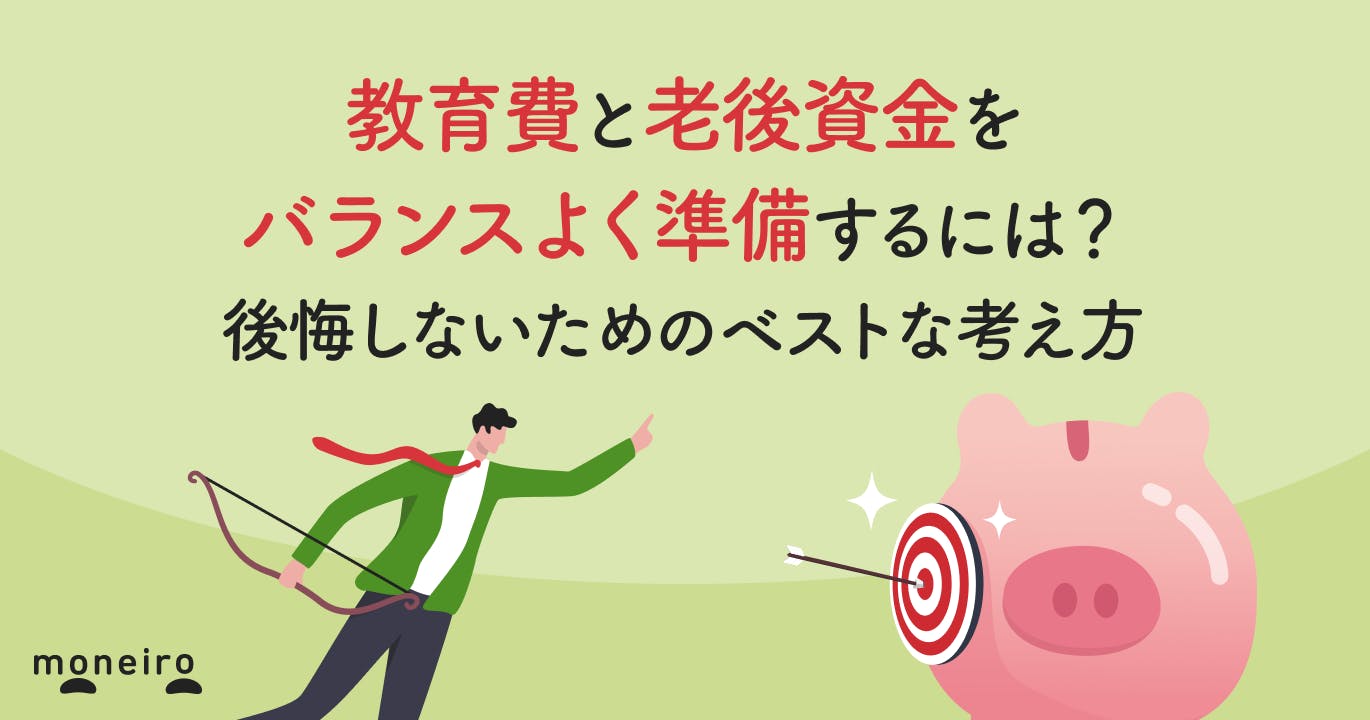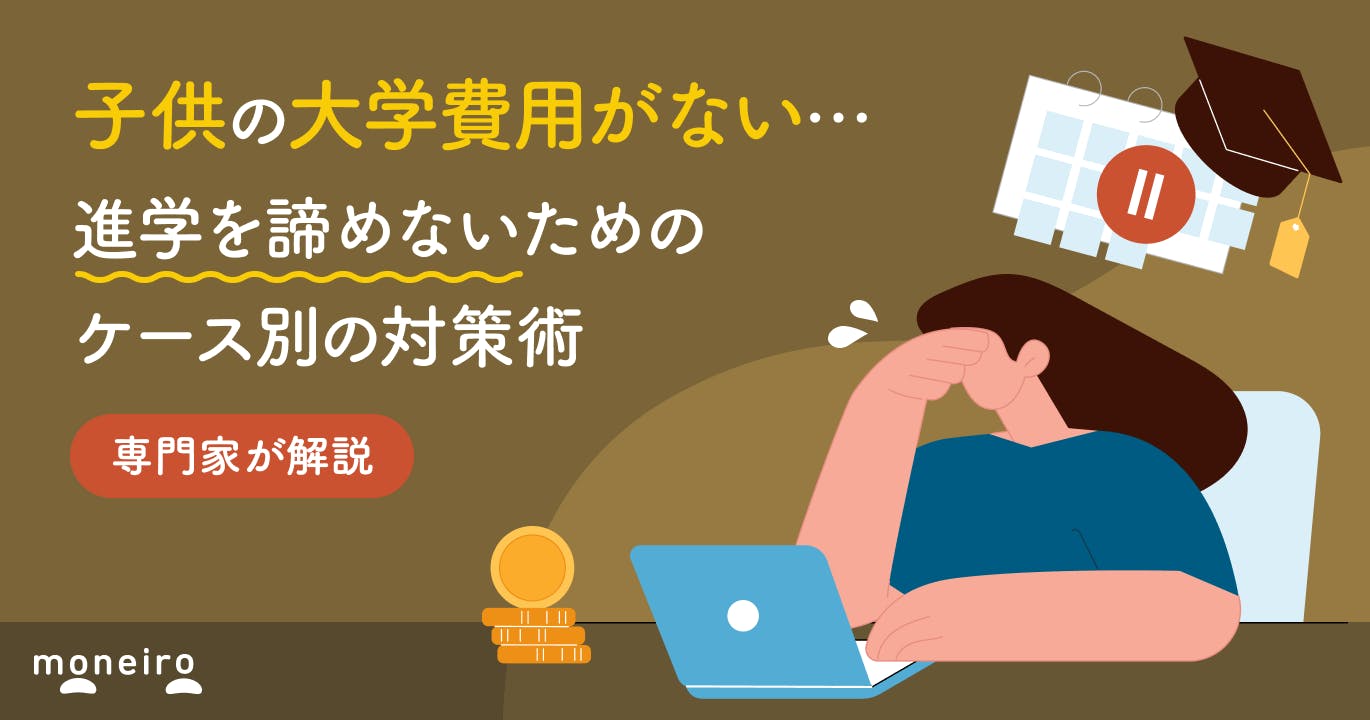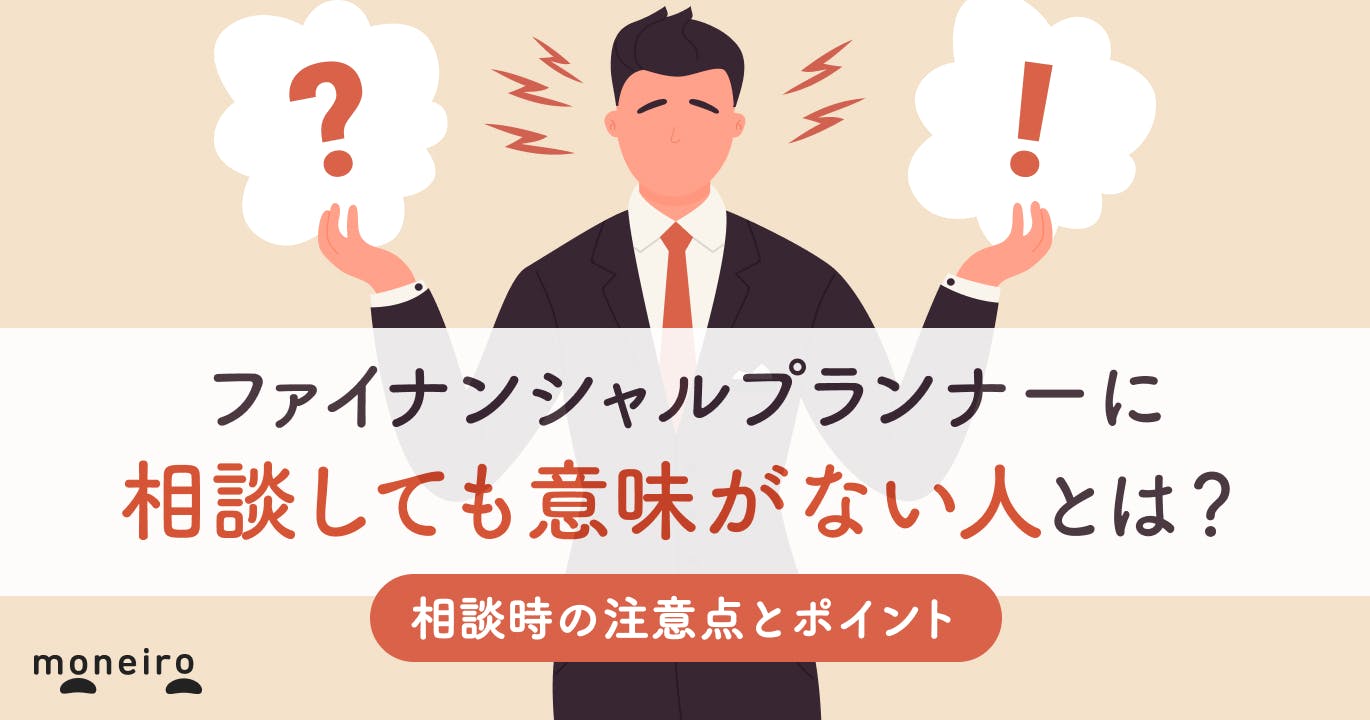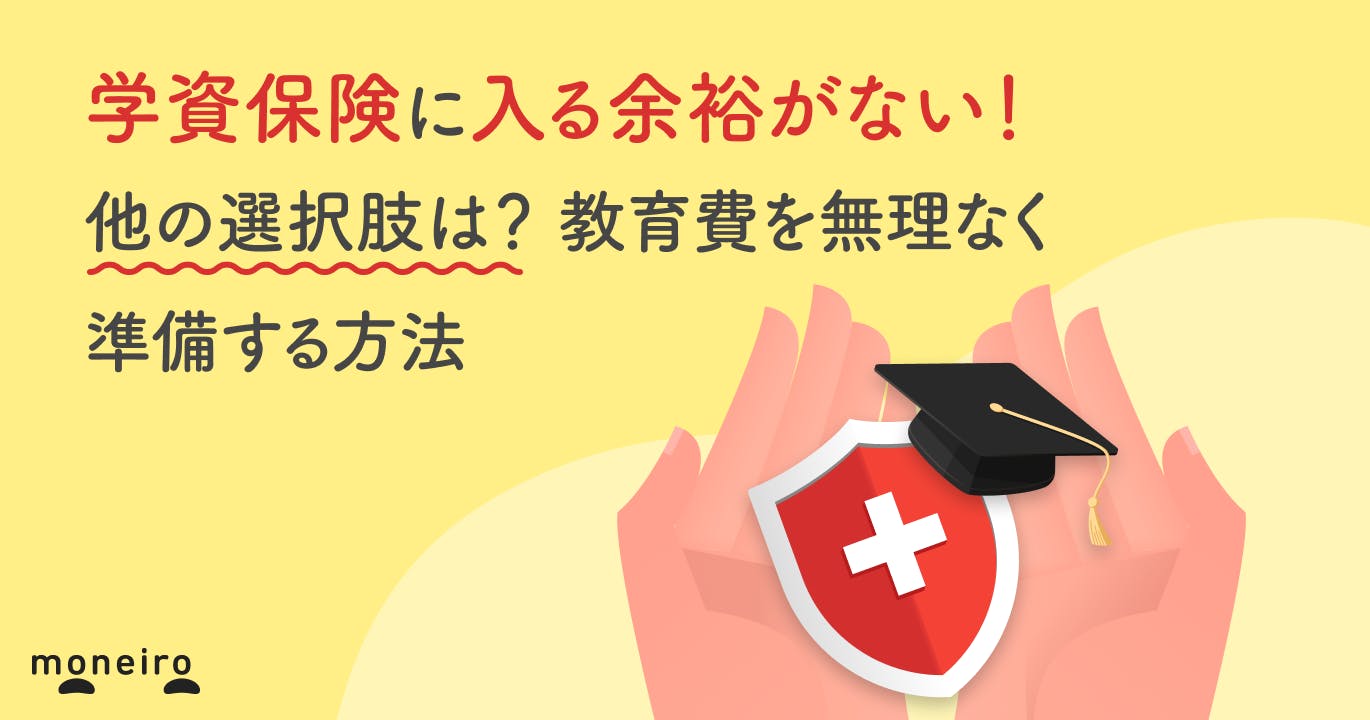
子供のための貯金は運用するべき?プロが教育費の準備方法と賢いお金の貯め方を解説
»自分たちの老後資金はいくら必要?|無料診断
子供の将来に備えて貯金をしている家庭は多いですが、「運用もした方がいいのか?」と迷うご家庭も多いでしょう。
教育費など使う時期が明確に決まっている資金は、運用リスクを取らず慎重に準備するのが基本です。一方で、結婚資金や将来のサポート資金など、時期が決まっていない目的なら長期運用を検討できます。
本記事では、「子供のための貯金を運用するべきか」の疑問に対して、教育資金を中心に「どの資金は運用すべきか」を整理しながら、賢いお金の貯め方・増やし方を専門家視点でわかりやすく解説します。
- 教育費など時期が決まっている資金の考え方
- NISAや学資保険など具体的な準備方法
- 子供の教育資金と自身の老後資金とのバランスの取り方
子育てのお金が気になるあなたへ
これから先、教育資金で困ることのないよう、将来必要な額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶オンライン無料相談:幅広く対応できる専門家に直接相談
子供のための貯金は運用すべき?目的別の考え方
子供のための資金準備は、そのお金をいつ、何に使うかという「目的」によって運用方針を分けることが重要です。
使う時期が決まっている資金は安全性を、時期が未定の資金は収益性を重視するなど、メリハリのある計画を立てましょう。
教育費など時期が決まっている資金「運用は慎重に」
高校や大学の入学金など、使う時期がはっきりと決まっている教育資金は、安全性を最優先に考える必要があります。
資産運用には元本割れのリスクがあるため、いざ資金が必要になったタイミングで市場が下落していると、予定していた金額を用意できなくなる可能性があるためです。
例えば、4年後の大学進学費用として準備していた資金が、直前の経済ショックで目減りしてしまう事態は避けなければなりません。
教育資金のように「いつまでに、いくら必要」とはっきりしているお金については、長期運用を前提としつつ、使う時期に合わせた丁寧な計画が必要です。
旅行・結婚・将来資金など時期未定のものは「運用OK」
家族旅行の費用や、子供が成人した際の結婚・独立資金など、具体的な使用時期が決まっていないお金については、積極的に資産運用を検討する価値があります。
長期間の運用が見込まれるため、リスクを抑えながら効率的にお金を増やすことが期待できます。
すぐに使う予定のない余裕資金であれば、ある程度のリスクを取ってリターンを狙う運用も有効な選択肢となるでしょう。
子供の教育費は実際いくら必要?時期別の目安
子供の教育費は、進路の選択によって総額が大きく変動します。事前に大まかな目安を把握し、計画を立てることが必要です。
(参考:令和5年度子供の学習費調査の結果|文部科学省)
(参考:国公私立大学の授業料等の推移|令和3年|文部科学省)
幼稚園〜高校までにかかる費用
子供の学習費は、公立か私立かによって大きく異なります。特に小学校と中学校では、その差がはっきりと現れます。
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高校までの15年間にかかる学習費の総額は、すべて公立の場合で約574万円、すべて私立の場合は約1,838万円と、約3倍以上の開きがあります。
以下は、学校種別の学習費の目安です。
(参考:令和5年度子供の学習費調査の結果|文部科学省)
※上記金額は各調査の年間費用を単純に年数倍した概算値です
どの進路を選択するかによって必要な資金額が大きく変わるため、早い段階で家庭の方針を話し合っておくと良いでしょう。
大学進学資金の平均額(国公立・私立)
教育費の中でも特に大きな割合を占めるのが大学の費用です。大学4年間でかかる学費の目安は、進路によって大きく異なります。
令和3年度の調査データによると、公立大学では約254万円、私立大学では約397万円かかります(入学料込み)。
また、これはあくまで学費のみの金額です。もし子供が自宅を離れて一人暮らしをする場合は、これに加えて仕送りや家賃などの生活費が必要になります。
大学進学を見据える場合、学費と生活費を合わせた総額を目標に、計画的な資金準備が不可欠です。
留学や私立医学部など高額ケース
子供の進路希望によっては、教育費が平均よりも大幅に高額になるケースも想定しておく必要があります。
代表的な例が、海外の大学への留学と国内の私立大学医学部への進学です。
海外の大学に正規留学する場合、学費や生活費を合わせると年間で数百万円以上かかることも珍しくありません。また、国内の私立大学医学部に進学する場合、6年間の学費総額は高額になるでしょう。
これらの進路は、通常の教育費プランとは別に、特別な資金計画が必要不可欠です。子供の将来の可能性を広げるためにも、こうした高額なケースが存在することを念頭に置いておくと良いでしょう。
子育てのお金が気になるあなたへ
これから先、教育資金で困ることのないよう、将来必要な額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶オンライン無料相談:幅広く対応できる専門家に直接相談
教育資金の準備方法
教育資金を準備するには、預貯金、制度の活用、保険商品など、さまざまな方法があります。
それぞれの特徴を理解し、ご家庭の方針やリスク許容度に合わせて組み合わせることが大切です。まずは基本となる方法から着実に始めましょう。
①基本は預貯金でコツコツ積み立てる
教育資金準備の最も基本的な方法は、預貯金で着実に積み立てることです。特に、毎月決まった額を自動的に別の口座に移す「自動積立定期預金」などを活用すると、計画的に資金を貯めやすくなります。
預貯金の最大のメリットは、元本が保証されている安心感です。万が一金融機関が破綻した場合でも、預金保険制度(ペイオフ)により1金融機関あたり元本1000万円とその利息までが保護されます。
現在の低金利環境では、預貯金だけで資産を大きく増やすことは期待できませんが、「お金を減らさない」という確実性は、時期が決まっている教育資金の準備において大切なポイントです。
資産運用のリスクを取りたくない場合や、準備期間が短い場合では、最も有力な選択肢と言えるでしょう。
②児童手当など制度を活用する
国から支給される児童手当を計画的に貯蓄・運用することも、教育資金準備の有効な手段です。児童手当は、子供が0歳から高校卒業(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで支給されます。
2024年10月からの制度拡充により、所得制限が撤廃され、第3子以降は月額3万円に増額されるなど、子育て世帯への支援が手厚くなりました。
仮に子供が生まれてから高校卒業まで全額を貯蓄した場合、総額で200万円以上のまとまった資金になります。
児童手当は生活費に充てることもできますが、「子供のための手当」として最初から無かったものと考え、専用の口座で管理し、将来の教育費に充てることで、大きな助けとなります。
③学資保険への加入は比較検討して決める
教育資金の準備方法として広く知られているのが学資保険です。学資保険は、貯蓄機能と保障機能を兼ね備えた保険商品で、子供の進学時期に合わせて祝金や満期保険金を受け取れるように設計されています。
ただし、加入を検討する際はメリットとデメリットを十分に理解し、他の金融商品と比較することが大切です。
学資保険のメリット・デメリット
学資保険は、計画的に教育資金を積み立てられる点が大きなメリットです。契約時に決めた満期日や進学の節目に満期保険金や祝金を受け取れるため、確実に資金を準備できます。
また、契約者に万一のことがあった場合でも、保険料の払い込みが免除され、予定通りの給付金を受け取れる仕組みも安心材料です。
一方で、返戻率は低金利の影響を受けやすく、必ずしも大きな増加が期待できるわけではありません。
さらに、中途解約すると元本割れのリスクがある点もデメリットです。
終身保険での教育資金準備という選択肢
終身保険を活用して教育資金を準備する方法もあります。終身保険は一生涯の保障が続くため、将来的に必要になれば解約や貸付で資金を引き出せる柔軟性があります。
また、解約返戻金を教育資金に充てられるだけでなく、相続対策としても活用できる点が特徴です。
ただし、学資保険に比べると教育資金の準備という目的に特化していないため、受け取りのタイミングや金額は自身で計画を立てる必要があります。
保障と資産形成を両立したい家庭に向いている選択肢といえるでしょう。
余力がある場合の運用方法|プラスαの選択肢
預貯金や学資保険で教育資金の土台を固めた上で、さらに資金的な余力がある場合は、資産運用を取り入れることで、より効率的に資産を増やすことを目指せます。
特に、長期間の運用が可能な場合は、リスクを抑えながらリターンを狙う選択肢が広がります。
長期で余裕資金を活用するならNISA
教育資金準備のプラスアルファとして資産運用を考えるなら、NISA(少額投資非課税制度)の活用が有力な選択肢です。
新NISAは、投資で得た利益(分配金や譲渡益)が非課税になる制度で、効率的な資産形成を後押しします。
特に、子供が小さいうちから始めれば、10年以上の長期運用が可能です。長期間にわたって毎月一定額を積み立てる「積立投資」を行うことで、購入価格が平準化され、価格変動リスクを抑える効果(ドルコスト平均法)が期待できます。
また、世界中の株式や債券に分散投資された投資信託を選べば、一つの国や資産に集中するリスクも軽減できます。
Q.子供名義でNISA口座を開設できる?
現在のNISAでは、子供名義で口座を開設することはできません。NISAの対象は18歳以上で、未成年は利用できない仕組みになっています。
以前は「ジュニアNISA」という制度で子供名義の口座を開設できましたが、2023年で新規受付が終了しています。
現在は親名義のNISAを使って将来の教育資金を準備するか、学資保険や終身保険など他の方法と組み合わせて備えるのが一般的です。
まとまった資金なら債券で堅実運用
もし、お祝い金などでまとまった資金があり、かつ株式投資のような価格変動リスクをあまり取りたくない場合は、債券での運用も選択肢の一つです。
債券は、国や企業などが資金を調達するために発行する有価証券で、満期(償還日)まで保有すれば、原則として額面金額が戻ってきます。
また、保有期間中は定期的に利子を受け取ることができます。
株式に比べて価格変動が穏やかで、比較的安定した運用が期待できるのが特徴です。発行体(国や企業)が財政破綻しない限り、満期時の元本割れのリスクは低いです。
リスクを抑えながら預貯金よりも有利な利回りを狙いたい場合に適した金融商品と言えるでしょう。
子供の教育費と自身の老後資金のバランス
子供の教育費を準備する際には、自身の老後資金とのバランスを考えることが非常に重要です。
教育費を優先するあまり、老後資金の準備がおろそかになると、将来的に困窮するリスクがあります。
両方のライフイベントを見据えた、長期的な資金計画を立てましょう。
教育費は「借りられる」が老後資金は借りられない
資金計画を立てる上で重要な考え方の一つに、「教育費は奨学金や教育ローンで借りることができるが、老後資金は誰も貸してくれない」という事実があります。
子供の進学のためにと、親が無理をして貯蓄をすべて使い果たしたり、老後資金を取り崩したりするケースは少なくありません。しかし、その結果、自分たちの老後の生活が立ち行かなくなっては本末転倒です。
もちろん、子供に借金をさせたくないという親心は理解できますが、まずは自分たちの老後生活を安定させることが、結果的に子供に迷惑をかけないことにも繋がります。
教育費の準備と並行して、老後資金の準備も計画的に進めることが、家族全体の将来にとって不可欠です。
NISAやiDeCoを活用して老後資金を確保
老後資金を効率的に準備するためには、NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度を最大限に活用することが推奨されます。
NISAは、教育資金の準備と並行して、老後資金のための運用にも利用できます。非課税保有限度額は1800万円と大きく、生涯にわたって非課税で運用できるため、長期的な資産形成に非常に有利です。
一方、iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税、受け取る際にも税制優遇があるなど、老後資金準備に特化した強力な制度です。
ただし、原則60歳まで資金を引き出せないため、教育資金のような途中で必要になる可能性のある資金の準備には向きません。
「いつでも引き出せるNISAは教育資金と兼用、引き出せないiDeCoは老後資金専用」といったように、制度の特性を理解し、使い分けることで、両方の資金を計画的に準備することが可能です。
お金の使い方に悩んだ時はマネイロに相談がおすすめ
子供の教育資金や自分たちの老後資金など、将来のお金の計画は非常に重要ですが、複雑で難しいと感じる方も多いでしょう。
「どの方法が自分たちに合っているのか」「具体的な計画の立て方がわからない」といった悩みは、一人で抱え込まずに専門家に相談するのがおすすめです。
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)やファイナンシャルプランナー(FP)は、特定の商品を売ることを目的とせず、中立的な立場からあなたの家庭の状況や目標に合わせた最適なプランを提案してくれます。
マネイロは、SBI証券と提携するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)です。資産運用の具体的な方法はもちろん、保険の見直しや家計全体のバランスまで幅広くサポートしています。
総合的なアドバイスを受けることで、将来への漠然とした不安を解消し、自信を持って資産形成に取り組めるようになります。
マネイロでは無料相談を行っているため、まずは気軽に相談してみませんか。
マネイロの無料相談予約はこちらから▽
まとめ
今回は、子供のための貯金や運用について、目的別の考え方から具体的な準備方法まで解説しました。
- 資金の目的で運用方針を決める:時期が決まっている教育費は安全性を、時期未定の資金は収益性を重視する
- 教育費の目安を把握する:進路によって1000万円~2500万円以上と大きく変動するため、早期の計画が重要
- 準備方法を組み合わせる:預貯金を基本に、児童手当や学資保険、余力があれば新NISAなどを組み合わせるのが効果的
- 老後資金とのバランスを忘れない:教育費と老後資金は並行して準備することが、家族全体の将来のために不可欠
子供の将来の選択肢を広げるためにも、ご自身の豊かな老後のためにも、この記事を参考に、ご家庭に合った資金計画を立ててみてください。
»まずは老後の必要なお金を確認|無料診断はこちら
子育てのお金が気になるあなたへ
これから先、教育資金で困ることのないよう、将来必要な額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶オンライン無料相談:幅広く対応できる専門家に直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください