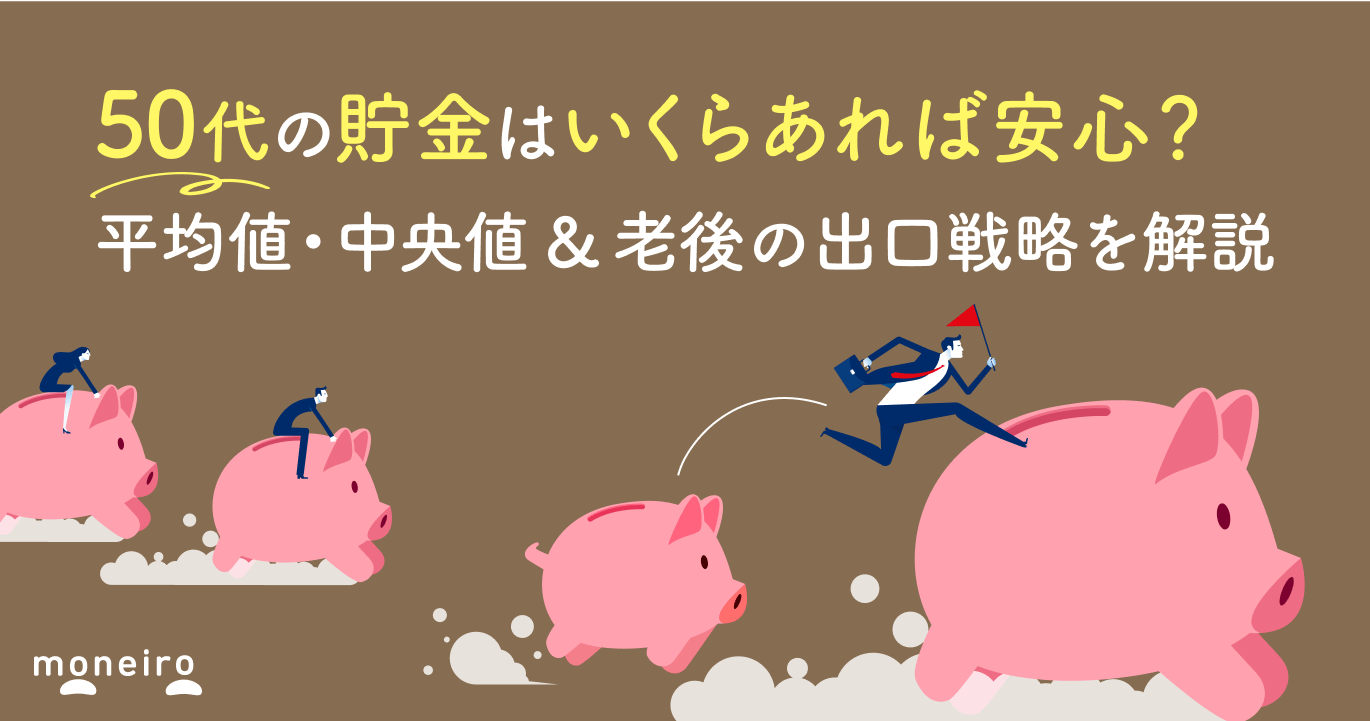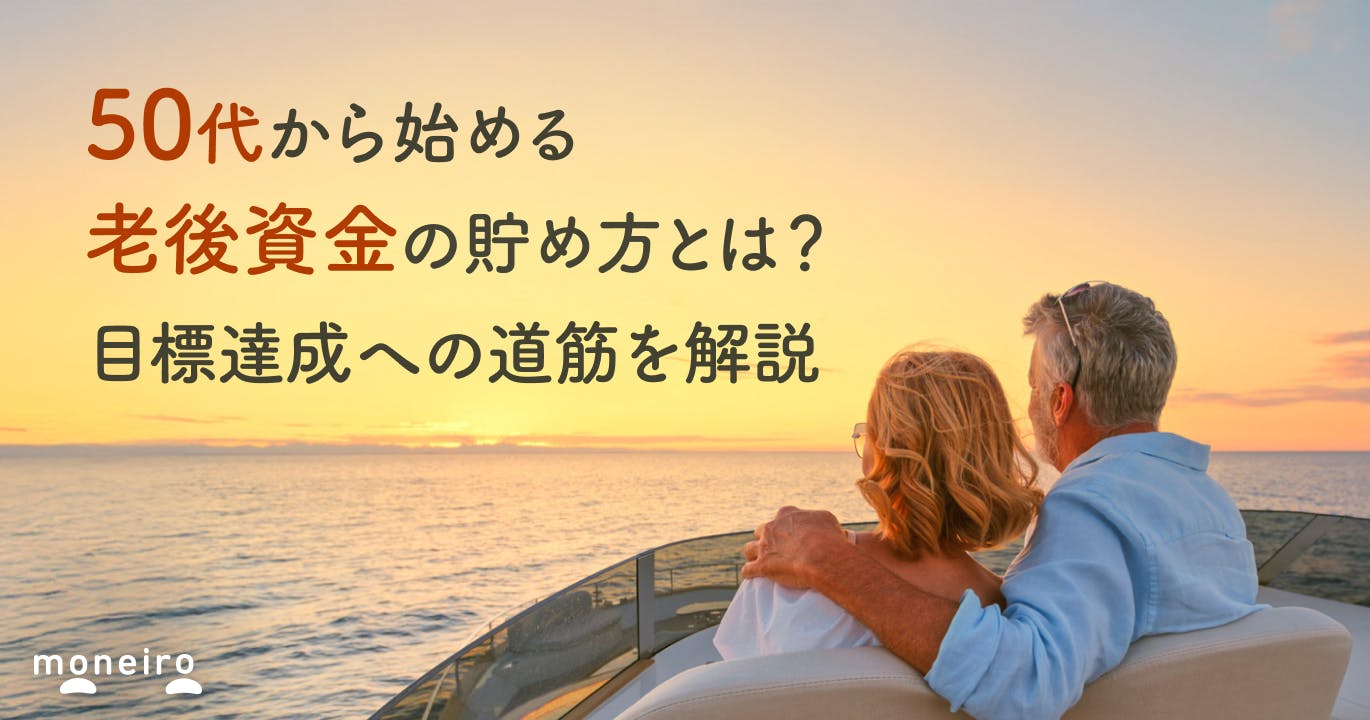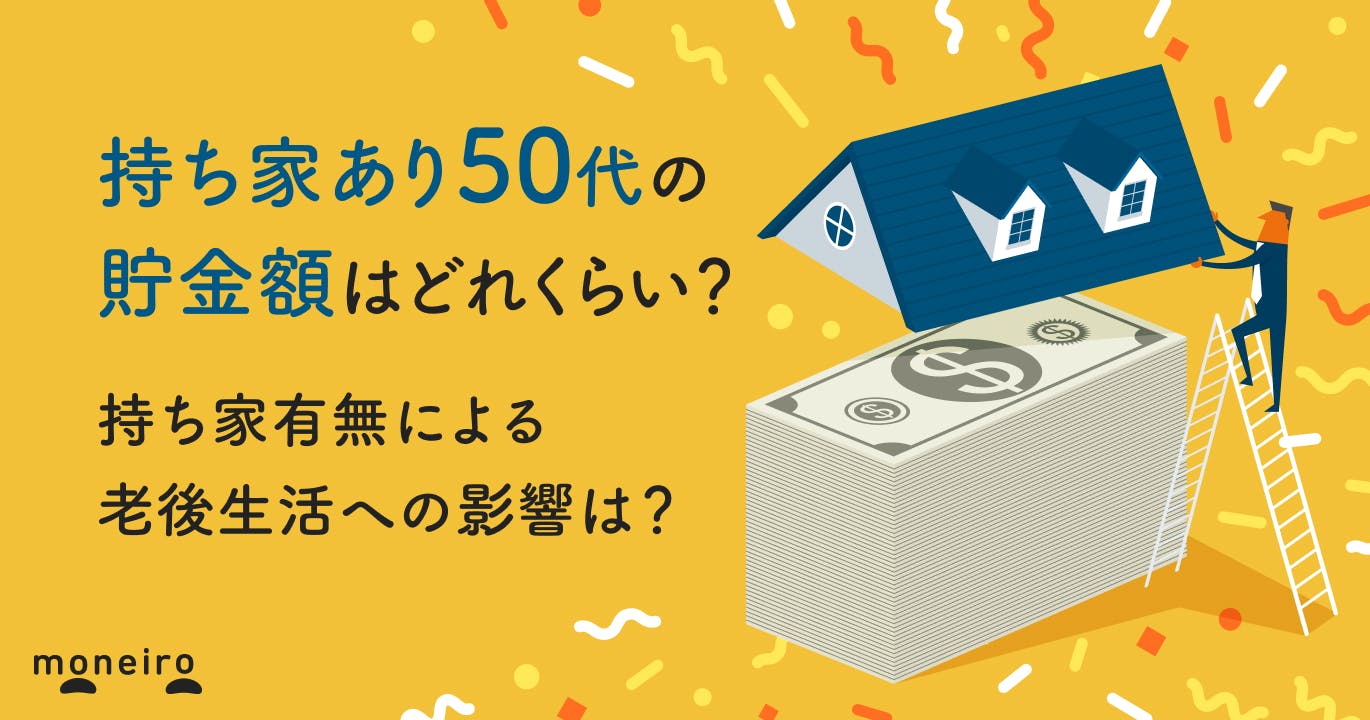50代の貯金はいくらあれば安心?平均値・中央値&老後の出口戦略を解説
【無料】あなたの不足額はいくら?老後の必要資金を年収・資産から診断
50代を迎えると老後の生活資金について考えることも増えてくるでしょう。現時点で貯金がいくらあれば安心なのだろう?と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません、
そこで本記事では、世帯別の平均貯金額や中央値を確認するとともに、老後資金の計画方法や退職金・年金の効果的な受け取り方、そして資産寿命を延ばすための「出口戦略」について解説します。
この記事を通じて老後の不安を解消し、安心してセカンドライフを送るための具体的なヒントを見つけていきましょう。
- 50代の単身世帯と2人以上世帯それぞれの平均貯金額と中央値
- 老後の生活に必要な資金を見積もり、不足額を把握するためのステップ
- 退職金や年金の賢い受け取り方と老後に向けた資産形成の具体的な対策
貯金額が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
50代の平均貯金額はいくら?
まずは、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」のデータをもとに、50代の平均貯金額と中央値を確認し、それぞれの違いを理解していきましょう。
平均値は全体の合計を世帯数で割ったものですが、一部の極端に高い貯蓄を持つ世帯に引き上げられやすい傾向があります。一方、中央値はデータを小さい順に並べたときにちょうど真ん中に位置する値のことを指し、より実態に近い金額を示す傾向があります。
50代(単身世帯)の平均貯金額は?
50代・単身世帯では、金融資産あり世帯が59.8%、金融資産なし世帯が40.2%となっています。そして、金融資産ありと回答した世帯の内訳は以下のとおりです。
50歳代の単身世帯(金融資産あり世帯)の平均金融資産保有額は1859万円、中央値は600万円となっています。この区分では、3000万円以上の世帯が18.7%を占めており、これによって平均値を大きく押し上げている可能性があります。
一方で、もっとも多いのは100万円未満の21.9%となっています。これは金融資産あり世帯のうちの割合で、「なし」世帯も合わせた全体でみると約13.1%が該当します。
また、金融資産なし世帯は全体の40.2%あり、これらを合計すると、全体の約53.3%が金融資産100万円未満であることがわかります。
50代(2人以上世帯)の平均貯金額は?
50代の2人以上世帯では、金融資産あり世帯は70.8%、なし世帯は29.2%となっています。金融資産あり世帯の金融資産保有額の内訳は以下のようになっています。
50歳代の2人以上世帯(金融資産あり世帯)の平均金融資産保有額は1677万円、中央値は700万円となっています。2人以上世帯では3000万円以上の割合がもっとも多く15.2%となっており、これが全体の平均を押し上げる結果となっています。
一方で単身世帯では保有資産100万円未満が半数以上でしたが、2人以上世帯では約37.9%で、約15%程度少ないことがわかります。これには、収入源の数の違いや、子育て等のライフイベントの違いによる貯蓄習慣の有無などが影響していると考えられます。
老後の「安心」のために必要な金額は?
老後に安心して生活するために必要な金額は、個々のライフスタイルや希望する生活水準によって大きく異なります。まずは具体的な金額を把握することから始めましょう。
老後に必要な金額を把握するステップ
老後に必要な金額を把握するためには、以下のステップで進めることが有効です。
退職後の生活費を見積もる
まず、退職後の基本的な生活費を具体的に見積もることから始めましょう。現在の生活費を参考にしつつ、退職後に増減する項目を考慮します。
例えば、通勤費が不要になったり交際費が減ったりするかもしれない反面、趣味の費用などが増えたりするかもしれません。
また、老後は医療費や介護費用、住宅のリフォーム費用、あるいは子どもや孫の結婚支援なども必要になることがあります。これら必要になる可能性のある支出も大まかに想定しておきましょう。
退職後の収入を把握する
次に、退職後の主な収入源となる年金や、受け取り方を選べる退職金の見込み額を把握します。
公的年金の受給見込み額は、ねんきん定期便などで確認できます。退職金については、勤務先の規定を確認し、おおよその金額を把握しておきましょう。これらの収入で、見積もった生活費をどれだけカバーできるかを確認します。
老後の不足金額を計算する
最後に、見積もった退職後の生活費から、把握した退職後の収入(年金や退職金など)を差し引き、月々または年間でどれくらいの金額が不足するのかを計算します。
その不足額が生涯にわたってどれくらいの総額になるのかを算出し、現在の保有資産額からその足りない金額を割り出すことで、老後資金として準備すべき具体的な目標額が見えてきます。
退職前に確認したい退職金&年金の受け取り方
退職金と年金は、老後資金の大きな柱となります。これらの受け取り方には複数の選択肢があり、自身の状況に適した方法を選ぶことが大切です。
退職金の有利な受け取り方は?
退職金は、主に「一時金として一括で受け取る」「年金形式で分割して受け取る」「その2つを組み合わせて受け取る」という3つの方法を選択できます。それぞれにメリットとデメリットがあり、特に税制面での取り扱いが異なります。
一時金で受け取る
退職金を一時金で受け取る場合、「退職所得控除」という大きな税制優遇が適用されます。これは、勤続年数に応じて非課税となる所得金額が大きくなる制度で、多くの場合、退職金全額または大部分を非課税で受け取ることができます。
また、健康保険料の算定基準となる所得には含まれないため、一時金で受け取っても翌年度の保険料が急激に上がることはありません。手元にまとまった資金が入り、老後の生活設計を立てやすいというメリットもあります。
年金で受け取る
退職金を年金形式で受け取る場合、受け取り額は「公的年金等控除」の対象となります。これは公的年金と同様に、一定額までは非課税となり、それを超える部分が課税対象となります。
年金形式で受け取るメリットは、計画的に資金を使うことができ、使いすぎを防げる点にあります。ただし、毎年の所得として扱われるため、所得税や住民税が発生し、翌年度の健康保険料の算定基準に含まれる可能性がある点には注意が必要です。
一時金と年金を併用する
一時金と年金を併用することもできます。一部を一時金として受け取り、残りを年金として少しずつ受け取る方法です。
この方法を選択することで、一時金として受け取ったお金で住宅ローンの返済や車の購入などまとまった支出に充て、残りを退職後の生活費に充当する、といった「いいとこ取り」の使い方ができます。双方のメリットを享受しながら、デメリットも軽減できる可能性があります。
年金の最適な受け取り方は?
公的年金の受け取りは、原則65歳からですが、個人の選択によって受け取り開始時期を調整することもできます。
繰上げ受給
65歳よりも早く(60歳から64歳までの間に)年金を受け取り始めることを「繰上げ受給」といいます。早く受け取れるメリットがある一方で、1ヶ月繰り上げるごとに0.4%(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%)が減額されます。なお、減額率は生涯にわたって続きます。
特に、早い段階で生活資金が必要な場合や、長期的に見て健康状態に不安がある場合には有力な選択肢になります。
繰下げ受給
反対に、65歳よりも遅く(66歳以降75歳までの間に)年金を受け取り始めることを「繰下げ受給」といいます。受け取りを1ヶ月繰り下げるごとに0.7%が増額され、仮に70歳から受け取りを開始すると42%増、75歳から開始した場合は84%増と大幅に年金受給額を増やすことができます。この増額率は一生涯変わりません。
健康で長生きが見込まれる場合や、受給開始まで他の収入や保有資産で生活資金をまかなえる場合は、検討してみるとよいでしょう。
繰上げ受給・繰下げ受給の損益分岐点は?
繰上げ受給と繰下げ受給のどちらで総受給額が多くなるかは、寿命によってことなります。
65歳時点で受給開始した場合と60歳から繰上げ受給を開始した場合の損益分岐点は「80歳10ヶ月」です。つまり、これよりも長生きをすると、総受給額で損をする計算です。
一方、70歳から繰下げ受給を開始した場合の損益分岐点は「81歳11ヶ月」となり、これよりも前に亡くなってしまうと総受給額で損をし、これより長生きをすると得をすることになります。
老後に向けた資金作り&資産寿命を延ばす具体策
退職までの残り期間は限られていますが、今からでも現実的なアクションプランを実行することで、老後の資金を増やし、資産寿命を延ばすことが可能です。
子ども独立後の「家計スリム化」と積み立て
子どもが独立すると、教育費などの支出がなくなります。このタイミングで家計を見直し、不要になった支出を洗い出すことが重要です。
例えば、保険料の見直しや、交際費や不要なサブスクリプションサービスなど、削減できる項目がないか確認します。そして、そこで浮いたお金を貯蓄や投資に回すことで、効率的に老後資金を積み立てていくことができます。
毎月少額からでも、継続的な積み立てが将来の大きな資産へとつながります。
貯金額が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
退職金のNG運用と賢い置き場所
退職金を受け取ったあとも、老後の不安から「もっと増やしたい」という気持ちがふくらむことがあります。そして、金融機関などのセールストークに乗せられてリスクの高い投資に手を出してしまうケースも少なくありません。
老後資金は将来のための大切な資金であるため、運用の失敗はなんとしても避けなければなりません。そのため、基本的は定期預金などで一定額をしっかり確保しつつ、必要に応じて、債券など比較的リスクの低い運用先を検討するのがおすすめです。
60歳以降の働き方を考える
定年後も働き続けることは、継続的に収入を得ることはもちろん、社会とのつながりを保ち、健康を維持する上でも有効な手段です。
60歳以降も働き続けるには、再雇用制度を利用して現在の会社で働き続ける、あるいはこれまでの経験を活かして再就職を目指す、シルバー人材センターを通じて地域貢献をしながら働く、といった選択肢があります。
老後も一定の収入があることで貯蓄を取り崩すペースを緩められ、資産寿命を延ばすことができます。老後の安心にもつながるでしょう。
50代の貯金に関するよくある質問(Q&A)
最後に50代の貯金に関する質問にお答えします。
Q. 50代からでも老後資金作りは間に合う?
はい、50代からでも老後資金作りは十分に間に合います。もちろん、早いに越したことはありませんが、この年代からでも対策を始めることで、老後の安心感を高めることが可能です。
具体的な対策としては、まず家計の見直しから始めましょう。子どもが独立した場合は減った支出を貯蓄に回せます。さらに保険や通信費など固定費を削減することでも、貯蓄額を増加させることができるでしょう。まずは無理のない範囲から、着実に資産形成を進めることが大切です。
Q. 50代で1000万円貯金している人の割合は?
上記でも紹介した金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」のデータによると、金融資産保有額が1000万円以上の割合は、50代・単身世帯で23.8%、2人以上世帯で28.4%です。つまり、おおむね50代の4人に1人くらいは1000万円以上の金融資産を持っていることになります。
まとめ
50代は、老後の生活設計を具体的に進める上で非常に重要な時期です。老後の安心を得るためにも、退職後の生活費を見積もり、年金や退職金などの収入を把握し、不足額を明確にすることが不可欠だといえます。
最初のステップとして、まずは現状の家計の見直しと貯蓄の最適化から始めましょう。また事前に退職金や年金の受取額がどれくらいになるかを想定しておくと、老後に足りない額を算出することもできるようになります。
50代からでも、こうしたアクションを着実に実行することで、老後の不安を解消し、安心してセカンドライフを迎えることができるはずです。
貯金額が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。