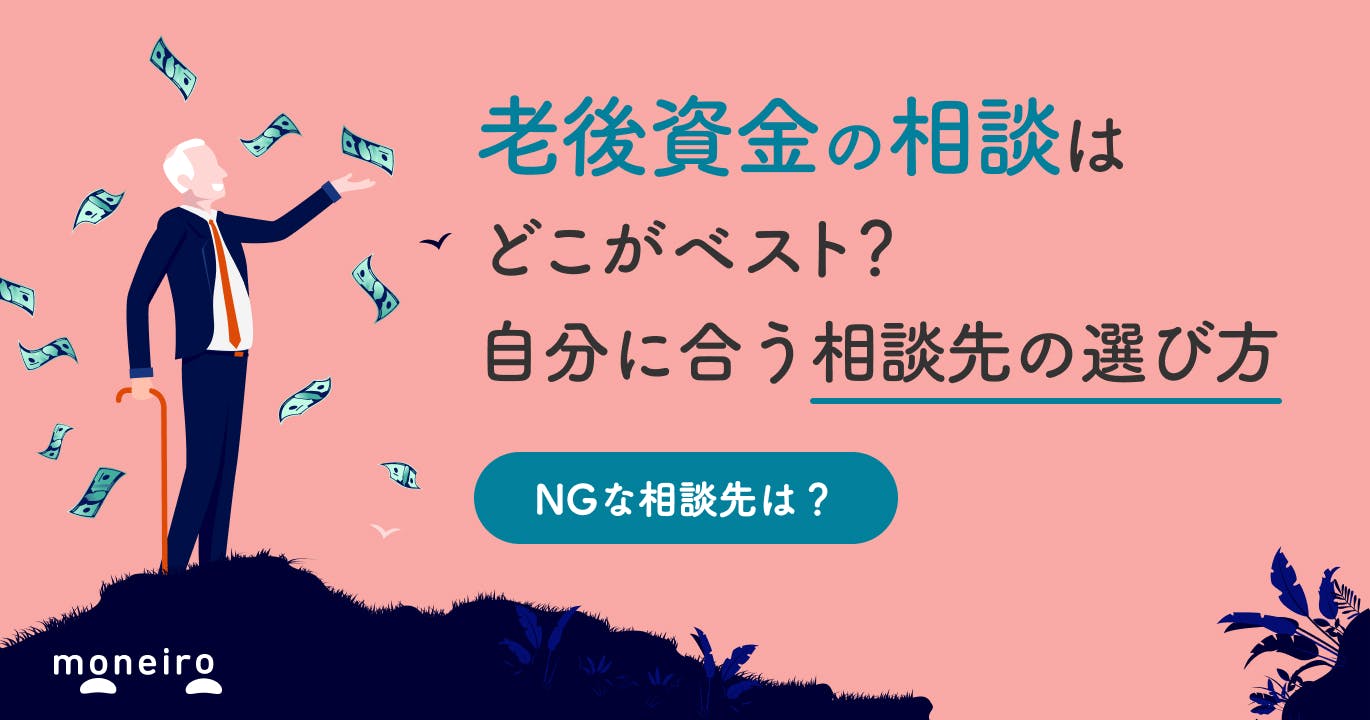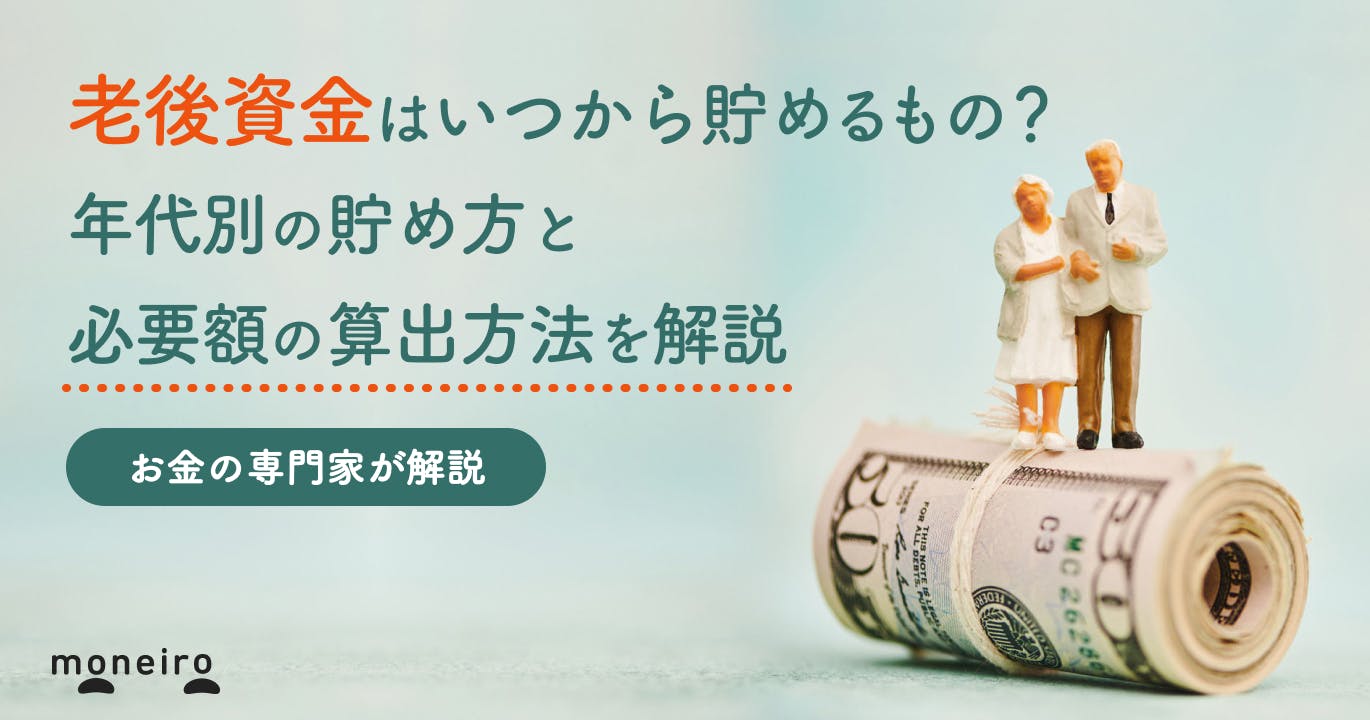独身の老後資金はいくら必要?平均的な不足額&ライフスタイル別シミュレーション
»面倒な計算は不要|本当に必要な老後資金を診断
「独身の老後資金はいくら必要?」将来に対する漠然とした不安を持つ独身の方も多いでしょう。
本記事では、公的な統計データに基づき、独身の老後資金の平均的な不足額を紹介するとともに、年金受給額やライフスタイル別のシミュレーション、介護・医療費を加味した最終的な必要額まで解説します。この記事を参考に将来の不安を解消しましょう。
- 高齢単身世帯の平均生活費と、年金の平均受給額から算出される老後の不足額
- 高齢単身者のライフスタイル別の不足額シミュレーション
- 生活費の不足額に介護費用や医療費などを加えた「最終必要額」
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ


独身の老後にはいくら必要?
老後資金の必要額を把握するためには、まず「毎月の支出」と「毎月の収入」の平均値を知り、その差額(不足額)を試算することから始まります。公的な統計データから、独身者の老後の平均的な収支を見ていきましょう。
【支出】高齢単身世帯の生活費
独身者の老後の生活費を知る上で参考になるのが、総務省が公表している「家計調査(家計収支編 2024年)」のデータです。
この調査によると、「高齢単身世帯のうち無職世帯」(世帯主が60歳以上の単身無職世帯)の1ヶ月間の消費支出の平均は14万9286円となっています。この金額は、日々の衣食住を満たすための最低限の生活費の目安と捉えることができます。
家計調査の「住居費」は持ち家前提
上記の平均消費支出14万9286円に含まれる「住居費」は、平均で1万2693円と非常に低い金額です。これは、統計対象である高齢単身世帯の86.6%が持ち家であるため、住宅ローンを完済している世帯が多く含まれているためです。
もし老後も賃貸住宅に住み続ける場合、家賃が別途必要となり、毎月の支出は大幅に増加することを念頭に置く必要があります。
ゆとりある生活がしたい場合はさらに資金が必要に
毎月14万9286円という平均支出は、あくまで「最低限の生活」を送るための目安と捉えたほうがよいでしょう。
趣味、旅行、レジャー、交際費といった精神的な豊かさや楽しみを追求するための「ゆとりある生活」を送るためには、さらに上乗せの資金が必要です。
具体的な目標額を設定するためにも、毎年の海外旅行や習い事など、具体的なやりたいことにどの程度の費用がかかるかを事前に見積もっておくことが大切です。
【収入】年金の平均受給額
老後の収入の柱となる公的年金について、厚生労働省が公表する「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」に基づき、平均受給額を見ていきましょう。
厚生年金の平均受給額
老齢厚生年金(老齢基礎年金を含む)の受給者全体の平均年金月額は、14万7360円です。この全体平均額は、高齢単身世帯の平均消費支出14万9286円と比べると、ほぼ「トントン」であることが分かります。
ただし、年金受給額は現役時代の収入や厚生年金の加入期間によって個人差が大きく、特に男女別で見ると大きな差があります。
65歳以上の平均受給月額は、男性が16万9484円、女性が11万1479円となっており、女性のほうが平均で約5万8000円低くなっています。この差は、主に現役時代の平均標準報酬額やキャリアの中断など、厚生年金の上乗せ部分の額に差が生じることに起因しています。
国民年金の平均受給額
自営業者やフリーランス、あるいは主婦など、国民年金(老齢基礎年金)のみに加入している方の平均受給額は月額5万7700円です。厚生年金加入者と比較して、平均で約9万円近く低い水準であることが分かります。
もし国民年金のみの受給となる場合は、より多くの老後資金を準備する必要があります。
「ねんきんネット」で自分の見込額を確認しよう
紹介した平均額はあくまで目安であり、個々人の正確な年金見込額は、加入履歴や保険料の納付状況によって異なります。
正確な見込額を知るためには、日本年金機構が運営する「ねんきんネット」を活用するのが確実です。ねんきんネットでは、これまでの加入記録や、将来の年金見込額をさまざまな受給開始年齢や働き方のパターンで試算できます。また、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」も、自身の年金見込額を確認する重要なツールとなります。
老後の平均的な必要額は?
老後の必要額は、「毎月の支出」から「毎月の収入」を差し引いた「毎月の不足額」に、老後生活が続く期間を掛けて算出します。
平均的なデータ(老後期間を65歳から90歳までの25年間=300ヶ月と仮定)で試算すると、高齢単身無職世帯の平均消費支出14万9286円に対し、厚生年金受給権者全体の平均年金月額は14万6429円です。その差額は月々2857円となり、25年間の不足額は、2857円 × 300ヶ月 = 85万7100円となります。
平均で見ると、年金で生活費がほぼ賄えるという結果になりますが、これは持ち家前提の生活費であり、かつ厚生年金全体の平均です。特に女性や国民年金のみの方、賃貸居住者の場合は、不足額が数千万円単位となるケースもある他、後述する介護費用なども考慮する必要があるため、個人差を考慮したシミュレーションは不可欠です。
【パターン別】独身の「生活費」不足額シミュレーション
ここでは、老後期間を30年間(360ヶ月)と想定し、ライフスタイルと年金受給額に基づいた、具体的な不足額シミュレーションを行います。
生活費は高齢単身無職世帯の平均消費支出14万9286円をベースとし、家賃変動分や住居費平均額(1万2693円)を調整して計算します。
パターン1:持ち家(ローン完済)× 厚生年金(男性平均)
このパターンは、老後資金の準備としては比較的余裕があるケースです。
- 毎月の支出(持ち家前提の平均消費支出): 14万9286円
- 毎月の収入(厚生年金 男性平均): 16万9484円
- 毎月の収支: 2万198円の黒字
平均的な生活を送る分には、公的年金だけで毎月2万198円の黒字となり、生活費の不足は発生しません。ただし、「ゆとりある生活費」や、後述する介護・医療費を考慮すると、別途資金準備が必要になります。
パターン2:持ち家(ローン完済)× 厚生年金(女性平均)
女性は平均年金受給額が男性より低いため、持ち家であっても不足が生じやすくなります。
- 毎月の支出(持ち家前提の平均消費支出): 14万9286円
- 毎月の収入(厚生年金 女性平均): 11万1479円
- 毎月の不足額: 3万7807円
- 不足額(30年間): 3万7807円 × 360ヶ月 = 1361万720円
老後期間を30年間と想定した場合、必要な貯蓄総額は約1361万円となり、男性と比較してかなりの大金が必要になることがわかります。
パターン3:賃貸(家賃7万円)× 厚生年金(女性平均)
住居費が平均より高くなる賃貸の場合、不足額が大きく跳ね上がります。
- 毎月の支出: 平均消費支出14万9286円から住居費1万2693円を引き、家賃7万円を加算し、合計20万6593円。
- 毎月の収入(厚生年金 女性平均): 11万1479円
- 毎月の不足額: 9万5114円
- 不足額(30年間): 9万5114円 × 360ヶ月 = 3424万1040円
このパターンでは、持ち家のあるケースと比較して、約2000万円以上多く準備が必要となります。このようなケースでは、家賃を大幅に抑えるといった対策も必要になるでしょう。
パターン4:賃貸(家賃7万円)× 国民年金(満額)
国民年金のみに加入している方が賃貸住宅に住む場合、もっとも老後資金の不足が深刻になる可能性があります。
- 毎月の支出: 賃貸(家賃7万円)を考慮し、20万6593円とします。
- 毎月の収入(国民年金 満額): 令和7年度の満額6万9308円※日本年金機構
- 毎月の不足額: 13万7285円
- 不足額(30年間): 13万7285円 × 360ヶ月 = 4942万2600円
このケースでは約4942万円という非常に大きな貯蓄総額が必要となります。ここまでの大きな額となると、自助努力による備えも難しくなってきます。
老後に向けて資金を備えていくのはもちろんですが、できるだけ家賃を抑えて支出を減らしつつ、老後も就労を続けるなどして一定の収入を確保するといった対策も重要になります。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
介護・医療費を上乗せした「最終必要額」を試算
上記シミュレーションで算出したのは、あくまで「生活費の不足額」です。独身の場合、いざという時の介護や医療、そして最期の費用についても、自分で全て賄う準備が必要です。
データで見る「介護」に必要な費用
独身者は、家族の介護力を期待できないため、施設入所や手厚い在宅サービスといった、お金で解決する手段に頼らざるを得ないケースが多くなります。
生命保険文化センターの2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、過去3年間に介護経験がある人が介護にかかった費用(単身世帯)は以下の通りです。
また、介護を行った期間の平均は約49ヶ月、住宅改造や介護用ベッドの購入費など、一時的な費用の合計は115万円となっています。
上記を参考に、仮に月額介護費用を9万円として計算すると、総額では115万円+(9万円 × 49ヶ月 )= 556万円が介護にかかる費用の目安となります。
もちろん、個人差はありますが、老後資金の計画には、このような介護リスクに対する備えも考慮したほうがよいでしょう。
忘れてはいけない「医療費」と「葬儀代」
高齢になると、病気や怪我のリスクが高まり、医療費の自己負担額が増える傾向にあります。公的医療保険の高額療養費制度があるとはいえ、先進医療や差額ベッド代、交通費など、想定外の費用がかかることがあります。
加えて、独身者は自分の死後のための「葬儀代」の準備も必要です。葬儀相談依頼サイト「いい葬儀」が実施した「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」によると、葬儀費用の平均総額は118.5万円となっています。死亡時に資金がない場合は「行旅死亡人」として扱われる可能性もあるため、最低限の葬儀費用と整理費用を確保しておくことが重要です。
さらに、住宅のバリアフリー化やリフォーム費用、車の買い替え費用といった突発的な臨時支出も、老後資金に含めておくと安心です。
【要注意】独身者が陥りやすい老後資金計画の落とし穴
独身者は将来頼る人がいないことが多いため老後資金はしっかりと用意しておく必要がありますが、貯めることにとらわれ過ぎて、間違った方法を取ってしまうこともあります。下記のような落とし穴には十分気をつけましょう。
過剰な節約による生活の質の低下
生活費の無駄な部分を削るのは資金作りにおいてはよいことですが、本来必要な部分まで削減するのは問題があります。
例えば電気代を節約するためにエアコンを使用せず熱中症になったり、風邪をひいたりしてしまえば余計な医療費がかかってしまいます。
また食費を削ることで栄養に偏りが出て健康を害してしまえば、病気のリスクを高めることもなりかねません。節約は大切ですが、あまりに生活の質を落とすことのないように注意しましょう。
リスクの高い投資への偏重
同じ金額を運用する場合、計算上は利回りの高いもので運用したほうが目標金額に早く到達できます。しかし利回りが高いということは相応にリスクも高いということです。
相場が上昇したときには大きな利益になりますが、反対に大きく下落したときには大きな損失になる危険性もはらんでいます。
基本的に、老後資金の準備は長期間にわたって行うものです。短期間でお金を増やしたいという気持ちも出てくるかもしれませんが、高リスクな投資商品に比重を置きすぎると、資金を作るどころか大きな損失を抱えてしまうことにもなりかねません。
情報選択の判断ミス
現在はインターネットに多種多様な情報があふれていて、分からないことがあれば即座に調べることができます。しかし時には間違った情報なども掲載されており、正しい情報を選択するのが難しくなっています。
特に独身者の場合は信頼して相談ができる人が周りにいないケースもあり、間違った判断をしてしまうケースもあります。将来のことやお金のことも含めて日頃から相談できる人を持つことで、自分と違った考え方を取り入れることができ、判断ミスの軽減に役立つでしょう。
老後資金が不安な場合は専門家への相談も有効
老後資金の目標額設定や、今後のライフプランなど、老後のことで不安を感じる場合は、お金のプロに相談することも有効です。専門家から意見を得ることで、客観的な視点と制度の最新情報に基づいた、より確実な計画を立てることができます。
相談から運用サポートまで無料の「マネイロ」を活用
マネイロは、さまざまな世代に向けた、お金の診断・相談サービスです。銀行・証券会社・保険会社などで実績を挙げたファイナンシャルアドバイザーが一人ひとりに担当としてつき、サポートを行います。
マネイロのアドバイザーは特定の金融機関に所属していないため、個人のライフプランや家計状況を総合的に判断し、最適な老後資金作りの方法や将来の運用方針について、客観的なアドバイスが可能です。
また、老後の生活費は健康状態や就労状況の変化によっても変わってくるため、その後のライフプランも定期的な見直しが大切です。
マネイロなら老後のファイナンシャルプランの相談を何度でも無料で対応できます。長期的なサポートを受けながら老後の資金計画を進めることができます。
\空いている日程から早速相談を予約してみる/
まとめ
独身の老後は、「足りるかどうか」を早めに可視化することが重要です。
独身の場合、年金・住居費・医療や介護など、すべてを自分一人で賄う前提になります。一方で、支出構造がシンプルな分、早めに把握できれば対策は立てやすいのも事実です。
まずは、老後に必要な金額と、年金・貯蓄でどれくらい賄えるのかを整理しましょう。不足が見えれば、今後の積立額や制度の使い方を現実的に調整できます。
マネイロの3分投資診断では、老後に必要な金額と現在の資産状況から、独身の老後資金の見通しを整理できます。
漠然とした不安を、具体的な判断材料に変えるための診断です。
»おひとりさまの老後資金をいますぐ無料診断
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。