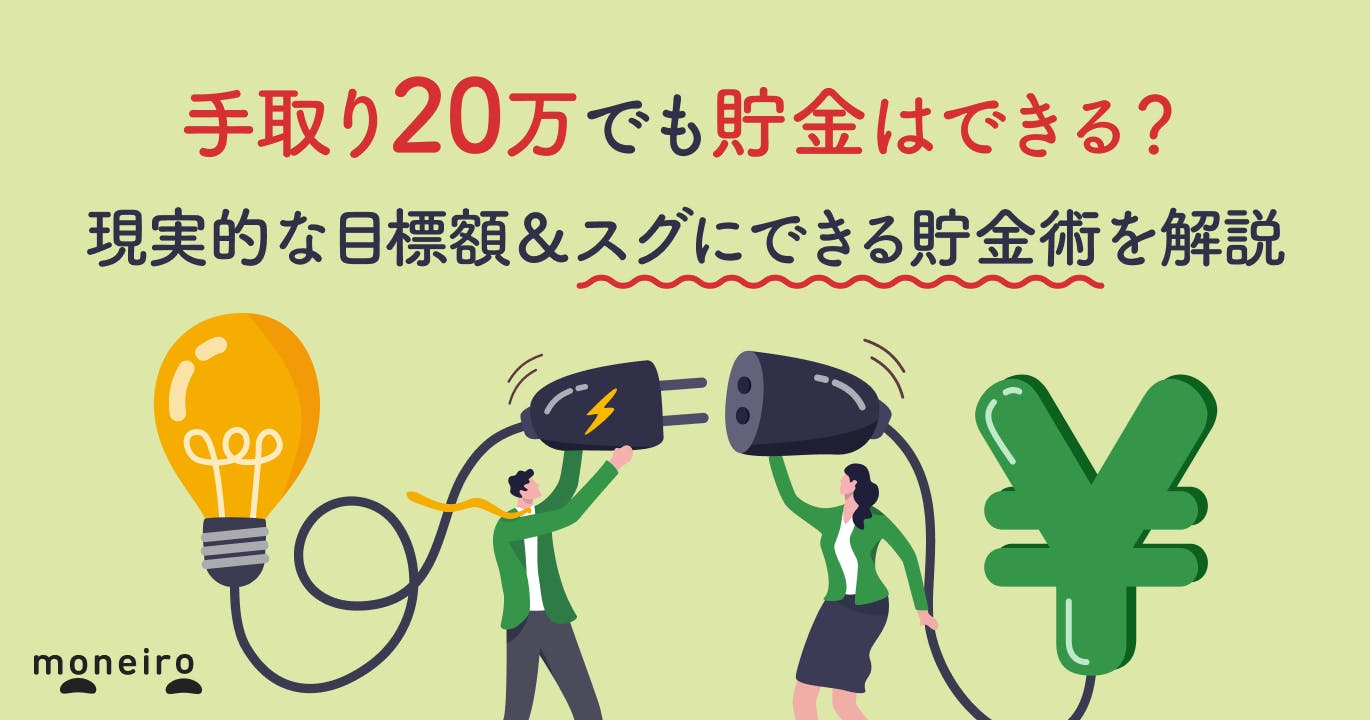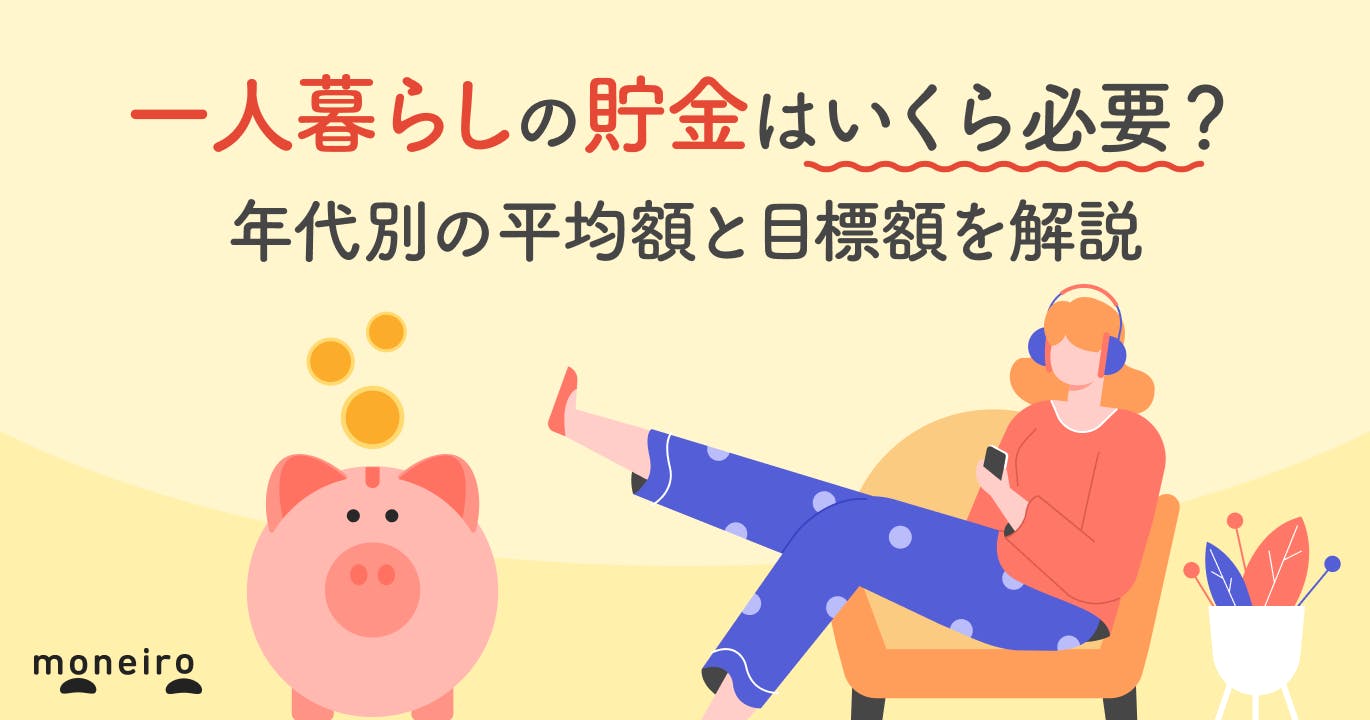手取り20万でも貯金はできる?現実的な目標額と今日からできる節約・貯金術
【無料】あなたはいくら?老後に必要な金額がわかる3分診断
「手取り20万円では貯金が難しい」と感じていませんか?そんなことは決してなく、収入の大小にかかわらず貯金は可能です。
この記事では、手取り20万円の方でも可能な現実的な目標額から、具体的な節約・貯金術、さらには少額からの資産運用まで、役立つ情報を網羅的に解説します。今日から実践できるヒントで、将来への漠然とした不安を解消し、着実に資産形成を進めていきましょう。
- 手取り20万円でも無理なく貯金を始める具体的な方法
- 手取り20万円の人のリアルな貯蓄状況と、現実的な目標額の目安
- 貯金体質を作るための家計見直し術
貯金や将来の備えが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後に必要な金額を把握して早めに準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
【基本】「手取り20万円」とは?額面と手取りの違い
収入の数え方には大きく分けて「額面」と「手取り」があります。まずはそれぞれの違いについてしっかり理解しておきましょう。
「額面(総収入)」とは?
「額面」とは、基本給に加えて、残業手当、通勤手当、役職手当など、会社から支給されるすべての給与・手当を合算した総支給額を指します。
「手取り」とは?「年収」はどちらで計算する?
「手取り」とは、給与明細に記載された総支給額(額面)から、税金(所得税、住民税)や社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険など)が差し引かれ、実際に銀行口座に振り込まれる金額のことを指します。この手取り額が、日々の生活費や貯蓄に回せる実質の金額となります。
なお、同じ額面収入であっても、個人の扶養家族の有無、加入している保険の種類、企業の福利厚生制度などによって、手取り額は変動する場合があります。
一般的に単に「年収」という場合は、この額面金額を1年間合計したものを指します。住宅ローン審査やクレジットカードの申し込み、転職活動などでは、この額面の年収を用います。
手取り20万円の人の年収はいくら?
手取り額は、一般的に総支給額(額面)の75~80%程度とされています。これは、額面からおよそ20~25%が税金や社会保険料として控除されるためです。
この仮定に基づくと、手取り20万円の人の額面月収は以下のようになります。
この月収をもとに、年収を計算してみましょう。
【賞与がない場合】
・月額面26.7万円 × 12ヶ月 = 約320.4万円
【夏と冬にそれぞれ1ヶ月分の賞与がある場合】
・月額面26.7万円 × 14ヶ月 = 約373.8万円
このように、手取り20万円であっても、賞与の有無によって年収は大きく変わってきます。まずは額面月収と年収を正確に把握することが、家計管理の第一歩です。
手取り20万円の人の貯金額はいくら?
では、実際に手取り20万円程度の人はどれくらい貯金できているのでしょうか。金融広報中央委員会が公表している「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」のデータをもとに詳しく見ていきましょう。
手取り20万円(単身世帯)の貯蓄額
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、単身世帯の貯蓄状況は以下のようになっています。
金融資産を保有している世帯の平均額・中央値
年間収入がある世帯のうち、「300万円未満」の単身世帯では、金融資産保有額の平均は1044万円、中央値が304万円となっています。また、一部の人が該当すると考えられる、年間収入「300~500万円未満」の世帯では、金融資産保有額の平均は1495万円、中央値が500万円となっています。
一般的に、平均値は一部の高額な貯蓄を持つ世帯によって引き上げられる傾向があるため、より多くの世帯の実態に近いのは「中央値」であるといえます。
貯蓄額の分布
各年収帯における貯蓄額の分布は以下のようになっています。
いずれの年収帯でも100万円未満がもっとも多く、全体の4~5人に1人が該当しています。一方で、1000万円以上の貯蓄がある世帯も一定数あり、300万円未満で25.6%、300~500万円未満では33.5%にも上り、平均値を押し上げる結果となっています。
手取り20万円で貯金ゼロの割合はどれくらい?
同じく「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、年間収入300万円未満の単身世帯では36.1%が、300~500万円未満の世帯では26.0%が貯蓄なしとなっています。
これらのデータは、手取り20万円の人が含まれる年収帯において、貯金がゼロの状態の人が決して少なくない現実を示しています。このことから、貯金がないことは珍しいことではないことが分かります。
目指すべき目標額の目安は?
手取り20万円での貯金においては、まずは「100万円」を目指すのが現実的な目標となります。100万円という金額は、病気や失業など、予期せぬ大きな出費や収入減があった際にも対応できる「生活防衛資金」として非常に重要です。
100万円を貯めることで、精神的な安心感が得られ、その後のより大きな資産形成へのモチベーションにもつながるでしょう。
100万円達成までの道のりは?
目標金額100万円達成までの期間を計算してみましょう。
・毎月3万円を貯金できれば、約3年弱(100万円 ÷ 3万円/月 = 33.3ヶ月 = 約2年9ヶ月)で達成
無理のない範囲で毎月の貯金額を設定し、具体的な目標期間を見据えて貯金を始めるとよいでしょう。
貯金や将来の備えが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後に必要な金額を把握して早めに準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
手取り20万円でも貯金するためのステップ
では、手取り20万円の人はどのように貯金を進めていけばよいのでしょうか。ここでは、効率的な貯金のための具体的なステップを紹介します。
支出を「見える化」する
貯金を始める上でもっとも重要なのは、まず自分の収入と支出を正確に把握することです。何にどれだけのお金を使っているのかが分からなければ、どこを節約すべきかも見えてきません。
家計簿アプリやスプレッドシート(もちろん手書きの家計簿でも構いません)など、自分が継続しやすい方法で毎日の支出を記録し支出を「見える化」しましょう。
食費、交通費、娯楽費など、費目ごとに分けて記録することで、無駄な支出が明確になり、削減ポイントが見えてくるでしょう。
固定費を見直す
家計の節約において、一度見直せば継続的に効果が得られる「固定費」は、最優先で手を付けるべき項目です。固定費とは毎月決まって発生する支出のことで、住居費(家賃)や通信費、光熱費、サブスクリプションサービスなどが該当します。
通信費を見直す
スマートフォンやインターネットの通信費は、多くの人が見直しの余地がある項目です。
大手キャリアから格安SIMへの乗り換えを検討したり、契約中のプランを見直して、実際のデータ使用量に合ったプランに変更したりするだけでも、毎月数千円単位での節約につながる可能性があります。不要なオプション契約を解除することも忘れずに行いましょう。
電気・ガス会社を見直す
電力とガスの自由化により、消費者はさまざまな会社やプランから自由に選べるようになりました。
現在契約している電力会社やガス会社よりも、ご自身のライフスタイル(昼間の使用が多いか、夜間が多いかなど)や家族構成に合った料金プランを提供する会社に切り替えることで、無理なく光熱費を抑えることが可能です。料金比較サービスなどを利用して、お得な会社・プランをシミュレーションしてみましょう。
サブスクを見直す
動画配信サービスや音楽配信サービス、オンラインフィットネス、電子書籍など、便利なサブスクリプションサービスは増え続けていますが、契約しているものの利用頻度が低いサービスはありませんか?
あらためて確認すると、ほとんど使っていないのに月額料金を払い続けているサービスも出てくるかもしれません。契約中のサブスクサービスをすべてリストアップし、本当に必要で頻繁に利用しているものだけを残し、不要なものは解約することで、確実な固定費削減につながります。
家賃は見直すべき?
家賃は毎月の支出の中で大きな割合を占めることが多く、削減できれば家計への影響が大きいといえます。
ただし、上記の項目に比べると、家賃の削減はQOL(生活の質)に直結する部分であるため、慎重な検討が必要です。一般的には家賃の目安は手取り収入の25~30%程度といわれており、見直す際もこのラインを1つの目安にするとよいでしょう。
変動費を見直す
固定費の見直しがある程度進んだら、次に日々の心がけ次第で節約効果が出やすい「変動費」に目を向けましょう。変動費とは、毎月支出額が変わる食費、交際費、交通費、趣味・娯楽費などです。
特に、少額な出費でも積み重なると大きな金額になる「ラテマネー」を軽視しないことが重要です。例えば、会社の行き帰りに毎日コンビニでコーヒーやお菓子を300円買っているとしたら、1ヶ月で300円 × 20日 = 6000円、1年で6000円 × 12ヶ月 = 7万2000円にもなります。
これを控えることで、1回は小さな額でも「塵も積もれば山となる」節約効果が得られます。さらに、外食の回数を減らして自炊を増やす、コンビニではなくスーパーを利用する、水筒を持参するなど、できることから実践してみましょう。
「先取り貯金」で貯金を仕組み化する
確実に貯金を増やすためのもっとも効果的な方法の1つに「先取り貯金」を仕組み化することが挙げられます。これは、給料が銀行口座に振り込まれたら、まず貯蓄に回す分のお金を先に確保してしまうという方法です。
この方法のメリットは、手元に残ったお金で生活する習慣が身につくため、使いすぎを防ぎ、計画的に貯蓄を進められる点にあります。意志の力に頼るのではなく、システムとして貯蓄のサイクルを作り出すことで、無理なく貯金が継続できます。
貯金用口座を作るとさらに効果的
先取り貯金を実践する際は、給与の振込口座とは別に貯金専用の口座を作るのがおすすめです。給料日直後に設定した金額が自動的に貯金用口座へ振り込まれるよう、自動積立(定額自動送金)サービスを設定するとよいでしょう。
貯金用口座を別にすることで、日々の生活費と貯蓄を明確に区別でき、貯めたお金にうっかり手をつけてしまうことを防げます。また、貯金用口座の残高が着実に増えていく様子を実感できるため、モチベーションの維持にもつながります。
貯金に慣れたら始めたい少額の資産運用
貯金がある程度貯まり、家計管理の習慣が身についたら、次は少額からでも始められる資産運用を検討してみましょう。貯蓄だけではお金が増えにくい時代において、インフレによるお金の価値の目減りを防ぎ、効率的に資産を増やすために、資産運用は有効な手段です。
100円から積立可能「NISA」
NISA(少額投資非課税制度)は、年間一定額までの投資から得られた利益(配当金や売買益など)が非課税になる、国が推奨する投資制度です。2024年からは制度が大きく拡充され、非課税投資枠が大幅に増えました。
NISAで特に推奨されるのは、長期・積立・分散投資に適した投資信託などを選ぶことです。毎月少額をコツコツと積み立てることで、市場の変動リスクを抑えつつ、着実に資産形成を目指せます。
多くの証券会社では、月100円といった非常に少額から積立投資を始められるため、投資初心者でも気軽にスタートできます。
節税効果大「iDeCo」
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、投資信託などの運用商品を選んで資産を形成する「私的年金制度」です。NISAと同様に税制優遇を受けながら資産運用ができますが、iDeCoにはNISAとは異なる大きな特徴があります。
特に最大のメリットは、掛金が全額所得控除の対象となる点で、所得税や住民税の軽減につながります。
また、運用で得た利益も非課税で再投資され、将来年金や一時金として受け取る際にも一定の税優遇措置があります。
ただし、原則として60歳まで資金を引き出すことはできないため、老後資金の形成を目的とした長期的な制度である点を理解しておく必要があります。
まとめ
「手取り20万円では貯金が難しい」と感じていた方も、この記事でご紹介したステップを踏むことで、貯金は十分に可能です。
まず、支出の「見える化」でご自身の家計の現状を正確に把握することが重要です。次に、通信費やサブスクリプションサービスなどの「固定費」と、食費や交際費などの「変動費」を見直しましょう。
そして、給料が振り込まれたらすぐに貯蓄分を確保する「先取り貯金」を仕組み化することで、無理なく着実に貯金を増やすことができます。貯金専用の口座を設け、自動積立設定を活用すれば、貯蓄はさらに加速するでしょう。
今回の記事を参考に、今日からできる小さな一歩を踏み出すことで、将来への漠然とした不安を解消し、より豊かな生活を目指していきましょう。
貯金や将来の備えが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後に必要な金額を把握して早めに準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。