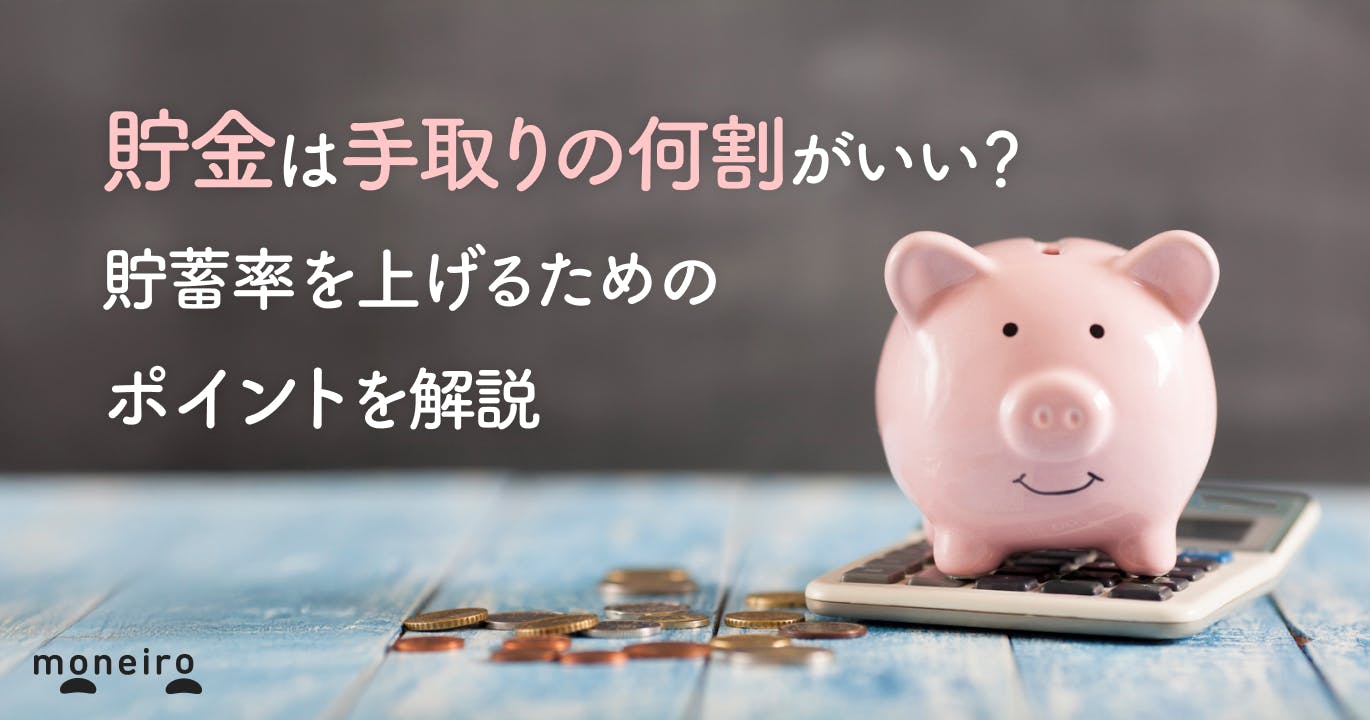
家賃は手取りの何割が目安?収入別の理想の賃料&後悔しないための決め方を解説
≫あなたは足りる?将来の必要額を年収から3分で診断
家賃は月々の支出の中でも大きな割合を占めるため、「家賃は手取り収入に対して何割くらいが適切なのか」と悩む人も多いでしょう。
そこでこの記事では、一般的な目安や、その割合の根拠、さらに具体的な収入に応じた適正家賃を詳しく解説します。この記事を参考に、最適な住まいを見つけましょう。
- 収入別・適正な家賃の目安
- 家賃を決める際に手取り以外に考慮すべき要素
- 後悔しないための具体的な家賃の計算方法と決め方
住居費が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
「家賃は収入の3割」が定説。本当?
家賃の目安として「収入の3割」という言葉をよく耳にするかもしれません。しかし、この「収入」が何を指すのかによって、その意味合いは大きく変わってきます。まずは基本をおさらいしておきましょう。
家賃の目安は「手取り」で考えるのが基本
家賃の目安を考える上でもっとも重要なのは、「手取り収入」を基準にすることです。
給与明細に記載されている「額面収入」は、社会保険料(健康保険、厚生年金など)や所得税、住民税などが差し引かれる前の金額であり、実際に自由に使えるお金ではありません。
これらの税金や社会保険料は給与から天引きされるため、実際に手元に残る金額、つまり「手取り」で家賃を考えるのが現実的です。額面で計算してしまうと、実際の生活費に使えるお金が想定よりも少なくなり、家賃が家計を圧迫する原因となる可能性があります。
家賃の目安は、手取り収入の25~30%
一般的に、無理なく生活できる家賃の目安は「手取り収入の25〜30%」とされています。
この割合が望ましいとされる理由は、家賃以外の生活費(食費、光熱費、通信費、交通費、娯楽費など)や、将来に備えた貯蓄とのバランスが取りやすいためです。
例えば、家賃が手取りの30%を超えると、食費や日用品などの生活必需品にかかる支出を削らざるを得なくなったり、趣味や貯金に回せる余裕がなくなったりするおそれがあります。
家賃が家計を圧迫すると、日々の暮らしが苦しくなり、精神的なストレスにもつながりかねません。
物価上昇で適正割合にも変化が
近年、食費や光熱費などの生活必需品の物価が上昇し、家計への負担が大きくなっています。収入が変わらなくても、以前より生活費がかさむようになっているのが実情です。
このような状況下では、家賃の負担はできるだけ抑えることが日々の安心感につながります。
例えば、家賃を手取り収入の25%程度に抑えられれば、物価上昇による生活費の増加にも柔軟に対応でき、家計にゆとりを持たせることができます。
生活費の変動リスクが高まる今だからこそ、将来的な支出も見越して、無理のない家賃設定を心がけることが大切です。
手取り月収別の適正家賃の目安
ここからは、具体的な手取り月収ごとに、家賃の目安とそこでの生活イメージを解説します。自身の収入と照らし合わせながら、具体的な家賃の上限をイメージしてみましょう。
≫あなたは足りる?将来の必要額を年収・資産から3分でシミュレーション
手取り15万円の場合の家賃目安
手取り15万円の場合、家賃の目安は3万7500円~4万5000円です。この金額では、東京23区内など都心部での一人暮らしは非常に厳しいといえます。
地方都市や都心から離れた郊外で、築年数が経っている物件や駅からの距離がある物件、またはワンルームなどのコンパクトな物件が主な選択肢となります。
また、家賃に回せる金額が限られるだけでなく、食費や光熱費、通信費などの生活費も厳しく管理し、節約を意識した生活が求められます。同様に貯金に回せる金額も少なくなるため、家賃はできる限り抑えることが、無理のない生活を送る上で不可欠でしょう。
手取り20万円の場合の家賃目安
手取り20万円の場合の家賃の目安は5万円~6万円です。手取り15万円の場合と比較すると選択肢は広がりますが、それでも都心部で駅近物件や一定の広さのある物件を探すのは簡単ではないでしょう。
とはいえ、一人暮らしであれば、郊外の比較的新しめの物件や、都心部でも広さを妥協すれば検討できる範囲に入ってきます。
家賃比率を抑えることで、生活費にゆとりを持たせたり、趣味や貯金に充てる金額を確保したりすることが可能です。この収入帯でも、家賃は可能な限り低く抑えることが、安定した家計を維持する上で重要になります。
手取り25万円の場合の家賃目安
手取り25万円の場合、家賃の目安は6万2500円~7万5000円です。少しずつ物件の選択肢が増えてくる金額帯といえます。
都心部でも、立地や広さのバランスを考慮すれば、一人暮らし向けの物件が見つけやすくなってきます。また、郊外や駅から遠い物件であれば、共同生活をする二人暮らしなどでも部屋を見つけられる可能性があります。
また、手取りが25万円あれば、毎月の生活費や将来の貯金についても余裕を持って計画を立てやすくなるでしょう。
手取り30万円の場合の家賃目安
手取り30万円の場合の家賃の目安は7万5000円~9万円です。この収入帯では、選べる物件の選択肢がかなり広がります。
一人暮らしであれば、広さによっては都心部の好立地な物件や駅近物件も視野に入ってくるでしょう。二人暮らしでも都心郊外であれば検討できる範囲になってきます。
ただし、収入に一定の余裕があるからこそ、将来のライフプランも考慮した支出のコントロールが重要になってきます。そのためにも、適切な家賃を設定することが大切です。
手取り35万円以上の場合の家賃目安
手取り35万円以上の場合、家賃の目安は8万7500円~10万5000円、さらに高収入であればそれ以上となります。比較的高収入帯であるため、家賃に余裕を持たせることが可能で、都心部での好立地や広さ、設備にこだわった物件など、希望する条件もある程度満たしやすくなるでしょう。
しかし、この収入帯であっても、家賃以外のライフプラン全体の支出を考慮に入れる必要性は変わりません。将来の住宅購入や子どもの教育費、老後資金、趣味や旅行など、大きな支出を見据えて、家賃にどれくらいの割合を充てるかを慎重に判断することが大切です。
なお、一定以上の高収入になると、無理に「25~30%」に当てはめて考えなくてもよい場合があります。これは、収入が増えるほど「手取りの25~30%」が家計に与える影響が小さくなるためです。
比較的多めの割合を家賃に当てても、趣味や投資、教育など他の優先事項にも資金を振り分ける余裕が生まれます。
住居費が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
家賃を決める上で手取り“以外に”考慮すべき5つの要素
家賃を決定する際には、手取り収入だけでなく、以下の5つの要素も複合的に考慮することが、後悔しない部屋選びにつながります。
ライフスタイルと価値観
今の快適な生活を優先するか、それとも将来を見据えて貯金や資産形成を優先するか、あるいは、家に何を求めるか(広さ、立地、築年数、設備など)などは人それぞれです。
例えば、自宅で過ごす時間が長く、快適な空間を重視するなら、少し家賃が高くても広さや設備を重視するかもしれません。一方で、外食や趣味への支出が多く、貯金目標も明確なら、家賃は抑えめにし、その分を他の支出に充てる方が賢明です。
自身の価値観や日々の過ごし方を深く掘り下げて考えることが、最適な家賃設定への第一歩となります。
同居家族の人数
一人暮らしと複数人暮らしでは、家賃以外の生活費の分担や、必要な部屋数・広さが大きく異なります。
例えば、二人暮らしであれば、光熱費や食費などを折半できるため、一人あたりの負担は軽減される可能性があります。しかし、それに伴い、より広い部屋や間取りが必要となり、家賃総額は高くなる傾向にあります。
家族が増える予定がある場合は、将来的な部屋の広さや間取りの変化も見越して、家賃の上限を検討する必要があるでしょう。
勤務先・通学先との距離や交通費
家賃が安くても、勤務先や通学先から遠く、交通費が高額になったり、通勤・通学時間がかかりすぎたりする場合は、そのメリットが薄れてしまいます。
長時間の通勤は、体力的な負担だけでなく、自由時間の減少にもつながります。毎月の交通費は、家賃と同様に固定費として継続的に発生するため、家賃と交通費を合わせた「トータルの住居コスト」で考えることが重要です。
場合によっては、交通費がかからない職場の近くの物件を選ぶほうが、結果的に経済的かつ快適な生活を送れることもあります。
契約時・入居後にかかる家賃以外の費用
家賃以外にも、賃貸契約時にはさまざまな初期費用がかかります。主なものとしては、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、日割り家賃、鍵交換代、保証会社費用、火災保険料などがあり、これらの合計は家賃の4~6ヶ月分にも上ることがあります。
また、入居後も毎月の家賃とは別に、共益費(管理費)や町内会費などがかかる場合があります。これらの初期費用や月々の家賃以外の費用も全て含めた「総支出」で考え、予算を組む必要があります。
将来のライフプラン
将来的に住宅購入や結婚、出産、子どもの教育費、転職など、予定されている大きな支出がある場合は、それを見越して現在どれくらい貯金に回す必要があるかを考慮し、逆算して家賃の上限を決める考え方も有効です。
例えば、数年後に住宅の頭金を用意したいのであれば、今からまとまった貯金が必要になります。その場合、現在の家賃はできる限り抑え、貯蓄に回す資金を確保することが重要です。
短期的な視点だけでなく、長期的なライフプランの中で家賃を位置づけることで、より堅実な家計運営が可能になります。
失敗しないための家賃の決め方
家賃の目安は「手取り収入の25〜30%」と述べましたが、それでも最適な家賃は価値観などによって人それぞれで異なります。
自分にとっての「ベスト」を見つけるためには、以下のステップを踏むことが重要です。漠然と家賃を決めるのではなく、具体的な数字を把握し、計画的に進めましょう。
まずは手取り収入を正確に把握する
家賃を考える上でもっとも基本となるのが、毎月の手取り収入を正確に把握することです。額面ではなく、税金や社会保険料が差し引かれた「実際に手元に残る金額」を確認しましょう。
給与明細を確認するか、会社の経理担当者に問い合わせるなどして、正確な数字を把握することが出発点です。
ボーナスなど、不定期であったり一定でなかったりする収入は家賃の計算には含めず、あくまでも毎月確実に入ってくる手取り収入で計画を立てることが重要です。
毎月の固定費と変動費を書き出してみる
手取り収入が把握できたら、次に毎月かかる固定費と変動費をすべて書き出してみましょう。
「固定費」とは、毎月一定額がかかる支出のことで、例として、携帯電話料金、インターネット料金、サブスクリプションサービス費用、保険料、ローン返済などがあります。
「変動費」とは、月によって金額が変わる支出のことで、食費、光熱費、水道代、交通費(定期券以外)、日用品費、交際費、娯楽費などが該当します。
これらを詳細に把握することで、家賃以外の支出がどれくらいあるのかが明確になり、家賃に充てられる上限額が見えてきます。
貯金目標額を設定する
将来のライフプランを見据え、毎月どれくらいの金額を貯金に回したいのか、具体的な目標額を設定しましょう。
例えば、「毎月〇〇万円貯金する」「〇〇年後に〇〇万円貯める」といった具体的な目標です。貯金は、緊急時の備えや将来の大きな買い物、投資など、豊かな生活を送る上で不可欠な要素です。
家賃を決める前に貯金目標を設定することで、無理なく貯蓄を継続できる家賃の上限を逆算して導き出すことができます。
適正家賃を求める計算式
これまでの要素を踏まえて、適正家賃を求める計算式は以下のようになります。
【計算式】
手取り − 貯金目標 − (家賃以外の)必要経費 = 家賃にかけられる上限額
ここでいう「必要経費」には、先ほど書き出した家賃以外の固定費や、最低限必要な変動費(食費、光熱費など、生活に不可欠な費用)を含めます。
この計算式を使うことで、収入とライフスタイル、貯金目標に合わせた、現実的で無理のない家賃の上限額を具体的に把握することができます。
例えば、手取り25万円、毎月5万円貯金したい、家賃以外の必要経費が10万円かかる場合、家賃に充てられる上限額は25万円 - 5万円 - 10万円 = 10万円となります。この計算結果を基に、物件探しを進めましょう。
まとめ
家賃は、毎月の生活費の中でも特に大きな割合を占める重要な支出です。後悔しない部屋選びをするためには、自身の「手取り収入」を正しく把握した上で、その「25~30%」という目安を基準にするのがセオリーです。
しかし、この割合もあくまで一般的な目安であり、現在の物価上昇や個人のライフスタイル、価値観、将来のライフプランといった、さまざまな要素も含めて考えることが不可欠です。
最終的に、自分にとっての最適な家賃を決定するには、まず手取り収入を正確に把握すること、そして具体的な貯金目標額を設定することが重要です。
この記事で解説したポイントを参考に、自分に適した家賃を見つけ、快適で無理のない新生活をスタートさせましょう。
≫あなたは足りる?将来の必要額を年収・資産から3分でシミュレーション
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
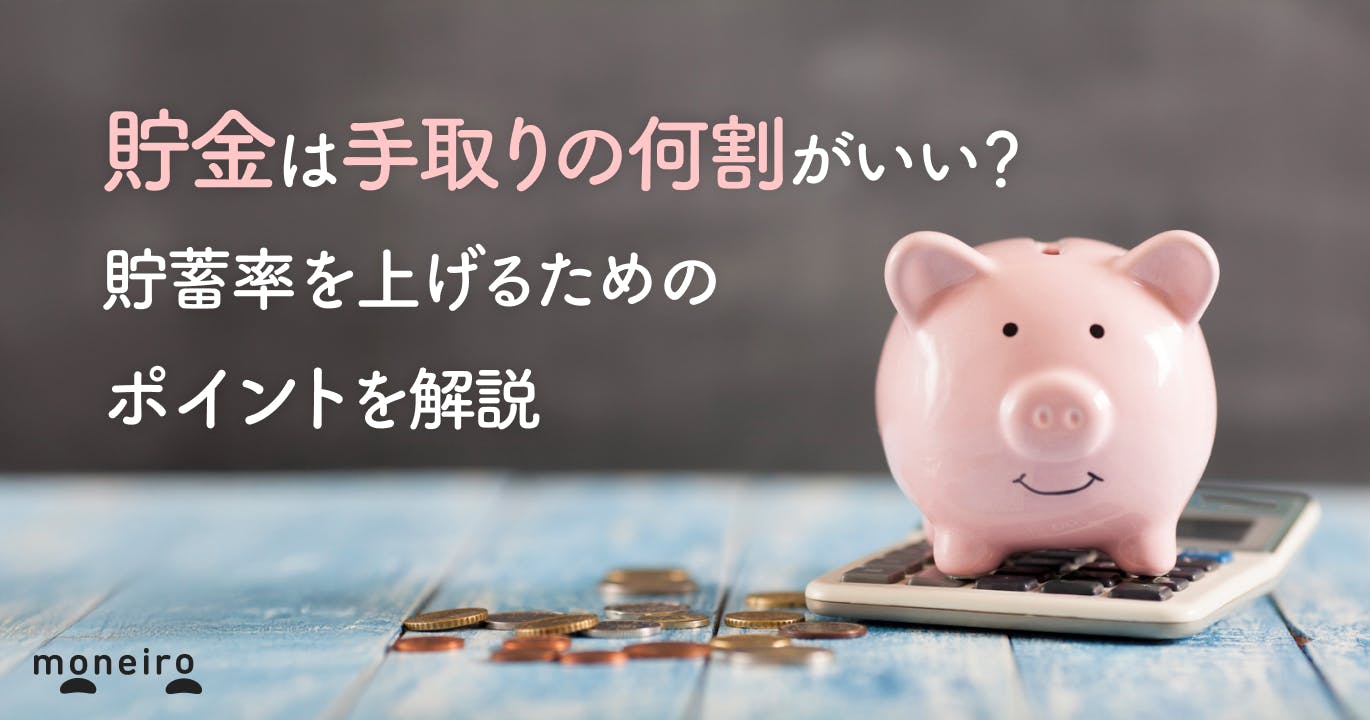

日本で物価高が進むのはなぜ?主な原因やトランプ関税の影響について解説
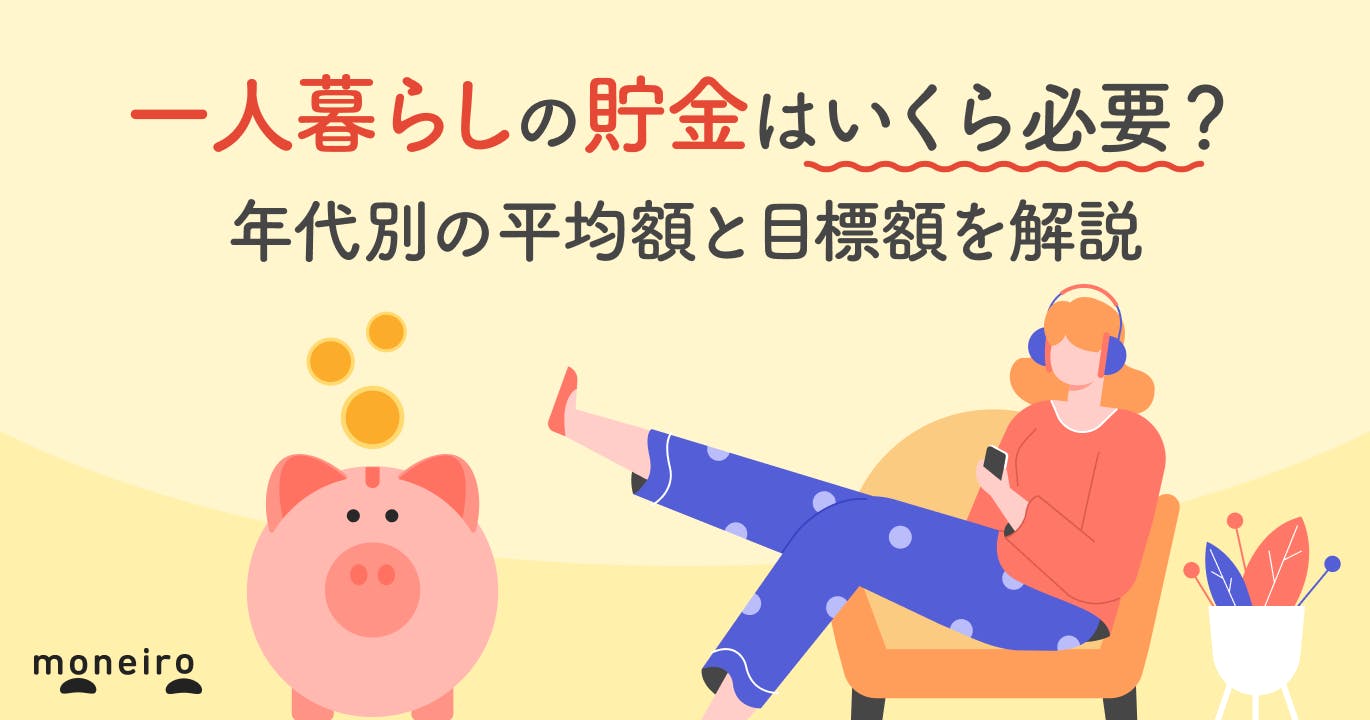
一人暮らしの貯金はいくら必要?年代別の平均額と目標額を解説
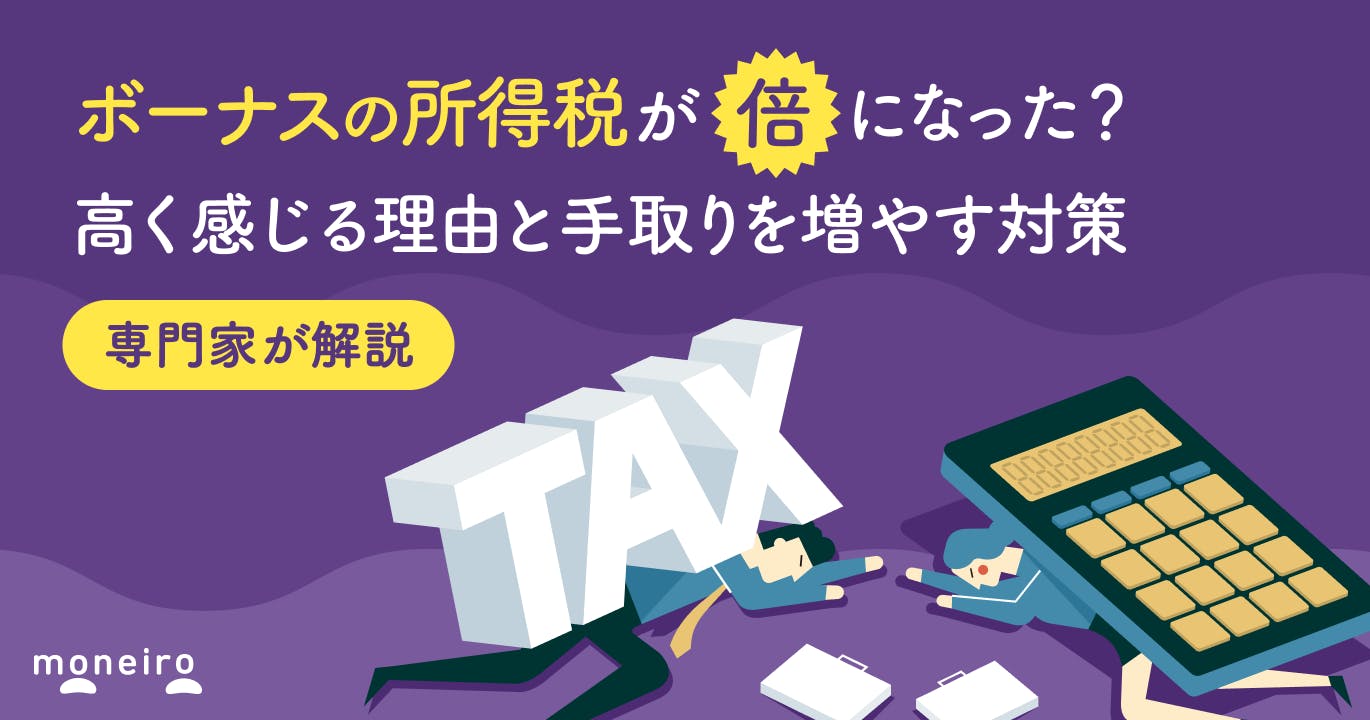
ボーナスの所得税が倍になった?高く感じる理由と手取りを増やす対策を専門家が解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
