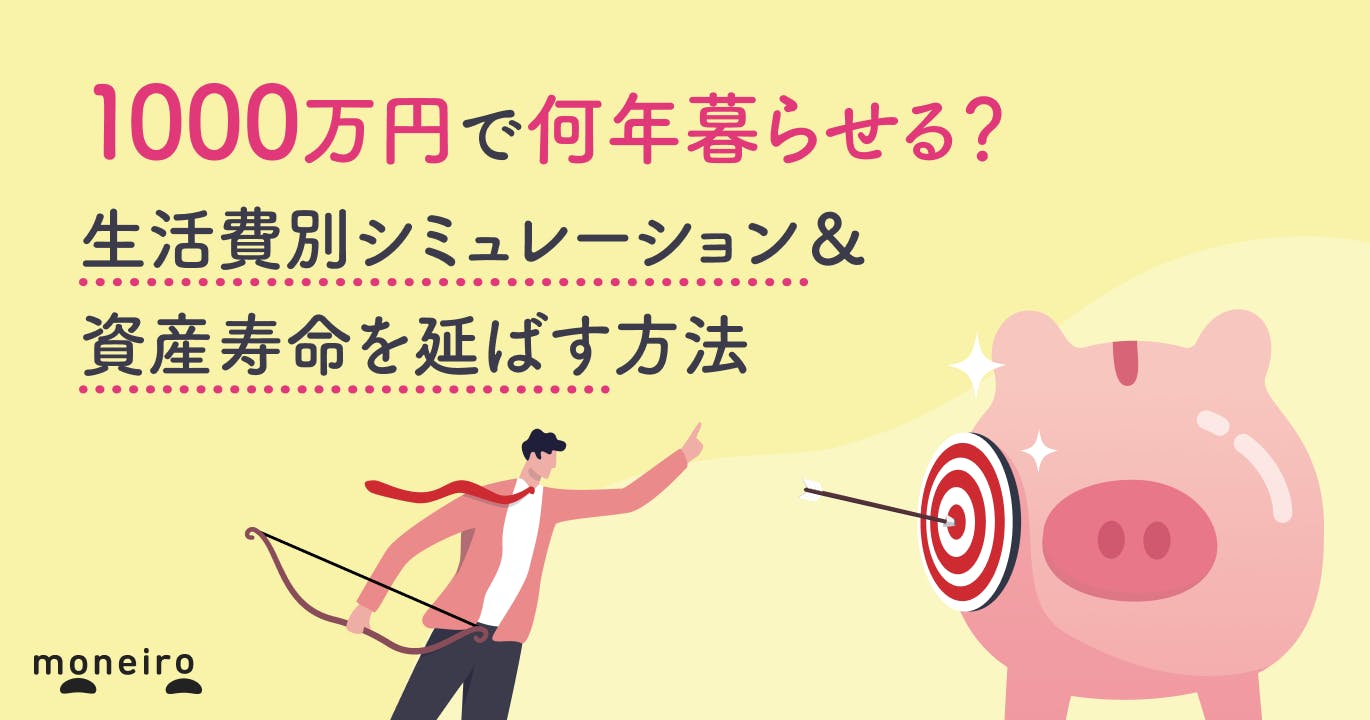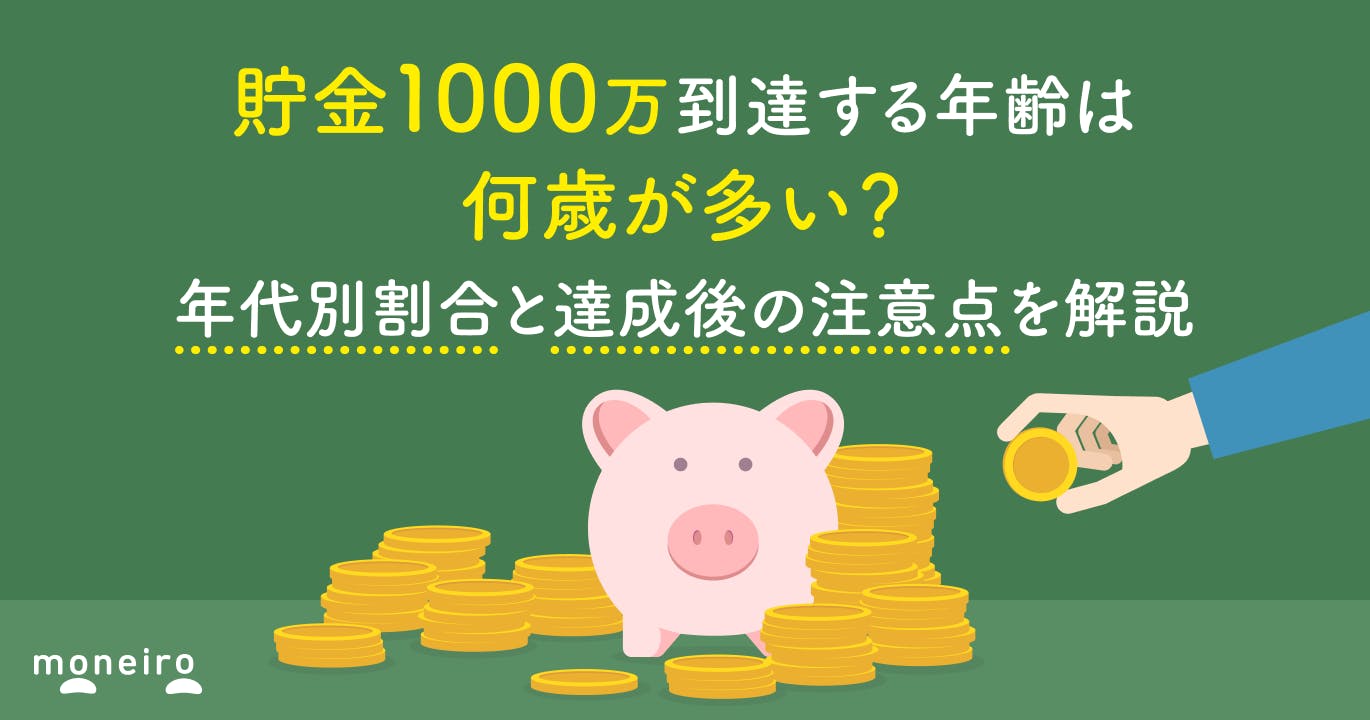
1000万円で何年暮らせる?生活費別シミュレーション&資産寿命を延ばす方法
≫あなたの貯金は十分?老後の必要資金を診断
貯金1000万円の達成は素晴らしい成果です。しかし、この金額で何年暮らせるか、本当に安心して生活できるのかという不安を抱える方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、生活費ごと、世帯構成ごとに、1000万円で生活できる年数を具体的にシミュレーションし、お金を長持ちさせる資産運用や節約術を詳しく解説していきます。
- 貯金1000万円を切り崩す場合と運用する場合で、何年生活できるか
- 年代別・世帯別に見て、貯蓄1000万円以上を保有している人の割合と平均額
- 1000万円という資産を長持ちさせるための具体的な戦略
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
1000万円で何年暮らせるかは「支出」と「運用の有無」で決まる
1000万円という大きな資産を貯めたことで、一時的な生活の安定を得ることができます。ただし、その資産が尽きるまでの期間、すなわち資産寿命は、基本的に「毎月の支出額」と「運用の有無」の2つの要素によって決まります。これらの要素を理解することが、資産を計画的に維持する第一歩です。
「貯金1000万円を切り崩すだけ」の場合、何年暮らせる?
まずは、1000万円の貯金をすべて現金で保有し、運用を一切行わずに毎月の生活費として切り崩した場合のシミュレーション結果を見ていきましょう。
まったく運用せずに取り崩し続けた場合、資産寿命は純粋に「1000万円 ÷ 月の支出」で算出できます。なお、計算上で小数点以下が生じた場合は切り捨てて年数を算出します。また、このシミュレーションでは税金や社会保険料の支払いは考慮していません。
月の支出15万円(単身・節約生活)の場合
月の支出が15万円の場合、1000万円で生活できる期間は1000万円 ÷ 15万円 = 66.6ヶ月となり、資産寿命は約5年6ヶ月です。
この支出水準は、地方在住で家賃の安い物件に住み、食費も自炊を中心にするなど、徹底した節約生活を送っている単身者をイメージした水準です。5年という期間は、次に収入を得るまでの期間としては、決して長いとはいえません。
もし、この5年間に病気や怪我などの突発的な出費が発生した場合、資金はさらに早く尽きてしまうリスクがあります。
月の支出20万円(単身・平均的生活)の場合
月の支出が20万円の場合、1000万円で生活できる期間は1000万円 ÷ 20万円 = 50ヶ月となり、資産寿命は4年2ヶ月です。
この支出は、一般的に都市部に住む単身者の平均に近い水準と考えられます。家賃や光熱費、通信費、娯楽費などが平均的な水準にある場合、わずか4年強で資金が底を尽きてしまう計算になります。
月の支出25万円(2人世帯・節約生活)の場合
月の支出が25万円の場合、1000万円で生活できる期間は1000万円 ÷ 25万円 = 40ヶ月となり、資産寿命は3年4ヶ月です。
この支出水準は、都市部での2人暮らし、または子供1人の世帯で、節約志向で生活する世帯を想定しています。2人以上の世帯では、単身世帯に比べて必要な生活費が増加しやすいため、支出管理が重要になります。3年間という期限で次の収入源を確保するためには、計画的な行動が求められます。
月の支出30万円(2人世帯・平均的生活)の場合
月の支出が30万円の場合、1000万円で生活できる期間は1000万円 ÷ 30万円 = 33.3ヶ月となり、資産寿命は約2年9ヶ月です。
この支出は、2人以上世帯の平均的な生活費に近い水準です。3年足らずで1000万円の貯蓄が尽きてしまうという事実は、貯金を切り崩すだけでは、資産寿命が非常に短いことを示しています。資産を維持するためには、支出を大幅に抑えるか、あるいは後述する運用や収入確保策が必須となります。
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
「1000万円を運用しながら取り崩す」場合、何年暮らせる?
次に、1000万円を年利3%で運用しながら、毎月の生活費を取り崩した場合のシミュレーションを解説します。
年利5%は、全世界の株式に分散投資するインデックスファンドなどで期待されるリターンの一般的な目安です。運用収益が得られることで、資産寿命がどれほど延びるのかを確認しましょう。
試算参照:資産運用シミュレーション|みんかぶ
月の支出15万円(単身・節約生活)の場合
運用をせずに取り崩す場合の資産寿命は約5年6ヶ月でした。もし1000万円を年利5%で運用しながら取り崩すと、資産寿命は約6年6ヶ月に延びます。
このケースでは、資産に対する5%の運用益が、資産の減少を緩やかにする効果があるため、資産寿命は1年程度延長されます。節約生活を送りつつ運用を取り入れることで、ただ取り崩すよりも長期的な安心感を得られる可能性があります。
月の支出20万円(単身・平均的生活)の場合
運用をせずに取り崩す場合の資産寿命は4年2ヶ月でした。年利5%で運用しながら取り崩す場合、資産寿命は約4年8ヶ月となります。運用を取り入れることで、資金が尽きるまでの期間が6ヶ月程度延びることになります。
月の支出25万円(2人世帯・節約生活)の場合
運用をせずに取り崩す場合の資産寿命は3年4ヶ月でした。年利5%で運用しながら取り崩す場合、資産寿命は約3年8ヶ月となり、約4ヶ月延びることになります。
支出額が大きくなるほど、資産の減少が早まるため、運用による資産寿命延長効果も相対的に小さくなります。それでも、特に2人世帯の場合は、突発的な支出も増えやすくなるため、少しでも資産寿命を延ばすための運用は有効な手段です。
月の支出30万円(2人世帯・平均的生活)の場合
運用をせずに取り崩す場合の資産寿命は約2年9ヶ月でした。もし年利5%で運用しながら取り崩す場合、資産寿命は約3年です。つまり約3ヶ月資産を長く維持できる計算となります。
資産1000万円に対して、月の支出が30万円となってくると、運用による資産寿命延長効果はだいぶ小さくなってきます。しかしながら、運用を取り入れることが、資産寿命を延ばすための必須戦略であることに変わりはありません。支出が大きい世帯ほど、運用による効率化と並行して、支出の徹底的な見直しが必要になるでしょう。
ここまでのシミュレーションを見ても分かるように、「資産1000万円」は、それだけで生活していくには決して十分な金額とはいえません。
時間的な余裕があるのであれば、取り崩し額をできるだけ小さくしつつ、運用も行うことによってさらに増やしていくことを考えたほうがよいでしょう。
そもそも貯金1000万円以上はどれくらいいる?年代・世帯別の貯蓄割合
1000万円という貯蓄額が、日本国内でどれくらいの水準にあるのかを、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」のデータを参考に見ていきましょう。
貯蓄1000万円以上の人の割合(単身世帯)
単身世帯において、金融資産保有額が1000万円以上である人の割合は、全体で21.5%です(1000万円以上の全階層の合計)。単身世帯のおよそ5人に1人が1000万円以上の金融資産を保有しています。
これを世帯主の年齢別に見ると、以下の通り、特に年齢が上がるほど割合が高くなっています。特に60歳代以上では、3分の1を超える単身者が1000万円以上の金融資産を保有していることが分かります。
なお、単身世帯全体の金融資産の平均値は989万円ですが、中央値は100万円です。この差は、資産保有が一部の層に偏っていることを示しています。
貯蓄1000万円以上の人の割合(2人以上世帯)
2人以上世帯において、金融資産保有額が1000万円以上である世帯の割合は、全体で31.9%です。約3世帯に1世帯が1000万円以上の金融資産を保有している計算になります。
世帯主の年齢別に見ると、以下の通り、単身世帯と同様に高齢になるほど割合が増加します。特に60代、70代では、2人以上世帯の半数近くが1000万円以上の貯蓄を保有していることが分かります。
2人以上世帯全体の金融資産の平均値は1374万円、中央値は350万円であり、1000万円は平均値よりは低いものの、中央値と比較すれば高い水準にあるといえます。
1000万円の資産寿命を延ばす4つの戦略
1000万円の資産寿命を延ばし、より長く安定した生活を送るためには、シミュレーションで明らかになった課題を克服するための、以下の4つの戦略を組み合わせて実行することが不可欠です。
1. 生活防衛資金を現金で確保する
運用を取り入れることは重要ですが、1000万円をすべて投資に回すのはリスクがあります。不測の事態(病気、失業、災害など)に備えるため、生活防衛資金を現金や流動性の高い預金で確保しておく必要があります。
生活防衛資金の目安は、生活費の6ヶ月分程度が理想です。万が一の時のための生活防衛資金を除いた資金を運用に回すことで、安全性と成長性のバランスを図ることが可能になります。
2. 支出(特に固定費)を徹底的に見直す
資産寿命を延ばすもっとも直接的な方法の1つに、毎月の支出を減らすことが挙げられます。特に、一度見直せば継続的に効果が得られる固定費を徹底的に削減することが重要です。
固定費の例としては、住宅費(家賃や住宅ローン)、保険料、通信費、サブスクリプションサービスなどが挙げられます。月の支出が1万円減るだけで、1年で12万円、10年で120万円の貯蓄が温存されることになります。支出額を減らすことは、確実な資産寿命延長策となります。
3. NISAをフル活用する
資産寿命を延ばすには、運用によるリターンを取り込むことが不可欠です。そのためのもっとも有効な手段がNISA(少額投資非課税制度)のフル活用です。NISAの最大のメリットは、運用によって得られた利益が非課税になる点です。
老後の生活資金や、当面使う予定のない1000万円のうち生活防衛資金を除いた分を、例えば、全世界の株式市場の値動きに連動するインデックスファンドなど、長期的な成長が見込める金融商品に配分することで、インフレによる現金の目減りを防ぎつつ、資産を効率的に増やすことができます。
金融機関によっては月々100円や1000円といった少額から始められるため、まずは少額から試してみるのもよいでしょう。 運用元本が大きいうちにNISAで利益を再投資し続ければ、長期的に資産を取り崩す際の支えとなります。
4. 一定額を働いて稼ぐ
1000万円をすべて切り崩す生活を避けるためには、一定額の収入を確保し続けることが、もっとも強力な戦略となります。これは、いわゆるサイドFIREやバリスタFIREといった、働き方と資産運用を両立させる考え方です。
完全にリタイアするのではなく、生活費の一部、たとえば月に10万円だけでも働くことで、1000万円の取り崩しペースを大幅に遅らせることができます。
労働収入は元本を減らさずに生活費を賄うため、これにより資産寿命は飛躍的に延び、運用資産をより長期的に複利で成長させる時間的猶予も得られるでしょう。
1000万円の貯蓄に関するQ&A
1000万円の貯蓄に関して、よくある質問とその回答をまとめます。
Q. 貯金1000万円でセミリタイア(FIRE)は可能?
貯金1000万円だけで本格的なFIRE(完全な経済的自立と早期リタイア)を達成することは、現実的には非常に困難です。一般的なFIREの目安となる「4%ルール」を適用すると、1000万円の運用で得られる年間収入は40万円程度であり、平均的な生活費にはまったく足りません。
これを月の収入に均すと3.3万円で、サイドFIREのための資金としても物足りない金額です。もしセミリタイアを目指すのであれば、この1000万円をさらに運用することで資産を増やすことも検討してみましょう。
Q. 60代(老後)で貯金1000万円は少ない?
「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、60代の単身世帯の金融資産の平均は1679万円、2人以上世帯の平均は2033万円です。この平均値と比較すると、1000万円は下回ります。しかし、単身世帯の中央値は350万円、2人以上世帯の中央値は650万円であり、中央値と比較すると高い水準にあるといえます。
老後の生活の安定度は、公的年金の受給額や持ち家の有無、健康状態によって大きく変わります。公的年金収入が安定しており、住宅費がかからない状況であれば、1000万円を運用しながら取り崩すことで、十分対応できる可能性があります。
Q. 1000万円を超えたら、預金保険制度(ペイオフ)は大丈夫?
日本の預金保険制度(ペイオフ)は、金融機関が破綻した場合に、預金者1人あたり、一つの金融機関につき、元本1000万円とその利息を保護する制度です。
そのため、1000万円を超える預金は、超過分が保護対象外となる可能性があります。ただし、安全性を高めるためには、複数の金融機関に資金を分散して預金することや、ペイオフ対象外の預金(外貨預金など)ではないかを確認することが重要です。なお、投資信託などの運用資産は、証券会社が破綻しても顧客資産は保全される仕組みになっています。
まとめ
貯金1000万円で何年暮らせるかのシミュレーション結果は、毎月の支出額によって2年から5年程度と、運用を取り入れない場合は非常に短い期間で尽きてしまうことを示しました。しかし、この資産寿命は「支出の見直し」と「運用の有無」によって大きく変えることができます。
年利3%程度の運用を取り入れることで、資産寿命を数ヶ月から1年以上延ばす効果が期待できます。長期的な安心を得るためには、固定費の削減やNISAを活用した運用、そして可能な範囲での労働収入の確保といった戦略を組み合わせて実行することが不可欠です。
1000万円という資産を最大限に活用し、賢く長く維持するために、これらの戦略を総合的に実行していくとよいでしょう。
≫老後資金は足りる?あなたの不足金額を3分で診断
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
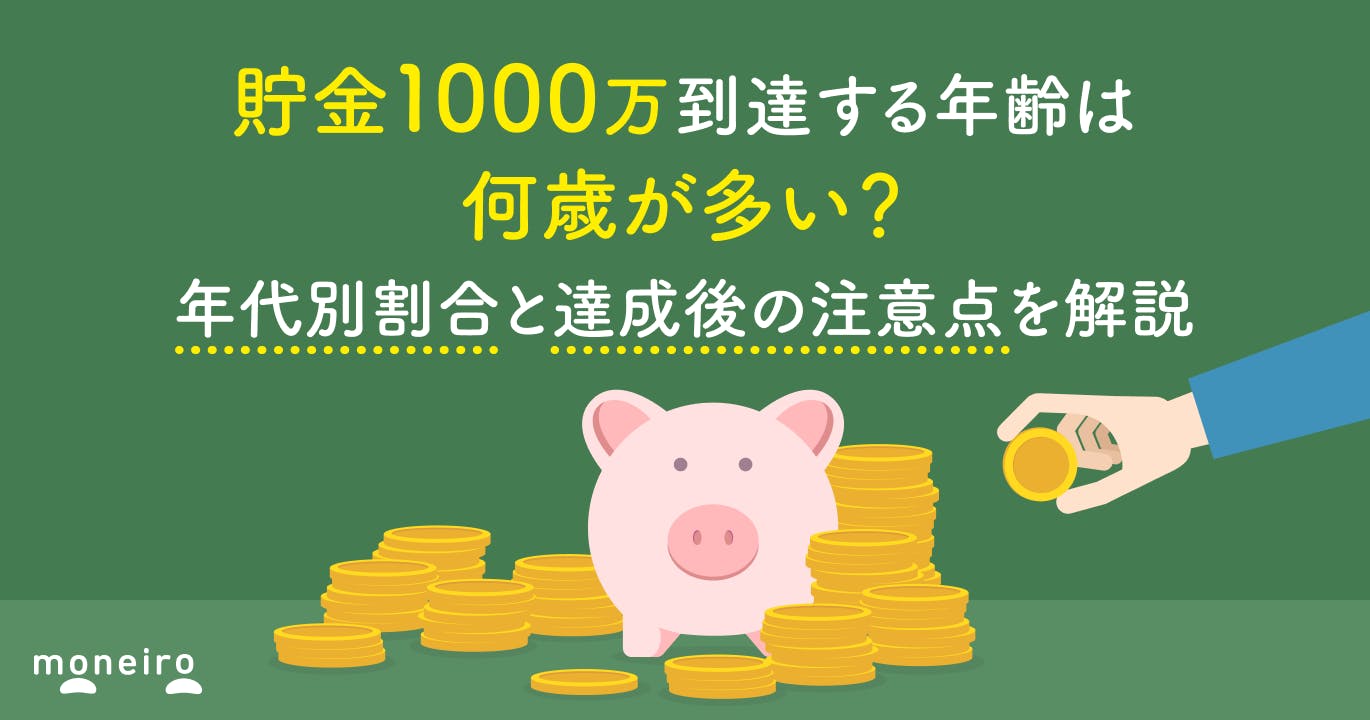

貯金1000万円はすごい?年代別の割合&達成方法・達成後の注意点を解説

正直みんな貯金はどのくらいある?年代別・年収別に平均額・中央値を解説
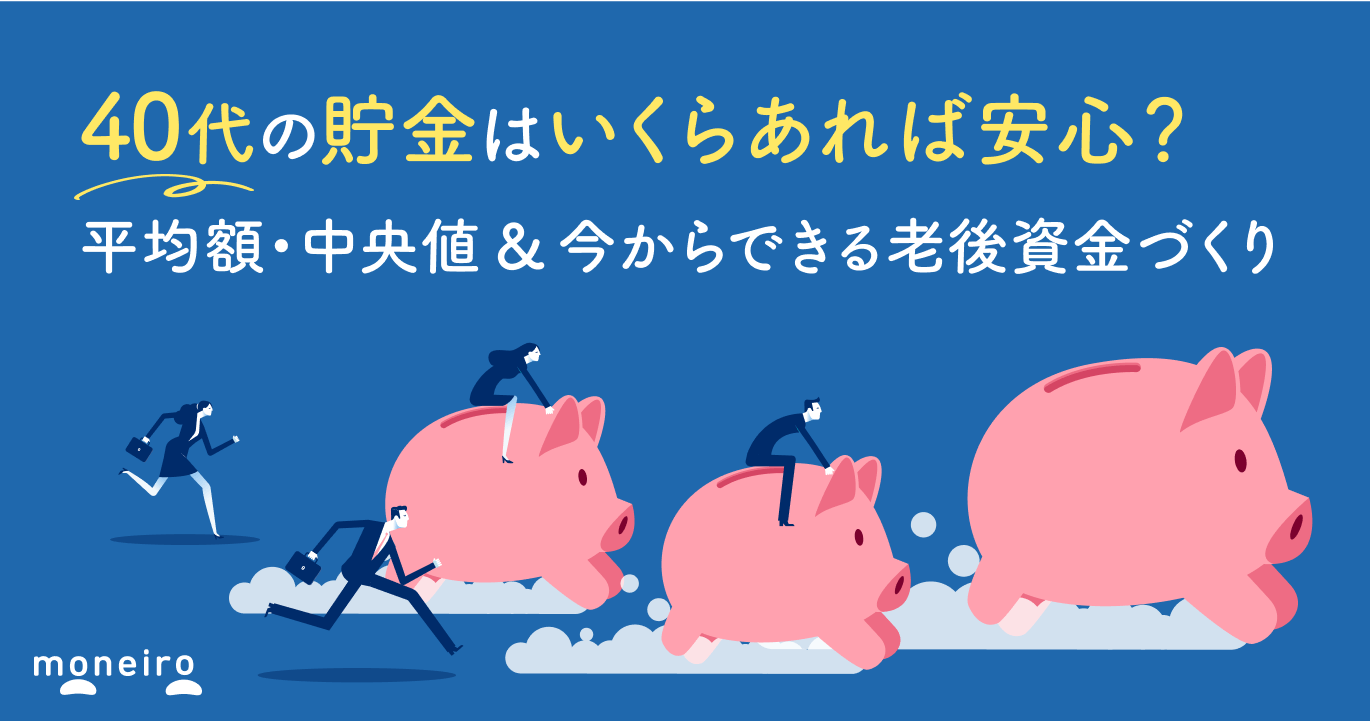
40代の貯金いくらあれば安心?平均額・中央値&今からできる老後資金づくり
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。