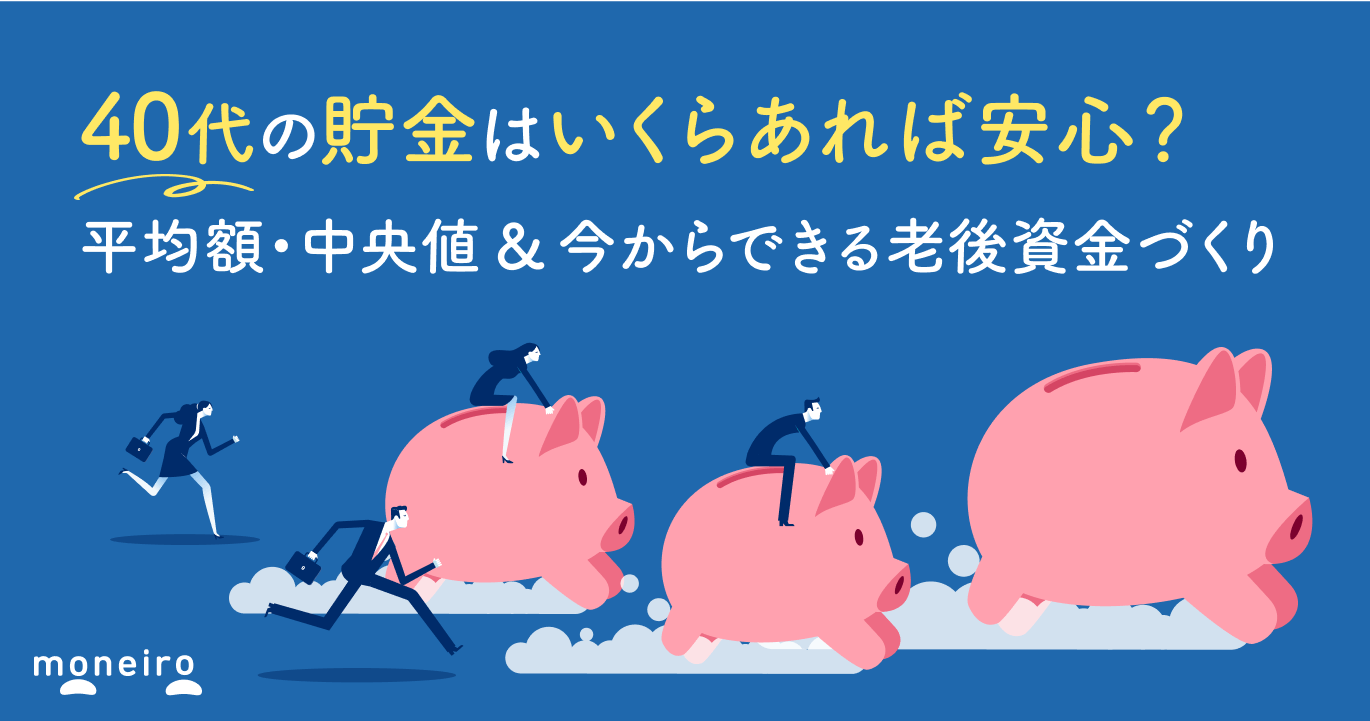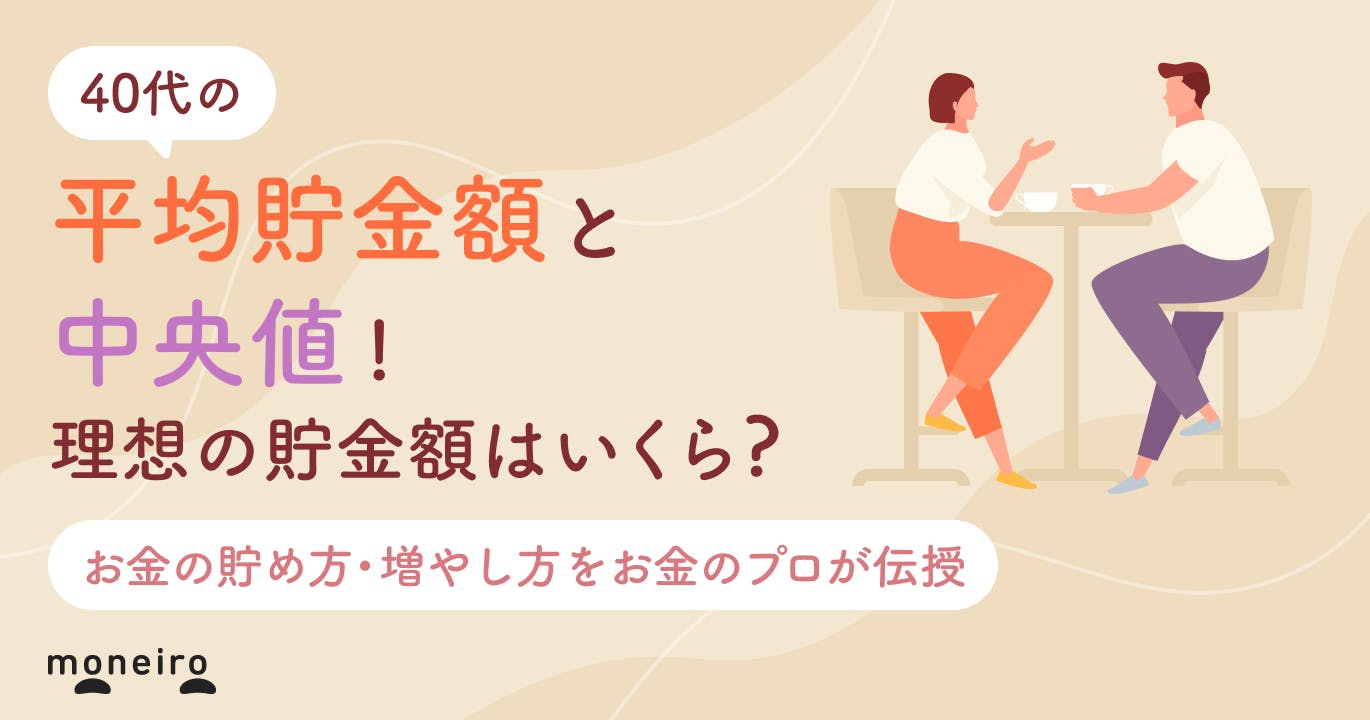40代の貯金いくらあれば安心?平均額・中央値&今からできる老後資金づくり
【無料】あなたの不足額はいくら?老後の必要資金を年収・資産から診断
40代になると、老後資金や子どもの教育費、住宅ローンなど、お金の心配が増えてきます。「貯金はいくらあれば安心できる?」と将来への漠然とした不安を感じる方も多いかもしれません。一体どれくらいの貯金があれば安心できるのか、具体的な目安を知っておくと、目標も立てやすくなるでしょう。
そこでこの記事では、40代の平均貯金額や中央値を世帯別に紹介するとともに、人生の三大資金に必要な目標額の考え方や、効率的な資産形成術までを解説します。もう遅いと諦めずに、今から計画的に将来資金づくりを進めていきましょう。
- 40代の単身世帯と2人以上世帯、それぞれの平均貯金額と中央値
- 老後資金や教育資金など、人生の主要な支出に備えるための具体的な考え方
- NISAやiDeCoなどを活用した、40代から始める効率的な資産形成術
貯金額が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶40代からの老後資金作り:まだまだ間に合う。効率的な資産形成術
40代の平均貯金額はいくら?
40代の貯蓄状況を知る上で、多くの方が気になるのが「平均貯金額」でしょう。しかし、平均値は一部の高額保有者に引き上げられやすい傾向があるため、より実態に近い「中央値」も併せて確認することが重要です。
ここでは、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」のデータをもとに、40代の世帯主が保有する金融資産の平均額と中央値を、単身世帯と2人以上世帯に分けて解説します。
40代(単身世帯)の平均貯金額は?
40代・単身世帯では、金融資産あり世帯が66.7%、金融資産なし世帯が33.3%となっています。そして、金融資産ありと回答した世帯の内訳は以下のとおりです。
40代の単身世帯(金融資産あり世帯)における金融資産保有額は、平均で1342万円、中央値は355万円となっています。
金融資産あり世帯でもっとも多いのが23.1%を占める100万円未満です。一方で次に多いのが13%を占める3000万円以上の世帯です。
40代はキャリアや給与面で、個人間で大きな違いが出てくる年代であり、それが貯金額にも表れていると考えられます。
40代(2人以上世帯)の平均貯金額は?
40代の2人以上世帯では、金融資産あり世帯は74.3%、なし世帯は25.7%となっています。金融資産あり世帯の金融資産保有額の内訳は以下のようになっています。
40代の2人以上世帯(金融資産あり世帯)の金融資産保有額は、平均で1293万円、中央値は520万円です。
単身世帯と比較すると、特に200万円以下の割合が下がるとともに、3000万円以上の割合も下がっており、逆に中間層が増加しています。
これには、子どもの教育費や住宅購入など大きな出費に向けた貯蓄が進む一方で、資産を築いた人はこうした費用が出ていくことで資産の減少が表れていることが考えられます。
40代の「安心」を左右する人生の3大資金+αはいくら必要?
40代は、教育資金、住宅資金、老後資金という「人生の3大資金」の準備が本格化する時期です。これらの費用に加え、介護費用や医療費といった予期せぬ出費への備えも重要になります。ここでは、それぞれの資金について、必要な考え方と目安について解説します。
教育資金の「最大の山」へ
40代の子育て世帯にとって、教育資金は大きな関心事であり、人生におけるもっとも大きな出費の1つになり得るものでもあります。特に大学進学時には、入学金や授業料、その他諸経費など、多額の費用が発生します。
大学4年間の学費はおおよそ、国公立大学の場合で200~300万円、私立大学で400~500万円、私立大学医科歯科系(6年)で3000~4000万円程度で、かなり大きな金額になります。
子どもの大学進学が近づいてきた時点でこれだけのお金があれば安心できますが、特に医学部・歯学部への進学を検討している場合は貯蓄だけでまかなうのは困難になります。
そこで、教育資金の準備として学資保険を利用して計画的に貯蓄を進めたり、それでも不足する場合には、教育ローンや奨学金なども活用したりして学費に充てていくことになります。
奨学金には返済不要な給付型と卒業後に返済が必要な貸与型があり、貸与型にはさらに無利子の「第一種」と有利子の「第二種」があります。
また、金融機関が提供する教育ローンも返済が必要です。いずれを利用する場合でも、家計を圧迫しないよう、家庭の状況に合わせて慎重に選択することが重要です。
貯金額が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶40代からの老後資金作り:まだまだ間に合う。効率的な資産形成術
老後資金の準備が本格化
老後資金の準備は、40代から本格的に取り組むべきテーマです。老後の生活設計を具体的にイメージし、必要な資金を算出することから始めましょう。具体的なステップとしては、以下の3段階が考えられます。
年金見込額の確認
まずは、ご自身が将来受け取れる公的年金の目安を把握することが重要です。ねんきんネットなどのサービスを利用して、現状の加入状況に応じた年金見込額を確認しましょう。
老後の支出を予測
次に、リタイア後の生活でどのような支出が必要になるかを具体的に見積もります。住居費、食費、医療費、趣味娯楽費、旅行費など、項目ごとに支出を考えることで、より現実的な老後生活に必要な資金が見えてきます。
不足額の算出
年金見込額と老後の予測支出から、不足する金額を算出します。この不足額が、現役時代に準備すべき老後資金の目標額となります。この目標額を明確にすることで、具体的な資産形成計画を立てやすくなります。
親の介護費用と自分の医療費
人生には、親の介護費用や自身の医療費といった想定外の出費も発生することがあります。これらの費用の備えについても、40代から考えておくべき重要な要素といえます。
生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、高齢で要介護状態になった家族・親族の介護にかかった平均月額介護費用は6.7万円、介護期間は平均で48.7ヶ月となっており、単純計算で1人あたり平均で約326.3万円がかかる計算です。
あくまで平均値であるため、個々人の状態によっても変わってきますが、1つの目安として覚えておくとよいでしょう。
また、自身の病気やケガに備える医療費も忘れてはなりません。日本の公的医療保険制度は充実していますが、差額ベッド代や先進医療費、入院中の食費など、公的医療保険だけではカバーしきれない部分もあります。
民間の医療保険に加入している場合は保障内容を見直したり、貯蓄で備えるなど、自身の状況に合わせた対策を検討しておきましょう。
40代のライフイベントにどう対応する?
40代は、教育資金がピークを迎えたり、住宅ローンの返済が本格化したりと、多くのライフイベントが重なる時期です。これらの大きな支出と貯蓄・資産形成を両立させるための戦略を見ていきましょう。
子育て世帯の「やりくり」戦略
子育て費用は家計に大きな影響を与えます。特に、子どもが成長して進学するにつれて教育費は増加する傾向にあり、大学進学に向けては高額な出費が予想されます。そのため、計画的な貯蓄と、必要に応じた外部資金の活用が重要になります。
学資保険
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための貯蓄型保険です。毎月一定額を積み立てることで、進学時などに祝金や満期保険金を受け取ることができます。
親に万が一のことがあった場合は保険料の払い込みが免除され、それでも教育資金は確保される保障機能が付帯している点が特徴です。
低金利時代においては貯蓄性が限定的となる場合もありますが、強制的に貯蓄できる点や、保障が付いている点に魅力を感じる方にとっては有効な選択肢となるでしょう。
奨学金・教育ローンも視野に
もし教育資金が不足する場合には、奨学金や教育ローンを視野に入れることも有効な選択肢です。奨学金には、返済不要な給付型と、卒業後に返済が必要な貸与型があります。
特に給付型は、家庭の経済状況や本人の学力など、厳しい条件があるものの、返済の負担がないため条件クリアの可能性がある場合は積極的に検討すべきでしょう。
一方の教育ローンは、入学金や授業料などまとまった資金を借り入れることができるため、教育資金のピーク時に活用できます。金利や返済期間、利用条件などをよく比較検討し、将来的な返済計画も考慮に入れながら慎重に選択しましょう。
住宅ローンの返済と貯金の両立
住宅ローンを抱える40代の方にとって、毎月の返済と並行して貯金を増やしていくことは大きな課題です。無理のない返済計画を立てつつ、日々の家計管理で無駄をなくし、貯蓄に回せる資金を捻出することが重要です。
例えば、毎月の固定費(通信費、保険料、サブスクリプションサービスなど)を見直したり、変動費(食費、娯楽費など)の節約を心がけたりすることで、着実に貯蓄を増やしていくことが可能です。
今からでも間に合う、40代からの資産形成術
40代からでも、効果的な資産形成を始めることで将来に備えることができます。特に重要なのは「時間」を味方につけることです。非課税制度などを最大限に活用し、着実に資産を増やしていきましょう。
NISAを最大限に活用
NISAは、投資で得た運用益に通常かかる20.315%の税金が非課税になる税制優遇制度です。2024年から新しいNISAが始まり非課税投資枠の大幅な拡大と、非課税期間が恒久化されたことで非常に強力な資産形成手段となりました。
40代からNISAを始める場合は、退職までの期間を考慮し、長期的な視点に立って積立投資を行うことが大切です。長期目線での運用を行うことで時間を味方につけ、価格変動リスクも分散しながら複利効果を享受することができます。
iDeCoで節税&資産運用
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税・住民税の節税効果を享受しながら資産運用ができる私的年金制度です。また、運用益も非課税で再投資されるため、複利効果を最大限に生かせるのも大きなメリットです。
40代から始めても、退職までの期間があれば十分な節税メリットと運用成果が期待できます。原則60歳まで引き出しができないという制約がありますが、「だからこそ老後資金作りに最適」と考えることもできます。
NISAと併用することで税制優遇の恩恵を最大限に活用しつつ、より効率的に老後資金を準備することが可能です。
住宅ローンの繰上げ返済 vs 資産運用
住宅ローンの繰上げ返済と資産運用、どちらを優先すべきか悩む方も多いでしょう。この判断のポイントは、「住宅ローンの金利」と「期待できる資産運用利回り」を比較することです。
一般的に、住宅ローンの金利よりも資産運用で期待できる利回りの方が高い場合、資産運用を優先するほうが効率的だといえます。特に現在の低金利時代においては、資産運用に資金を回すことで、より大きなリターンを得られる可能性が高まります。
例えば、年利1%の住宅ローンを繰上げ返済するよりも、年利3%で運用できるのであれば、資産運用を優先した方が長期的に資産を増やせる可能性があります。
ただし、ローン金利が高い場合や、借入残高が多い場合、または精神的な安心感を重視する場合は、繰上げ返済も有効な選択肢です。自身の状況やリスク許容度に合わせて最適なバランスを見つけることが重要です。
退職金や企業型DCの確認
勤務先に退職金制度や企業型DC(企業型確定拠出年金)がある場合は、その内容をしっかり確認することが大切です。
まずは、会社の退職金規程を確認し、いくら受け取れるのか、どのような条件があるのかを把握しましょう。将来の退職金が、老後資金計画にどのように組み込まれるかを具体的に検討できます。
企業型DCに加入している場合は、積極的に活用しましょう。マッチング拠出(会社拠出金に加えて、自分で掛金を上乗せできる制度)の利用を検討すれば、拠出額を増やし、より効率的に資産形成ができます。
運用商品の見直し(スイッチング)を定期的に行うことも重要です。自身の年齢やリスク許容度に合わせて、運用商品を最適なものに調整し、資産を最大限に成長させましょう。
まとめ
40代は、教育資金、住宅資金、老後資金といった人生の三大資金への準備が本格化する重要な年代です。さらに、予測の難しい介護や医療費への備えも含め、早めの計画と実行が将来の「安心」を形作る鍵となります。
具体的には、NISAやiDeCoといった税制優遇制度も活用しながら、長期・積立・分散投資で複利効果を味方につけることで、効率的に資産を増やしていくことができるでしょう。
場合によっては住宅ローンの繰上げ返済も検討するなど、自身の状況や今後のライフプランに合わせた最適な資産形成戦略を立て、将来にわたる経済的なゆとりを着実に築いていきましょう。
貯金額が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶40代からの老後資金作り:まだまだ間に合う。効率的な資産形成術
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。