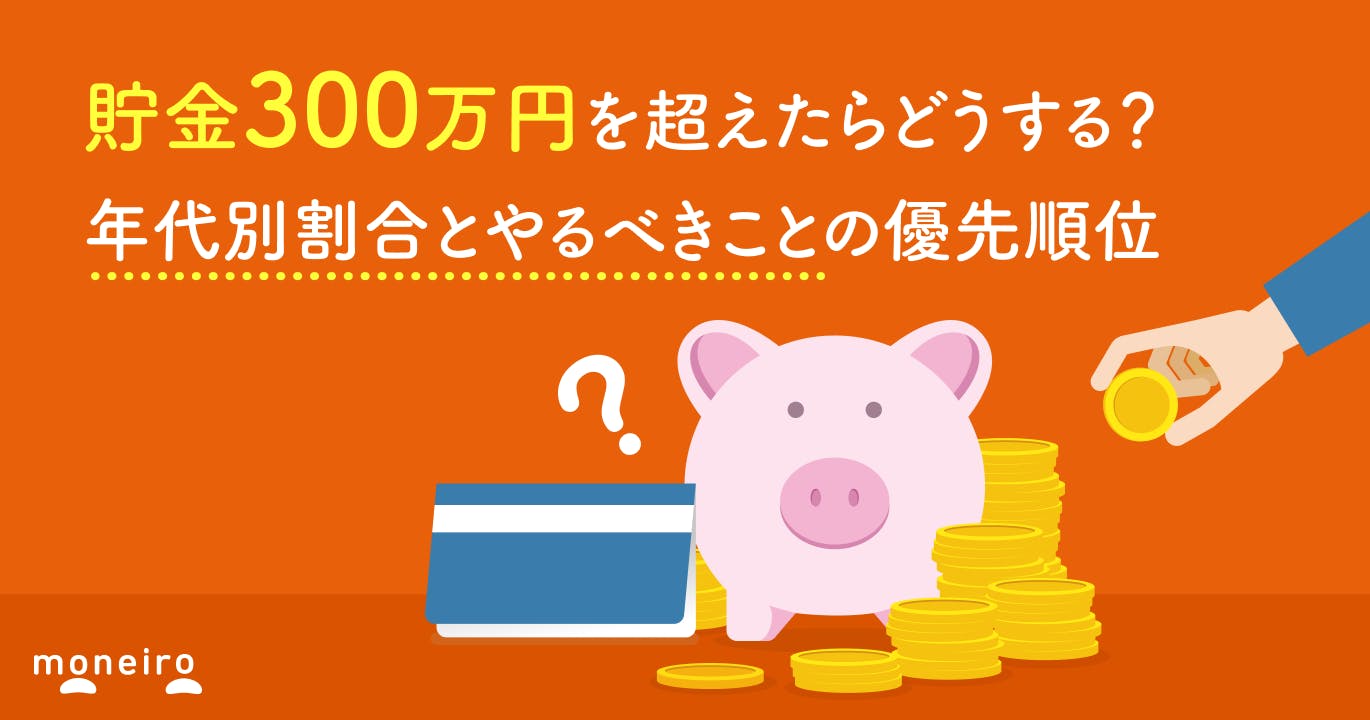
貯金1000万到達する年齢は何歳が多い?年代別割合と達成後の注意点を解説
≫今の貯金額で足りる?将来の不足額を診断
貯金1000万円という目標は、多くの方にとって経済的な安心感を得るための大きなマイルストーンです。実際に貯金1000万円に到達する年齢はどれくらいが多いのか、保有している人がどのくらいいるのかは、多くの方が気にされる点でしょう。
本記事では、金融広報中央委員会の最新データに基づき、貯金1000万円を達成した人の年代別・年収別の割合を解説します。さらに、最短で達成するための具体的なステップや、達成後に陥りやすい注意点まで、詳細かつ分かりやすく解説します。
- 年代別・年収別の金融資産1000万円以上の保有割合の実態
- 貯金1000万円を最短で達成するための戦略的ステップ
- 目標達成後に陥りやすい浪費や投資リスク
将来に向けた貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
貯金1000万円に到達した人が多い年代は?
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」のデータによると、金融資産保有額が1000万円以上の世帯の割合(金融資産非保有世帯を含む)は、単身世帯では上位20%強(21.5%)、2人以上世帯では上位30%強(31.9%)です。
なお、ここでの「金融資産保有額」には、現金の他、株式や投資信託、債券、生命保険などの金融商品も含まれます。
単身世帯(一人暮らし)の年代別割合
単身世帯において、年代別の金融資産1000万円以上の保有割合を見ると、特に若年層では金融資産を持たない割合が高い傾向にあります。
20代では、1000万円以上保有割合はわずか3.2%にとどまります。しかし、年代が上がるにつれて割合は増加し、40代以降は1000万円以上保有層が2割を超え、資産形成が進んでいることが分かります。
各年代の1000万円以上保有割合は以下の通りです。
平均値と中央値には大きな乖離が見られ、一部の高資産層が平均値を押し上げている実態が分かります。特に50代では、平均値が1087万円であるのに対し中央値は30万円と極端に低く、資産形成が二極化している厳しい現実がうかがえます。
2人以上世帯(夫婦・家族)の年代別割合
2人以上世帯は全体的に単身世帯よりも金融資産非保有の割合が低く、資産形成が進んでいることが見て取れます。
2人以上世帯では、30代ですでに1000万円以上を保有する世帯が18.4%おり、40代(24.0%)、50代(28.4%)と着実に割合が増加します。特に60代・70代では、1000万円以上の保有割合が4割を超えています。
各年代の1000万円以上保有割合は以下の通りです。
貯金1000万円以上の「ボリュームゾーン」は何歳?
1000万円以上の金融資産を保有している割合は、年齢が上がるほど高まることが分かります。
単身世帯、2人以上世帯のいずれにおいても、60代と70代が保有割合のもっとも高いボリュームゾーンです。特に2人以上世帯では、60代の42.7%、70代の44.7%が1000万円以上を保有しており、退職や子育ての完了といったライフイベントを経て、本格的な資産形成が完了している層が多いことが分かります。
また、いずれの世帯構成でも、50代から60代にかけて大きく割合が増加しており、退職金によって大幅に資産を増やしたことが要因として考えられます。
≫今の貯金額で足りる?将来の不足額を診断
【FP監修】貯金1000万円を最短で達成する5つのコツ
貯金1000万円を達成するためには、漫然と貯蓄するのではなく、計画的かつ戦略的に行動する必要があります。貯蓄を加速させるための5つのステップを紹介します。
1. 収支の現状把握と「先取り貯蓄」の徹底
貯蓄の第一歩は、現状の家計を正確に把握することです。家計簿アプリやクレジットカードの利用明細などを活用し、毎月の収入と支出を「見える化」しましょう。固定費と変動費のバランスを明確にすることで、無意識の「ムダ遣い」を発見し、支出最適化の土台ができます。
支出の見える化ができたら、「残ったお金を貯める」のではなく、「先に貯蓄分を取り分ける」仕組み、すなわち「先取り貯蓄」を実践しましょう。
給与が振り込まれた直後に貯蓄専用口座や投資口座へ自動的に資金を移動させることで、強制的に資産形成を進められます。
積立日を給与日直後に設定できる積立定期預金なども有効な手段です。
2. 固定費(住居費・保険・通信費)の抜本的見直し
支出を見える化したら、次に「固定費」の見直しに着手すべきです。固定費は、一度削減すれば長期的に効果が続くため、貯蓄の入金力(貯める力)を大きく高めるもっとも有効な手段です。
具体的には、以下のような項目を見直しましょう。
- 住居費:賃貸であれば家賃交渉や引っ越し、住宅ローンであれば借り換えを検討する
- 通信費:格安SIMや契約プランの見直しを検討する
- 保険料:不要な特約がないか確認し、保障内容を本当に必要なものに絞り込む
- サブスクリプション:利用頻度の低い動画配信サービスなどを解約する
3. 目的別(生活防衛・中期・長期)に口座を分ける
先取り貯蓄を徹底し、さらに効率的に資産を管理するためには、貯蓄の目的別に口座を分けることが効果的です。
給与口座とは別に、すぐに使う予定のない「生活防衛資金」用の普通預金口座、数年後に使う可能性がある資金用、そしてNISAなどを活用する「長期資産形成」用の投資口座を明確に分けましょう。
これにより、各資産の役割が明確になり、貯蓄と投資が混ざることを防ぎ、それぞれの目的に合わせたリスク管理が可能になります。
4. 副業・転職による「収入アップ」も同時に目指す
支出の管理と投資による効率化を進めた上で、貯蓄スピードを決定的に高めるのが「入金力」です。
特に若いうちは、本業以外に副業を検討することで、純粋な手取り収入を増やし、貯蓄に回せる金額を増やせます。Webライティングやデザイン、あるいはスポットバイトなどの副業も近年増加しており、スキルや時間を有効活用できる自分に合ったものを検討してみましょう。副業は、スキルアップや将来的なキャリアチェンジの準備にもなり、資産形成以外にもメリットがあります。
5. NISA(つみたて投資枠)を活用し「お金に働いてもらう」
先取り貯蓄の仕組みとして、成長性の高い資産形成を可能にするNISA(少額投資非課税制度)は非常に有効です。NISAは2024年に刷新され、非課税保有限度額が大幅に拡大しました。
NISA口座を通じて毎月定額を自動で積立投資することで、市場の成長の恩恵を受けながら、非課税で効率的に1000万円達成を目指すことができます。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)も並行して活用することで、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。これは、実質的に手取り収入(入金力)が増えることと同じ効果をもたらします。
iDeCoは原則60歳まで資金を引き出せません。これはデメリットとして挙げられることも多いですが、逆にいうと、老後資金を着実に準備するための強力な仕組みとして機能することも意味し、メリットにもなり得ます。
将来に向けた貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
【年収別】貯金1000万円の到達年齢シミュレーション
1000万円達成に必要な毎月の貯金額は、目標期間と現在の貯金額によって変わります。ここでは、現在の貯金額がゼロ(0円)からスタートし、利息や運用益を考慮しない、単純な計算で1000万円に到達するシミュレーションを行います。
毎月必要な貯金額 = 1000万円 ÷ 達成までの目標期間(ヶ月)
年収300万円(独身・実家暮らし)のケース
- 年収300万円未満の単身世帯の1000万円以上保有割合(全年齢)は16.3%です。
- 手取り月収を20万円と仮定し、貯蓄率を20%(毎月貯蓄額4万円)とした場合でシミュレーションします。
- 1000万円 ÷ 4万円/月 = 250ヶ月(20年10ヶ月)。
- もし25歳から貯蓄を始めた場合、到達年齢は45歳になります(25歳+20年10ヶ月)。
年収500万円(独身・一人暮らし)のケース
- 年収300~500万円未満の単身世帯の1000万円以上保有割合(全年齢)は24.7%です。
- 手取り月収を30万円と仮定し、貯蓄率を25%(毎月貯蓄額7万5000円)とした場合でシミュレーションします。
- 1000万円 ÷ 7万5000円/月 = 133ヶ月(約11年1ヶ月)。
- もし28歳から貯蓄を始めた場合、到達年齢は39歳になります(28歳+11年1ヶ月)。
年収700万円(2人以上世帯・DINKS)のケース
- 年収500~750万円未満の2人以上世帯の1000万円以上保有割合(全年齢)は31.8%です。
- 世帯手取り月収を45万円と仮定し、貯蓄率を30%(毎月貯蓄額13万5000円)とした場合でシミュレーションします。
- 1000万円 ÷ 13万5000円/月 = 74ヶ月(約6年2ヶ月)。
- もし30歳から貯蓄を始めた場合、到達年齢は36歳になります(30歳+6年2ヶ月)。
- NISAなどを活用し、年利数%の運用益が得られれば、さらに目標達成期間を大幅に短縮できる可能性があります。
【重要】貯金1000万円到達後の注意点と対策
1000万円という目標を達成すると、多くの人が安心感・達成感を覚えますが、それゆえに陥りやすい「落とし穴」があります。次の目標に向けて資産を伸ばしていくために、以下の注意点とステップを意識することが重要です。
注意点:達成感による浪費と投資リスクの甘い見積もり
目標を達成した途端に、「頑張った自分へのごほうび」として高額な買い物をしたり、それまで我慢していた趣味や贅沢に歯止めが効かなくなるケースがあります。特に危険なのは、余裕ができたことで無意識に生活レベルを上げてしまうことです。一度上がった生活レベルを下げるのは難しいため、達成後も倹約意識を保ち、今後の生活に必要な支出を明確に区別することが大切です。
また、資産が1000万円に達すると、少々の損失は許容できるという心理が働きやすくなり、リスク許容度を超えたハイリスクな投資に傾倒してしまうことがあります。資産規模が大きくなるほど、リスク管理の重要性も増すことを忘れてはいけません。
対策1:複数の金融機関に口座を分散する
預金残高が1000万円を超えた場合、資産保全の観点から預金保険制度(ペイオフ)を意識する必要があります。
ペイオフとは、万が一金融機関が破綻した場合でも、預金者を保護するための制度です。しかし、保護されるのは「1金融機関につき預金者1人あたり、元本1000万円までとその利息」までとなります。
つまり、1つの銀行に1000万円を超える預金(普通預金・定期預金など)を預けていた場合、1000万円を超える部分は保護されない可能性があります。このリスクに備えるため、1000万円を超える預金は複数の金融機関に分散させることが、もっとも簡単で効果的な資産保全対策となります。
対策2:預金から「資産運用(投資)」へシフトする
1000万円は大きな目標ですが、仮に年間支出が300万円の場合、この金額では約3年強の生活費にしかなりません。完全に早期リタイア(FIRE)を目指すには、年間支出の25倍程度(約7500万円)が必要とされており、1000万円はそのためのスタート資金として機能する金額です。
資産寿命を延ばし、インフレにも負けない資産を作るためには、預金から資産運用へのシフトが重要です。ただし、資産のすべてを投資に回すのは危険です。
まずは、生活費の6ヶ月分程度の「生活防衛資金」を現預金で確保した上で、それを超える余裕資金をNISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用し、長期的な資産拡大を目指すとよいでしょう。
貯金に関するQ&A
貯金に関するよくある質問にお答えします。
Q. 資産1000万円で何年暮らせる?
資産1000万円で何年暮らせるかは、個々の年間支出額によって大きく異なります。もし生活費が年間300万円の場合、利息などを考慮しなければ、1000万円では約3年強の生活費にしかなりません。これは数年間の生活費を賄う緊急予備資金や、副業やアルバイトで生活費を補填するセミリタイアのスタート資金としては機能しますが、完全にリタイアするには不十分な金額です。
Q. 貯金1000万円を超えると税務署にばれる?税金はかかる?
貯金1000万円を超えたからといって、それ自体で税金がかかることはありません。ただし、将来的に相続が発生した場合、貯金を含むすべての遺産に対して相続税がかかるかどうかは基礎控除額によって決まります。
日本の相続税の基礎控除額は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」です。仮に法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3600万円となります。1000万円の貯金のみが相続対象であれば、相続税の心配はないといってよいでしょう。しかし、他に不動産や金融資産がある場合は全体の合計額を確認する必要があります。
Q. 40歳の貯金の中央値はいくら?
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(2024)」によると、世帯主が40代の金融資産保有額は以下の通りです。
- 単身世帯(一人暮らし):平均値は883万円、中央値は85万円
- 2人以上世帯(夫婦・家族):平均値は944万円、中央値は250万円
中央値は実態に近い数字として参考にされます。いずれの世帯構成でも中央値は1000万円には大きく届かない水準となっています。
Q. 40歳で2000万円の貯金がある割合は?
40代で金融資産保有額が2000万円以上(2000~3000万円未満と3000万円以上を合算)を保有している割合は以下の通りです。この年代においては、おおよそ1割強の世帯が2000万円以上の金融資産を保有していることが分かります。
- 単身世帯:2000万円以上保有割合は合計で12.3%(2000~3000万円未満 3.7% + 3000万円以上 8.6%)
- 2人以上世帯:2000万円以上保有割合は合計で12.0%(2000~3000万円未満 5.5% + 3000万円以上 6.5%)
まとめ
貯金1000万円は、単身世帯では約2割、2人以上世帯では約3割のみが達成している、大きなマイルストーンといえる経済的な目標です。年代が上がるにつれて保有割合は高まり、特に40代以降の世帯にとっては決して非現実的な目標ではありません。
目標達成のためには、まず支出の見える化と固定費の削減、そしてNISAやiDeCoを活用した先取り貯蓄の仕組み作りが重要となります。さらに、副業や各種優遇制度を活用して入金力(貯める力)を高めることも欠かせません。
また、1000万円を達成した後も、達成感による浪費やリスク許容度を超えたハイリスクな投資に陥らないよう注意し、資産保全と投資へのシフトを通じて、継続的な資産拡大を目指しましょう。
1000万円の次のステップとしては、現在の収入や貯蓄状況から、NISAとiDeCoの最適な活用バランスを検討することが重要になってきます。特にiDeCoは掛金が全額所得控除となるため、高収入で税率が高い方ほど「入金力」を間接的に高める効果が大きく、手元の1000万円を、さらに次の目標につなげるための柱として活用を進めていきましょう。
≫今の貯金額で足りる?あなたの将来の不足額を診断
将来に向けた貯金額が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
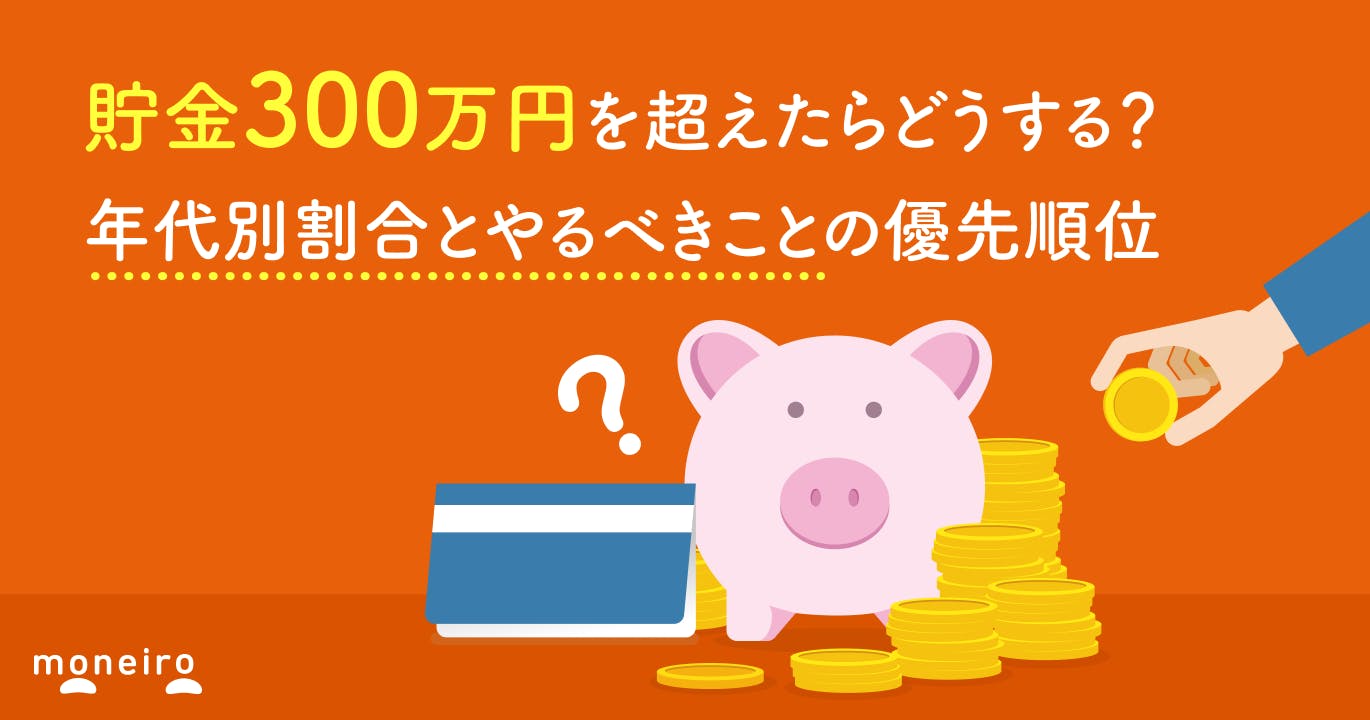

貯金1000万円はすごい?年代別の割合&達成方法・達成後の注意点を解説

世帯年収の平均・中央値は?年代別・世帯の種類別のリアルな年収データを解説
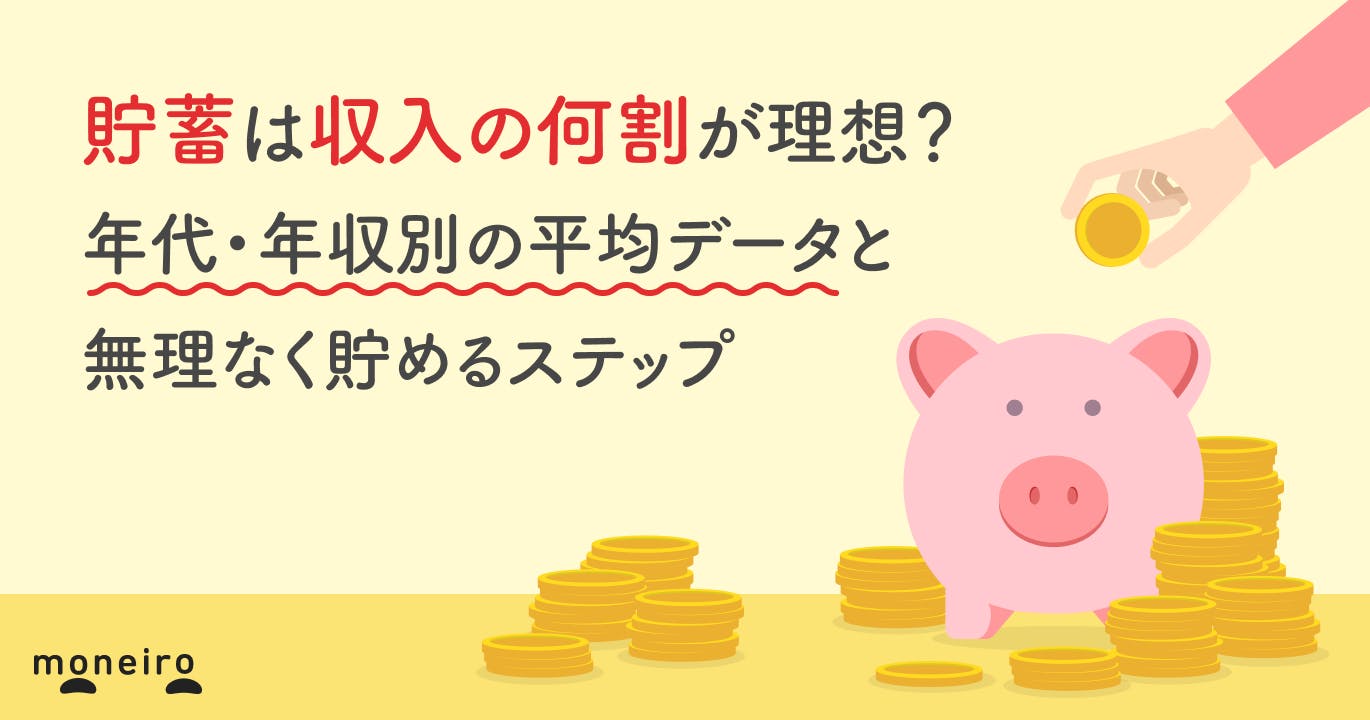
貯蓄は収入の何割が理想?年代・年収別の平均データと無理なく貯めるステップ
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
