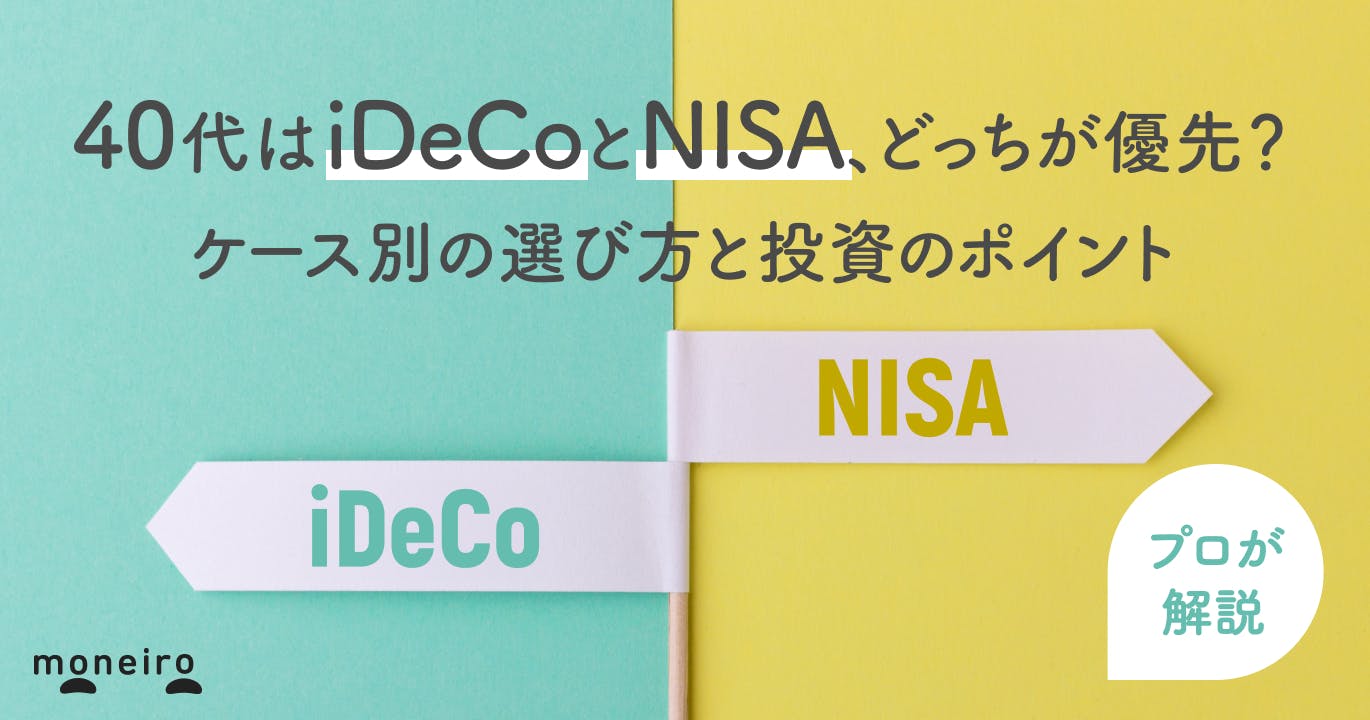40代から始める資産運用のすすめ~3つのポートフォリオ例とポイントをプロが解説
»40代の資産運用は何がベスト?無料診断はこちら
「40代の資産運用では、どのようにポートフォリオを組むべき?」「ポートフォリオの見直し方法は?」と、資産運用について悩んでいる40代の人も多いのではないでしょうか。
40代は教育資金、住宅資金の支払いをしながら老後資金を準備する必要があります。
一方、仕事のリタイアまで20年ほどあるため、長期運用を行うことで老後資金を準備することができます。
自身の資産運用の目的と目標額、リスク許容度に合わせてバランスの良いポートフォリオを組むことが大切です。
本記事では「40代の資産運用におけるベストなポートフォリオの組み方を知りたい」と思っている人に向けて、ポートフォリオを組む際のポイント、ポートフォリオ例について投資のプロが解説します。
- 40代は教育資金の準備と並行して老後の準備を行うことが大切
- ポートフォリオの組み方は「目的と目標額に合わせる」「自身のリスク許容度を踏まえてバランスを考える」など
- ポートフォリオは半年や1年に1回など、定期的に見直し(リバランス)をすることが大切
老後資金の準備方法について悩んでいるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:将来必要な金額と自分に必要な投資がわかる
▶40代から始める資産運用:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:幅広く対応できる専門家に直接相談

.jpg?w=490&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
40代の資産運用の重要性
「40代から資産運用を始めても遅いのでは?」と感じている人もなかにはいるかもしれません。
40代における資産運用の重要性について、詳しく見ていきましょう。
老後資金の準備としてまだ期間を確保できる
資産運用は長く運用することでリスクが軽減され、安定的なリターンが得られるといわれています。
老後の始まりを60歳・65歳とすると、40代から約20年の期間を確保できるため、長期運用が可能といえるでしょう。
40代から資産運用を始めることは決して遅くはなく、資産運用によって安定的に老後資金の準備ができる年代といえます。
参考)40代で資産運用を始めた場合のシミュレーション
上記は40代で資産運用を始めた場合のシミュレーションです。
毎月3万円を想定利回り3%で積立投資を行うと、60歳までの20年間で約980万円になります。一方、50歳から10年間の場合は約418万円となり、40代から始めた方がお金を効率的に増やせることがわかります。
収入の安定期を活用できる
40代で家族がいる場合、教育資金や住宅資金の支払いが発生する一方で、収入が安定してくる時期でもあります。
収入の安定期を活用して、将来に向けた資産形成を計画的にすることができます。
インフレリスクに備える必要がある
日本では1990年代半ばから約30年間にわたってデフレ社会、物価が下落傾向となっていたため、ほとんどの40代は社会人になってからインフレを経験していません。
しかし、世界的インフレの影響で日本も2023年からインフレになりました。また、IMFの予想では2029年まで2%台のインフレが続く予想がでるようになり、大きな転換点を迎えようとしています。
仮にIMFの予想通りにインフレが続いた場合、2023年に100万円で買えたモノは2030年時点で約113万円必要になります。
今後は、インフレリスクを前提としたマネープランが必要になったといえるでしょう。
インフレリスクに備えるには、インフレに強い資産を持つことです。インフレに強い資産とは主に以下の3つがあります。
- 金や不動産などの実質資産
- 株式
- 外貨建資産
上記をふまえ、自身の投資目的やリスク許容度に合わせて金融商品を選択し、資産運用を行いましょう。
(参考:第2節 デフレの原因と克服への課題 - 内閣府)
教育資金の準備が終わった後に老後資金を考える必要がある
教育資金は目の前の関心ごとになりますが、教育資金がひと段落した後は老後資金の問題が待ち受けています。
しかし、教育資金の準備が落ち着いた後の準備では間に合わない可能性があります。特に、老後資金は教育資金や住宅資金と違って借り入れができません。
少額からでも長期運用を行うことで効率的にお金を準備することができるでしょう。教育資金の準備と平行して老後の準備も行うことが大切です。

資産運用を始める前に行うこと
資産運用をより効果的に行うために、まず以下の内容を行いましょう。
資産運用の目的と目標額を明確にする
資産運用と言っても、さまざまな金融商品や投資方法があります。自分に合う方法を選択するために、まず資産運用の目的と目標額を明確にしましょう。
目的と目標額を明確にせず資産運用を始めてしまうと、ゴールがないままスタートしている状態に陥り失敗につながります。
資産運用の目的とは「お金の使い道」のことであり、例えば老後資金などです。目標とは使い道の必要金額です。この2つをしっかり確認することで、自分に合った金融商品や投資方法が見えてきます。
現状の資産状況、収入、支出を把握する
資産運用は長期運用を行うことでリスクが軽減されリターンの安定が期待できます。
資産運用を続けるためのポイントは無理のない範囲で投資をすることです。そのためには、現状の資産状況、収入と支出をしっかり把握することが大切です。
現状の資産状況の把握は預金だけでなく、既に保有している株式などの金融資産も該当します。
収入と支出に関しては変動のあるボーナスは少なめに計算し、年間収支を把握できると良いでしょう。
自分のリスク許容度を把握する
リスク許容度を把握することは、無理なく長期投資を続けるための重要なポイントです。
投資の価値が一時的にどれくらい下落しても精神的・経済的に耐えられるかを示す度合いのこと
例えば、50%の下落でも平気な人もいれば、10%程度の下落でも不安を感じる人もいるでしょう。
リスク許容度は、主に次の4つの要素から把握できます。
- 年齢(投資可能な時間)
- 家族構成やライフイベント
- 保有資産や年収
- 性格
これら4つの要素を踏まえて、自分自身のリスク許容度をしっかりと把握することが大切です。無理のない範囲で投資を続け、長期的な資産形成を目指しましょう。
ポートフォリオを組む時の3つの基本知識
ポートフォリオとは金融商品の組み合わせのことであり、具体的な運用商品の組み合わせを示したものです。
資産運用を行う際はポートフォリオを組むことが必要です。
以下の基本知識をあらためて理解してポートフォリオを組みましょう。


金融商品の種類
投資を始める際はまず「何に投資しているのか」を把握することが重要です。
投資対象として代表的なものには、以下のような種類があります。
- 株式
- 債券
- REIT(不動産投資信託)
- コモディティ(商品)
これらの投資対象はさらに国内資産と海外資産に分けられます。海外資産の場合は、投資先が先進国なのか新興国なのかでリスクやリターンの特徴も異なります。
投資対象を把握することで、金融商品の特徴を理解しやすくなるだけでなく、ポートフォリオを組む際に投資内容が重複しないように調整することができます。
バランスの取れた資産運用のためにも、自分の投資対象をしっかり確認しましょう。
リスクとリターンの関係
投資における「リスク」とは、危険度を示すものではなく「値動きの幅」を意味します。一方、「リターン」とは投資によって得られる収益のことです。
一般的に、値動きの幅が大きい(リスクが高い)資産は、リターンも大きくなる傾向があります。
投資する資産ごとにリスクとリターンの特徴は異なります。国内資産よりも海外資産の方が、リスク・リターンは一般的に大きくなります。
投資する資産の特徴を理解し、リスクとリターンのバランスを考えながら資産運用を行うことが大切です。
分散投資
投資は一つの資産に集中して投資してしまうと、状況が悪くなった場合に資産全体のダメージが大きくなってしまいます。
そのため、投資をする際は株式と債券のように、値動きや特徴が異なる複数の資産を組み合わせましょう。リスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指すことができます。
40代のポートフォリオの組み方
40代でポートフォリオを組む際は以下のポイントをおさえておきましょう。
1.資産運用の目的と目標に合わせる
資産運用の目的を確定することで「何年後にいくらの金額を準備すれば良いか」という目標が定まってきます。
資産運用の目的から投資可能期間が見えてくるため、目標額に合わせた投資先が自ずと見えてきます。
例:老後資金のために資産運用を始める場合
老後資金の目標金額は【(支出-収入)×12ヶ月×20~25年】で計算することができます。
生活費(支出)は食費や光熱費だけではなく、賃貸の予定であれば家賃も含めて計算します。また、趣味や娯楽に一定額お金をかけたい場合であればそれも含めます。
収入である年金額はねんきん定期便の確認や公的年金シミュレーターを使用して把握しましょう。
目標金額が確定したら、現在の貯蓄金額や退職金見込み額を差し引くことで不足額がわかります。
不足額を把握したら次に金額に合わせてポートフォリオを組みます。
不足金額が毎月の積立金額で足りない場合は、成長資産が期待できる資産へ積立投資をするなど、ある程度リスクを取るなどしてポートフォリオを組んでいきましょう。
ただし、リスク許容度や現在の資産状況によって自分に合った金融商品は異なります。「金融商品選びに自信がない」「専門家の意見が聞きたい」という人はFPやIFAなど、専門資格を保有し、投資経験のある専門家に相談するのがおすすめです。
マネイロコンシェルでは
・目標金額
・無理のないプラン
・投資と保険のバランス
を加味して、相談者様に合わせた資産運用をご提案します。
≫マネイロの相談・診断サービスを見てみる
2.リスク許容度を踏まえて資産のバランスを考える
40代は定年まで約20年あるため、比較的リスクを高めた資産運用が可能ですが、20代・30代と異なり損失をした場合の回復時間が限られています。
また、50代では定年が間近になることも考え、無理のないリスク許容度で資産のバランスを考えた運用を心がけることが大切です。
3.投資期間を考慮する
投資期間もポートフォリオを組む上で大切な要素です。
一般的に、投資期間が短いほどリスクが低い債券などの資産にします。一方で、投資期間が長くとれる場合は株式などのリスクの高い資産の比率を高くしてポートフォリオを決めていきましょう。
4.分散投資を心がける
リスクが高い資産ばかりに投資を行うと、暴落の際に資産が大幅に下がる可能性があります。
同じ国や地域、同じ資産に偏らないように分散投資を意識して行いましょう。
株式を保有しているなら異なる動きをする債券を組み合わせたり、景気・経済の変動の影響を分散させると良いでしょう。
5.健康リスクにも備える
資産運用を長期的に続けるために、健康リスクを配慮することも大切です。
例えば、老後資金準備で資産運用を始めた場合、前提として健康で働き続け今と変わらず安定的な収入があることになります。
万が一、働けなくなった時、病気や怪我で一時的にまとまったお金が必要になることも考えて、民間の保険を活用して備える対策をとりましょう。
参考)40代のがんに関するデータ
男女別にがんの罹患者数を見ると、男女ともに40代になると罹患者が増えていることがわかります。
また、国立がん研究センターの「患者体験調査報告書令和5年度調査(速報版)」によると、診断時に収入のある仕事をしていた人の中で、がん治療のために休職・休業した人は 53.4%、退職・廃業した人は 19.4%にのぼります。
この調査結果からも、病気になった際の経済的負担に不安を覚える人もいるでしょう。
経済的負担はがん保険や就業不能保険などで備えることができるため、治療費負担などが心配な人は民間の保険を検討しましょう。
(参考:患者体験調査報告書令和5年度調査(速報版)|国立がん研究センター)
老後資金の準備方法について悩んでいるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:将来必要な金額と自分に必要な投資がわかる
▶40代から始める資産運用:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:幅広く対応できる専門家に直接相談
40代のポートフォリオ例【プロが解説】
40代がどんな商品にどのくらいの割合で投資をしているのか、3つの事例を参考にポートフォリオを見ていきましょう。
①老後資金をしっかり確保したい40代共働き夫婦の場合
- 教育資金はある程度確保できているため、余裕資金で比較的低リスクの外貨建ての貯蓄型保険を活用(※)→65歳時点で550万円を目指す
- 万一に備えて介護と死亡保障と積立投資が同時にできる介護保障付変額保険に、夫婦それぞれ保障1000万円で加入→年利回り6%の運用で65歳時点、夫婦で約1800万円の見込み
- ネット証券でNISA口座を開設し、投資信託で積立投資→年利回り5%、65歳時点で約2900万円
- 医療保険は最低限の確保として、万が一のことがなかった際に健康祝い金が入るタイプに見直し
※為替は購入時の為替で、積立利率は購入時と変更がない場合を想定
②万が一に備えつつ老後資金を準備したい40代共働き夫婦の場合
- 預金は夫が自営業のため、生活防衛費を1ヶ月あたり30万円とし、年間360万円を準備したいとのことだったので、預金の残りは教育資金に充てることに。今後も児童手当と給与から準備を計画
- NISAで投資信託、個人年金保険を想定利回り6%で運用→目標の3000万円は準備できる予定
- 万が一のために病気や怪我の保障を確保したいというご要望に合わせて、夫が就業不能状態になった場合、毎月10万円を確保できる内容で就業不能保険をご提案
③老後資金をしっかり確保したい40代独身の場合
- まとまったお金を安定運用したいとのことだったので、比較的低リスク商品である外貨建て債券(米ドル)をご提案
- NISAのつみたて投資枠を活用してインデックス型の投資信託に毎月積立投資
- iDeCoの節税メリット、個人年金保険の保険料控除のメリットを受けたいとのご要望があったため、毎月の貯金をiDeCoと個人年金保険に充てる
参考)40代の金融資産保有額
40代が保有する金融資産保有額は「金融資産を保有している世帯」に限定すると平均が1181万円、中央値が500万円でした。
また、金融資産を保有しない世帯を含めると、平均は811万円、中央値は180万円となります。
実態を表しているといわれている中央値に注目すると、金融資産を持っている人と持っていない人の差が大きいことがわかります。
ポートフォリオは定期的な見直しが大切
一度決めたポートフォリオですが、投資を始めると評価額は日々変わるため一定の割合を保つことはできません。
例えば、株式資産を50%、債券資産を50%のポートフォリオを組んだとします。運用開始から株式市場が順調なため株式資産の評価が上がり、ポートフォリオ比率が株式資産70%、債券資産30%になりました。
資産全体で見ると増えているのでこのままで良いと思われがちですが、一方で当初のリスクを高めているため見直し(リバランス)をして元の50%:50%に戻すことが必要です。
リバランスの確認は、半年から1年に1回程度を目安にしていくといいでしょう。
見直し例:現状の運用からリスクをおさえた場合
- 目標の達成度が良好
- 年齢が上がるにつれてリスクを抑えたい
上記のようなケースでは株式の比率を下げ、債券などの安定的な資産の比率を高めましょう。
具体的には、株式資産を一定割合売却して、その売却資金で債券などの安定的な資産を買い戻します。
見直し例:現状の運用から積極的な運用に変更した場合
- 目標の達成度が芳しくない
- リスク許容度が高くなった
上記のようなケースで積極的な運用に変更したい場合は、債券などの安定的な資産の比率を低くし、株式の資産を高めることで積極的な運用が望めます。
具体的には、債券などの安定的な資産を売却して売却代金で株式資産を買い戻します。
40代の資産運用に関するよくある質問
40代からの資産運用でよくある質問について、資産運用のプロがわかりやすく回答していきます。
Q.暴落が起こった時、ポートフォリオの割合は変えるべき?
自分のリスク許容度に合わせたポートフォリオを組んでいるのであれば、割合は変えなくていいでしょう。
暴落が起こり回復するまでの期間は専門家でも予想するのは難しいです。例えば、2024年の日経平均は7月に34年ぶりの史上最高値の4万2000円台を更新しましたが、7月31日の日銀の追加政策金利発表をきっかけに翌営業日の8月2日、3日の2日間で6668円の大幅下落、そして3万1458円まで下落しています。
しかし、その後株式市場は急回復し、2024年10月半ばには一時4万円になるなど正常化を取り戻しています。
このように、短期的に戻る場合もあります。短期的に変動が大きい場合はリバランスが難しいため様子を見るほうが賢明です。
(参考:日経平均株価:リアルタイム推移・最新ニュース |日本経済新聞)
Q.円安・円高の時のベストな投資先は?
円安方向に向かう時は米ドルなどの外貨建資産に投資をしましょう。一方で、円高方向に向かう時は国内資産の投資を検討しましょう。
しかし、為替のトレンドのみではなく、例えば債券であれば、利回りが過去の中で高い場合などに外貨建債券を検討することも一案です。
高い金利の時に長期債券を持つことで高い金利を固定することができるため、為替リスクを低減することができます。
円安・円高のみで判断するのではなく、自身の投資目的、目標額に合わせて金融商品を選択することが大切です。
Q.教育資金、住宅資金、老後資金、どれを優先にするべき?
資産運用で準備する場合はまず老後資金から検討しましょう。老後資金が必要になる時期まで長期運用を行えるため、リスクを抑えた運用が期待できます。
一方で、教育資金や住宅資金は入用時期も決まっているため、比較的運用できる期間が短くなっています。教育資金であれば、長くて18年です。
仮に、大学の入学費の際に暴落が起こってしまうと、損失確定してまで売却することになってしまいます。
また、教育資金と住宅資金は借り入れ(ローン)はできますが、老後資金は老後に入ってからの借り入れが難しくなるため、計画的に準備を進めなくてはいけません。
Q.投資金額はどう決めれば良い?
投資金額は、余裕資金の範囲で始めましょう。余裕資金は、全体の貯蓄から生活防衛費と予定資金を引いた金額です。
生活防衛費の目安は会社員であれば6ヶ月分、自営業者であれば6ヶ月から1年分の生活費を目安にしましょう。
また、予定資金については
- 10年以内に予定している娯楽費
- 住宅資金
- 教育資金
などを計上します。
毎月の積立投資を考える際の投資金額は、月の収支から少なくとも「10年以上積立を継続できる金額」で決めると良いでしょう。

40代の資産運用に悩んだらマネイロに相談
金融庁が実施した「リスク性金融商品販売に係る顧客意識調査結果」によると、資産運用における悩みは「金融商品を選択する時」と回答した人の割合が一番高く、次に「保有商品に含み損が発生した時」という結果でした。
このような悩みに対して、相談先として投資未経験者は家族の次に金融機関の担当者に相談しているようです。
金融関係者に相談したい方は、マネイロがおすすめです。
マネイロは金融機関から独立しているIFA(ファイナンシャルアドバイザー)であり、中立な立場で相談者に合わせたご提案が可能です。
また、投資金額に関係なく相談者全員に担当者がつくため、運用後の相談も何回でも無料で行うことができます。
無料相談は主にオンラインで実施しており、40代の忙しい世代でも隙間時間を利用して資産運用の相談をすることが可能です。
(参考:リスク性金融商品販売に係る顧客意識調査結果|金融庁)
・ライフプランに合わせた資産運用を行いたい
・投資と保険の適切なバランスを知りたい
・将来の必要資金に合わせた投資を教えてほしい
など、マネイロでは相談者一人ひとりに合わせて、資産運用のコツをご提案できます。
≫マネイロの無料相談サービスを見てみる
まとめ
40代における資産運用は、老後まで約20年と時間があること、収入の安定期に入ることなどをふまえると老後資金の準備に適している年代でもあります。
ただし、教育資金の準備、住宅資金の支払いなども同時に行う必要があるため、きちんと計画を立てることが大切です。
まずは資産運用の目的、目標額を明確にし、自分に合った金融商品や投資方法を選びましょう。
また、投資リスクを最小限におさえるために、投資先が偏らないために分散投資を意識したポートフォリオづくりが重要になっていきます。
さらに、資産運用を長く続けられるように老後前の病気や怪我などのリスクにも配慮し、計画的に資産形成していきましょう。
»自分に合う資産運用は?3分でわかる無料診断はこちら
老後資金の準備方法について悩んでいるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:将来必要な金額と自分に必要な投資がわかる
▶40代から始める資産運用:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:幅広く対応できる専門家に直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください



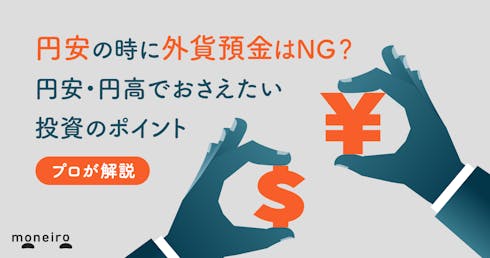
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)