
やってはいけない老後の資産運用とは?退職金を失う失敗パターンと対策を解説
>>老後資金は大丈夫?あなたに必要な金額を3分で診断
やってはいけない老後の資産運用とは?退職金や貯蓄を無駄にしないため、老後の資産運用において避けるべき7つの罠と、失敗しないためのステップを分かりやすく解説します。
この記事を読んで、老後の限られた資産を守り、より長持ちさせるための具体的な方法を確認していきましょう。
- 老後の資産運用に「失敗が許されない」理由と資産運用を阻害する3つの制約
- 老後の資産運用で絶対に避けるべき7つの「やってはいけない罠」
- 老後の資産状況を実行するための3ステップ
老後の資産運用が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後の資産運用をサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
老後の資産運用は失敗が許されない。その理由と3つの制約とは?
多くの人が老後の資金を確保するために資産運用を検討しますが、老後の資産運用は、現役世代の運用とは異なり、「失敗すると取り返しがつかなくなるかもしれない」という危機意識を持つことが重要です。
なぜなら、老後には大きく3つの「制約」があるからです。
時間の制約
老後の資産運用における最大の制約の1つは「時間」の制約です。現役世代であれば、仮に投資で損失を被ったとしても、労働収入や長い投資期間を利用して、時間をかけて損失を回復する機会があります。
しかし、定年を迎えた後の運用では、損失を取り戻すための十分な期間が残されていません。
市場の急落などで資産価値が大きく下落した場合、回復を待つ前に生活資金を取り崩さなければならなくなるリスクがあります。そのため、老後の運用は短期的な大きな利益を追求するよりも、資産の目減りを避けることが最優先となります。
収入の制約
2つ目の制約は「収入」の制約です。現役世代は給与という安定した追加投資の原資がありますが、老後の主な収入源は年金となります。年金収入は生活費の基盤となるものであり、追加の投資資金を生み出すことは簡単ではありません。
運用で損失が発生した場合、それを補填するための「追加投資の原資がない」ため、損失はそのまま資産全体を押し下げます。つまり、一度失った資産を取り戻すためのリスクを取る機会が限られているため、現役時代よりも慎重な資産配分が求められます。
心理的な制約
最後に「心理的」な制約です。老後の資産は、文字通り「生活そのもの」に直結しています。運用で損失が生じた場合、その損失額が現役世代の時よりもはるかに重く感じられます。損失が生活への不安に直結するため、人は冷静な判断を保つことが難しくなります。
例えば、市場が下落した際に、本来なら長期保有すべき局面であっても、生活不安からパニックになり、安値で売却してしまうといった行動(狼狽売り)に走りやすくなります。この心理的な制約を乗り越えるためには、事前に自身の許容できるリスクの範囲を正確に理解しておくことが不可欠です。
やってはいけない老後の資産運用の7つの罠
老後の限られた資産を危険に晒す、絶対に避けるべき7つの具体的な行動パターン(罠)を解説します。これらの罠に陥らないよう、細心の注意を払う必要があります。
1. 退職金一括投資
長年勤め上げて受け取った退職金は大きな金額となるため、これを「一括で投資」してしまうことは非常に危険です。特に退職後すぐに市場のピークで購入してしまった場合、その後の市場の下落によって、資産の大半を失うことになりかねません。
老後の資産運用は、一度にすべてを投入するのではなく、時間的な分散を意識した運用、例えば「ドルコスト平均法」を用いた積立投資や、複数年に分けて慎重に投資を行うことが、市場の変動リスクを抑えるために推奨されます。
2. 営業トークを鵜呑みにした「丸投げ運用」
金融機関の営業担当者が進める商品を、その説明を鵜呑みにして「丸投げ運用」してしまうことも避けるべきです。すべて「おまかせ」してしまうと、販売側の利益が優先される商品に投資してしまうことになりかねません。
特に手数料(信託報酬や販売手数料など)が高い商品は、運用成績が上がったとしても手数料が資産の成長を大きく妨げてしまう可能性があります。
複雑な仕組みの金融商品や、高コストなアクティブファンドなどは特に注意が必要です。投資を行う際は、必ずその商品の手数料構造と、なぜその商品が自分にとって最適なのかを深く理解することが求められます。
3. 理解できない投資商品に手を出す
「よくわからないが、儲かりそうだから」という理由で、内容をよく理解していない投資商品に手を出すのは禁物です。特に、海外の複雑な仕組債や、デリバティブを多用したファンドなど、仕組みが複雑な商品はリスクを正確に把握することが困難です。
理解できないものに投資し、市場が予期せぬ動きをした際に、なぜ損失が出たのかを把握できなければ、適切な対応ができません。投資の原則として、「自分が理解できるもの」に限定して投資を行うべきです。
4. ハイリスク・ハイリターン投資
老後の資産運用において、大きなリターンを狙ってハイリスクな投資に手を出してはいけません。FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産(仮想通貨)、先物取引などは、短期間で大きな利益を得る可能性がある一方で、その元本を大きく毀損するリスクも非常に高い投資です。
老後の資産運用は「減らさない」ことが非常に重要であり、資産全体が生活基盤と直結している以上、これらの投機性の高い商品に手を出すのはおすすめできません。
5. 「元本保証」「超高利回り」などの儲け話に乗ってしまう
「元本保証」「超高利回り」「必ず儲かる」といった、あまりにも都合の良い儲け話には最大限の警戒が必要です。このような甘い話は、投資詐欺である可能性が高いといえます。
特に、LINEのトークルームなどを利用した勧誘や、金融庁に登録していない無登録業者による勧誘には注意が必要です。
もしこのような勧誘を受けた場合は、すぐに投資を決断せず、必ずその業者が金融庁のサイトで正式に登録されているかどうかを確認する習慣をつけましょう。
老後の資産運用が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後の資産運用をサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
6. NISAを活用しない
税制優遇制度であるNISA(少額投資非課税制度)を活用しないのは、運用において大きな機会損失です。特に2024年から始まった新しいNISAは、非課税で保有できる期間が無期限化され、生涯にわたって利用できる大きな非課税投資枠(最大1800万円)が設けられました。
老後の資産運用において、運用益に一切税金がかからないこの制度は、資産の目減りを防ぎ、手取り額を最大化するためのもっとも強力なツールの1つです。「もう若くないから」とためらう必要はまったくなく、何歳からでも始められるこの制度を使わないという選択肢はありません。
7. そもそも自分のリスク許容度を理解していない
老後の資産運用で根幹となるのが、自身の「リスク許容度」を正確に理解しておくことです。リスク許容度とは、自分がどれくらいの損失までなら精神的・経済的に耐えられるかという尺度です。
これを理解しないまま投資を始めると、市場が下落相場に入った際に、損失に耐えきれずにパニックになり、運用計画を破綻させてしまうことにつながります。自分の生活資金、予備資金、運用に回せる資金を明確に分離し、冷静な判断ができる範囲でのみ投資を行うことが重要です。
老後の資産運用はどうすればいい?失敗しないための3ステップ
老後の資産運用を成功させるためには、感情的な判断や安易な儲け話に流されるのではなく、論理的かつ段階的なステップを踏むことが重要です。
STEP1.資産の棚卸しと現状把握
まず最初に行うべきは、自身の資産状況と将来の収支の「棚卸し」と「現状把握」です。具体的には、現在保有している資産(現金、預金、保険、不動産、投資信託など)をすべて洗い出し、そのうち「投資に回してもよいお金」を明確にします。同時に、毎月の年金収入と支出(収支)を洗い出し、不足額や余裕額を把握しておきましょう。
また、「ねんきんネット」などを活用して、公的な年金の見込額を正確に確認しておくことも、将来設計の土台として非常に重要です。この現状把握こそが、リスク許容度を決定する基礎となります。
STEP2.資産運用の方針を決める
老後の資産運用の方針は、若い時に比べて大きく変わります。現役時代は「資産を増やす」ことが主目的となりますが、老後は「資産を減らさない」「資産を長持ちさせる」ことの重要性が格段に高まります。
具体的には、値動きの異なる複数の資産(株式、債券など)を組み合わせた「分散投資」が基本となります。例えば、比較的安定した値動きが期待できる債券と、長期的にインフレを上回る成長が期待できる株式を、自身のリスク許容度に応じて組み合わせます。
ただし、中心にはより低リスクな債券(国債や社債など)を据えるのがおすすめです。
例えば、65歳時点では資産全体の50%程度を債券にしておくといった配分が推奨されます。以降は、年齢を重ねるごとに債券の比率を高めていくことで、市場変動による影響を抑え、安心感が高まることができます。
STEP3.NISAの活用と実行
STEP2で定めた低リスクを重視した方針に基づき、実行に移します。実行の柱となるのは、税制優遇制度であるNISAを最大限活用することです。
NISAには、年間120万円まで積立投資に適した「つみたて投資枠」と、年間240万円まで一括投資も可能な「成長投資枠」の2種類があります。例えば、まずは「つみたて投資枠」で低コストのバランス型ファンドを毎月コツコツと購入しつつ、退職金などのまとまった資金の一部を「成長投資枠」で債券ファンドなどに数回に分けて投資する、といった戦略が考えられます。
重要なのは、NISAという有利な制度のなかで、STEP2で決めた「減らさない」ための方針を着実に実行し、市場の短期的な動きに惑わされないことです。
老後の資産運用で迷ったときは専門家へ
老後の資産運用は、現役時代と比べて失敗が許されないからこそ、不安や疑問が生じた際は、信頼できる専門家へ相談することも賢明な選択の1つとなります。
FP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家から意見を得ることで、客観的な視点と制度の最新情報に基づいた、より確実な計画を立てることができます。
相談から運用サポートまで無料の「マネイロ」を上手に活用
マネイロは、さまざまな世代に向けたお金の診断・相談サービスです。銀行・証券会社・保険会社などで実績を挙げたファイナンシャルアドバイザーが一人ひとりに担当としてつき、サポートを行います。
銀行や証券会社など、特定の金融機関に所属していないため、個人のライフプランや家計状況を総合的に判断し、老後に最適な運用方法やポートフォリオについて客観的なアドバイスの提供が可能です。
また、運用は一度始めたら終わりではなく、定期的な見直しが大切です。マネイロなら運用後の相談も何度でも無料で対応。長期的なサポートを受けながら資産形成を進めることができます。
\空いている日程から早速相談を予約してみる/
老後の資産運用に関するQ&A
老後の資産運用に関するよくある質問と回答を以下にまとめました。
Q. 老後の資産運用でおすすめの投資先は?
老後の資産運用では、先に述べたように「減らさない」ことを特に重視したほうがよいでしょう。そのため、比較的価格変動が少なく、安定した収益を期待できる「債券」を上手に使うことが推奨されます。
日本国内の債券や、格付けの高い先進国の国債などをポートフォリオの中心に据えた上で、低コストのバランス型ファンドやインデックスファンドも一部取り入れることで、リスクを抑えた運用が可能になります。
Q. 退職金をすべて預金するのはよくない?
退職金をすべて預金に回すことは、一見リスクがないように見えますが、現在の超低金利環境下では、実質的に資産が目減りしていくリスクがあります。
インフレによって物価が上昇し続けた場合、預金だけでは購買力を維持できず、結果として老後資金の目減りにつながります。
そのため、必要な生活費や緊急予備資金を除いた「運用に回してもよいお金」については、リスクを抑えた運用を行うことで、資産の長寿命化を目指すのが、より望ましいといえます。
Q. 定年後からNISAを始めても遅くはない?
定年後からNISAを始めることは、決して遅くはありません。NISAは税制優遇制度であり、運用益が非課税になるメリットは、投資期間の長短に関わらず享受すべきものです。
現役時代に投資の経験がなかったとしても、定年後の「減らさない運用」を目的とした低リスクのポートフォリオをNISA枠内で組むことは、資産を効率的に長持ちさせるための有効な手段です。
まとめ
老後の資産運用は、現役世代とは異なり、「時間」「収入」「心理」の3つの大きな制約があるため、「失敗が許されない」という意識を持って取り組む必要があります。
特に記事で紹介したような、退職金一括投資やハイリスクな商品への投資、理解できない商品への手出しといった、7つの「やってはいけない罠」を回避することが、老後資産を守るための第一歩です。
失敗を避けるためには、まず資産の棚卸しを行い、その後、「増やす」よりも「減らさない」「長持ちさせる」ことに重点を置いた運用方針を定め、NISAなどの制度を最大限活用して実行に移すことが重要です。
このプロセスを通じて、冷静かつ計画的に資産を管理し、安心して老後を過ごすための基盤を築きましょう。
>>老後資金は大丈夫?あなたに必要な金額を3分で診断
老後の資産運用が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後の資産運用をサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
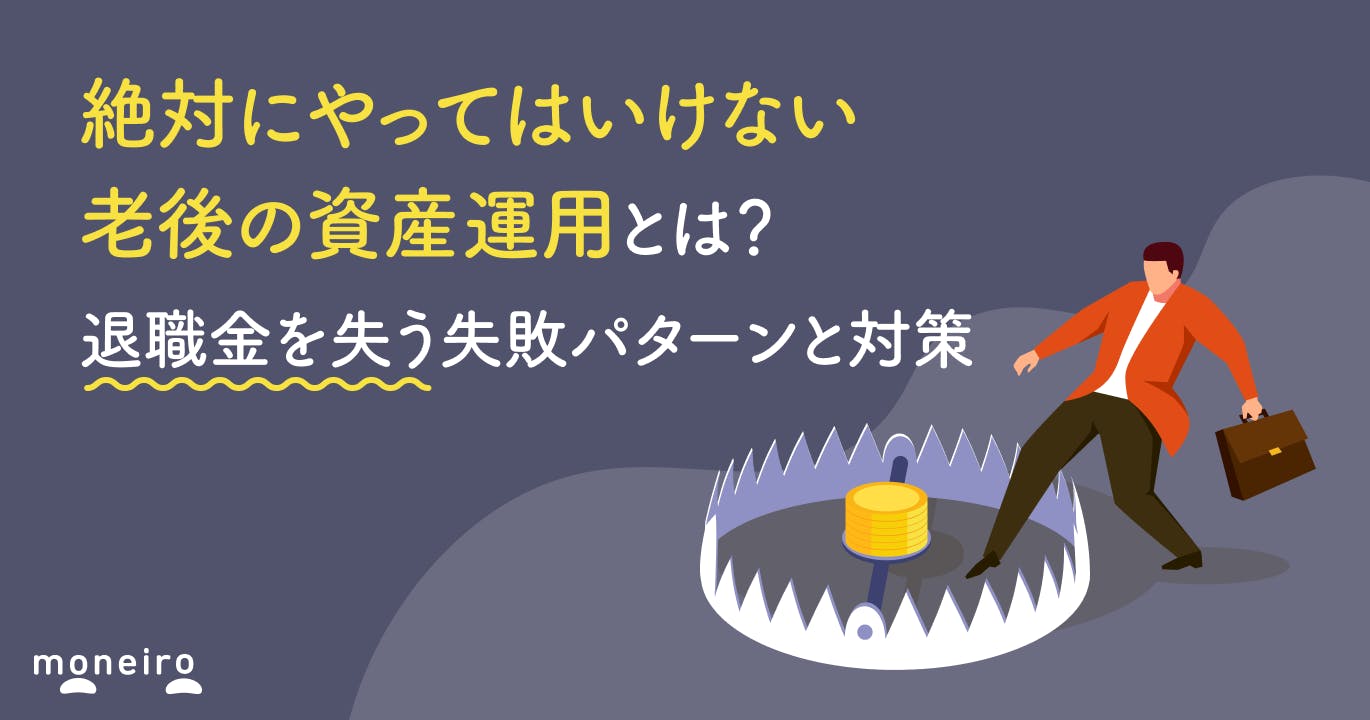
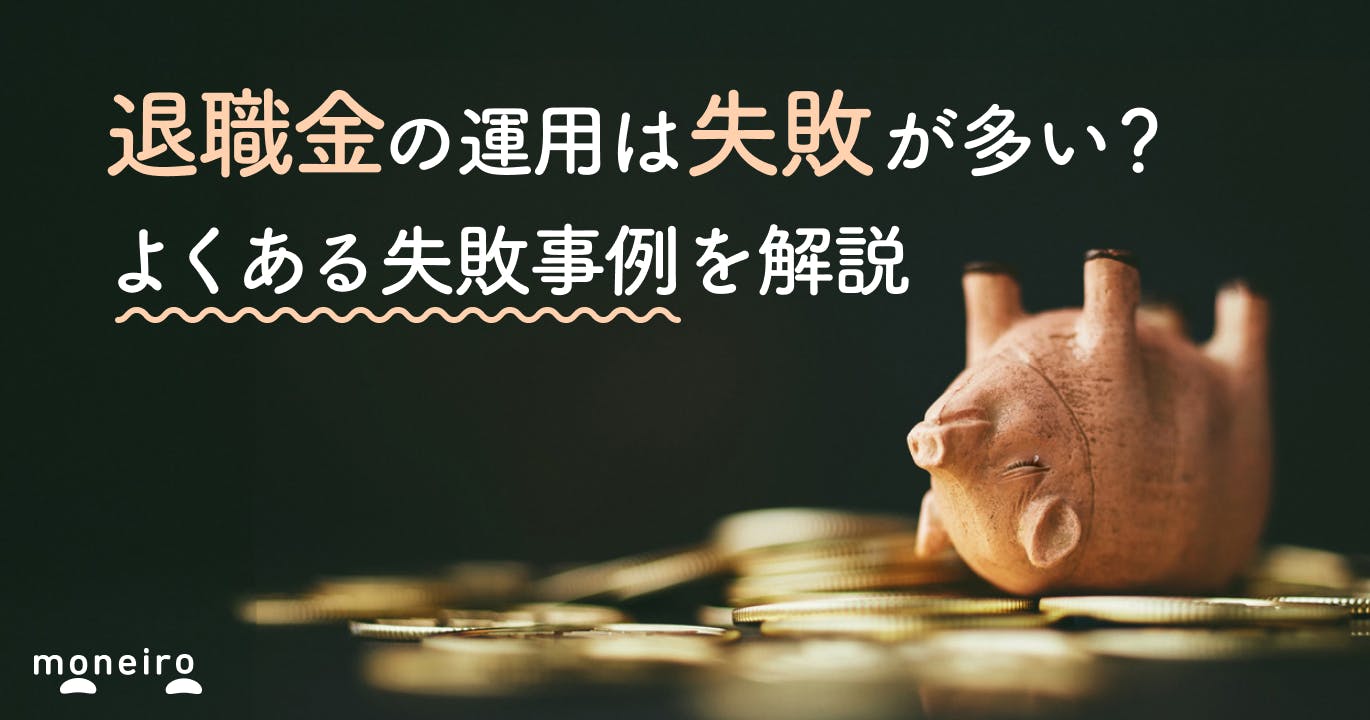

.png?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)