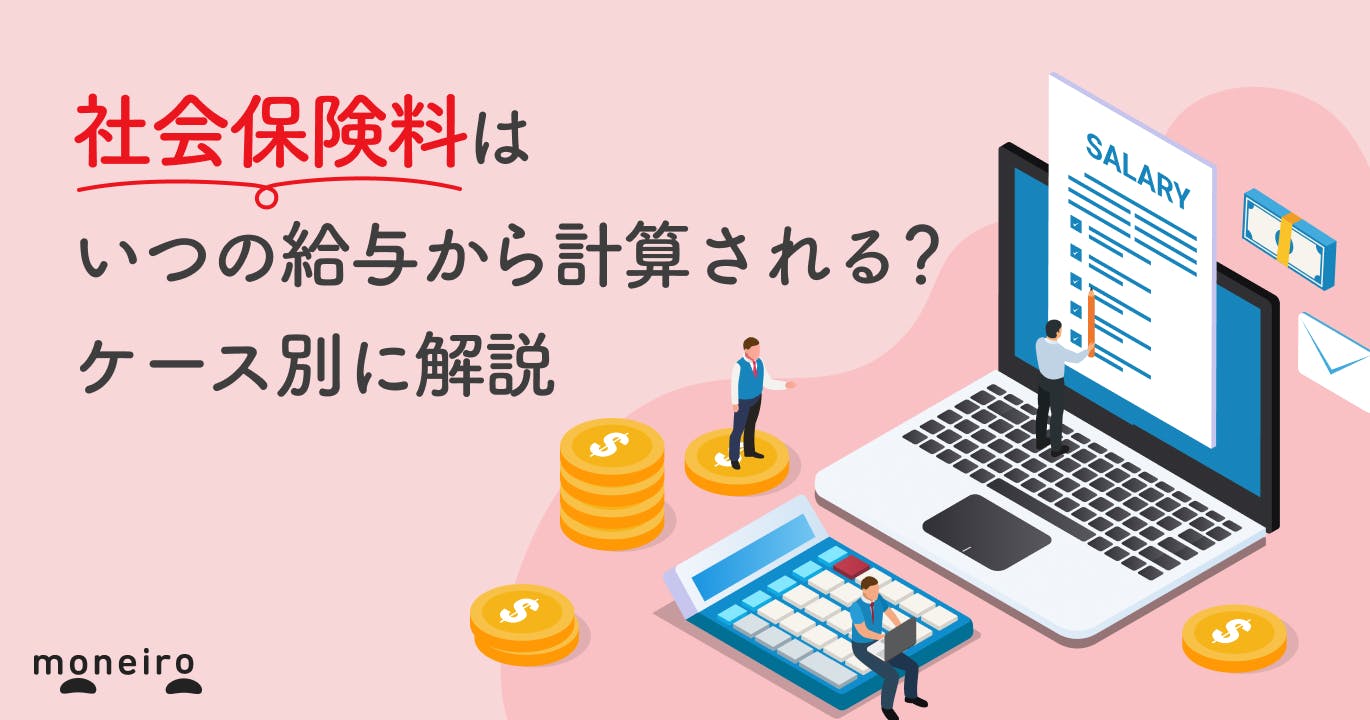企業年金と厚生年金は両方もらえる?専門家が条件・金額・注意点をわかりやすく解説
≫年金だけで生活できる?老後のお金を3分で診断
「企業年金と厚生年金は両方もらえる?」という疑問は、多くの会社員や退職予定者が抱えるものです。
結論からいえば、企業年金は公的年金(国民年金・厚生年金)とは別の制度であり、条件を満たせば両方受け取ることが可能です。
ただし、受給金額や方法は制度の種類や加入期間によって異なり、税金や社会保険料が増えるケースもあります。
本記事では、企業年金と厚生年金を併給できる条件や仕組み、受給額の目安、税金への影響、そして手続きの流れまで、わかりやすく解説します。
自分がどれだけ受け取れるのか、今から確認して老後の資金計画に役立てましょう。
- 企業年金は公的年金(国民年金・厚生年金)とは別の制度のため、条件を満たせば両方受け取ることができる
- 企業年金と厚生年金など含めた年金収入が増えると、受け取り方によっては税金や保険料負担が増える
- ベストな受け取り方は個人によって異なるため、事前にシミュレーションを行うことが大切
将来のお金が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
企業年金と厚生年金、両方もらえる仕組み
厚生年金は国が運営する公的年金制度の一部で、会社員や公務員が加入します。
一方、企業年金は企業が任意で設ける私的年金制度で、確定給付企業年金(DB)や確定拠出年金(DC)などがあります。両方の受給要件を満たせば同時に受け取れます。
まずは基本的な仕組みと注意点を確認しましょう。
公的年金と企業年金の位置づけの違い
日本の年金制度は「3階建て」に例えられます。1階が国民年金、2階が厚生年金、3階が私的年金になります。
企業年金は企業が従業員の老後資金を支援するために独自に設ける私的年金制度の一つです。公的年金に上乗せする形で、より豊かな老後生活を送るための資金源となります。
併給できない例や例外ケース
公的年金と企業年金は併給できます。しかし、公的年金の中では、老齢年金と遺族年金など、複数の種類の年金受給権がある場合、原則1つの年金しか受給できません。
ただし、老齢厚生年金と企業年金は互いに干渉することなく受け取ることが可能です。
(参考:年金の併給または選択|日本年金機構)
企業年金の種類と特徴をおさらい
企業年金は制度によって特徴や受け取り方が異なります。
仕組みを理解しておくことで、自分がどの制度に加入しているか、将来いくら受け取れるかの見通しが立てやすくなります。
確定給付企業年金(DB)
将来受け取る年金額が、あらかじめ定められている制度です。企業の責任で運用が行われるため、加入者自身が運用リスクを負うことはありません。
企業型確定拠出年金(DC)
企業が拠出した掛金を加入者自身が運用し、その成果によって将来の給付額が決まります。運用次第で年金額を増やす可能性がある一方、運用リスクは加入者自身が負います。
確定拠出年金の個人向けの制度が「iDeCo(イデコ)」です。
退職一時金制度
企業年金とは別に、退職時に一度にまとまった金額が支給される制度です。企業年金と退職一時金の両方がある企業もあります。
両方もらえる条件と対象者
企業年金と厚生年金は、それぞれの加入期間や年齢要件を満たせば併給可能です。加入している制度の条件を確認しておきましょう。
≫あなたは年金だけで生活できる?老後のお金を3分で診断
勤務年数や加入期間の要件
老齢厚生年金は原則10年以上の加入期間が必要です。一方、企業年金を受け取るには、企業の年金規約に定められた勤務年数や加入期間の要件を満たす必要があります。
一般的には、勤続3年以上などと規定されていることが多いです。
受給開始年齢と併給のタイミング
厚生年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、企業年金は60歳から受け取りが開始される場合が多いです。したがって、60歳から65歳の間は、企業年金のみを受け取ることになります。
企業年金がない場合の代替制度
企業年金制度がない会社に勤めている場合でも、個人で老後資金を準備できる制度があります。
例えば、iDeCo(個人型確定拠出年金)は企業年金と同様に掛金を自分で運用し、老後資金を形成する私的年金制度です。税制優遇を受けられるメリットがあります。
企業年金と厚生年金を併給した場合の計算方法
企業年金連合会「企業年金に関する基本統計」によると、確定給付企業年金(DB)の老齢給付金の平均受給額(年額)は62万円です。
これを厚生年金の平均受給額と合算することで、おおよその合計額を計算できます。
ただし、企業年金(DC)は、個人の運用実績によって金額が大きく変動するため、一概にシミュレーションすることは困難です。
受給額の計算方法の基本は以下のとおりです。
・企業年金(DB):勤務期間や給与水準などに基づき、企業の規約で定められた計算式で決まります
・企業年金(DC):勤務期間や給与水準に応じた掛金の運用実績によって決まります
併給による税金・社会保険料の影響
年金収入が増えると税金や保険料負担も増える可能性があります。受け取り方の工夫で軽減できる場合もあります。
所得税・住民税が増えるケース
企業年金を「年金形式」で受け取ると、公的年金と合算して「雑所得」として課税されます。
収入が多い場合は、所得税や住民税が増える可能性があります。
国民健康保険料・介護保険料への影響
年金収入が増えると、国民健康保険料や介護保険料の負担額が増加する場合があります。
税負担を抑えるための受け取り方(年金・一時金選択)
企業年金の受け取り方には「一時金」と「年金形式」の2つの選択肢があり、それぞれ税金の扱いが異なります。
・年金形式:雑所得として扱われ、公的年金等控除が適用されます
どちらが有利かは個人の状況によって異なるため、シミュレーションを行うことが重要です。
企業年金と厚生年金を受け取るための手続き
受給にはそれぞれの制度に応じた申請手続きが必要です。
必要書類と提出先
厚生年金は日本年金機構、企業年金は各企業の年金制度を運営している団体が窓口となります。必要書類はそれぞれ異なるため、事前に確認が必要です。
受給開始までのスケジュール
厚生年金は、65歳になる誕生月の3ヶ月前に、日本年金機構から年金請求書が送付(65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給していない場合)されます。企業年金は、企業の担当部署に問い合わせて手続きを進めます。
手続きの注意点(遅延・不備対応)
手続きに不備があると、受給開始が遅れる可能性があります。書類に不備がないか、期限内に提出できているかをしっかり確認しましょう。
よくある失敗と回避のポイント
併給できるといっても、受給額や税負担の見通しを誤るケースがあります。
受給額を見誤る
企業の規約や運用実績によって、企業年金の受給額は大きく変わります。会社の担当部署や年金制度の通知を確認し、正確な受給見込み額を把握しましょう。
税金・保険料負担を見落とす
年金額が増えることで、税金や社会保険料の負担が増える可能性があります。これらの負担額も考慮して、手取り額を計算することが大切です。
制度変更への対応が遅れる
年金制度は常に変化しています。最新の制度変更情報を確認し、必要に応じて自身の老後プランを見直しましょう。
まとめ
企業年金と厚生年金は、それぞれの条件を満たせば併給可能です。受給額や開始時期、税金・社会保険料への影響を踏まえた上で計画を立てることが、安定した老後生活につながります。
早めに加入状況や見込額を確認し、不明点は勤務先や専門家に相談しましょう。
≫あなたは年金だけで生活できる?老後のお金を3分で診断
将来のお金が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。