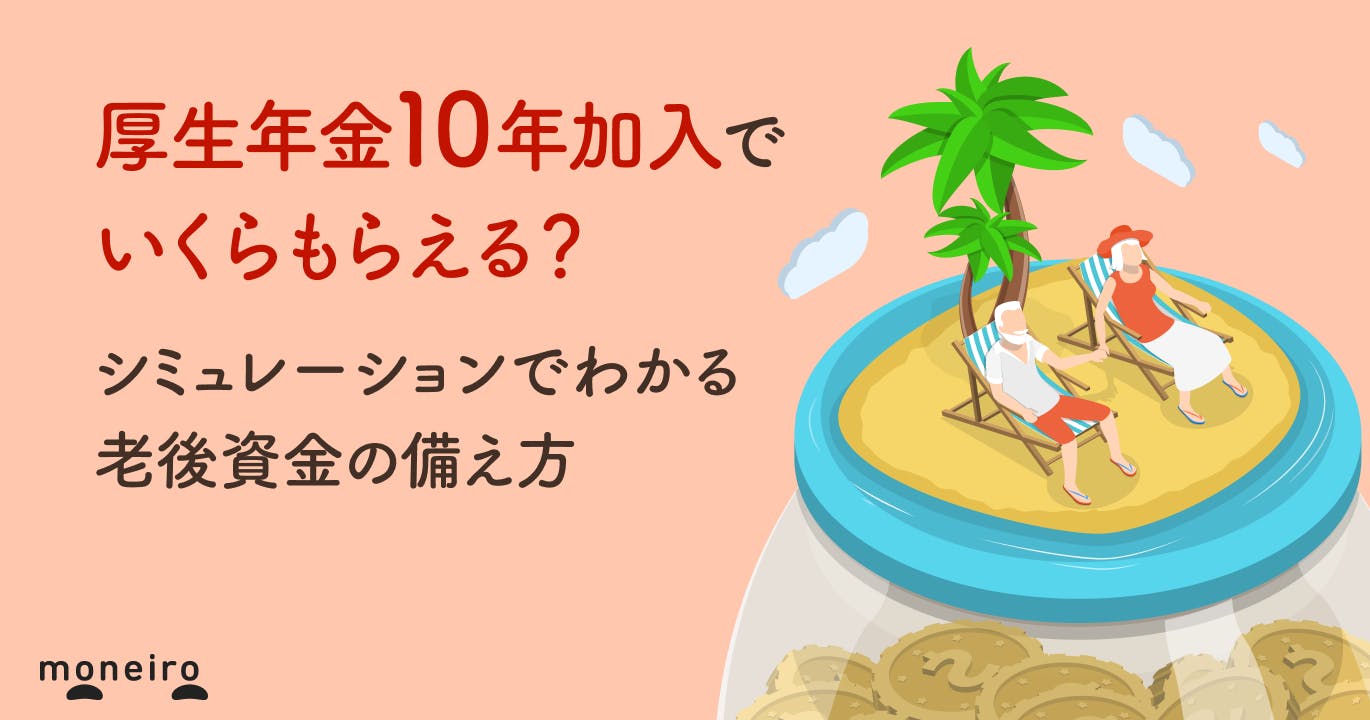厚生年金10年加入でいくらもらえる?シミュレーションでわかる老後資金の備え方
≫年金だけで老後は足りる?あなたの必要額を今すぐ診断
「厚生年金に10年だけ加入した場合、実際いくらもらえるのか?」「それだけで生活できるのか?」と不安に思う人は少なくありません。厚生年金は、2017年の制度改正により「国民年金または厚生年金に10年以上の加入」で受給資格が得られるようになりました。
本記事では、国の公表データをもとに厚生年金10年の受給額をシミュレーションし、国民年金との合算額や家族構成による違いを解説します。
さらに、公的制度の中で年金額を増やす方法や、不足分を補う私的年金・資産形成の手段についても紹介。将来の備えを考えるための指針を専門家視点でまとめます。
- 国民年金と厚生年金を合算して加入期間が10年以上あれば、厚生年金への加入期間は1ヶ月であっても、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れる
- 厚生年金に10年加入、残りの期間に国民年金保険料の未納がなければ老齢基礎年金を満額もらえるが、両方合わせても受け取れる年金額で老後をまかなうのは厳しい可能性が高い
年金受給額が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶オンライン無料相談:年金の不安を専門家に直接相談

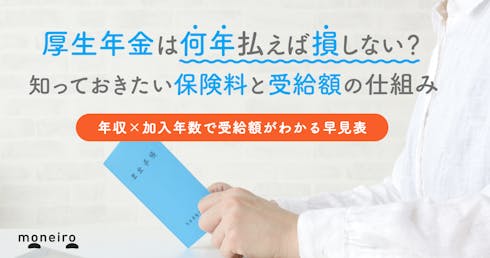
受給資格期間が10年以上あれば厚生年金は「1ヶ月加入」で受給資格がある
公的年金を受け取るためには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。これは、2017年に行われた制度改正によるもので、それ以前は原則として25年以上の受給資格期間が求められていました。
国民年金と厚生年金を合算して加入期間が10年以上あれば、厚生年金への加入期間は1ヶ月であっても、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れるようになっています。
受給資格期間に含まれるもの(国民年金・免除期間・空白期間など)
受給資格期間(10年)には、以下が含まれます。
- 国民年金の加入期間
- 厚生年金や共済年金の加入期間
- 保険料免除期間(全額免除・一部免除)
- 学生納付特例・若年者納付猶予期間
- 「空白期間」(海外在住などで日本の年金制度に加入できなかった期間)
老齢基礎年金の受給資格期間には、国民年金保険料を納付した期間の他、保険料の免除期間や猶予期間、合算対象期間(空白期間)などが含まれます。
厚生年金保険の被保険者期間は、この老齢基礎年金の受給資格期間にも含まれます。
例えば、会社員が厚生年金に加入している期間は、国民年金にも加入していると見なされます。
また、産前産後休業や育児休業期間中は、保険料が免除されても年金受給額には影響しないように、保険料を納付した期間として計算されます。

厚生年金に10年だけ加入した場合の受給額
受け取れる厚生年金は、「老齢基礎年金(国民年金部分)」と「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の合計です。
- 老齢基礎年金(満額):2025年度で 年額83万1700円(40年加入で満額)
- 老齢厚生年金(報酬比例部分):加入期間や標準報酬月額に応じて加算されます
厚生年金(老齢厚生年金)の受給額は、以下の計算式で計算できます。
報酬比例部分については、以下の計算式で計算できます。
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの厚生年金加入期間の月数
【平成15年4月以降】
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間の月数
平均年収300万円で10年加入した場合
平均年収:300万円
平均標準報酬額:26万円
(経過的加算と加給年金額は0円)
計算式は以下のようになります。
老齢厚生年金額は、年額約17万円(月額約1.4万円)となります。これに国民年金加入期間に応じた老齢基礎年金を加えた額を受け取れます。
平均年収500万円で10年加入した場合
平均年収:500万円
平均標準報酬額:41万円
(経過的加算と加給年金額は0円)
計算式は以下のようになります。
老齢厚生年金額は、年額約27万円(月額約2.3万円)となります。これに国民年金加入期間に応じた老齢基礎年金を加えた額を受け取れます。
平均年収700万円で10年加入した場合
平均年収:700万円
平均標準報酬額:59万円
(経過的加算と加給年金額は0円)
計算式は以下のようになります。
老齢厚生年金額は、年額約39万円(月額約3.3万円)となります。これに国民年金加入期間に応じた老齢基礎年金を加えた額を受け取れます。
年金受給額が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶オンライン無料相談:年金の不安を専門家に直接相談
厚生年金の加入期間が短い時の注意点
厚生年金の加入期間が10年の場合、老齢厚生年金の金額は数万円程度にとどまる場合が多くなります。
残りの期間に国民年金保険料の未納がなければ老齢基礎年金を満額もらえますが、老齢基礎年金を加えても生活費をまかなうには不足する可能性があります。
夫婦二人世帯の老後の最低日常生活費は平均で月額約25.6万円、65歳以上の単身無職世帯の平均消費支出は月額約15万円です。
これらの生活費の目安と、10年加入の場合の年金受給額を比較すると、公的年金だけでは生活費が不足する可能性が高いことがわかります。
(参考:家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要)
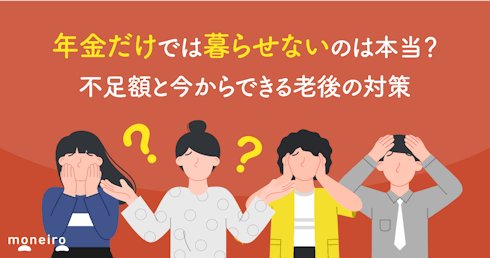
家族がいる場合に受給額が変わるケース
厚生年金は本人だけでなく、配偶者や子どもがいる場合に加算や遺族給付があります。
加給年金が受けられる条件と金額
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳までの子どもがいる場合に加算される年金です。
配偶者には年間23万9300円(令和7年4月から)が加算され、さらに生年月日に応じた特別加算が上乗せされる場合があります。
10年間の加入期間ではこの要件を満たせないため、加給年金は対象外となります。
遺族年金で配偶者や子どもが受け取れる場合
厚生年金に加入中または加入していた人が死亡した場合、遺族は遺族厚生年金を受給できます。遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額が基本です。
特に、厚生年金の被保険者期間が300ヶ月(25年)に満たない場合でも、300ヶ月とみなして計算される特例措置があります。
これにより、たとえ加入期間が10年と短くても、遺族はより多くの年金を受け取ることができます。
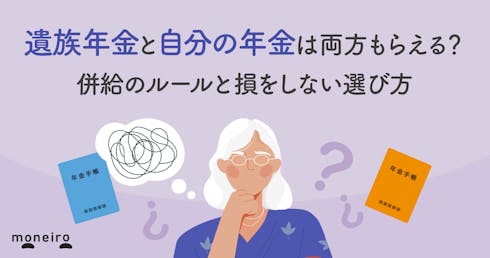
将来の年金額を増やすためにできること
厚生年金に10年しか加入していなくても、工夫次第で受給額を増やす方法があります。
繰下げ受給で最大84%増やす方法
年金は、本来の受給開始年齢である65歳以降に受給を遅らせる「繰下げ受給」を選択することで、受給額を増やすことができます。
1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額され、75歳まで繰り下げると最大84%増加します。
60歳以降国民年金に任意加入または厚生年金加入で受給額を増やす
60歳になった時点で国民年金の未納期間があれば、60歳以降も国民年金に任意加入して老齢基礎年金を増やせます。また、厚生年金には70歳まで加入できるため、60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、老齢厚生年金を増やすことも可能です。
この増加分は生涯にわたって続くため、長期的に見ると大きな差となります。
在職老齢年金制度を活用する
60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、「在職老齢年金」の仕組みにより、年金と給与の合計額が一定額を超えると、年金の一部が減額されることがあります。
ただし、老齢基礎年金は減額されず、全額を受け取れます。この支給停止調整額は、62万円に引き上げられる予定です。
≫年金だけで老後は足りる?あなたの必要額を今すぐシミュレーション
厚生年金10年だけでは足りない?不足分を補う方法
短期間加入の厚生年金では生活費を十分にカバーできないため、私的年金や投資での備えが必要です。


iDeCoや企業型DCで老後資金を上乗せ
老後の生活費不足を補うために、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)といった確定拠出年金制度を活用する選択肢があります。
これらの制度は税制上の優遇措置があり、効率的な資産形成をサポートします。
国民年金基金や付加年金で基礎年金を増やす
国民年金基金や付加年金は、老齢基礎年金に上乗せして年金額を増やすための制度です。これらの制度には厚生年金加入中は入れませんが、国民年金加入者(任意加入者も含む)は加入できます。
付加年金は月額400円の保険料で、将来の年金額が「200円 × 納付月数」増えます。国民年金基金は付加年金と同時に利用することはできませんが、自分で掛金や年金額を選んで加入できます。
NISAで長期資産形成を行う
NISA(少額投資非課税制度)も、老後資金を形成するための有効な手段です 。NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度で、長期的な資産形成を後押しします。
まとめ
厚生年金は2017年の制度改正により、国民年金と合わせて10年の加入期間があれば受給資格を得られるようになりました。
ただし、実際の受給額は、標準報酬や国民年金との合算状況にもよりますが、年間数十万円から月額で数万円程度にとどまるケースが多く、老後の生活費を十分に賄うには不足します。
家族がいる場合には加給年金で支給額が上乗せされる可能性もありますが、それでも生活費全体をカバーするには限界があります。
将来の年金額を増やすためには、繰下げ受給や任意加入など公的年金制度を活用する方法が有効です。さらに、不足分については私的年金制度や投資などによる資産形成を組み合わせて備えることが大切です。
厚生年金10年の受給額を正しく理解し、早めに対策を講じることが、老後の安心につながります。
≫年金だけで老後は足りる?あなたの必要額を今すぐシミュレーション
年金受給額が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶オンライン無料相談:年金の不安を専門家に直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

老後に必要なお金はいくら?単身・夫婦の世帯タイプ別必要額を解説
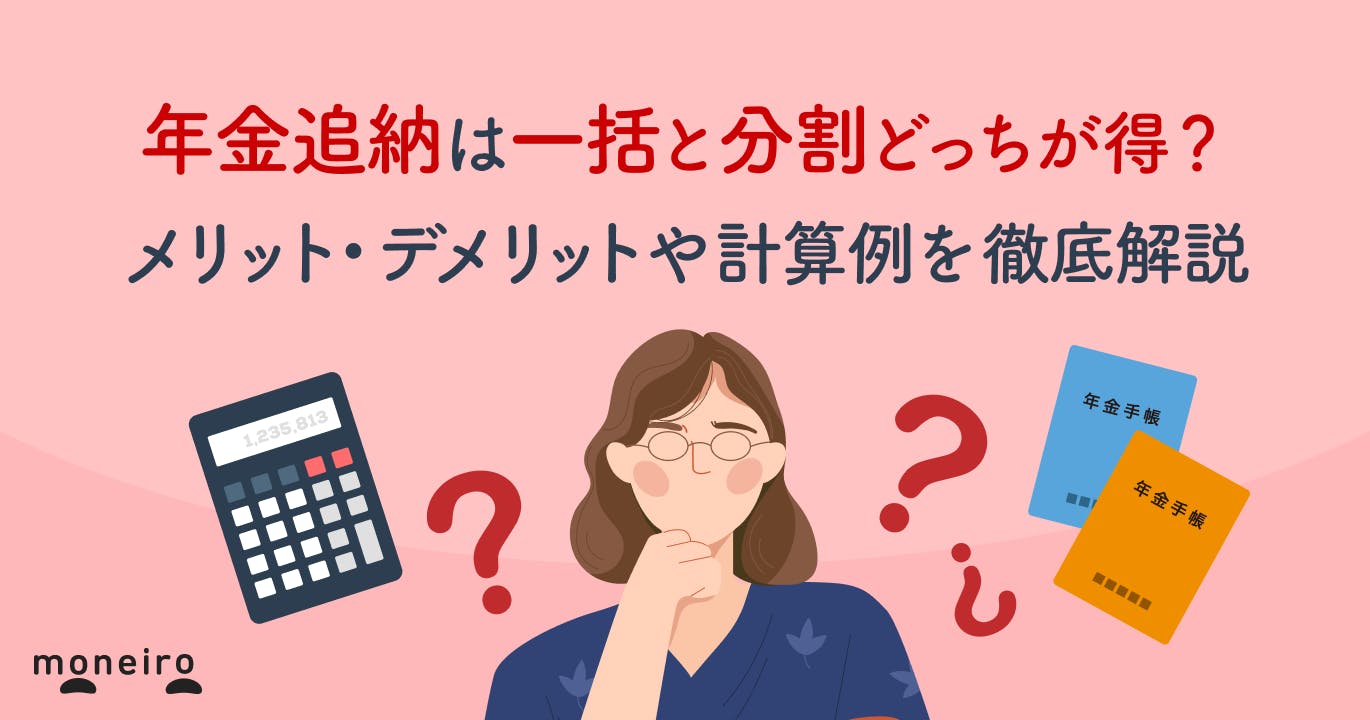
年金追納は一括と分割どっちが得?メリット・デメリットや節税効果を専門家が解説

老後破産する人の特徴とは?原因や破産しないための対策を解説
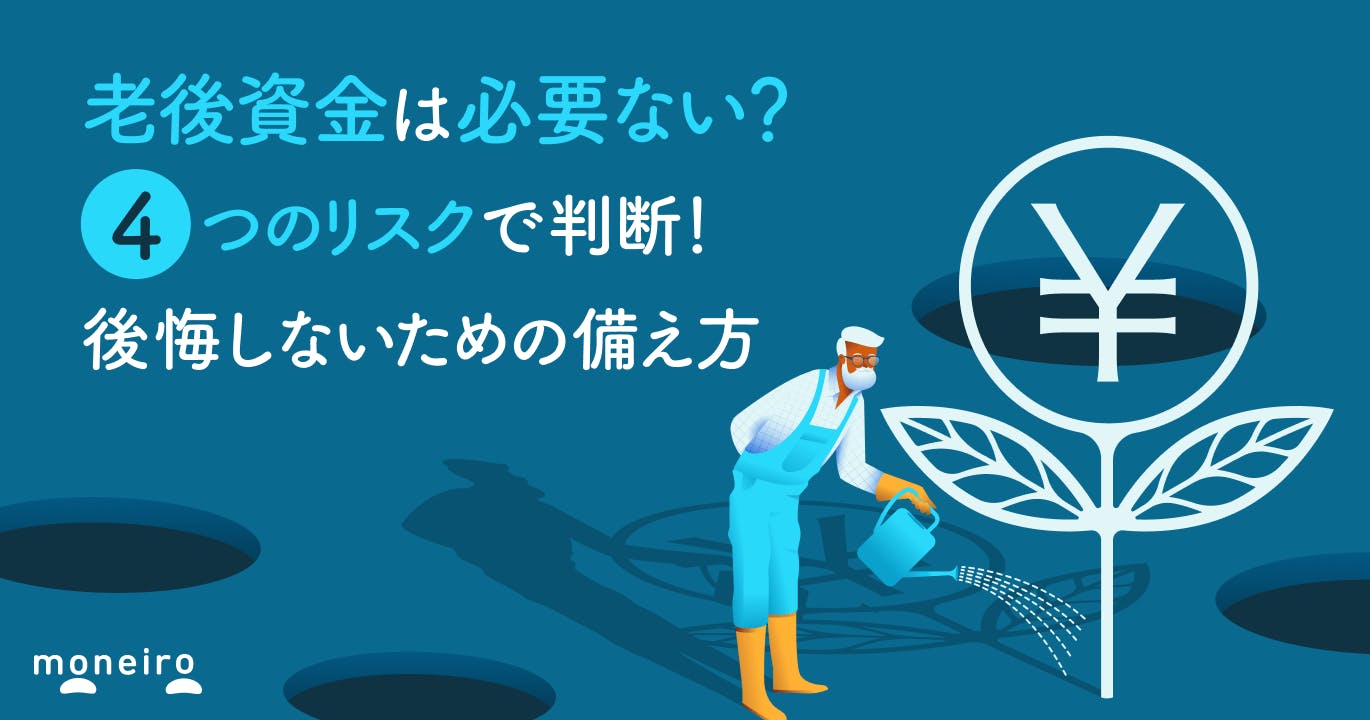
老後資金は必要ない?4つのリスクで判断!後悔しないための備え方と賢い選択肢を解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。