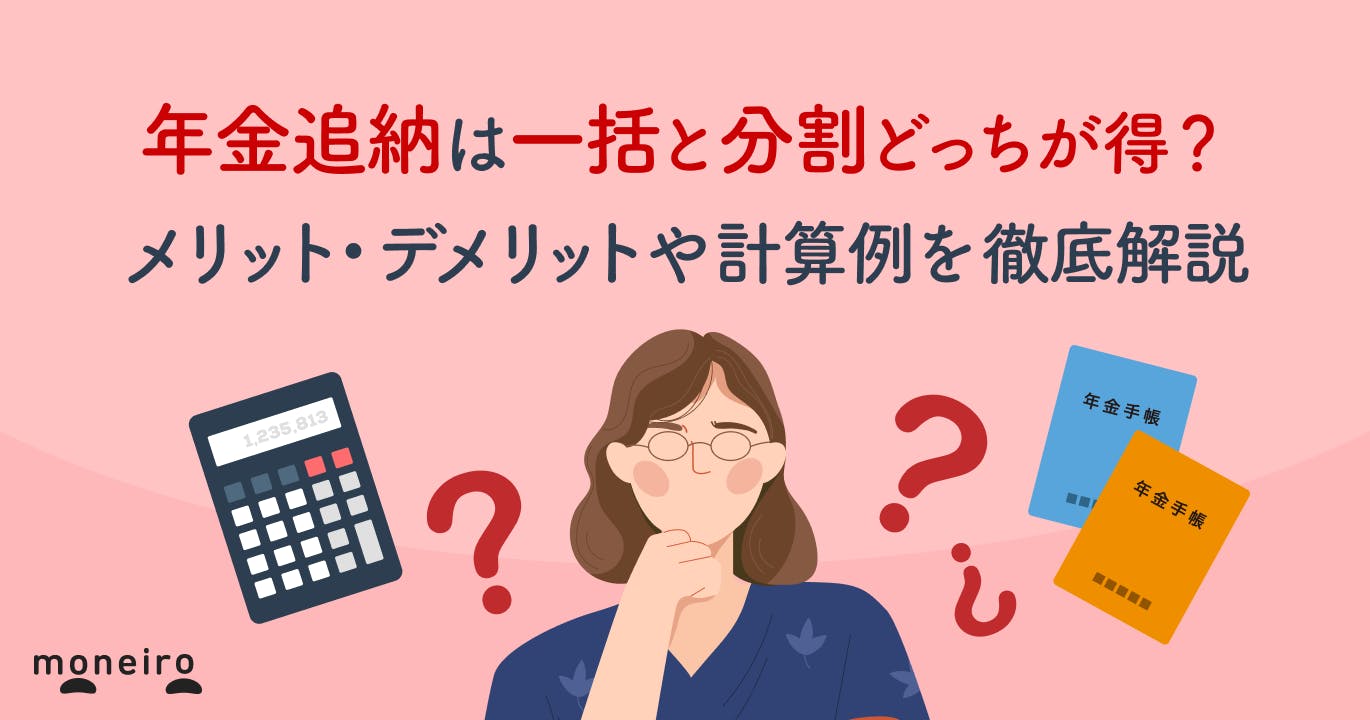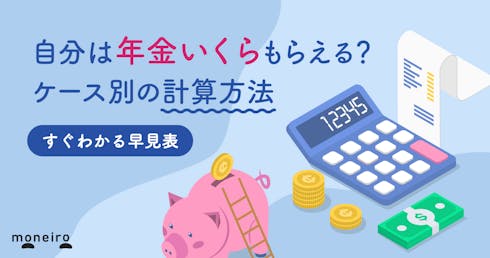
年金追納は一括と分割どっちが得?メリット・デメリットや節税効果を専門家が解説
≫年金だけで老後資金は足りる?あなたのケースで診断
国民年金の追納は、未納や猶予期間の保険料を後から支払う制度です。
しかし、一括払いと分割払いでは総額や加算金の有無が異なり、支払い方法次第で実質負担額に差が生じます。
さらに、追納時期によって将来の年金額や節税効果も変わるため、「どちらが得か」は人によって異なります。
本記事では、一括・分割それぞれのメリット・デメリット、追納した場合に増える年金額を専門的な視点で解説します。制度の基礎から損得比較まで理解し、後悔のない追納方法を選びましょう。
(参考:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構)
- 国民年金保険料の追納の一括払いのメリット・デメリットは「手続きが一度に済む」「一気に払うためまとまった資金が必要」
- 国民年金保険料の追納の分割払いのメリット・デメリットは「少額ずつ進められる」「3年以上前の分には加算が上乗せされる」
- 短期でまとめて支払えるなら、一括払いの方が得。一方、家計に無理なく進めたい場合は、早めに分割で開始するのが賢明
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
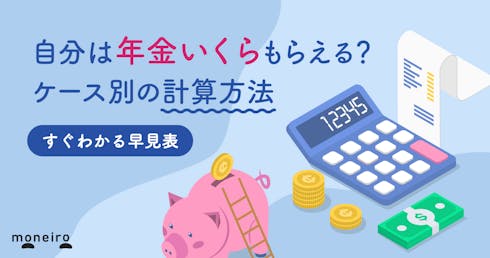

国民年金保険料の追納とは
追納とは、過去に免除・猶予・学生納付特例を受けた国民年金保険料を、後から納付して将来の年金額に反映させる制度です。
追納した保険料は社会保険料控除対象となり、節税効果も得られます。
追納できるケース
対象となるのは全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例など、国民年金保険料の納付が猶予または免除されていた期間です。
追納できるのは、これらが承認された月の前10年以内の期間に限られます。
免除制度と猶予制度の違い
免除制度は所得や事情により納付が免除される制度です。受給資格としては月単位で算入され、年金額にも一定の割合で反映されます(例:全額免除で0.5か月分など)。
一方、納付猶予制度は納付時期を後ろ倒しする措置のことです。受給資格には算入されますが、追納しない限り年金額には反映されません。
追納可能な期間と期限(10年ルール)
追納可能な期間は、承認を受けた翌年度から起算して前10年以内です。ただし、追納には順序があり、古い時期から順に納付する必要があります。
また、免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に加算金が上乗せされるため、早めに追納することが大切です。
なお、納付猶予や学生納付特例を利用している人の追納率は極めて低く、2024年時点で猶予利用者は7.0%、学生特例では8.9%にとどまっています。
一括払いと分割払いのメリット・デメリット
追納は一括払いか分割払い(1〜6ヶ月単位)か選択可能で、それぞれに特徴があります。
一括払いの場合
【メリット】
・手続きが一度で済む
・加算金が発生する前にまとめて支払えば、余計な負担を抑えられる
・社会保険料控除の対象として一気に節税可能
【デメリット】
・家計の負担が大きくなるため、一度に支払う資金が必要
分割払いの場合
【メリット】
・家計に負担をかけずに追納可能。少額ずつでも進められるのが安心
・追納分が都度社会保険料控除の対象となる
【デメリット】
・手続きに手間がかかる
・分割にすると支払いが長期化し、結果的に加算金が増える可能性があります。3年以上前の分には加算が上乗せされる
追納は一括と分割どっちが得?税金と手取りで徹底比較
一括払いは節税効果が高く、分割払いは家計負担の調整に優れています。
例えば40万円を一括払いで追納すると、所得税20%・住民税10%の計算で、約12万円の節税効果が期待できます。実質的な負担は、約28万円になります。
一括払いは、その年に支払った保険料の全額が「社会保険料控除」の対象となります。そのため、その年の所得税・住民税の課税所得が大きく減り、税金負担が軽減されます。
所得が高い人ほど、高い税率が適用される部分が減るため、節税効果が大きくなります。
一方、分割払いは、その年に支払った分だけがその年の社会保険料控除の対象となります。そのため、一括払いのような大きな節税効果は得られませんが、数年にわたって節税効果を分散させることができます。
所得が低い年が続く場合など、少しずつ節税したい場合に有効です。
ただし、分割払いで加算金がつく場合、追納額が増えるため、実質負担も増加します。特に古い分ほど加算金率は高く、10年前では約2%程度上乗せされます。
比較すると、短期でまとめて支払えるなら、一括払いの方が得ですが、家計に無理なく進めたい場合は、早めに分割で開始するのが賢明です。
追納で年金はいくら増える?費用対効果を徹底検証
日本年金機構によれば、全額免除の期間を1年間追納すると、老後の年金が年間で約1万円増加し、猶予や学生納付特例では年間約2万円増加します。
また、学生納付特例を2年間追納した場合、月額で3466円の増加、10年分で約41.6万円の増額となり、追納額40.2万円を上回り、費用対効果が高いことがわかります。
※令和5年度と令和6年度の2年間学生納付特例の承認を受けたと仮定し、老齢基礎年金(国民年金)の満額は月額6万9308円(令和7年度)で計算
≫年金だけで老後資金は足りる?あなたのケースでシミュレーション
60歳以降の年金増加策を徹底比較
追納以外にも、年金を増やす方法があります。
繰下げ受給で増える年金と注意点
受給開始を遅らせることで、増額された月額を得られます。具体的には、1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増、75歳で84%増となります。
ただし、遅らせるほど受給可能な期間が短くなるリスクも伴います。
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合の年金増加
60歳以降も厚生年金に加入していると、保険料納付と加入記録が増えることで年金額がさらに上乗せされます。
受給条件や働き方によっては支給開始年齢や調整が必要になります。
国民年金保険料の追納手続き
追納には所定の手続きが必要です。
申請方法と必要書類
「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所に提出します(窓口・郵送とも可)。その後、納付書が送付され、金融機関・郵便局・コンビニで納付可能です。
ただし、口座振替やクレジットカード払いは利用できません。
手続き時には、基礎年金番号通知書や本人確認書類(マイナンバーカードなど)が必要です。
納付期限や注意点
追納は古い分から順に行う必要があります。さらに、3年以上前の追納には加算金がつくため、可能な限り早く手続きを行うのが望ましいです。
まとめ
国民年金の追納は、将来の年金受給額を増やすための有効な手段です。一括払いと分割払いでは、支払う保険料の総額は変わりませんが、社会保険料控除による節税効果の現れ方が異なります。
分割払い…手元資金の負担を抑えたい場合に有効です
追納によって増える年金は、費用対効果で見ても、長生きするほど「お得」になります。一方、繰り下げ受給や60歳以降も厚生年金に加入して働くといった、他の年金を増やす方法も存在します。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身にとって最適な選択をすることが大切です。
≫年金だけで老後資金は足りる?あなたのケースでシミュレーション
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

老後の生活費はいくらかかる?一人暮らし・夫婦の平均は?データをもとに解説

60歳からの国民年金「任意加入」は得?損?加入すべき人の特徴と年金の仕組み
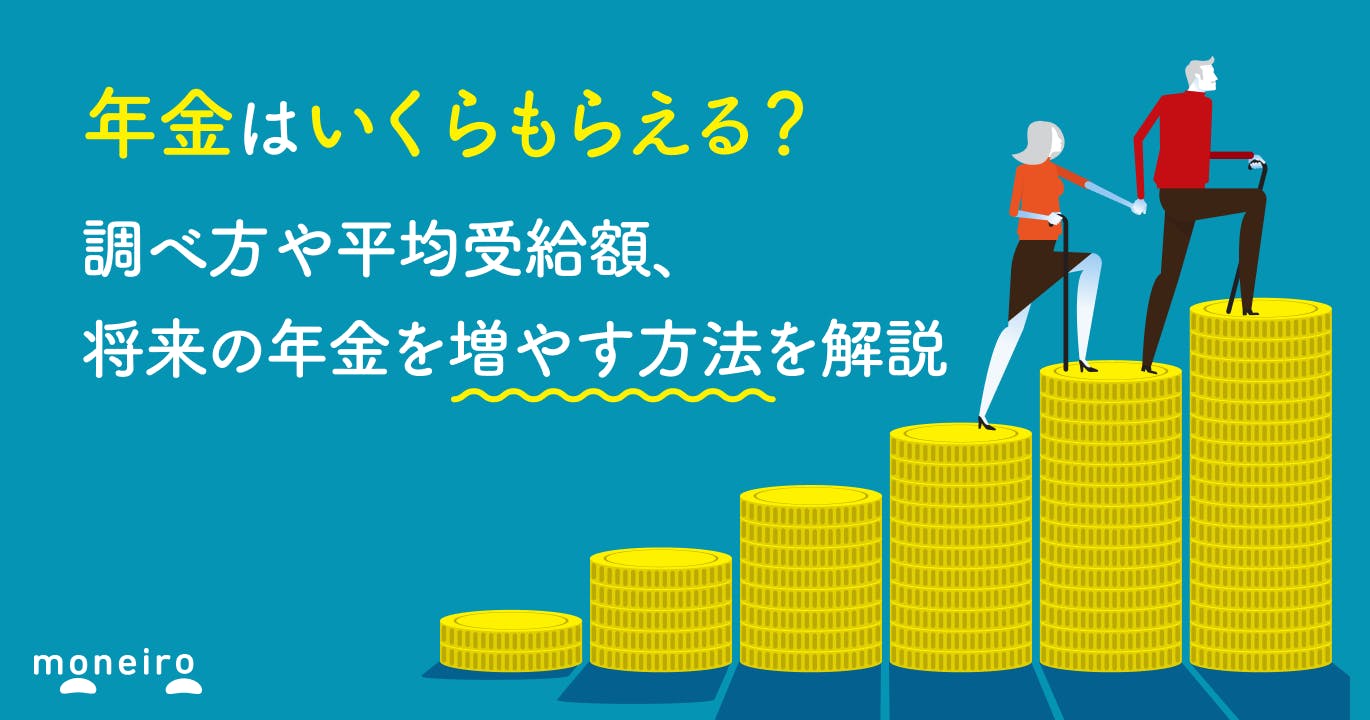
年金はいくらもらえる?調べ方や平均受給額、将来の年金を増やす方法を解説

年金から引かれるものとは?手取りが減る理由と少しでも減らすための対策を解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。