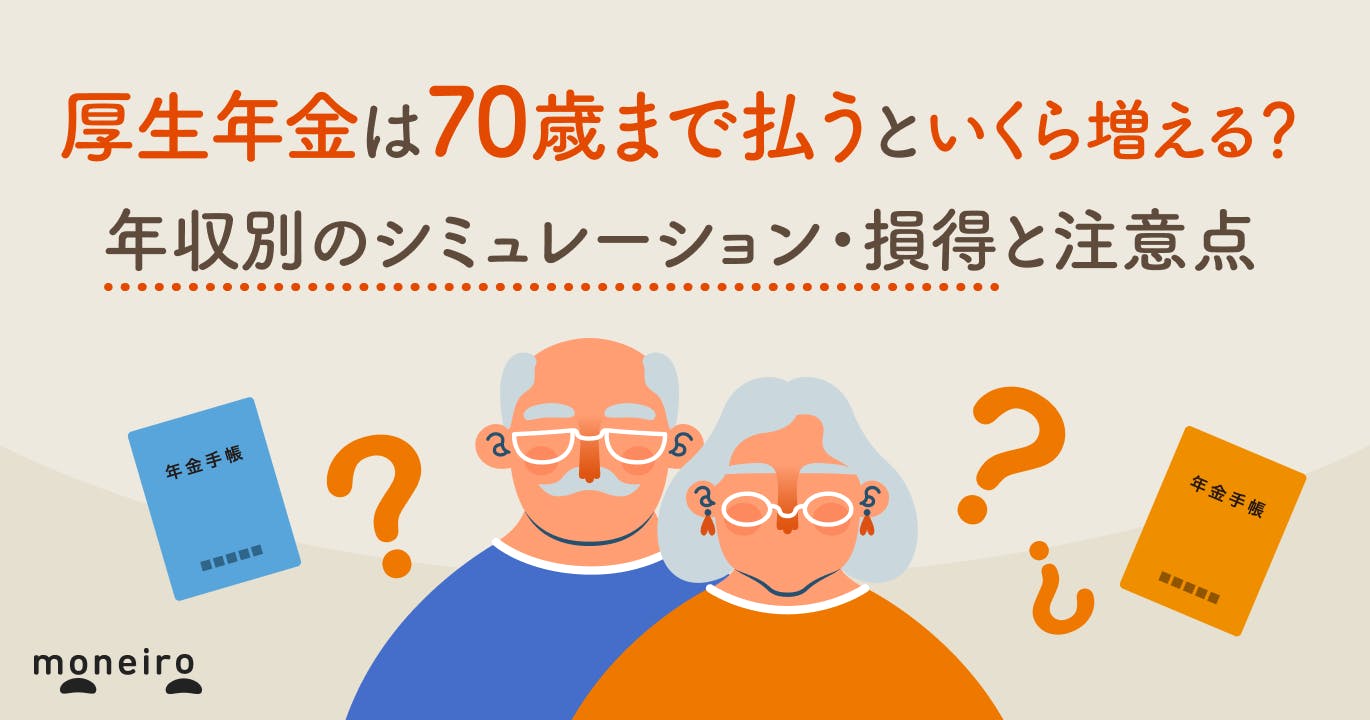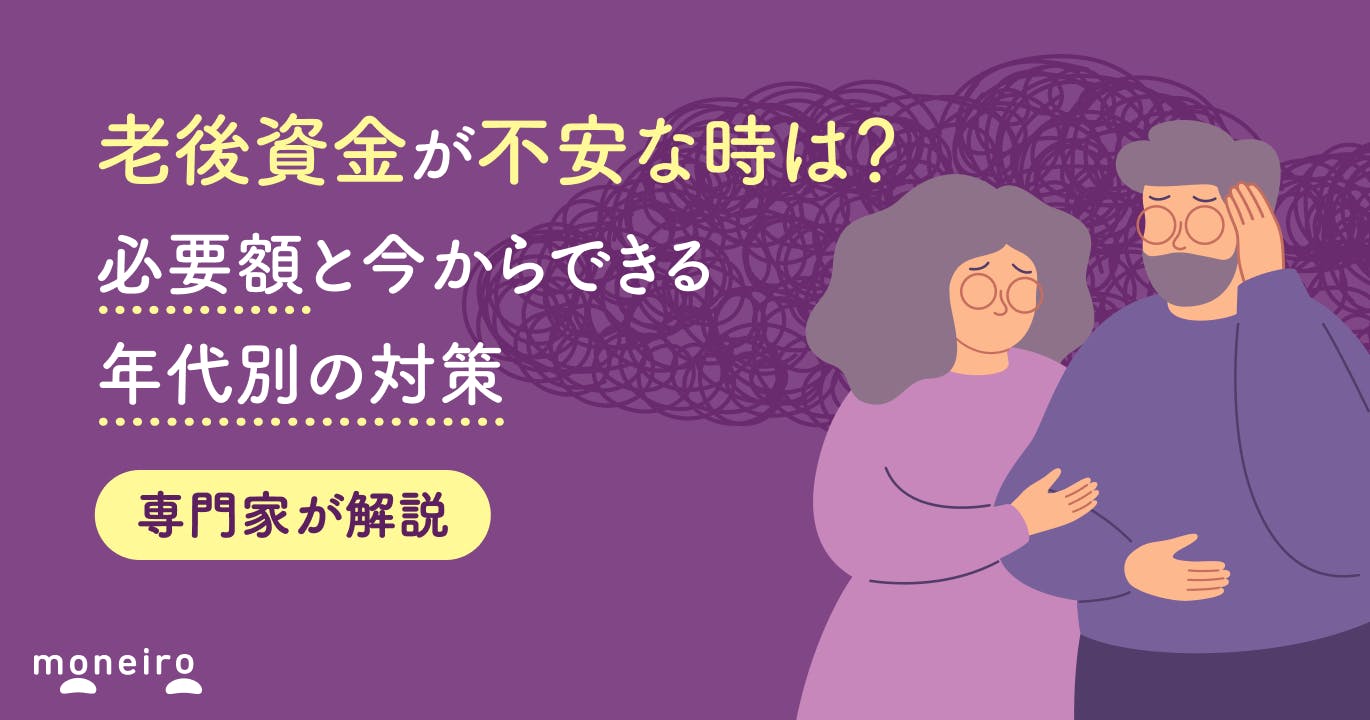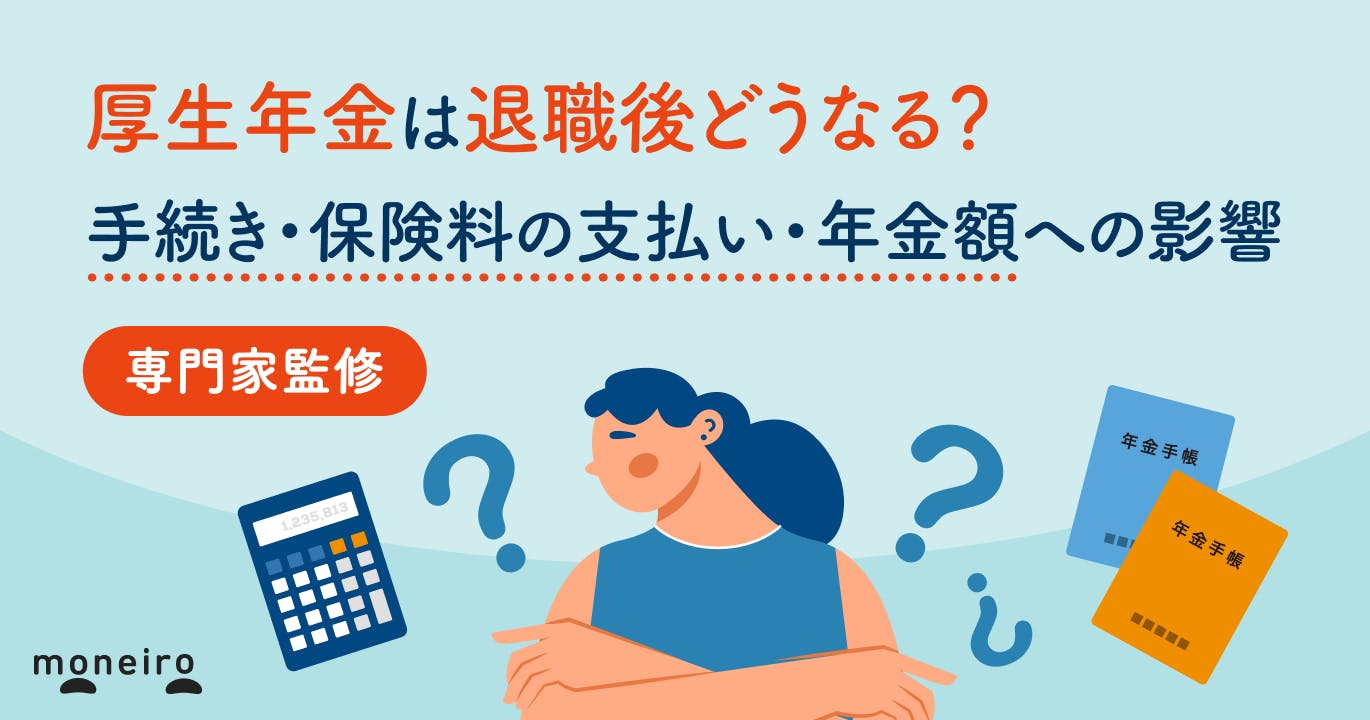
厚生年金は70歳まで払うといくら増える?年収別のシミュレーション・損得と注意点
≫年金だけで老後は安心?あなたの不足額をチェック
「70歳まで働くと年金はいくら増える?」と老後資金を準備する中で、将来もらえる年金について気になっている人も多いでしょう。また、定年延長や再雇用制度の広がりにより、こうした疑問を持つ人が増えています。
厚生年金は原則70歳まで加入でき、支払い期間が長いほど将来の年金額が増える仕組みです。
ただし、70歳まで払い続ければ“必ず得”というわけではありません。加入義務の範囲、在職老齢年金との関係、負担とリターンのバランスを正しく理解することが大切です。
本記事では、年収別の増額シミュレーションや損益分岐点、働き方別の注意点まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
- 70歳まで厚生年金を支払った場合の年金増額シミュレーション
- 70歳まで厚生年金を支払うメリットとデメリット
- 在職老齢年金や繰下げ受給との関係性
将来もらえる年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金は何歳まで加入できる?
厚生年金は、原則として70歳になるまで加入できます。厚生年金保険の適用事業所で働く70歳未満の人は加入が義務付けられています。
会社員や公務員として働いている間は、毎月の給与と賞与から厚生年金保険料が天引きされる形で納付が続きます。
70歳到達時に自動で資格喪失になる
厚生年金の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に自動的に喪失します。特別な手続きは不要です。これにより、70歳に到達した月以降は厚生年金保険料を納める必要がなくなります。
例えば、5月10日が70歳の誕生日の場合、その前日である5月9日に資格を喪失します。したがって、5月分の保険料から納付が不要となります。
ただし、70歳以降も同じ会社で働き続ける場合は、在職老齢年金制度による支給停止の有無(標準報酬月額など)を確認するために「70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
70歳以上、厚生年金保険料の負担はなくなりますが、在職老齢年金制度は継続して適用されます。
70歳以降は任意加入
会社に勤めている場合でも、70歳になると厚生年金保険への加入資格はなくなります。ただし、老齢年金を受け取るための必要な加入期間(10年)をまだ満たしていない人が、70歳を過ぎても働いている場合は、任意で厚生年金に加入することができます。
これを「高齢任意加入被保険者」といい、加入を希望する際は「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。
また、厚生年金保険の適用事業所以外で働いている70歳以上の人でも、次の条件を満たせば任意加入が認められる場合があります。
- 事業主が、厚生年金保険への加入に同意していること
- 厚生労働大臣の認可を受けていること
これらの要件を満たしたうえで、加入を希望する場合は「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。
70歳まで厚生年金を払うと、いくら年金が増える?
70歳まで厚生年金を払い続けると、将来受け取る老齢厚生年金額が増加します。増える金額は、加入期間中の平均年収と加入月数によって決まります。
年収が高いほど、また加入期間が長いほど、年金の増額幅は大きくなります。
厚生年金の計算式
将来受け取る老齢厚生年金の受給額は、主に「報酬比例部分」で構成されます。この報酬比例部分は、厚生年金への加入期間とその間の給与や賞与の金額に応じて計算されるため、加入期間が長く収入が高いほど年金額は増えます。
報酬比例部分の基本的な計算式は以下の通りです。
これは、賞与も計算の基礎に含まれるようになった2003年(平成15年)4月以降の加入期間に適用されます。
- 老齢厚生年金(年額) = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
ここでいう「平均標準報酬額」とは、加入期間中の毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の総額を、加入月数で割った平均額のことです。
上記の計算式により、長く働き続けるほど、また収入が高いほど、将来の年金が増える仕組みになっています。
年収別シミュレーション
65歳から70歳までの5年間(60ヶ月)、厚生年金に加入して働いた場合に年金がいくら増えるのか、年収別にシミュレーションしてみましょう。
計算を簡略化するため、賞与はないものと仮定します。
計算には、昭和21年4月2日以降生まれの方(2003年3月以前に厚生年金加入歴あり)に適用される従前額保障の計算式(平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 加入月数)を用いると、より実態に近い金額を算出できます。
例えば平均月収20万円で5年間働くと、70歳以降に受け取る年金額が毎年約6.9万円増えることになります。
この増額分は生涯にわたって続くため、長く生きるほどその恩恵は大きくなります。
60歳・65歳・70歳まで働いた場合
60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、将来の年金額を増やすことができます。働く期間が長くなるほど、その増額効果は大きくなります。
例えば、平均年収300万円(月収25万円)の方が、60歳以降も働き続けた場合の年金増額の目安は以下のようになります。
- 60歳から65歳まで(5年間)働いた場合:年金額が年額で約8.7万円増えます。
- 60歳から70歳まで(10年間)働いた場合:年金額が年額で約17.3万円増えます。
70歳まで10年間働き続けると、65歳で退職した場合に比べて、増える年金額は約2倍になります。
この増額分は生涯にわたって受け取れるため、仮に65歳から85歳まで年金を受給したとすれば、10年間働くことで累計で346万円(17.3万円×20年)も多く年金を受け取れる計算になります。
≫年金だけで老後は安心?あなたの不足額をシミュレーション
増える年金額と支払う保険料のバランス
70歳まで厚生年金に加入し続けることで年金額は増えますが、その間は保険料を支払い続ける必要があります。この「増える年金額」と「支払う保険料」のバランスを考えることが重要です。
厚生年金保険料率は現在18.3%で、これを会社と従業員で半分ずつ負担します。つまり、自己負担率は標準報酬月額(または標準賞与額)の9.15%です。
例えば、平均年収360万円(月収30万円)の人が65歳から70歳までの5年間働いた場合を考えてみましょう。
- 支払う保険料の総額(自己負担分):30万円 × 9.15% × 60ヶ月 = 約165万円
- 増える年金額(年額):30万円 × 5.769/1000 × 60ヶ月 = 約10.4万円
この場合、支払った保険料(約165万円)を増えた年金額(年約10.4万円)で回収するには、約15.9年(165万円 ÷ 10.4万円)かかります。
つまり、70歳から年金を受け取り始めた場合、86歳頃まで長生きすれば、支払った保険料以上のリターンを得られる計算になります。
これはあくまで単純計算ですが、何歳まで生きれば元が取れるのかという「損益分岐点」を意識することで、ご自身の健康状態や家族構成と照らし合わせ、より納得感のある判断ができるでしょう。
将来もらえる年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
70歳まで払うメリットと注意点
70歳まで厚生年金を払い続けることには、定年後も給与収入を得たうえに年金額が増えるという大きなメリットがある一方、保険料負担が続くなどのデメリットも存在します。
自身の状況に合わせて、両方の側面を理解し、総合的に判断することが重要です。
メリット①将来の年金受給額が着実に増える
70歳まで厚生年金に加入し続ける最大のメリットは、将来受け取る老齢厚生年金額が着実に増えることです。厚生年金の受給額は、加入期間と現役時代の収入に基づいて計算されるため、長く働くほど年金額は増加します。
例えば、年収360万円の人が60歳から70歳までの10年間働き続けると、年金額は年額で約21万円増える計算になります。この増額分は生涯にわたって支給されるため、長生きするほどその恩恵は大きくなります。
仮に90歳まで年金を受け取るとすれば、累計で420万円も多く受け取れることになり、老後の生活に大きな安心感をもたらすでしょう。
また、働くことで収入を得られるため、年金受給開始までの生活費を賄える点も大きなメリットです。
メリット②繰下げ受給と併用でさらに増額も可能
70歳まで働き続けることで安定した収入が確保できるため、年金の受給開始を65歳から遅らせる「繰下げ受給」を選択しやすくなるというメリットがあります。
繰下げ受給を利用すると、将来受け取る年金額を大幅に増やすことが可能です。
年金の受給開始は、1ヶ月遅らせるごとに受給額が0.7%ずつ増加します。
例えば、70歳まで5年間繰り下げると年金額は42%、75歳まで10年間繰り下げると最大で84%も増額されます。
仮に65歳時点で月15万円の年金を受け取れる人が70歳まで繰り下げた場合、月々の受給額は約21.3万円に増加します。
70歳まで働くことで得られる収入で生活を賄いながら、将来の年金額を大きく増やせるこの選択肢は、老後の資金計画において有効な手段と言えるでしょう。
注意点①社会保険料の負担が重くなる
70歳まで厚生年金に加入して働くことのデメリットとして、社会保険料の負担が続く点が挙げられます。厚生年金に加入している間は、厚生年金保険料を支払い続けなければなりません。
厚生年金保険料率は18.3%で、これを会社と従業員で折半するため、自己負担率は9.15%です。例えば、月収(標準報酬月額)が30万円の場合、毎月2万7450円の厚生年金保険料が給与から天引きされます。
将来の年金額が増えるとはいえ、現役で働いている間の手取り収入がその分減少することは念頭に置いておく必要があります。
家計状況と照らし合わせ、保険料負担が重すぎないか検討することが大切です。
注意点②在職老齢年金で一部カットされる可能性
60歳以降に厚生年金に加入しながら年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という制度に注意が必要です。
これは、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の報酬比例部分(基本月額)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
2025年度の基準額は51万円です。「給与+年金」の月額合計が51万円を超えると、超えた額の半分が年金からカットされます。
例えば、老齢厚生年金(報酬比例部分)が月12万円、給与が月45万円の場合、合計は57万円となり、基準額を6万円超えます。この場合、超過額の半分である3万円が年金から引かれ、実際に受け取れる老齢厚生年金額は9万円になってしまいます。
せっかく年金を受け取れる年齢になっても、収入によっては満額受け取れない可能性がある点は、大きなデメリットと言えるでしょう。
ただし、この基準額は2026年4月以降に引き上げられる予定であり、制度の動向を注視する必要があります。
「70歳まで払う」と「70歳からもらう」は別の話
70歳までの働き方を考える上で、「70歳まで厚生年金保険料を払う(加入延長)」ことと、「年金の受け取り開始を70歳まで遅らせる(繰下げ受給)」ことは、別の制度であることを理解しておく必要があります。
厚生年金の「加入延長」と「繰下げ受給」の違い
厚生年金で老後の受給額を増やす方法として、「加入延長」と「繰下げ受給」がありますが、この二つは仕組みが異なります。それぞれの違いを正しく理解し、自分に合った方法を選択することが重要です。
65歳以降に加入延長して増えた年金額は、繰下げ受給による増額(月0.7%アップ)の対象にはなりません。繰下げで増額されるのは、あくまで65歳になるまでの加入実績で計算された年金額のみです。
つまり、「長く払って老齢厚生年金の基本額を増やす」のが加入延長、「受け取りを我慢して受給額を増額する」のが繰下げ受給と覚えておくと良いでしょう。
繰下げ受給を70歳まで遅らせるといくら増える?
年金の受給開始を65歳から遅らせる「繰下げ受給」を利用すると、年金額を大幅に増やすことができます。増額率は1ヶ月あたり0.7%で、この率は生涯変わりません。
もし70歳まで、5年間(60ヶ月)繰り下げた場合の増額率は以下のようになります。
- 0.7% × 60ヶ月 = 42%
これは、65歳時点で受け取れるはずだった年金額が1.42倍になることを意味します。
例えば、65歳時点での年金額が月15万円(年180万円)の場合、70歳まで繰り下げると受給額は以下のようになります。
- 月額: 15万円 × 1.42 = 21.3万円
- 年額: 180万円 × 1.42 = 255.6万円
月額で6.3万円、年額で75.6万円も増える計算です。70歳まで働くなどして収入があれば、この制度を活用しやすく、老後の生活に大きなゆとりをもたらすことができます。
なお、繰下げは最大75歳まで可能で、その場合の増額率は84%になります。
70歳まで働くのは得?判断のポイント
70歳まで働くことが一概に「得」とは言えません。
金銭的な損益分岐点だけでなく、自身の健康状態や働きがい、退職金制度など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断することが大切です。
他の資産形成手段と比較検討することも有効です。
健康・勤務条件・退職金とのバランスを考える
70歳まで働くかどうかは、金銭的な損得勘定だけで決めるべきではありません。給与収入やご自身の健康状態、仕事に対するやりがい、勤務条件といった要素も総合的に考慮することが大切です。
働くこと自体が健康増進につながり、社会とのつながりを保つことで生きがいを感じられるという側面もあります。健康寿命が延びれば、将来の医療費や介護費の削減にもつながる可能性があります。
また、会社の退職金制度も重要な判断材料です。勤務年数に応じて退職金がどのように変動するのか、規定を確認しておきましょう。
無理のない範囲で楽しみながら働ける環境であるか、そしてそれがライフプラン全体にとってプラスになるかを、多角的に見極めることが重要です。
繰下げやiDeCoなど他の老後対策と比較する
70歳まで厚生年金に加入して働くことは、老後資金を増やす有効な手段の一つですが、それが唯一の選択肢ではありません。他の制度と比較検討し、ご自身に最も合った方法を見つけることが重要です。
比較すべき主な選択肢には以下のようなものがあります。
- 年金の繰下げ受給:年金の受け取りを70歳や75歳まで遅らせる方法です。保険料の負担なく、受給額を最大84%まで増やせます
- iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で掛金を拠出し、運用して老後資金を作る私的年金制度です。掛金が全額所得控除になるなど、税制上のメリットが大きいのが特徴です
- NISA(少額投資非課税制度):投資で得た利益が非課税になる制度です。いつでも引き出しが可能で、柔軟な資産形成ができます
70歳まで働くことによる年金増額の効果と、これらの制度を活用した場合の効果をシミュレーションし、ライフプランやリスク許容度に合った最適な組み合わせを見つけましょう。
まとめ
70歳まで働いて厚生年金に加入することで将来の年金額を増やせる一方、保険料負担や在職老齢年金のリスクも存在します。
金銭的な損得だけでなく、ご自身の健康状態やライフプランを総合的に考慮し、繰下げ受給やiDeCo、NISAといった他の選択肢とも比較しながら、最適な老後設計を立てることが大切です。
まずは「ねんきんネット」などを活用してご自身の年金見込額を把握し、具体的な資金計画を始めることを推奨します。
≫年金だけで老後は暮らせる?結果がすぐわかる無料診断はこちら
将来もらえる年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
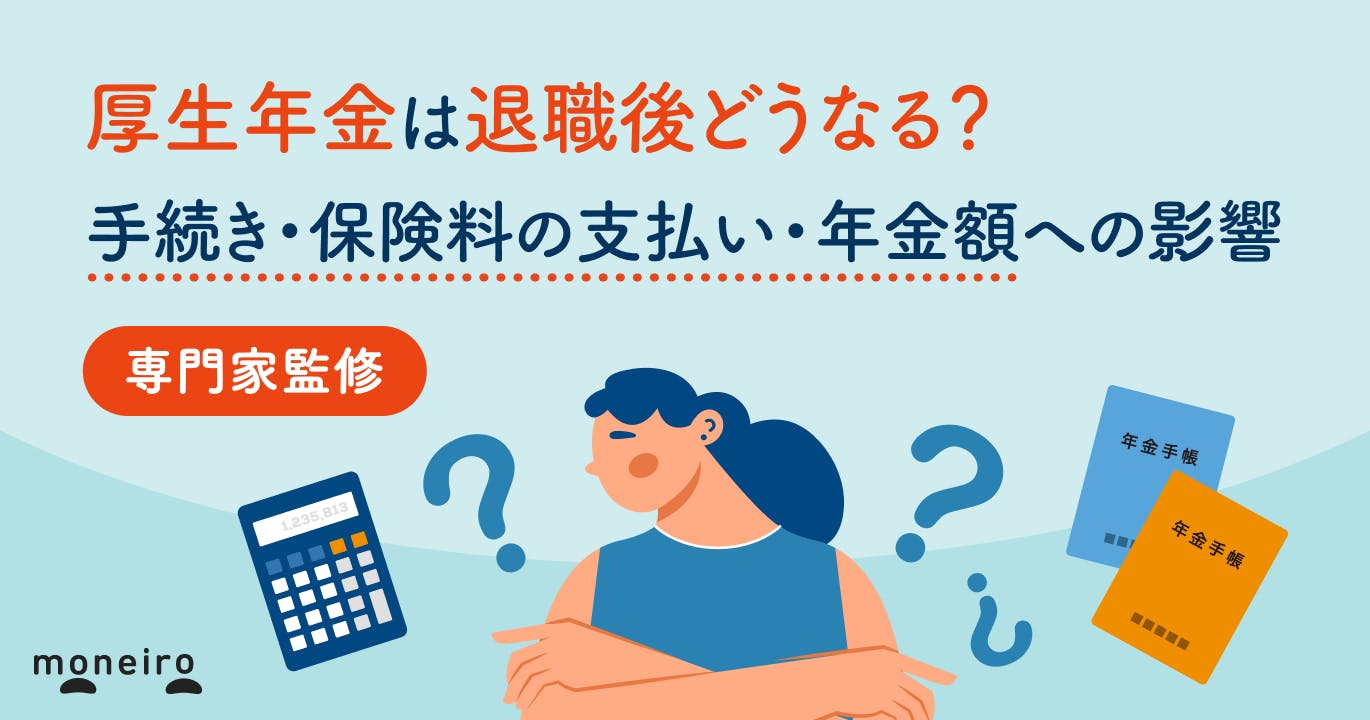

60歳以上も厚生年金に加入し続けるデメリットは?損しない働き方と制度を解説

年金から引かれるものとは?手取りが減る理由と少しでも減らすための対策を解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。