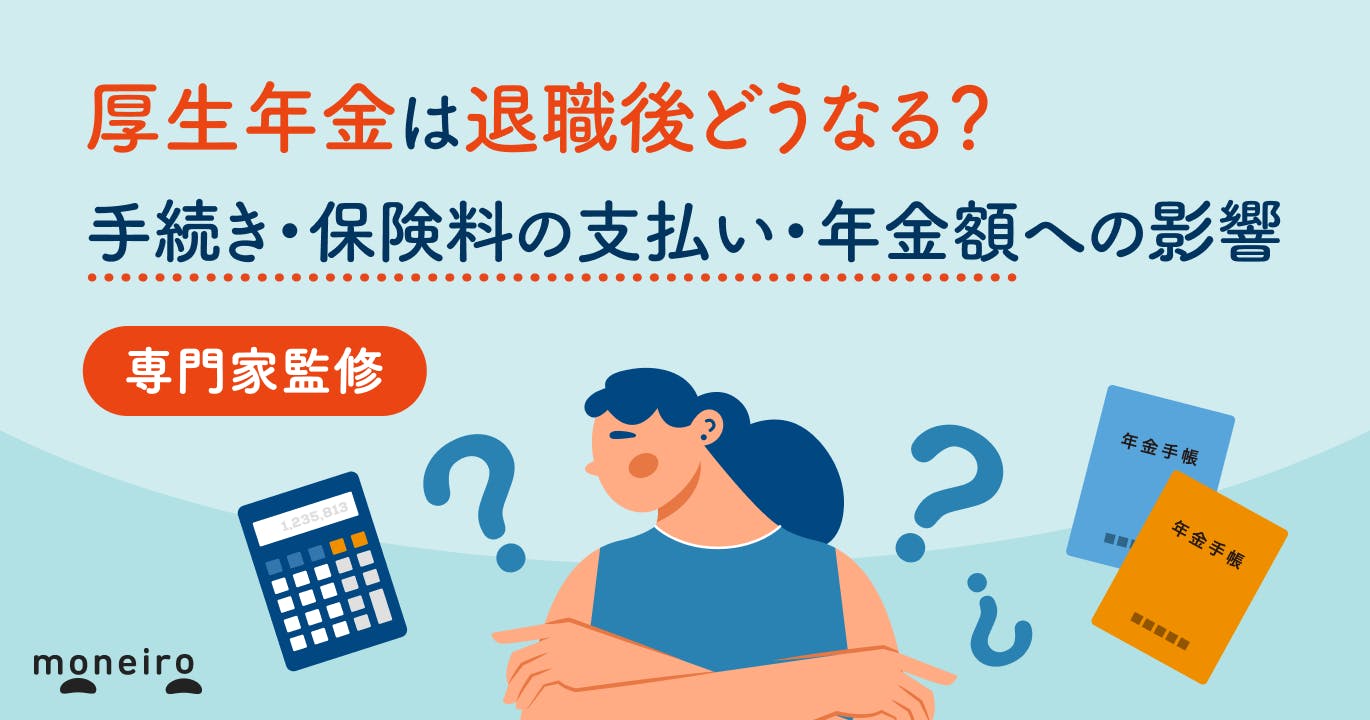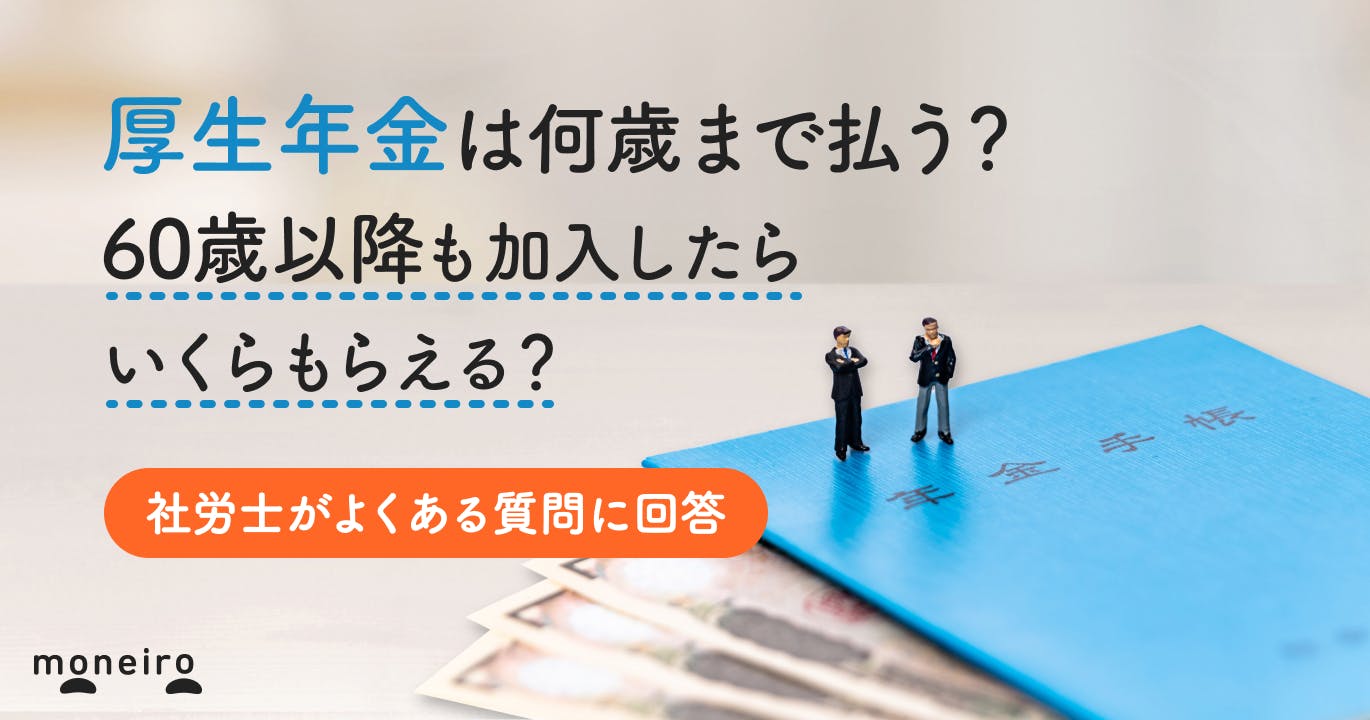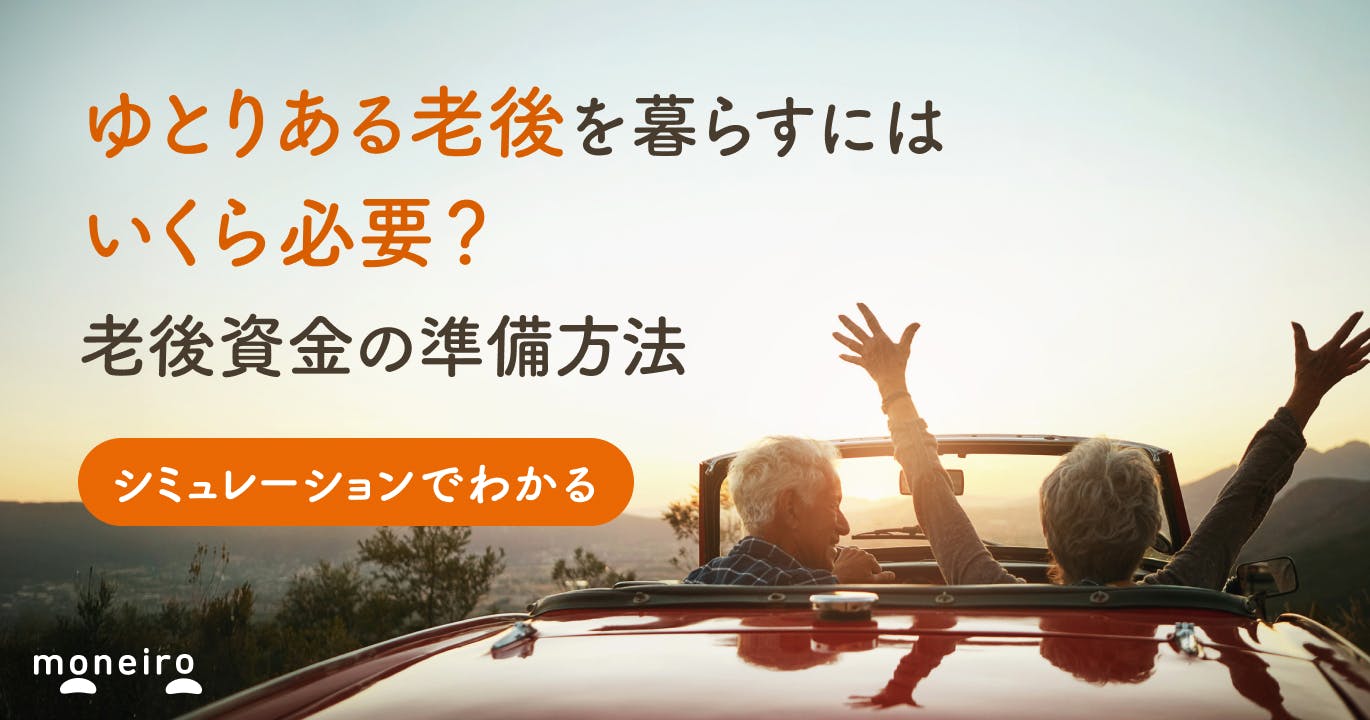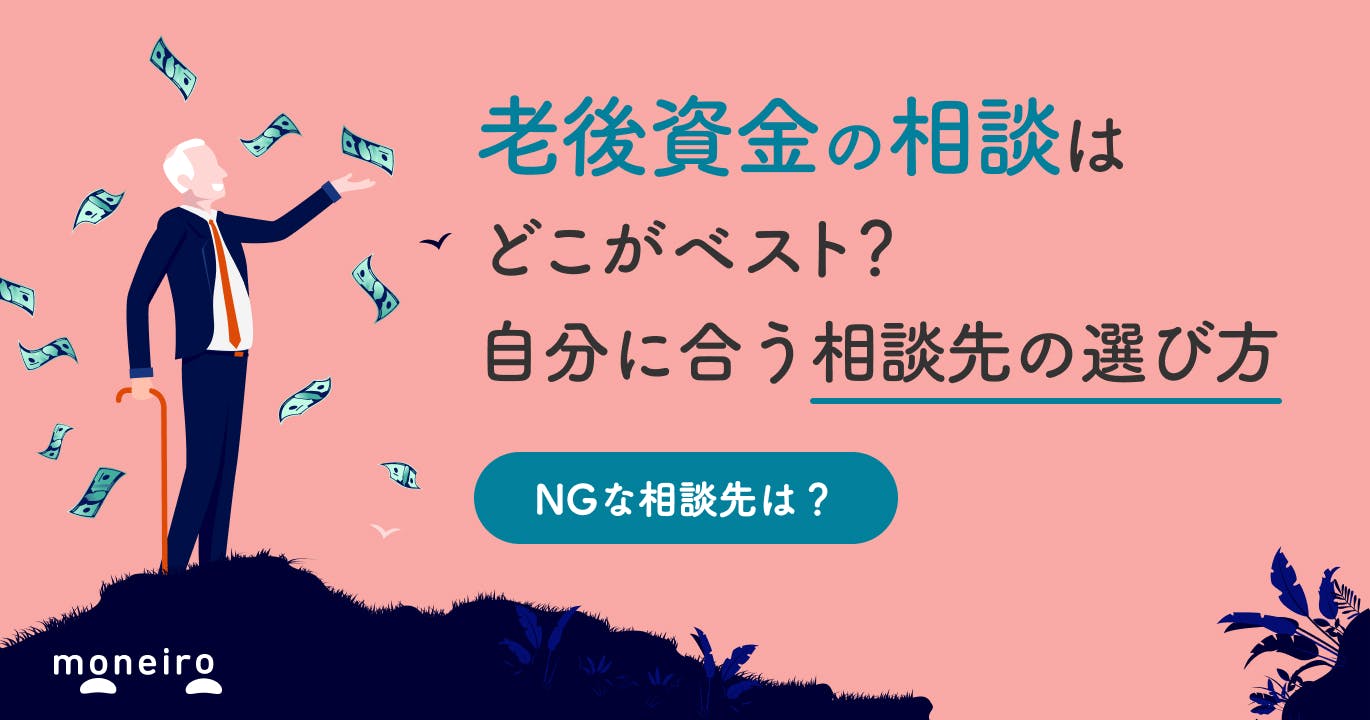厚生年金は退職後どうなる?手続き・保険料の支払い・年金額への影響をわかりやすく解説
»年金だけでは老後は足りない?無料診断はこちら
会社を退職すると、厚生年金の加入資格はなくなります。その後は国民年金への切り替えや配偶者の扶養に入るなど、状況に応じて対応が必要です。
しかし「切り替えを忘れるとどうなる?」「将来の年金額は減るの?」と不安を感じる人も多いでしょう。
本記事では、退職後に厚生年金がどう扱われるのかをわかりやすく解説します。
国民年金への切り替え手続き、扶養や任意加入の選択肢、将来の年金額への影響、さらに定年退職後の受け取り方まで網羅。仕組みを正しく理解し、退職後の生活設計に役立てましょう。
- 退職後の年金加入の3つの選択肢
- 退職が将来の年金額に与える影響
- 具体的な手続き方法と期限
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
退職したら厚生年金はどうなる?基本の仕組み
会社を退職すると、厚生年金の加入資格は失われます。そのため、国民年金への切り替えや、配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)に入るなどの手続きが必要です。
手続きを怠ると将来の年金受給に影響が出る可能性があるため、基本の仕組みを正しく理解しておきましょう。
退職と同時に厚生年金の資格を喪失
会社員や公務員が加入する厚生年金は、勤務先を通じて加入する制度です。そのため、会社を退職すると、厚生年金の被保険者資格を失います。
資格を失うタイミングは「退職日の翌日」と決まっています。例えば、3月31日に退職した場合、4月1日が資格喪失日となります。資格喪失日をもって、厚生年金の加入期間は一旦終了します。
退職後は国民年金や扶養への切り替えが必要
厚生年金の資格を失った後は、自動的に他の年金制度に移るわけではありません。自身の状況に合わせて、国民年金への切り替えや配偶者の扶養に入る手続きを自ら行う必要があります。
日本の公的年金制度は、働き方などによって以下の3種類に分かれています。
- 第1号被保険者: 自営業者、フリーランス、学生、無職の方など
- 第2号被保険者: 会社員や公務員など厚生年金に加入している人
- 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている配偶者
退職後は、第2号被保険者から第1号または第3号被保険者へ切り替えることになります。どの区分に当てはまるかによって、手続き方法や保険料の負担が変わります。
切り替えを忘れた場合のリスク(未加入)
退職後の年金切り替え手続きを忘れてしまうと、国民年金の「未加入期間」が発生してしまいます。この未加入期間は、将来受け取る年金額に直接影響します。
未加入期間があると、その期間分、将来の老齢基礎年金が減額されます。
さらに、未加入期間が長引くと、老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間(原則10年)を満たせなくなる可能性もあります。
また、病気や怪我で障害が残った場合に支給される障害年金や、万が一の際に遺族に支給される遺族年金が受け取れなくなるリスクもあります。
退職後の年金加入は3つの選択肢
退職後の年金の加入方法は、主に3つの選択肢があります。自営業者などになる場合は「国民年金」、配偶者の扶養に入る場合は「第3号被保険者」、そして60歳以降であれば「国民年金の任意加入」という選択も可能です。
自身の状況に合った方法を選びましょう。
国民年金に加入する
退職後に自営業を始める人、フリーランスとして活動する人、または次の就職先が決まるまで期間が空く人は、国民年金の「第1号被保険者」として加入手続きを行う必要があります。
これは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられている国民年金の基本的な形です。
会社員時代は厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれていましたが、退職後は自身で国民年金保険料を納付することになります。
手続きは、住んでいる市区町村役場の窓口で行います。
配偶者の扶養に入る(第3号被保険者)
退職後、配偶者が会社員や公務員として厚生年金に加入している場合、一定の条件を満たせばその扶養に入り「第3号被保険者」となることができます。
第3号被保険者になると保険料の自己負担はなく、その保険料は厚生年金加入者全体で負担します。そのため、自身で保険料を払わずに将来の老齢基礎年金を受け取る権利を得られる仕組みです。手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。
60歳以降は任意加入も可能
60歳で定年退職を迎えると、国民年金の強制加入期間は終了します。
しかし、老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たしていない場合や、納付期間が40年に届かず満額を受け取れない場合には、65歳まで「任意加入制度」を利用して国民年金に加入することができます。
これにより、受給資格を満たしたり将来の年金額を増やしたりすることが可能です。
さらに、65歳時点で老齢年金の受給資格を得られていない人は任意加入の特例(高齢任意加入)によって、70歳まで国民年金に加入できます。老後の資金計画に応じて、これらの制度を上手に活用することが重要です。
退職が将来の年金額に与える影響
退職によって厚生年金の加入期間が中断または終了することは、将来受け取る年金額に直接的な影響を及ぼします。
加入期間が短くなれば年金額は減少し、未加入期間が生じると受給資格自体を失うリスクもあるため、注意が必要です。
加入期間が短くなると年金額は減る
将来受け取る老齢厚生年金の額は、主に「加入期間の長さ」と「加入期間中の平均収入(標準報酬月額・標準賞与額)」に基づいて計算されます。
加入期間の長さと平均収入によって算出されるのが老齢厚生年金の「報酬比例部分」です。
具体的には、加入月数が1ヶ月短くなるだけでも、その分だけ将来の年金額は減少します。退職して厚生年金に加入しない期間が長くなるほど、生涯にわたって受け取る年金額が少なくなることを理解しておく必要があります。
特に、早期退職を検討している場合は、その後のライフプランと合わせて年金額への影響を慎重にシミュレーションすることが重要です。
ねんきん定期便・ねんきんネットで確認する方法
年金記録や将来受け取れる年金の見込額は、定期的に確認することが大切です。主な確認方法として「ねんきん定期便」と「ねんきんネット」があります。
「ねんきん定期便」は、毎年誕生月に日本年金機構から郵送される書類で、これまでの加入実績や年金見込額が記載されています。
一方、「ねんきんネット」は、通じて24時間いつでも年金情報を確認できる日本年金機構のインターネットサービスです。
より詳細な加入履歴の確認や、将来の働き方を変えた場合の年金額シミュレーションも可能です。退職を機に、これらのツールを活用して現状を把握し、将来設計に役立てましょう。
未加入期間があると受給資格を失う可能性も
老齢年金を受け取るには、保険料を納めた期間や免除された期間を合計した「受給資格期間」が原則10年以上必要です。
退職後に国民年金への切り替え手続きを行わず、年金制度に加入しない「未加入期間」が生じると、この期間は受給資格に算入されません。
未加入期間が長引いて受給資格期間が10年に満たない場合、たとえ厚生年金を長年払っていても老齢基礎年金も老齢厚生年金も受け取れなくなる重大なリスクがあります。
将来の受給権を失わないためにも、退職後の国民年金手続きは必ず行うことが重要です。
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
退職後に必要な手続き
退職後は、速やかに年金の切り替え手続きを行う必要があります。手続きは住所地の役所で行い、期限は退職の翌日から14日以内です。特に転職までの空白期間がある場合は、保険料の支払いについて注意が必要です。
資格喪失証明書を使った国民年金切り替え
退職後に国民年金へ切り替える際には、退職した会社から発行される「健康保険資格喪失証明書」などの退職日を証明する書類が必要です。
この証明書は、あなたが会社の厚生年金・健康保険の資格を失ったことを公的に証明するものです。書類を住んでいる市区町村役場の窓口に持参することで、スムーズに国民年金(第1号被保険者)への加入手続きを進めることができます。
会社によっては退職後、自動的に郵送してくれる場合もありますが、もし手元に届かない場合は、速やかに会社の担当部署に発行を依頼しましょう。
離職票や退職証明書でも代用できる場合があります。
役所での手続き方法と期限
国民年金への切り替え手続きは、原則として退職日の翌日から14日以内に、年金事務所または自身が住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で行います。
手続きには、以下のものを持参するのが一般的です。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職日が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書、離職票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
また、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから電子申請が可能です。役所に行く時間がない場合は、電子申請をしてみるのも良いでしょう。
いずれにせよ、期限を過ぎると年金の未加入期間が発生してしまうため、速やかな手続きが肝心です。
転職までの空白期間がある場合の注意点
転職先が決まっていても、退職日から入社日まで1日でも空白期間がある場合は、原則として国民年金への加入手続きが必要です。
年金保険料は日割りではなく月単位で計算されるため、資格を失った月と再取得した月が異なる場合に、その間の月の国民年金保険料を納付する義務が生じます。
例えば、9月15日に退職し、10月15日に入社する場合を考えます。厚生年金の資格を失う日は9月16日、再取得日は10月15日です。この場合、9月は国民年金に加入し、9月分の保険料を納める必要があります。
一方で、9月15日に退職し、同じ月の9月26日に入社した場合は、資格を失う日と再取得日が同月のため、国民年金保険料の支払いは発生しません。これを「同月得喪(どうげつとくそう)」と呼びます。
ただし、この場合でも役所での手続き自体は原則必要となります。
定年退職後の厚生年金の受け取り方
定年退職後に受け取る年金は、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金から支給される「老齢厚生年金」が基本です。
受給開始時期を調整したり、働きながら年金を受け取ることも可能で、ライフプランに合わせた選択が大切です。
老齢厚生年金+老齢基礎年金が基本
日本の公的年金制度は、2階建て構造になっています。1階部分が、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金から支給される「老齢基礎年金」です。そして、会社員や公務員が加入する厚生年金は、この基礎年金に上乗せされる2階部分にあたり、「老齢厚生年金」として支給されます。
したがって、厚生年金に加入歴のある場合は、原則として65歳から、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることになります。
これにより、国民年金のみに加入していた人よりも、手厚い保障が受けられる仕組みになっています。
繰上げ・繰下げ受給のメリット・デメリット
老齢年金の受給開始は原則65歳ですが、本人の希望により受給開始時期を早めたり、遅らせたりすることができます。
繰上げ受給は60歳から64歳の間に受給を開始する方法です。早くから年金を受け取れるメリットがありますが、1ヶ月早めるごとに年金額が0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)減額され、その減額率は生涯続きます。
繰下げ受給は66歳から75歳の間に受給を開始する方法です。受給開始を遅らせることで、1ヶ月あたり0.7%年金額が増額され、その増額率は生涯続きます。
75歳まで繰り下げると、最大で84%も年金額を増やすことが可能です。
自身の健康状態やライフプランに合わせて慎重に選択しましょう。
まとめ
退職すると厚生年金の資格を失うため、国民年金への切り替えや配偶者の扶養に入る手続きが14日以内に必要です。
手続きを怠ると未加入期間となり、将来の年金額が減るだけでなく、受給資格を失うリスクもあります。
退職は、ご自身の年金記録を確認し、老後のライフプランを見直す良い機会です。本記事を参考に、必要な手続きを漏れなく行い、安心して新しい生活をスタートさせましょう。
»年金以外でいくら必要?将来資金を無料でシミュレーション
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。