
50代からでもFIREは可能?必要金額・年金・現実的な資金計画を専門家が解説
»FIREするにはいくら必要?無料診断を今すぐ試す
「FIRE(経済的自立と早期リタイア)」という言葉を耳にしても、「もう50代では遅いのでは?」と感じる人は多いでしょう。
しかし、FIREは20〜30代の特権ではありません。老後資金とFIREを一体で考えれば、50代からでも実現可能です。
本記事では、FIREに必要な金額の目安に加え、50代からの現実的なアプローチとして「年金を組み合わせた部分FIRE」「退職金・運用の活用法」などを具体的に解説します。“働き方を選べる老後”を目指すための最短ルートを、専門家の視点でわかりやすく紹介します。
- 50代がFIREを考える上で大切な3つの支出
- 年金や退職金を考えたFIRE必要額の計算方法
- 今から始められる資産作りの具体的なステップ
FIREの資金がいくら必要なのか気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる

50代からFIREを目指すのは遅い?現実的な可能性
50代からのFIREは決して遅くありません。むしろ、これまでのキャリアで築いた資産や経験、そして将来の見通しの立てやすさから、とても現実的な選択肢と言えます。
大切なのは、20代や30代とは違うアプローチで計画を立てることです。
FIREの本来の目的は「早期リタイア」ではなく「選べる働き方」
FIREは「Financial Independence, Retire Early」の略で、「お金の自立と早期退職」と訳されます。しかし、その本質は単に仕事から完全に引退することだけを指すのではありません。
お金の基盤を築くことで、収入のためだけに働くという制約から解放され、自らの意思で働き方や生き方を選択できる自由を手に入れることが、FIREの真の目的です。
実際にFIREを達成した人の中には、完全に仕事をやめるのではなく、より情熱を注げる分野で仕事を続けたり、パートタイムで社会との関わりを維持したりする人も少なくありません。
つまり、FIREとは「仕事を完全にやめる」ことではなく、「仕事をするかしないか、どんな仕事をするかを自分で選べる状態」を目指すライフスタイルなのです。
50代でもFIREを目指す人が増えている背景
近年、50代でFIREを目指す人々が増えています。この背景には、いくつかの社会的・個人的な要因が考えられます。
一つは、働き方の価値観の多様化です。終身雇用が当たり前ではなくなり、定年まで一つの会社で働き続ける以外の選択肢を模索する人が増えました。
特に50代は、子育てが一段落し、自身のキャリアや人生の後半戦について深く考える時期と重なります。
また、インターネットやSNSの普及も大きな要因です。多くのブロガーやインフルエンサーが自身のFIRE達成までの道のりを発信しており、それが刺激となって「自分にもできるかもしれない」と考えるきっかけになっています。
40代や50代でまとまった資産を築き、仕事中心の生活から、より自由な時間を重視するライフスタイルへ移行する事例が広く知られるようになりました。
50代FIREの最大の強みは「年金と退職金の見通しが立つこと」
50代からFIREを目指す最大の強みは、老後資金の柱となる公的年金や退職金の受給額が、かなり正確に見通せる点にあります。
若い世代が将来の年金制度に不安を抱えるのとは対照的に、50代はこれまでの加入実績に基づいた具体的な金額を把握しやすいのが特徴です。FIRE計画を立てる上で、将来受け取れる年金や退職金は、準備すべき自己資金額を算出するための大切な要素です。
これらの収入を事前に計算に含めることで、FIRE達成までに必要な資産額を現実的な範囲に引き下げることが可能になります。
例えば、完全にリタイアする期間を「年金受給が始まる65歳まで」と区切り、その間の生活費だけを自己資金で賄う計画を立てることができます。
65歳以降は年金収入を生活費に充当できるため、生涯にわたって全ての生活費を資産運用だけでカバーするよりも、目標達成のハードルは格段に低くなります。
50代がFIREを考える前に整理すべき3つの支出
50代からFIREを目指すには、まず現状の支出を正確に把握し、リタイア後の生活費を現実的に見積もることが不可欠です。
特に、ライフステージの変化に伴い増減する支出項目を洗い出し、長期的な視点で資金計画に盛り込む必要があります。
老後の生活費(月25〜30万円前後)を基準に試算
FIRE後の生活費を見積もる際、一つの目安となるのが一般的な高齢者世帯の平均支出額です。総務省の「〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要」の調査内容によると、世帯主が65歳以上の無職世帯(2人以上)の消費支出は25万6521円(約26万円)です。これを年間に換算すると312万円になります。
もちろん、これはあくまで平均的な数値であり、個々のライフスタイルによって大きく異なります。例えば、趣味や旅行にもっと費用をかけたい場合は、より多くの資金が必要になります。一方で、現在の支出が月20万円程度であれば、それを基準に計画を立てることも可能です。
まずは現在の支出を洗い出し、「どの程度の生活水準を維持したいか」を具体的にイメージすることが、現実的なFIRE計画の第一歩となります。
住宅ローン・教育費が残っている場合の影響
50代でFIREを検討する際、大きな障害となりうるのが住宅ローンや子どもの教育費といった大きな固定支出です。これらの支払いが残っている場合、FIRE後のキャッシュフローに大きな影響を与えるため、計画段階で必ず整理しておく必要があります。
住宅ローンが残っている場合は、退職金などで繰り上げ返済を検討するのも一つの手です。リタイア後の無収入期間にローンの返済が続くと、精神的にも経済的にも大きな負担となります。
また、子どもの大学進学などが控えている場合、教育費のピークがFIREのタイミングと重なる可能性があります。必要な教育資金を確保した上で、FIRE計画を立てることが重要です。
これらの大きな支出の目処が立っていない段階でのFIREは、計画そのものを見直す必要があるかもしれません。まずは家計全体の支出を見直し、これらの大きな固定費をどう扱うかを明確にしましょう。
医療・介護など“50代以降に増える支出”も見込む
FIRE計画を立てる際、現在の生活費だけでなく、将来的に増加が見込まれる支出も考慮に入れることも大切です。特に50代以降は、医療費や介護費用といった健康関連の支出が増加する傾向にあります。
若いうちは健康でも、年齢を重ねるにつれて病気や怪我のリスクは高まります。急な入院や手術で高額な医療費が必要になる可能性もゼロではありません。また、親の介護や自身の将来の介護に備える資金も必要になるかもしれません。
実際に、介護施設への入居には毎月数十万円の費用がかかるケースも珍しくありません。
こうした不測の事態に備えるため、生活費とは別に「生活防衛資金」を確保しておくことが推奨されます。一般的には生活費の半年~1年分、あるいはそれ以上のまとまった資金を、すぐに引き出せる形で準備しておくと安心です。
FIRE計画には、こうした突発的な出費に対する備えも必ず盛り込んでおきましょう。
FIREに必要な金額の計算方法|年金を含めた現実シミュレーション
FIRE達成に必要な資金額は、「4%ルール」という基本的な考え方を用いて算出できます。50代からの計画では、将来受け取る年金額を考慮に入れることで、より現実的な目標設定が可能になります。
具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。

基本の「4%ルール」で必要資産を算出
FIREの必要資金額を計算する上で基本となるのが「4%ルール」です。これは、「年間の生活費を、投資元本の4%以内に抑えることができれば、資産を減らすことなく生活できる」という考え方です。
この理論の根拠は、米国の株式市場の過去のデータに基づいています。S&P500などの株価指数の平均成長率が約7%であるのに対し、物価上昇率が約3%であることから、その差である4%の範囲内で資産を取り崩せば、元本は理論上減らないとされています。
この4%ルールを逆算すると、FIREに必要な資産額は「年間の生活費 × 25倍」というシンプルな式で求めることができます。
例えば、年間の生活費が300万円であれば、300万円 × 25 = 7500万円が目標資産額となります。
まずはこの計算式を基本として、年間の支出額を当てはめて、目標額を把握することから始めましょう。
50代からのFIREは“年金受給までの期間”がポイント
50代からFIRE計画を立てる上で最も重要なポイントは、リタイアしてから公的年金の受給が開始される65歳までの期間をどう乗り切るかです。
この期間の生活費を自己資金で賄うことができれば、65歳以降は年金収入を生活の基盤にできるため、生涯にわたって必要となる資金額を大幅に圧縮できます。
具体的には、資金計画を以下の2つの期間に分けて考えます。
- リタイアから65歳までの期間:この期間は収入が途絶えるため、生活費の全額を貯蓄や資産の取り崩しで賄います
- 65歳以降の期間:年金収入で不足する生活費のみを、資産運用益などで補填します
このように計画を分けることで、特に65歳以降に必要な自己資金額を大きく減らすことが可能です。
50代のFIRE計画は、「年金受給までのブリッジ期間」の資金をいかに確保するかが成功の鍵となります。
夫婦2人暮らしのFIRE必要額シミュレーション
50代夫婦がFIREを目指す場合の必要資金額を、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
ここでは、55歳でリタイアし、夫婦2人で生活していく場合を想定します。
【Bさん夫婦の状況】
- 年齢:45歳(10年後の55歳でFIREを目指す)
- 世帯年収:1000万円
- 現在の貯蓄額:4500万円
- FIRE後の年間生活費:420万円(月35万円)
- 65歳以降の年金受給額(夫婦合計):年間約280万円
このケースでは、まずリタイアする55歳から年金受給が始まる65歳までの10年間の生活費を全額自己資金で賄う必要があります。
- 55歳〜65歳の必要資金:420万円 × 10年 = 4200万円
次に、65歳以降の生活費を計算します。年金収入だけでは年間140万円(420万円 - 280万円)が不足するため、この不足分を資産運用で賄うことを考えます。「4%ルール」を適用すると、必要な運用元本は以下の通りです。
- 65歳以降の必要資金:140万円 × 25 = 3500万円
したがって、Bさん夫婦が55歳でFIREするために必要な資金額の合計は、7700万円(4200万円 + 3500万円)となります。
現在の貯蓄4500万円と、これからの貯蓄でこの目標額を目指すことになります。
50代からFIREに近づくための現実的なステップ
50代からFIREを目指すには、闇雲に貯蓄するのではなく、戦略的なアプローチが不可欠です。
支出の最適化、税制優遇制度の活用、退職後の収入源の確保という多角的な視点から、着実に資産形成を進めていくことがポイントとなります。
① 家計のスリム化と固定費見直し
FIREへの第一歩は、収入を増やすことと同時に、支出を徹底的に見直すことです。特に、毎月決まって出ていく「固定費」の削減は、一度見直せば効果が継続するため効果的です。
50代の家計で見直すべき主な固定費には、以下のような項目が挙げられます。
- 住居費:住宅ローンの借り換えや、より家賃の低い物件への住み替えを検討する
- 通信費:スマートフォンの料金プランを格安SIMに見直す
- 保険料:保障内容が過剰になっていないか、必要な保障に絞って見直す
- サブスクリプションサービス:利用頻度の低いサービスは解約する
FIRE達成には、できる限り支出を抑え、投資に回せる資金を最大化することが大切です。まずは家計簿アプリなどを活用し、家計を正確に把握することから始めましょう。
② iDeCo・NISAなどの税制優遇制度を最大限活用
50代からの資産形成を加速させるためには、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった税制優遇制度の活用も検討しましょう。
iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税を軽減しながら老後資金を準備できる制度です。運用益も非課税で再投資されるため、複利効果を大きく享受できます。
50代からでも、65歳まで掛金を拠出できるため、残り期間で着実に資産を積み上げることが可能です。
一方NISAは、年間最大360万円までの投資で得られた利益が非課税になる制度です。生涯にわたる非課税保有限度額も1800万円と大きく、50代からのラストスパートに最適です。
特に、退職金などのまとまった資金を非課税枠で運用することで、効率的に資産を増やすことが期待できます。
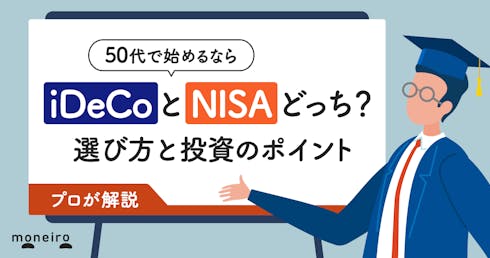
③ 退職金・企業年金の運用プランを立てる
50代のFIRE計画において、退職金や企業年金は重要な資産となります。これらをどのように受け取り、どう運用するかによって、FIRE達成の実現可能性が大きく変わってきます。
まずは、勤務先の退職金制度を確認し、将来いくら受け取れるのかを正確に把握することから始めましょう。
退職金の受け取り方には、一般的に「一時金」として一括で受け取る方法と、「年金形式」で分割して受け取る方法があります。それぞれ税金の計算方法が異なるため、どちらが手取り額で有利になるかをシミュレーションすることが重要です。
受け取った退職金を、前述のNISAなどを活用して適切に運用することで、FIRE後の資産寿命を延ばすことが可能です。
ただし、退職金は長年の労働の対価である大切な資金です。リスクの高い投資に一度に全額を投じるのではなく、許容できるリスクの範囲内で、分散投資を心がけるなど、慎重な運用プランを立てることが求められます。

④ FIRE後の収入源を確保(副業・年金繰下げ・配当収入など)
FIRE後の生活を安定させるためには、資産の取り崩しだけに頼るのではなく、複数の収入源を確保しておくことが有効です。これにより、資産が目減りするペースを緩やかにし、精神的な余裕にも繋がります。
具体的な収入源としては、以下のようなものが考えられます。
- 副業・パートタイム:これまでのキャリアで培ったスキルを活かして、フリーランスや顧問として働く。あるいは、興味のある分野でパートタイムの仕事を始める。これは「サイドFIRE」の考え方にも通じます
- 資産運用による収入:高配当株や不動産投資信託(REIT)などをポートフォリオに組み入れ、定期的な配当金や分配金収入を得る
- 年金の繰下げ受給:公的年金の受給開始を65歳以降に遅らせることで、1ヶ月あたり0.7%ずつ受給額を増やすことができます。例えば70歳まで繰り下げると42%、75歳までなら84%も年金額が増加し、生涯にわたる安定収入を強化できます。
⑤ 医療保険・社会保険料の負担を把握する
FIRE計画において見落としがちなのが、退職後の医療保険や社会保険料の負担です。会社員時代は、健康保険料や厚生年金保険料の半分を会社が負担してくれていますが、退職後はこれらの費用が全額自己負担となります。
退職後の健康保険の選択肢は、主に以下の3つです。
- 任意継続被保険者制度:退職後2年間、会社の健康保険に継続して加入できます。保険料は在職中の約2倍になりますが、扶養家族がいる場合は有利になることがあります
- 国民健康保険:住んでいる市区町村が運営する保険に加入します。保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、退職翌年は高額になる可能性があります
- 家族の被扶養者になる:配偶者や子どもが加入する健康保険の被扶養者になる方法です。収入などの条件を満たす必要があります
また、60歳未満で退職した場合は、国民年金保険料の支払いも必要になります。これらの社会保険料は、FIRE後の支出計画に必ず含めておくべき重要な項目です。
事前に状況に合わせて試算し、年間の負担額を把握しておきましょう。
サイドFIRE・スローFIREという現実解
FIREにはいくつかの形があり、必ずしも完全に労働から離れる「完全FIRE」だけが選択肢ではありません。特に50代から目指す場合、より現実的で達成しやすい方法として「サイドFIRE」や「スローFIRE」が注目されています。
サイドFIREとは、資産運用による収入で生活費の大部分を賄いつつ、残りの不足分を副業やパートタイムなどの労働収入で補うスタイルです。プチFIREとも呼ばれます。
例えば、年間300万円の生活費が必要な場合、200万円を資産運用で、残りの100万円を労働で得るといった形です。これにより、完全FIREよりも目標資産額を低く設定できるため、達成のハードルが大きく下がります。
一方、スローFIREは、徐々に労働時間を減らしていく段階的なリタイアを指します。フルタイムからパートタイムへ、そして最終的には完全にリタイアするなど、時間をかけて緩やかに働き方を変えていくスタイルです。急激な環境変化を避けられるため、精神的・経済的な安定を保ちやすいという利点があります。
FIREの資金がいくら必要なのか気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
50代からは「完全独立」より“働き方の自由”をゴールにする
50代からのFIRE計画において、最も重要なのは「完全に働かないこと」を最終目標にしないことです。むしろ、「経済的な制約から解放され、自らの意思で働き方を選べる自由を手に入れること」をゴールに設定する方が、より現実的で幸福度の高いリタイア生活に繋がります。
FIREの本質は、仕事が義務ではなく選択肢の一つになる状態を築くことにあります。完全に仕事をやめることも、情熱を注げる分野で働き続けることも、あるいはパートタイムで社会と関わることも、すべてが自分の裁量で決められる。この「選択の自由」こそが、FIREがもたらす最大の価値です。
50代は、これまでのキャリアで培った豊富な経験やスキルがあります。それを活かして、収入のためではなく、やりがいや社会貢献のために働くという選択も可能です。
完全な経済的独立に固執するよりも、自分らしい働き方を見つけることを目標に、柔軟なFIRE計画を立ててみてはいかがでしょうか。
FIRE後に後悔しないためのチェックリスト
念願のFIREを達成しても、その後の生活で「こんなはずではなかった」と後悔するケースは少なくありません。
計画段階からリタイア後の生活を具体的にイメージし、定期的に計画を見直していく姿勢が重要です。以下のチェックリストを参考に、後悔のないFIREを実現しましょう。
生活費・年金・運用の3要素を毎年見直す
FIRE計画は、一度立てたら終わりではありません。特に、「生活費(支出)」「年金(収入)」「資産運用(利回り)」の3つの要素は、社会情勢やご自身の状況によって変動する可能性があります。
そのため、少なくとも年に一度はこれらの要素を見直し、計画をアップデートすることが不可欠です。
例えば、想定以上に物価が上昇すれば、生活費は計画よりも多くかかります。また、年金制度の改正によって受給額が変わる可能性もゼロではありません。資産運用の利回りも、市場の動向によって常に変動します。
定期的にキャッシュフロー表などを見直し、現状が計画通りに進んでいるかを確認しましょう。
もし計画との乖離が大きくなっている場合は、生活費を切り詰めたり、働き方を見直したりといった軌道修正が必要になります。
想定外の支出(医療・介護・物価上昇)に備える
FIRE計画を立てる際には、日々の生活費だけでなく、将来起こりうる「想定外の支出」にも備えておく必要があります。特に、医療費、介護費用、そして継続的な物価上昇は、計画を大きく狂わせる要因となり得ます。
年齢を重ねれば、大きな病気やケガのリスクは避けられません。また、親や自分自身の介護が必要になる可能性も考慮しておくべきです。これらの費用は数百万円単位になることもあり、通常の生活費とは別の資金枠で準備しておくことが賢明です。
このための備えが「生活防衛資金」です。生活費の半年から2年分程度の現金を、投資とは別に確保しておくことで、突発的な出費が発生しても、運用中の資産を取り崩すことなく対応できます。
また、4%ルールは過去のデータに基づくものであり、将来の物価上昇が想定を超える可能性も念頭に、余裕を持った資金計画を心がけましょう。
リタイア後も社会的つながりを維持する
FIRE後の生活で意外な落とし穴となるのが、社会的な孤立です。長年勤めた会社を辞めると、同僚との日常的な交流がなくなり、社会との接点が急激に減少することがあります。
経済的な自由を手に入れても、精神的な充足感がなければ、幸福なリタイア生活とは言えません。そうならないためには、リタイア前から会社以外のコミュニティに参加しておくことが大切です。
- 趣味のサークルや地域のボランティア活動に参加する
- サイドFIREとして、やりがいを感じられる仕事で社会と関わる
- 家族や昔からの友人との時間を大切にする
こうした活動を通じて、退職後も新たな人間関係を築き、社会的な役割を持つことが、精神的な安定と生きがいにつながります。
FIRE計画には、お金の計算だけでなく、こうした「心の健康」を保つためのプランも盛り込んでおきましょう。
定期的にライフプランをアップデートする
FIRE後の人生は、計画通りに進むことばかりではありません。自身の健康状態の変化、家族構成の変動、あるいは新たな興味や目標の発見など、ライフプランは常に変化しうるものです。
そのため、一度立てた計画に固執せず、定期的に見直し、柔軟にアップデートしていく姿勢が求められます。
例えば、リタイア後に新たな趣味が見つかり、その活動にもっと時間やお金を使いたくなるかもしれません。あるいは、健康上の理由で、当初想定していたアクティブな生活が難しくなる可能性もあります。
こうした変化に対応するためには、年に一度など定期的に自身のライフプラン全体を振り返る機会を設けましょう。現在の生活に満足しているか、将来やりたいことに変化はないか、資金計画に無理はないかなどを点検し、必要であれば計画を修正します。
生涯設計を継続的に見直すことで、変化に対応しながら、より豊かで満足度の高いリタイア生活を送ることができるでしょう。
まとめ
50代からのFIREは、決して不可能な夢ではありません。むしろ、年金や退職金の見通しが立てやすいという大きな強みがあります。
成功の鍵は、完全なリタイアに固執せず、サイドFIREやスローFIREといった柔軟な選択肢を視野に入れることです。
まずはご自身の支出を正確に把握し、将来の収入(年金など)を考慮した上で、現実的な目標資金額を設定しましょう。
そして、iDeCoやNISAといった制度を最大限に活用しながら、着実に資産形成を進めていくことが重要です。
本記事を参考に、あなたらしい「働き方の自由」を手に入れるための第一歩を踏み出してください。
50代からのFIRE、ただの夢で終わらせない。
»あなたの現状に合わせた最適資産運用プランを3分で診断
FIREの資金がいくら必要なのか気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
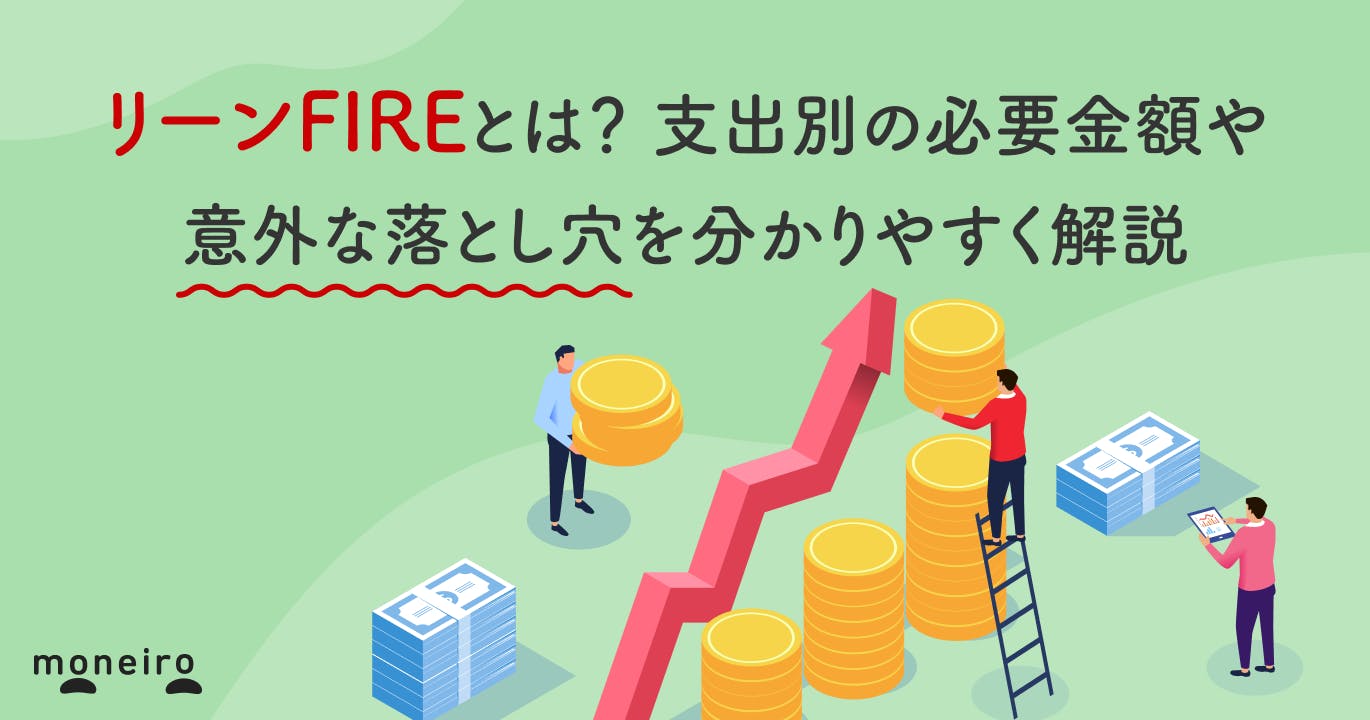
リーンFIREとは?支出別の必要金額や意外な落とし穴を分かりやすく解説

5000万円でFIREできる?実現可能なライフスタイルと将来の選択肢を解説
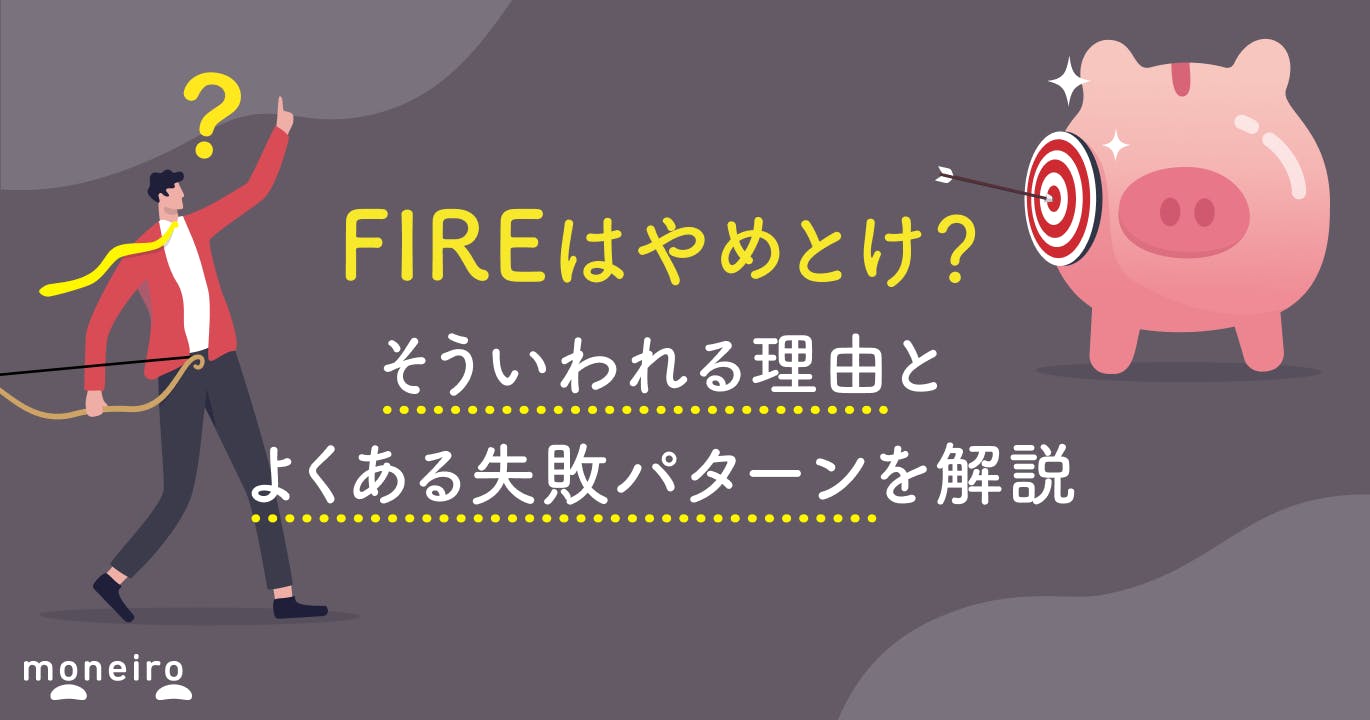
FIREはやめとけ?そういわれる理由とよくある失敗パターンを解説

FIREにはいくら必要?種類別&コーストFIREの必要資金をシミュレーション
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
