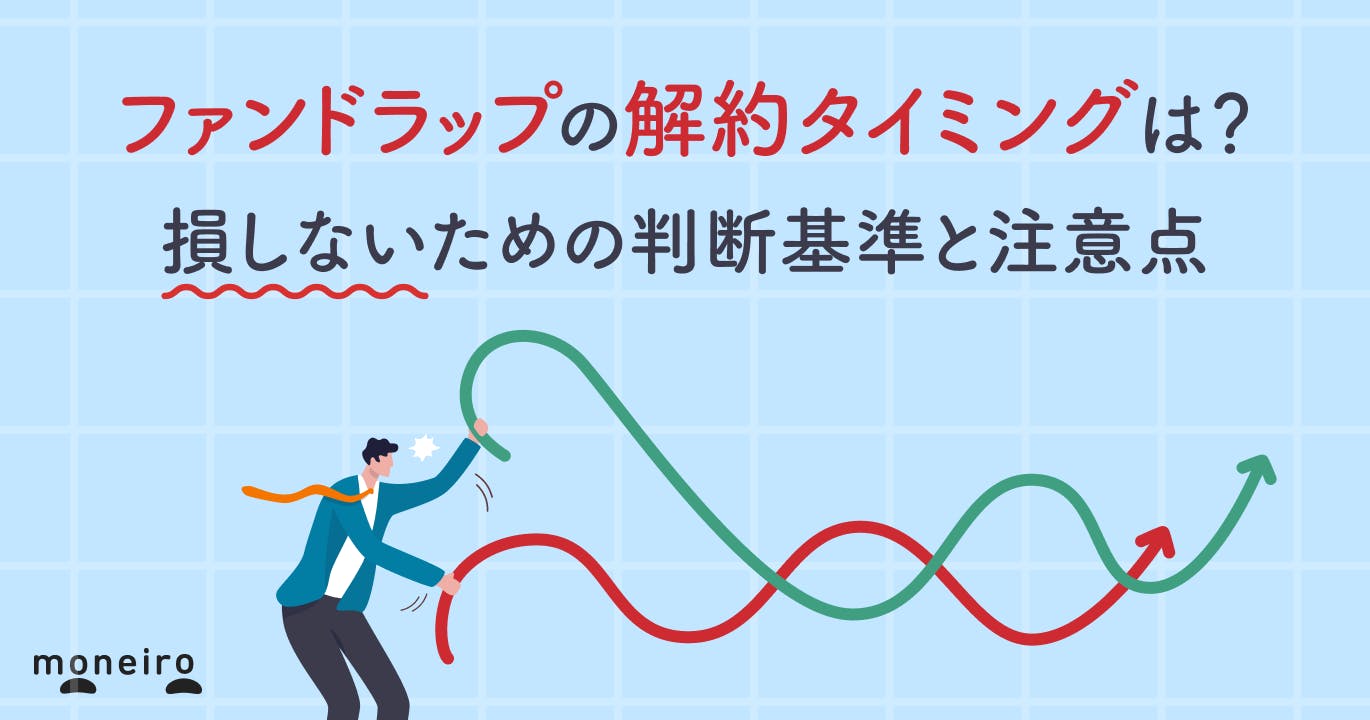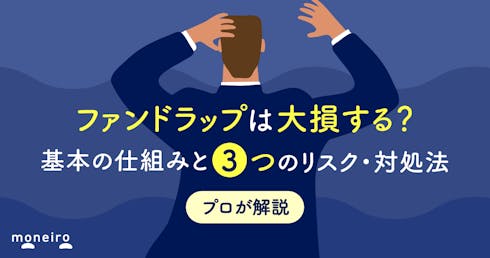
ファンドラップの解約タイミングは?損しないための判断基準と注意点をプロが徹底解説
»まずは自分に合う投資を今すぐ無料診断
「最近ファンドラップの成績が伸びない」「手数料が高い気がする」そんな不安から解約を考える人も多いかもしれません。
しかし、解約のタイミングを誤ると、思わぬ損失やコストが発生することもあります。
本記事では、ファンドラップの解約すべき・続けるべき判断基準を専門家の視点でわかりやすく解説します。さらに、損しないタイミングの見極め方、解約にかかるコストや税金、そして解約後の再投資の選択肢まで投資のプロが徹底解説します。
- 解約を検討すべき3つの判断ポイント
- 相場状況に応じた解約タイミングの考え方
- 解約時に知っておくべき注意点
投資信託の運用で悩んでいるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:必要老後資金額と準備方法がわかる
▶一括投資診断:まとまったお金の運用方法がわかる
▶オンライン無料相談:専門家にスマホで直接相談
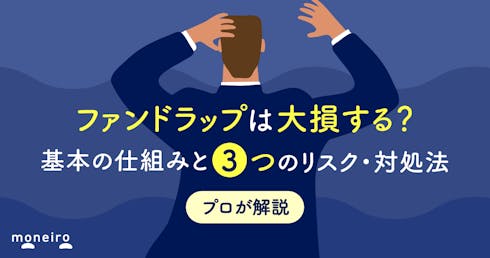
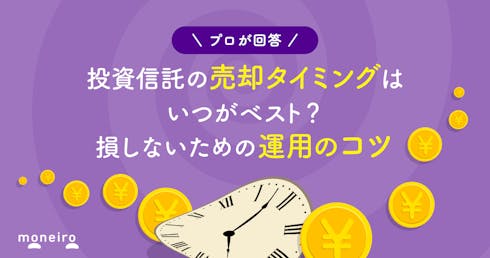
ファンドラップの解約タイミングに迷った時の判断ポイント
ファンドラップを続けるか解約するか迷った時は、投資の目的と状況で判断することが大切です。短期的な損益だけで判断すると、長期的なリターンを逃す可能性もあります。
解約を検討する際に確認しておきたい判断のポイントをわかりやすく解説します。
①最初の目的と今の目的にズレがあるか
ファンドラップを解約しようか迷う時のひとつの要因に、運用目的の変化が挙げられます。
例えば「老後資金」のために運用を始めたのに、年月が経過すると、目的が「教育資金」や「住宅購入の頭金」など、別の目的に変わることがあります。
また、年齢や家族構成の変化によって、自身のリスク許容度も変化します。若い頃は積極的に運用したいと思っても、退職が近づけばリスクを取ることに慎重になり、安定運用を重視したくなるのは自然なことです。
自身のライフステージの変化とともに、運用の目的にズレが生じ、その結果、解約を検討することも十分あり得ます。
このような場合は、すぐに解約するより、資産全体のなかでファンドラップがどのような役割を果たしているか、どんな位置づけなのか、状況をいま一度見直してみましょう。必要があれば、解約やプランの変更を検討します。
②運用実績とベンチマークに差があるか
運用実績を長期的な視点で見て、市場平均を下回る状態が続く場合は、解約や他サービスへの乗り換えを検討するタイミングです。
多くのファンドラップはバランス型のポートフォリオで運用されていますが、運用成果が良いのか悪いのかは、そのファンドのベンチマークとの乖離で判断ができます。
例えば、市場が10%上昇しているのに、自分の運用ではそれを下回っている場合、パフォーマンスがベンチマークより劣っている可能性があります。
一方、市場が下落しても損失が小さいなら、リスク管理が上手く機能していると評価できます。
運用レポートを定期的に確認したり、担当者に運用状況を聞いたりして、パフォーマンスをデータで判断する姿勢が大切です。
③手数料とリターンのバランスが悪くないか
ファンドラップは専門家に運用を一任する「投資一任契約」を金融機関と結びます。そのため、自分で投資信託を購入・運用するよりもコストがかかります。
例えば、手数料が年2%かかり、リターンが年3%なら、実質の利益は1%です。同種の投資信託で同じリターンが見込めるなら、手数料を払い続ける意味が薄れてしまいます。場合によっては、解約を検討するタイミングにしても良いかもしれません。
ただし、ファンドラップを利用する意義については冷静に判断したいところです。ファンドラップは、長期分散投資を投資家に代わって専門家が行う仕組みです。
運用成績の評価は正しく行った上で、解約の是非を検討しましょう。
ファンドラップの解約タイミングの考え方|ケース別
ファンドラップの解約を考えるのであれば、相場の下落時やリバランスの時期、契約更新のタイミングで検討することもできます。
それぞれのケースを見ていきましょう。
相場が下がっている時
相場が下がっている時は、自分の資産が減っていく状況に、誰しも焦りを感じがちです。特に、相場が急落する時は、含み損が大きく膨らむので、誰しも一度は解約を考えてしまうものです。
しかし、ファンドラップは分散投資をしながら、長期的な資産形成を目指すサービスです。短期的な下落で慌てて解約するのはいったん止めて、今が本当にベストな解約時期なのか冷静に判断しましょう。
急落時に売却してしまうと、相場が回復したときに自分の資産も一緒に上昇するチャンスを逃してしまいます。
また、長期投資による複利効果は、時間をかけるほど大きくなります。短期の運用では十分な効果を得られません。解約は、できるだけ長期運用を経てからにして、短期の値動きに惑わされないようにしましょう。
一方で、投資によって自分の心理が不安定になるということは、自身のリスク許容度とポートフォリオが合致していない可能性もあります。解約よりも、むしろポートフォリオの資産配分を見直す機会として考えても良いでしょう。
リバランス時
ファンドラップでは、定期的に資産配分を調整する「リバランス」が行われます。
例えば、株価が上昇して株式比率が高まりすぎた場合、一部を売却して債券を買い増すなど、ポートフォリオのリスクとリターンを調整するために行います。
多くの金融機関では四半期や半年ごとに実施されるので、リバランスの時期に、あらためて運用方針を見直すのも悪くありません。
リバランス報告を受け取ったら、リバランスの理由を確認し、自分のライフプランやリスク許容度と合っているかを見直しましょう。
ズレを感じたら、担当者に相談したり、プラン変更・解約を検討するタイミングです。
契約更新の時
ファンドラップは、多くの場合、1年ごとの自動更新です。そのため、更新時期になったら、手数料やサービス内容を見直すのもおすすめです。
長くファンドラップを継続していると、毎年のことなので関心が薄れがちになるかもしれませんが、思ったようにパフォーマンスが出ていないこともあります。資産全体を見直すタイミングとして活用しましょう。
また、更新時には手数料の改定や新サービスが追加される場合もあります。
更新案内は必ず確認し、満足のいく運用成果が得られているのであれば、利益確定のために解約を検討しても良いかもしれません。
ファンドラップを解約する上での注意点
ファンドラップの解約を決断する前に、いくつか知っておくべき注意点があります。
注意点として、解約時にコストが発生すること、すぐに現金化できないこと、そして利益に対し税金が発生することなどが挙げられますが、事前に把握しておけば想定外の事態を避けられます。
途中解約でも運用報酬は日割りで発生する
多くの金融機関で解約手数料は無料ですが、支払い済みの投資一任報酬は原則返金されません。
また、報酬は四半期などの後払いが一般的で、前回の支払日から解約日までの運用報酬が日割りで清算されます。
例えば、みずほ証券のファンドラップの場合、解約手数料は不要ですが、最大で約3ヶ月分の投資一任報酬は返金の対象外になっています。
さらに「成功報酬併用型」の場合、解約時点までの運用益に成功報酬が発生する場合があります。
解約前に、契約書や約款で解約手数料の仕組みを必ず確認しておきましょう。
ファンドラップ口座内の投信はすぐ換金できない場合がある
ファンドラップの解約を申し込んでも、即日の現金化は困難です。
一部のファンドラップでは、契約後3か月は解約不可などの制約があるほか、解約金の振込までに7〜10営業日程度、それ以上の日数を要する場合もあります。
一般的に投信の売却・清算には時間がかかります。そのため「来週までに現金が必要」といった急な資金需要に対応できない場合がほとんどです。
解約予定日から逆算し、余裕をもって手続きを進めましょう。
利益確定時の課税に注意
ファンドラップを解約して利益(譲渡益)が出た場合、利益に対して約20%の税金がかかります。多くは特定口座(源泉徴収あり)での取引になるため、原則として確定申告は不要です。
他口座の損失と損益通算したい場合や、損失の繰越控除(最長3年)を行う場合は確定申告が有効です。大きな利益や他の損失がある年は、節税のために確定申告を検討しましょう。
ちなみにNISAはファンドラップでは使えません。
担当者から止められる場合がある
対面型でサポートを受けるファンドラップでは、解約意思を伝えると担当者から継続や代替提案を勧められることがあります。
ヒアリングは顧客保護の観点で有益ですが、お金の必要時期が明確なら、解約する意思をぶらさないことが大切です。なぜ解約が必要なのか、その理由を自分の中で明確にしておきましょう。
感情的な判断ではなく、納得できる根拠をもって決断できれば、後から「解約しなければよかった」と後悔することも少なくなります。
必要なら面談前に「最終意思」や「現金化したい日」などを担当者に伝えたり、引き留めに備えて要点をメモしておけば、解約理由を説明する時などに備えられます。
証券会社ごとに申込期限・処理日が異なる
解約申込の締切時刻や、売却・振込スケジュールは各社で異なります。
必ず「解約受付日」「約定日」「受渡日(振込日)」を事前に確認し、資金需要日から逆算して申し込みましょう。
ファンドラップの解約方法
ファンドラップの解約は、契約した金融機関によって異なりますが、一般的には対面、電話、またはオンラインで手続きを行います。
必要書類を提出後、金融機関が売却処理を行い、指定口座に資金が振り込まれるという流れが基本です。
① 解約(売却)手続きの依頼
ファンドラップの解約を決めたら、まずは契約している金融機関に解約の意思を伝えます。
対面型の証券会社や銀行で契約した場合は、担当者に来店を求められることが一般的です。解約の意思を伝えて、手続きを進めてもらいましょう。
このとき、解約手続きに必要な書類や、今後の流れや解約で発生する費用についても聞いておくと安心です。
一方、オンラインで完結するタイプのファンドラップであれば、ウェブサイトや電話での手続きが中心となります。
② 書類提出またはオンライン申請
解約の意思を伝えた後、金融機関から指示された方法で正式な手続きを行います。
対面での手続きの場合は、店頭で解約申込書などの書類に署名・捺印をします。本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)や印鑑が必要になる場合が多いので、事前に準備しておくとスムーズです。
オンラインで契約したファンドラップの場合は、会員ページにログインし、画面の指示に従って解約手続きを進めるのが一般的です。手続きの途中で不明な点があれば、カスタマーサポートに電話やメールで問い合わせることができます。
③ 売却実行・資金振込
解約の申し込みが受理されると、金融機関はファンドラップ口座内で保有している投資信託などの売却手続きを開始します。この売却処理には数日を要するのが一般的です。
すべての資産の売却と清算が完了した後、税金や手数料が差し引かれた金額が、あらかじめ指定した銀行口座に振り込まれます。
解約を申し込んでから実際に資金を受け取るまでには、通常、7〜10営業日程度かかります。ただし、金融機関や保有している資産の内容によっては、それ以上の時間がかかる場合もあります。
売却資金を使う時期が決まっている場合は、余裕を持って解約手続きを始めましょう。
ファンドラップの運用がうまくいかない理由
ファンドラップの運用が期待通りに進まない主な原因は、コストと得られる利益のバランスです。
プロに一任できる手軽さの裏で、コストが利益を圧迫しやすい商品構造なので、結果的に「思ったより増えない」「運用がうまくいかない」と感じる投資家が少なくありません。
金融庁の「リスク性金融商品の販売・組成会社による 顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」の調査内容によると、「想定した利益が得られない」ことが解約理由として一定割合を占めると示されています。
一方で、中・長期投資への理解不足、顧客のリスク許容度と商品のミスマッチなども指摘されています。
(参考:「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」)
IFAに相談するという新しい選択肢
証券会社の担当者だけでなく、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に相談すれば、中立的な立場から助言を受けられます。
多種多様な金融商品を客観的に比較できるだけでなく、家計全体とライフプランを踏まえた継続的な提案も期待できます。

IFAに相談するメリット
- 中立性:特定金融機関の販売方針やノルマに左右されないアドバイス
- 豊富な選択肢:金融商品・サービスの幅広い品揃え
- 総合提案:ライフイベントに合わせた資産運用プランを作成・提案
- 伴走支援:運用方針の定期点検・見直しを継続的にサポート
マネイロのIFAの利用で叶えられること
マネイロでは、ファンドラップの見直しや投資信託の選び方について、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に無料で相談できます。
複数の金融機関を比較しながら、あなたに合った資産運用の形を一緒に考えることが可能です。
マネイロでできること
①将来の資金計画を最適化:教育費・住宅購入・老後資金など、資金が必要になる時期に合わせた運用プランを策定。解約のタイミングや税(※)に関するアドバイスも可能
※正確な計算はマネイロではできません。税理士等にご相談ください
②ファンドラップのコスト・成果を「見える化」:ファンドラップで支払っている手数料(投資一任報酬・信託報酬・成功報酬など)を踏まえ、その運用成果を客観的に分析
③効率的な運用プランの提案:現在の運用方針・プランを変更したい場合は、その他の投資信託や運用方法(ロボアド、積立投資など)など、目的や意向に沿った代替プランを提案。リスクとリターンの再設定も可能
④実行まで徹底サポート:売却や購入時期のスケジュールを整理し、必要書類や受渡日の管理までサポート。その後の運用方針やリバランスルール、損益通算など税金の手続きについてもアドバイス可能
ファンドラップを続けるなら見直したい3つの対策
ファンドラップの運用を継続する場合でも、「任せきり」は禁物です。定期的にポートフォリオを確認し、手数料と成績のバランスをチェックするなど、主体的に関わる姿勢が重要です。
ポートフォリオ配分を半年ごとに確認する
多くのファンドラップでは、年に1〜2回、あるいは四半期ごとなど定期的にリバランスが行われます。そのタイミングで送られてくる運用報告書は、必ず内容を確認しましょう。
どのような資産クラス、例えば株式や債券などの比率が変更されたのか、また、その理由も理解することが大切です。
定期的にポートフォリオを確認し、とくに契約当初に設定したリスク・リターンが目標から乖離していないかをチェックしましょう。
手数料と運用成績のバランスを定期チェック
ファンドラップは専門家に運用を任せるサービス(投資一任契約)なので一定の手数料がかかります。
「手間の削減」や「専門家による運用の価値」にコストを支払っているので、そのメリットを感じられているか、納得のいく運用が続けられているか、定期的に確認しましょう。
そのためには、運用報告書などを必ず確認し、支払った手数料と得られたリターンを比較することも必要です。例えば、年間の手数料率が1.5%、リターンが1%未満であれば、実質的なリターンは得られていません。
また、運用成績を市場全体の動向を示すベンチマーク(日経平均株価など)と比べてみることも大切です。運用成績が悪くても、他のファンドも同様の成績であれば、一概に運用が悪いとは言えません。
ファンドラップの多くは、投資信託を組み合わせたバランス型のポートフォリオで運用されているので、長期運用の観点で成績を見ることも必要になるでしょう。
各資産の運用成績の見方が分からない場合などは、担当者や中立的な立場のIFAなどに尋ねてみるのもひとつの方法です。
方針変更時は説明をしっかり受ける
ファンドラップは「お任せ」のサービスですが、それは「任せきり」にして良いということではありません。金融機関の担当者とは、コミュニケーションをしっかり取るようにしましょう。
特に、金融機関側から運用方針の変更やリバランスの提案があれば、なぜそのような変更が必要なのか、具体的な理由を尋ねることも大切です。
市場環境の変化、新しい金融商品の登場、あるいはリスク管理の観点からなど、方針変更には理由があるものです。
納得できる説明が得られない場合や、自身の考えと異なる方針を提案された場合は、疑問や要望を積極的に伝えましょう。
まとめ
ファンドラップの解約タイミングは、契約目的とのズレ、市場環境と比較した運用実績、手数料とリターンのバランスという3つのポイントから総合的に判断することが重要です。
短期的な相場の下落で焦って解約すると損失を確定させてしまう可能性があるため、長期的な視点を忘れないようにしましょう。解約する際は、手続きにかかる時間や税金などの注意点を事前に確認しておくことが大切です。
運用を続ける場合でも、定期的な見直しを行い、主体的に資産と向き合う姿勢が大切です。
必要に応じてマネイロのIFAのサービスを活用し、自身にとって最適な選択をしましょう。
マネイロの無料相談のご予約はこちらから▼
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

ファンドラップと投資信託の違いは?比較でわかる仕組み・費用・選び方
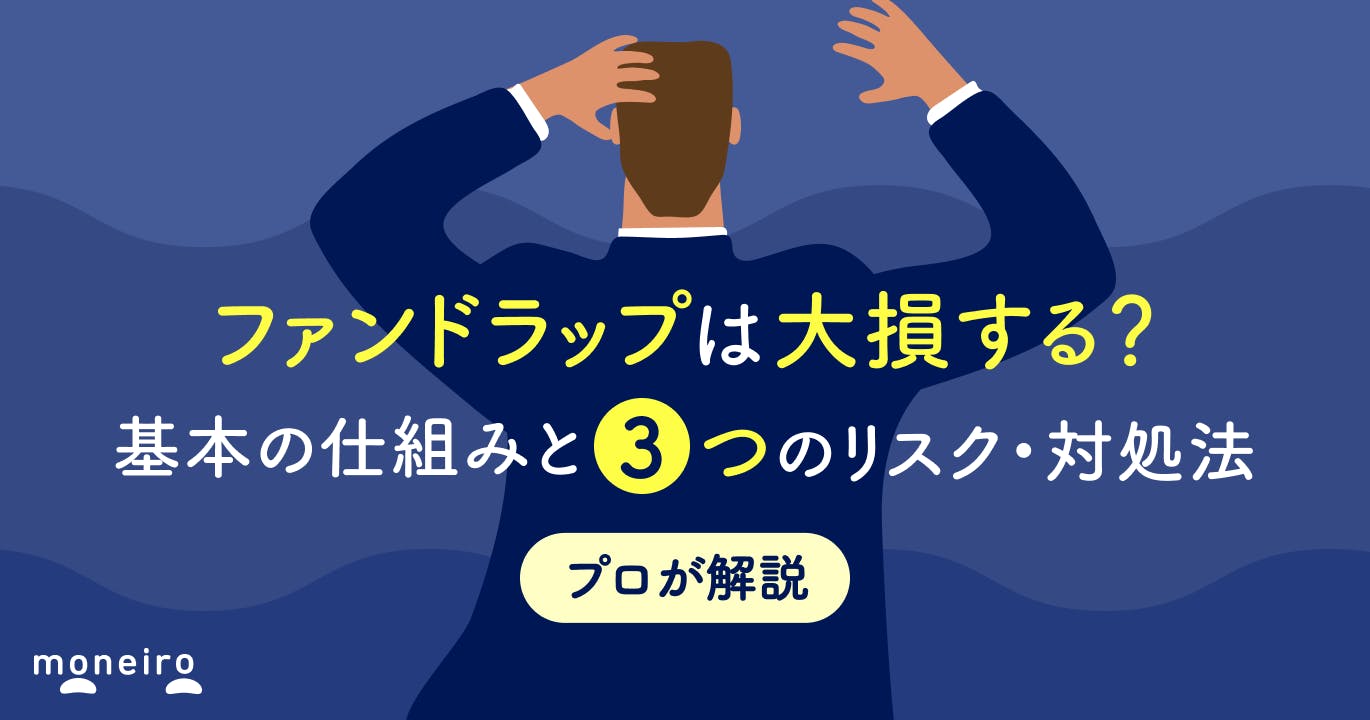
ファンドラップは大損する?基本の仕組みと3つのリスク・対処法をわかりやすく解説

5000万円をインデックス投資したら?リスクと投資戦略をケース別にプロが徹底解説
監修
土屋 史恵
- ファイナンシャルプランナー/金融ライター/編集者
神戸市外国語大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。遺言信託など資産承継ビジネスに強み、表彰歴あり。その後は長年の金融機関勤務経験を活かし、金融メディアに転職。記事執筆や編集などを担当。現在はフリーランスとして活動中。AFP、FP2級、証券外務員一種を保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。