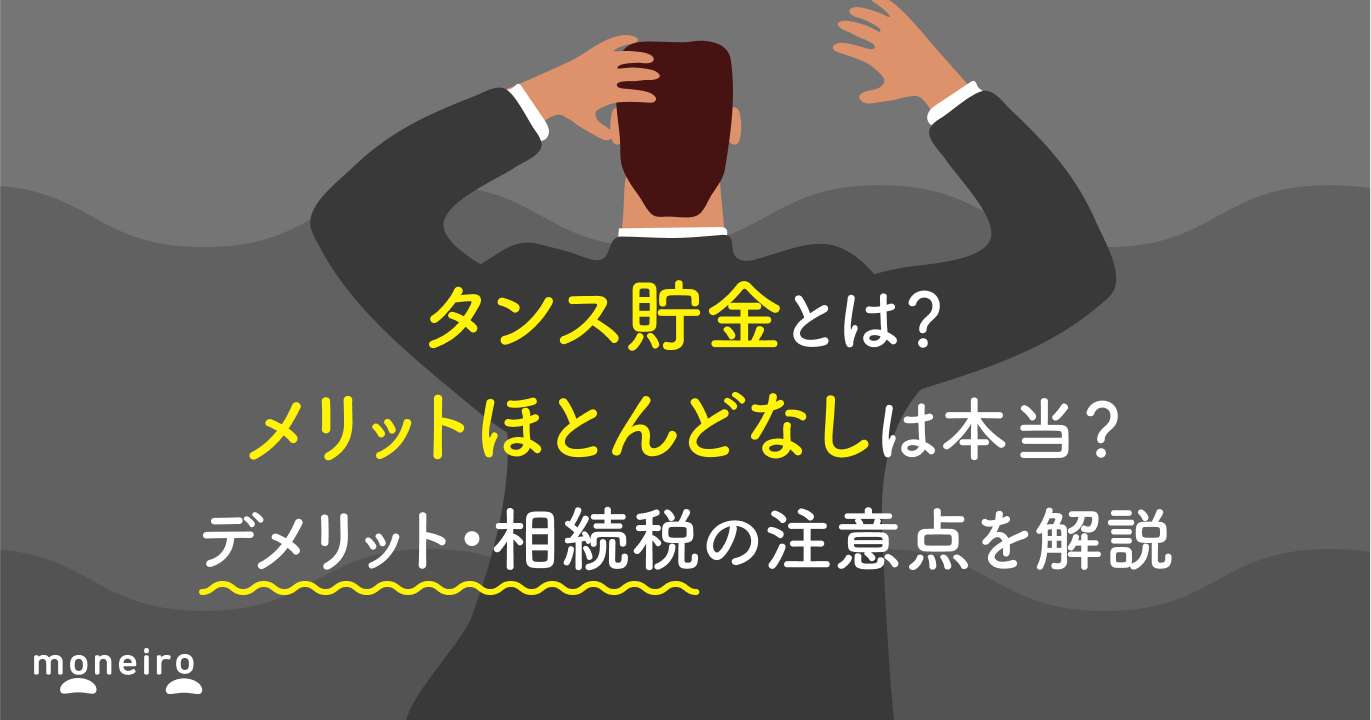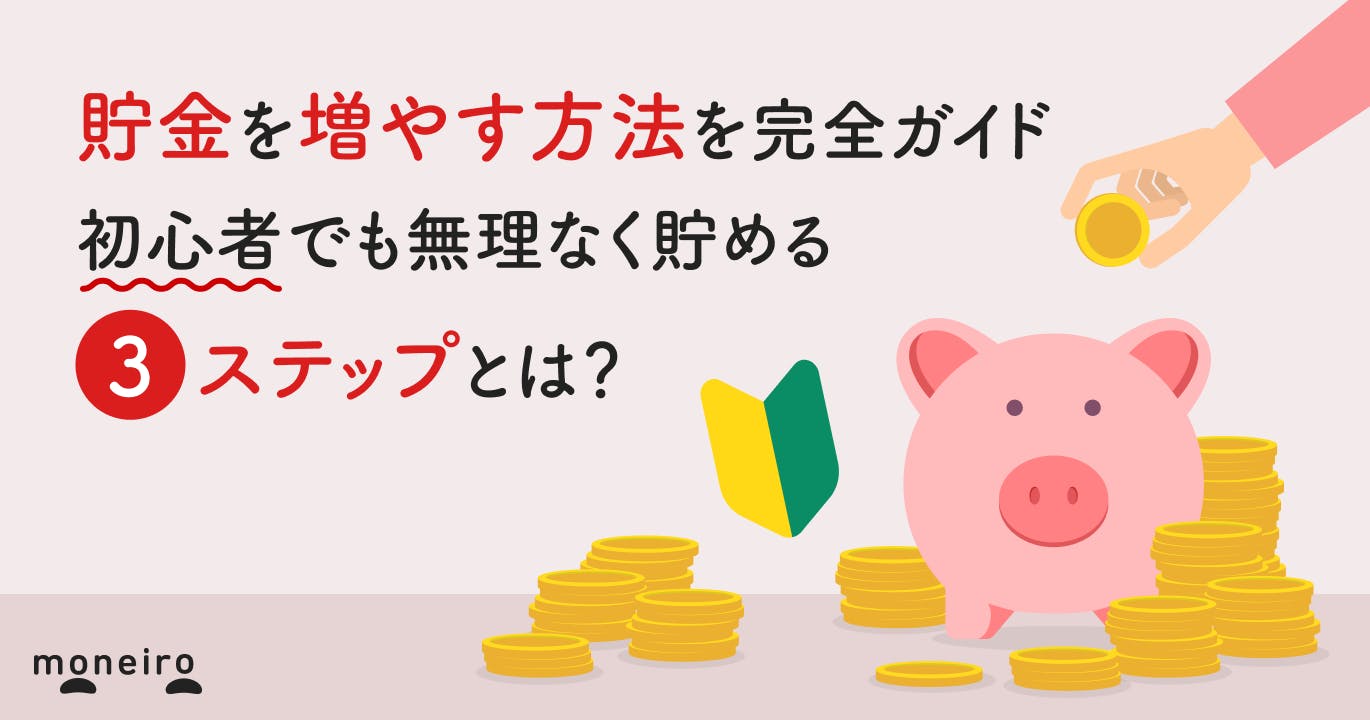
タンス貯金とは?メリットほとんどなしは本当?デメリット・相続税の注意点を解説
≫老後の資金は足りる?あなたの不足額を3分で診断
「タンス預金」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、銀行などに預けず、自宅で現金を保管する行為を指します。手元に現金がある安心感はありますが、そのメリットは限定的です。
本記事では、タンス預金がもたらす致命的なデメリット、特に盗難・災害・インフレのリスク、そしてもっとも危険な相続税の注意点を徹底的に解説します。安全に資産を守るための方法についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
- タンス預金の概要と日本に眠るタンス預金の金額
- タンス預金の致命的なデメリットが存在する理由
- タンス預金のリスクを回避し、資産を守るための具体的な代替手段
将来の備えが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
タンス預金とは?「眠れる資産」はいくらある?
まずはタンス預金がどのようなものを指すのか、またその資産額はどれくらいに上るのかを解説します。
タンス預金の合計は約50兆円
タンス預金は、金融機関の集計には含まれない、自宅などに保管されている現金のことを指します。第一生命経済研究所の試算によると、日本の家計が保有するタンス預金の合計額は、約50兆円に上るとされています。
この金額は、「眠れる資産」とも呼ばれており、日本の総世帯数(約5000万世帯と仮定)で単純計算すると、一世帯あたり約100万円の現金を自宅に保管している計算になります。
タンス預金は減少傾向
近年、タンス預金は微減傾向にあると考えられています。これは、マイナンバー制度の普及や金融機関の情報共有の進展、そして相続税対策として金融資産を適切に運用する意識の高まりなどが影響していると見られます。
しかし、高齢化社会においては、自宅に現金を保管しておきたいというニーズは根強く残っており、特に「コロナ禍」に代表されるような、災害や社会不安、経済不安が高まった際には、一時的にタンス預金の額が増加する傾向も見られます。
タンス預金の限定的なメリットと致命的なデメリット
タンス預金は堅実な現金保管法のように感じられますが、実はさまざまなリスクを抱えています。ここではメリット・デメリットを詳しく解説します。
タンス預金のメリット
タンス預金のメリットは実は非常に限定的であり、主に「手元に置いておくこと」から得られる心理的な安心感に集約されます。
いつでも使える安心感
銀行の営業時間やATMの利用時間に縛られず、必要なときにいつでも現金を取り出して使える安心感があります。特に、災害時や通信障害が発生し、電子決済や銀行サービスが利用できなくなった場合に、生活に必要な費用をすぐに確保できる点はメリットです。
金融機関の破綻リスク回避(ペイオフ対策)
万が一、金融機関が破綻した場合でも、タンス預金であれば直接的な影響を受けません。預金保険制度(ペイオフ)により、銀行預金は元本1000万円とその利息までしか保護されないため、それを超える金額を保有している人にとっては、タンス預金はリスク分散の一環と考えることができます。
預金封鎖への備え
歴史的に稀なケースですが、過去には国が経済危機に対応するために預金の引き出しを制限する「預金封鎖」が行われた事例があります。タンス預金は、このような極端な事態が発生した場合でも、国や金融システムの管理外にあるため、現金の利用が保証されるという側面があります。
将来の備えが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
タンス預金の致命的なリスク・デメリット
メリットは限定的である一方、タンス預金には資産価値を毀損する致命的なリスクや、重いペナルティを招く税務リスクが存在します。
災害・盗難で資産を失うリスク
タンス預金の最大の物理的リスクは、盗難や火災、地震などの災害による資産の全損です。盗難保険や火災保険の多くは、自宅に保管された現金に対して補償上限額を設けており、多くの場合、高額なタンス預金は全額補償の対象外となります。
また、水害や火災により現金が焼失・損傷した場合、再発行は原則として不可能であり、文字通り資産を失うことになります。
特殊詐欺にかかるリスク
自宅に高額な現金を保管していると、特殊詐欺の標的になりやすいという危険性があります。警察官や自治体の職員などを装った詐欺師が「キャッシュカードの交換が必要です」「現金を預かります」などと持ちかけ、自宅にある現金をだまし取ったり、引き出させたりする手口が横行しています。
タンス預金は銀行を介さないため、一度だまし取られると被害回復が極めて困難になります。
税務リスク(申告漏れ)
もっとも深刻なリスクの1つが、相続発生時の税務リスクです。
タンス預金は「税務署には極めて高い確率で把握される」と考えるべきです。税務署は、KSK(国税総合管理)システムにより全国民の所得や納税状況を一元管理しており、相続税の調査では、亡くなった人の過去10年分の預金移動履歴や所得、不動産の売買履歴などを徹底的に調査します。そこから「生前の収入に対して相続財産が少なすぎる」といった矛盾点を突き、タンス預金の存在を指摘します。
申告漏れが発覚した場合、本来の相続税に加え、以下の重いペナルティ(附帯税)が課されます。
- 過少申告加算税:追加で納める税額の10%(一定額を超えると15%)
- 無申告加算税:納付すべき税額の15%(一定額を超えると20%)
- 重加算税(意図的な隠蔽と判断された場合):もっとも重く、最大で40%
これらに加えて、納付が遅れた日数に応じた延滞税も課されるため、結果として本来の税額の1.5倍近くを支払うケースも珍しくありません。
インフレリスク(金利がない)
タンス預金は利息を生み出さないため、インフレーション(物価上昇)が進行すると、現金の実質的な価値が目減りするというリスクがあります。例えば、インフレ率が年率2%で推移した場合、100万円の現金は10年後には購買力が約82万円相当にまで低下します。
銀行預金であればわずかでも金利がつきますが、タンス預金はゼロ金利のため、このインフレリスクに無防備です。
機会損失リスク
タンス預金として現金を保有していると、本来得られたはずの運用益を得る機会を失います。これは「機会損失」と呼ばれます。
特に低金利時代であっても、NISAやiDeCoなどの優遇税制を活用した資産運用や、インフレに強い金融商品に投資することで、資産価値の維持または増加を図ることが可能です。タンス預金は、これらの資産成長の機会をすべて放棄している状態といえます。
≫老後の資金はどう作る?あなたに最適なプランを診断
タンス預金の代わりは?目的別の資産管理・運用法
タンス預金のリスクを理解した上で、手元の現金を安全かつ有利に管理・運用するための目的別代替手段を解説します。
少しでも有利な金利で預けたい人:大手ネット銀行・定期預金
現金の安全性は維持しつつ、メガバンクの普通預金よりも高い金利を得たい場合は、大手ネット銀行の普通預金や定期預金が有力な選択肢です。
ネット銀行は実店舗を持たない分、運営コストが低く、その分を預金金利に還元している傾向があります。また、定期預金を利用することで、普通預金よりもさらに高い金利で預けられることが一般的です。
とにかく安全に保管したい人:複数銀行への分散預金
金融機関の破綻リスク(ペイオフリスク)を徹底的に回避したい場合は、1つの金融機関につき1000万円以内を目安として、複数の銀行に分散して預金する方法がもっと安全性が高いといえます。
これにより、各金融機関が破綻した場合でも、預金保険制度によって全額(元本1000万円まで)が保護されます。タンス預金よりも、盗難や火災のリスクを回避できます。
安全性を保ちつつインフレ対策もしたい人:個人向け国債(変動10年)
インフレが進行する中で現金の価値を守りたいが、元本割れは避けたいというニーズには、「個人向け国債(変動10年)」が適しています。
この商品の大きな特徴は、市場金利に連動して半年ごとに適用金利が見直されるため、インフレ(金利上昇)に強い点です。
さらに、最低金利0.05%が保証されているため、景気が悪化して市場金利が下がったとしても、元本割れのリスクがなく安全性が非常に高いのが特徴です。
相続を円滑に進めたい人:生命保険の活用
現金を相続対策の一環として管理したい場合、生命保険の活用が有効です。死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。現金を生命保険に変えることで、この非課税枠を活用しながら相続税の負担を軽減できます。
また、生命保険は受取人が指定できる「受取人固有の財産」であるため、原則として遺産分割協議の対象外となります。
これにより、他の相続人の同意がなくても、受取人が単独で手続きを進め、比較的短期間で現金化できるという大きなメリットがあります。
当面の葬儀費用や納税資金を確保する上でも非常に有効な手段です。
長期的な資産形成も考えた人:NISAを活用したインデックス投資
タンス預金のように眠らせている資産を、将来に向けた長期的な資産形成に役立てたい場合は、NISA(少額投資非課税制度)を活用したインデックス投資が推奨されます。
NISAは、投資で得た利益(配当金や売却益)が非課税となる制度です。世界経済全体に分散投資するインデックスファンドなどに長期的に積立投資を行うことで、インフレ対策としても有効です。
≫老後の資金はどう作る?あなたに最適なプランを診断
タンス預金に関するよくある質問
タンス預金に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。
Q. タンス預金はいくらまでなら税務署にバレない?
結論からいえば、「いくらまでならバレない」という安全な金額の基準は存在しません。税務署は、高額な現金の動きがあった場合や、相続税の申告時に資産内容に不自然な点がないかを厳しくチェックします。
仮に少額であっても、故人の生前の収入や支出パターン、高額な贈与の有無などから、タンス預金として隠匿していた現金はほぼ確実に把握されます。
税務リスクを回避するためには、金額の大小に関わらず、すべての資産を適切に申告することが必須です。
Q. 亡くなった親の部屋から現金が見つかったら、どうすればいい?
親が亡くなった後にタンス預金を発見した場合、その現金は相続財産として扱われます。隠さずに、相続税の申告対象として加える必要があります。
もし、その現金を相続人が勝手に使ってしまい、申告しなかった場合、税務調査で発覚した際に、重い追徴課税の対象となります。
速やかに弁護士や税理士などの専門家に相談し、遺産分割協議の対象としつつ、正しい金額で相続税の申告を行うことが重要です。
Q. 「へそくり」もタンス預金として相続税の対象になる?
はい、「へそくり」も原則として相続税の対象になります。へそくりが現金であれ、名義預金であれ、その現金を形成した原資(資金の出どころ)が亡くなった人(被相続人)の収入や財産であれば、それは相続財産とみなされます。専業主婦の方が、夫から受け取った生活費をやりくりして貯めた現金や預金は、その典型例です。
ただし、配偶者が自身のパート収入などから貯めた現金(特有財産)であることが客観的な証拠(給与明細、入出金記録など)で明確に証明できれば、相続財産にはなりません。
しかし、長年にわたる夫婦の生活の中では、お互いの資金が混ざり合っていることが多く、「これは完全に自分の収入だけで貯めたものだ」と証明することは困難な場合があります。
自身の特有財産であることを明確にするためには、給与が振り込まれる口座と生活費の口座を分ける、ご自身の収入を証明できる資料(給与明細や源泉徴収票など)を保管しておくといった、生前からの準備が重要になります。
まとめ
タンス預金は、「いつでも使える」というメリットがある一方で、盗難・災害による物理的な損失、インフレによる実質価値の目減り、そしてもっとも危険な相続時の税務リスクを抱えています。
特に、相続時の申告漏れは、重加算税などの重いペナルティを招き、結果として資産を大きく失う原因となります。タンス預金の代替手段としては、ペイオフ対策としての分散預金や、インフレに強い個人向け国債、そして相続対策としての生命保険活用など、目的別に最適な方法を選択することが重要です。
安全かつ効率的な資産管理を行うためにも、できるだけ、リスクの高いタンス預金を別の管理方法に移行し、より安心できる資産管理・資産運用を行いましょう。
≫老後の資金はどう作る?あなたに最適な資産形成プランを診断
将来の備えが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
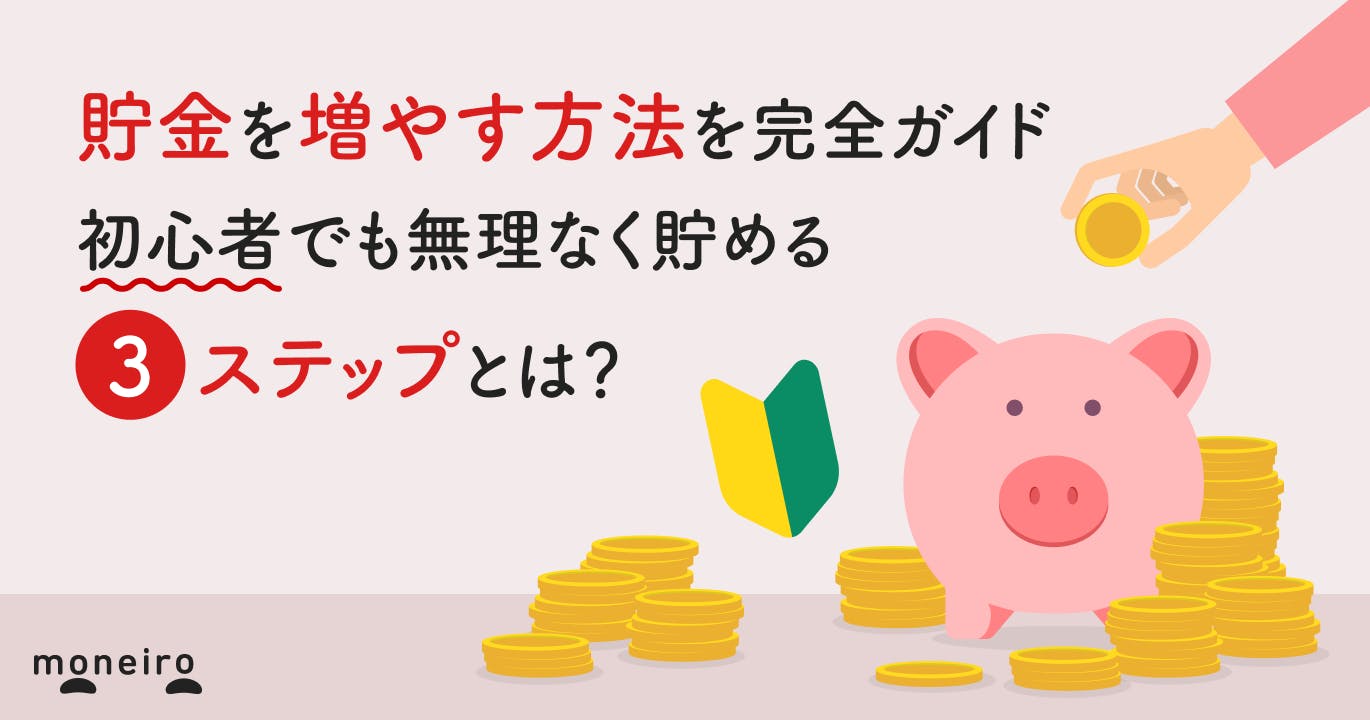

先取り貯金(貯蓄)とは?メリット・デメリット&ケース別の始め方を解説

貯金1000万円はすごい?年代別の割合&達成方法・達成後の注意点を解説
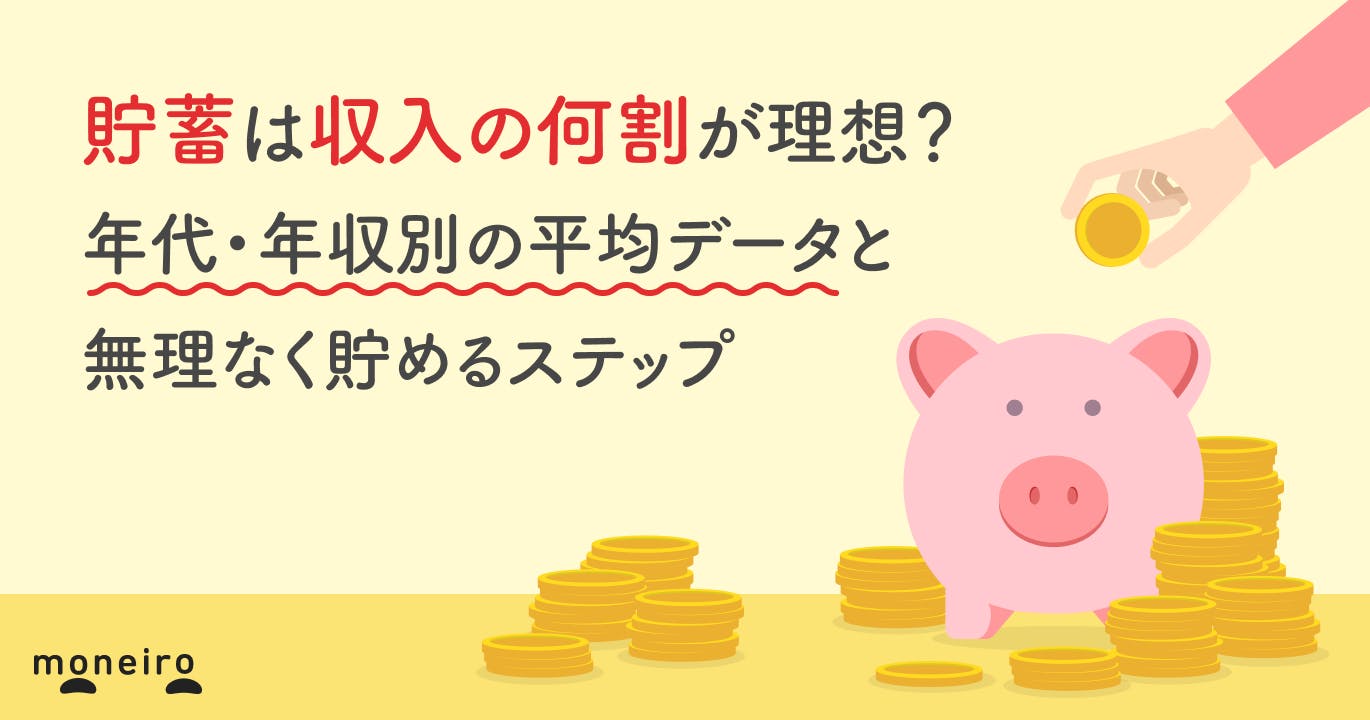
貯蓄は収入の何割が理想?年代・年収別の平均データと無理なく貯めるステップ
監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。