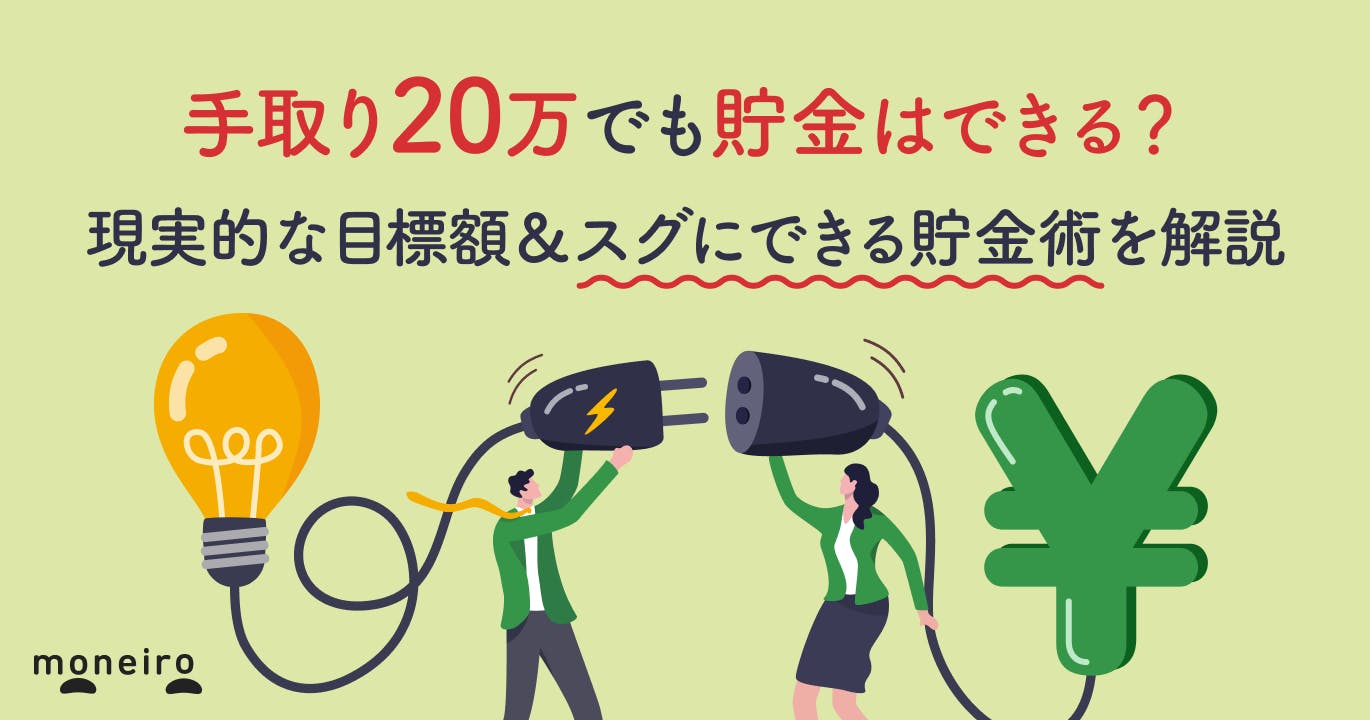
先取り貯金(貯蓄)とは?メリット・デメリット&ケース別の始め方を解説
>>あなたの必要資金はいくら?無料で簡単診断
「給料が振り込まれても、月末にはほとんど残っていない」「なかなか貯金が続かない」と悩む人は多いでしょう。しかし、貯金は意志の力ではなく仕組み化することが重要です。
「先取り貯金(貯蓄)」は、収入が入った直後に貯蓄分を別口座に移す、もっとも確実な貯金法です。本記事では、この先取り貯金の基本やメリット・デメリットを徹底解説し、堅実な資産づくりをサポートします。
- 「最強の貯金法」とも呼ばれる先取り貯金の具体的な仕組み
- 先取り貯金がもたらすメリットと、挫折を防ぐための具体的な対策
- 目的別・初心者でも確実に始められる具体的な貯金・資産形成の方法
将来の備えが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
先取り貯金(貯蓄)とは?「最強の貯金法」といわれる理由
先取り貯金とは、収入を得た(給与が振り込まれた)直後に、使うお金とは別に貯蓄分を自動的、あるいは強制的に別口座へ移してしまう貯金手法を指し、「最強の貯金法」と呼ばれることもあります。
残ったお金を貯金していく「残し貯金」では、月末にどれだけ使ったかを反省し、残ったお金を貯蓄に回そうとします。しかし、これは意志の力に頼ることになるため挫折しやすいという大きな欠点があります。
一方、先取り貯金は、給与が振り込まれた時点で貯蓄してしまうことで、「もともとなかったもの」として、残った金額で生活するというルールが成り立ちます。こうすることで、毎月の貯金が確実になり、無意識的に貯蓄を習慣化することができます。
先取り貯金(貯蓄)のメリット・デメリット
先取り貯金は、資産形成に非常に有効な手段で、多くのメリットがあります。一方でデメリットもあるため、双方をしっかり理解した上でスタートしましょう。
メリット
まずは先取り貯金のメリットから見ていきましょう。
貯蓄を自動的に増やせる
先取り貯金の最大の利点は、貯蓄プロセスを完全に自動化できることです。銀行の自動積立サービスや、勤務先の財形貯蓄制度などを利用すれば、給与が振り込まれたタイミングで、設定した金額が自動的に貯蓄用口座や投資口座へ移されます。
これにより、貯蓄を忘れる心配がなく、毎月確実に資産が増えていく安心感を得られます。貯蓄が着実に進むことで、モチベーションの維持にもつながります。
無駄遣いを防げる
先取り貯金を行うと、貯蓄を終えた後の残りの金額が、その月使える「生活費の上限」となります。そのため、支出をコントロールするのに非常に有効です。
人は手元にあるお金を使い切ってしまう傾向がありますが、最初から貯蓄分がない状態にすることで、自然と使える金額の枠内で生活する習慣が身につきます。これにより、無駄遣いを防ぎ、効率的な家計運営が可能になります。
貯金のストレスを軽減できる
毎月、手動で貯金額を計算したり、「今月は使いすぎてしまった」と自己嫌悪に陥ったりするストレスから解放されます。
自動的に貯蓄が実行されるため、その後の残りの生活費の使い道については比較的自由に判断できます。残ったお金を計画的に使えばよいため、精神的な負担が少なく、貯金を意識せずに生活を送ることができます。
デメリット
次にデメリットもしっかり確認しておきましょう。
生活費が圧迫される可能性
先取り貯金でもっとも注意が必要なのは、貯蓄目標額を高く設定しすぎたために、日常の生活費が過度に圧迫されてしまうことです。
例えば、手取りの50%を貯蓄に回すなど、非現実的な目標を立てると、日々の食費や交際費を極端に切り詰める必要が生じ、貯金生活自体が苦痛になり、かえって挫折の原因となります。
適切な貯蓄率は人それぞれですが、一般的には手取りの10~20%程度が1つの目安になります。家計の状況に応じて、無理のない範囲で設定することが重要です。
急な出費に対応しにくい
先取り貯金によって収入を先に差し引いてしまうことで、病気や冠婚葬祭などの急な出費が発生した際に、手元の「生活費用口座」のお金で対応が難しくなる場合があります。
さらに、先取り貯金で自動積立定期預金やiDeCoなど、流動性の低い(すぐに引き出せない)資産に振り分けている場合は、なおさら急な出費に対応しにくくなる可能性があります。
最初の設定に手間がかかる場合も
先取り貯金を始めるためには、給与の振込口座とは別に貯蓄用口座を開設し、自動振替や自動積立の設定を行う必要があります。
特に複数の金融機関を利用する場合や、財形貯蓄制度など複雑な手続きが必要な場合は、最初の設定に手間と時間がかかることがあるでしょう。
とはいえ、一度設定してしまえば、その後は自動的に貯蓄が続くため、この最初の手間を惜しまないことが成功のカギとなります。
先取り貯金(貯蓄)で挫折する3つの壁とは?
先取り貯金は仕組みさえ作れば確実ですが、それでも「続かない」と感じる人もいるでしょう。その原因となる「3つの壁」と対策を解説します。
目標が高すぎる・低すぎる「金額設定の壁」
貯蓄目標額が無理なレベルに設定されていると、生活が苦しくなり、貯蓄を中断しやすくなります。反対に目標額が低すぎると、「これくらいなら貯めなくてもいいか」とモチベーションが低下します。
対策として、まずは手取り収入の10%を目安にスタートし、無理なく継続できる金額を見つけましょう。
また、貯蓄目標は「短期(1年以内)」「中期(3~5年)」「長期(10年以上)」に分け、それぞれに紐づく具体的な金額を設定することで、常に目標を見失わずに継続することができます。
急な出費で取り崩してしまう「生活防衛資金の壁」
貯金が順調に進んでいても、家電の故障、突然の医療費、車の修理代など、予期せぬ大きな出費があると、せっかく貯めた先取り貯金を取り崩さざるを得なくなります。1度でも貯金を崩す経験をすると、「次の取り崩し」の精神的ハードルを下げてしまい、結果的に挫折につながりやすくなってしまいます。
これを防ぐために、最初に「生活防衛資金」を確保しておくことが望ましいといえます。
月々の生活費の3~6ヶ月分を目安に、すぐに引き出せる普通預金で確保しておく資金のことです。
この資金を先に確保し、基本的に手をつけない予備費とすることで、急な出費があっても資産形成を中断せずに済みます。
何のために貯めているか分からなくなる「目的喪失の壁」
ただ漠然と「老後のために貯めなきゃ」という意識だけでは、長期にわたってモチベーションを維持するのは困難です。また、目的が不明確なまま貯金を続けていると、目の前の欲しいものに対する誘惑に負けやすくなります。
対策として、貯蓄の使い道を具体的にイメージすることが重要です。例えば、「3年後に結婚資金として150万円」「5年後に車の買い替え費用として300万円」のように、貯蓄に名前をつけて視覚化します。
目的が明確になれば、貯金は「我慢」ではなく「目標達成への投資」となり、持続力を高めることができます。
将来の備えが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
ケース別・先取り貯金(貯蓄)の始め方
貯金に対する姿勢や資産形成の目的に応じて、最適な先取り貯金の仕組みは異なります。以下のケースを参考に、自分に合った始め方を選びましょう。
ケース1.まずは強制的に貯める習慣をつけたい人向け
貯蓄の経験が浅く、とにかく強制力のある手段で確実に貯める習慣をつけたい人には、以下の方法が適しています。
1. 銀行の自動積立定期預金
手軽で確実な方法です。給与振込口座と同じ銀行で自動積立定期預金を設定すれば、毎月決まった日に普通預金から定期預金へ自動的に振り替えられます。
普通預金よりも金利は高い反面、急な出費時に引き出しにくい(中途解約が必要)ため、生活防衛資金とは別で設定しましょう。
2. 勤務先の財形貯蓄制度
財形貯蓄制度では給与から天引きされるため、自己判断で貯蓄額を変えることができず、強制力が非常に強い点が資産形成をする上でメリットになります。財形貯蓄には主に以下の3種類があり、目的によって選ぶ必要があります。
- 一般財形貯蓄:貯蓄目的が自由。
- 財形住宅貯蓄:住宅の取得やリフォームが目的。
- 財形年金貯蓄:老後資金の形成が目的。
特に住宅と年金の財形貯蓄には、合計で元本550万円まで非課税になる税制上の優遇措置があります。ただし、年金貯蓄や住宅貯蓄は目的外の払い出しに制限やペナルティがある点に注意が必要です。
ケース2.貯めながら「増やす」ことにも挑戦したい人向け
生活防衛資金を確保済みで、インフレに備えて貯蓄を積極的に増やしたい人には、税制優遇を活用した資産運用が推奨されます。
1. NISA(少額投資非課税制度)
投資で得られた利益(分配金や売却益)に対して通常かかる約20%の税金が非課税になる制度です。非課税メリットが非常に大きい他、少額(月100円程度)から始められ、いつでも解約できるため、資産形成の第一歩としても最適です。
特に、「つみたて投資枠」では長期・積立・分散投資に適した商品が厳選されており、初心者でもリスクを抑えながら始められます。
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
老後資金準備を目的とする人向けの私的年金制度です。自分で掛金を拠出して運用を行います。最大のメリットは、掛金全額が所得控除の対象となる点です。また運用によって得られた利益も非課税となります。
ただし、NISAと比べて引き出しの自由度が低いのがデメリットです。原則60歳になるまでは資金を引き出せないため、短期的な資金ニーズには向いていません。
>>あなたに向いている資産運用は?無料で簡単診断
ケース3.保障も同時に備えたい人向け
万が一の事態に備え、死亡保障や医療保障を確保しつつ、貯蓄も同時に行いたい人には、積立型の保険商品が選択肢となります。
積立型の保険(終身保険・個人年金保険など)
これらの保険は「保障+貯蓄」の機能を持っています。死亡保障を確保しながら、解約返戻金や満期時にまとまった金額を受け取れます。
特に若いうちに加入すれば、保険料を安く抑えつつ、地道に長期間積み立てられるメリットがあります。ただし、利回りの低さと途中解約のリスクには注意が必要です。
- 低利回り:円建て定額保険の運用利回りは、NISAなどを利用した投資信託と比べると低い傾向(0.3~1.5%程度)にあります。※外貨建て保険や変額保険は大きめのリターンが狙える可能性がありますが、元本割れのリスクもあります。
- 途中解約:契約後すぐに解約すると、多くの場合、支払った保険料の総額よりも少ない金額しか戻ってこない(元本割れする)リスクがあります。
保障と貯蓄を分けて考え、貯蓄は効率のよい金融商品で、保障は掛け捨ての割安な保険で確保する、としたほうが、トータルの効率がよくなるでしょう。
先取り貯金(貯蓄)に関するよくある質問
先取り貯金に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 手取りが少なく、どうしても貯金に回すお金がない場合どうすればいい?
まず、家計を見直し、貯蓄に回す原資を作ることから始めましょう。特に、毎月自動的に出ていく固定費(通信費、保険料、サブスクリプションサービスなど)は削減効果が大きいでしょう。
固定費の削減が難しい場合は、「収入を増やす」という選択肢も検討します。方法としては副業やスキルアップ投資、転職などが考えられます。
それでも貯蓄が難しい場合は、目標額を大幅に下げてみましょう。例えば、最初は月に1000円だけを自動的に貯金する設定にします。
重要なのは金額の大きさではなく、貯蓄を「ゼロ」にしない習慣をつけることです。この習慣がつけば、収入が増えた際に自然と貯蓄額も増やせるようになるはずです。
Q. 先取り貯金とNISA、どちらを優先すべき?
基本的には、生活防衛資金の確保を優先し、その上でNISAを先取り貯金の一部として組み込むべきです。
まず、急な出費で困ることのないよう「生活防衛資金」として生活費の3~6ヶ月分を普通預金で確保しておきます。これが準備できたら、長期的な資産形成のため、NISAの活用を検討しましょう。
NISAも毎月の自動積立を設定されるため、実質的に「先取り貯金」として活用できます。現金貯蓄で安心を確保し、NISAで将来の資産増加を目指す、という2段階の仕組みを作るとよいでしょう。
Q. 収入が不安定な場合、先取り貯金のルールはどうすればいい?
フリーランスや個人事業主など、収入が月によって大きく変動する場合、毎月定額を先取り貯金に回すのは難しい場合があります。
この場合は、年単位あるいは四半期単位で貯蓄ルールを設定することが有効です。例えば、収入が多い月にまとめて貯蓄用口座に移すか、あるいは年間収入目標から必要経費と生活防衛費を差し引いた金額をあらかじめ試算し、そのうちの一定割合を年間の貯蓄目標として設定します。
さらに、「定額」ではなく「定率」で毎月貯めていくという手もあります。収入が入った時点で、その10%を別口座に移す、という方法です。ただし、都度計算の手間などが発生するため、やや面倒なのは難点といえます。
もし入金忘れなどを防ぐために自動化したい場合は、想定される収入の下限額をベースにして自動積立の額を決めるという方法もよいでしょう。
まとめ
先取り貯金は、個人の意志の力に頼らず、自動で資産を増やしていく「最強の貯金法」の1つで、無駄遣いを防ぎ、貯蓄のストレスを軽減できるといったメリットがあります。しかし一方で、目標設定を誤ると生活を圧迫するリスクもあります。
挫折を防ぐためには、手取りの10~20%を目安に無理のない金額を設定するとともに、事前に生活防衛資金(生活費3~6ヶ月分)を確保しておくことも重要です。
貯蓄の目的が明確であれば、自動積立による「強制的な貯蓄」に加え、NISAやiDeCoといった税制優遇を活用した貯めながら増やす仕組みも取り入れることで、より効率的かつ安全に将来の資産を形成することができます。
先取り貯金の理解を深めて今日から仕組みづくりを始め、確実な資産形成の一歩を踏み出しましょう。
>>あなたの必要金額は?将来に不足するお金を診断
将来の備えが気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
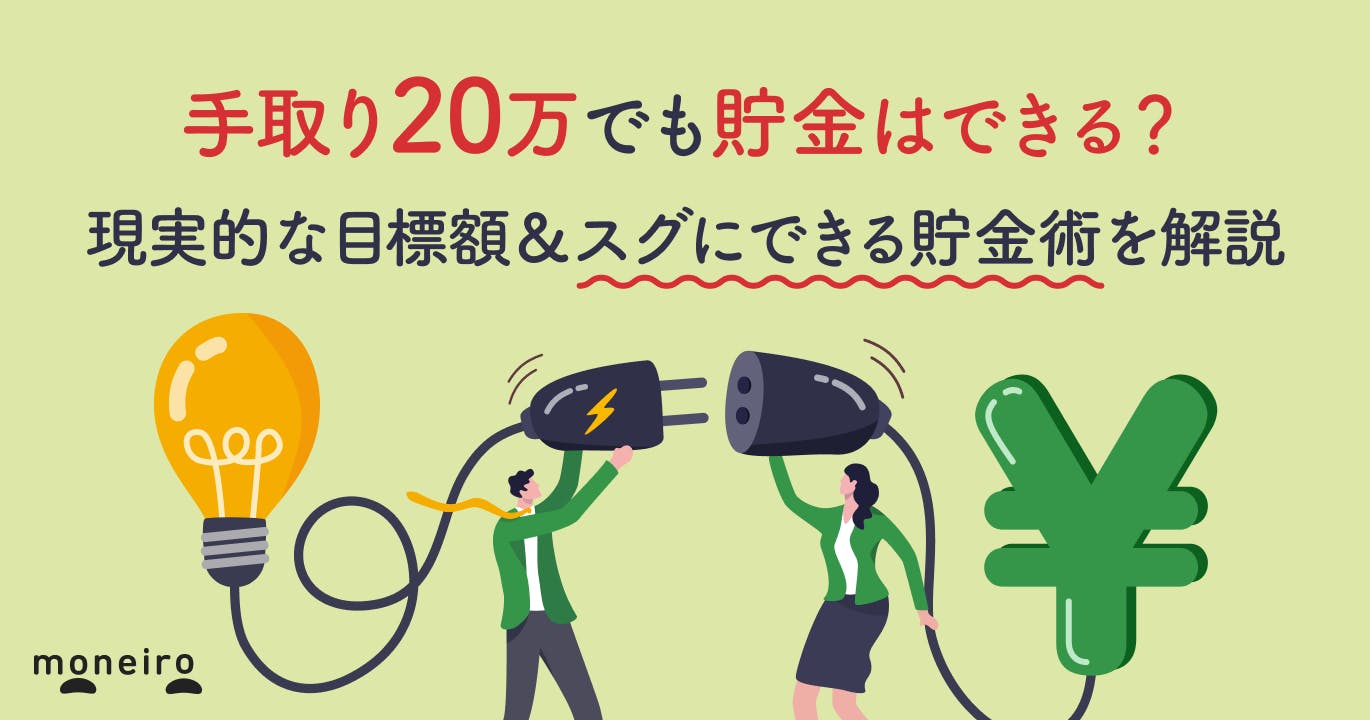

【プロ監修】少ない給料で貯金する方法を解説。今日から始められる簡単5ステップ

正直みんな貯金はどのくらいある?年代別・年収別に平均額・中央値を解説

家賃は手取りの何割が目安?収入別の理想の賃料&後悔しないための決め方を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
