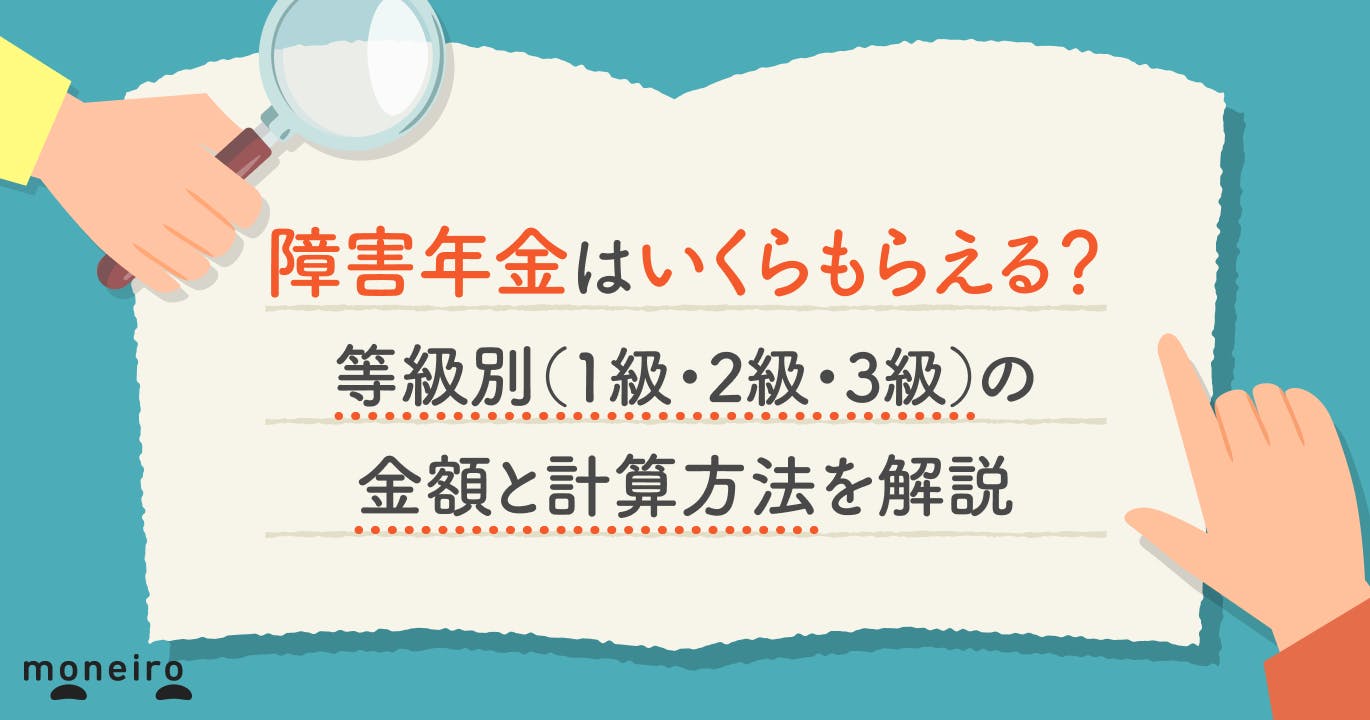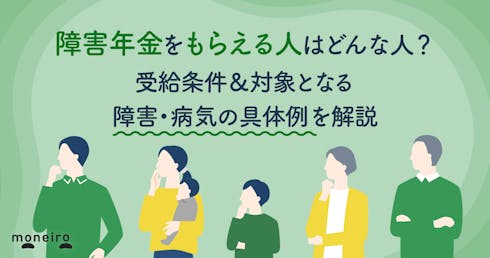
障害年金はいくらもらえる?等級別(1級・2級・3級)の金額と計算方法を解説
≫将来の備えは大丈夫?あなたの老後の不足額を診断
「障害年金はいくらもらえる?」そんな疑問にお答えします。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる重要な制度です。
本記事では、障害基礎年金(1級・2級)、障害厚生年金(1級・2級・3級)の金額一覧や受給条件、また、障害者手帳との違いまでを網羅的に解説します。この記事を読んで、不安を解消しましょう。
- 障害基礎年金、障害厚生年金の最新(令和7年度)の金額と計算方法
- 障害年金を受け取るために満たすべき3つの要件
- 障害年金と障害者手帳の特徴や違い、申請の必要性について
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
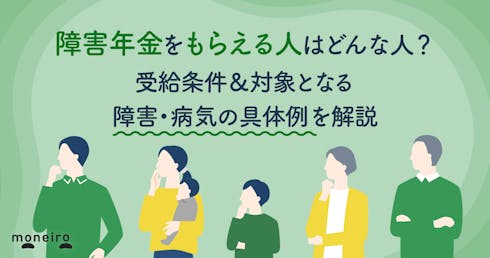

2つの障害年金「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違い
障害年金制度には、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらの年金が請求できるかは、障害の原因となった病気やけがで「初診日」にどの年金制度に加入していたかによって決まります。
「初診日」に加入していた年金制度で対象が決まる
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。
- 初診日に国民年金に加入していた方: 自営業者、学生、専業主婦の方などが該当します。障害等級表の1級または2級に該当する場合に「障害基礎年金」が請求できます。
- 初診日に厚生年金に加入していた方: 会社員や公務員の方が該当します。障害等級表の1級または2級に該当する場合、「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。また、2級に該当しない軽い障害のときは、3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりもさらに軽い障害が残ったときは、後述する「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる場合もあります。
障害年金をもらうための3つの受給要件
障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が、規定された加入期間内にあることが求められます。
- 障害基礎年金の場合:国民年金加入期間、20歳前、または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間のいずれかに初診日があること。
- 障害厚生年金の場合:厚生年金保険の被保険者である間に初診日があること。
障害認定日要件
障害の状態を判断する「障害認定日」に、法令に定める障害の程度に該当していることが必要です。障害認定日とは原則、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日をいいます。障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日を障害認定日とします。
- 障害基礎年金の場合:障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 障害厚生年金の場合:障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
なお、障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには、「事後重症による請求」として、65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出すれば、翌月から年金を受給できる場合があります。
保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料の納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
- ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
参照:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この納付要件は適用されません。
障害年金はいくらもらえる?2025年度(令和7年度)の金額早見表
障害年金の年金額は等級や、加入していた制度によって異なります。特に報酬比例で計算される障害厚生年金は、現役時代の給与や加入期間によって金額が大きく変わりますが、障害基礎年金と障害厚生年金3級の最低保障額は固定されています。
以下は、2025年度(令和7年4月分から)の基準となる年額と月額の早見表です(昭和31年4月2日以後生まれの方の金額を適用し、月額は年額を12で割って小数点以下を切り捨てています)。
参照:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
※障害厚生年金1級・2級は、元の給与(報酬)によって金額が大きく変わります。上記金額は、報酬比例部分を含まない固定額や最低保障額であり、これに、次で詳しく解説する「子の加算額」や「配偶者加給年金」が加わる場合があります。
≫将来の備えは大丈夫?あなたの老後の不足額を診断
障害基礎年金(自営業・学生・主婦など)はいくら?
障害基礎年金は、国民年金と厚生年金の加入者が対象となり、年金額は定額で、毎年、物価変動率と名目手取り賃金変動率に基づいて改定される仕組みです。令和7年度の年金額は以下のとおりです。
等級別(1級・2級)の金額一覧(年額・月額)
障害基礎年金は、障害の程度に応じて1級または2級に分けられ、年額が決まっています(昭和31年4月2日以後生まれの方の金額。子の加算額は除く)。
- 1級:103万9625円(月額 約8万6635円)
- 2級:83万1700円(月額 約6万9308円)
障害基礎年金1級の年金額は、2級の年金額の1.25倍に設定されています。
子の加算額はいくら?
障害基礎年金には、受給者に生計を維持されている子がいる場合、年金に加算額が上乗せされます。「子」の対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
令和7年4月分からの子の加算額は以下のとおりです。
- 1人目および2人目:1人につき23万9300円。
- 3人目以降:1人につき7万9800円。
(例)障害基礎年金2級で、生計を維持している子が2人いる場合の合計額
83万1700円(2級) + 23万9300円(子1人目) + 23万9300円(子2人目) = 131万300円
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
障害厚生年金(会社員・公務員など)はいくら?
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者であった期間に初診日がある場合に支給されます。障害厚生年金は、現役時代の給与や加入期間に応じて計算される報酬比例の年金額であり、金額が個人によって大きく変わる点が特徴です。
等級別(1級・2級・3級)の計算方法と最低保障額
障害厚生年金は1級から3級まであり、計算方法は等級によって異なります。
- 1級:(報酬比例の年金額)× 1.25 + 〔配偶者の加給年金額〕
- 2級:(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額〕
- 3級:(報酬比例の年金額)
参照:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
障害等級1級・2級の場合、障害厚生年金に加えて障害基礎年金(子の加算を含む)も支給されます。
3級には、年金額が低くなりすぎないよう最低保障額が設けられています。令和7年4月分からの3級の最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれの方)は、62万3800円です。報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
配偶者加給年金額(配偶者の加算)はいくら?
障害厚生年金の1級または2級を受給する場合、受給者に生計を維持されている配偶者がいるときに、配偶者加給年金額が加算されます。
加算の対象となるのは、65歳未満の配偶者で、加算額(令和7年4月分から)は、23万9300円です。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(20年以上の被保険者期間などがある場合)または障害年金を受け取る権利がある間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
3級より軽い障害が残った場合の「障害手当金(一時金)」
障害厚生年金には、障害等級3級に該当しない、比較的軽い障害が残った場合に支給される一時金である「障害手当金」の制度があります。
これは、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに支給されます。
障害手当金は、「報酬比例の年金額」の2年分として計算されます。この一時金にも最低保障額が設定されています。
障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳は、名称が似ていますが、根拠法も等級区分も審査機関も異なる、まったく別の制度です。
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳の総称です。これらの制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、手帳を持つことで、障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援策や、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けやすくなります。
例えば、精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。しかし、精神障害者保健福祉手帳で2級と認定されても、障害年金では3級または不支給になるケースもあります。
そのため、年金が必要な場合は年金の請求を、手帳によるサービスが必要な場合は手帳の申請を、それぞれ別個に行う必要があります。
障害年金に関するQ&A
障害年金に関するよくある疑問・質問に回答します。
Q. 障害年金の等級はどのように定められますか?
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により障害の程度(等級)が定められています。
例えば、1級は他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態であり、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が相当します。
2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級(障害厚生年金のみ)は、労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
Q. 障害認定日を過ぎてから症状が悪化した場合、請求は可能ですか?
はい、可能です。これを「事後重症による請求」といいます。
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには、請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
Q. 精神障害で障害年金3級だといくらもらえる?
精神障害で障害年金3級に認定された場合、障害厚生年金が支給されます。金額は、現役時代の給与に基づいた報酬比例の年金額ですが、最低保障額が適用されます。
令和7年度の最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれの方)は62万3800円です。
なお、精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動しない点には注意が必要です。
まとめ
障害年金制度は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた際に、現役世代の方を含めて支援する公的制度です。
障害年金には、年金加入者全員が対象となる障害基礎年金(1級・2級)と、厚生年金加入者が対象となる障害厚生年金(1級・2級・3級)があります。令和7年度の基準額として、障害基礎年金2級は83万1700円、障害厚生年金3級の最低保障額は62万3800円と定められています(昭和31年4月2日以後生まれ)。特に障害厚生年金1級・2級の年金額は、報酬比例で計算されるため、個々の給与や加入期間によって異なります。また、生計を維持する子や配偶者がいる場合、加算が行われます。
なお、障害年金を受給するには、「初診日」「障害認定日」「保険料納付」の3つの要件を満たすことが必須です。もし、障害年金制度に手続きで不明な点や分からない点がある場合は、日本年金機構の「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」または、お近くの年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。
≫将来の備えは大丈夫?あなたの老後の不足額を診断
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
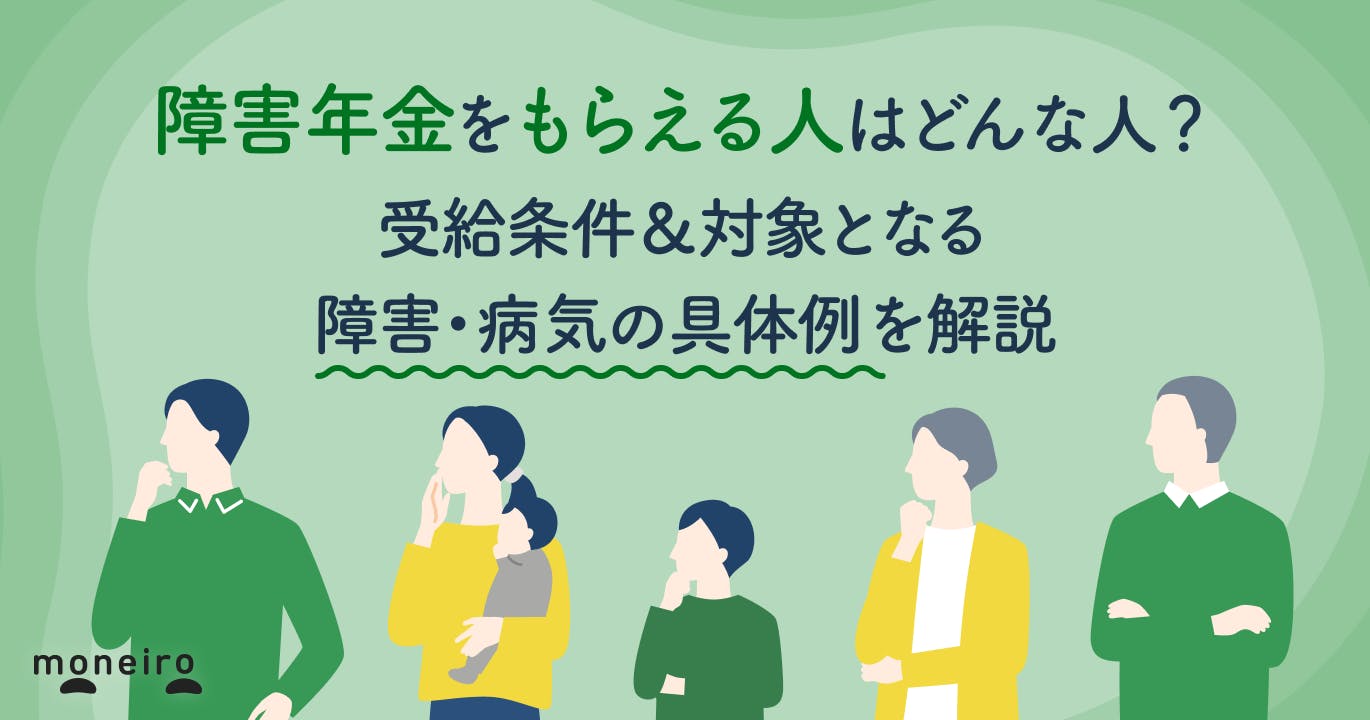
障害年金をもらえる人はどんな人?受給条件&対象となる障害・病気の具体例を解説
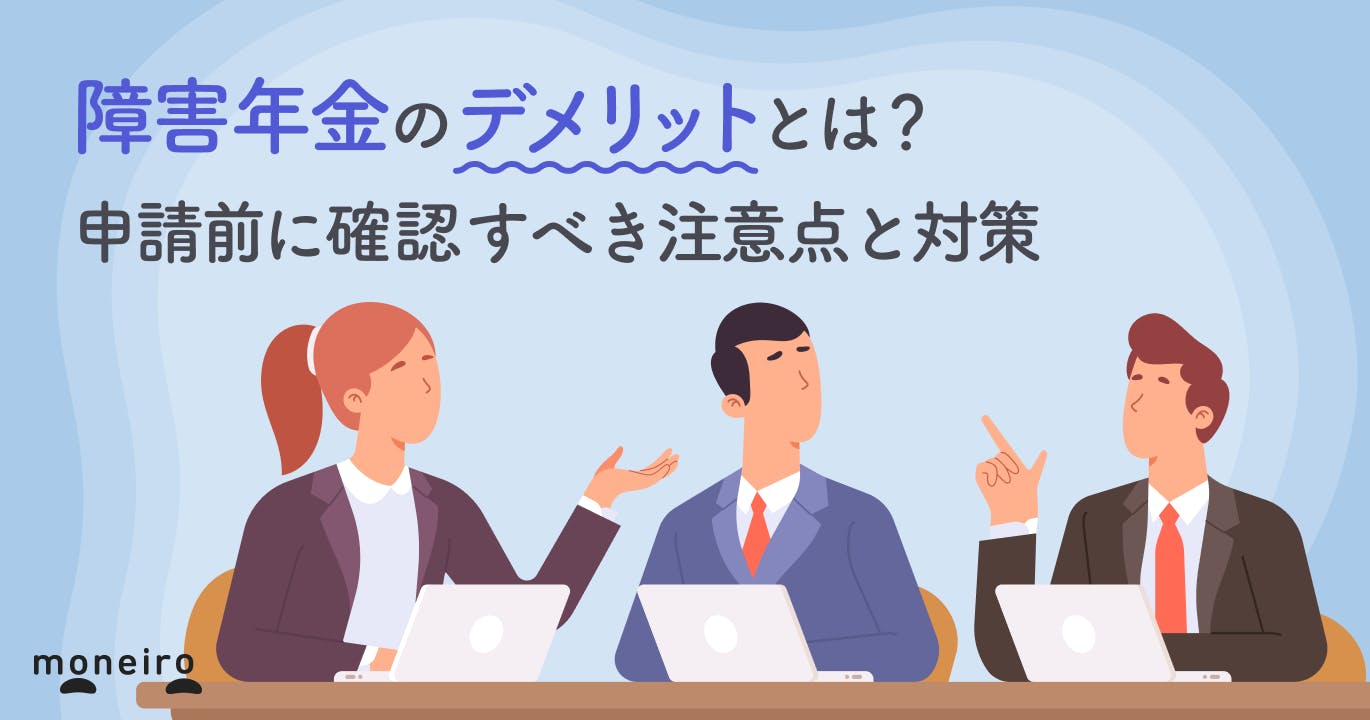
障害年金のデメリットとは?申請前に確認すべき注意点と対策

障害年金がもらえない人は何が原因?7つの理由と不支給・却下を防ぐ方法を解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。