
生活費の贈与はいくらまで非課税?仕送りや教育費のケースを解説
≫あなたの将来に必要なお金はいくら?3分で診断
「生活費の贈与はいくらまで非課税になるのか」という疑問をお持ちの方は多いでしょう。実は、生活費の援助には金額の上限は設けられていませんが、渡し方を誤ると贈与税の課税対象となってしまう可能性があります。
この記事では、贈与税が非課税になるための具体的な条件と、課税対象となる注意点を事例を交えて詳しく解説します。
- 個人間の贈与で贈与税がかかる条件と、非課税となる具体的なケース
- 親や祖父母からの生活費や教育費の援助が贈与税の対象とならないための条件
- 贈与税の基礎控除110万円の活用方法や、その他の非課税措置について
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門


【大前提】贈与税は相手が子どもでもかかる
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率を掛けて計算されます。
原則として、個人からこの基礎控除額・年間110万円を超える財産をもらった場合、財産を受け取った人が贈与税を負担することになります。これは、親から子、祖父母から孫といった親族間の贈与であっても同様です。
生活費の贈与には贈与税がかからない場合がある
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課税されるのが原則ですが、例外的に非課税となる場合があります。その代表例が、扶養義務者(親や兄弟姉妹など)から受け取る通常必要と認められる生活費(仕送り)や教育費です。
具体的には、結婚式の費用を親が負担した場合でも贈与税はかかりません。これは、日常生活を維持するために必要な援助であり、贈与税の趣旨とは異なるためです。
生活費・教育費が非課税になる3つの必須条件
扶養義務者からの生活費や教育費の贈与が非課税となるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。これらの条件を理解し、適切に贈与を行うことが重要です。
条件1.扶養義務者からの贈与であること
生活費や教育費が非課税となる大前提として、贈与者が「扶養義務者」である必要があります。
扶養義務者とは、民法上で扶養する義務がある人のことで、具体的には配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)や兄弟姉妹などが該当します。
「扶養義務者」の範囲は?
「扶養義務者」は、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、および家庭裁判所の審判によって扶養義務者となった3親等内の親族が該当し、叔父や叔母など、直系血族や兄弟姉妹ではない親族は該当しません。これらの親族からの援助は、原則として扶養義務者からの贈与とはみなされず、贈与税の対象となります。
条件2.「通常必要と認められる」生活費・教育費であること
非課税となる生活費や教育費は、「通常必要と認められるもの」に限られます。これは、社会通念上、通常の生活を送る上で必要な範囲の費用を指します。具体的には、食費、家賃、医療費、被服費、交通費、また学費、塾代、習い事の費用などが含まれます。例えば、結婚式の費用や学費を親が負担しても贈与税はかかりません。
しかし、過度に豪華な旅行費用や趣味に多額を費やすための資金など、社会通念上、通常の範囲を超えるような支出は「通常必要と認められるもの」とは判断されず、贈与税の課税対象となる場合があります。
受け取った財産の使途が明確で、必要な範囲に収まっていることが重要です。
条件3.「必要な都度」直接費用に充てられていること
生活費が非課税となるには、その財産が「必要な都度」贈与され、かつ「直接その費用に充てられている」ことが条件となります。これは、将来の生活費として、多額の現金をまとめて一括で贈与するようなケースでは、贈与税の課税対象となる可能性があることを意味します。
例えば、子どもが自立した後に使うかもしれないとして、まとまった金額を事前に渡してしまうと、それは「必要な都度」の贈与とはみなされません。
実際に費用が発生した時に、その都度必要な金額を渡す、または贈与者が直接支払いを行うといった方法が望ましいとされています。
【要注意】生活費の援助でも贈与税がかかるケース
生活費や教育費の援助であっても、渡し方や使途によっては贈与税がかかる場合がありますので注意が必要です。
生活費として余ったお金を貯金・投資してしまった
生活費として受け取ったお金であっても、その全額を生活費や教育費として使い切らず、余った分を貯金したり、株式や不動産などの投資に回したりした場合は、その余った金額に対して贈与税が課される可能性があります。
非課税となるのは、あくまで「通常必要と認められる範囲で、必要な都度、生活費や教育費に充てられた」場合です。したがって、余剰資金を形成するような受け取り方は、贈与税の対象となるリスクがあります。
将来の生活費として一括で渡してしまった
将来のためにと良かれと思って、子どもや孫の生活費をまとめて一括で渡してしまうと、贈与税の課税対象となる可能性があります。
非課税の条件は「必要な都度」渡すことであるため、将来を見越して多額の資金を一括で贈与することは、この条件を満たしません。
毎月決まった額を渡し「定期贈与」とみなされた
毎月決まった額を長期間にわたって贈与し続けると、税務署から「定期贈与」とみなされることがあります。
定期贈与とは、例えば「毎年100万円を10年間にわたって贈与する」といったように、贈与契約によって確定した合計額の贈与を行うことです。この場合、毎年の贈与額が110万円の基礎控除内であっても、将来にわたる総額について贈与契約が成立していると判断され、その総額に対して贈与税が課される可能性があります。
もらったお金で不動産や車など資産を購入した
通常必要な生活費として受け取ったお金であっても、その資金で不動産や車などの高額な資産を購入した場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。贈与税は、著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合や、対価を支払わないで不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合など、「みなし贈与」として課税されるケースがあります。
通常必要な生活費として受け取ったお金は、あくまで日常生活に消費されることが前提です。それを資産の購入に充てると、実質的には資産の贈与を受けたとみなされ、贈与税が課されるリスクがあります。
資産購入の資金援助を行う場合は、別途、贈与税の基礎控除枠や特例制度の活用を検討する必要があります。
扶養義務のない人(叔父・叔母など)から高額な援助を受けた
生活費や教育費の贈与が非課税となるのは、「扶養義務者相互間」の場合に限られます。したがって、生計を一にしない叔父や叔母、友人など、法律上の扶養義務のない人から高額な生活費や教育費の援助を受けた場合、原則として贈与税の課税対象となります。年間110万円を超える援助を受けた場合は、贈与税の申告と納税が必要になるため注意が必要です。
家族間の援助であっても、扶養義務者以外の親族からの援助は、年間110万円の基礎控除の範囲を超える場合、課税される可能性が高いことを理解しておく必要があります。
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
贈与税を軽減するための具体的な方法
贈与税の負担を軽減するためには、以下の具体的な方法が有効です。
暦年贈与を上手に活用する方法
暦年課税制度は、贈与税の基本的な課税方法の一つであり、毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。この基礎控除額を毎年活用し、計画的に贈与を行うことも可能です。
例えば、贈与契約に基づき110万円以内の金額を贈与すると、贈与税はかかりません。贈与する金額を細かく分割し、長期間にわたって少しずつ贈与することで、将来的に相続する財産を減らし、相続税対策にもつながります。
夫婦間の贈与に使える「配偶者控除(おしどり贈与)」
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、「贈与税の配偶者控除」(通称:おしどり贈与)を利用することができます。この制度を適用すると、基礎控除110万円とは別に最大で2000万円、合計で2110万円までが非課税となります。
この特例は、居住用不動産の贈与に限定されますが、夫婦間の居住用不動産に関する贈与税の負担を大きく軽減できる非常に有効な制度です。
ただし、この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に居住し、その後も居住する見込みであることなどの条件があります。
特例制度の活用
贈与税には、特定の目的のために設けられた非課税措置がいくつかあります。これらを活用することで、多額の財産を非課税で贈与することが可能です。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
直系尊属(父母や祖父母など)から、居住用の家屋の新築、取得、増改築などのための資金を贈与された場合、一定額までが非課税となる制度です。適用期限は令和8年12月31日までとされています。非課税限度額は、省エネ等住宅で1000万円、それ以外の住宅で500万円です。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
直系尊属から、30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与する場合、最大1500万円までが非課税となる制度です。適用期限は令和8年3月31日までです。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を一括で贈与する場合、最大1000万円(結婚資金は300万円まで)までが非課税となる制度です。適用期限は令和9年3月31日までです。
贈与の証拠を残すことも重要
贈与税の課税対象となるか否かの判断において、贈与の事実やその内容が明確であることは非常に重要です。特に、非課税となるべき贈与であるにもかかわらず、それが税務署に正しく認識されないと、贈与税の課税を受ける可能性もあります。
贈与契約書の作成
贈与契約書を作成することは、贈与の事実と贈与の内容を明確にする上で非常に有効な手段です。口頭での約束であっても贈与は成立しますが、書面に残すことで「いつ、誰から誰へ、何を、いくら贈与したか」が客観的に証明できるようになります。そのため、贈与を行う場合には、贈与契約書を作成しておくことが非常に重要です。
銀行振込の活用と記録の保管
現金を直接手渡しするよりも、銀行振込を利用することで、贈与の記録を明確に残すことができます。振込履歴には、送金元、送金先、金額、日付が記録されるため、贈与の証拠になります
また、振込の際に「生活費」や「教育費」など、贈与の目的を摘要欄に記載しておくことで、使途の証明にもつながります。通帳やネットバンキングの取引履歴は大切に保管し、いつでも確認できるようにしておきましょう。
生活費の贈与に関するQ&A
生活費の贈与に関するよくある質問と回答を以下にまとめました。
Q. 離れて暮らす子どもへの「仕送り」も非課税になる?
はい、離れて暮らす子どもへの仕送りも、原則として贈与税はかかりません。親は子どもに対する扶養義務者であり、その子どもが自立して生計を営むことができない場合、親が生活費を負担することは扶養義務の履行とみなされるためです。
ただし、非課税となるのは、あくまで「通常必要と認められる生活費」として「必要な都度」渡され、かつ「直接生活費に充てられている」場合に限られます。
例えば、子どもが遊興費に充てるために過度な金額を送金したり、受け取った仕送りを貯蓄したりした場合は、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
Q. 夫婦間で生活費を口座移動させるのも贈与になる?
夫婦間での生活費の口座移動は、通常、贈与税の課税対象にはなりません。夫婦は互いに扶養義務者であり、協力して生活費を分担する義務があります。そのため、夫婦間で通常の生活に必要な範囲で金銭をやり取りすることは、贈与ではなく、生活費の分担とみなされます。
ただし、以下のようなケースでは贈与税の対象となる可能性があります。
- 生活費として通常の範囲を超えるような多額の金銭を一括で移動させ、それが貯蓄や投資に回された場合。
- 夫が妻に多額の金銭を渡し、妻名義で不動産や有価証券を購入した場合(みなし贈与に該当する可能性)。
「通常必要と認められる」範囲内での生活費のやり取りは問題ありません。
Q. 孫の塾代を祖父母が直接塾に支払う場合はどうなる?
孫の塾代を祖父母が直接塾に支払う場合、原則として贈与税はかかりません。祖父母は孫に対する直系尊属であり、扶養義務者とみなされるためです。親が子どもの教育費を負担しても贈与税がかからないのと同様に、祖父母が孫の教育費を直接支払う行為も、通常必要と認められる範囲であれば非課税となります。
この場合も、「必要な都度」支払われること、および「直接教育費に充てられる」ことが条件です。祖父母が孫に塾代として現金を手渡し、孫がそれを貯蓄に回したり、他の目的で使ったりした場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります
まとめ
生活費や教育費の贈与は、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となります。特に重要なのは、「扶養義務者からの贈与であること」「通常必要と認められる範囲であること」「必要な都度、直接その費用に充てられていること」の3つの条件です。これらの条件が守られない場合、例えば余ったお金を貯蓄したり、将来のために一括で多額を渡したりすると、贈与税の課税対象となるリスクがあります。
贈与を行う際は、贈与契約書の作成や銀行振込の利用など、証拠を残すことも税務上のトラブルを避ける上で不可欠です。自身の状況に合わせて、これらの制度や注意点を理解し、適切な贈与を行うことで、税金負担を軽減し、円滑な資産承継を行いましょう。
≫あなたの将来に必要なお金はいくら?3分で診断
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
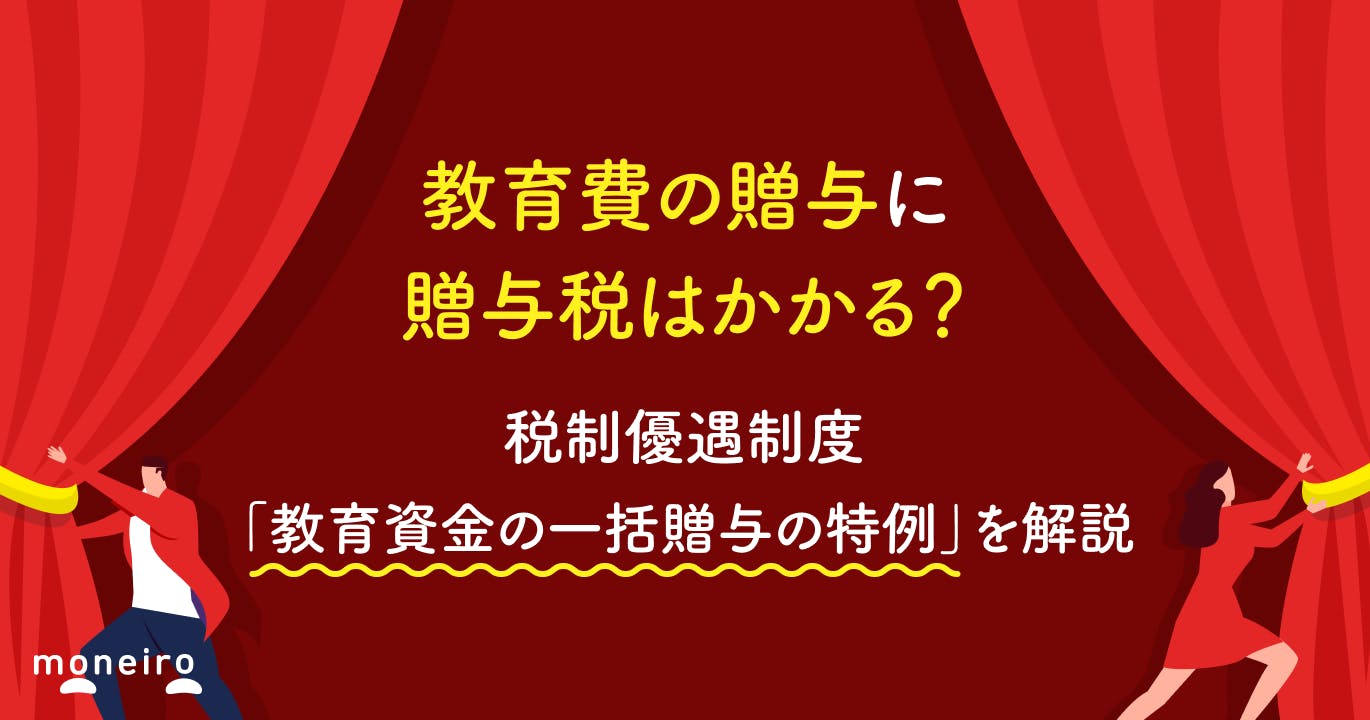
教育費の贈与に贈与税はかかる?税制優遇制度「教育資金の一括贈与の特例」を解説
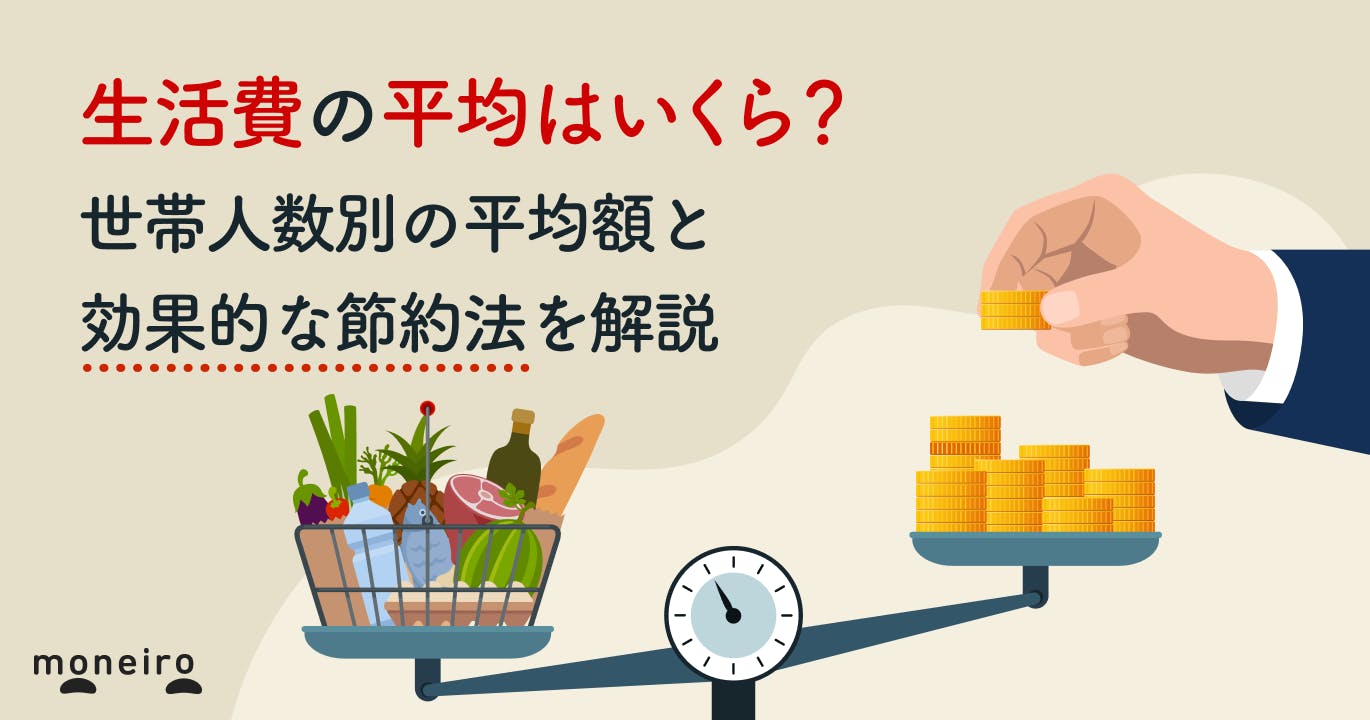
生活費の平均はいくら?世帯人数別の平均額と効果的な節約法を解説

子ども名義の貯金はいつ渡す?贈与税はかかる?専門家が注意点と税金の仕組みを解説

